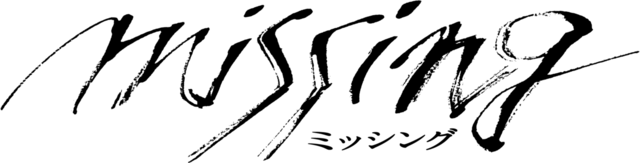ミッシング : 特集
【“ぶっ壊れた”石原さとみが、想像の遥か上だった】
6歳の娘が突然、失踪した。その時、母親は──衝撃が
すぎると話題沸騰 “傑作しか作れない監督”が放つ
限りなく哀しく優しい物語に、あなたは何を感じるか?

最初に断言しておこう。石原さとみが“あまりにも凄すぎた”映画、それが「ミッシング」(5月17日公開)だ 。
「ヒメアノ~ル」「空白」の𠮷田恵輔監督がメガホンをとった本作。劇中での石原は“あなた”が出会ったことがない“別次元の石原さとみ”だ。誰もが知る国民的女優が“ぶっ壊れていく”。そんな超刺激的要素に絶句し、予想以上の涙腺崩壊ストーリーに心をぐわんぐわんと揺さぶられる――。

𠮷田監督とのタッグを熱望し続けた石原が、出産後初の映画撮影として1年9カ月ぶりに芝居に臨んだ作品であり、我が子の失踪で極限まで崩壊していく母親を演じている。
待望の復帰作? 体当たりの演技で新境地開拓? いいや、そんな表現ではまったくもの足りない。石原が「自分を壊してください」と𠮷田監督に願い、そして創出された常軌を逸した気迫と熱演が観る者に突き刺さる……この映画が高らかに告げるのは“石原さとみの新章の始まり”だ。稀有な瞬間を絶対に見逃してほしくはないので、本記事で魅力を徹底的に解説していこう。
【#石原さとみぶっ壊れてる】なぜここまで話題なのか?
“新境地開拓”の言葉では生ぬるい、衝撃の一部を解禁

あらすじや作品概要は予告映像からご確認いただくとして、まずはゲリラ豪雨のように降り注ぐ本作の衝撃についてご紹介していこう。
●石原さとみの衝撃①:手入れされていない外見
唇は常に荒れ、髪はボサボサ、服とメイクは質素…“美のカリスマ”を脱ぎ捨てた熱演

石原さとみと言えば、輝かしいほどの“美”が観る者の目を引く。しかし本作では、疲弊した母親・沙織里を驚くべきトーンで演じていることが、息をのむほどの見どころだ。
トレードマークの唇は常に荒れた状態で、髪はパサつきボサボサ。顔の周りには乱れた前髪やおくれ毛がちらつく。服もメイクも超高級とはほど遠いものばかり。彼女の全身から“疲弊”の二文字がにじみ出す……。
撮影中は体を緩めるためにあえて添加物の多い食事をとったり、髪はシャンプーではなくボディソープで洗ったという石原。“美のカリスマ”としての自分を脱ぎ捨てる覚悟の役作りを経て、本作の沙織里にたどり着いている。
●石原さとみの衝撃②:ぶっ壊れる嗚咽、絶叫、罵倒、暴力、決壊…「こんな姿、観たことがない」と唖然

「ああ、壊れたんだ……」と直感するような、石原さとみの熱演がすさまじい。ときには“ヤバすぎる”と直視できないほど鬼気迫る演技を、とにかく映像で食らってもらいたい。
取材してくれるテレビ局のロケ車に追いすがり絶叫、不甲斐ない弟の髪を引っ張りまくり罵倒、メッセージアプリで「死ね死ね死ね」と信じられない速度で連打……予告はあくまでも一部のシーンのみを収めており、本編ではさらに、さらに、さらに衝撃的なシーンがすさまじい勢いで現れては消え、また現れる。

特に「終盤の警察署でのシーン」は何が何でも目撃していただければと思う。ここ10年でも最も破壊力がある瞬間のひとつであり、「こんな姿、こんな映画、観たことがない」と唖然とし、“人生で初めて味わう感情”に驚くだろう。
●石原さとみの衝撃③:さらなる“極限の向こう側”へ…光に包まれ、手を伸ばすその先に…ただ娘に会いたい、その結末とは?

高い負荷がかかる役に挑んだ俳優に対し、私たちはよく“新境地開拓”などと書いたりするが、本作の石原さとみはそんな言葉では生ぬるい。彼女自身が「自分を壊してください、と監督にお願いした」と語る通り、全編を通じて、極限の壁を何枚も突破し続け、名状しがたい境地へたどり着いた姿を観ることができるのだ。
愛する娘が失踪したことですべてが狂ってしまった人々が、光を見つける物語……その結末はいかに? ぜひ劇場で確かめ、ご自身の胸に宿った感情に、名前をつけてあげてほしい。
【監督・𠮷田恵輔も天才的】傑作しか作れない男が、
「ミッシング」で自身最高傑作を更新した――

さらに注目してもらいたいのは「監督・脚本:𠮷田恵輔」というクレジット。これだけで本作のクオリティは、すでに保証されたようなもの。多くの映画.comユーザーはご存知だろうが、𠮷田監督は天才だからだ。このパートで、その魅力を説明しよう。
●𠮷田恵輔とは? 「ヒメアノ~ル」「空白」などの鬼才人の心の深淵を描写する、圧巻の“傑作しか作れない男”

まずは、𠮷田監督のフィルモグラフィを遡ってみる。
森田剛の“狂気”を引きずり出した「ヒメアノ~ル」や、安田顕の極限を描破した「愛しのアイリーン」など、原作のエッセンスを魅力的に抽出して映像化に成功。オリジナル脚本の作品も多数手掛けているのも特徴的で「さんかく」「ばしゃ馬さんとビッグマウス」「麦子さんと」「犬猿」「BLUE ブルー」「神は見返りを求める」に加え、娘を亡くした父親と関係者たちの苦悩、償い、赦しを描いた「空白」も発表している。

どの作品にも通底しているのは、人間描写の圧倒的な緻密さだ。人間のおかしみや悲哀、根底に潜む欲望、羨望、いやらしさをこれでもかと見せつけてくる。そのリアルさは「𠮷田監督は、人の“心”が実際に見えるのではないか?」と感じてしまうほどだ。
映画.comもこれまでの作品を“目撃”してきているが、全作に“傑作認定”の判を押したいと思うほど。つまり、𠮷田監督は“傑作を作る男”ではない。大袈裟に聞こえるかもしれないが“傑作しか作れない男”なのだ。
●「ミッシング」は光を見つける<わたしたち>の物語張り裂けるほどの感動に、心が揺れる…“𠮷田恵輔史上、最高傑作”にふさわしい渾身作

本作は母親だけが共感できる物語ではなく、“誰もがどこかで共感できる物語”でもあると感じられるだろう。
𠮷田監督が本作の脚本を書く発端としたのは「辛いことや耐えられないことがあったときに、人はいかに折り合いをつけるのか」というテーマだったそうだ。
つまり、これは誰しもが直面する辛いことを描いた<わたしたち>の物語であり、この間口の広さが「𠮷田監督が最高傑作を更新した」と感じたポイントだ。

<わたしたち>のひとりである筆者も共感を禁じ得なかった。この作品が“他人事”ではない“自分事”の物語だったからだ。具体的な感想は記事の最後に書くが、予告編に使用されている「絶えず心揺さぶられる傑作」(ニッポン・コネクション)、「胸が張り裂けるほどの感動」(ファーイーストフィルムフェスティバル)というレコメンドには何度も、何度も頷いてしまった。
【レビュー】鑑賞中は嗚咽し、鑑賞後も思い出して泣く
“自分にも起こり得る物語”を食らった編集部員の感想

最後にお届けするのは、実際に鑑賞した映画.com編集部メンバーによる感想(ネタバレなし)だ。30代男性の筆者は、作品から放たれた“力”にあてられ、未だに動揺が続いている様子。一体何を感じとったのだろうか。
●筆者紹介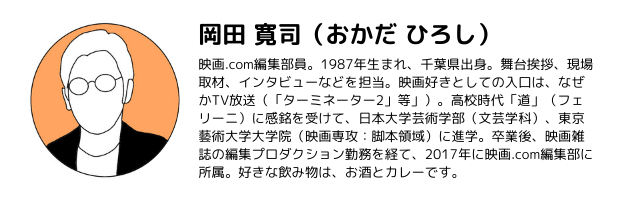

傑作と対峙した時、僕がとる行動は2つのパターンに分かれる。ひとつは、座席から立ち上がらず、暫く余韻に浸るというもの。もうひとつは、席を立ったら、まずはひたすら歩き続け、映画から受けた膨大なエネルギーを消化すること。「ミッシング」は“歩き続ける”に当てはまった。
僕は「ミッシング」試写会場を出て歩き続けたのだが……流石に困り果てた。歩いても、歩いても、気持ちが昂ぶり続けていたのだ。

要因の一つとなったのが、石原さとみが体現した“役の生き方”だ。生死不明の娘をひたすら追い求める姿には、ただただ圧倒される。しかし、彼女は実生活でも一児の母になったばかりだ。こんな思いが頭をもたげる。これほど役の人生に肉薄して“映画の世界”から“実生活”に帰ってこれるのだろうかと。そんな不安を覚えるほどの“覚悟”を感じた。
沙織里の彷徨から伝わってきたのは、希望にすがり続けることの苦しさだった。「きっと生きている」「きっとまた会える」を信じ続けることの難しさ――鑑賞から日が経ったが、沙織里の苦闘を思い起こさない日はない。
●沙織里を取り巻く人々の“人生”にも心奪われる 石原さとみと対等に渡り合う“注目俳優”を見逃さないで
𠮷田監督は、主人公の沙織里だけに肩入れをしない。彼女の日常が軌道に乗った時「あなたの“人生”は、あなただけのものではない」とばかりに、周囲の人々の“人生”が唐突に介入する。ここに圧倒的なリアルを感じてしまった。
娘の失踪に対する“温度差”で沙織里とすれ違う夫・豊(青木崇高)、人間らしさと仕事の責務によって板挟みになる記者・砂田(中村倫也)、市井の人々、SNSの住人たち……“自分にも起こり得る物語”として感情移入してしまう対象が、きっと見つかるはずだ。

そんな“周囲の人々”を演じた俳優のなかでも、特に森優作(沙織里の弟・圭吾役)には注目してほしい。「野火」「佐々木、イン、マイマイン」「ゾッキ」でも異彩を放っていたが、人間の“不安定さ”を表現する力は、当代随一ではないだろうか? 本作の石原さとみと対等に渡り合っているなんて、ちょっと凄すぎる……。彼もまた、石原さとみとはタイプの異なる“天才”だった。
●感情の完全同期→滝のような涙、鑑賞後も心が揺れ続けて……「ミッシング」には“人を変える力”があった
さて、ここまでは「映画.com編集部」の一員として語ってきたが、最後に「父親としての私」としての感想も付記しておきたい。
試写会に参加した際、通常であればエンドロールが終わるまで「映画を観察する」ことができる。それが仕事だからだ。ところが、本作は違った。夫・豊に“わたし”を見つけ、その感情に完全同期してしまった結果、もはや仕事どころではなくなっていた。この物語に「父親」として取り込まれ、ありえないほどの嗚咽を漏らす。滝のような涙だった。
試写会場を出ると、映画に携わった人々に感想を聞かれる。どうにか感想を述べなくてはならないのに、言葉を上手く飾れない。「とても良かったです、とても――」。苦しまぎれの言葉は、語尾が震えていたと思う。

落ち着きを取り戻すため、歩いて、歩いて、そして寄り道をしてから家へと帰った。出迎えてくれた子どもの頭を撫でると、映画の内容がフラッシュバック。“ここにちゃんといる”という事実が、無性に泣けてきた。
「公開されたら一緒に観に行きたい映画があるんだけど」と妻を誘う。試写会から帰ってきて、そんなことを言うのは初めてだった。それからは毎日のように、本作の魅力を伝え続けている。「“僕たちの物語”でもあると思う」という言葉とともに――。
鑑賞後に“人を変える”。「ミッシング」には、その力があった。