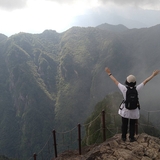対峙のレビュー・感想・評価
全110件中、21~40件目を表示
観ているのが辛く胸が張り裂けそうな作品
銃乱射事件の加害者と被害者の両親が顔を合わせて対話するストーリー。
観ているのが辛く胸が張り裂けそうな作品。
加害者も被害者も親にとってはどちらも大事な息子。
ずっと平行線のままだと思いました。
平行線どころか殴りかけてもおかしくない感情になります。
被害者は加害者がなぜこんな事件を起こしたのか知りたいし
加害者は被害者に赦しをもらいたいと思うし。
やっぱりまともな感情にはいられないでしょう。
ずっと苦しい
つらいつらすぎる。
ずっと苦しい映画だった。
配信で観たが、一気に観れなかった。ちょっと中断しながら観た。
最後、部屋に残された被害者の親をみて虚しさを感じた。あなたたちを心から赦すと言ったけど、気持ちのいい別れではなくぎこちなくて、教会に残される描写がそのまま彼らの心が残されてるようだった。
加害者母が戻ってきて、今まで話した息子の見逃した危険な兆候とは違う、たしかに怖いと思った、危険で見逃せなかった個人的なエピソードを話したところつらかった。
最後までみた後、
加害者親が赦すと言われても喜んでるようには見えなくて、父親は居心地が悪そうだったし早く帰りたい感じだったのは、彼らの赦すという言葉では何も救われないからじゃないかと思った。
加害者家族も被害者家族もどちらもつらい。
加害者親は自分が犯罪者ではないけど、未成年の犯罪者の親で責任があって、誰もが親のせいに思う。加害者が死んでるから生きてる両親に批難が集中して、でも息子がどうしてしたか、どうすればよかったかなんて親もわからない。
被害者親は赦すことで自分たちを救おうとした。
前に進むために赦すという選択肢があるのは被害者側だけなんだと気づいた。
赦すことは加害者側のためではない。
加害者親も救われるかと思ったらそうは見えなかった。
あの教会に最後までいて讃美歌を聞いて心を癒されたのは被害者親で、先に帰られて残されるのは事件に残されるようだと思ったけど、癒しの歌を聞けた。
加害者親のあの後の歩いて帰るのを想像するとつらい。
話せなかったこと
犯人はサイコパスか
精神病か
それとも可愛い息子か
悩める少年か
2つの家族が加害少年をどう解釈するか。1つの答えは出ないでしょう。
何を求めてここに来たのか。
罰を与えるため。それとも赦して前に進むため。
少年はもう死んでいるので、家族同士で話し合う。何度目かの対話なのでしょう。4人それぞれでも少年の解釈は違う。それが描かれていました。
別の過去を望んだままでは生きていけない。それが真実なのでしょう。
映画も音楽も聖歌も、前進するためにある。
本作は、深刻な事象に光を当て、
登場人物たちの心の奥底を克明に描き出す、
心理劇の傑作である。
オープニングシーンから、
机の配置、イスの角度、ティッシュの置き場所、
といった細部の描写が観客の注意を一点に集める。
これは、単なる写実的な描写にとどまらず、
これから始まる緊迫した状況への予兆として機能している。
カメラは、登場人物たちの表情をクローズアップで捉え、
彼らの心の揺れ動きを正確に映し出す。
眼球の動きや目線の交差といった、
微細な表情の変化は、
言葉を超えたコミュニケーションとして機能し、
観客にステマのようにシグナルを送り続ける。
これは、キャストたちが経験と訓練によって培った、
非言語コミュニケーションの高度な技術である。
登場人物たちの心理戦が、言葉は最低限の分量で、
身体表現によって繰り広げられる。
限られた空間の中で、
彼らは姿勢、頭の角度、呼吸といった身体の細かな動きで、
defenseのアクション、retaliationのリアクション、
互いの心理状態を探り、間、タイミングをコントロールし、
駆け引きを行う。
物語は、4人の人間関係が複雑に絡み合い、
徐々に破綻していく様を描き出す。
それぞれの立場や価値観を持ち、
互いに衝突し、そして理解しようとする。
この過程で、
人間の心の奥底にある醜い部分や、脆い部分が露呈していき、
感情と感情が対峙する時に論理的思考は不毛だという事もあからさまになる。
最後に、
見事なエンターテインメント作品にとどまらず、
人間の心理に関する深い洞察を提供する。
特に、感情をコントロールすることの難しさ、
そしてその重要性が浮き彫りになる。
感情に任せて演技をすることは、時に危険な状況をもたらす。
そのため、俳優は、感情をコントロールし、
役柄に没入するための高度な技術を身につける必要がある。
昨今、スポーツ界でもメンタルトレーナーが重要視されつつあり、
NPBでも2球団が専属トレーナーを起用している。
映画界でもインディマシー・コーディネーターが話題になっているが、
メンタルトレーナーの起用と、
演技の理論と実践を体系的に教習するシステム導入も急務である。
サイコには神の声は届かない
フラン・クランツという新人監督さんが撮った本作の英語原題は“MASS”。英語で“ミサ”を意味するらしい。プロテスタントとカソリックのちょうど中間に位置する“聖公会”教会?の一室で、これからなにやら重た~い雰囲気のミーティングが行われるらしいのだが、表れた2組の夫婦がなんのために呼び出されたのか、観客になかなかわからない演出がとられている。
トランプ政権時代、アメリカ内に広まった“分断”にインスピレーションを得たと語っていた監督さんではあるが、元々あった格差を極大化したのは何を隠そうあのオバマ元大統領なのだ。LGBTQなど人権的な差別に米国民の目をむけさせ、肝心要の貧富格差を裏でこっそり極大化させたのは、リベラルの代名詞このバラク・オバマなのである。現大統領のバイデンはそのオバマの操り人形といっても過言ではないだろう。
そんな民主党政権が、他国の戦争をけしかけるくせに自国ではなぜか銃規制を強化する。その矛盾がアメリカ人の子供たちに良い影響を及ぼす筈もなく、銃乱射事件の犯人を子にもつ老夫婦と、その犠牲になった子供の父母が対面し、事件後一応の和解をするまでを描いた問題作なのである。歳をとってから授かった子供のため家庭でも孤立、人殺しゲームCODにはまったあげく、お手製のパイプ爆弾を製造して警察沙汰に、今回(名ばかりの)友人の銃を借りて事に及んだことが次第にわかってくる。
誰がどうみても“サイコ”にまちがいないガキんちょを野放しにした甘々の夫婦を、話し合いの最中に激昂糾弾に及ぶ殺された子供の父親(ジェイソン・アイザックス)。その奥さんは「あなたたちを赦すことは、あの子を忘れること」と言って、老夫婦を睨み付ける。「幸せになんかなりたくない。学校の成績なんかどうでもいい!」と自分の部屋にとじこもっていった次男をどうすることもできなかった、と老夫婦はただ不毛な言い訳を繰り返す。
済んだことを蒸し返してああだこうだと口論しても、満足いく解決に結び付かないことは映画中盤にしてもはや明らか。そこでこの若き監督はその解決策として、“信仰”による結びつきを無理やりラストにもってくるのである。確かに日曜日に教会に通う人が多い地域では、凄惨な事件の発生率はすくないという話しをどこかで聞いたことがあるが、本作のエンディングはハッキリいって強引すきて映画らしくないのである。
泉にこんこんとわき出る湧水や、騎士とチェスをたしなむ死神、壁に写り込む水面の輝きをもってして“神”を顕在化させようとしたベルイマンの演出に比べると、あまりにも安易すぎやしないか。魂から神が逃げ出してしまったような脱け殻人間に、信仰による安らぎを思い出させるにはどうすればよいのか。バラセンに巻きつけられたテープの揺れごときで、それが表現できるとはとても思えないのであるが....
ぜひ観てほしい!
「対峙」という固いタイトル、銃乱射事件の加害者と被害者の両親が教会で会うという重苦しいストーリー。
かなり身構えて観始めましたが、観終わった後の感情は全く違っていました。
対話を通して浮かびあがる人間の哀しさ、優しさ、尊さ、不条理な運命に翻弄されてもよりよく生きることをあきらめない強さ、、感動があふれて涙が止まりません。
ラストシーンは今まで観た映画の中でも最高に愛に満ちていて、深い余韻に包まれました。。
教会のオープンでカジュアルな明るい雰囲気も素敵。
スタッフの女性や青年も親しみやすく優しい人たちで、答えのない重苦しい悲劇に日常の生活感を添えてくれます。
会合の準備、お花の箱、聖歌隊の歌の練習など、ふつうの生活の一コマにこんなに感動し癒やされるとは。。
全く違った立場にあっても真摯に対話し、たとえ答えは出なくても分かりあおうと努力を重ねることをあきらめてはいけない。
観てよかったと心から思える映画です。
聖歌の練習で泣けた
どこにでもいる普通の人たち
ほぼ4人の会話劇やけど、ひりひりした感じが伝わってきてこちらまで緊張感MAXで鑑賞した。
被害者側もそうやけど、加害者の両親も普通の人のような感じやし、これは止めることができたのか。赦すというのが意外ではあったけど、自分たちが前に進むためにはどこかで折り合いをつける必要もあるからってことなのかな。加害者側の母親の気持ちも分かるし複雑な気持ちになった。加害者側の父親は、ほとんど感情を出さないポーカーフェイスな人という印象やったけど、その分未だ気持ちが整理できないままなんやろうなと思った。
殺人事件の加害者の両親と被害者の両親が4人だけで話し合うというのは...
タイトルなし(ネタバレ)
舞台はほぼ教会の部屋
登場人物も、かなり限られている
実際の事件は、彼らの話の中に出てくるだけ
淡々と進む会話劇
冒頭の神経質なほどの準備から始まり、当事者がやってくる
けれど、しばらくはどちらがどちらの親なのか、はっきりしない
ようやくどちらがどちらの親なのかが分かってくるが、話はいきなり核心に行かず、なんとなくさぐりあうような雰囲気が続く
互いに夫婦間で事前の準備や話し合いが行われてきたことが垣間見えるような、夫婦での牽制が入る
それが徐々に、感情を帯び、徐々に、核心に入っていく
この時間は、当初は、それぞれがなにかに納得したい、答えを得たい、というものに見えたけれど、最後まで観ると、ゆるしを求めていたのだろうと思えた
被害者の親は、憎むことで過ごした時間に終止符を打ち、憎む対象を赦すことを自分に許す
加害者の親は、赦されざることをした息子をそれでも大切な我が子でもあったと思う感情を持つことを自分に許す、こんな悲劇が起きる前に止めることが出来なかった自分を許す
赦しがなければ、つらく苦しい感情にとらわれ続けてしまうから
許すことで、歩き出せるから
でも、それを行うことの難しさ
そんな風に感じた
そして、加害者の親には、やはり責任を求めてしまう気持ちが働いたものの、観ていると、少なくともこの話の中の両親は、ごくごく普通の、どう扱っていいかわからない10代の子供に悩み、手探りで日々を過ごしていたどこにでもいる普通の親、にも見えた
ラストの加害者の母の告白もそう
どれほど自分を責めてきたのかがよくわかる
私の産んだ子はモンスターだった。
6年前の銃乱射事件の加害者ヘイデンの両親(リチャードとリンダ)
被害者エヴァンの両親(ジェイとゲイル)
彼ら4人は6年経ても息子を失った哀しみから立ち直れない。
そんな4人が時間と費用をかけて、ようやっと会う事になった。
ラスト以外には音楽が全くない。
回想シーンも再現シーンもない。
対立する4人がただただ向き合い対話する=対峙
一幕一場の舞台劇のような映画です。
どんなに平静を装っても加害者への憎しみとその両親への怒り。
息子を奪われて、やっと立っているジェイとゲイル。
その日の凶行を現す言葉が映像よりもよほど恐ろしい。
一番冷静に見えたヘイデンの父親ジェイ(リード・バーニー)は、
被害者一人一人の死に様を分刻みで覚えている。
ダニエルは3発撃たれた。2発は頭、1発は心臓。
……机に座って息絶えた。
ジュリアナは脚に2発、1発は膝、もう1発は腱、
……大動脈が撃たれてガラス片が目に入り、
……這って外へ逃げようとして力尽きた。
ヴァネッサは4発撃たれた。腹に2発、頭部2発。
……机の下でうずくまり命乞いをしたのを息子は撃った。
エヴァンは必死で這った。血の跡がそれを現している。
……それでもヘイデンは追ってトドメをさした。
リンダは言う
「私は人殺しを育てた」
☆☆☆
モンスターは一定の確率で生まれると思います。
育てた親になんの責任もない・・・私はそう思っています。
防ぎようがないのです。
どんな映像よりも生々しい。
「2番目はほしくなかった」
「生まれてこなければ良かった・・・」
10人の被害者は追悼式が行われた。
けれど11番目は追悼されない。
葬式も断られたて墓にも苦労した。
この映画で会話のチカラ、言葉の強さを思い知らされました。
役者たちの力量がどんな映像にも勝り迫って来る。
対峙して言葉をぶつけ合い本音を吐き痛みをぶつけた事で、
エヴァンの母ゲイル(マーサ・プリンプトン)は最後に、
決意したように言います。
「あなたたちを赦します」
「ヘイデンを赦します」
加害者家族のリチャードとリンダも、ジェイとゲイル同様に
愛する息子を失った被害者なのだ。
被害者と加害者の夫婦は互いを思い遣り帰路につく。
彼らが少しでも晴れ晴れした気持ちで生きていくことを、
私は心から願いました。
究極の密室会話劇(プライム配信開始されたので必見すよ)
公開していた劇場が少ないのがとても勿体無い良質作品です!
内容があまりにも重過ぎて 鑑賞後にとりあえず椅子から立つのすら呆然としてしまい放心状態になるような内容で、簡単に結論の出ないテーマなので色々と考えさせられますよ。
子供の居る親ならマジで2、3日余韻で何も出来なくなるレベルだとおもいます!
会話のみで回想シーンや事件のシーンが全く無くて
ここまでやるのは凄いですね、普通ならそういうシーンありますから!
あと 導入部分で被害者と加害者と親がどっちかという説明が一切無いから 会話を聞きながら見てる人が探っていく作りも面白かったですね。
あとクライマックスは劇場全員泣いてました(悲悲悲)
対峙はクロースって作品にも近くて加害者と被害者の対話の話というのは同じでしたね。
以前感想書いていてパスワード忘れて使えなくなった お主ナトゥはご存じかの ほうに
詳しく書いてるので 暇な方は是非(ペコちゃん招き猫の写真は一緒)
緊迫感
重いです。とても深刻で重い映画。
ざっくりは予習していきましたが、不要でした。
事前に知らない方が良かったかもしれません。
アメリカでは、残念ながら珍しくない学校での銃乱射事件
6年の時を経て、どちらも息子を失った被害者と加害者の両親がテーブルを挟んでまさに「対峙」する映画
どんな会話になるのかとこちらも固唾を飲み、時に涙しながら見ました。
初めは、理性的にはじまり、魂の叫びがぶつかり合うような緊迫の約2時間
演者の演技力なくしては、成り立たない作品です。
なんとなく、他人事のような加害者の父
精一杯いろいろなことを言っていても、距離があるような・・・
初めと終わりの教会職員のちょっととぼけた感じに少し癒されました。
なんとなく「また?」と遠い国のニュースとして見ていたものが
加害者、被害者一人一人に同じような背景とストーリーがあり、残された家族の苦悩があることを改めて感じた作品でした。
「赦し」の意味 もしかすると「赦す」ことによって、前に進める、解放されるのは被害者の方かもしれない。
後から、被害者の父を演じていたのが、ハリーポッターのルシウスマルフォイを演じた役者さんとあとで知り、役者さんってすごいなあ・・・と個人的に感動しました。
題材は重く、鑑賞後も投げかけられた問いについて考えさせられる一作
米国のある高校で起きた銃乱射事件の被害者遺族と、事件直後に自殺した犯人の男子学生の両親が対面し、事件について互いの思いを語り合う様子を描いた作品です。
題材が題材だけに、楽しい気分で劇場を後にするという鑑賞感はまず期待できず、気分が沈んでいる時の鑑賞は一考を要します。
ほとんどの場面は同じ教会の一室、登場人物もほぼ二組の夫婦に限られているにも関わらず、終始緊迫感の漂う彼らの表情、そして言葉一つひとつの重さに、画面から目を逸らすことが難しいほど。
本作が投げかける問いは、「乱射事件を起こすような人間は”異常”なのか?」、「その異常性を事前に察知可能なのか、その察知と対処の責任を、近親者は負うべきなのか」など、鑑賞後も繰り返し問い直したくなるものばかりです。
「私たちは何かを間違えた。しかしいつ、どう間違えたのかがどうしても分からない」という加害者側夫婦の言葉は非常に考えさせられるものがあります。ドキュメンタリーと見紛うような作りですが、ちょっとした仕草が後の描写に活かされたりと、作劇的な工夫も盛り込まれていて、劇映画としての作り込みも実感することができます。
結末については、犯人像のより別の側面を浮かび上がらせた、という見方と、本筋の明確さをやや損なったという見方など、いくつか見解が分かれそうです。どのような結末となり、それをどのように解釈可能か、是非ともご自身の目で確かめて欲しいところです。
対話による探り合いや究明という普遍のドラマをミニマムに作った傑作
ほぼ時間いっぱい、高校で起きた銃乱射事件の犠牲者の両親と加害者の両親との対面が描かれる。事件の概要も4人の対話が進むうちに徐々に観客に知らされるという構成。
犠牲者の両親側は極力感情を抑え、同じ「子を持つ親」という立場から、何故子が凶行に走ったのか、その兆候に気付けたのではないか、と相手の見解を聞こうとするが、加害者の両親側は、捜査時に話せることは全て明かし終えているという姿勢をとったり、世間からのバッシングの果てに淡々とした態度をとったり、はたまた「子を持つ親」として子を失った被害者遺族の痛みに過剰に寄り添おうとする。
その両者の空回りとすれ違いが冒頭から強い緊張を生み、物語を牽引していた。
凄惨な事件と対話を「誰が悪い」「何が悪い」という論調に持って行くことなく、子の成長においてどこにでもある場面を想像させることで、観客にも事件とその成り立ちを「他人事」にさせない構成が見事だった。
全員が得たいものを得られた時間になったとは言えないかも知れないが、彼らにとって、事件から前に進むためにプラスの時間になったことが救いだった。
点数はつけられません
作品の良し悪しの問題ではなく、
内容的に点数をつけ難い作品でした。
また、ほぼ全編ワンシチュエーションかつ
2組の中年夫婦の対話劇のため集中力が必要不可欠です。
.
.
通常、親というものは精一杯の愛情を子どもに注ぐし、
なにかしら異変を感じれば、原因を追究し
最善の措置をとるべく、動くものだと思っています。
(そうじゃない毒親もいますが…)
.
しかし
何がきっかけで凶悪犯罪に手を染めることに
なってしまったのか、本当に親はその小さな異変に
果たして気が付けるものなのでしょうか。
子どもたちのサインは見逃さないという
絶対的な自信はどこから来るのでしょう。
親を思う子どもほど、気づかれまいとするのではないかと…
未成年の犯罪には親が原因であることのように
言われがちだけれども、それってどうなのかな。と
本作を観て、ふと思った次第です。
.
.
また、これは宗教的な思考もあるかもしれませんが
自分が被害者側の親であれば
とても「赦す」ことはできないだろうと思いました。
当然、加害者家族もですが担任や学校、世の中全てを
呪ってしまいそうです。
ラスト、あの被害者の母親はとても苦しそうに
でも前に進むために大きな決断をし「赦す」と言いました。
正直、自分には何年経過しようと言えない言葉のように思います。
ただ、その分、自分も救われないのかもしれません。
.
.
やはり第三者としての立場でしか観ていないため
安易に加害者側・被害者側、
どちらの意見も理解できるとは言えません。
「手紙」も良かった
時に息苦しさを感じながら圧巻の演技を堪能
アメリカの高校で実際に起きた銃乱射事件の被害者の両親と加害者の両親が、6年後に集まり対話する映画。
観終わった後、しばらく包然と座っていました。
私も同じ母親として、どちらの母親の気持ちもわかるんですよ。
それだけにつらくてつらくて。
ゲイルが「息子を近くに感じたいから、あなた達を赦します。ヘイデンのことも、赦します」と涙ながらに言葉を絞り出すシーンは涙腺崩壊。
憎しみは何も生まないんですね。
この2人は、6年間苦しみ倒して、このためにこの日ここに来たんだ。
でも一方で、加害者の両親も、この6年間どれほどの非難と誹謗中傷に晒されてきたか。
何を言っても、聞いてもらえない事もあったろう。
思春期の悩み?コミュ障の末路?子育ての失敗?
我が子がまさか人殺しになるなんて。
「いっそのこと、息子は生まれてこなければよかったのかもしれない」と、父親。
こんな事、そう口にできない。
どちらも、我が子を愛していた気持ちは同じ。
それだけに、やるせない。
でも、LIFE GOES ON.
生きていかなくてはならない。
ラストに流れる讃美歌のタイミングが・・・
ここで歌声が、その歌詞が、心に沁みる沁みる。
それにしても、4人の演技の素晴らしいこと!
BGMもなく、9割のシーンが部屋の中の会話劇。
誤魔化しのきかない丸裸の作品です。
ブラボー!
緊張感が持続するスリリングな会話劇
ある事件によって息子を失った被害者の両親と、その事件を引き起こした加害者の両親の対峙をスリリングなダイアローグで綴った作品。全編ほぼ4人による密室会話劇となっており、終始ヒリつくような緊張感が持続する作品である。
普通であれば裁判に訴え出るのが筋だろうが、被害者の両親はそれだけでは気が済まなかったのだろう。法の裁きではなく、直接会って加害者側の口から事件の背景や謝罪の言葉を聞きたかったのだと思う。裁定人の計らいで教会の1室を用意された彼らは、そこで初めて対面することになる。
なるべく事前情報なしで観た方が良いと思うので敢えて伏せるが、そこには裁判だけでは単純に割り切ることのできない被害者側の憎しみ、やり場のない怒りが相当強く残っていたことが分かる。彼らの心中を察すると不憫極まりなかった。
映画は二組の両親のやり取りをフラットに描いていくが、中盤に差し掛かるあたりから徐々に夫々が貯め込んだ本音が露わになり激しい口論に転じていく。
被害者側には息子の理不尽な死への怒りと悲しみがある。一方、加害者側にも彼らにしか分からない苦悩があったことが分かってくる。夫々の悲しみ、悔恨、苦悩が約100分間、熱量高く表現されていて最後まで画面に引き込まれた。
監督、脚本はアメリカ人俳優フラン・クランツ。フィルモグラフィーを見ると、M・ナイト・シャマランの「ヴィレッジ」やホラー愛に溢れた「キャビン」といった作品に出演したということだが、申し訳ないがまったく印象に残っていない。そんな彼が初めて撮った作品が本作ということだ。中々どうして、初監督作とは思えぬほど、しっかりとした作品になっている。
全編会話劇というスタイルのため、映画と言うよりも舞台劇に近い作りになっており、演出的な面白みには欠ける作品かもしれない。しかし、演者の細かい所作を漏れなくキャッチしつつ、丁寧に緩急をつけたところは見事で一瞬も退屈する暇はなかった。
また、意味深に映し出される有刺鉄線に結ばれたリボンのカットは、本作で最も創意に満ちたキラーショットと言えよう。様々な想像を喚起させるという意味で非常に興味深く読み解ける。
更に、映画は4人を迎え入れる教会の職員の視座から始まるのだが、これがシリアスな物語に適度なユーモアをもたらしている。観客が映画に入り込みやすくするための第三者的視点という役割も持たされており、このあたりの工夫は実に上手いと思った。
ただ、映画の締めくくり方は教義的な感じがして、個人的には少し安易さを覚えた。そもそも対話の舞台を教会の1室に選定した時点で、これは最初から狙ったことなのだろう。いかにもアメリカ映画らしい。
尚、本作を観て故・小林政弘監督の「愛の予感」という作品を思い出した。「愛の予感」も、事件の加害者と被害者の親が対峙するという物語で、セリフを排した静謐で実験精神あふれる作品だった。セリフの応酬で畳みかける本作とは真逆で、感情を心の奥にしまい込む日本人の気質がよく表れており、両作品を見比べてみると色々と興味深いものが見えてくるかもしれない。
全110件中、21~40件目を表示