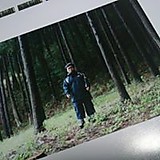怪物のレビュー・感想・評価
全320件中、161~180件目を表示
ヒリヒリして
是枝監督の映画は初めて見ましたが、映像の美しさやカットの妙がとても素敵でそりゃ評価の高い監督なんだなと納得。
映画論は分からないので、ただ自分の感想ですが、シングルマザーにいじめに虐待に教育現場問題、モンスターペアレント、LGBTと詰め込みまくって(それなのにまとまっているのはすごいことなんだと思いますが)、ちょっと疲れてしまいました。
飴のシーンと消しゴム拾うところが違和感。なぜ先生を貶めたのかも考察が浅いのかよく分かりませんでした。そしてこれから小学生になっていく子どもを持つ親としては、そんな嘘つかれたら分からないよと怖くなってしまいました。
湿度を感じる映画
個人的に印象に残る映画って、
湿度を感じる映画だなぁと思います。
全然違いますが、パラサイトを見た時も同じようなじめっとした空気を終始感じました。笑
人の怒り、焦り、後悔、憎しみ…様々な感情が、
役者さんたちの芝居、そして映像を通して湿度を持ってとてもリアルに伝わってきました。
特に保利先生の視点からのシーンでは、
追い詰められる保利先生の焦りや怒りが、流れ落ちる不快な汗を通してとても伝わりました。
人間の想像力には悲しいかな限界があって、
この映画は3人の視点から描かれているけれど、それでも全部を描き切れることは到底ない。
"答えはないからこそ面白い"というありきたりな結末ではなく、観終わった後に
"人間ってなんなんだろう"
"私たちの見えてるものって主観でしかないんだな"と、
ちょっとじとっとした、なんとなく不快な後味が残りました…。
でも、いい映画です。
設定ありきで登場人物が動いているように感じました
是枝監督の映画を初めて見る者の感想です。
前情報等や期待は特に無く、たまたま時間があったので暇つぶしに見に行った形なので、何かしらのバイアスがかかってない公平な目で見れたのかと思います。
序盤は母親視点で物語が進みますが、この時点で母親以外の登場人物(主に学校関係者)の行動がおかしく、理解できないような行動をしています。
中盤から保利先生へ視点が変わった際、この一連の物語を多角的な視点で見せることで物語の全容が分かる映画なのかと思い、この時点でかなり映画にすごく引き込まれました。
あの時あの人はなぜこのようなことをしたのか、次がどんどん気になってきます。
中盤の先生のパートが幾分か進んだ後、これは尺が足りるのかとふと気になりました。
というのも序盤から行動がおかしかったのは保利先生だけで無く、子供や校長等まだまだいたため、どういった畳み方をするのか、少し不安になりました。
終盤子供視点となり、一応の答え合わせとなるようなパートとなるのですが、登場人物の不可解な行動に最後までちゃんとした説明は無く、不完全燃焼で映画は終わってしまいました。
終わってから思ったことはこの映画は中盤私が思い描いていた多角的な視点で物語を追っていくものでは無く(登場人物の行動が理解できるようになっていく物語では無く)、視点によって誰しもが怪物になり得るというような一種の啓蒙的な作品だったのかなということでした。
そう言う作品として捉えたらこういうまとめ方でも少しは納得できるような気がするのですが、それでも登場人物の行動がおかしすぎて終了後ももやもやとしたものが残りました。
特に気になったのは下記
1.みなと君はなぜ追い詰められて行ったのか
一応それらしい描写は見られましたが、なぜ子供はあんな大事件になるような嘘を吐き、またそのことに対して特に罪悪感が無いまま進んでいったのか。
いじめられていた子の方が何かしらの行動を起こすのは分かります。ただこの子は最後まで特に自分から行動は起こしませんでした。
好きな子がいじめられていたからなんとか助けたい、これなら分かります。ただ、みなと君がやったことは保利先生を陥れるような嘘をついただけで、みなと君には全く利が無いような行動でした。
母親からの追及をかわすための嘘としてもおかしいし、物語の根幹とも言うべきこの嘘の動機に説得力のあるものは無かったように感じました。
2.同性愛について
今こういったテーマが流行だからでしょうか、あまり必要性を感じなく、取ってつけたように組み込まれていました。
おそらくこれが子供達を追い詰めた主な原因かと思いますが、これも別に同性愛をテーマにする必要が無く、終盤にぽっと設定が出てきました。なぜぽっと出の設定のように感じたかは単純に同性愛ということが分かったからといって中盤までに散りばめていた謎が解けることが無かったからだと思います。
後、子供の頃って普通に女の子より男の子同士でいる方が楽しいと感じるし、恋心というのも正確に分からなかったように思います。口には出さなかったけど小さい頃って普通に同性と遊んでいる方が楽しいし、自分って同性愛なのかな?くらいのこと少しはよぎることあった人も少なくないのではないかなと思います。
子供の頃の同性愛は大人になってからの同性愛とはまた別で特に珍しいものではなく、追い込まれるような要因にもならない気がします。(人それぞれだとは思いますが…)
3.なぜ先生は怒られている時に飴を舐めたのか
あんなにまともな先生なのになぜ舐めたんでしょう…
4.校長先生はなぜあんな態度なのか
途中までは孫が亡くなって心が壊れてしまったのかと思いましたが、終盤のみなと君との接し方や写真の位置を気にする場面でそれは間違いだと感じました。
最後までこの人の行動は謎です。多分誰が見ても彼女は怪物です。
他にもありますが上記のような中々理解できない行動が散見された為、物語の都合や演出の都合で登場人物を動かした結果、よく分からない物語になったように感じました。
私は上記のような行動に理解ができませんでしたが、人によって理解できるのかと思いますので(実際評価も高いですし)、やはり映画は見る人によって感じ方が全然違うなということを再認識しました。
難しい。
見終えて面白かったです。でもどう伝えれば良いのかが難しい映画でした。
3視点で物語が進んでいき物語により怪物が異なりますが、最後の子どもたちの視点で答え合わせができました。
ラストシーンですが、あの二人はようやく自由になれたんだと捉えました。
さて、作中に出てくる「豚の脳みそ」や「男らしく」、「父みたいになって欲しい」此等は全て偏見から生まれるワードです。このことから私は作品においての怪物は「偏見」であると思いました。
自分の中では怪物の正体が理解できたのですが、これを言語化して相手に伝えるのが滅茶苦茶難しい…何せ偏見って生まれ持った考えであり、そう簡単に受け入れることができませんからね。
う〜ん、やっぱ是枝作品微妙
それぞれの視点からストーリー展開が違って見えたのはよかったけど、
ラスト2人の子供は死んだのか、生きてるのか曖昧な表現だったのでモヤモヤした😅
一番意味わかんなかったのが、
なぜ子供同士の同性愛をもってきたのかですかね😅
カンヌでどれだけ評価されても、是枝監督の作品はな〜んかスッキリしないな😅
タイトルなし(ネタバレ)
気になってたので鑑賞。
それぞれの視点から描かれる出来事。
なんていうか、うまく言語化できんな、、、
学校側がとりあえず最悪ってことはわかるけど
なんかもう、あーってなる
純粋な子供を通して、大人のエゴや願望やらが浮き彫りになり、その結果出てくる歪みみたいなものを見せつけられた感覚なのかな、、、?
なんかもう、本当に学校が最悪すぎる。
でも、それでもあの2人は自分たちで希望を見つけながら生きていくのかな。
なんか、上手いこと言えんな。
とりあえず、何気ないシーンで子供達の逃げ場が失われてることが説明されるのが辛いね。
音楽ももちろん良いし。
あぁーってなる作品でした。
90/100
最高です!
これは本当にピュアな恋愛物語なのです。ただみなと君は人を好きになっただけなのです。大人は固定概念で勝手な想像をしてしまいます。それは仕方のないことで、誰かが悪いわけではありません。(でも中村獅童さんは本当に悪いです。)大人目線から入り辛い物語に見せかけているから、ラストの2人が明るい緑の中を叫びながら走っていく楽しそうな姿により感動するのです。そのギャップが凄すぎるのです。私は映画館で泣きました。是枝監督、坂本龍一さん、坂元裕二さんのいい所が全部出ていると思います。最高です!
誤認
凄い作品だった。
エンドロールが終わり、館内が明るくなるまで席を立てなかった…呆然としただただ脱力してた。
ラストカットを見ながら浮かんだ言葉は「ごめんなさい」だった。
タイトルの「怪物」
前半に感じたソレと、ラストに感じたソレは全く違うモノだった。同じ言葉で表せるも本質が違う。脚本の内容ともリンクするとても優れたタイトルだった。
冒頭から兎に角惹きつけられる。
というか…目を背けられないのだ。ショッキングな事柄ではあるのだが、ほんの些細なキッカケで起こりうる事ばかりで、身近に潜む事ばかりだ。
なんという狡猾で優れた脚本であろうか…冒頭の数分間で、ものの見事に意識が作品に囚われてしまう。
この社会に「怪物」はいる。
ずっと昔から。でもここまで育ってしまったのは何が原因なのだろうか?誰のせいなのだろうか?
…おそらくならば大人とカテゴライズされる人達だ。
育てるにあたり与えた原料は色々ある。
保身だったり、体裁だったり、先入観だったり、隔離だったり、噂だったり、無言だったり。
社会を滞りなく収める為の術を餌に「怪物」は育っていく。それこそ宇宙のように無限に拡張し続ける。
何回も食い止める機会はあったはずだと考えさせられる。瑛太氏を通して語られるソレらは、会話や対話の必要性を訴えてくる。
誤解と先入観が産む『思い込み』
点在し独立する立場による視点を前半は描いていく。
安藤さんからの視点を思えば違和感だらけだ。
彼女は「何故?」を問いかけ訴える。その解明を妨げる『前例』と『マニュアル』彼女は一方的にモンスターペアレンツの烙印を押される。
そして瑛太氏は責任を負わされ解雇される。
何も解明されぬまま1人の人間の運命が狂わされる。
そこから展開される瑛太氏の視点。
表面化されない事のオンパレードで、彼の行動原理が説明される。冒頭に出てきた「ガールズバーに居た」って話すら、火事の時に遭遇した生徒の「近くで先生に会ったよ」から派生した『噂』なのだろう。
それを吹聴した途端にその正誤を担うのは事実よりも、語り部との関係性に転嫁される。
勿論、その『噂』に真実味を与えてしまう人間性もありはするが、それこそ曲解でしかない。
瑛太氏は瑛太氏で、結婚まで考えている彼女から間違った『先入観』を植え付けられる。
各々が振り翳している斧は『自己防衛本能』と『正当性』なのである。
次は校長の視点なのかなと思っていたのだけれど、展開されたのは当事者である子供達の視点だった。
あぁ、なるほど、と単純な事を複雑化させている存在に気付く。大人である僕達だ。
子供の感性を僕達はいつの頃からか亡くしてしまっている。子供達の間で交わされるそれぞれはとても尊いものから発生している事ばかりだ。
思い遣りや、友情や、冒険心やら…だけど、その視点を大人達は共有出来ないから、自分達の納得できる理由を押し付けてしまう。それは親としての責任感でもあるのだろうし『答え』を無理矢理にでも見つけないと不安に耐えられないのだろうとも思う。
昨今、浮上している性同一障害を絡めているのは、流石と思えてしまう。
そして、ふと立ち返る。
コレが現代の現状なのか、と。
なんという悍ましい世界を、今の子供達は生きているのだろうか、と。
大人達が導き出す最善策に子供達の意思は全く反映されてはおらず、むしろ蹂躙されてるんじゃないかと思う。子供の視点からすると『大人達』こそが怪物だ。
子供達がやってる事は、今も昔もそうは変わらない。秘密基地を作ったり、友情を育んで、今に一生懸命で。
ただ不憫で仕方がないのは『親』から『普通』を押し付けられる事だ。
湊は性同一障害を。
依里は、きっとIQが高すぎるのだと思う。
『普通』なんて曖昧な価値観は唾棄した方が賢明だと俺は思う。周りと較べる事でしか生まれない価値観であるといい加減気付くべきだし、そんな事に左右される程愚かで悍ましい事はない。
『普通』なんてものは管理する側が管理しやすいようにする為に拵えた檻でしかないのだから。
作中で明確に語られる悪意は『親』と『イジメ』だけだと思う。
その他のモノは悪ではない。
『イジメ』の主犯である彼にも『親』によって労働を科せられ自由を抑制されるストレスの源が提示される。
新聞にチラシを挟み込んでるのが彼ではないかと思うのだけど…違うかな。
なんせ、今作には発露に至り関与する原因なり源が無数に散りばめられてるような気もしてて、2回目を観たら驚く程緻密な仕掛けにぶったまげるんじゃないかとも思ってる。
土砂に埋もれた窓を親と先生が必死になって取り除こうとする絵が印象的だった。
掻き出せど掻き出せど、泥は流れ込み、どんなに踠いても泥が無くなる事はない。コレはなんの揶揄なのだろうか?現状に抗い必死に子供達を救い出そうとする人達が置かれている環境そのものなのだろうか?
とめどなく溢れ出す川の防波壁なのかな?それにも無力さを感じとってしまう。
そしてラストに至る。
台風一過。
快晴の眩い光の中に駆け出す湊と依里。
青々と生い茂る草っ原を、笑いながら走ってゆく。
彼らが走っている場所は『大人達』によって危険と判断された柵の向こう側ではなかったか。
実に逞しく、実に楽しげで、彼等を取り巻く様々な厄介事をまるで歯牙にもかけず、一心に突き進む。
ここに至り、タイトル「怪物」が示す事に気付く。
恐怖や脅威を内包する存在も「怪物」だし、突出した才能を有し前人未踏の記録や功績を残した者も「怪物」と呼ばれる。
後者は傑物と同意であると思うし、すべからく一般の人々が想像する理解の範疇の外にある。
全ての子供達には、後者である傑物としての「怪物」になりうる可能性があり、大人達が張り巡らした鎖を破壊し続け成長する「怪物」でもある。
そんな希望を抱いたラストでもあった。
そして、こんな社会にしてしまった後悔に苛まれた。俺もそんな社会を作った『大人達』の一員だからだ。
なので…俺はこの作品を作り上げた怪物達のせいで、呆然とし、エンドロールが終わって館内が明るくなって尚、席を立てずにいた。
「次回上映の為、館内の清掃を行います。お客様におかれまして速やかに退出いただきますようお願い致します。」
映画館のスタッフが毎回言うのであろうアナウンスを初めて聞いた作品にもなった。
今年のアカデミーは今作が総ナメだろうと思われる。
坂本龍一さんの奏でる音楽は、凝り固まって沈殿するドス黒い何かを、解きほぐすかのように優しく静かに、染み渡っていくようであった。
🔳追記
他の方のレビューを読むに子供死亡説なる解釈もあるようだ。なるほど、ソレも無くはないと唸る。
考えてみると台風一過の時間経過があり、廃バスから脱出してくるってのは不可解なタイミングでもある。
だとするなら、そんな未来を摘み取ったのは誰だってオチにもなりはするのだが…現代に蔓延る怪物は、その全容を把握できないほど巨大で邪悪で凶悪な代物で、無慈悲な公平さを擁し、突如襲いかかってくるのであろう。
僕達はなんてものを産み出してしまったのだろうか…。
死亡説に感化された訳ではないのだが、その方向の感想もしたためずにはおられなかった。
怪物=誰が作ったか分かりもしないような固定観念を土台とした同調圧力
「怪物だーれだ」というセリフが繰り返される印象的な予告編が印象的で、半年前から観ることを楽しみにしていました。
怪物は、一言にするなら「誰が作ったか分かりもしないような固定観念を土台とした同調圧力」でした。
・既存の体制保持のための無理筋な対応
・噂で動く田舎の凝り固まった人間関係
・家父長的考え方が社会に浸透しているせいで、暴力親にも認められる親権
・片親への偏見
・同性愛への偏見
・いじめ(映画ではいじめ主導者が教室の空気を支配)
自然や街の中を飛び回る子供たち、日本の小学校に通った人なら誰しも懐かしく感じそうな校舎(吹き抜けなど、モダンな構造でしたが)、なぜか安心してしまう廃列車、素晴らしい映像でした。
そして作品の中心的役回りとなっている子供の。常にポジティブな言葉に感動しました。
ラスト、列車は銀河鉄道になって宇宙に向かったんだと思いました。
怪物はどこにいる?
是枝監督って子供の自然な演技を引き出すのが
改めて上手だなと感心させられました。
この子役黒川想矢さん、柊木陽太さんは見事でした。
また、この映画の冒頭部分の輪郭を作った安藤サクラさんの存在感と迫力、
対照的に校長役の田中裕子さんが奥歯に物が詰まったような演技が絶妙でした。
役者陣だけでなくこの物語の脚本、構成も絶妙でした。
物悲しく優しい坂本龍一氏の音楽と諏訪湖の風景が
より心の内側に染み込んでくるようでした。
子供のいじめ。子供は残酷です。
私もいじめられたことがありました。
私の親友は同調圧力に負けて、私をいじめ、
私は裏切られた気持ちになりました。
映画のワンシーンにもありましたが見ていて
気が気でなかったですがこの二人の友情は
堅固だったようで、微笑ましかったです。
子供の世界って大人にはわからないなと
改めて思い知らされました。それに嘘もつくし。
その後はどうなったのでしょうか?
豪雨の中、廃電車(秘密基地)から抜け出した二人は
やがて野に放たれ、遠くに線路を見つけました。
それは希望の線路に見えましたが…
「怪物だーれだ」
不思議とこのフレーズ、予告編観て以来
毎日ひとりごとのようにつぶやいてます。
印象的で強いフレーズなんですよね。
怪物とは一人一人の心の奥底にあるもの。
だから答えも違うもの。
なのかもしれません。
メタファ
怪物とは誰のことなのか
そして
観客はいずれ気付く
人ではなく
認識違いの隠喩なんだと
隠喩がいくつかあり
ストーリーのキーに
豚の脳→特異なものの象徴
うまれかわり→現状の環境からの脱出
鏡文字→逆側への思い
三つの視点
母親、教師、子供
の三部構成により
同じシーンでの行動の意味が
徐々に明かに
大切なものを守るために
登場人物がそれぞれ
嘘をつき
まずいことには
沈黙で蓋をしてしまう
その守りたいものの代わりに
差し出すものが何なのか
順番は意見が別れると思いますが
最後の生贄は
本作では教師でした
友達 〉学校 〉いじめ 〉保利
本作で核心を得たのは、
前半、死んだ目をしていましたが
後半は血の通った言動をみせた
校長の言葉
「誰かじゃないとつかめないもの
ではなく、
誰にでもつかめるものが幸せ」
と。
人の根っこの部分に触れる作品で、
教科書にはのっていない
社会の機微に溢れた作品でした
起こっている現象の意味を
読み解く力や知りかたが
身についていれば
自分や周りの人が
少しでも不幸を回避できるのに。
といつも外野が後から…
「怪物だーれだ」認知の歪みによって、誰しもが怪物になりうる
シングルマザーの早織、担任の保利、星川、麦野の子ども達2人からの視点から徐々に謎が解き明かされていく。
本作が面白いのは早織の視点に立てば、生気が抜けたような校長や、普通では考えられないくらいのおかしな学校の対応。とにかく先生達が気持ち悪くて、腹立たしかった。
それが不思議なことに保利先生からの視点で見ると、早織がまるでモンスターペアレントのように映ってしまう。「なーんだ、保利先生、普通にいい人じゃん、可哀想」ってなってしまう(しかし、学校側の対応には憤りを感じる)。
始まったばかりのあの不気味な感じも、時間と共に少しずつ霧が晴れていく。
保利先生、校長先生がここまで違うのは、見る人の視点によって全く違うということを表現してのあえて誇張しての演出ではないだろうか。前半の保利や校長は早織にはそのように写っていたと。
それぞれのシーンがそれぞれの視点でこんなにも変わるのかと、その構成や演出に唸らされる。
その人の視点によって人は誰しも“怪物”になるし、“怪物”として他人から映ってしまうのだ。
そしてもう一つのテーマとして描かれているのはマイノリティ、同性愛。このテーマをついに子どもに持ってきたかと!!とはいえ、最近このテーマ扱い過ぎでお腹いっぱい感はあるけれど。
私が思う本作の1番の魅力は、一つの答えがないところ。
結局のところ放火犯だって、校長が孫をはねたことだって、作文の頭文字の言葉の続きも、星川くんのお父さんのことも、そしてラストの2人の行方も、答えはない。全て観る人の想像に委ねている。
余白を沢山作ってくれることで、私たちは沢山想像して、作品について考え、語り合うことができる。
それにしても、田中裕子の名演にはあっぱれだ。冒頭の不気味な顔や、音楽室で管楽器をレクチャーするシーンとかめちゃくちゃ痺れた。表情で語るとはまさにこのこと。
息を呑むほどの諏訪の景色も美しかった。
そしてエンディングで流れる坂本龍一さんの美しくドラマティックな音楽に涙が流れました。
巧みな演出にぐいぐい引き込まれた2時間だった。
怪物!?
観終わった後、「怪物!?」って首を傾げる。
それを題したのも、あえてのことかしらとも感じられた。
そもそも映画の内容に対して論ずることなのか!?という気持ちでいる。
と言うのも、今の日常を客観視でみたような感覚だから。
私自身の日常にも、映画の主となるテーマは違えど、コミュニケーションの掛け違いで受け取り方が異なり、思いもよなぬ方向に出来事が進む。
そのため、日頃の出来事とかさなり、自身もであり周りもであり、その要因を映画を通じて見えてきたように思えた。
どう普段の私生活に落とし込めるのか、、、。
物語に対する内容より、通じて日常の出来事に対して、ディスカッションすべきその取っ掛かりを感じた作品であったと思う。
最後に私にはまだ子供はいないが、映画の子役のような感情など芽生えたとき、私は子供の気持ちを解放させ、生きやすくその感情のままでいいのよ!って言ってあげられるのだろうか。問いかけが始まる。
実は構成に甘さを感じた
あそこまで教師を貶める理由があったのかな?
その教師は日記から何を読み取ったのかな?
飴をなめるのは前後とも、あの場での行動とも合わない。
カンヌで脚本賞を取った作品だけど、実は雰囲気で強引に押してるところがある。
ラストも何か結論からはぐらかしている気がする。
ホモセクシュアリティな感情と人間の幸せとは
この作品は、安藤さくらが単純に教師の子供への暴力(本当は暴力ではない)を、勇気凛々と解決していくストーリーと最初は思っていましたが、途中からその想像は見事に打ち砕かれました。結論を言ってしまえば、本当の主人公である2人の少年のホモセクシュアリティな感情が、嘘を誘発し、引き起こした人間模様だと私には思えました。いじめ問題をさまざまな視点から見ると、真実は全く違うのです。その不思議なストーリー展開は、脚本家の面目躍如なのでしょうか。物語が進行していくに従って、真実が全て明らかになっていくところは、まるで鮮やかな謎解きのようです。時間軸は何度も引き戻されて、これでもかこれでもかと真実を明らかにして行きます。つまり安藤さくらの正義も、永山瑛太の正義も、全て意味を持たなくなるほど昇華していくのです。怪物というテーマについても、出演者たち全てが怪物に見えましたが、最終的には怪物でもなんでもないのです。ただ、全員が縁起の法則によって絡み合い、感情をぶつけ合い、時には憎み合ったり、罵り合ったりしていますが、結局全ての事象はなんの意味もなく、ただ、それを見る人が、幸福だの不幸だのと判断しているに過ぎないということを、この作品では教えてくれている気がしました。ラストの、少年たちが走り回る姿は、青春の喜び、至高の喜びに満ちていましたが、これはどんな人の人生も、完璧なのだと示唆してくれているように思えました。
追記 田中裕子のセリフ。「誰もが手に入れられるものが本当の幸せ」。含蓄のある言葉です。
後半が残念
怪物はいなかった
是枝作品だから結局そうなるんだろうなと思ったけど。瑛太目線の中盤まではすごく面白かった。後半はダレてきて、なんとか小さい方の子役の演技力でもった感じ。
中村獅童がいい味だしてたからもっと掘り下げて欲しかったなー。こどもを虐待する理由が(自分は学歴もありエリートだったのに妻に逃げられ酒におぼれ、頼みの子供が同性愛者なのが許せないから?)もう少しほしかった。
個人的に、是枝作品の一番の怪物は「誰も知らない」のYOUだと思う。
追記
見終わったあとはこんな終わりか。という感じだったが、あとからチクチクと色々なシーンを思い出す。一度見なのに内容を鮮明に思い出せる作品になった。
怪物だーれだ?
登場してくる人たち、それぞれに思いや正義があって、怪物な芽も持っている。
本人の知りうる限りでは、普通なことも違うところからみたら、筋違いでしかないことも。
そんなあり得る日常を演じている俳優陣が素敵。
音楽やごく自然な風景もいい。
それぞれの人物のスクリーンには出てこなかった裏設定を考えると、怪物になってしまう原因もあると思ったり。
いろいろな視点で思ってみるという、鑑賞後の楽しみをいただきました。
だって人間だからね
観終えた後でもモヤッとした霧が晴れなかったのはヨリ君の父である中村獅童、ホリ先が自宅に行った際「あんた大学は?」と尋ね、自らを「前はXX不動産(?)だった」と語るプライド臭プンプンの男が自らの子供を「バケモノ」だと言い、妻は何処へ?そして玄関のチャイムはガムテで塞がれ、最後にはヨリ君はバスタブの中痣だらけでグッタリ、御本人は暴風雨の中路上で酒を煽る。うーん、子供のどこにバケモノを感じ、なぜ虐待に至ったのだろう?ここの描写はもう少し丁寧にしてほしかったな。
まあ、それはさておき作品全体を通じ「人間ってそうだよなぁ」と思わせる象徴は高畑充希さんの有り様だったと思います。優しい言葉をかけているようで実は不干渉、自分に嫌なことが及んできそうになれば逃げるに限る。
誰もがそうですが、心無い言葉や根拠のない憶測を口にしたとき、大概は「いやいやいや、そんなことありえないでしょ」と返すのだろうが、例えば「ホリ先は火事の時ガールズバーにいた」・「実は孫をひいたのは校長」・「ホリ先が階段から突き落とした」・「お前女みたいだな」なんてことがどこかのタイミングで多数の意見になった途端、それに異を唱えるのではなく黙り込む、黙示の承認をしてしまうのが人間だからね。
そう思ったら、今作のようなお話は未来永劫我が国では起こり得るのだろうなと、ちょっと虚しさが拭えなくなるものを観させてもらった気がします。
さて、ラストシーンですが、校長とラッパを吹きあったミナト君が「自分はありのまま、嘘はつかない」と踏ん切りをつけヨリ君の家へ行き、二人の秘密基地で一夜を過ごした翌朝「ガコッ」と開けたドアから駆け出す、ああ、子供二人には明るい光が差し込むのか、そこだけでも救いがあった。なんてスクリーンを見つめながら思ったのですが、帰りの道すがら、どうにも台風一過の風景にしては風景が泥だらけじゃなくお花畑感満載だったので、これは別の世界に行ってしまったのかもしれないなと考えを改めたのですが、それよりも前の中村獅童の路上飲んだくれシーンとヨリ君のバスタブグッタリシーンもあったから、まだまだ別の展開もあったのだろうか、受け取り方はそれぞれにお任せします、7日もしれませんね。
ワタシ的には「どうすればよかったのだろう」と考えるのではなく「日本人の性で、発想の大転換がない限りこの手の出来事はなくせない」だろうと無力さを感じる作品でした。
全320件中、161~180件目を表示