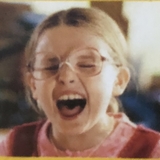怪物のレビュー・感想・評価
全687件中、121~140件目を表示
丸投げされたラストシーン
湊の母親への告白で担任保利と学校への憎しみを見せた後に保利目線での検証するように時間が戻る。実際これが真実なのか?保利の自己弁護の映像では?あれっこのプロット3番目の殺人で使ってたんじゃないかな。それとラストの投げっぱなところ気になった。豚の脳ミソでも生きずらく無い世界に変わったって事?よくわからん?結論是枝氏は合わん。
「怪物だーれだ」と言いたくなる
視点が変わればここまで印象が変わるものなのか。 息子が学校でいじめ...
視点が変わればここまで印象が変わるものなのか。
息子が学校でいじめられているような雰囲気で始まり、どうやら担任に問題があるようだと。
学校に行ってみれば実際にこの担任が相当におかしな人間で、母親が怒るのももっともだ。
ところが担任の視点に変わると、意外に普通の人間ではないか。
児童への接し方も特別問題があるようには見えない。
まあ、保護者との面談中に飴をなめるのはあり得ないが。
そして、息子の方が実はかなりの問題児のような感じになっている。
さらにさらに視点が変われば、息子にもおかしな行動を取る理由があり・・・・。
二転三転で考えさせられた。
そして、結局何が怪物なのか。
田中裕子演じる校長もなかなかの怪物だったが、中村獅童演じる友人の父親が一番の怪物だというのが私の感想。
思い込みが怪物を生み出す
構成が巧い。脚本が巧い。 でも、技巧に走り過ぎたせいか、先生たちの...
二つ目の視点までは面白かったけれど
3本の軸による物語
シングルマザーの沙織は息子の湊がある日、
担任教師に暴力を受けたと思い学校へ問い詰めに行く。
その後、担任の保里の物語へバトンが渡され
息子の湊へ受け継いでいきストーリーの本筋が明らかになる。
「怪物」だーれだ、と語る二人の子供。
思春期になる彼らは大人や周りの同級生たちに
知られたくない事実を大人を巻き込んで隠していく。
ラストシーンがどうなったのか、という部分が
この物語のキーになっているが湊がその答えを答えていると考えている。
ミスリードの多重構造として綴られ、途中までは
こうなんじゃないか、と思う部分が全て覆される。
ある意味、タイトルさえもミスリードを誘う文言であり
2時間という時間内で同じ軸の物語を3層で描くが
退屈することなく見事な演出力で進みきる。
人は自分でない誰かを悪者にして社会を生きていく。
決して一方向からの視点で判断してはいけないのだと考えさせられる。
アイドルタレント起用や漫画映像化の多い邦画の中において
今一番光り輝く監督である。
わからなかったです。
雰囲気でカバーしてる感じ。
視点を変えることで、見え方が変わる…
っていうのをいいことに好き放題やってる感じがした。
いやいや、さすがにそうはならなくないか?
みたいなシーンが多かったな。
時系列に全部並べ替えたら違和感を覚えたことの原因が究明できる気がする。
というわけであまり好みではありませんでした。
前半と後半の振れ幅
あのラストをもってハッピーエンドと受け取りたい
もう、思い出しただけでも泣きそう。エンドロールが終わっても泣きっ面が直らなくて、油断すればまた泣きそうで…。とにかく素晴らしいの一言。是枝作品の中でも断トツの傑作かなと。
坂元裕二氏がカンヌで語っていた「自分が加害者だと気づくのは難しい」視点、それを秀逸な点で浮かび上がらせる。奇妙な会話と不気味な輪郭におどろおどろしく感じていたはずが、その渦の中心から見える景色がこんなにも違うとは。足りない想像は簡単に創造出来ない。だからこそ、広がった景色に驚くのだと思った。
やはり今回も、というべきなのは、子供が持つ未熟を是枝監督は愛している点だと思う。小学生特有のイジり、といえばそれまでで、大人は年々それを拒む。それはきっと、単純化を求めすぎた大人故の弊害だ。それを3つの視点を繊細に描くだけでなく、三原色が重なった時に色が変わるように、その真実も変えてゆく。矛先に伸びた影はあまりにも残酷で美しく、圧倒されるばかりだった。
安藤サクラさん、永山瑛太さん、そして子供2人の視点から描きながらも、それぞれが抱えた正義も共鳴する所がまた突き刺さる。張り詰めた糸をそっと撫で下ろして観ていた分、涙腺となって溢れたのかもしれない。
ラストシーン、絶対に忘れることは無いと思った。怪物とは何か、カンヌの賞がこの作品に与えた意味も含め、僕はそれをハッピーエンドだったんだと受け取りたい。
子どもが傷つくのがただただ辛かった作品
全687件中、121~140件目を表示