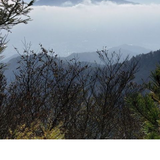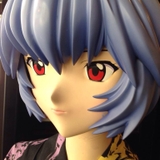ゴジラ-1.0のレビュー・感想・評価
全2054件中、1001~1020件目を表示
ゴジラ映画として適当に作っているとしか思えない。
総合60点位、
ゴジラマイナス1のネタバレ有りレビューです。
ネタバレされたく無い方は読まない事をお勧めします。
では始めます。
大まかなストーリーラインは俺の好みで大好きです。
ゴジラを題材にしつつ反戦を主題のテーマにすえ、主人公である敷島の戦争を終わらせ、戦後を踏み出す為の物語として作られただろう本作。
ストーリーラインのおおまかな流れやワダツミ作戦。
戦艦高雄や響と雪風に震電まで使うのは俺好みで好きです。
ゴジラを深海にまでガスボンベで落とし一気に浮上させ倒す。
あの世界の当時の日本として、ゴジラを倒しうる最高の作戦を立案できてる。
ここまでの発想力やドラマの流れは最高に大好きだ。
推定二万トンのゴジラを海底に落とし引き上げる。
特撮としての戦い方として、当時の日本でやれそうな作戦として壮大で面白く最高だ。大好きだ!!
ストーリーは決して悪く無い。
だが、圧倒的にゴジラ作品として細部に詰めが甘かった。
それはゴジラ特撮映画好きからしたら、適当に作ったように映る程に…。
ドラマ部分と特撮部分に分けて解説していこう。
先ずは特撮部分。
ゴジラの説明画像の圧倒的な少なさ…。
これはいただけない。
ゴジラが泳いでいるシーンを俺は見れて無いんだ…。
俺は見落としてしまった?
ゴジラはどうやって泳いだ?
シッポを横にくねらせて?それとも縦にくねらせて?
後ろ足と前足の位置は?動かしてた?畳んでた?
ワニのように?イグアナのように?
足のつかない海面ではどうやって体を維持してた。
ワダツミ作戦の時、ゴジラのどの部分にワイヤーとガスボンベはどう巻きついた?
海中へと落ちるシーンはどう落ちた?もがいた?暴れた?
引き上げる時のゴジラは頭が上?下?
俺にはそこがまるで分からなかった。
他のゴジラ映画でも泳いでるシーンは殆ど無かっただろ?と言われるかもしれないが、本作は海上でのワダツミ作戦がメインの作戦となる。そこらの画をおざなりにしてはいけない。
何もゴジラをもっと映せと言っているわけではない。
ワンカット3~5秒程の説明画を要所要所に細かく入れておけば分かるものの…。
細かいゴジラの画が全然足りてなさ過ぎて、ゴジラの実在感まで無くなって薄っぺらい存在になってしまった。
山崎貴監督はドラマは作れるが、特撮映画を撮る為の妄想力と想像力と特撮脳が足り無いと断言出来る。
それを如実に表していたのが。
ワダツミ作戦でゴジラが海底へと沈み着底する瞬間で見てとれる。
ゴジラを直立不動のままで海底に着底させてどうするのっ!?
それまでゴジラは海の中を沈みゆくのに何もせず直立不動のままただジッとしていたの?
ゴジラに演技させる事も出来ない想像力と特撮脳では、ゴジラの存在感は薄れるばかりだ。
他にもゴジラを誘導する為の重要な飛行機だろうに1機しか飛ばさなかったり、ワイヤーとガスボンベでゴジラを沈めるのに、体格と全長を考えたら底引き網状にした方が良くはないか?とか。
どうも、ワダツミ作戦に現実感と人々の真剣さ必死さを持たせ、特撮として見せる事が出来てなかったように感じた。
特撮映画って誇大妄想レベルの大ウソを、真実味や、リアルさ、ソレッぽさ、で虚飾して現実感を出す映画だと思う。
その為には怪物側の演技も演出も必要だし、作戦を遂行する側の真剣さ、そこに生きる必死さが、現実感を一つ一つ作っていくんだと思うのよ。
その真剣さと必死さが映画全体からイマイチ感じられない。
これもこの映画にのめり込めないマイナス要素になってる。
ゴジラを誘導する大事な任務を敷島の震電1機のみに任せるのはどうなんだ?
その1機が潰されたらワダツミ作戦自体が台無しだろ?
震電を更に2機飛ばしても良いし、事実を重視するならそれがゼロ戦でも良いし、ゼロ戦もない設定ならセスナでも良い。
ただ1機だけに任せる作戦では絶対に無いはずだ。
ゴジラを海底から引き上げるシーンでもそう。
タグボートの数を何艘も集めてあっても、その小さな船体ではどこか真剣さ特撮として壮大さにかけチープにしか見えない。
特撮でウソをつく時は大きく大胆にされど繊細に丁寧につくのだ。
小型のタグボートで数を集めるより、さらに戦艦なり、なんなら冒頭部の兵員輸送船なりを数隻集めてきても良かったのでは?
更に言うならば、この時にワダツミ作戦をもう1回しかけ、ゴジラをさらに海底へと叩き落として船を連結してゴジラを引き上げた方が特撮としては見応えがあったし、最後の特攻でゴジラを倒せたのに説得力にも繋がっただろう。
彼らは本当にゴジラを倒したいと思って、最善の行動しているのか?
そう疑問に思えてくる部分がドラマ部分でも見てとれる。
では次にドラマ部分の解説。
やたら気になったシーンが…。
ワダツミ作戦の前に艇長の秋津と学者が、見習の水島を置いてゆくと告げるシーン。
水島はその場に立ち止まり「何でですか!?なんで連れていってくれないんですか!?」と
大声で質問するシーン。
演技として、あれが最良なの?
秋津と学者のセリフ回しはあまりに古臭いし。
水島は独自に行動し数多のタグボートを従え駆けつける程の男なんだろ?
だったらあの立ち止まってただ大声で質問するシーンで良かったの?
二人に追い縋るような必死さも真剣さも無いのに、あんな大胆な行動が独自に本当に出来るのか?
人物像と行動がどうもチグハグに見えるシーンだ。
次に敷島が震電の整備を橘に任せたいシーン。
整備の橘が見つからず、震電の整備が一向に進まない。
それを見た学者が「整備員は他にもいます」と敷島を説得しようとするのに、敷島は橘にこだわりこれを断固拒否する。
行動の整合性を加味するならば、敷島はゴジラを倒す事よりも…。
ゴジラへと特攻し自らの戦争を終わらせたいのだろう。
その為の爆弾を積ませる為に、自らを憎んでいるだろう橘に固執した。他の整備員では罪悪感に苛まれるからだろう。
それは分かるし敷島からしたら、特攻するただこの一点での最善手なんだろう。
だが、その前段階の悪辣な手紙でおびき寄せる下り含め必要か?
ゴジラが憎くて自らは不甲斐なく悔しくて仕方ないんではないの?
橘に固執し過ぎて、震電を整備出来ないままゴジラが来たら意味が無いだろ?
更に言えば、震電の整備員を橘ふくむ3人しか揃える事が出来なかったのは演出としてどうなの?
ゴジラがいつ来るか分からないから急いでるんだよね?
他に整備員はいるんだよね?なんなのこのチグハグさ。
敷島のエゴのみが全面に出され、私はあのシーンはまったく共感出来ない。
で、1番疑問に思ったのが…。
ラスト。
死んだと思った典子さんが生きていた事が分かり会いに行くシーン…。
まったくもって感動出来ない後味の悪いラストだ。
純粋に運良く生き残っていたなら、あまりにご都合主義的展開で萎えるし蛇足。
首の黒いアザが考察されてるようにゴジラ細胞で、それによって助かって生存していたなら…。
敷島の戦争がいつまでも終わらない事になってしまうではないか。
こちらだと映画のメインテーマ、戦争を終えるからは大きくズレてしまう。
ゴジラは死んで無いと思わせるシーンは、その前の海中へと沈んでゆく半壊のゴジラの蠢く塊を見せてる事で成立している。
どう考えても黒いアザは、敷島の戦争はいつまでも終わらないぞと見せたい演出にしか見えない。
敷島をさらに苦しめてどうしたいの?
あのラストよりは、銀座のゴジラ事変で確実に慰霊碑が出来るだろうから、その銀座慰霊碑に明子ちゃんと二人で詣る姿を見せ歩き出すような終わらせ方のがよっぽど自らの戦争を終わらせるストーリーラインとしては納得いく。
私には山崎貴監督が見せたい画、撮りたい画、思いつきの画だけを撮っていただけで、キャラの整合性や自らのテーマすら無視し。
感動の押し売りをしたいが為に適当に作ったようにこの映画からは感じた。
まとめ。
ゴジラマイナス1は、ストーリーラインは良いのだ。本当に良いのだ。ゴジラのCGも決して悪くはなかった。
だからそれだけで60点は出せる。
だが、物語の演出と見せ方、特撮があまりにも下手過ぎる。
どれもこれもチグハグだらけの中途半端に作られてて見てられない。
私には、何度も見たいと思えるレベルの映画ではなかった。
203㎜砲で撃たれて大きなダメージを受ける辺りはゴジラも生き物なんだなと感慨深い
シナリオも特撮も3DCGも役者さんもスタジオセットも非常に良くてずーっと集中して感情移入して見続けられましたし最後の30分はずっと涙ぐんで観続けた映画は初めてかもしれません。
そんな素敵な素晴らしい映画ですが一番印象に残ったのは重巡高雄とゴジラの戦いでした。
先ず数発の20㎝砲弾で打撃を与え、ゴジラに圧し掛かられても転覆せずに逆に至近距離からの砲撃で深手を与えた高雄に感動していました。もし魚雷を搭載していれば接近してくるゴジラに撃ち込んで砲弾とは比べ物にならない大きなダメージを与えてその時点でゴジラを葬っていたのではなどと考えてしまいました。まぁ、一旦武装解除後なので92式魚雷までは供給されなかったのでしょう。
シン・ゴジラのゴジラは通常のあらゆる火力に無傷でしたがこちらのゴジラは米海軍の複数の重巡洋艦、あるいは40cm砲を搭載する戦艦で排除できるレベルだったというのも時代背景を受けた強さの調整だったのだろうと思いました、
ゴジラ映画でやらなくてもいい
非常にガッカリ
星2なのはゴジラが良かったから
通称バーニングゴジラの造形が好きなので
今回のゴジラは結構好みの造形でした
総評
ゴジラの名を借りた
チープな人間ドラマを詰め込んだ映画
ゴジラでしなくていい
メッセージ性は全くなし
詳細
主役のゴジラに対しての深掘りがない
基本設定の放射能で変異が全く関係ない
申し訳程度にクロスロード作戦の原爆実験を受けて大型化したと思わせてるが
それまでに出てきた小さなゴジラの誕生はどうやって?
「島の住民がゴジラと呼んでいた」
と名前を出したいだけなら
もっと違う方法があったろうに・・・
そうかこの映画はゴジラが主役ではなかったのか
ゴジラ-1.0なのに
その最初にゴジラが出てくるまで
またそこから次に出てくるまで
クソつまらない人間ドラマを見せられて
帰りたくなる衝動を抑えるのに必死だった
そしてお決まり
ヒロインが生きてましたハッピーエンド
いらない実にいらない
他に描かないといけないことあるだろう!
いらない人間ドラマのせいで
シン・ゴジラでもなぜ東京に向かっているのかまでは分からなくても
なんで1度上陸したのに海に戻ったのかなど
ある程度の行動考察はされていたのに
全く考察もしていないのがかなり違和感を覚えた
不明な巨大生物のはずで行動原理など考察もしていないのに
なぜそこらへんの野生動物と同じで縄張りがあると思ったのか
録音した声を聴かせたら怒って戻ってくるとおもったのかぶっ飛びすぎて頭が混乱
もうちょっと筋が通るように脚本できなかったのか
せめて島の住民がなんでゴジラと呼ぶのかぐらい描いても良かったのでは?
暴れるだけにしても
ゴジラVSシリーズみたいにゴジラの敵が全くわからずただただ赤ん坊の癇癪のように暴れ回っているゴジラ
それになんの意味があるのか?
時代背景も現代と違うとはいえ
国も米軍もあんな理由だけで全く関わってこないのはさすがに無理がありすぎる
東京が核攻撃の如く吹っ飛んでるのにも関わらず
それでいて唐突な国会議事堂を守るように展開して砲撃する陸軍戦車
何アレ?
そして映画最後の
ゴジラ再生 ヒロインに不気味に浮かぶアザ
今回のゴジラがどんな存在なのか全くわからないのにそんな最後を見せられても謎すぎ
続編でまた同じような人間ドラマをするつもり?
少しマニアックになるが
強く見せるために噛ませにされた重巡洋艦高雄は要らなかった
素人が操艦してたのかな?と思う戦い方
脚本のかたが無理に重巡高雄を出したかったのではと感じる
別に機雷の爆発で倒れませんってだけでも十分脅威のインパクトはあった
その機雷も口の中でコロコロって
飴ちゃん舐めてるのかな?とは思ったけど
局地戦闘機震電もしかり
終戦間際に島の守備隊のいち整備兵が
震電のことを知っていたのも違和感があるし
戦中の通常戦闘機とは違い動力系は後部 過給機(ターボチャージャー)付きを時間制限ありで整備
ましてや機銃外して爆弾装備に改造って
設計やテスト飛行などにも関わってないんだから
いくら敏腕整備士でも無理
ゴジラと因縁があるからと無理に出す必要があるのか?
しかもそこまで無理に出しておきながら追加で二人出てきたけど誰?
その二人で良かったんじゃ?
正直これならまだ零戦を出して改造の方が
あの時特攻できなかったゴジラを撃てなかったけど今回は?!
とドラマが作れたのでは?
まあ要らないけど
唯一良かった点は
ゴジラが怖く描かれていた点
通常兵器では敵わないという強さ
どうやって倒せばという絶望感は
わかりやすくそこだけはゾクゾクワクワクできた
シン・ゴジラとは別ベクトルの感じで
しっかりゴジラしてくれててよかった
立ち泳ぎは・・・ん〜可愛かった(皮肉)
倒し方は映画 お約束かな
シン・ゴジラもそうでしたし
そこはゴジラ映画安定かなと
シン・ゴジラが面白かっただけに
大きく期待外れ
生き残ってしまった
まずは見た後こう思う
生きてるんかーい!!
あんな爆風でよく生きてたね
戦争×ゴジラ
グッときました。
生き残ってしまった人、憧れる人
絶対的王者ゴジラ、戦後ゼロからのマイナス
どう復興して行くんだろうか。
しかも死んでないからなぁ。
破壊しまくってるゴジラだけど、
やっぱりかっこいい。
面白かったけど物足りない
小さい頃からゴジラ映画が好きで毎回欠かさず
映画館でみています。
私のゴジラ感は圧倒的な存在で恐怖心をあおり
町を破壊尽くす怪物です。
人間達は団結して近代兵器で立ち向かいますが
ゴジラには全く歯が立たず絶望感に陥ります。
そこで優秀で専門的な人間が集まり協議して
ゴジラ対策を作り上げ用意周到して圧倒的な怪物に立ち向かう そこにゴジラや自衛隊のテーマソングが流れて心震え感動を覚えます。
今回の作品は今までのゴジラ映画と違いを見せる為に昭和の戦後設定でしょうが自分の印象としてはゴジラの登場時間が少なく感じました。ゴジラ対策もあまりにもご都合主義で準備や時間推移が???で人間の思惑通りにゴジラが動いてくれた印象ですね。
でも映像の迫力は素晴らしかったと思います。
わかりやすくて面白かった
ベタなのがいい
先の展開が読めるのに、ウルっとさせられたりハラハラさせられちゃう
ゴジラの圧倒的なパワー感と俳優さんの演技力に尽きる映画でした
最後のあれは、ちょっと、?ですけど
ゴジラ細胞の恩恵なんだそうです
途中まではこんなに救われない主人公なのに、ちゃんとハッピーエンドになるのかい??って不安にさせられました
昭和ゴジラ第一作を斬新オマージュした令和ゴジラ映画の戦争と人間
日本の特撮映画の金字塔「ゴジラ」の生誕70周年を記念した、大作の謳い文句から予想した娯楽映画ではなかった。幼い頃に夢中になった初期の子供向け怪獣映画や、ハリウッド映画に何度もリメイクされた派手な特撮娯楽大作とは制作のコンセプトが違って、大人が観るべき内容に驚きつつも映画の出来としてはスッキリした印象を持った。それは太平洋戦争における日本軍の戦い方の反省と、敗戦後の国防の在り方、そして唯一の被爆国としての立場など、ゴジラ第一作のメッセージに呼応する脚本の地味で確信的で分かり易いまとめ方に、作者山崎貴の力量を見たからである。先ず評価すべきは、この敗戦直後の時代設定から導き出される、ゴジラに日本人がどう戦うのか、戦わざるを得ないのかを、生き残った元特攻隊員敷島浩一の苦悩を主体に描いた脚本の独創性であろう。
ただし終戦の1945年から47年を背景にする時代設定は、第五福竜丸がビキニ環礁の水爆実験で被爆した1954年に制作した第一作「ゴジラ」のテーマの一つである反核メッセージを考えると、矛盾している。しかし、既に広島と長崎に原爆を投下された日本人にとって、その恐怖は切実極まりないものであったはずである。また百田尚樹原作の「永遠の0」と三田紀房原作の「アルキメデスの大戦」を映画化した山崎貴監督の経歴の蓄積が、この映画に結実したと思える内容になっている。廃墟と化した国土、食糧難による飢餓との闘い、生きて行くだけで精一杯の貧しい生活から漸くひと息ついたかどうかの時に、怪獣ゴジラの未知の破壊力と対峙しなくてはいけない。連合軍の実質米国のGHQに統治支配下で軍事力を放棄させられた無防備な状態で、国の命令を受けた民間の組織が集結する。この敗残兵の有志の集まりが、日本人の底力を見せることになる。政府も役人も正式な軍隊も登場しないゴジラ映画の誕生だ。
ゴジラファンとして嬉しかったのは、決戦のクライマックスの映像の迫力だった。ゴジラの不気味な造形と存在感、動きの全て、それに戦艦のVFXの映像美と見応え充分で見事。更に伊福部昭の永遠の名曲を生かした演出も素晴らしい。ここぞという使い方に作者のゴジラ愛が溢れている。役者では主演を務めた神木隆之介が難役の熱演。特攻の生き残りに深い慙愧と仲間を死なせた罪に苦悶する人物像は、時に怒りを表に出し過ぎに見える。内面に隠した演技が理想だが、これは山崎監督の演出法もあるので役者だけの問題では無い。それでもいい演技を見せてくれた。意外と言っては失礼なのだが、この映画で一番のいい味を出していたのは、元技術士官野田健治役の吉岡秀隆だった。豊富な髪をなびかせ、淡々とした話し方と熟年から漂う落ち着きと飄々さ。決死の作戦でも一人一人の命が大切と語る野田の人間性が浮き上がる。欲を言えば、周りの戦後直後の男性の髪形にもっと拘りがあれば良かった。山田祐貴、青木崇高、佐々木蔵之介も其々に役割のキャラクター表現を全うしている。浜辺美波と安藤サクラの女優陣も安定した演技。どちらも日本女性の淑やかさがある。これら大作にしては有名俳優の少なさが顕著であるが、このキャスティングもこの映画の魅力になって、けして大味になっていない。
独創性のある脚本の面白さ、細かく観れば難点も無い訳ではないが、これが山崎監督のオリジナルということで高く評価したい。反核と反戦から、平和を守るために軍備をどう構築しなければならないかの、日本の課題にまで問題提起した真剣さが、怪獣映画ゴジラの恐怖を最大限にスペクタクル化した作品、観て損はない。
もう少しゴジラがみたい
評判が良かったので観に行ってみた。
ストーリーは戦後の日本に関東大震災でなく、ゴジラが来てしまったというものだ。
ゴジラのシーンは、ハリウッド版やシン・ゴジラより少なかったが、迫力はずば抜けていた。
小さい頃にビデオ屋さんで借りてみていたゴジラ映画は人間ドラマが9割ゴジラが1割で、ラストにゴジラが暴れまくって終わるものだった。
ハリウッド版がゴジラやモンスターのシーン多すぎるんだが、ハリウッド版を観てしまったあとに旧構成のゴジラを見ると何か物足りない。
人間ドラマ部分は、戦後を知らないが、キャラが漫画みたいでリアリティが欠けて魅力が足りなかった。
神木くんも随分情けない役だった。
バイクシーンはどうしてもトムクルーズと比べると、やりたいことは一緒のはずが全然違う。。。お子ちゃまに見えるw
ラストの展開も想定内で、ゴジラにもっと悪あがきして欲しかった。
全体的には悪くなかったが、
もう一捻り、もう少しゴジラをみたかった。
つまらない
ゴジラが主人公ではないゴジラ映画
年齢的にもマトモに見ているのは平成ゴジラ以降で昭和ゴジラはチラホラ見ている程度のファンです。
ムトーさんがでてくるハリウッドゴジラあたりからゴジラの新作映画は大体微妙で斜に構えて見るようになりましたし、監督が監督だったのにも関わらず、今作は高評価で対応に困りかねたので心を無にして見ました。
普通に面白かったです。
前半パートの人間ドラマの長さとクサさには辟易としましたが、通して見てみればあのくらい丁寧に長くやったからこそ、後半の主人公の覚悟に感情移入しやすくなったと思います。
というようにあくまでメインは人間たちであって、ゴジラを見たい方々には受け容れられない作品になったかなと思います。
全年齢故のグロなし死亡シーンや丁寧に説明しすぎる点、都合が良すぎるハッピーエンド等も気になりました。
そこそこオタク的には幸運艦が出てきて震電が出てきて背鰭展開式熱戦とかやられたら+10000点
現在にも警鐘を鳴らす日本の為の反戦映画
山崎貴監督作である「アルキメデスの大戦」での冒頭に描かれた、戦艦大和の戦闘場面、対空砲で米軍機を撃ち落とし喜ぶ若い日本兵が、その機体からパラシュートで脱出して、海に着水したパイロットを、直ぐに味方の飛行艇が着て救出していく様子を、啞然と見ているシーンが出てくる。
決して、本編とは関係のないシーンだが、この「ゴジラ−1.0」で回収される伏線だったのかもしれない。
ゴジラとの決戦を前に、兵士の生命を粗末に扱ってきた旧日本軍を否定し、生きるための戦いを宣言する吉岡秀隆。特攻から逃げた過去と愛する者を奪ったものへ、死を持って決着をつけようとする神木隆之介に、生きろと伝える青木崇高。
無能な国家指導者による、無謀な戦争ではなく、自分たちと自分の大切な人たちが生き抜く為に、目前の脅威に立ち向かおうとする姿には、感動させられた。
「シン・ゴジラ」が政治家をトップに官僚たちなど国家権力に携わる者が戦ったのに対し、今回は民間人たちでゴジラに戦いを挑む設定は、フランスからの撤退に多くの民間人が協力した、ダンケルクを彷彿とさせる。
そして、ラストの神木隆之介とゴジラの一騎打ちに、あの「アルキメデスの大戦」の冒頭シーンが回収される。
殊更、過去の対米戦争を正当化し、権力の側に媚びる昨今の風潮をも否定する、日本人による日本の為の反戦映画であり、やはりゴジラは、逆説的な反戦、反核兵器の絶対的なアイコンなのだと確信させられる作品だった。
それでいて、VFX技術の凄まじい進歩によって、最もリアルな生物としてのゴジラを見れる作品でもある。
呉爾羅!初めてしったゴジラの漢字!
ネタバレしてますので読まないで鑑賞してください🤗。
本日TOHO新宿にて鑑賞しました。
ネタバレします。
最初から、ゴジラが、人間咥えて襲います。
私は、この手の描写苦手なんです。(*≧∀≦*)
手が小さいゴジラは、怖いです。
今回の設定は、戦後まもない日本が舞台です。
いや、この時代設定するのに、制作費は、現代設定より、2.3倍かかったと思いました。凄い熱意です。😅🥹🤗。
ミニチュアもかなり意識して取り入れていてこだわりが感じられました。
今回のゴジラは、最初の伏線が素晴らしいです。ゴジラは、顔など攻撃を受けると損傷します、でも再生します。
これが、最後の作戦に登場します。
今迄のゴジラは、無敵でしたが、今回は、ちゃんと破壊されて一様倒されます。
この視点は、私は気にいりました。
この時代設定にアメリカがもちろん語られますが、登場させず、警察予備隊も登場しません。
なので、民間の元海軍の設定で登場します。
この設定私は、好きでした。
そして今回は、人ではなく、ラスト戦闘です。
「震電」に乗り神木隆之介が、ゴジラに体当たりするシーンです。
伏線があり、脱出するかなあと思いましたが、目がしらが熱くなりました。
「インデペンデンス・デイ」を思わず
想起しました。
いや素晴らしい絵でした。
ナイス👍😊カットでした。🥹😁。
ツッコミは、ありますが、皆様鑑賞して
感じて欲しいかなぁー!!🤗。
次回作作って下さい。
この映画の関係者の皆様お疲れ様でした。
ありがとございます♪♪。
(((o(*゚▽゚*)o)))🥹😃🤗。
メイド・イン・ジャパンと胸張れます!
「シン・ゴジラ」がすごく面白かったので、今度はどんなもんだかなぁという気持ちで観に行きましたが、めちゃくちゃ面白かった上に物語としても感動しました。
映像がすごいだろうとドルビーで観ましたが、もうド迫力!ゴジラ登場シーンでは開いた口がふさがらず、あの恐怖感は初めて「ジュラシックパーク」を観た時のレベルでした。
音響と音楽もすごかったです。音楽は鐘の入ったドラマチックなオーケストラでもしかしたらと思ったとおり佐藤直紀さんで!盛り上がりの中にも悲壮感や哀愁が感じられて物語に重厚感をプラスしていました。ドルビーは音が最高です。
後から冷静に思い返すと「ん?」という場面もありましたが、観ている最中はそんな余裕もなく胸が熱くなり、ワァワァ盛り上がって登場人物たちを応援していました。
たくさん映画を観ていると、作品ひとつひとつの印象があまり残らなくなってきますが、今回は久々にしばらく余韻に浸れそうです。さすが本家本元のゴジラ映画です。やった!
技術はどれだけ進化しても、表現の手段にすぎません。その技術を使ってどんな物語を描くのかが問題なのであって、技術自体が目的になってはアカンのです!
目も耳も心も満足です。たくさんの人に楽しんで欲しい作品でした。
最高の映画
絶対に映画館で見た方がいい映画というのはなかなかないものですが、これは絶対に映画館で見た方がいい。家族で見ても、デートで見ても、1人で見ても感動できる。数々の映画を見てきましたが、私にとっては人生で1番の映画でした。
何より良かったのは音です。邦画特有の大きい音がやたらに大きい設定が、艦隊や銃火器の爆裂的な音を際立たせ、映像と相まって目の前でゴジラと人間が戦いを繰り広げているかのような錯覚に陥ります。また無音になるシーンの使い分けが非常に良く、緊張感がより一層際立ちました。
喜び、怒り、悲しみ、楽しみが詰まった映画で、ゴジラとの戦いとクサイけど王道な人間ドラマがお互いを高め合い、感動させられました。
正直見る前は監督の悪い前評判ばかり見ていて、 ゴジラが出てくる邦画だし一応見ておくか、くらいの感覚で見に行ったのですが、完全に自分の前評価をひっくり返されました。山﨑監督に土下座してお詫びしたいくらいでした。本当に良かった。悪いところがない。明日への希望いっぱいに映画館を出られたのは初めてでした。
p.s. 現代に生きる私にとって佐々木蔵之介の演技は過剰に感じる部分もありましたが、改めて考えてみると戦争に行ってたくらいの世代の、江戸っ子の船乗りであれば納得のいく言葉遣いなのかなと思っています。
ゴジラの出るヒューマニズム映画
ヒューマニズム映画として見ると、心にぶっ刺さったので、★5をつけました。今の日常が戦争とか悲しいニュースにあふれているので、本作に見られる人間のもつ善性、情深さだったり、寂しくて暖かい優しさを祈りのように感じました。
ゴジラ映画としては、シン・ゴジラから見始めた新参者ですが、純粋にアドレナリンが出て面白かったです。ゴジラが暴れるところは絶望を感じるほどには怖かったです。
昭和の時代から長年観続けて来た「ゴジラ」、ここに一つの到達点を示したと実感させられた
映画の冒頭数分でもうすっかり“入って”しまいました。
(『次元大介』とかとは真逆の状態で)数分のうちに名作確信したという意味で。
この映画について語るのが困難です。
ただただ、「本当に凄いこと(仕事)をやってくれた....」との思いが自然にわきあがったに尽きます。
素晴らしかった俳優さん達のこととか、いっぱいあるのだけれど、精神的に「なにも言うことは無い」状態になりました。
元から、山崎監督ということで何の不安も無く、唯一無二的に期待値高めで臨みましたが、それでも全然余りある位だったという事です。
特に今回の作品は、日本人以外の海外の人々に是非観てもらいたい、終戦後の日本人の背負って来た負目や思いとその姿、メンタリティを少しでも感じて理解してもらえたらとも強く思いました。
あくまでも、個人的な見解、感想です。
「スター・ウォーズ」もまだ存在せず、「怪獣映画」のビデオ化など夢物語のように遠い時代、名画座での上映も殆どされなくなって、鑑賞可能だったのは“東宝”が価値の認識に乏しく保全に勤めて来たとは言い難いコンディションの、保存状態の劣悪なれど何とか上映可能なフィルムで新宿のビレッジや池袋文芸坐(の文芸地下)などで時々行われたオールナイト上映。
そうした時代背景から「ゴジラとか何とか怪獣映画って子供が観るものでしょう?」と揶揄され、好奇の白い目で見られながらもそうしたものに足を運んだ日々。
それでも、その時代から一切ブレる事なく50年以上の月日、昭和〜平成〜令和までシリーズを観続けてきて、これまで生きて来て良かったとさえ思えた。(既に鑑賞叶わぬ友人・知人たちも....)
そのように思う事が出来る、“ゴジラ”映画に於ける「一つの到達点」を達成してくれたのではないかと実感できたからです。
当時の“同好の士”たちは今どうしているのだろうか?
今回、池袋グランドサンシャインのIMAX レーザーの大型スクリーンでの鑑賞を望んでそれを果たすことが叶って、終映後に場内から出ると丁度夕刻の、ガラス張りの池袋の街を一望できる12階のガラス越しに、見事に夕陽に染まった池袋の街が眼前に広がっていました。
恐らくここから駅の右手方向までをも見渡すことが出来るその場所に、1997年には閉館した先述の上映館“文芸坐(と文芸地下)”があったのだと思うと、そうした感慨ひとしおに劇場を後にしました。
追加
ちょっと落ち着いたので、気付いた点を幾つか…..
今作の“ゴジラ”自身についてですが、これまでの「核の脅威の象徴」とか「破壊神」「自然の脅威」といったこれまでのとは違った切り口で、イメージとしては『ジョーズ』(第一作)と思いました。
特に、「トドメは口の中でドッカン」がマンマな気も(笑)?
限りなく「獰猛な生物」的イメージであり、ジャンル的にも「海洋モノ」部分が占める割合も多いなど。
要するに、スペクタクルな部分(後半の攻防戦)は『ジョーズ』(第一作)イメージということで。
勿論、原点である初代を踏襲した“核の化身”として、「帝都東京の潰滅」を外す事はありえない事です。
今回、登場時には『キングコング対ゴジラ』に登場するコングのごとく”魔神”として姿を現します。
冒頭から、ただの被爆の権化的怪獣としての登場ではではないのです。
「ゴジラ」=”地球そのものの化身(神)”として捉えられ、それを「愚かな人類」が被爆させてしまうという部分が物語の冒頭ではなく中盤前ほどに位置しており、はっきりとその過程を挟んで後半に繋がってい行くというのが、今作の重要な部分であると解釈しています。
これにより、「帝都東京の潰滅」もまた、間接的にアメリカによってもたらされたとも言えると。
音楽について、『ゴジラ』『モスゴジ』『キンゴジ』から引用されていましたが、第七艦隊とも闘ったシーンのある『モスゴジ(米版)』のでこれは分かるとして、『キンゴジ』は?
今回の“ゴジラ”は体型的にお顔小さめ体デカめ系なのが初代やモスゴジと違い、キンゴジの体型に近い印象ですね。
あと、キングコング(キンゴジの)の生物的イメージとも被る音楽表現で通じるのかも知れません。
主なキャストは、「朝の連続ドラマ」系で存在感を示した面々と、山崎作品の出演陣となっていて、自身としても馴染みのある、既に実績も確かな「俳優」の方々で何の違和感も覚えず最後まで楽しませて頂きました。
(逆に、通常は誰かしらには違和感覚えたり不満感じたりするという事が殆どなので....)
特に主演のお二人は、ついこの前までも毎朝「夫婦」としてお姿見ていた事もあり、違和感無さすぎというか、息もピッタリのコンビネーションに見えてしまう。
要するに、中途半端なタレントやアイドル紛いのを排してもらえた事で、「映画の格を貶める」ことに繋がるとかいうような懸念も無しという事で。
蛇足ながら、今回鑑賞しながらその先の展開についてが分かった部分は少なくなかったです。
これは、自慢とか、見え透いてるとかの意味などでは全く無いです。
ストーリーから受ける、主人公たちへの感情移入や共感を感じながら観ていて「こうだったら良いのに」や「こうなって欲しい」と思っていたら、そのような形に実現したという感じです。
それは、山崎監督が考えたり願ったストーリーは、鑑賞している多くの人の願いの延長上に一致するように描かれているんだろうと感じ、そのように創られた作品なのだろうと思わずにはいられませんでした。
追記
12月1日より、いよいよ全米公開が始まった。
全米における興行収入は現地で5日には1436万ドルを突破して34年間破られなかった記録を更新。
歴代実写邦画作品の中で、全米興収ランキング1位を樹立した。
因みに、それまでの歴代邦画作品は、北米では1989年に公開された畑正憲氏の『子猫物語』の約1329万ドルという興収記録が長期に渡り1位だったのを、今回ついに塗り替えた形となった。
アメリカの映画批評家たちは「山崎の低予算での印象的なビジュアル、感動的な人間ドラマ、そして社会的批評のための怪獣の比喩の使用のために、この映画を一斉に賞賛した。」
映画批評集積サイトのロッテン・トマトに於いても、94件のレビューがあるうち映画支持率は97%、平均点では8.2/10となっており、同サイトの総意は「魅力的な人間の物語がアクションを支えている『ゴジラ マイナスワン』は、大量破壊現場の合間にも真に説得力を失わない怪獣映画である」としている。
CinemaScoreが調査したアメリカの観客は本作にA+〜Fの評価のランクで、「A」の評価を与えた。PostTrakによるアメリカの観客の調査では、全体の92%が肯定的な評価であり、83%は間違いなくこの映画を勧めるとの解答を得ている。
やはり、“名作”たり得るものというのは、「国」や「人種」「性別」などの違いを凌駕した存在たり得、これらの評価の意味するところが何よりの証としての結果であると、今作についての自身の思いやその評価に間違いはなかったことを裏付けることが出来たかのような満足を今、得られた思いでいる。
所謂、”名作”=”大ヒット作”という図式は、必ずしも当てはまるようなことにはいかないこと、”名作”だからといって必ずしも多くの大衆の支持を得られるわけでは無いということは、これまでの数十年の映画鑑賞歴の中で嫌になるほど実感してきたことではあるけれども、今作のようにそのどちらもを両立させることに成功した作品というものは、ある意味”奇跡”であり、今後の映画史の中でもその輝きが失われるようなことは無い存在となろう。
そういう意味では、まさに「これから(このあと)が大変」ですね.....
追記2
こうなるとある作品について、結果や評価が”総意”に近い形の高さが示されている作品について真逆の『最低評価』を下しているレビューから見ていくのって寧ろ楽しいというか、とても面白いですね。
「そういう受け止め方する(方なん)んだ」とか「そんな考え方がある(方なん)んだ」とか「そんな解釈は考えてもみなかった」とか、今更のようにいろいろと勉強になります(笑)。
当然ですが、「”総意”的なことが全て正しい」わけでは無いですしね。
全2054件中、1001~1020件目を表示