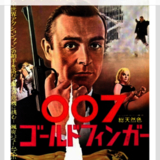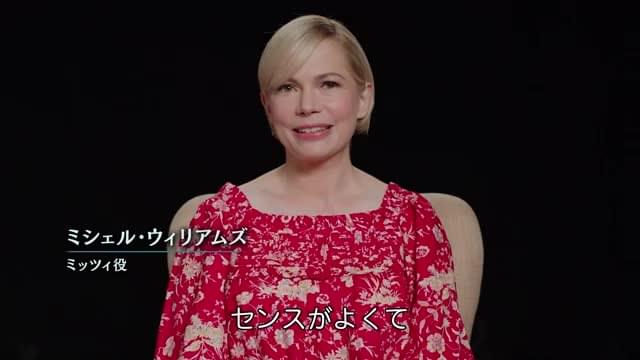フェイブルマンズのレビュー・感想・評価
全313件中、81~100件目を表示
ラストが描く未来
3.6チャーミングな母親だったのかな
私だけかな? 映画好きで語るならばスピルバーグ無しじゃ語れないんとちゃうの?
どうもいかんせん,スティーブン・スピルバーグというと、映画を観るならば大概の人には「あっ,それ知ってる!」という所謂メジャーな?作品が多いと思われる。 で、私事だが(スピルバーグ以外の作品に置いて)色んな作品を観て行く内に,わりと変わったものを観る様になってきた気がする。 たまに「何処が良いの?」とか…言われちゃう事も多々ある中、また<非常に悪い言い方になっちゃうが>形式ばった(所謂,一般受けしやすく&反論されにくい無難なシナリオ的な)感じになっちゃったりしてるんじゃないの?と思いつつ,鑑賞してみた。
大変失礼な言い方になります。わりとキャスティングで観る作品を決める私だが、何と無くそうだよなぁ⁈的な思いだったが,調べた結果,やっぱりヒース・レジャーの亡くなる直前迄の奥さんだった。ミシェル・ウィリアムズが透け透けのドレス?で踊ってるだけだけれども、私には十二分に観る価値在ったと思えた。
最初からゴチャゴチャ言っちゃったが、自伝的作品と謳って居たが,私には意外にも面白かったのは云いたい処…。
宝石のような小さな映画
自伝的作品だという。映画を初めて観る日から始まり、どのようにしてスピルバーグを模した主人公サミー・フェイブルマンが、映画を撮ること、ものごとをフィルムに収めることに夢中になっていったかを、丁寧に紡いで行く。
家族や友だちなどとの関わりも描かれるが、通常の成長物語りとは違う。
サミーはレンズを覗き、フィルムを編集することで、世界のありようを認識する。撮影されたものの善悪より前に、彼はその美しさに魅了されてしまう。そこに映画づくりの魔力があり、それはとても恐ろしいものでもあるのだろう。
スピルバーグは今でも映画の魔力にとらわれたままなのだと、観るものは思い知る。
彼の目はすなわちカメラのレンズであり、世界は映画なのであろう。
ならば身も心も映画に捧げた状態のこの巨匠こそが映画そのものなのではないか、そんなふうに独りごつ。
ビンテージ感溢れるフィルムの色、俳優陣の演技のゆったりとしたうまさ、被写体のありようを最大限に捉えるカメラワーク。それらのすべてが、ただただ美しい。
映画に囚われてしまった少年。そんなこととは無関係に迫る、心の外にある現実という世界。
それといかに折り合いをつけるか、それとも折り合うことを拒絶するか。
映画という武器を手にした主人公が、実際にどうやってそれと戦っていくか。その先は、この映画では描かれない。
あくまでも小さな心に映画が満ちる美しさだけを、これ以上ないほど丹念に描く。
だれにでもあった少年少女の日々の夢。もう記憶の向こうにかすれて消えていきそうな小さな日々。
それをもういちど見せてくれる宝石のような映画だ。
演技と演出と、ミシェルウィリアムズのちから
もう少し続きが観たかった
映画好きなら誰もが知る、スピルバーグ。
そのスピルバーグの自身の生い立ちを映画にした、ということで
とても気になり鑑賞。
少年時代、どうやって映画の世界にのめりこんでいったのか、
そしてその才能を如何に開花させていったのか。
一方で愛にあふれた家族内で発生するドラマ。学校でのいじめや恋愛、そして、別れ。
せつなさも感じる彼の思春期のお話。
いろいろあった人生、いよいよ映画界へ、というところで。。。
そのあとがもう少し見たいのだが!笑
せめて、激突!、ジョーズぐらいまでは笑
ルーツをたどる
どこまでが事実でどこまでが演出なのか。
探ることこそ無粋というやつだろう。
それもこれもまるっと受け止め残るのは監督のルーツ、
これは家族についての、とりわけ母親の物語なのだ、ということだろう。
だからして主人公と映画の関係を深掘りするより家族それぞれの表情やエピソード、
母親を中心にした人間関係が丁寧に描かれている。
同時に劇中、それらを狂わせる悪者的立場で「映画、映像」は登場し、
不穏の象徴ときらめくような対象としては出てこない。
懺悔でもなく、そういう事があったと言わんばかり淡々とした本作は想像していた以上に抑えられた作品で予想と違っていた。だがどうともはっきりさせることなく終わる悪者的映画、映像の件に転機があったことだけは感じられ、傷つきながらも手放すことだけはしなかったその後にアーチストの狂気と現実を垣間見る。
公のスピルバーグ像を讃えるものでなく、大変パーソナルな思い出をスチール写真のように切り取った一作は、文学短編を読み終えた後に似て少し心がざわついたままである。
追記
もっと快活、豪胆な物語をみたかった、といったような感想を多く見かけるが
冷静に考えて、自身の人生を、自身が監督して、自身の映画として公開しているのである。
それでいて内容が自分スゴイだろ、なんてあるわけない。
できるとしたらうぬ惚れた、メタ認知不能の、恥ずかしいくらいイタイ人物である。
だからして華々しい内容にならないのは当然なのである。
そこが本作のもっとも生々しい点であり、ナイーヴな真実に触れた証でもあると感じている。
興行映画としては少したいくつかも
すごく楽しみにしていたがいきなり戸田奈津子先生の字幕が出てぐっとくる。この映画は単なる興行映画では無いのだろう、スピルバーグ先生だからこそ許される2時間半で何かすごい事件が起こるわけでもなく映画フリークスの幼少期から大学生までの半生を彼の家族をとりわけ両親と父の友人との関係性を含めて丁寧に心の機微を着々と描きとおしたどちらかと言えばたいくつな映画かも知れない。スピルバーグで無ければ2時間に切られてもおかしくないしその方がテンポが出て面白くなるであろうがそれでも私にとっては大切な大好きな一本である。「スーパーエイト」で食い足りなかった8ミリ映画制作のあれやこれやを存分に見せてくれてエディット作業中のモニターがストーリー展開に大きくからむ作りも良く考えたもので母親役のミシェル・ウィリアムズがおそらくは実人生の経験も反映していて素晴らしい、特に竜巻を観に行くシーケンス。スピルバーグとは一回り以上年が離れているが私も高校生の文化祭で8ミリ映画作りにはまってその後の人生が決まった。最初からビデオがあった世代の人には到底分からないであろうピンで穴を開けたりもするこのフィルムを切ってセメダインでつなぐ編集作業やテープレコーダを回して音をシンクロさせる上映会などノスタルジー満開でたまらん。映画作りの映画はいつだって間違いなく面白いのだが、今回特に良かったのは戦闘で部下を死なせてしまった小隊長に演技をつけるシーン。これまではしょってきた演出部分を丁寧にじっくり描いて見せられたのも2時間半のなせる業であろう。クライマックスでジョンフォード監督に面会するシーンも秀逸で地平線が上か下かのカメラアングル論とそれに続くラストカットが驚きであった。映画スタジオの中の通りを遠ざかる主人公をまさにローアングルでパンアップするカメラがぶれる。興行映画としては明らかにNGテイクで、スピルバーグは意図的に画竜点晴を欠いたことよ。
映画に心を奪われた1人の少年の普通の人生
観た人は「あれを普通と思うか?!」と感じるかもしれない。
映画館で初めて映画を観て、あるシーンの虜になった少年が辿った人生は、
たしかに特殊に見えるかもしれない。
でも、人生の苦しみや葛藤や怒りは他者から見えないだけで、誰しもが抱え込んでいるものだろう。
サミー少年の場合、それが映画を好きになったことに起因しているだけである。
思っていたのと違うという感想もちらほら見かけた。
それも納得できる。あのスピルバーグ監督の半自叙伝的と聞いて、想像する内容とはかけ離れている。
数々の名作を世に送り出した巨匠の少年期、さぞかしドラマティックで映画愛に満ち溢れているのだろうと思ったら、
ドロドロのファミリードラマだったのだから。
カメラが撮るのは揺ぎ無き真実でも、それが編集によって虚構となる。
映画という芸術の本質を若くして悟ってしまった少年サミーの痛みを伴う人生記だった。
これをスピルバーグ監督の半自叙伝とするのであれば、彼にはやはり映画を愛する心があるんだと思う。たとえ、痛みを伴っても映画を作り続け、生涯を捧げてきた監督の人生がそれを物語っている。
良い作品
感情移入しにくい
スピルバーグの家族ストーリーがメイン
好きなことを仕事にする
好きなことを仕事にできる人は幸せだ。自分の好きなことはあくまで趣味にしかならず仕事にはならない、それでお金を稼ぐことは難しいという考えに至り、夢を諦める人は多い。私自身も映画は相当好きなものの1つであったが、そういった類のものを仕事にすることはできず、今は好きなことで仕事をしていない人間の1人である。
主人公のサミーは、映画や写真や音楽などに興味を持ち、それらを通して自分の感情や考えを表現していく。周りから理解されなかったり反対されたりすることもあるが、自分の好きなことを貫いていく。母親のミッツィは、芸術家肌のピアニストで、息子の夢を応援しているが、父親バートとは仲が悪く、父親の親友ベニーとの浮気が発覚してしまう。最後はバートとは離婚し、ベニーの元へ行ってしまうという結果となり、自分自身に正直に生きていく。
この映画に出てくる人物は、世間に縛られることなく表現者として自由奔放に生きている人が多いが、そのセリフの中で「芸術は麻薬である」「自分自身を表現することは誰かを犠牲にしたり、傷つけたりしてしまうことがあるが、それを怖れないで」「映画製作は心をズタズタにする」というものが印象に残った。この言葉からは芸術に取りつかれた人間の狂気を感じるが、その一方で、芸術に熱中して仕事にすることができるのは幸せなことで才能を持った数少ない人だけに許された特権なのではないかとも思った。
父親には趣味にしかならないといわれた映画製作を仕事にして見事才能を開花させたスピルバーグは、今後も良質な映画を製作して人々を楽しませていくだろう。憧れはあっても元々才能がない凡人は、彼のような才人の作品をたくさん観て評価する側にまわるほかない。
全313件中、81~100件目を表示