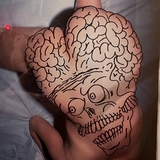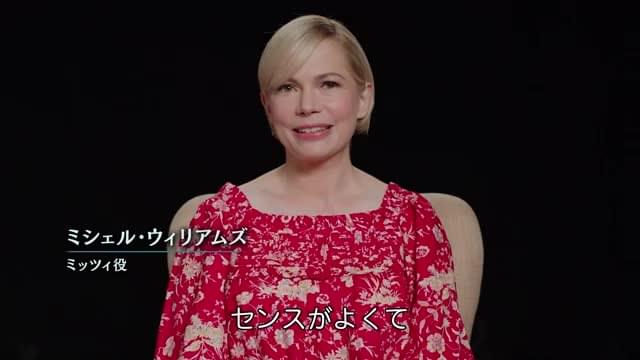フェイブルマンズのレビュー・感想・評価
全313件中、41~60件目を表示
お相手はセス・ローゲン
全人類が彼の映画を観たことがあるスティーブン・スピルバーグ監督の自伝的作品にして、続けざまに公開される「映画の映画」の本命、予告だけで涙していた一作だが、スピルバーグはどう才能を開花させていったのかというより、ママの浮気で家庭がぐずぐずになっていくファミリームービーだった。たしかにタイトルはフェイブルマン家だし。とはいえ、オレに言われるまでもなくスピルバーグは映画を撮るのがうますぎるので、2時間半飽きることはない。
宇宙人や恐竜好きの内向的でオタクな青年が描かれるのかと思いきや、仲間とともに8ミリを回し、ガールフレンドができて…と、スピルバーグ、普通に青春していた。一方で、家族の崩壊やユダヤ人差別によるイジメがあったり、そういった負の要素ですらフィルムで表現し、それが彼の創作意欲の原点にあるということか。
珍しくまともな役のポール・ダノがファーストシーンで、人間の脳は1秒24コマの~と言うところ、エンパイア・オブ・ライトでのトビー・ジョーンズとまったく同じ発言。一方、ラストのジョン・フォードも全人類もれなく印象に残る。公開初日に観てから10日ほど経つが、始めと終わりを映画の映画らしく押さえてあるせいか、なんかいい作品だったと思わざるをえない。
スピルバーグの原体験を知る必見作
音楽を真面目に聴き始めた頃にデビューしたジャクソン・ブラウンやイーグルスを同期だと思うのと同様、スピルバーグやルーカスを同期だと勘違いしている。
そう、中学生の時に『激突!』と『アメリカン・グラフィティ』に出会った。
これはそんな同期の一人、スティーブン・スピルバーグの二十歳頃までを描いた自伝的な作品。50年間寄り添ってきたとはいえ、知らないことばかりだった。彼の原体験を知ることができて嬉しかった。
そして我がミューズ、ミシェル・ウィリアムズ💕
彼女を見てるだけで幸せになるっちゅうもんだ。
ラストはまさに泣き笑い🤣ジョン・フォード作品のポスターに嗚咽を漏らし、リンチの登場にクスッとした。実に爽やかなエンディングだった。
.
.
自分が映画館で初めて観た映画は「モスラ対ゴジラ」だったかな。ザ・ピーナッツが出てたやつ。夢の中に何度も登場したゴジラ。どんな細い路地に逃げ込んでも必ず見つかってしまうのは何故だろうといつも悩んでた。
そう、そんなことを思い出さずにはいられない作品だった。
横綱相撲を思わせる圧倒的な「映画」
続きも観てみたい。
戸田奈津子先生
家族との思い出を映画の物語にした!
幼少期に父親に連れられて見せられた
サーカスの映画がスピルバーグ監督自身が
映画に魅せられるきっかけとなりました。
彼は本を出版していつか家族を物語
「フェイブル亅にした映画を製作したいと書かれたそうですが今回の作品で自伝的映画が
実現されて良かったと思いました。
家族でキャンプに行った先でカメラで撮影したり、列車の模型を激突させた情景を自主映画にした少年時代でした。
父親はエンジニア、母親はピアノを弾く芸術家気質、妹たちがいました。
学校のいじめ、部活、差別的なことを経験しながら転機を迎えた16歳、スピルバーグ監督の映画はすべて家族の思い出が着想に含まれているそうです。
ラストの地平線が上か下かにより、映画の面白さが変わってくることは初めて知りました。
家族愛がつまったストーリーでした。
ベーグルって食べたことないけど、なんだか食べたくなってきたなぁ。
両親に連れられて初めて観た映画『地上最大のショウ』によって幼い頃から8ミリカメラで映画を撮る楽しさを覚えたサミー少年。機関車模型をプレゼントされるやいなや、早速観た映画のような撮影をする天才。ボーイスカウト時代に仲間たちと自主映画を作るなどして、10代のうちに監督の才能が開花してたんだなぁ~と、スピルバーグファンならば垂涎モノの劇中劇。むしろフィルム編集の方に力を入れていたような気もする。
ユダヤ人にはクリスマスは関係ない!ハヌカ祭りを祝おう♪などとユダヤ人に関する豆知識もいっぱいで、高校時代のユダヤ人差別も描かれています。そんな中でも初恋は「ジーザス命!」といった雰囲気のキリスト教徒の同級生モニカ(クロエ・イースト)が相手。恋愛には宗教も人種も関係ないといったエピソードも。
なんと言ってもこの映画最大の魅力は母親役のミシェル・ウィリアムズ。ピアニストとしての魅力とともに妖艶な踊りも披露してしまう(透け透け度は『バビロン』のマーゴット・ロビーの方が上)。『ジャズ・シンガー』絡みでバビロンとも共通点があるところが面白い。
母親の言葉とか色々と納得する台詞もあったけど、最も印象に残っているのは「Art is a drug」かな。登場人物で言えば、ボリス伯父さん(ジャド・ハーシュ)やジョン・フォード(デビッド・リンチ)のインパクトが凄い。
気になるのがスピルバーグの作品群に影響を与えた体験は何だったのか。祖母の死に立ち会った際に見た頸部の律動なんかは『E.T.』や『ジュラシックパーク』に影響してるし、ペットの猿なんかは『レイダース』に?ほんのワンカットだったけど、サミー少年が手で影絵を作ってるところは『E.T.』その他に見られる手のこだわり。さすがに「おサボり日(ditch day)」のビーチは『ジョーズ』に繋がるかはわかりません・・・
原点なんだな。
映画の申し子なんだなぁ
この人のジョン・フォードでもう一本作ってほしい
すべての出来事には意味がある。
毎度の遅がけレビューにてストーリーは割愛。
ミシェルウィリアムズとポールダノの好演がとにかく素晴らしく、どの場面も終始魅了されました。
特に母ミッツィの弾く美しいピアノの音色(グランドピアノは勿論スタインウェイ&サンズ)と、至る所で使われる光と影の対比の演出がジョンウィリアムズ御大の音楽と相まって印象的でした。
葉巻を燻らす矍鑠なジョンフォード監督の言葉も素敵!
(こちらのキャストは後で知ったらまさかのお方)
そこからのウィットに富んだこれぞスピルバーグ節と言わんばかりのラストカットに思わずニヤリ。
『バビロン』や『ワンス・アポン・ア・タイム・インハリウッド』を観た時と同じく、この時間がまだ終わらないで欲しいぐらい多幸感に溢れた約2時間半でした。
これでイイのだと思える作品
スピルバーグの自伝的映画が、アカデミー作品賞候補に挙がった!?
その興味だけで観にいきました。
有名映画評論家(町山氏)が
ずいぶんと前にスピルバーグの青春時代のことを
「映画オタクで、いじめられっ子の陰キャだった」と語っていましたが
その触れ込み通りに描かれていました
(本人が描いたのがスゴイ!)
本編は展開力が素晴らしく
母親のキャラ付けも面白く
編集も、映像、音楽も付けるクレームは見当たりません
映画のお手本というべき作りでした
なんで作品賞候補になったのか分かりません
普通に面白いけど
テレビ東京のお昼の枠で見るような映画かな
とも思いました。
他の監督のクレジットだったら、ここまで評価されなかったかも
最後にデビッド・リンチを連れてきたのは
スピルバーグ流エッジの効いた演出でしたね。
自伝的であり家族を描きエンタメでもある
自伝と寓話(fable)の狭間で展開される家族の物語
そうかこうして、『スティーヴン・スピルバーグ』という映画監督は
形作られて来たのだな、との思いを深くする。
電気技術者の父とピアニストの母。
奇しくも「理」と「芸」が交差する出自。
それを冒頭のシークエンスで実に上手く描き起こす。
映画とは何かを論理的に説明する父。
それに比して「兎に角、わくわくどきどきするの」と
より蠱惑的な誘いをする母。
暗闇を怖がる少年をどうやって映画館に連れ込むかの手練手管に、
両親の特性が現れる。
あとあと登場する妹達を含め、
こうした家族(Fabelmans)の存在が大きく影響したのだと。
彼の映画館での原体験は〔地上最大のショウ(1952年)〕。
それも五歳の頃だと言う。
翻って自分は「東映まんがまつり」だったことを考慮すると
彼我の差は大きい(笑)。
初めて観る大画面に興奮し
「すげ~」「面白れ~」とつい口に出していたら、
隣に座った人にキツク注意されたのは今でもトラウマ。
二本目は〔怪獣島の決戦 ゴジラの息子(1967年)〕だったのだが、
その後はふっつりと観に行けなくなってしまったのは何故だろう。
おっと、閑話休題。
以降、彼は観ることと合わせて
撮ることにものめり込む。
与えられた8ミリカメラで、
最初は家族旅行のスナップ的な記録が、
やがては妹達に演技をさせた物語り作品に、
あげくには同級生をも大挙動員した大作へと繋がり。
カメラとフィルムは常に共に在り、
楽しさを生み、時に苦々しさの元となり、
やがて生きる為のよすがへとなって行く。
が、その根底には、
初めて映画館で観た映画に驚きの目を瞠った原体験が。
中でも彼が最も入れ込んだシーンが
『リュミエール兄弟』による
〔ラ・シオタ駅への列車の到着(1895年)〕と
近似の描写なのは象徴的。
本作でとりわけ印象的なシーンがある。
母親の『ミッツィー(ミシェル・ウィリアムズ)』が実母を亡くしたあとで鬱状態となり、
夢現の中で、亡き母からの電話を取るシーン。
これって、〔ポルターガイスト2(1986年)〕で
『キャロル・アン』が(翌朝に亡くなる)おばあちゃんと
(おもちゃの)電話で話すシークエンスと瓜二つ。
よかった
映像から訴える力は流石
巨匠は巨匠を知る
家族の物語
観客の心を惹きつけまくります
全313件中、41~60件目を表示