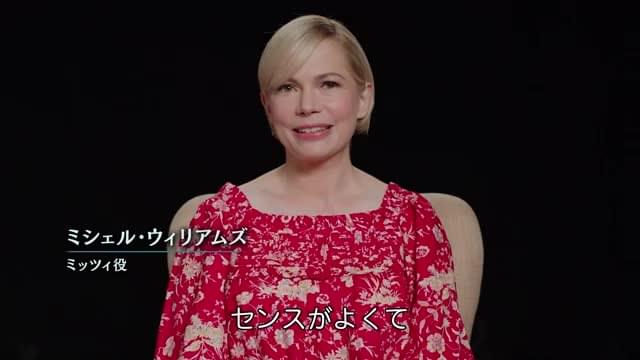フェイブルマンズのレビュー・感想・評価
全313件中、201~220件目を表示
興行映画としては少したいくつかも
すごく楽しみにしていたがいきなり戸田奈津子先生の字幕が出てぐっとくる。この映画は単なる興行映画では無いのだろう、スピルバーグ先生だからこそ許される2時間半で何かすごい事件が起こるわけでもなく映画フリークスの幼少期から大学生までの半生を彼の家族をとりわけ両親と父の友人との関係性を含めて丁寧に心の機微を着々と描きとおしたどちらかと言えばたいくつな映画かも知れない。スピルバーグで無ければ2時間に切られてもおかしくないしその方がテンポが出て面白くなるであろうがそれでも私にとっては大切な大好きな一本である。「スーパーエイト」で食い足りなかった8ミリ映画制作のあれやこれやを存分に見せてくれてエディット作業中のモニターがストーリー展開に大きくからむ作りも良く考えたもので母親役のミシェル・ウィリアムズがおそらくは実人生の経験も反映していて素晴らしい、特に竜巻を観に行くシーケンス。スピルバーグとは一回り以上年が離れているが私も高校生の文化祭で8ミリ映画作りにはまってその後の人生が決まった。最初からビデオがあった世代の人には到底分からないであろうピンで穴を開けたりもするこのフィルムを切ってセメダインでつなぐ編集作業やテープレコーダを回して音をシンクロさせる上映会などノスタルジー満開でたまらん。映画作りの映画はいつだって間違いなく面白いのだが、今回特に良かったのは戦闘で部下を死なせてしまった小隊長に演技をつけるシーン。これまではしょってきた演出部分を丁寧にじっくり描いて見せられたのも2時間半のなせる業であろう。クライマックスでジョンフォード監督に面会するシーンも秀逸で地平線が上か下かのカメラアングル論とそれに続くラストカットが驚きであった。映画スタジオの中の通りを遠ざかる主人公をまさにローアングルでパンアップするカメラがぶれる。興行映画としては明らかにNGテイクで、スピルバーグは意図的に画竜点晴を欠いたことよ。
おじさんの匂いがした
スピルバーグの原点
スピルバーグの、ってのなくていいくらい
想像してたのとまったく違ってた。「E.T.」の家庭に父親がいなく、母親がテンション高めで、妹がお父さんのことを言うと泣いたりするあたりがスピルバーグの子どもの頃に見ていた家族の姿だと思っていたが、もっとディープでした。そして母親と父親の間に起こった出来事。伝え聞いていたカメラを持った神童の姿もチョロチョロっと描かれるのだけど、そのカメラはもっと見てはいけない世界を捉えてしまっていた。
映画は偉人の伝記ではなく、むしろあまり見せたくないパーソナルな秘話。幼年期青春期に自分の手にシネカメラがありました、という少年の話で、虚構に魅せられる少年が、真実しか映さないカメラを通して映し取ってしまった真実に悩み、また真実だけど中身が映ってない、ということに悩むいじめっこがいたり、アメリカ映画といよりは、ヨーロッパのアート映画のテーマのよう。これ、スピルバーグの自伝、とかいう設定なく描いても良かったのではと思ってしまう。いや、フェイブルマンという名前にしてるくらいだから宣伝の仕方よりはその趣向ではあるのだろう。ただ、ラストシークエンスのあの巨匠の登場は問答無用に感動。そしてラストカットのゆらっ、はニンマリする。
スピルバーグ少年の「夢と闇」
TOHOシネマズ上野にて鑑賞。
スティーヴン・スピルバーグ監督が自ら取り上げた自伝的映画。
監督の少年時代における「夢と闇」を描いた作品であるが、なかなか面白かった。
怖がりのスピルバーグ少年が両親と映画館に……と「おっ、映画ワールドの始まりか?」などと思ったら、家族関係も多く描かれていて、映画ワールドどっぷりの作品でないあたりは監督が「どうしても描きたかったこと」なのだろう。
個人的には、TV映画「刑事コロンボ~構想の死角」や元々テレビ映画で後から劇場公開された「激突」ぐらいまで描いて欲しかった。
『ガンスモッグ』や『地獄への脱出』などの自主映画は劇中映画として描かれるものの、本作に登場している出演者が映っているので「この映画用に撮影した自主映画風の映像」なのか…?
しかし、家族ドラマにおいて、「えっ、こんなことまで映像化しちゃうの?」という驚きは、あちらこちらで……(^^;
自分が学生時代に観た『地上最大のショウ』は、当時、黒澤明・キューブリック・ヒッチコックにハマりまくっていたこともあり、「なんだか退屈で長い映画…」だと思えたが、本作鑑賞後、改めて観直してみたいと思った。
<映倫No.49526>
地平線(明日)はどっちだ?
世間の評判が△△△の親でも、
子どもにとっては世界一の親。
反対に、
世間の評判が世界一の親でも、
子どもにとっては◯◯◯の親。
地平線のように、
どちらかに振り切れ!
と、
言わんばかりに、
振り切る親、子、友人、
振り切られる親、子、友人、
の気持ちを立体的に巧みに描写していた。
ハラハラドキドキの演出は世界一だけど、
気持ちの機微を細かく描写することは、避けがち?の、
スピルバーグにしては珍しい、
驚いた。
ちょっと脱線。
母親のセリフ、
「あなたはCRASHに魅了されている」
『DUEL』に激突、しかも!を、
名付けた高橋さん、
その慧眼に改めて驚く。
無名時代のスピルバーグ作品、
チキチキマシーンシリーズの買付け、
あざーす!
ちなみに、
ゴレンジャーの産みの親だそうです。
ライオン丸の刀の鎖を考案した人、
コンドールマンの中に入ってた人、
ライダーの◯◯◯、
そんな人たちとたまに出会ったり、
話しを聞いたりします。
戻る。
カミンスキーの心の眼のような、
カメラフレームの切り方、
ワークにはため息の連続。
ステディ、ドリーのワークのお手本。
下手なステディ、移動、手持ち、ドローンが、
多すぎる昨今、最低限の事はやってほしい。
芸は身を助ける
先だって劇場で予告編を観た時、有名とはいえ映画監督の人生映画なんてとは思ったが、評価が高かったので観る事にした。
それにしても親子3人で観る人生初めての映画が殺人もある様な列車の脱線事故映画かなとあきれた。その衝撃映像が影響して家で鉄道模型を買ってもらうが、普通は鉄っちゃんの方へ行くのにママがカメラを与えたもんだから映像へ行くんだね。
ミシェルウィリアムズ扮するサミーはユダヤ系と言う事で差別を受けたりするんだけど、カリフォルニアへ行ってからちょっと展開が変わったね。
途中意味の分からない所が二カ所ほどあって、ママの情緒不安定さがさっぱり理解に苦しむが、良い家族とは言えないし、まあ結局芸は身を助けると言う事なのかな。成功者なんだからまあこんな生い立ちだったよと言う内容だったね。
期待してたのとちょっと違った
印象的だったのは、家族、学校関係のゴタゴタでつらいシーンの合間合間に、あ!スピルバーグだ!っていうカメラワーク?とか表現のシーンが入ってくるところにワクワクした。
この言葉・考え方を覚えておきたいなっていうセリフもいくつもあった。
仕事でストレスが溜まっていてどうしようもない時に映画館に行ったので、観ながらスピルバーグ監督に文芸作品よりもエンターテイメントって感じの映像を求めてしまっていたので、もっと違うコンディションの時にもう一度観たい。
現実は映画とは違う、という考えをスピルバーグが人生の中で何度も直面しながらも映画を撮り続けてきたのかなと思うと考えさせられた。
親子って何だろうっていうのも、考えさせられた。
余裕ができた時にもう一度観たい、でも、もう一度観るにはけっこう気合いがいる作品…。
字幕戸田奈津子っていうのが嬉しかった。
スピルバーグの作品を観るのに参考になるがスピルバーグマジックのネタバレに落胆するかも
私に語学力があったなら
巨匠も最初は、しくじり少年
フェイブルマン家の話
よくあるファミリーの物語。特に母親役のミシェル・ウィリアムズが良かった。
スピルバーグ監督の青年期までの過去の記憶。
どのようにしてスピルバーグが世界的なヒットを生み出す監督になっていったのか、それに興味があったが、それほどでもなかった。
印象に残ったのは、母親役のミシェル・ウィリアムズ。明るく振る舞うが、苦悩するシーンも演じきっておりとても良かった。子ども3人を育て、スピルバーグには映画への興味を全面的に支援する。父親は真面目で几帳面なエンジニア、そしていつも一緒に仕事をしている友人。この良好な関係に変化の兆しが表れていく。
映画づくりでいえば、若かりし頃の情熱やトリックづくりの仕掛け、機材のプレゼント、制作した映画上映会は家族で試写など普通の家庭にもよくありそうな微笑ましいエピソードが心を和まさせる。
一方、学校でのユダヤ人への差別・いじめなど、キリスト教徒との違いも実感として分からない私たちに考えさせられたシーンもあった。
最後の方は前半と違った「転」が繰り広げられるが、「結」のところはちょっと物足りなかった。
スピルバーグ監督の過去が明かされる自伝的作品。 本年度ベスト。
予告編が映画作りの愛に溢れた作品みたいな感じで期待して鑑賞。
だけど映画作りの要素は少なめ。
スピルバーグ自身の幼少期から映画監督になる事を決意する迄を描いたストーリーでした(汗)
そんな思い込みから出だしでスピルバーグ(本作での名前はサミー)が家族と初めて映画を観るシーンから、サミーが8ミリカメラである乗り物を撮影するシーン。
その後、ある工夫で銃を撃つシーンで火花が飛んでいる様に見せるシーンなどに引き込まれる。
その後も映画作りのシーンがあると思いきや思ってもいない展開に。
本作のメインはスピルバーグの自伝がメインだと言うことに気付く(笑)
期待と違った展開に新たに気持ちを入れ替えて鑑賞する事に(笑)
近くにいたオジさんはこの頃、早々と劇場を後に(笑)
多分、自分と同じ感じで鑑賞していたと推測です。
サミーが与えられた8ミリカメラで家族の団らんを撮影し、編集して家族と一緒に観るシーンが印象的。
そんな編集作業の中、あるシーンにに気が付いてしまう展開。
幸せそうな家族だけど知って驚く新たな事実は本当の事なのか?
気になるところ。
サミーがこのシーンを何故編集してしまったのか謎。
その場面を何故編集する事にしたのかは後になって知るけど、そうする事の意味も解らず。
サミーがユダヤ系アメリカ人と言うことで学校でのイジメが辛い。
卒業前に学校をサボって海で皆で遊ぶシーンの映像が良い。
そこにも映画作りの遊び心のある工夫が印象的。
終盤、ある映画監督の巨匠と数分だけ会話するシーンのセリフが印象的。
そこからのラストのワンカットはメッチャ良かったです( ´∀`)
手堅い自叙伝だけどオカンの章はやや厚め
スピルバーグ監督の自伝的作品だけど、タイトルのフェイブルマンズは寓話の人々とも取れるからかなりフィクションなんでしょうね。鉄道模型の衝突シーンを皮切りに、主人公が家族の記録や友人と戦争映画や西部劇を撮るシーンはとても楽しく、ちょっとした工夫でリアルで迫力あるシーンを演出するのは、スピルバーグ自身楽しんでいる感じです。一方で、卒業アルバム映像で学園のヒーローが、実物よりも素晴らしく撮られていることに重圧を感じてしまうエピソードは、映像の魔力みたいで面白いです。とは言え、中盤から母親の比重が高くなり映画少年の主人公の話と家族のエピソードのバランスが悪くなるので、なんかすっきりしない展開になるのは残念。役者ではミッシェル・ウィリアムスが大熱演、ポール・ダノもバットマンでのリドラーの凶暴演技とは真逆の慈愛溢れる父親を好演でした。
地平線は真ん中に有るとつまらない
初めて映画館に行き、その時観た列車の衝突に衝撃を受け、映画に夢中になった少年サミー・フェイブルマンは、母親から8ミリカメラをプレゼントされた。買ってもらった模型機関車を衝突させそれを撮影することから始め、映画撮影の夢を追い求めていった。母親はそんな彼の夢を理解してくれたが、父親はその夢を単なる趣味としてしかみない。サミーはそんな両親と、父親の転職と引越しで、さまざまな人々との出会い、失恋などを経験する話。
サミーが主役なんだろうけど、母役のミシェル・ウィリアムズの複雑な心情を描いた作品のようにも感じた。
夫は優しいし、子供は4人もいて父親としても子供の相手をしてたし、稼ぎも十分で理想の男のように思ったけど、あれでもダメなんだね。夫婦は難しいものだと思う。
キリスト教徒がユダヤ人を嫌う理由がキリストを殺した事だと明確に言ったのは知ってはいたが、劇中に若者が言うのは初めて聞いたかも。違う宗教の人同士の恋愛の難しさも感じた。劇中映画も面白かったし、フォード監督の、地平線は下や上に有ると面白い、という言葉は印象に残った。
『バビロン』よりエグい母
全313件中、201~220件目を表示