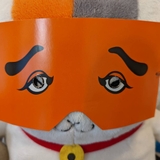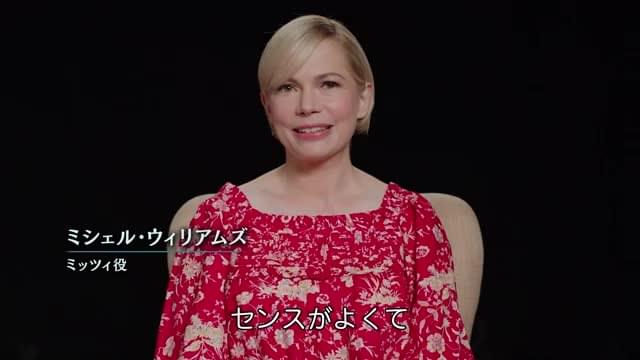フェイブルマンズのレビュー・感想・評価
全389件中、221~240件目を表示
スピルバーグ家の物語
スピルバーグが成功するまでのサクセス・ストーリーだと思っていました。
ファースト・カットのお母さんがメインだったんですね!
やはり、メロドラマは苦手なようです。良いシーンは有りますが、全体的に良くないです。
最後のこの人にこの役を演じさせたスピルバーグ、汚いなー‼️
「映画うま男」を創り出したもの
スティーブン・スピルバーグ
言わずと知れた「映画監督」の
代名詞と言えるほどの世界最高の
ヒットメーカー
幼少期に観た映画に魅入られ
17歳の時にハリウッドスタジオに
出入りするようになり作った短編
「アンブリン」が
アトランタ映画賞を受賞
ユニバーサルとの契約を得て
1971年「激突!」
1975年「ジョーズ」など
低予算をアイデアと特殊効果で
ひっくり返す作品で
世界的にブレイク
その後は自身のルーツである
ユダヤ人にまつわる本質的な
テーマの「シンドラーのリスト」
など社会は作品も展開
多種多様なジャンルをこなし
映画マニアからは
「映画うま男」と呼ばれ(?)
映画界の頂点に君臨しっぱなし
である
というスピルバーグ氏のその
ハリウッドに出入りするように
なるまでを描いた今作
どうだったか
主人公を氏をモデルとした
サミー少年に留まらず
「フェイブルマン家」として
扱うことで誰の視点に偏る
こともなくそれぞれの心情を
主張させる展開はあたかも
NHK朝ドラのようで逆に新鮮
内容を通じて映画が自分にとって
人々にとって何であるかという
思いが伝わってきました
先日も似たようなテーマの
「バビロン」という作品が
ありましたがそれより
なじみやすかったです
だって朝ドラだから
アリゾナに住む
ユダヤ系の「フェイブルマン家」
新しもの好きで優しいが
いったんスイッチが入ると
相手かまわず早口で喋り始める
ナード系の機械技師のバートと
芸術家肌でファンキーで奔放
なピアニストのミッツィ
そんな間に生まれたサミー少年は
映画に連れられ見た作品は
「史上最大のショウ」
機関車と車が激突し
大事故が起こるシーンを強烈に
脳裏に焼き付けたサミーは
せっかくバートにプレゼントされた
模型機関車も憑りつかれた様に
ミニカーと激突させるので
バートは頭を抱えますが
ミッツィはその行動に意味を感じ
バートのカメラをこっそり
サミーに渡しその「シーン」を
撮って見せるよう言います
サミーはクローゼットの奥の
即席映画館で最高のそれを
ミッツィに見せます
それがサミーの「キャリア」の
始まりだったのです
そんなミッツィの口癖は
「出来事には意味がある」
その頃バートはRCA社で
同じエンジニアとして
親交を深めていたベニーと
共に開発していた
真空管コンピュータ「BIZMAC」が
認められIBMがバートを引き抜き
アリゾナを出る話が出てきましたが
ミッツィはそれを強く拒絶します
何故なのでしょう
やがてボーイスカウトでも
短編映画で評判の作品を
作るようになったサミーは
拳銃が弾を発射する後入れの
フィルム効果等を編み出し
父も感心しますがそろそろ
そういう趣味よりも実質的な
車の運転なども覚えてと
言われるのを嫌がるように
そんな折ミッツィの母が亡くなり
悲しみに暮れるミッツィを
案じたバートはサミーに
欲しがっていた編集機を与え
一家とバートの仕事上から
家族ぐるみの付き合いの
ベニーおじさんと行った
キャンプの短編ビデオの
編集してミッツィに
見せてやってくれと
頼まれます
サミーは正直乗り気には
なれなかったのですが
そのキャンプ映像の
編集中に不意に映った
ミッツィとベニーの
「密接さ」を知り
困惑しミッツィ(とベニー)
を拒絶するように
なっていきます
ミッツィはそれに対し
怒りを見せるのですが
サミーにその理由を
打ち明けられ
どうしていいかわからない
サミーは秘密を洩らさない
ようにします
アイデアと工夫で
思うまま寓話を撮ってきた
サミーが
単なるキャンプを
映像に残したことで
思わぬ真実を残す
その「真実性」の怖さを
知ったので
カメラで撮ることに
恐怖をも覚えてしまった
ようです
そんな折ミッツィの
母の兄であるボリスおじさん
が弔問に来ますが
映画関係の仕事をしていると
サミーに伝えると
母方の家に伝わる
芸術家肌の妥協できない
我慢できない性分が
お前にもある
どうしても我慢
できないから覚悟せえよ
と言われてしまいます
結局家族は
カリフォルニアへの
引っ越しが決まり
ミッツィがアリゾナを離れる
事を拒否し続けた「理由」
ベニーから餞別として
最新型8mmカメラを
贈られますがサミーは
前述の恐怖からもう映像は
撮らないと拒否(結局受け取る)
バートはもう成長して
やめたものだと思って
いたのですが
バートはベニーとミッツィ
の関係にもまるで気がついて
おらず仕事の成功しか
頭にないようで
そこへも少なからず
不満があるのでしょう
結局カリフォルニアに越した
フェイブルマン一家
サミーはユダヤ系である事で
転校先のハイスクールで
スクールカースト頂点の
ローガンやチャドらから
とことん虐められますが
サミーも結構やり返すので
トラブル続き
引っ越すんじゃなかったと
父を恨みますが
ふと知り合った
ガールフレンドのモニカの
勧めで最新カメラを貸して
あげるからと卒業イベントの
撮影を頼まれます
そんな折引っ越し後から
家事も何も手に付かず
ベッドで寝てばかりになった
ミッツィにバートもついに限界
「離婚」と相成ってしまいます
理由を受けとめられない妹らは
混乱しますがサミーは既に
知っていますし
(妥協できない性分も
ボリスから聞いてますし)
淡々と卒業イベントの編集を
進め工夫も凝らした見事な
作品を作り上げます
さて卒業パーティー当日
サミーはモニカに
両親が離婚するので一緒に
ハリウッドに来ないか的な
重たいプロポーズをして
しまい大爆死
しかしその傷心冷めやらぬまま
上映したサミーの映画は大ウケ
チャドは徹底してマヌケに
描写されローガンは
「無欠の英雄」のように描かれ
ローガンに女子勢は夢中に
なりますがローガンはだんだん
複雑な表情になります
そしてサミーに詰め寄ります
「なぜあんな撮り方をした」
するとサミーは
「お前は最低な野郎だ」
「だが"あの中"なら仲良く
なれるかもしれないと思った」
とハッキリ言いきります
するとサミーを見つけた
チャドが仕返しに
殴りかかってきますが
なんとローガンが
チャドをぶん殴って
追い払ってしまいます
そしてローガンは
あろうことか慟哭し始めます
周囲に対し強い男と
虚勢を張ってきた
自分を映像で見透かされて
しまったという事でしょうか
思わぬリアクションに
サミーは困惑しますが
「このことは秘密だ」と
告げられローガンは去ります
かつて
現実を映像に残すことで
不都合な真実を切り取ってしまう
怖さを目の当たりにしたサミー
ですが今度は演出をもって
人をフィルムに映し出す事で
作り出される理想がその人を
押しつぶしてしまう
事もあるということを
スティー…じゃなかった
サミーは知ったのでしょうか
まぁローガンは単純に
感動したんだと思いますが
そして1年後
サミーは離婚後父についていって
カリフォルニアの大学に行った
ようですが相変わらず差別は
なくならず映画の仕事がしたい
と方々に手紙を出しまくっては
お祈りされる日々にうんざり
バートは気を落とすなと
たしなめますが
ミッツィからの手紙が
届いておりそれでベニーと
幸せそうにしている姿を見て
バートも一気に態度が変わり
したいようにしなさいと
サミーに言います
バートも自分の夢にばかり邁進
していたわけではなく
バートなりに家族のために働き
ミッツィの幸せも願っていた
所はあったと思いますが
届かない部分があった
ベニーとの関係は結局
知っていたのか不明ですが
(映画の中でもどちらとも
とれる描写でした)
アーティストの妥協なき感性
はバートなりに感じ取って
いたのだと思います
バートにそう言われた
サミー宛の封書には
ハリウッドのスタジオから
話を聞きたいというものが!
なんかハリウッドスタジオの
ツアーを抜け出してスタッフと
仲良くなって3日間のフリーパス
貰ってその間に人脈を作った
なんて逸話もありますが
それはあくまでスティーブ(笑)
そして面接に臨むサミー
テレビシリーズの仕事を依頼され
すると伝説的な監督を紹介されます
その監督は葉巻をくゆらせながら
「地平線を上か下に取るだけで
その映画は面白い!
真ん中にある映画は退屈だ!
それだけ覚えておけ!」
という金言を授かります
本当に言われたんでしょうねw
ここのシーンだけですが
圧倒的なキャラを見せつけた
デビッド・リンチさすが
そして足取り軽くハリウッドの
スタジオの間の通りを向こうへ
去っていくサミー
彼に待っているものは?
というところで映画は閉じます
別に自分は映画マニアではないので
歴史的な作品に詳しいわけでは
ありませんがそれでも作品から
伝わってくるメッセージは
色々ありました
スピルバーグ監督の言葉で
一番好きなのは何かの番組で
「映画監督に憧れる若者に
アドバイスお願いします」と
司会に言われたときに
「その質問には答えられない」
「なぜなら私も
映画監督に憧れているのだから」
人は生きている限り
道のまだまだ途中…
ほ~。← (納得のほ~)
スティーブン・スピルバーグ監督の原体験を元にした自伝作品。
初めて行った劇場で映画の虜になるサミー。
母親に8ミリカメラをプレゼントされ、そこから子供ながらに仲間を集め映画を製作していく話。
映像を撮影してはダメな箇所を模索しながら修正し、納得出来た作品を観せる。
作品を観て喜ぶ人の姿を見て映画製作の楽しさを知る。
この作品には監督になるまでの話だけでなく家族内でのドラマ、学校でのドラマも描写されてる。
ラストのフォード監督に言われた地平線の話、「上と下にある地平線は面白い、地平線が真ん中にくるのはつまらない」、は何か深いな!
監督だけでなく何か私にも刺さりました!
意味はわからないけど(笑)
スピルバーグの作品を観るのに参考になるがスピルバーグマジックのネタバレに落胆するかも
巨匠監督誕生までの前日譚!! スピルバーグ監督の少年期の葛藤と,モラリストたろうとした両親の苦悩をフィルムが淡々と捉えた青春愛憎映画
巨匠スティーヴン・スピルバーグが映画監督として頭角を現す前の、少年期における人間形成の過程を描くドラマ映画であり、少年期の彼の投影であるサミー・フェイブルマンの成長が主軸ではあるのですが、主演はミシェル・ウィリアムズ演じるサミーの母リアであり、彼女が夫とともに"良き親・良き配偶者"であろうと努めつつもままならない現実に傷付き悩む等身大の大人たちの物語でもあります。
また、幼年の折に映画の魅力に取りつかれてのめり込む豊かな好奇心の発露と成功体験、両親との相克や同年代の少年からの被差別によるコンプレックスと衝突、そして淡い恋…等々、実に瑞々しいジュブナイル的青春映画としても胸を打つ一本でした。
ホームドラマとして、そして青春映画として非常に楽しめたのですが、スピルバーグ監督は大衆を楽しませるエンターテイナーとしての側面がかなり強いということが本作であらためてよく解りました。
つまりは、己の存在理由を掛けて、世の中への挑戦状のように自身の内奥のマグマを叩き付けるような内省的な作家とは対極に位置するであろう、ということです。
職業選択に際しても、母の後押しで父からも映画業界に進むことを全面的に支持されており、その点、両親や周囲の反対を押し切って己の信じる道に飛び込む類の人生形成を経た人のギラつきのようなものは感じられません。
もちろんそれが悪いということではなく、それがゆえに広範な人々が享受出来る娯楽のチャンネルを掴みえたということでしょうが、そうした創作活動の源泉を垣間見られたという意味でも意義深い作品でした。
映画は紛れもなく芸術である!
現在76歳になったスピルバーグの人生も、いかに完璧な軌跡を描いていたかを知る貴重な名作だと思います。初めて大スクリーンで観た列車などの衝突シーンから彼の映画人生はスタートします。おそらくこの映画を観た時のショックは、彼の精神の小宇宙の激震だったのでしょうか。それが、彼の使命を覚醒させ、映画人生の爆進が始まったと思うと感無量です。育った環境は、比較的裕福で、芸術家肌でピアニストの母、ITの秀才である父、賑やかな3人の姉妹に囲まれ、ほとんど好きなことを阻害されることもなく順調に天才性を育みました。もちろん人生には幸福に見えるものばかりが存在することはありません。半分恵まれていれば、残りの半分は不幸に見えることが訪れます。そのリアルさを存分に作品の中で描き切っていて見事だと思います。ユダヤ人であるがための差別、宗教の問題にも触れています。途中まで家族はまるで絵に描いたような仲の良さで協調的なやり取りがありますが、後半は母親の不倫?によって家族は崩壊します。それでも、その経験は今のスピルバーグにとっては、映画を創作する幸せの因になっていると確信しているのでしょう。人生は、さまざまなことが起こりますが、全てが最終的には、幸せと愛に満ちていると言えるのかもしれません。セリフの中で「出来事は全て意味がある」という言霊がありましたが、その意味は全て愛なのでしょう。いずれにしても、こんな名作に触れられた至福の時に感謝します。
追記 少年から青年になる時代に、観る人を楽しませる映画ストーリーの仕掛け作りに精を出していたものが、後年、世界的ヒットを成し遂げた「ジョーズ」(サメ)に見事に生きているかと思うと、天才の人生シナリオはやはり完璧なのでしょう!
私に語学力があったなら
巨匠も最初は、しくじり少年
イジメ迫害が!
これでイイのだと思える作品
スピルバーグの自伝的映画が、アカデミー作品賞候補に挙がった!?
その興味だけで観にいきました。
有名映画評論家(町山氏)が
ずいぶんと前にスピルバーグの青春時代のことを
「映画オタクで、いじめられっ子の陰キャだった」と語っていましたが
その触れ込み通りに描かれていました
(本人が描いたのがスゴイ!)
本編は展開力が素晴らしく
母親のキャラ付けも面白く
編集も、映像、音楽も付けるクレームは見当たりません
映画のお手本というべき作りでした
なんで作品賞候補になったのか分かりません
普通に面白いけど
テレビ東京のお昼の枠で見るような映画かな
とも思いました。
他の監督のクレジットだったら、ここまで評価されなかったかも
最後にデビッド・リンチを連れてきたのは
スピルバーグ流エッジの効いた演出でしたね。
自伝的であり家族を描きエンタメでもある
愛ゆえに
スピルバーグ監督の自叙伝的な作品ということで、全ての監督作は観れてはいませんが、代表作は一通り通っているのでその知識の勢いで鑑賞。
んー…。長さはそこまで感じませんでしたが、物語がそこまで面白くなくてのめり込めなかったです。ウトウトは全くしませんでしたが、最後まで何だかなーって感じが抜けなかったです。
まず良かったところを列挙していくと、学生時代のエピソードで創意工夫を重ねながら映画を作っていく様子はとても楽しかったです。戦争映画を作る際に大手映画を作るには予算が足りないので、地面に仕掛けを作って銃弾に当たった風に仕上げたり、わりかしグロテスクな血まみれな様子を映像に映し出したり、やられ役達が移動を繰り返すなど、しっかりした作品になっている、スピルバーグの原点を観ているかのようで嬉しくなりました。これがサメ映画の金字塔である「ジョーズ」へと繋がっていくのかと思うとワクワクするばかりでした。
街並みのロケーションや音楽も素晴らしく、アカデミー賞にノミネートされるのも納得なくらい心地の良い映像とサウンドに包まれてとても良かったです。
ただ、全体的に母親のしょうもない不倫劇がずっと垂れ流しにされているので、その点はずっとノイズになっていました。スピルバーグの実母をモチーフにしていると思うので、悪く描けないのは分かりますが、自分勝手な母親が父親の親友とイチャつく、引っ越しする際も親友を連れて行かない(正しくは連れて行けない)事を責め立てる、キャンプ場でガッツリ手を繋いで、挙げ句の果てには離婚して親友の元へ戻るという酷さ。これが現実に近いものと考えるとスピルバーグは少年時代相当苦労したんだなと思いましたが、観客としてはそんなものは別にどうでもいいので、映画作りに勤しんだ描写をもっと描いて欲しかったなというのがあります。父親も苦しんでるんだかよく分かりませんでしたし、母親は中々にクレイジーで好きにはなれませんでした。姉妹は良い子達でしたけどね。
ユダヤ人差別とか歴史の授業で習ったくらいの知識なので、住んでいる場所がガッツリ変わるとこうも差別されるんだなと勉強になりました。ただ、この差別が映画作りに活きていたとは思えず、いじめられてた少年を少しだけ見返したくらいなだけなのはどうにもいただけなかったです。こればかりは好みの問題です。
というか後半に差し掛かってから学園ドラマに何故か舵を切ったので、その辺でも面白さが無くなってきたなと思いました。キャリアを語る部分で根幹を作った学生時代を必要とするのは分かりますが、どこかで観たというか観たことのあるアメリカの普通な学園ドラマを今更観せられても…という気持ちに襲われました。
終盤の卒業ムービーお披露目会で、なぜか好かれた彼女に両親の離婚とプロポーズの言葉を同時に渡したらフラれるという急展開には、ん?と首を傾げざるを得ませんでした。宗教には疎いのでそこら辺が引っかかった上での実話だとしても、これまた映画作りには直結しない描写で必要性を感じませんでした。
終盤、大学に行ったら行ったで病んで、映画の道へ進み、ジョン・フォード監督に喝を入れられ名監督スピルバーグへと歩み出すシーンはなんだか煌びやかでした。ここからジョーズを作る手前までを描いて欲しかったなとしみじみと。
2023年に入って多くなった"映画"の映画。どこか捻ったところや尖ったところが無いと退屈に思えてしまう場面が多くなってしまい、今作も例に漏れず。「エンドロールのつづき」と一緒で映画好きな少年の平凡な物語、作っている側の自己満足で終わってしまう作品はどうにもテンションが上がらず…。オスカーがこういう作品を好むのは分かっていますが、そういえば例年のアカデミー賞と相性が悪いのをすっかり忘れていました。このあと出てくる作品にも畏怖しながら過ごしていきます。
鑑賞日 3/5
鑑賞時間 17:00〜19:45
座席 J-23
ラスト数分に詰まったもの
ズルい
フェイブルマン家の話
スピルバーグのファンなら120%楽しめる
幼い頃の映画との出会い、夢中で撮った8ミリ映画、両親との関係、学園生活や初恋、映画人との出会いなどが、150分という時間の中にみっちりと詰め込まれており大変見応えのある作品になっている。一人の少年の夢への希望、葛藤と成長を過不足なく描き切った手腕は見事で、改めてスピルバーグの無駄のない語り口には脱帽してしまう。唯一、母親が別居を切り出すシーンに編集の唐突さを覚えたが、そこ以外は自然に観ることが出来た。
また、あれだけの巨匠であるのだから、やろうと思えばいくらでもマニアックに自分語りができるはずであるが、そうしなかった所にスピルバーグの冷静さを感じる。確かに彼の”私的ドラマ”であることは間違いないのだが、同時に夢を追い求める若者についてのドラマとして誰が観ても楽しめる普遍的な作品になっている。
ファンの中にはハリウッドで成功を収めていく過程をもっと見てみたかったという人がいるかもしれない。そのあたりは資料を探ればいくらでも見つかるので別書を参照ということになろう。とりあえず本作ではスピルバーグの人格形成や家庭環境、映画界に入るきっかけといった草創期に焦点を置いた作りになっている。
とはいうものの、自分もスピルバーグの映画をリアルタイムで追ってきたファンの一人である。やはり幼少時代の映画との出会いや、仲間と一緒に8ミリカメラを回して自主製作映画に没頭するクダリなどは、特に興味深く観れた。後の「激突!」や「未知との遭遇」、「プライベート・ライアン」等の原点を見れたのが興味深い。
また、両親の不仲や暗い学園生活、ユダヤ人であることのコンプレックス等、プライベートな内容にかなり深く突っ込んで描いており、スピルバーグの人となりが良く理解できるという意味でもかなり楽しめた。
そしてもう一つ、ただの映画賛歌だけで終わっていない所にも好感を持った。
映画は人々に夢と希望を与える娯楽であるが、時として大衆を先導するプロパガンダにもなるし、心に深い傷を植え付けるトラウマにもなるということをスピルバーグは正直に語っている。
例えば、サミーは8ミリカメラで家族のプライベートフィルムを撮影するのだが、そこには映ってはいけないものまで映ってしまい、結果的にこれが平和な家庭生活に亀裂を入れてしまう。映画に限らず映像メディアが如何に罪作りな側面を持っているか、ということを如実に表したエピソードのように思う。
あるいは、彼は高校時代の思い出にクラスメイトが集うイベントを撮影して、それを卒業のプロム会場で上映する。ところが、これが周囲に思わぬ物議を呼んでしまう。これも映画は編集次第で誰かを傷つける”凶器”になり得る…ということをよく表していると思った。
デビュー時こそエンタメ路線で次々とヒット作を飛ばしたスピルバーグであるが、ある頃から彼は社会派的なテーマを扱うようになった。世間ではオスカー狙いだのなんだのと言われていたが、決してそれだけではなかったように思う。彼は映画が人々に与える影響力の大きさということを信じて疑わなかったのだろう。
観終わってすぐに内容を忘れてしまう映画もあるが、良くも悪くもいつまでも心に残っている映画もある。そんな映画が持つ功罪を、スピルバーグはこの青春時代に身をもって知ったのではないだろうか。彼の作家性の基盤はすでにこの頃から培われていたのだと思うと、本作は更に興味深く観れる作品である。
映画って本当に良いもんですよね~
自伝と寓話(fable)の狭間で展開される家族の物語
そうかこうして、『スティーヴン・スピルバーグ』という映画監督は
形作られて来たのだな、との思いを深くする。
電気技術者の父とピアニストの母。
奇しくも「理」と「芸」が交差する出自。
それを冒頭のシークエンスで実に上手く描き起こす。
映画とは何かを論理的に説明する父。
それに比して「兎に角、わくわくどきどきするの」と
より蠱惑的な誘いをする母。
暗闇を怖がる少年をどうやって映画館に連れ込むかの手練手管に、
両親の特性が現れる。
あとあと登場する妹達を含め、
こうした家族(Fabelmans)の存在が大きく影響したのだと。
彼の映画館での原体験は〔地上最大のショウ(1952年)〕。
それも五歳の頃だと言う。
翻って自分は「東映まんがまつり」だったことを考慮すると
彼我の差は大きい(笑)。
初めて観る大画面に興奮し
「すげ~」「面白れ~」とつい口に出していたら、
隣に座った人にキツク注意されたのは今でもトラウマ。
二本目は〔怪獣島の決戦 ゴジラの息子(1967年)〕だったのだが、
その後はふっつりと観に行けなくなってしまったのは何故だろう。
おっと、閑話休題。
以降、彼は観ることと合わせて
撮ることにものめり込む。
与えられた8ミリカメラで、
最初は家族旅行のスナップ的な記録が、
やがては妹達に演技をさせた物語り作品に、
あげくには同級生をも大挙動員した大作へと繋がり。
カメラとフィルムは常に共に在り、
楽しさを生み、時に苦々しさの元となり、
やがて生きる為のよすがへとなって行く。
が、その根底には、
初めて映画館で観た映画に驚きの目を瞠った原体験が。
中でも彼が最も入れ込んだシーンが
『リュミエール兄弟』による
〔ラ・シオタ駅への列車の到着(1895年)〕と
近似の描写なのは象徴的。
本作でとりわけ印象的なシーンがある。
母親の『ミッツィー(ミシェル・ウィリアムズ)』が実母を亡くしたあとで鬱状態となり、
夢現の中で、亡き母からの電話を取るシーン。
これって、〔ポルターガイスト2(1986年)〕で
『キャロル・アン』が(翌朝に亡くなる)おばあちゃんと
(おもちゃの)電話で話すシークエンスと瓜二つ。
よくあるファミリーの物語。特に母親役のミシェル・ウィリアムズが良かった。
スピルバーグ監督の青年期までの過去の記憶。
どのようにしてスピルバーグが世界的なヒットを生み出す監督になっていったのか、それに興味があったが、それほどでもなかった。
印象に残ったのは、母親役のミシェル・ウィリアムズ。明るく振る舞うが、苦悩するシーンも演じきっておりとても良かった。子ども3人を育て、スピルバーグには映画への興味を全面的に支援する。父親は真面目で几帳面なエンジニア、そしていつも一緒に仕事をしている友人。この良好な関係に変化の兆しが表れていく。
映画づくりでいえば、若かりし頃の情熱やトリックづくりの仕掛け、機材のプレゼント、制作した映画上映会は家族で試写など普通の家庭にもよくありそうな微笑ましいエピソードが心を和まさせる。
一方、学校でのユダヤ人への差別・いじめなど、キリスト教徒との違いも実感として分からない私たちに考えさせられたシーンもあった。
最後の方は前半と違った「転」が繰り広げられるが、「結」のところはちょっと物足りなかった。
スピルバーグ監督の過去が明かされる自伝的作品。 本年度ベスト。
予告編が映画作りの愛に溢れた作品みたいな感じで期待して鑑賞。
だけど映画作りの要素は少なめ。
スピルバーグ自身の幼少期から映画監督になる事を決意する迄を描いたストーリーでした(汗)
そんな思い込みから出だしでスピルバーグ(本作での名前はサミー)が家族と初めて映画を観るシーンから、サミーが8ミリカメラである乗り物を撮影するシーン。
その後、ある工夫で銃を撃つシーンで火花が飛んでいる様に見せるシーンなどに引き込まれる。
その後も映画作りのシーンがあると思いきや思ってもいない展開に。
本作のメインはスピルバーグの自伝がメインだと言うことに気付く(笑)
期待と違った展開に新たに気持ちを入れ替えて鑑賞する事に(笑)
近くにいたオジさんはこの頃、早々と劇場を後に(笑)
多分、自分と同じ感じで鑑賞していたと推測です。
サミーが与えられた8ミリカメラで家族の団らんを撮影し、編集して家族と一緒に観るシーンが印象的。
そんな編集作業の中、あるシーンにに気が付いてしまう展開。
幸せそうな家族だけど知って驚く新たな事実は本当の事なのか?
気になるところ。
サミーがこのシーンを何故編集してしまったのか謎。
その場面を何故編集する事にしたのかは後になって知るけど、そうする事の意味も解らず。
サミーがユダヤ系アメリカ人と言うことで学校でのイジメが辛い。
卒業前に学校をサボって海で皆で遊ぶシーンの映像が良い。
そこにも映画作りの遊び心のある工夫が印象的。
終盤、ある映画監督の巨匠と数分だけ会話するシーンのセリフが印象的。
そこからのラストのワンカットはメッチャ良かったです( ´∀`)
全389件中、221~240件目を表示