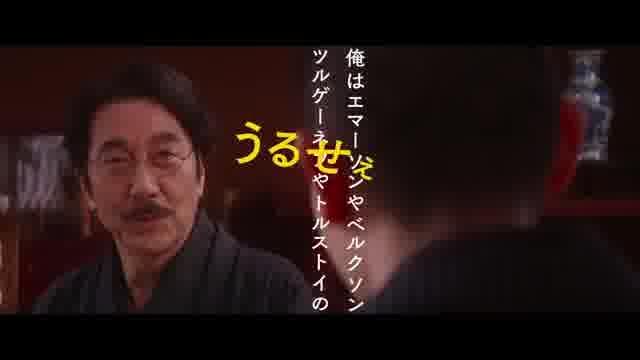銀河鉄道の父のレビュー・感想・評価
全205件中、161~180件目を表示
「ありがとがんした」
残念だけど、凡作である。私なら人に勧めない。
当初、直木賞受賞作品である原作を読んでから鑑賞しようと考えていた。書店で文庫本の厚さを見て断念した。長編で時間がなかった。だから、もともと原作が駄目なのか、或いは映画化作品が悪いのか判断できない。
カメラワークが安定していず、絶えず画面が動いている。当初は宮沢賢治の先の定まらないブレる人生を表現しているかなと思ったが、作品を書き始めからもブレるので、居心地が悪い。
役者さんはよく演っていると思うが、演出又は脚本に問題があるのか、或いはもともとの原作がその程度の作品かもしれない。物語を面白くするため、多少の脚色は認めるが、やり過ぎかなと思ってしまう。最後の鉄道列車での再会はいい締め繰りだと思うが、どうせならもっとVFXを使用して、いかにも銀河を走る鉄道列車にしてほしかった。
壮大な親バカ物語
子供ファーストの父
直木賞を受賞した作品の映画化。原作も発売当時に既読し、ストーリーや展開は、原作のイメージ通りの内容であった。『雪わたり』や『やまなし』等、今もなお小学校の教科書に掲載されている宮沢賢治作品。激動の明治、大正、昭和と生き抜き、亡くなって初めて、世に認められるようになった宮沢賢治の作品だが、現在では、、日本を代表する文士として、多くの人に愛され、誰もが知ることとなっている。
しかし、名前や作品はよく知っていても、宮沢賢治自身の事はよく知らなかったので、今回改めて、賢治の父の視線で描かれた本作を通して、宮沢賢治という人となりの理解も深まった。揺らめくランプの炎のシーンが随所に盛り込まれ、当時の日本の原風景が色濃く残る、賢治の故郷と相まって、温かなレトロ感を映し出している。
宮沢賢治の人柄については、「アメニモマケズ・・・」の詩から、質素で誠実で、田畑を耕しながら作品を手がけていたイメージを持っていた。しかし実の所は、質屋の倅で、金持ちのボンボンであること、先見性の無く新しいものに飛びついては失敗を繰り返す、不肖の息子。尚且つ、父に表面では反抗しながらも、実のところはファザコンで、妹への異常な愛情を示すシスコンの意外な面もあり(ただ、映画ではそこのところは、あまり色濃くは出していませんでしたが…)真っ直ぐな心持ちの人であることを伝わってきた。
そんな賢治の一番の理解者で、無上の愛を捧げたのは、やはり父・政次郎であり、その姿は、当時の父親像からしたら、子供の思いに寄り添い、後押しをしてくれる、先進的な子供ファーストの父親であったのだろう。
本作の見所は、やはり賢治と政次郎の親子役を演じた、菅田将暉と役所広司のアカデミー賞俳優同士による、親子愛情劇であろう。賢治のラストシーンは、魂を揺さぶる2人の演技に、熱いモノが込み上げてきた。そんな中で、賢治の妹役を演じた、森七菜の凛とした演技も、印象に残った。
なるほど、父親目線のストーリーだからか。
予告編を観て、タイトルに父がついているので、宮沢賢治が作家として頑張るのを父親が反対したり応援したり、色々揉める話かなと想像しながら着席。
岩手県花巻市で質屋を営む宮沢家に生まれた長男にお爺ちゃんが賢治と名付ける。それから始まる父親の政次郎と賢治の関係。あっという間に中学生卒業!?しかもそんな成績で?親としては家業を継いで欲しいよね、長男だし。でも嫌がる賢治はまったくちがう夢を語る。こりゃ長い対立になるなと思ってたら、そうでもない。娘トシの言葉に説得され賢治を農業高校に進学させる。なのに辞めちゃう。そして宗教家になろうとする?本当、ワガママというか自由奔放な人生だ。そして妹の言葉からやっと作家になる事にする賢治。やりたい事をこんなにバンバン変更する息子を応援し続ける父親。賢治がどうやって生活してるか一切分からなかったので、金持ちの父親が援助し続けていたと想像。いい意味で本当に親バカだ。少し物足りなかったのが、賢治にプロの作家感が全然ないのに突然自分の本を持ってきたり、本屋さんで売られていた事。あ、父親目線だからか!と納得。
とにかく役所広司さん、なりたての父親から爺さんになるまで、見事な演技、流石です。菅田君もヘンテコな奴、しっかりはまってたよ。
そこそこ楽しめました。
号泣。。。しなかった
宮沢賢治の名前を知っている人にお勧めする映画
【”あの家族ありて、宮沢賢治ありき。”それまでの宮沢賢治像を粉砕した父の”駄目息子だが愛せずには居られない。”という想いが尊い。そして、妹トシを演じた森七菜さんの畢生の演技が輝く作品でもある。】
ー 序盤は、私が勝手に思っていた”聖人”宮沢賢治の姿とは違う、我儘で生きる道の定まらない賢治の姿にやや違和感及び新鮮な想いを覚えながら鑑賞。
因みに原作は未読である。-
◆感想
・前半は賢治(菅田将暉)の妹トシを演じた森七菜さんの演技に驚く。
ー 何時からこんなに凄い女優さんになったの!田中泯さん演じる厳格な祖父が認知症になり暴れた時に、”綺麗に死ね!”と言ってビンタを張るシーンには参りました。
更に彼の有名な”永訣の朝”の死の間際のトシを演じるシーンも参りました。
”うまれでくるたてうまれてくるたて/こんどはこたにわりやのごとばかりで/くるしまなあよにうまれてくる”という原作の言葉をトシが実際に伝えるシーン。
賢治が記した”永訣の朝”を換骨脱胎した最良の形ではないだろうか。
トシが居たから宮沢賢治は詩人になり、更に”日本のアンデルセン”になった事が分かるのである。-
・賢治が生まれた時からの父(役所広司)の溺愛振りは男親として良く分かるが、終生、嫌、賢治が死んでからも賢治全集を出版した父の息子への想いは素直に頭が下がる。
■やや違和感を感じたシーン、だが。
・賢治が日蓮宗に傾倒し、浄土真宗を信じる父に対し反発する故か、法蓮華経を狂ったように口にしながら、白装束で団扇太鼓を叩くシーン。
実際に賢治は日蓮宗に傾倒していたそうだが・・。
狂的感じがして、作風から浮いていた気がするのである。
あのシーンは賢治の不器用だが、ひたむきな性格が表れたシーンであるとも思う。
■賢治臨終のシーン
ー 名優、役所広司の演技が炸裂する、涙零れるシーンである。
彼の有名な”雨ニモマケズ”を賢治が患った際に、父が賢治が籠っていた祖父の家で見つけ、蝋燭の僅かな明かりで、驚きの表情で読む姿と発した言葉。
”良い詩だ、賢治”
からの、”雨ニモマケズ”を涙しながら大きな声で臨終間際の賢治に聞かせるシーン。
そして、賢治は僅かに目を開いて”初めて褒められたじゃ・・。”と呟くのである。
<今作は今や、世界の宮沢賢治を、父を筆頭にした家族の視点で描いた作品である。
そして、今の世間が認める宮沢賢治があるのは、彼を愛した彼の家族がいたからだという事に気付かされるのである。
更に言えば、役所広司、森七菜(今作の”MIP”だと、私は思う。)、菅田将暉、坂井真紀、田中泯という俳優陣達の演技の凄さにも改めて敬服した作品でもある。>
■追記 <2023年5月11日>
・当初、評点を3.5にしていたが、俳優陣の演技及び今までにない賢治像を見せてくれた事を鑑み、4.0に変更させて頂く。
理由は、今作鑑賞後、宮沢賢治の幾つかの作品(”よだかの星””ビジテリアン大祭”)を読み返した時に、今作が言わんとしている事が腑に落ちたからである。
父の偉大さ、愛の深さ、そして宮沢家
宮沢賢治・・・名前は知っているが、詳しい生い立ちは知らず。
それを、父親目線から描いた本作。
質屋の長男、後継ぎとして生まれ、期待されるも、
童話書いたり、人口宝石の製造や、日蓮宗への傾倒、と
何がしたいのか目的も見つけられず、右往左往、自暴自棄な日々。
そんな賢治を引き戻したのが、妹トシ、そして家族。
代表作のタイトルやフレーズがところどこに散りばめられ、
「雨ニモマケズ」や「銀河鉄道の夜」のところでは涙うるうるでした。
父親政次郎を演じた役所広司、演技がすごすぎ、うますぎ。
親ばか、甘すぎ、ともとれるが、とにかく賢治をはじめ、家族への愛の深さ、
受け止める度量、器の大きさを存分に描いていた。
そして、賢治役の菅田将暉もすばらしかった。
親との衝突、いろいろな悩み、葛藤の表現。
意外と言ったら叱られそうだが、妹トシ役の森七菜の度胸のよさ、
芯の強い女性を見事に演じており、よかった。
娘二人がこの春社会人となった私も父として、どうだったのか、
また、80歳になった私の父は元気にしているのか、と
ふと思い浮かべてしまった。
家族とはこうありたいものだ。
まるでドキュメンタリーを観ているような感動がある‼️❓
宮沢賢治といえば、国語の教科書で見て、ああこれかレベルで、本屋などでも見慣れない、ある意味、神格化された、存在です。
それが映画化されると聞き、胡散臭い、道徳じみたものを予想していましたが、予想を良い方で裏切り、少なからず感動しました。
役所広司と菅田将暉を観ていると、演技が上手いとゆうレベルではなく、まるで、そこに本人がいるかの如く、引き込まれていくのです。
いかんせん、音響がセリフに被せる如く、うるさすぎて、演技を台無しにする演出が最悪ではあります。
こんな親子、森菜々の妹、良い家族だ、それが短命な人生で、より輝いて見えるのかもしれません。
変人の伝説が多い賢治ですが、こんな理解のある親父は、最高の父だと思いました、良いものを見せて貰いました、ありがとうございました😊😭
驚きは余り感じませんでしたが、安心して感動に浸ることができました。
門井慶喜の同名の直木賞受賞作を映画化。詩人で童話作家の宮沢賢治(菅田将暉)と父、政次郎(役所広司)の強い絆で結ばれた親子の物語に、心温まることでしょう。
賢治の誕生から37歳の若さで亡くなるまで。短いとはいえ、濃密に生きた時間を、2時間8分の上映時間に収めるのだから、駆け足気味になるのはやむを得ませんが、政次郎の視点という軸があるので、散漫な印象にはなりませんでした。
物語は、賢治が質屋を営む裕福な政次郎の長男として誕生するところから始まります。 賢治が赤痢にかかれば、医者になど任せられないと、政次郎はつきっきりで看病するなど、跡取りとして大事に育てらます。
けれども、家業を「弱い者いじめ」だと断固として拒み、農業や人造宝石に夢中になって、父・政次郎と母・イチ(大空ゆうひ)を振り回すのでした。
家業の質屋を継いでもらいたいはずの政次郎が、賢治の妹、トシ(森七菜)のお世辞にまんまと乗せられ、進学を許してしまうのです。
そんな中、賢治の一番の理解者である妹のトシが、当時は不治の病だった結核に倒れてしまいます。賢治はトシを励ますために、一心不乱に物語を書き続け読み聞かせるのでした。しかし、願いは叶わず、みぞれの降る日にトシは旅立ってしまいます。「トシがいなければ何も書けない」と慟哭する賢治に、「私が宮沢賢治の一番の読者になる!」と、再び筆を執らせたのは政次郎でした。
「物語は自分の子供だ」と打ち明ける賢治に、「それなら、お父さんの孫だ。大好きで当たり前だ」と励ます政次郎。だが、ようやく道を見つけた賢治にトシと同じ運命が降りかかるのでした。
子供の頃に赤痢で入院した賢治を泊まり込んで看病する政次郎に、祖父の喜助(田中泯)はおまえは‟父親すぎる”と言われていました。
本作で一貫するのは、政次郎の親バカぶりです。あの頃の時代の父親像といえば、威厳を崩さず、愛情を隠しながら、我が子の所業を見守ることが当たり前でした。
その点政次郎は、一見頑固オヤジのように見えますが、大人になっても家を出て下宿生活をする賢治に仕送りをしたりと、子どもの現状を常に考えて一番いいことをしてやろうとする、優しいというか子どもに甘い父親だったのです。
けれども賢治は、人造宝石なるものを作って商売をしたい。日蓮宗とともに生きていくのだ!そういうことを突然言い出だして、政次郎を驚かせ、あたふたとさせてしまうのです。
このあたりの描写は、聖人視されがちな賢治とは違う姿が見られ、興味深いところでした。賢治も怒る政次郎を無視してはおらず、父子の二人三脚によって、踏み外しそうになった道が軌道修正されていく様子が伝わってきます。役所と菅田の2人の演技巧者が楽しげに役に没頭。醸し出されるユーモアが心地よかったです。
政次郎は、また賢治の書く童話のファンでした。面と向かっては口に出せない息子への愛を、童話のファンという口実で伝えていたのでしょう。照れ隠しのような笑顔とぶっきらぼうな言葉で。未完で終わる『銀河鉄道の夜』を朗読する姿には、親として賢治にしてやれなかった多くのことを残念に思う気持ちがあふれていました。
役所広司は原作にある‟厳格だが、妙に隙だらけの父親”というような一文から、政次郎という人柄のヒントを得たと言います。
右往左往してきた賢治との親子関係ですが、あの時代には珍しい親子の絆を強く感じました。
トシが亡くなり、賢治が病魔に襲われ、死の影が濃厚に。一般にイメージされるような賢治の姿が描かれ、政次郎が寄り添うようにそばに寄り添います。驚きは余り感じませんでしたが、安心して感動に浸ることができました。
ただ政次郎の目から語られる本作は、宗教家としての賢治が全く語られません。30年前にある著作家の盛岡講演会に参加したあと、同じ参加者からのお誘いで、賢治の生家におもねき、当時存命だった実弟の宮沢清六さんから、詳しく兄賢治の思い出を聞くことができたのです。
そこで出た話は、本作とは全く違う宗教家というか、魂の真実を語り続けた賢治の姿でした。なかでも思い出に残るひと言は、「兄は農業学校の教壇に立つと、いつも人の一生とは、時間を旅する旅人のようなものだ」というたとえ話を生徒たちに話しかけて、輪廻転生を力説していたそうなのです。
政次郎がファンだと公言した賢治の童話がなぜ時空を越えたファンタジックな世界観に包まれているのか、賢治の宗教観を切り離して描いても彼の本質を捉えられないだろうと思います。
今生の死が終わりではなく、来世につながっていくこと。そこに賢治の大きな希望があったのです。
一説によると、賢治は生まれ変わって、現代で青春映画を描く旗手となっているという話があります。「人生は旅人」であるとした賢治の言説から、その可能性もなくはないでしょう。ちょっと不思議な悲恋を描く作品からは、「銀河鉄道の夜」などの過去の作品で描かれた世界観と共通するところはあります。
とにかくひとりの有名作家の父親という視点だけで終わった本作は、成島出監督の人生の本質に対する観点の限界を感じずにいられませんでした。
父から見たハラハラする宮沢賢治
宮沢賢治ではなくあくまでも宮沢賢治の父が主人公。子煩悩で親バカでもあるお父さんが微笑ましく役所広司の芝居がしっくりくる。
宮沢賢治自体の人生全ては描いておらず、父から見た宮沢賢治だ。
親というのは子どもがいくつになっても、我が子のことは心配で可愛い存在なのだ。
そういう視点から描かれた宮沢賢治像は観るものも親目線で見てしまう。ちょっとハラハラもする。
宮沢賢治本人の葛藤や心の内はあまり描かれていないので、日蓮正宗にハマったシーンなんかは結構ヤバい人にも見えてしまう。
難しいと思うが菅田将暉はなんでもサラッと演じてしまって大したものだ。
途中までは、別に風の又三郎の父でも、雨ニモマケズの父でも良いでは無いかと思わせつつ予想通り、最後に銀河鉄道の夜のシーンが出てきて泣かされる。
森七菜演ずる妹が元気な時も結核になってからも賢治の心の支えになっていたと思う。
エンドロールの曲がやけにチープなのを除けば面白かったと思う。
純粋な精神を取り囲む素晴らしい家族愛
直木賞を受賞した原作は未読である。宮沢賢治の父についてはあまり資料がなく、出てくる作品ごとに人格が大きく変わっている。井上ひさしの「イーハトーボの劇列車」に出て来た父は、理屈ばかり先走る息子の行動を、自分は門外漢のはずの法華経信仰に立脚した理屈によって息子を論破して、花巻に連れ帰るという強靭な人格の持ち主だった。
本作の父・政次郎は一見厳格な人物のようで、実は息子にも娘にも甘さを残した好人物であった。自分も人の子の親として子育てを終えた時期であり、子よりも親の方に関心が向く。個人的にこの政次郎には同感すること甚だしく、実に好ましい人物であった。人は誰もが純粋な精神を持つが、時々妥協しないと生きて行くのには非常に苦労する。賢治はこの妥協が苦手な人物で、あくまで自分の理想を追求しようとして生きた。こういう子を持った父親はさぞ大変な思いをしたはずである。
政次郎が主人公と言いながら、話の軸は息子の賢治と娘のトシになっている。賢治は中学卒業の時に法華経を読んで感動し、家の宗派が浄土真宗であるにも関わらず法華経の信仰を続けて死ぬまで変えなかった。賢治の創作は全て法華経信仰の上に成立していると言って良い。それをちゃんと描いて欲しかったのだが、周囲の空気も読まずに太鼓を叩いてお題目を唱えまくるという行動は、怪しげな新興宗教の信者のようで少し違うのではと思った。それにしても、あれほど熱心に法華経を信仰した賢治を若死にさせたのでは、法華経のご利益も頼むには値しないとしか思えない。
作品を自費出版したもののほとんど売れず、死後に評価が高まって、今や宮沢賢治研究を本業とする者までいるというのは、あたかもゴッホのようである。彼らの作品は、妥協を嫌って自分の純真さを保ち続けた者だけが見せられる世界のように思える。人々が彼らの作品に魅せられるのは、自分たちが成し得なかったそうした純真さの追求が何物にも代え難い尊いものに思えるからであろう。「鬼滅の刃」の竈門炭治郎の心象世界のような美しさといえば伝わりやすいかも知れない。
残念だったのは「イーハトーボ(ヴ)」という言葉が一度も出て来なかったことである。賢治が理想郷として提唱したもので、この世界観があってこその賢治の人生ではなかったか。自分が何者で、何を成すために世の中に生まれたのか、人の人生とはそれを探求するためにあるとも言えるものであり、我が子を育ててみるのが最も早道だと思うのだが、未婚だった賢治には、そういう理想郷が必要だったのであろう。
役者は本当に文句なく、役所広司も菅田将暉も森七菜もハマり役だった。菅田は結核で死ぬ役に合わせてかなり減量して臨んでいたようだった。役所広司の若作りは CG のようであったが、それほど違和感はなかった。菅田はチェロを自分で弾いており、見事な成り切りっぷりだったが、それならば賢治が帽子をかぶってコートを着て農場に佇む有名な写真も再現してほしかった。
音楽も演出も感動を盛り上げる力が半端なく、本当に泣けて仕方がなかった。唯一腹が立ったのはエンディングの全く関係もない能天気な歌である。何故あんなもので感動に水を差すのか、真意が図りかねた。
(映像5+脚本4+役者5+音楽4+演出5)×4= 92 点。
久々の森七菜の着物姿が良かった
質屋を営む宮沢政次郎の息子・賢治は長男で家業を継ぐ立場なのに中学に進学を希望し、中学校卒業後は農業高校(今の岩手大学農学部)へ進学したり、卒業後は人工宝石の製造販売をしようと考えたり、浄土真宗の家なのに日蓮宗へ傾倒したり、とマイペースで自由気ままに過ごしていた。そんな賢治に対し、父政次郎は新しい父親像を目指し、賢治の希望を叶えてやろうと甘やかしてしまっていた。やがて、妹のトシが結核にかかり、賢治はトシの希望で物語を書くようになり・・・そんな賢治を見守る父は・・・という話。
宮澤賢治の事をほとんど知らずに観に行ったので、彼がそんなに優秀だった訳でもなく、若い時から文学青年でも無かったのだと初めて知った。宮澤賢治に興味が無かったので、銀河鉄道の夜も風の又三郎も読んだかもしれないが内容はほとんどおぼえていない。
そんな宮澤賢治の両親が素晴らしく、当時の長男に対する押し付けも無く、愛に包まれた家庭を作ってたのが素晴らしかった。役所広司と菅田将暉はさすがで、良い味出してた。
久々に観た妹・トシ役の森七菜は着物が似合ってて存在感が有った。
坂井真紀、田中泯、も良かった。
学校で習ったくらいな知識でした
『宮澤政次郎』一家!!
本作の主人公はそのタイトル通り
『宮沢賢治』の父親の『宮澤政次郎(役所広司:演)』。
『賢治』原作の映画化やアニメ化は数多くあれど、
稀代の有名人である作家本人にスポットを当てた作品は少ないと記憶。
直近のノンフィクション、
『今野勉』による〔宮沢賢治の真実-修羅を生きた詩人(2020年)〕のような著作を底本に
妹の『トシ』を含めて劇的な映像化もできたとは思うが。
にもかかわらず敢えてその父親を描こうとのモチベーションは
原作者の『門井慶喜』からして頗るユニークな視点。
とは言え、こうして主人公としての父親の生涯を俯瞰すると、
時代を越えた感慨を持つのも事実。
授かった長男を溺愛するあまり入院に付き添い、
却って病を感染されてしまうなどはその好例。
イマで言うところのイクメンの嚆矢か?
いやその親バカぶりは膏肓に入っているとの表現があてはまる。
時として悩み、時として反発し、しかし
傍から見れば思わずくすりと笑ってしまう
愛したばかりに弱みを見せる父親の可笑しさ。
二男三女に恵まれはするものの、
上二人の男女を共に結核で亡くすのは痛恨の極み。
結核についていえば、
当時の特効薬ストレプトマイシンが世間に出回るのは1950年以降のこと。
栄養が十分に足りている家の人間でも罹ってしまうのは
死病と恐れられることの背景。
また、次男が元々の生業である質屋を
機械等を扱う「商会」に業態変更するなどの変転も体験。
が、やはり、『政次郎』の一番の心配のタネは
長男だったろう。
そのエキセントリックな性格や突飛な行動は、
今の基準で見ても甚だ異端。
三十七歳で亡くなるまで独身を貫き、
(ただ本作では『保阪嘉内』との関係性による懊悩は
すっぽり抜け落ちているが)、
家を重視する当時の社会規範から見れば
(いくら最愛の息子とはいえ)それなりに手を焼いたことだろう。
『トシ』についても女学校時代にはスキャンダルに見舞われ辛酸をなめ、
家族も辛い思いをしているハズだが、
そのあたりのエピソードもすっぽり外しているのは、
やはり長男との関係性を強く前面に出したいがためかとも納得はする。
準主演の『菅田将暉』は
奇矯な行動と、相反する温和さも併せ持ち、
最後は諦念の境地に至る『賢治』を
鬼気迫ると評しても良いほどの渾身で演じる。
観ていて鳥肌が立ってしまうほどの。
父の深い愛 〜 俺は修羅になる
人生に悩む息子宮沢賢治を心配しながらも寄り添い穏やかな眼差しで見守り続けた父政次郎を、役所広司さんが時にコミカルに魅力的に演じる。
苦悩しながらも活き活きと瞳を輝かせ実直に生きた宮沢賢治を菅田将暉さんが熱演。日本アカデミー賞助演男優賞なるか…。
賢治の妹トシを演じた森七菜さん( 未だ21歳とは驚き! 👀 )の熱演に涙。
田中泯さんの存在感、坂井真紀さんの柔らかな物腰に魅せられた。
ひたむきで実直な言葉で綴られた数々の作品の誕生は、宮沢賢治の生き方を尊重した父親と温かく見守り続けた家族の支え故なのですね。
美しく穏やかなラストシーンは、宮沢賢治の世界観そのものでした。
是非映画館で。
映画館での鑑賞
宮沢家という一つの家族の物語
初日舞台挨拶付きの回を鑑賞。
方言に苦戦したと言ってたが、東北人ではない自分には違和感なし。監督が、本来は「賢治」は方言的な発音で「けんず」になる為、映画の中で「けんず」にするか「けんじ」にするか、かなり悩んだそうな。
教科書に出てきたいくつかの作品に触れたことしかなかった宮沢賢治。こんな人物、こんな人生だったとは知らなかった。
2時で少々詰め込んだ感はあるが、父親目線でまとめていると思えば許容範囲。
雨ニモマケズは学校で暗記したので今でもほぼ暗唱出来るくらいだが、映画を見る前と後で感じるものが全く変わる。
宮沢賢治の作品を読みたくなった。
余韻に浸りたいのに、ラストシーン後に流れ出した女性ボーカルの曲でさめてしまいそこが少々残念。
全205件中、161~180件目を表示