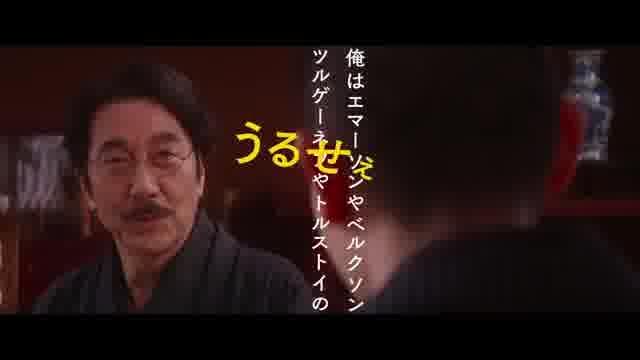銀河鉄道の父のレビュー・感想・評価
全206件中、1~20件目を表示
父でありすぎる父から見た息子・宮澤賢治
いやはや、宮澤賢治を子に持つと大変だ。それでも、そこに愛情があれば苦労が喜びに変わるのは、世間の親と同じなのかもしれない。
賢治は次から次へと行き当たりばったりで奇妙な行動に走るが、何故そうしたくなったのかという彼の内心の描写は、物語の中ではあまりされない。賢治が有名なこともあってつい物語の中心に置きたくなるが、主人公はあくまで父の政次郎だ。
賢治の動機に関する説明が少ない分、彼の行動はいっそう奇異に見える。胡散臭い商売(人造宝石)を思いついたり、宗教にのめりこむ。こんな家族が自分に実際にいたらもう大変だ。賢治の気持ちに同調するというより、政次郎の心労に同情する気持ちで見てしまう。
予告映像の雰囲気やテーマソングから受ける明るい印象に反して、中盤以降は死別の悲しみが繰り返し描かれる。祖父の喜助、トシ、そして賢治。「永訣の朝」が脳裏にあると、序盤にトシが登場した段階で死の気配を感じる。
これは、政次郎が肉親の死を介して生きることの意味に触れる、そんな物語でもある。子に先立たれる親の悲しみは、経験のない身には想像する術もないが、親子愛だけでなく、死の受容の物語であるように見えた。
賢治はもちろん強烈だが、トシの人となりがまた印象的だ。
賢治の進学を政次郎に進言するアプローチとして、ただゴリ押しのお願いをするのではなく、父をうまいこと持ち上げて納得させる。認知症の傾向が出はじめて暴れる喜助の頬を張り、「きれいに死ね」と言い放って抱きしめる。爽快感を覚えるほど、賢くて気丈だ。
インパクトのある「きれいに死ね」だが、原作のトシは喜助に面と向かってこう言ってはおらず、喜助宛ての手紙をしたためている。手紙の主旨を表す言葉として地の文に「きれいに死ね」という言葉が出てくるのだが、手紙の本文は実際に宮澤トシが祖父に宛てて書いた手紙の文章がそのまま全文引用されている。この文章が、祖父の心情への配慮も行き届いていて実に見事なのだ。
ちなみにこの手紙は、政次郎の意向により喜助に見せられることはなかった。
原作で手紙の要約として提示された言葉を、本作ではトシがずばり口にしたわけでちょっと複雑な気持ちにもなったが、映像化するならこうするしかないし、森七菜の演技がよかったので原作とは違うよさがあるシーンになっていた。実在の宮澤トシがこのメッセージを祖父に伝えたいと思ったその願いが、フィクションの中で叶えられたような不思議な感慨があった。
賢治が亡くなる場面で政次郎が「雨ニモマケズ」を朗読し始め、その後号泣という演出は、正直御涙頂戴感が強くてスーッと冷めてしまった。そしていきものがかりの流れるエンドロール……いきものがかりは予告で分かってはいたけれど、いきものがかりのファンの方には申し訳ないけれど、「星めぐりの歌」でも流してくれた方がまだ余韻にひたれたかな。
邦画にありがちなアレンジで最後に安っぽさが出たのは残念。
役所広司にしか表現しえないこの父親像
誰もが人生において宮沢賢治の詩や物語に心動かされるにつけ「賢治はどのような人だったのか」とは思うだろうが、その父親までは想像が及ぶまい。本作は偉人伝記において助演か脇役の存在に過ぎない「父の視点」で宮沢家の肖像を情緒豊かに綴った物語。やがて賢治が農業と並行して執筆を続け、彼の死後になって評価されるのは広く知られた話であるし、妹の存在が執筆活動を精神的に支えたという逸話も聞き覚えがある。それに比べて、父は文学的な素養があったようにも見えず、木訥で、平凡。賢治を精神的に力強く導いたわけでもなさそうだ。けれど役所広司演じるこの主人公は、賢治の創作世界を決して否定せず、自らがいちばんの読み手であり、理解者であろうとする。それがどれほど賢治の支えになったことか。常に浮遊するようなカメラワークが役所と菅田の化学反応を流動的かつ柔軟に捉え、彼らにしか築くことのできない父子の愛のかたちを実直に謳っている。
宮沢賢治についての知識と、観客自身の経験値によって評価が変わりそう
明治から昭和初期の時代を生きた作家・詩人、宮沢賢治の伝記映画は過去にもあるが、「銀河鉄道の父」は小説家の門井慶喜が賢治の父・宮沢政次郎を主人公に据えた直木賞受賞作の映画化。役所広司が演じる政次郎の視点から、賢治(菅田将暉)、賢治の妹・トシ(森七菜)ら家族の成長や試練を綴っていく。成島出監督と役所とのタッグは1月公開の「ファミリア」から2作連続で、「油断大敵」「聯合艦隊司令長官 山本五十六」を合わせて通算4度目。
宮沢賢治の代表的な詩や小説を読んでいても、生い立ちは知らないという人も多いだろうから、賢治の生涯をたどる入門編としての意義もある。波乱万丈に生きた人物なので、駆け足の紹介になっている点や、賢治の創作の真髄にまでは迫りきれない父親視点ゆえの限界など、物足りなさも。
政次郎が当時の父親としては異例なほど熱心に子育てに関わり、賢治やトシが病の折には献身的に世話をする様子も描かれるので、子育て経験のある親世代の観客には政次郎やその妻(坂井真紀)に感情移入しやすいだろうか。若い世代でいまいち話に入り込めなかったとしても、さまざまな人生経験を積んで遠い将来に再見したらまた違った評価になるのかもしれない。
日没のマジックアワーの時間帯を狙ってワンテイクで決めたという屋外の火葬シーンでの菅田と役所の熱演など、見応えある映像は確かに劇場の大スクリーンでの鑑賞にふさわしい。ただ、個人的には「ファミリア」の現代性の方がより響いた。
宮沢賢治を主役に据えるのではなく、宮沢賢治の父親を主役にすることで宮沢賢治を描いた実話。
本作は、宮沢賢治の父親を主役にする事で宮沢賢治を描いた実話・直木賞受賞作「銀河鉄道の父」の映像化作品です。
主演の役所広司は宮沢賢治が生まれたての時から、宮沢賢治が37歳の段階や、それ以降も(吉永小百合の如く)演じ分けているのは意外にも違和感がありませんでした。
本作の面白さは、何と言っても父親を主役に据えることで「宮沢賢治の一家」を通して宮沢賢治の立ち位置や家族からの影響などが分かる事でしょう。
実際に、これまで見た事がない視点で宮沢賢治が描かれていて、ようやく俯瞰して宮沢賢治という人物像が見えた気がします。
本作は基本は実話なのですが、ラストシーンの件は、史実とは異なります。
ただ、「宮沢賢治の一家」の家族愛の物語を描くには、史実とは少し違うラストもリアリティーがあって良いと思いました。
宮沢賢治の優しさ、過集中ゆえの脆さまで心に響く。宮沢賢治をこれまでにない視点で描いた傑作!
本作でメガホンをとった成島出監督は、「マルチな才能で資料が膨大すぎる宮沢賢治を1本の映画では描ききれないと思っていた」とおっしゃっていた。しかし本作の原作に出会い「これだ!」と動き出した原動力が、本編を最後まで見るとよくわかる。
長男である賢治の父親(政治郎)の「親っぷり」を存分に演出しながら、賢治の家族も丁寧に描かれており、賢治の様々な挑戦がダイジェスト版のように随所にちりばめられている。家族に焦点を合わせることで、あまり知られていない賢治と彼を支えた家族の物語を描くことに見事なまで成功させた。
質屋を営む両親が、自由な長男・賢治の数々の決心にその都度驚く表情や姿も見どころの一つとなるほど、些細な場面でも見逃せない演技が満載なのだ。
設定では岩手の花巻市が主な舞台なので、方言を学ぶところから役者は相当苦労しただろうし、何より主演の役所広司を筆頭に演技が素晴らしかった。
夜になると小さな灯りを頼りに執筆をしていた宮沢賢治を象徴しているように、町並みも街灯を抑えていたからか、星が特に美しい。これはランプの灯りを最大限に活かし、ライティングを徹底的にこだわり、高感度カメラを使用するなどの隠れた制作の苦労によって成り立ったものだ。明治、大正、昭和を感じる背景の雰囲気もどこか懐かしく、あたたかい気持ちになる。
このような様々な制作の苦労もあり本作の体温が伝わり、ラストの展開を含めて涙が止まらなかった。
家族愛がテーマ
特に賢治に対する父・政次郎の愛は凄まじく、この時代にしては柔軟な父親で驚きました。賢治は幼い頃から病弱で手がかかったこと、また長男でありながら実家の質屋を継がず父・政次郎と喧嘩が絶えなかったこともあり、その分、他の子供よりも特別に可愛かったのではないかと想像します。また、賢治は自分を理解してくれるトシに対して愛情深く、トシが結核に冒されたときは彼女が喜ぶように物語を一生懸命に書いたり、看病に徹するシーンは兄妹愛を感じました。とにかく本作品で心が洗われ、何処かに置き忘れた何かを思い出させてくれるなど人間の本質に迫った作品
宇宙の中で
ラストは泣ける。前半はあまり盛り上がらないが、それは後半に生きてくるので、我慢して観よう
父の視点で描くというアイデアがうまくハマっていると思う。この映画というより、原作の門井 慶喜氏のアイデアだが。
この映画を見る前は、宮沢賢治は偉人で、子供の頃から立派だったのだろうと思っていたが、そうでもない姿が描かれる。なので、観ていて、しばらくは気持ちが盛り上がらない。でも、父親の視点で観ているので、「そうだよなあ。子供って親の期待通りには育たないよなあ」と、宮沢親子に共感する気持ちになる。あとで調べてみると、宮沢賢治が挫折したり、脇道にそれたりしたのは、実際にあったことのようなので、宮沢親子の葛藤もこれに近かったのだろうと思った。
映画の後半は、文学に励む姿や、農業指導をする姿が描かれて、自分が抱いていた宮沢賢治イメージに近づく。後半は、感動的なセリフがたくさんでてきて、泣けた。特にラストの賢治の死の場面は、涙があふれた。
前半の「親の期待通りには育ってくれない」ということや「賢治自身、思った通りに行かない」ことが、後半のセリフの背景にもなっているので、共感がより深くなった気がする。
宮沢親子に役所広司と菅田将暉を配したのは正解。観ていて爽快とは言えない前半から映画に入って行けたし、映画の仕上がりを数段上げていると思う。
エピソードを上手に切り取ったり、感動的なセリフを創ったりした脚本の坂口理子さんにも拍手。アリガトガンシタは何度か出てきたが、どれも感動的。
津軽弁なので、セリフが聞き取れないところがあったので、Amazonの配信で字幕ONにして鑑賞。
子供への期待と愛と先立たれる辛さ
最近ハマっている時代背景の映画。宮沢賢治の家柄や生い立ちを知り勉強になった。役所広司と菅田将暉の見た目と演技が間違いないのはともかく、この娘すごいなと思ったら「この恋温めますか」の森七菜だった。成長した演技にやられました。菅田さんの狂気と悲哀の演技も素晴らしい。時に劣等感を感じながらも優秀な妹に度々助けられ、支えられ、愛し、依存し、失う切なさ。結核で亡くなるのが当たり前の時代にトシに続いてそれを宣告された時の本人の受け止め方と父親の受け止め方の対比。安定しない息子が期待と違った道でなくてもやっと自分の力で歩み始めた安堵と期待。応援する気持ち。そして娘に続いてそんな息子を失うやるせなさ。繊細な子供に親が与える影響やら子供への後悔ない接し方や愛情表現など、またいろいろ考えさせられました。
原作既読。キャストも雰囲気もなかなか良いと思ってたら、喜助役の田中...
原作既読。キャストも雰囲気もなかなか良いと思ってたら、喜助役の田中泯が出てきただけで主役も脇役も全部食ってしまう恐ろしい演技力に圧倒された。父親役はイメージが違った
もっと親のスネかじりで浪費家の宮沢賢治が見たかった
寝た
冒頭から全てがクサすぎて観ていられなかった。せっかく役所広司や菅田...
雨ニモマケズに初めて泣かされた
父親は良かったが
明るい話だと思ったら、、
全206件中、1~20件目を表示