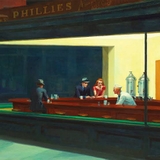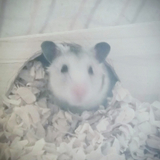福田村事件のレビュー・感想・評価
全377件中、81~100件目を表示
幽霊なんかよりも、よっぽど怖い
オウム真理教のAや佐村河内守のフェイクなど、ドキュメンタリー作家である森達也監督初の劇映画。
関東大震災後の流言飛語などで、朝鮮人や社会主義者が殺されたのは歴史の授業で習ったと思う。(映画の最後に6千人殺害されたと説明があった)
しかし、現在は千葉県野田市となっている福田村で、四国からの行商人9人が、聞いたことのない方言などを理由に日本人ではないとされ、村人に虐殺された事件があったことは、この映画で初めて知った。
当日も結構客が入っていたけれど、重い内容の映画にも関わらず、予想以上にヒットしているようです。
現在も何かあると、SNSでデマを流す奴がいるけれど、根底にある差別意識と群集心理は恐ろしい。心霊スポットや幽霊なんか全然大した事ないよ。
人類の進歩とは。
福田村事件。こんな事件のことは全く知らなかった。1923年、今からちょうど100年前の史実。10年前でもかなり昔に感じるものだが、100年前はこんな暮らしだったのかという描写、フィクションと分かっていても衝撃を受ける。あんな暮らしできないよ。
当時熱狂する者もあった共産主義・社会主義の実験は失敗に終わり、資本主義を基盤とした社会に生きるのが我々現代人なのだが、この先どうなっていくのだろうか。
朝鮮や中国ばかりではなく、他国の者を揶揄する、誹謗中傷する言葉が飛び交う昨今。しかし、今に始まった訳ではなく、人間というのは余所者を排除することで自らのテリトリーを広げ守ってきた訳で、本能にただ従っていると異端を排斥する方向に流れるものなのだろう。それは、欧州の移民希望者に苦慮する現状をみても明らかだ。理想と現実は異なる。
だからといってその状況を追認・黙認していることがイイとは思わない。ただ「見てるだけ」ではいけない。やはり、人間が後天的に獲得する理性で感情や衝動をコントロールする術を、一人一人が磨いていかないとなのだろう。できない人が少なくないという問題はあるのだが。
玉石混淆の情報に振り回されること、重大な事象にパニックとなること。人間はなかなか成長しないなと思う。その成長しないという事実を知り少しでも成長しようと努めるのが、今を生きる人間のあるべき姿だと思うんだけどな。自分自身はできているだろうか。そして、これから先の人類はどうか。
朝鮮人なら殺してもええんか
福田村は現在の千葉県野田市の一部分
「朝鮮人なら殺してもええんか」と断末魔の叫び(沼部新助・讃岐から来た薬売り行商の支配人)
-----------------
関東大震災(1923年・大正12年)があった時、メディアは「新聞」だけでした。AMラジオは同震災の教訓として始まる。
こうした環境では何が正しいのか、分からない状況となっていたのです。
さらに、9月3日に当時の内務省がデマを打電。当時の日本政府が「デマ」を煽ってしまったのです。
打電内容は書籍「福田村事件」49ページ目に記載があります
----------------------
讃岐から来た薬売り行商15名が福田村に投宿していたが、朝鮮人との疑いをかけられ、福田村や田中村の自警団によって虐殺。
6歳、4歳、2歳の幼児、妊婦も含まれていた。
タブーに向き合った
関東大震災で、朝鮮人大虐殺は、あったということ。福田村事件では、結果的に日本人を殺害してしまったという皮肉
被差別部落について 薬売り行商人は香川県の被差別部落出身
-----------------------
千葉日日新聞の女性記者 恩田楓は原作にはない設定ですが、存在感あると感じています。
以下、恩田楓を中心にコメントします
夜、楓は和服を着ている朝鮮飴売りの少女と出会う。「いっしょに歩いてください」「オネガイ」と必死な姿。歩いていると自警団に見つかってしまう。
逃げるのだが足を引っかけられて少女は捕まってしまう。観念し「キム・ソンリョ」と本名を言った途端に自警団の竹槍が突き刺さる。返り血を楓は浴びる。
-------------------
翌朝、千葉日日新聞事務所で上司の砂田に「私の目の前で朝鮮人の女の子が自警団に殺されました、書かせてください」と述べるが
砂田は「朝鮮人が放火したり、爆弾を所持していると、内務省からの通達があった」と返す
「記者が目撃した事実より、内務省の電文を信じるのですか。それを紙面に載せるんですか。その結果、なにがおきてるか、部長は責任を取れるんですか。」楓は述べる
砂田は「俺は書かないで起きることのほうが怖い」と返す
楓は「わからないなら書くべきじゃない」
「私たち新聞は何のために存在しているのですか。読者を喜ばせるためですか。権力のいうことはすべて正しいのですか」
普通の人々が犯す大惨事
きわめて普通の人達が、ひとたびパニックになると、不安と恐怖に駆られ、このような大惨事を犯すのは、今も変わりがないのではないか。
被差別部落からの行商団だったことが悲惨な事実が語られなかった一因になったと思うし、頭の「朝鮮人だったら良いのか」の台詞は重い。
事実とは異なる報道や大本営の通達を行った人々、どさくさに紛れて社会主義者を処刑した警察、デマを信じ煽動された民衆の暗い歴史を私達はもっと知るべき。
メディアの矜持が薄れ、フェイクニュースが増えている今、容易ではないが、情報の真偽を問い、自らの頭で思考する重要性を感じる。妄信や決めつけ、格差や不条理による不安や不満、己れも気がついていない深層心理は怖い。
森達也氏の独自の視点と問題提起力のファン。
ドキュメンタリーの方がいいかも
差異を受容する
愚行録‼️
自分は流されずに戦えるか
過去でも他人事でもない
「朝鮮人なら殺してもいいのか」
答えは1つ
誤った情報に追い立てられ
冷静な判断を欠き
集団心理に呑まれる姿は
人の残虐性はすぐ隣にあること
理性を失う状況においては
自分もそうなり得る可能性が
あることを教える
罪なき人々
特に何も知らないこどもたちまでもが
あっけなく
さっきまでの善人により
命を落とす殺戮の衝撃
それが
この国の史実だということ
そして
恐ろしい火種は消えず
いまも世界中のどこかで
繰り返される差別や争い
発展を遂げてきた人間社会の
暗部の哀しみの歴史として
過ぎ去ったことではなく
他人事でもないのだ
あの絶叫の答えは
変わらずひとつなのだろうが
現実はひとつではない
重い内容だが
今までもこれからも
私たちは集団で生きる人間なのだ
ましてや
情報手段が進化し続ける社会においては
負の威力も計り知れない
私達は武器さえなく殺め、
殺められてしまうかも知れない
これは目を背けてはいられない物語だ
共同体の維持に必要なのは、絶えず他者を異化し続ける「良心」
ようやく見た。
9月1日前後にマスコミでは盛んに宣伝していたが、それから1ヶ月半余りがすぎてしまった。その当時のような、この映画をめぐっての喧騒さはない。
一つひとつ起こった出来事をすぐさま忘れてしまうこの国にあっては、関東大震災やその際に生じた悪夢さえも100年記念として過ぎ去ってしまう。
それは、私たちの誰もが、狂気に満ちて殺戮の道具を手にした村人と同じだからだ。さまざまな肩書きを、必要のないまでの肩書きを手にし、いたずらに借り物の名を名乗りながら、その出来事を単なる通過儀礼のようにように振る舞う彼らと同じだからだ。
通過の儀式。たしかに、それは通過の儀式だった。そのあまりにも小さな無知の共同体の一人ひとりにとって、その共同体を維持する儀式だった。それゆえ、すでに過酷なまでに虐げられてきたその旅人たちは、何の躊躇いもなく、彼らの贖罪山羊になったのだった。
手を下したものは、人定の法によって裁かれようとも、おそらくはその共同体を維持しようとする行為は正当化されたのかもしれない。しかし、今ここにある法によって裁かれ刑に服してとしても、裁かれていないものがそこには残っている。
私たちが、この映画を通して出会うのは、まさに裁かれることを拒否し続ける我々の「良心」のあり方だ。
もう一度振り返ってみればわかる。
この映画の誰一人として、その程度の違いはあるにせよ、自分のことを「良心的」であると疑ってやまない人々だ。過去の事実に向き合うことによって苦しむ夫、その村への移住し夫との生活という現状を嘆く妻、被差別部落出身であることにより仕事の保証を得ようとする沼部、性(さが)に忠実であろうとする咲江、従軍経験を正直に吐露する倉蔵、在郷軍人会の長谷川、そして記者の恩田。
この良心だけは誰にも裁けない。だからこそ、それが良心として残ってしまう。そして、それが集団的になればなるほど、徒党を組めば組むほど、良心は狂気と何ら変わらなくなってしまう。疚しい良心とはまさにそのようなものだ。
例えば、澤田の語った次の言葉は、自分の良心を正当化すると同時に、その良心によって他者を、自分の向こう側へと完全に「異化」しようとするものだった。
3월 1일 만세 사건으로 우리나라는 당신들의 나라에 너무 심한 일을 해 버렸다.
그것을 사과하러 왔다
그래서 교회 안으로 들어가길 바란다”
この「教会」は、彼ものたちの共同体であるとともに、此のものたちの共同体を作るものでもあったということだ。ただ、彼が感じた良心こそ、自分を外在化する疚しい良心そのものなのだ。自己憐憫に陥ることは、自分を守る最後の術である。
しかし、この「良心」は共同体の外側であればあるほど、繋がりを欠いていて、分断的だ。登場人物中、アノ共同体に「内化」できなかった者たちが、疚しさがない「良心」を持つものだと見えてしまう。というのも、ソノ共同体を「外在的に」しか受け入れることができなかったからだ。澤田夫婦、咲江や倉蔵がそれにあたる。村長はまさにその境界線に位置している者の姿だ。
しかし、そうだろうか。これは共同体の「外側」に安心すべく良心が存在していることを意味してい他のだろうか。もし、そのような解釈が成り立つとすれば、それは陳腐な良心劇としかこの映画は評価されないだろう。
あの澤田の姿は、良心的であろうとすることを望む私たちの疚しさそのものを見事に映し出してはいないのか。
この映画は、まさにこうして、内側と外側という人間関係の境界線がいとも簡単に崩れやすく脆いものであるのか、そしてその際の徹底して良心的な自己弁護を図ろうとする人間の存在そのものを冷徹に描き出していると言えるだろう。
誰が悪いとは言えない
関東大震災中に劇中で描かれていたような事件があったことを知らなかった。
悲惨な結末を迎えたが、誰が悪いとは言えないと感じた。
大切なことは、自分で考え、情報を精査する力だと思った。
それはいつの時代も変わらない。
だが、時代的に自分から得られる情報には限界があり、デマを流され、戦時中の思想統制が行われ、さらに震災が起きたという混乱の最中であれば集団ヒステリーは大いに起こり得る。
ましてやそれが村という閉鎖的な空間で起こり、村に住む人々は今よりも選択の自由がない。
村長の言葉でもあったように、当時はその地で生まれ育ち、一生を終えるという考えが根強かった。
だからこそ、村の集団の多数派に抗うことは難しい。もし抗えば村の中での自分の立ち位置も危うくなるかもしれない。
村長も終盤までは自分の「意思や考え」を貫き通す姿勢を持っていたが、最後には多数派に抗えなかった。
これがたった100年前のこととは信じ難い。
唯一の希望は静子の存在であろうか。彼女の言動には賛否あると思うが、彼女の自由な生き方や発想は村という凝り固まった場所の解放であるかのように感じた。
主役いなくても成立するのでは・・・
暴走しない自信はない
いつもの映画館①で
月曜日に月を観たばかりだ
最近のハイペースでスタンプが6個たまり
本作鑑賞はロハ
今まではカードにスタンプを捺してもらうという
アナログスタイルで気に入っていたのだが
これからは年会費を払って
鑑賞ポイントはデジタル管理になるようだ
で映画は満点だ
起承転結の骨組がしっかりした
極めて出来のよいエンターテインメントだ
喜怒哀楽 幸福 性愛 慈愛 嫉妬 侮蔑 差別 憐憫
人生の要素が全て描かれている
過去の事件を題材にしつつ
現代社会に対して痛烈なメッセージをぶつけている
東出とかピエールとか訳あり役者陣の起用が嬉しい
あと水道橋博士も
反ポリコレの気骨というか慈愛すら感じる
出演陣は誰かに寄り掛からずに
自分の足でしっかり立てる人たちばかりだ
柄本明の息子の嫁を演じた女優の色気にはやられた
いったい誰なんだあれは
女性記者は東京新聞の望月記者がモデルではないか
コムアイとか田中麗奈 女性の強さというかしたたかさ
それに比べて男の愚かなこと
自分が生まれた村にも似たような過去があったのではと錯覚
田中麗奈が村を歩くところ
オラが初めて妻を連れ帰ったときを想起
オラは井浦新的な立ち位置なのだが
一方であんな騒動に直面してしまったら暴走しない自信はない
オラが感じたこの映画のキーワードやキーアイテム
整理できないので羅列
・差別的な感情
・排除の論理
・かつての農村の風俗
・白磁の指輪と豆腐
・扇子
・被差別部落
・お上からの通達
・流言飛語
・それぞれの名前
・水平社の決起文
これから人口減少に向かう日本
外国人を受け入れない覚悟はない きっと長いものには巻かれる
留学生 技能実習生 特定技能といった在留資格の外国人が増える
そんな世の中でこういう忌まわしい過去を思い出すのは重要だ
(ここから映画と無関係)
終了して昼の2時 雨の予報だったが何とか天気は持ちこたえて
県庁前のベンチで缶ビール2本とポテチコンソメ
アルコール3.5%を試したら確かにいつもよりダメージ小
駅前のはなまるうどんでカレーライスとコロッケ
だったら松屋でもよかったかなと
家に帰ったのが夕方5時 直後に雨が降り出した
今日もいい休みだった
「あなたはいつもみているだけなの?」
137分、監督は森達也、めんどくさがってたけどしぶしぶ観に行きました。やだー、おもしろいじゃない。長さは感じませんでした。思想を演説してるような映画を想像してたんだけど、違った。ちゃんと映画だ!
何かのインタビューで森監督はエロ要素を入れたくなかったけど強く言えず後悔しているというようなことを言っていた。なに言ってるんだ、エロがなかったら出来事であって、映画にはならないじゃないか。
村人たちに交錯する、情念の発露の結果が惨劇に結びついているのだと思う。そこを丁寧に書いていたのがよかった。それぞれエピソードとして面白かったし。義父に胸押しつけるのは笑った。
女性にいろいろ託しすぎな気はするものの、みんな個性があり、各々の思いがあり、複雑さを想像させるのがとても良かった。田舎=女性=他者って感じ。
善良な人たちが群衆心理で酷いことを…という触れ込みだが、「善良な村人」など一人もいない。ずるかったり、弱かったりする人たちがいる。
人権派の村長が惨劇の目の前でなにもできなかったり、「上がそうしろと言ったからだ」と自らの罪を引き受けない姿こそが本質だと思った。
守ろうと声を上げた人たちが救いだし、きちんとやるべきこと(=声を上げること、みてるだけでいないこと)も提示しているのが誠実だと思った。たとえ無力だったとしても。ちゃんと応えてくれた人もいたし。
有名な俳優たくさん出てるし、もっとキャッチーな宣伝もありだったのでは。左翼映画だとばかり思ってたよ。
それにしてもみんな肌つやがよい。村人に見えるまで時間がかかった。1923年は祖父が3歳。祖父母を思うと、当時の人たちは「近代的自我」みたいなのはあまりなかったんじゃないかな。はっきり意見をいう女性たちにやや違和感はあった。仕方ないけど。新聞記者に夢見すぎかな。サラリーマンだよ。部長に意見なんてしない。
良かったシーン
馬買ってきなっていうたくましさ
土手で妻の不貞をみている男と目が合うところ
新聞記者と社会主義者はなんか浮いてた
水道橋博士よかった。ああいう役はやっぱり背の低い男でなくてはいけない。デカいとああはならないんだな
貧すれば鈍する
燃えあがる女たちの情念
森達也監督がこの事件を偶然知ったのは2000年とのこと。わたしが全然知らなかったのは当たり前。香川(讃岐)から全国各地に行商して廻る一団は「穢多(被差別部落出身者)とわかったら、薬を買って貰えなくなる」という瑛太のセリフ。これは映画の設定に過ぎないと思っていたら事実そのもので、犠牲者の遺族や生き残った証人は表沙汰になるのを嫌ったため、長年埋もれていた事件だと後で知った。村の自警団の中心となる在郷軍人たちは実刑判決となるが、恩赦で刑期半ばの1年ほどで釈放されたのも事実。この映画であきらかにフィクションの登場人物は半島で教師をしていたデモクラシー思想の澤田(井浦新)とその妻、静子(田中麗奈)と女性新聞記者役の木竜麻生。関東大震災の混乱のなか甘粕大尉に殺された大杉栄と伊藤野枝の事件はこの事件の10日後だが、水道橋博士が演じる鬼気迫る病的キャラと濃いえんじ色の軍服に甘粕大尉を想起。在郷軍人会なんてアメリカではポピュラーだが日本にはないと思っていた。循環式浴槽で増殖するレジオネラ菌による肺炎の別名である在郷軍人病は初めて発見されたきっかけはアメリカの退役軍人の集会で集団発生しだことから付けられた病名。水道橋博士のこの演技が決まらないとこの映画のバックボーンが決まらないので、よくガンバった。
そして、行商の親方の頭を斧で叩き割り、虐殺事件の口火を切った若い女役。MIOKOが韓国が世界各地に設置している従軍慰安婦の少女像にソックリだったのにはドキリとした。
この監督、只者ではない。
この映画のレイティングはPG12だが、それ以上にエロく感じた。田中麗奈が情動のままに船頭(東出昌大)に迫り、舟の上で自らズロースを脱ぎ捨てる。それを岸から見ている夫。白磁の結婚指輪を豆腐に忍ばせて置くコムアイ。シベリアに抑留され白木の箱になって帰って来た夫の遺骨を抱えた女は船頭ととっくに出来ていて、寂しかったからどうしょうもなかったときっぱり言い放つ。夫が出征している間に義父の子供を身籠った女(向里祐香)も積極的。乳房を露にして義父(柄本明)の亡骸を抱き寄せた。これらの女たちの情念に私は伊藤野枝のそれの激しさを見たような気がした。
松浦祐也も目立たないが実に達者である。
人気俳優も皆達者だったけど、水道橋博士と松浦祐也がいい仕事。
アメ売りの娘と行商団の交流もあざとい演出。木竜麻生が彼女の手を取り、自警団をやり過ごそうとする場面での撲殺シーンはエモ過ぎた。アメを買ってくれた一行に丁寧に御辞儀していた娘の清らかで素直な様は白眉だった。
行商に出発する少年にお守りを渡す橋の上の少女。御守りの中身は単なる御守りではなかったのも実に憎い。
本所での火災旋風では何万もの命が奪われた。火災で生じた竜巻に吸い込まれて飛ばされる人間を見た人の証言も物凄くショックだったが、この映画の旋風もすさまじいものだった。
芸能界は在日朝鮮人がたくさんいるのよと当事者ご本人の口から聞いたことがある。この映画に出演している俳優の中で公表している人はいないと思うが、演じている俳優が互いに意識することはないのだろうか?そんなことも考えながら観た。最近じゃ政界もそうかもしれません。つい、疑心暗鬼になってしまいます。
千葉日日新聞の女性記者役の木竜麻生(新潟新発田市出身の美人)は生粋の日本人だと思うが、彼女の甘ったるい感じはなんだかこの映画の緊張感を少しユルくしてしまったような気がした。上司役のピエール瀧との対比はよかったけど、私は大好きな黒木華がよかったなぁと思ってしまった。
映画の感想は人それぞれで、そんなことを思いながら観ていた映画ファンもいだということで🙏
心に留めるべき事件なのでしょうが…
歴史的事実が題材とはいえ、旧「八つ墓村」みたいだったらどうしようと怯えながら観に行きました。同時にどんなにおぞましい内容でも目を背けずに見るぞ!見て考えるぞ!と覚悟を決めて観に行きました。
そのせいか、なんか、思ったよりもソフトというか、観客のショックを和らげようとする制作側の配慮がかなり感じられて、映画の印象が薄くなったように思えました。
あの女性記者は、安全圏で視聴する現代の観客の共感(と正義感の満足?)を得るために登場させたのか?村長が群集を必死で止めようとしていたのは、福田村の子孫の方々への配慮なのか?等いろいろ考えてしまいました。
現実はもっと無表情で淡々としていたのかな。日常と非日常は連続していて何の前触れもBGMもなく、いきなり血を見るほどエスカレートしたのかな。
不安や恐怖によるストレスが高まって集団ヒステリーから暴力事件に発展することは、今でも起こりうることですし、日頃の差別や、差別の自覚・うしろめたさがあるゆえの「仕返しされるかも」妄想が恐怖を拡大することもあるでしょう。でも、警察の謀略というのはひどすぎます。
映画をきっかけに体験したことのない状況について思いを馳せ、自分ならどうするだろう、現在アタマでこれが正しいと思っていることを、そんな極限状況で実行する勇気があるだろうかと考えこまずにはいられません。
それだけ大切なことを描いてくれた作品でした。
…もうちょっと登場人物がシンプルでもよかったなぁというのが残念でした。
全377件中、81~100件目を表示