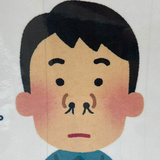福田村事件のレビュー・感想・評価
全377件中、181~200件目を表示
心の握り拳をギュッと握りました
前回満席で観れずに帰ってようやく観れた。予想してたのより全然面白かった。脚本がしっかりしていた。事件に至る人々が村へ吸い寄せられていってやってくる9月1日という字幕と共に転がり始めるクラッシックなドラマの作りで、これで予算がもっとあって演出がもっと余裕あればもっと映画的なものができたのかもしれないけど、これはこれで、やはりそのメッセージ的なものの強さがあってまったく飽きずに心の握り拳をギュッとしながら観ていた。
朝鮮アメのお返しで涙がこぼれるが、ああ、これはきっと何かの布石になるのだろあと思うと予想以上のバッドな結末へと向かう。ソルジャーブルー、シンドラーのリスト、虐殺トラウマ映画史のいくつか、今村昌平的な幻影もしっかりあるが、決してそれは映画的に昇華されてはいない。いないけれど、やはり描かれている中身が強い。水道橋博士とコムアイはキャストも知らずに観に行ってたので一瞬誰かわからなかったが驚くほどよかった。俳優陣はみんなよかったな。東出はよくこの役を引き受けたな、と。
結果的にはこれはとにかく若い人たちは学校でみんなで見るべき映画だと思った。ハロウィンや阪神タイガースで大盛り上がりしてる連中をエキストラに配置すればとてもリアリティが出る映画が出来そうな今日この頃。
やっと観る勇気が出た。そして、期待を幾重にも超えた作品だった。
それは、監督森達也が何年も熟成した自身初の劇映画作品であり、
脚本家:佐伯俊道、井上淳一、荒井晴彦の三名の智慧を借りたからだ。
作品内容は、期待を遥かに超える邦画として記念碑的な作品であることは間違いない。
幾重にも展開される人物達が持つ社会性が、
関東大震災を契機に隠蔽された福田村事件と展開されて行く。
こんなにも広範囲でかつ日本的な社会問題を集約した作品があっただろうか?
スタッフに役者も時代背景どんどんと溶け込んで一つの危機的な爆発的なエナジーとなり、
コングが撃ち落とされる。
見事な展開だった。
まるでスリラー作品を観ているようで危機感に身構えてしまう。
日本人をよく知りたい人は、
是非、観ておいて為になる作品と推薦します。
( ^ω^ )
関東大震災直後の混乱の中で実際に起こった虐殺事件・福田村事件を題材にメガホンを取ったドラマ。
1923年、澤田智一は教師をしていた日本統治下の京城(現・ソウル)を離れ、
妻の静子とともに故郷の千葉県福田村に帰ってくる。
澤田は日本軍が朝鮮で犯した虐殺事件の目撃者であったが、静子にもその事実を隠していた。
その年の9月1日、関東地方を大地震が襲う。
多くの人びとが大混乱となり流言飛語が飛び交う。
9月6日、香川から関東へやってきた沼部新助率いる行商団15名は、
次の地に向かうために利根川の渡し場に向かう。
沼部と渡し守の小さな口論に端を発した行き違いにより、
興奮した村民の集団心理に火がつき、後に歴史に葬られる大虐殺が起こってしまう。
澤田夫妻役を井浦新、田中麗奈が演じるほか、
永山瑛太、東出昌大、柄本明らが顔をそろえる。
集団心理だけどもっと歴史を見よう
「集団心理」だけど、
その一言だけで片付けるとちょっち悲しい。
「集団心理が暴走」とか「集団心理が怖い」とか、お馴染みの集団心理だから説明がつく、納得できる、仕方がない、と思ってしまうからだ。思考がその結論まで辿り着いたら即止まったみたいに。
日本人は確かに集団心理が強い、この映画も「群れること」「個人の思考」を観る人に気づかせた。(そして最近の処理水問題で日本がとりわけ大きな集団に見える)けど関東大震災後のこの虐殺は集団心理だけではないと思う。
よく考えると集団心理の定義は狭いような広いような...
この映画では村人に限った話だった。けど国家戦争も単純に二つの「集団」がぶつかっている、とみていい。(もちろん中に独立思考を持ってる個体もあるが、衝突がある時点でその人たちが作用しないようなモノ。)
いずれにせよ、集団心理で括ると、もっと広い視野でしか見えない何かを、もっとよく見ないと気付かない細かい何かを見逃すのではないかと思った。
一例として、戦時中に作られ、集団心理の作用に加勢したプロパガンダ映画はまた国家という「集団」によるもの、こんな一概した結論に何の意味があるだろう。
政治政権はどうだろう。
幸いにこの映画は当時の社会的背景への描写が上手く、女記者と新聞社、飴を売る朝鮮人の女の子などなどを通して、「時代」を感じさせるシーンを続々と見せてくれた。そのシーンたちの手助けこそが、もっと長い歴史を振り返る機会・視点を与えてくれていると思う。
政治、国家主義とか、イデオロギーとか...もうちょっとシンプルな言葉だと、倫理、人性、差別、信仰、戦争...色々あるのでは。
これらの側面からもう一度、集団から離れ、日本人としてではなく、人間として日本は一体どんな国だったのか、どんな国になっていこうとしているのか、自分は何を信じるべきだろうか、を考えることが大事だと思った。
バラエティ番組、娯楽映画ばかり盛んでいる日本では、このような渋く真実だけを伝えようとする映画、内省をしようと呼びかける映画はとてもありがたい。
いろんな面に広がる思考が、100年後の今を生きる人間の行動につながっていると信じたい。
考え続けよう。
今日は思い切りへこみたいなあ
朝鮮には良い人もいれば悪い人もいる。日本人も同じです。
星判定不能、何故なら停電で途中退場…
それが何か問題ですか?
欧米に踊らされて中国の土地を自国の領土にしようとした時「虐げられ無知で無能で貧乏な朝鮮人を中国から救う」というのが日本の大義名分だった。だから今も続く朝鮮の人への差別や蔑視は教育とメディアの犯した大罪。この頃から壮大なデマは始まっていたんですよね。
出自による差別も明治政府が創った嘘の歴史とそれを教えた教育、今も続く天皇崇拝、敬語乱発のメディアの罪
相手より上から物を言いたくて、相手を黙らせたい時、差別や蔑視は多用される。
「お前センジンか?アカか?兵隊逃れが!マオトコが言うな!エタの薬は何が入ってるか分からんぞ!女のくせに!非国民が!天皇陛下万歳と言ってみろ!」
SNSでも人を自死に追いやる言葉やデマはあるけれど、一旦軍事体制になってしまえば差別や蔑視に抗って自分が正しいと思うことを貫くには物理的な命の危険を覚悟しなければならない。
「それでも地球は回っている」と言って死刑になった人々に似ている。
映画の中で一番印象深いのは
「朝鮮人なら殺してもええんか?」
という言葉
戦前が既に始まってるとは言われるが、まだまだ命の保障があるうちに差別や蔑視と闘う言葉を持たなければならない。
「いいえ私は共産党員ではありませんがそれが何か問題ですか?」
「いいえ私は朝鮮人ではありませんがそれが何か問題ですか?」
「はい私は女ですがそれが何か問題ですか?」
「ぞうさんぞうさん、お鼻が長いのね?」
「そうよ、母さんも長いのよ。それが何か問題ですか?」
過去の失敗をかみしめることは未来にとって不可欠
2023/9/6に鑑賞した。
見終わって気づいたけど、福田村事件が起きたのは1923/9/6で、ちょうど百年前のことだった。
百年は、遠い昔のようでそうでもない。
1923年は大正12年で、私の父方の祖父母は大正6年あたりに生まれているから、彼らはもう生きていた時代なんだな。
東出昌大と永山瑛太が小競り合いを始めたあたりからの、凄惨で愚かな描写には強いショックを受けた。
加害者は無知で偏見があり、毎日必死で生きているどこにでもいる人たちだった。
私も、不安定な状況に追い込まれれば、あのような凶行を起こしうると思った。
あるいは、澤田(井浦新)のように何もできずに、誰かが誰かを殺すことを傍観してしまうと思った。
永山瑛太達の行商団は、被差別部落出身者だったらしい。パブではあえて伏せられていたようにも思った。
彼らも出自によって差別されることもある。差別されるものが、より”下”を設けて憎悪をぶつける。
愚かしいことだけど、今の世でもよく見る光景で、瑛太はにがにがしく思ってるようだった。
らい(ハンセン病)の患者に適当な口上で薬を売り、その罪悪感を別のらい患者への小さな施しですこしだけ慰める。
仲間が発する朝鮮人への憎悪をそらすために、朝鮮飴を売る女の子からたくさん飴を買って、女の子から扇子をもらう。この伏線すごいなと思った。
柄本明とその息子夫婦のくだりはなくても本編に支障はないけど、田舎の閉塞感、親子の微妙な関係が生々しく、印象に残った。
狭い村で、娯楽も社交も思想もぜーんぶ共有するしかない。村の空気にそぐわないことはできない。
あの感じ、地元を思い出す。
東出昌大と浮気する豆腐屋の嫁は、コムアイだったらしい。初めましてだった。
コムアイが豆腐に指輪を仕込んで井浦新・田中麗奈夫妻に波紋を投げかけたところで、東出・田中の船上のまぐわいを恨んで何かやばいことしないか心配してしまったけど、そっちは杞憂でよかった。
水道橋博士がすごいいやな役をしていて、学がある村長への劣等感、そんな中で在郷軍人会の会長?という、肩書ができて少しは劣等感をかき消せると躍起になってる感じがすごーく出てて、よかった。
新聞社でのやり取りも緊張感があって、脚本もすごくいいと思うし、役者も豪華でよかった。
永山瑛太を殺したのは、乳飲み子を背負っている出稼ぎ夫が朝鮮人に殺されたと信じてしまった若い女だった。
彼女を断罪すればいいとは思えない。
世の中の悪事は大体(共産)主義者、不逞鮮人がやってるとの言説が流布し、実際に共産主義者と朝鮮人をいじめ倒しているから恨まれてるって分かってるし、真偽を確かめる術がない。
その状況で、反抗できるわけないよね。
でも愚かしい差別や、差別を燃料にした虐殺は起きてほしくない。その防止には何ができる?
教育?大事だけど万能じゃない。格差是正?富める者が既得権益を手放すとは思えない。
人間の歴史は、美しい面と福田村事件のような惨たらしい面があり、特効薬はない。
ので、現時点で道半ばなのは致し方ないのだけど…
鑑賞後にニュース動画を見たら、松野官房長官が、朝鮮人虐殺は記録がなくて確認不能と言っていて、びっくりした。そういえば小池都知事は、虐殺被害者追悼集会への追悼文を出さないし、南京大虐殺もやっていないって考えるひともいるし…何を見るとそんな見解になるのか理解できない。そんな意見の人に政治を担われたくないと思った。
映画『福田村事件』を観て、「鮮人」という蔑称を初めて知った。まだまだ知らないことが多いんだなと思った。
日本人の弱さを噛み締める
アメリカの人種問題を扱った舞台作品を見たので
日本の差別問題もちゃんと見ておこうと思い鑑賞。
逆差別の意識を持った人たちが作ったのではと勘繰っていたところはあるが、誰かを一方的に責めるのではなくきちんと集団心理の恐ろしさを描いたものだった。
なぜこのような事件が葬り去られていたのか。たまたま被害者に日本人が混ざっていたからこれだって後に明るみに出ただけで、迫害は日常的に横行してたのだと思う。部落民のことすら私たちはほとんど知らない。
多数派に流されやすく、反対意見を述べることもできず、みんながやってるならうちもやる、今も昔も日本人のありのままの姿。戦争が人をさらに狂わせたとは思うものの、今の世代だって本質は何も変わらない。今SNSで起きてる言葉の暴力がいつか同じように恥ずかしいと皆が当たり前に思う日は来るんだろうか?
終わって気づいた水道橋博士、演じる自己陶酔感と、井浦新の臆病心、そして豊原功輔の自己弁護、どれもとても人間くさくてリアルだった。
ここのところ現実逃避のように見たくもない流行り映画をたくさん見てたけど、もっと色々考えることに繋がるものこそ映画として見る意味があるのではと思えた。まあ結局現実逃避の軽い映画も必要なんだけど。
--
鑑賞後久々夜の渋谷を通って帰ったが、ただ酔っ払って騒ぎたい若者の町と思ってたのにそれ以上に奥は荒んでた。街は汚いし警察があちこちで尋問してるし、それでも堂々とラリってる人たちが暴れてる国よりはマシなんだと思うが日本も大概だなと思うにはピッタリすぎる締めくくりだった。
--
しかし朝日新聞のクラファンで資金集めしたと聞くとどうしても捏造問題があたまをよぎりモヤモヤする。。
私もあなたも誰もが持つ人間の根源的怖さが描けたと思う。
命の使い方とタイミングは、自分で選ぶ。
100年前の、逃げ場も娯楽もない閉塞的な村社会の息苦しさは、想像以上だった。
お互いに見張り合うようなコミュニティの中では、プライバシーの概念もない。
事の是非を自分以外に委ね、ただロボットのように思考停止で生きる世界。
心底怖いなと感じた。
20歳の頃から、ひとりで海外に行く前に、武道の先生から護身術の手ほどきを受ける習慣がある。
先生は、どんな屈強な男性でも鍛えられないいくつかの急所を、実践を交えて教えてくれる。
幸い、今までその技を海外でも国内でも使ったことはないけれど、見えない武器を持っていると随分心強い。
そして、危険に対して敏感になる。
この映画を観て、護身術の先生の言葉を思い返した。
「私が教える技は、あなたの心、身体、命が絶体絶命の時だけに使いなさい。
但し、相手が一人で、武器を持っていない時だけ。
武器を持っていたり、複数人の時は、中途半端な抵抗はかえって最悪の事態を招く。
その時は、命を守ることだけ考えなさい。」
自分の信念を貫くこと。
矜持を守ること。
それは、人間としてとても大切なことだ。
けれど、そこにこだわるあまり、判断ミスをしてはいけない。
私は、命を守ることは、何より大切だと思う。
自分に使命があると知っているなら、なおさら。
大学生の息子たちは、この映画を観たらどう感じるだろう。
きっと、私よりももっと遠い世界の話だと思うのは間違いない(^-^;
朝鮮人なら殺してもええんか!瑛太さんの魂の叫び
まさに心の叫び、魂の叫びだ。
この魂の叫びが殺戮の引き金になった。
何とも皮肉な何とも残酷な何とも救いようのない展開。
思わず監督を恨んだ。
加害と被害
犠牲になってしまう、永山瑛太演じる香川の行商人の言葉
この映画のテーゼでもあろうかと思う
朝鮮人なら、殺してもええんか
多くのレビューで
評価されるのも、むべなるかなというところか。
長らく、ドキュメンタリーで傑作を撮ってきた森達也監督。初の劇映画というところで、一抹の不安がないわけではなかったが杞憂に終わった。
この題材をよく映像化された。製作陣スタッフ、強力なキャスト陣に敬意を表したい
企画やシナリオに、荒井晴彦氏が名を連ねているのも大きい。
100年もの間、闇に葬られていた歴史事実
映画の下敷きになった原作も読んだが、埋もれていた史実を丹念に取材した辻野弥生氏にも感服。
いまだ、関東大震災時の流言蜚語による虐殺を正視しない、この国の為政者たち。
震災時の虐殺はなかった、とする説などが流布する現代日本
俗な言葉になるが加害にも向き合わず、日本黒歴史ともいえる事実に目をそむけつづけるならば、歴史は繰り返されるだろう。違う形で。との言葉を残したのはどの歴史家であったか。
自分に問いかける。あの場、時代に生きていたなら自分はどう行動しただろう。殺す側?殺される側?傍観している?
煽っている?…
この作品は重層的かつ多層的に作られている。
つまり、視座がひとつではないというところ。
差別が構造的かつ複雑にあり、朝鮮人と間違われ殺害された日本人。彼らは被差別部落出身者たち。その彼らも大陸の人々に対する差別、ハンセン氏病の人々に対する差別心があり、それらをも描いている。
多くの方が見られることをお勧めする
真っ当なメッセージ
戦争中の不穏な空気感や、村社会の閉塞感などが淡々と丁寧に描かれ、事件が起こる流れが分かりやすくなっていたと思います。
人種差別だけでなく様々な差別意識についても触れられ、差別感情を煽る新聞等の存在も考えさせられます。
村の男女関係の描写は予想外に生々しく描かれて、抑圧された女性の立場も意識させられ、これはこれで印象的でした。
男女関係は複雑な心情を描いているように感じたためか、軍人や村長など他の人物描写はちょっと単純にも感じました。
とは言え、当時は実際にこういった雰囲気だったのかもしれませんし、これで人物たちのスタンスや事件への流れが分かりやすくなっており、差別意識の愚かさや集団心理の恐ろしさなども強くはっきりと伝わるようになっていたと思います。
行商の沼田のセリフも、至極真っ当な意見で大いに共感できます。
事件が起こったのは当時はそういう時代だったからとも言い切れず、やはり現代の日本においても重ねられる部分があり、改めてどこへ向かうのか考えるべき、という強いメッセージが伝わる作品でした。
23-110
今まで観てきた映画の中で最も濃厚でした
事実を元にしたフィクションではあるものの、人間の原罪を深く浮き彫りにした、大変示唆深い映画でした。
今まで観てきた映画の中で最も濃厚な内容でしたので、見終わったあとの余韻が深く、現実の世界への順応するのに時間がかかります。
「人間って何なのか」に関心がある方は、必見です。
全377件中、181~200件目を表示