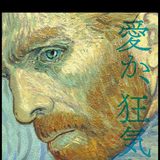美と殺戮のすべてのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
いま彼女を力強く突き動かすもの
本作はまず、世界的に名高い写真家ナン・ゴールディンの現在地を映し出す。そこには「オピオイド危機」をもたらした元凶、大富豪サックラー家に対して仲間と共に抗議の声を上げる彼女の姿が。もともとサックラー家は美術界への支援も厚く、名だたる美術館の有力なスポンサーである。だがゴールディンはその強大な影響力にいっさい怯まず、血塗られた支援金に頼る美術館に対して「目を覚ませ」と訴える。彼女が声を上げ続けるのは何故なのか。その原動力はどこから来るのか。命題への答えは半生を紐解くことで見えてくる。育った家庭環境。最愛の姉。カルチャーの只中で仲間や自身を被写体にしてシャッターを切り始めたこと。80年代、仲間が次々とドラッグ中毒やエイズで亡くなったことーーー。あらゆる記憶と経験はゴールディンの血となり肉となって生きている。その点と線が繋がっていく様に決意が垣間見える。静謐な中に揺るがぬ芯を併せ持った一作である。
主題は両方なのだろう
ナン・ゴールディンの半生を描いたドキュメンタリー
鎮痛剤オキシコンチン使用による被害者を
支援する団体P.A.I.N.を創設し、オキシコンチンを販売する製薬会社パーデュー・ファーマ社とそのオーナーである大富豪サックラー家、そしてサックラー家から多額の寄付を受けた芸術界の責任を追及していく活動が
日の目を見るのは報われた気がします。
それにしてもナン・ゴールディンの生き様自体が
凄まじく、そこにまず驚きましたし、
お姉さんのエピソードはいたたまれない気持ちに
なりました。
ドキュメンタリーでなくとも映画化たり得る人生で
凄さを感じましたね。
私にとってのナン・ゴールディンは、
再生YMOの写真集を撮った方。
そこでナン・ゴールディンの名前が頭にあったので
本作を観ようと思ったきっかけになりました。
生と死は紙一重
好きか嫌いか、で言ったら決して好きな作品ではない。でも、凄いか否かと聞かれれば間違いなく凄いという作品。
オキシ乱用撲滅のために立ち上がった活動家ナンのドキュメンタリーフィルムとしてトレイラーから受けた印象はそのままに。一方でトレイラーでは一切触れていなかった(ように思える)写真家ナンの家庭環境や実の姉に起きた悲劇。一見交わることの無さそうなその2本の筋が、映画の経過とともに少しずつ交わり始め、最後には一つになるという現象は実に見事で美しく、エロさすら感じる。
『人生』ってその人が生を受けてから死すまでの本人主役の一つの壮大な長編劇。でも、時に死して尚、自分以外の人の人生に良くも悪くも影響を及ぼすことがある。影響を受けた人生の主人公は自分が主役であるということを忘れずしっかりとコントロールする術を持たないと翻弄されてしまう……
見応えはあるけど、観ていて苦しさの強い作品。
#映画好きと繋がりたい
オピオイド麻薬の企業と戦った人々
オピオイド麻薬の被害を出した
サックラー社を告発。
全米で50万人が死亡した。
サックラー社の寄付を 受け付けない様に
世界の美術館に 要請。
個人の刑事告発を見送る条件で 和解金。
米国の民衆のパワーは 強く、正しい事をする人々がいる。
コールジェーンでは 当時 違法の中絶を 無許可、
無免許 違法下でした女性がいた。
自分が正しいと思ったから。
途中でギブアップ
稼いだもの勝ちの世の中
薬は使い方を誤ると毒にもなる。オキシコンチンは日本でも販売されている薬剤で、適切に使用すれば有用な薬だ。オキシコンチン自体が悪いのではなく、その不適切な使用が問題である。製薬会社が処方した医師にリベートを提供したり、依存性リスクを過少にプロモーションしたりすることは言語道断である。またそれに引っ掛かって処方医が適切に使用しなかったのも、プロフェッショナル意識がなく同罪だと思う。規制をしても、それをかいくぐろうとする者が出てくる。結局はモラルの問題だ。金を稼いだ者ほど、偉いとみなされ名声も金次第という世の中を作っているのは我々一人一人だ。どうやって稼いだのかも我々一人一人が厳しく評価すべきだ。自分自身に対しても。
抗議活動というアート
鎮痛剤として世界中の人々に投与された〈オキシコンチン〉は強オピオイド(鎮痛・陶酔作用のある化合物)で非常に高い中毒性があり、薬物乱用者が続出すると共に、死者は50万人を超えてしまった。この映画はそんな凶悪な薬物を使ってしまった写真家・ナン・ゴールディンが自分と同じように苦しんだ人々と共にサックラー家を訴訟し、責任を追求するドキュメンタリー。
かと思っていたんだけど、6割以上がナン・ゴールディンのこれまでと自信がシャッターを切った写真の話とスライドショーであり、オキシコンチンに対する訴訟の様子は僅か。この映画だけじゃその問題のモヤモヤは解決しないし、背景をわかっていないと理解も難しい。苦悩と再起の様子が描かれている作品だと想像していたから、コレジャナイ感が凄かった。これなら最初からそう宣伝してくれたらいいのに、、、予告が酷いや。
ひたすら説明。ずっと同じ構図。
彼女の魅力を伝える映画としても微妙な出来栄え。原因は観客の心を掴む気のない編集にあると思う。こんなかったるい雰囲気で淡々と話されても、正直興味を持てない。ゴールディンが撮る写真は斬新で、今なお世界中の美術館から重宝される理由が容易に分かる。「写真の持つ意味はひとつじゃない。」彼女が何故カメラを向け続けるのか、何故誰も撮らないものを撮ろうとするのか、そういった本質的な部分はスライドショーから読み取れて、考えさせられるものがあった。
しかしながら、それが抗議活動と関連するとは到底思えず、なんなら訴訟が二の次になっているため、監督はゴールディンのドキュメンタリーを作りたかっただけなんだろうなと思ってしまった。少なくとも、〈殺戮の天使のすべて〉ではないぞ、これは。
20世紀は
騒動の発端である薬害問題関連のニュースを一通り知ってから臨んだ方がベター
2024.4.4 字幕 MOVIX京都
2022年のアメリカ映画(121分、R15+)
実在の写真家ナン・ゴールディンの半生を描いたドキュメンタリー映画
監督はローラ・ポイトレス
原題は『All the Beauty and the Bloodshed』
物語の舞台は、メトロポリタン美術館、ハーバート美術館、グッゲンハイム美術館を皮切りにして、フランスのルーヴル美術館、ロンドンのテート・ブリテン(展示会)へと続いていく
全6章の構成になっていて、「Merciless Logic(無慈悲な必然性)」「Coin of the Realm(生きる術)」「The Ballad(バラード)」「Against Our Vanishing(消えゆく命)」「Escape Hatch(逃げ道)」「Sisters(彼女たち)」という流れになっていた
ナン・ゴードウィンはLGBTQ+を被写体にしたり、サブカルチっくなアンダーグランドの世界を写す写真家で、映画では彼女の作品をスライドショーにまとめたものが映し出されていく
また、ナンの被写体になった女優や監督などの作品が登場し、彼女がどんな人物であるかを紐解いていく
そして、ナン自身が立ち上げた「P.A.I.N.」の活動内容が並行して描かれていた
彼女自身が手術後に使用したオピオイド製剤の依存症に苦しめられた経験があり、その販売元のパデュー・ファーマ社に対する怒りを伝播させていく
パデュー・ファーマ社はサックラー家が牛耳る会社で、「使用量によって医師にキックバックする」という経営手段と、「依存性を隠して宣伝する」という広報活動は悪質性が高かった
裁判などの結果も無視し薬の販売を続けていて、それに対して薬物依存の被害者の会が行動を起こしている
その一つがナンが行なっている抗議活動となっていた
映画は、オピオイド問題を描いているわけではなく、その活動とナン自身がどのような人物かを紐解く内容となっている
彼女に興味があれば良いが、オピオイド危機の詳細を知りたいという人にとっては、そのさわりぐらいしかわからないと思う
映画には多くの関係者が登場し、抗議活動の内容、団体の横のつながりなどが描かれていく
彼女たちの目的が「オピオイドで儲けた金を寄付として受け取るのはやめろ」というもので、ナンは自分の作品が収蔵されている美術館などでそれを行なっていく
この方法に賛否はあるだろうが、問題の注目を集めるという点においては有効で、実際に寄付の拒否などが起こっていた
ナンが行動を開始したのが、オピオイド系の薬品が自動販売機で売られそうになって、それが拒否られたというニュースを見たのがきっかけとなっていた
依存性の高い鎮痛薬を処方箋なしで自販機で売るというのは大概凄いことだが、本当に儲け優先なんだと思わされる
映画では、このあたりの騒動とか薬害の規模に関してのイメージが掴みにくのが難点だが、アメリカではずっと報道され続けているものなので、「知っていることが前提」で映画は作られている
日本でも最近同じような問題が起こっているし、コロナ禍のワクチン騒動もまだ始まったばかりという感じになっているので、いつ何時同じような騒動に巻き込まれるかはわからない
その時に真摯に向き合う企業がほとんどないというのは過去の歴史が証明しているので、その時は「自分ごとだ」と思わずに、助けを求めたり、情報提供も兼ねて協力しあう必要があるのではないだろうか
いずれにせよ、問題を知りつつ、ナン・ゴールディンがどのような写真を撮っているかを知ってる前提で鑑賞した方が良いと思う
見たこともない人がひたすら喋る系のドキュメンタリーなので、興味がないと船を漕ぐのは必至かもしれない
個人的にはあまりピンと来るところはなかったのだが、そもそもの抗議活動自体があまり好ましくないと思うので、向ける矛先が違うように思う
寄付を受け取っているから同罪とまで言われるのも無茶な論理になっているので、受け取るなと強要するよりは、寄付などせずに救済に回せと直球をぶつけた方が良いのではないだろうか
それが効かないから別の方策を試みているのだろうけど、寄付を拒否した理由が「単に面倒だから」という感じになっている気がするので、目的が達成されているかは不明瞭であるように思えた
オキシコンチンと製薬会社サックラー家
美と殺戮のすべて
神戸三宮にある映画館 kino cinéma(キノシネマ)神戸国際にて鑑賞2024年4月2日(火)
「殺戮」は「さつりく」と読み多くの人を殺すという意味
全米で50万人が命を落とした「オピオイド危機」。薬害を招いた鎮痛剤「オキシコンチン」を過剰に販売促進したパーデュー社とその所有者たるサックラー家と戦う薬害抗議団体「P.A.I.N.」の活動を追うドキュメンタリー。
1953年生まれの女性写真家ナン・ゴールディンは、親しい友人やアーティストを対象、タブー視されてきたサブカルチャー、アンダーグラウンドカルチャー、エイズ、LGBTQなどを対象とした社会派として活動。
この作品では、幼少期からの人生と経歴、写真家としてのコレクションとその解説が前半、2017年に設立した薬害抗議団体“P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now)”の活動記録が後半
-------------------------
製薬会社は慈善事業のひとつとして、美術館などに膨大な金額の寄付を行っており、ニューヨーク、ロンドン、パリなどでは、「サックラー家」の展示施設が存在し宣伝になっているので、P.A.I.N.はそれを取り除くのが目的のひとつ。
-------------------------
ストーリー
ナン・ゴールディンは手術後に処方された鎮痛剤「オキシコンチン」によりオピオイド中毒になる。生還した後、
ニューヨークにあるメトロポリタン美術館の「サックラー・ウイング」エリアで、講義デモを行っているシーン。オキシコンチンの容器を投げ、水が張られた池にプカプカたくさん浮かんでいる
当初は草の根だった抗議活動はやがて実を結び、大きなうねりとなって世界中の美術館に波及。サックラー家とパーデュー社は責任を認めざるを得なくなる。
P.A.I.N.の抗議活動はルーブル美術館でも行われ、やがて多くの美術館がサックラー家の寄付を断るようになる。
--------------------------
変化と影響(パンフレットより)
デビッド・リンデと、パーティシパント社のドキュメンタリー映画製作部門の役員トリッシュ・ウオード=トートレスは、美術館やその施設が、世界に対して責任を負っているという点で一致する。「P.A.I.N.」がオビオイド危機とサックラーの慈善活動の関連性を白日の下に晒すために行った活動について知る中で。彼らはゴールディンと彼女の勇敢さに触発された。
「わたしたちは、サックラーの名を施設から排除する驚くべき活動について認識していましたが、P.A.I.N.の目標は、単にサックラー説明責任を求めるだけでなく、オビオイド危機に対するハームリダクション(薬物の使用を止めさることではなく、薬物使用によるダメージを減らすことを目的とした政策、プログラム、または実践のこと)の取り組みなど、より広範なものだとすぐに気づかされました」とウオード=トートレスは説明する。
---------------------------
サックラー家はこれまで、全米各州で何千もの民事訴訟を起こされた後に破産を申請し包括的な説明責任を回避することに成功したが、ゴールディンとP.A.I.N.の抗議活動により、アート界における彼らの地位は事実上剝奪された。今や世界中で、なにを行ったかを知っている。我々がアメリカの数十億ドル規模の企業に影響を与えることができたのは、私の誇りであり喜びです」とゴールディンは付け加える。
今日においてP.A.I.N.は、サックラー家を筆頭とした製薬会社との和解で得た資金を全米のハームリダクションと過剰摂取防止センターに活用するよう主張し続けている。今ところ、VOCAL-NYやHowsing Worksなど、影響を受けたコミュニティと緊密に連携する草の根団体を支援するために募金活動を行っているが、彼らの主な目的は薬物の安全な消費場所を合法化することである。「この危機を脱する唯一の方法は、エビデンスに基づいたハームリダクションに資金を投じ、血を流さずに麻薬戦争と戦う事です。この映画に対する私たちの願いは、依存症の悪いイメージをすこしでも払拭することなんです」とミーガンカプラーは付け加える。
監督・制作 ローラ・ポイトラス
作品の中では、とても美しい音楽が流れていました。
映画の説明からして、 もちろんメインとしてはオキシコンチンについて...
映画の説明からして、
もちろんメインとしてはオキシコンチンについての
ドキュメントだと思って見たのに、
ナンさんの人生についての映画だった
最初からそのつもりで見たらもっと違う感想を持てた筈だけど、
(そもそも見なかったと思うけど)
低い点数にせざるをえない、ごめんなさい
紅麹どころではない
基本ストーリーは製薬会社を経営する「サックラー家」は全米で50万人以上が死亡する原因になったとされる「オピオイド鎮痛薬」を売り巨万の富を得る。そのサックラー家を追い詰めていくナン・ゴールディンと仲間たちのドキュメンタリー映画。ただ途中からナンが過ごしてきた70年代カルチャーやLGBT、偏見、エイズ問題と多岐にわたり、最終的にはナンの姉の死と家族を巡るインパクトの強い物語まで展開していく。久しぶりに骨太のドキュメンタリー映画を観ました。
個人とアートと社会的活動が・・・
毎回審査員が設定される映画祭での受賞作品となると、ハマるかハマらないかで作品の印象ががらりと違ってくる、と勝手に思いこんでいるんですが、この作品は後者の方で、そんなに長いわけでもないのにめっちゃ長く感じました。
写真家(?)を追ったドキュメンタリーということで、大部分がスチールで構成され、そこに語りやらナレーションが加わるといった大まかな流れ─言い方があれですけど、まるで絵本の読み聞かせのような感じで、かなり眠かったです。
社会的活動をするアーティスト(?)を追いつつ、そのインディビジュアルに深く切り込んでいって、自由奔放な人生そのものがアートだと言わんばかりの、なかなかダイナミックな展開のように今更ながらに思うのですが、自分には全く響いてこなかったので、アートは自由だ!としか言えません。あまりに自由すぎて、いったい何をしたいのか何を伝えたいのか、全く理解できなかったというのが正直なところ。
申し訳ないけど、ヤバイくらいにつまらなかったなぁ
抗議活動ですらアートにする
普段なら{ドキュメンタリー}の類は観ないのだが(除く、テレビ視聴)、
本作は現時点で
IMDb:7.5
Metascore:91の高評価。
加えてスポットライトがあてられる『ナン・ゴールディン』は女性の写真家で
『YMO』の写真集〔NOT YMO - YMO in NEW YORK〕も撮り、
或いは『荒木経惟』とのコラボもあり。
本来の彼女の作品は「サブカルチャー」や「アンダーグラウンド」をテーマにした
センセーショナルなものであることも背中を推す。
ところが映画は、彼女や支持者たちが「MET」を訪れ、
製薬会社を非難するデモンストレーションを繰り広げ、
ダイ・インをする場面から幕を開ける。
警備員に阻まれ、来場者の好奇の目が集まるなか、
強い意志での行動。
製薬会社を営む大富豪『サックラー』家が
自社の「オキシコンチン」による薬物中毒で
全米で五十万人以上が死亡する原因になった事実に背を向ける一方で、
一家が美術館に多額の寄付を行い、
家名を冠したコーナーを設けていることに抗議したもの。
同様の示威行動は「グッゲンハイム美術館」を始めとして、
「サックラー」が寄付をし、
その名が記されている多くの美術館で行われる。
{ドキュメンタリー}を観て気になるのは、どこまでは「素」であり
どこからが「作為」なのかの境界は鑑賞者には捉えきれぬこと、また、
制作者の主観はどうしても入るので
必ずしも中立的で客観的なものではないこと。
わけてもモノローグのシーンは
語り手が虚飾を捨て去り、
ありのままを告げているのかは疑問に感じるところ。
映画は彼女の現在の「活動」と並行し
幼少期の経験、世に出るまでの経緯を
あけすけに描く。
姉の『バーバラ』を自殺で亡くしたこと、
活動初期の被写体でもあった「LGBTQ」の知人たちをエイズで亡くしたことが
彼女の作品にも、またイマイマの活動にも大きく影響を与えたことも。
とりわけ後者については、一部のコミュニティ間での奇病との
どこか他人事の政府の無策が、結果、被害を拡大させたことが
今でも怒りとなり行動原理となる。
その中で浮かび上がって来るのは、
なんと凄まじい半生か。
両親との関係性には壁があり、
恋人からは暴力を振るわれ失明寸前に追い込まれ、
自身も薬物中毒からの離脱を経験。
とは言え、それら全てが芸術と活動のバックボーンになっているのだ。
環境活動家による気候変動への抗議として
名画にスープ等を投げつける
自分の手を接着剤で貼りつける
等が成されたことを思い出す。
それと本作での彼女等の行為を
どうしても引き比べてしまう。
アーティストが行うだけあり、
より{インスタレーション}に近いとの感想を。
自分の人生
知りもしない写真家の内面を大仰に言われてもねぇ
薬害を根拠に美術界への莫大な寄付を拝受した施設をターゲットにピケ活動を実践する。要するに汚い金を尻尾巻いて受け入れるな、一件正当に見える論理。ですが、薬害であれば真っ先に起こすべき運動相手は違うでしょ、警察であり保健に関する役所であって、百歩譲って不買運動でしょ。ご自身がアートの方だから? 開館中に集団で押しかけ、一斉に空ボトルをまき散らし、盛大にチラシを舞い上げ、真っ赤な横断幕を掲げる、一般の閲覧者たちの迷惑顧みず。最近もあったルーヴル美術館で環境活動家らが「モナ・リザ」に向かってスープを投げつけるという事件、「健康で持続可能な食べ物」の権利を主張してとか。ヒトラーに愛されたワーグナーの曲に罪はあるのか?に近い、としか言いようがありません。
そもそも彼女の事を何も知らない私達、世界的に名高い写真家ナン・ゴールディンと言われても。彼女の作品は当然に画面に登場するけれど、前世紀末のポップカルチャーの危なさを抱えた写真で、良いも悪いも見当つきません。で、冒頭から本作の縦軸としてこの活動が縦断的に挿入され、最後にはメトロポリタンに引き続き、大英やらルーブルやらもサックラー家の名を削除し、よかったよかったと成果を描く。けれど名を消して、受け入れた財産は返却したのかまるで不明。そこまで言うなら大英博物館なんてアフリカ大陸等から強奪した宝物がごっそりあると言われてますよね。
この活動の根底にあるのが彼女の生い立ちにあると述べる。些かエキセントリックにも感ぜられるけれど、彼女の両親が子を持つべき人物ではなかった、とまで言ってのけるのは傲慢にしか聞こえない。写真のみならず映像でも登場する一家はどこにでもあるフツーに問題も抱えた家族写真じゃないですか。さらにレズビアンを苦に自殺した姉の影響をあげる。その余波で里子にも出されたとか。さらに80年代から90年代のポップなシーンでのゲイカルチャー、そしてHIVポジティブによる死者への共感。写真機材の財源確保のために娼婦にすらなった過去まで言う。久しぶりに聞くジョン・ウォーターズやディヴァインの名まで引用し、ケバケバしいドラッグの世界にどっぷりと浸かる姿を映し出す。
だから何なの? 「シチズンフォー スノーデンの暴露」で第87回アカデミー長編ドキュメンタリー賞を受賞したローラ・ポイトラス監督だから本作も素晴らしい? なんて気負いでしかない。数回に渡ってスライドショーとして彼女の写真が次々と映し出されるが、写真の凄さは動画にはない切り取った一瞬の真実こそにある。こんなドキュメンタリー動画なんぞより、彼女の作品写真集を見るべきでしよ。「All the Beauty and the Bloodshed」なんて大仰なタイトル、まさに羊頭狗肉ですね。
全23件中、1~20件目を表示