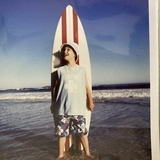ザリガニの鳴くところのレビュー・感想・評価
全444件中、221~240件目を表示
これは怖さではなく、はじめての感情。 「Carolina」の歌詞が、込み上げる気持ちに纏わる布のように絡んできて、震えた。どうしようもなく。
湿気を帯び躍るようなエネルギーを放つ植物たち。
樹木は壮大な時間をかけ空へ向かい、揺れる葉の隙間からやさしい光を届ける。
水面を揺らす風と鳥たちのざわめき、原生種の花々の香りが漂うなかで虫たちは賑わいを増す。
神々が鎮座する領域で安らかに繋がりゆく命。あるいはひっそりとそして時に残酷に朽ちる刹那。
深く重い摂理は、人間社会の後づけの概念やルールなど太刀打ちしようもない。
1950年代〜ノースカロライナ
巨人が両腕を広げたようなその湿地帯で、カイアは幼少期から家族と別れひとりで生きる。
たくましく純粋でのびのびとした娘に成長しやがて町に住む青年と恋をする。
1人目はカイアの兄の同級生で幼ななじみテイト。2人目は町の有力者の息子チェイス。
そんなある日、湿地で発見された遺体。事故か事件か。
町ではあれよあれよと噂が立ち犯人にされる〝湿地の娘〟カイア。
ついに拘束され陪審員裁判にかけられている法廷での様子と過去の流れを混ぜ込み展開していく。
なぜカイアはひとりになったか。
なぜ殺人容疑者としてそこにいるのか。
事件の謎、真実は…
サスペンス、ミステリーにとどまることはなく多様性をもって最後まで誘い続ける。
そう、語り手は犯人探しだけをさせたいのではなかった。
時代背景からも読み取れる、戦地から戻った軍人のストレス、貧富の差、人種的差別、権力がもたらす歪みなどに、人間の偏見、エゴ、集団意識がつくる無神経な排除の構造など、現代に至っても普遍的にある陰に密かにスポットをあてる。また、あたたかい記憶に与えられる力、数少なくも手を差し伸べようとする存在の尊さにも。
絶望と孤独の先に何があろうとたちむかったカイアの一生を通じて訴えかけてくるのだ。
そして何より、目を見張り息をのむような繊細で豊潤な自然界の描写が不可欠だったことを納得させるのは、生き物として知り尽くした自然界がカイアに授けたものを知ったあとだ。
叙情的な味わいーではいいつくせなく胸に刺さるのはなぜだろう。
確かめたくて翌日にもう一度観た。
そして、これこそは、いつもみたいに書きすぎないレビューを!と思ってだいぶ我慢中😅
〝湿地は光の世界…
〝…点在する本当の沼〟
そうだね、カイア。忘れないよ。
カイアのそばで見守ってくれた人々に私は敬意を込めたい。
その世界観に浸かり本能に触れるなにかを感じにぜひ観にいかれることをおすすめしたい。
稀有な映画だ。
(訂正済み)
独りで在ることを選択した少女
幾度か出てきた「淡い悲しみ」と言う言葉がとても印象的でした。幼い者を理不尽に縛りつける悲しみ、人が生きていく上で背負わなければならない悲哀。でも、カイアは悲しくとも、屈しなかった。
◉カイアの選択
カイアの父は自らを護るため、孤立して暮らす。ある意味、とても潔い。だが、家族は父に着いていけず湿地を去る。世間に出れば辛い思いもするだろうが、やはり孤独よりは他者との交わりを選んだ。
しかしカイアは、父さえ去った湿地で生きることを決めた。戦争から生還した父の人生は、ほぼ無色に近いようなものになってしまったと思えるのですが、カイアは孤立の中で、自然に溶け合う暮らしを続けて、自らの世界を構築していった。
◉湿地で輝く
カイアは生存のためジャンピンやメイベルとの間に人同士の触れ合いを経験し、やがて積極的な男と女の関わりにも踏み込んでいく。
デイジー・エドガー=ジョーンズ演じるヒロインの、消え入りそうなぐらい繊細なのに、簡単にはへこたれない、したたかな表情。そして少年のような雰囲気を強く漂わせるのに、思いがけず肉感的な肢体。名前の付けようのない不思議な宝石であり、湿地でのみ輝き続ける存在として描かれている彼女の姿に、観る者は惹かれていった訳です。
チェイス殺しの嫌疑をかけられても、カイアは身の潔白が晴れるかどうかより、とにかく湿地を離れずに済むことだけを切望する。
自分の意思に命をストンと預けられる。本当に強いなぁ!
それでいて恋心に身を委ねる時の、素直な欲望。頑なであるのに、デートにすぐに応じたり、男を家に招いたり、かなり奔放!
◉独りで在ること
人にとって、生涯で多少なりとも触れ合って、更に喜怒哀楽を共有できる相手は、ほんの一握り。それでも自分を大切にして生きていれば、誰かと出会えるし、おまけに残酷な運命にも出逢ってしまう。
やがてカイアの元に戻って来る恋人も、一度は彼女から離れていった。身勝手な恋人にも散々、振り回される。それでもジャンピン夫妻はカイアの生き様に優しく寄り添ってくれたし、弁護士トム・ミルトンもカイアへの偏見に怯むことなく、彼女に振りかかった疑惑を必死で解いてくれた。老いてはいたけれど、実に男前でした。
カイアの生き方が表していたものは、「独りっきりで居ること」ではなくて、「在り方として独りで生きること」だったと、私は思いました。湿地を隔てた所でカイアを思う隣人は一握りではあっても居て、そこに人同士の繋がりはあったのですからね。
カイアは自然科学の知識体系を独力で身につけた。少し超人過ぎやしないかとビックリしましたが、鳥・昆虫・魚・貝や植物の細密画に没頭する。それは「独りで在ること」を確かめて、かつ満たされるための作業も兼ねていたのだと思いました。
◉湿地は消えない
この物語の一方の骨格であった、カイアへの疑惑の謎解き。物見台周辺に足跡が無かったこと、板が1枚外れていたこと、本の打ち合わせ前後のアリバイ、そして赤い毛糸。それらの疑惑がほぐれていった道筋は、ストーリーに描かれた部分に限定すれば、論理と言うより老弁護士の熱量の結果と感じました。
ただ人の足跡は湿地の満潮で消えた……と言うのはちょっとワクワクしました。そして湿地の中の沼に溶け込むように、カイアは息を引き取った。
湿地は人々の存在を静かに呑み込んで、ずっと在り続ける。
ザリガニって鳴くの?
今日は12月1日。映画の日ということで、いつもなら映画館ではまず観ないだろうと思うジャンルの映画を観てきました。
「ザリガニの鳴くところ」このタイトルからして観に行かない。小説ならありかもしれないけど、映画のタイトルとしてはどうかと。レンタルでも借りないかも。
でも、観て良かった。良作です。
ジャンルとしては、法廷ミステリー、ラブストーリー、そして女性の半生を描いたヒューマンドラマ的な要素もあるのかな。
湿地帯の自然の中で生きた女性の半生を描いていて、そこに変死体事件や恋愛が絡むのですが、原作が良いのか脚本が良いのか、はたまた演者が良いのか、ストーリーに引き込まれました。
でもザリガニは最後まで出てこなかったよね?
痴話もの
やめられない。
質問!観た方に聞きたいです!
最後に遺品からネックレスが出てきたからカイアが犯人だとなっているようですが、どう考えてもテイトですよね?
証拠として扱われた繊維がテイトにもついていることもわざとらしいまでにアピール。
渋るカイアを出版社に行かせて最大のアリバイを確保させたのはテイト。
ネックレスをはぎとる理由を持っているのはむしろカイアよりテイト。
だいたい家宅捜索でネックレスは出てきていないんですよ。繊維のもと同様に『誰かが』持っていたと考えるのが自然では?
なんでこれで彼が犯人だと誰も思わないのか?
見かけるものだと
①ネックレスを彼女が持っていたことに衝撃を受けていたから
自分が持っていて、おそらくなくしたなり処分したはずのネックレスをカイアが持っていたならそりゃ驚くでしょ。
②エンディングテーマが自然そのものであるカイアが犯人だと示唆に富んでいる。
余程のアホでない限り、テイトが自分のために犯した罪だとカイアは気が付きます。それは自分が引き起こさせた犯罪。十分に歌詞に合致すると思いますが。
明記されていない以上、悪魔の証明を求めることになってはしまいますが、テイトが犯人でないことを示すものが何一つとしてないんですよね……
スズメも良いけどザリガニも見なきゃ損
後半は一気に盛り上がる!
事前情報無し、予告編程度の知識で鑑賞。もちろん原作未読。
ミステリーっぽいスタートから、家庭内の不和や暴力が描かれる(この辺りが少しダレる感じw)。
雑貨屋の黒人夫婦だけが味方という過酷な環境(-_-;)
そしてせっかく良い雰囲気だった彼氏は、大学進学のために家族と同様に彼女のもとを去ってしまい、その隙間にチャラ男が入り込んでくるのだが、このチャラ男が絵に描いたようなクソ野郎で、暴力は振るうわ、二股をかけるわ、ストーキングをするわ、最低なヤツで、観客のヘイトを一身に浴びる事にww
そして後半は問題の法廷シーンへ。
あの検事のネチネチした追及がまた何とも嫌らしく、彼女の初老の弁護士とのコントラストが素晴らしい。
そして、懸命な弁護で彼女は無罪を勝ち取り、初恋の彼と結ばれて、永い年月を過ごした末に彼女の故郷でもある“沼地”で生涯を終える。
この辺りの平穏なシーンが続いたあとに、あの衝撃の結末。
だけど彼女を責める事は出来ないなぁ。
幕を閉じる
アメリカでヒットした小説の映画化、日本では全く知らない名前だったので、完全に知識ゼロの状態で鑑賞しました。
悪くはない、王道なミステリーなんですが、想像通りのことも起きないくらい普通のミステリーで驚きもなく、面白いとは言えないまでも、つまらないわけではない微妙な作品でした。
殺人容疑で疑われた沼の娘ことカイアが裁判にかけられる、それまでのお話がメインですが、基本的にはラブストーリーが展開されて、出会いと別れと暴力が付き纏う感じでした。最初の恋人のテイトは進学と留まる事で別れ、次のチェイスは町の人気者ですが、高圧的な態度でしか接して来ず、こいつが死んでも何も思わないなーと思える人間で、カイアを殴ったり家を荒らしたりとコイツなんで人気者なんだ?と思わざるを得ませんでした。しかも婚約者いるという隙のなさ。
ラブストーリー7割ミステリー3割くらいのバランスなので、物語が多くは動かず、ミステリーもあっさりめという満足度はやや低めになってしまいました。裁判終了後はカイアの人生の幕が閉じる瞬間まで描くというなかなか衝撃的な終わり方に持っていったのは少し驚きました。
役者陣はとても良くて、デイジー・エドガー=ジョーンズさんは初めて見ましたが、とても美しく、自然と一体化している煌びやかさがありました。嫌なやつを演じ切ったハリス・ディキソンもお見事です。夫妻も最高に人当たりが良くて好きです。
不思議な映画でした。アメリカの小説ってこんな感じなんだなーと思いました。原作にも触れてみようと思います。
鑑賞日 11/29
鑑賞時間 16:10〜18:25
座席 G-11
「私は湿地だった」
ノースカロライナ州の湿地帯で発見された若い男の死体。彼は町の裕福な家の青年だった。
やがてある少女が容疑者として挙げられる。
たった一人、その湿地帯で生きる「湿地の少女」。
彼女はなぜそう呼ばれるのか。
そして男の死の真相は…。
原作はアメリカ合衆国の動物学者、作家のディーリア・オーウェンズの同名小説。
リース・ウィザースプーンの製作会社ハロー・サンシャインが映像化権を獲得し、彼女自身もプロデューサーを務め、テイラー・スウィフトが志願して本作の楽曲を書き下ろすなど話題の多かった本作。
結末は正真正銘の衝撃!
というトレーラーのラストに惹かれて鑑賞したが、正直途中でオチが分かってしまった。
原作は未読なので何とも言えないが、少なくとも映画本編ではそれとなくヒントを出していたような気がする。
「ザリガニの鳴くところ」の意味は最後までいまいちよく分からなかったが、とりあえず本作はミステリー的にどうこうと言うことではなく、さまざまな要素を詰め込んだストーリーがとにかく面白かった。
ー無垢な少女がたった一人であらゆる困難を乗り越えて成長していくー
どおりでペリーヌ物語や小公女セーラが面白かったわけだ。
ちなみにNetflixのテイラー・スウィフトを追ったドキュメンタリー「ミス・アメリカーナ」は、ある意味本作の戦うカイアを地で行く作品となっている。
価値観
ノースカロライナの湿地を舞台に起こる、ヒューマンミステリー。地元の人から「湿地の女」と呼ばれるカイヤの逮捕から、湿地で孤独に生きてきたカイヤの物語が紡がれていく。
この話の主題は「価値観」だと思う。「価値観」とは「生きる」「善悪」に象徴された我々が培ってきたものだ。法廷という「善悪」を裁く場で「生きる」ことを望んだカイヤの話が展開されることで、観客・読み手に「価値観」を通してミスリードを発生させることが出来ていた。
結末に向かうまでのストーリーとしては一貫性があった。父親の暴力によって引き裂かれた家族。孤独に生きてきた彼女の支えとなったテイト、チェイスの裏切りと暴力。
ラストで明らかになる真実は、カイヤの人生を振り返れば合点がいく。湿地で生き、自然の摂理の中で育った彼女にすれば「生きる」ための防衛反応であり、「善悪」とは我々の尺度で測られたものでしかないのだ。
振り返れば、暴力に屈しないと決めたカイヤは、ボートの音に気付き草むらに隠れ、石を握っていた。そして一度も無実は訴えていない。ただ湿地=homeに帰りたかっただけなのだ。
クライマックスでは、カイヤが「裁くのは彼ら自身よ」と陪審員への感情を弁護士に伝える。弁護士はカイヤの思いを受けて、「我々が持ってきた偏見を捨てて、事実のみで判決を下してほしい。今一人の人間としてカイヤを見るチャンスなのだ」と訴えかける。
このシーンを含めて弁護士を我々に重ねることが出来る。これまでに救うことが出来なかった彼女の言葉を自身の「価値観」で判断して弁護する。そこには、生い立ちを知った同情や目を背けた後ろめたさが渦巻く。そして、判決でやっぱりカイヤは「無実」なのだと安堵する。
今作の小説が高く評価された部分はこの「価値観」を描く上で、自然の摂理、生物の描写が細かく、クライマックスに向けてカイヤの生き方とリンクしていくところだろう。
だが映像では描き切れているとは言えない。最後にペンダントが出てきたところで、「カイヤが殺していたんだ」という驚きで終わってしまう。時間に限りがある中で、人間模様に時間を割かざるを得ず、自然の摂理を描く時間が足りなかったように思う。
今作を通して我々はあらゆる「価値観」で生きていることを思い知らされる。ミステリー要素は薄いかもしれないが、ヒューマンドラマとしては中々の見ごたえがある作品になっている。
主演のデイジー・エドガー=ジョーンズの演技は表情も豊かで素晴らしく、生物や植物のイラスト美も一見の価値はあるだろう。
ザリガニの鳴くところは自分で作るしかない
ある日ノースカロライナの湿地帯で男性の遺体が発見され、その湿地に1人で住む女性カイアが容疑者として捕えられ、彼女の生い立ちと裁判の行方が描かれていくミステリー。
テーマの1つが、自分と立場が異なる他者への理解、なのだろうけどその他者への理解がいかに不可能であるかを描いている話っぽかった。それも、結局この映画の登場人物は誰も他者への理解なんてできてなかったように見えたから。
カイアを好奇な目で見る外部の人はもちろん、カイアの味方の人達もカイアは清廉潔白という"偏見"を持っていたし、被害者のチェイスも男を知らない従順な自分だけの湿地の娘という"偏見"を持っていた。誰もカイアを真に理解していなかったのかなと思った。
それも、裁判で全く発言をしていないように、カイアって誰の方へも歩み寄ってないんよね。カイアの置かれた孤独で辛い立場も分かるけど、異なる立場どうしの迎合は対話から始まると思っていて、カイアからの歩み寄りも少しは必要だと思う。湿地におびき寄せるみたいなナレーションであったように、自分は口をつぐみながら周りの人を動かしてた。
良いイメージも悪いイメージも全ては偏見。そもそも他者への理解自体が偏見ってことか、と最後の最後で悟った(笑)
まぁでもずっと孤独で生きてきて、幸せだと思っていた家族揃っていたあの頃が、自分も暴力を経験することで初めて最初から安心出来る場所ではなかったことがわかったら、そりゃ自分で安心出来る場所を作らなきゃってなるだろうなと思った。
湿地と共に生きた女性
映画館にて鑑賞しました。
ミステリー小説が原作ということですが、なぜ人が死んだのかという点よりも、被告人となった主人公の半生がメインで描かれていきます。
ひどい家庭環境と偏見の中で生きてきた主人公の人生は、見ている側にも辛くなります。見ているとなんとなく主人公に同情していきますね。
結果、主人公は無罪となりましたが、彼女の死後、裁判でも話題に出てきた貝のネックレスが見つかります。よくよく考えると、劇中で主人公は殺人については認否については明言しているシーンはなかったな、と思いました。(自分の記憶の中では。)
湿地で生活し、湿地の一部となった彼女にとっては、出版社の人に話したように、生きるためには善も悪もなかったのでしょう。(だからといって彼女がチェイスを殺したかどうかも分からないですが。)そう考えると、善と悪を作る生き物って人間だけなのかも、とふとよく分からないことを考えたりもしました。
湿地帯もカイアの映像もきれい!
何故高評価なのか理解できない。
冒頭部分で青年の変死体が発見され、カイヤという主人公の女性が、その嫌疑を掛けられる。
その後、弁護士にカイヤが自身の半生を語るという形で、カイヤの生い立ちの回想がはじまるわけだが...
その生い立ちが、面白みに欠けている。
もう少し情緒豊かに表現してくれれば、また違った感想になったかもしれないが、実に単調で淡々としている。
父親によるDVや母親の家出、恋人の裏切り等、孤独な立場に立たされるカイヤであるが、それらが叙事詩のようにあったことを並べただけのようで、心の琴線には触れなかった。
本来、孤独の描写とかは好きな性分であるので、感情移入もできるし、グッとくるはずであるのに、この映画の鑑賞に際しては、まるでそれを感じなかった。
また、父親によるDVや学校に打ち解けられないカイヤが、色恋に対しては、その傷やハンデなど微塵もないが如く、事も投げに、心開いて、対応できる点なども、ご都合主義に思えてしまった。
中盤辺りから、そのようなストーリーに対する懐疑心が生まれてしまったので、終局に当たっても、「そうなの。でも、だからなんだろう」と思えてしまった、
どこかで似たようなドラマを観たことがあるような即視感も相まって。
一つよかった点を上げるとすれば、壮大な自然を映した映像美だろう。
そこだけよかった。
ということで、私には何故この映画の評価が高いのかまるで分からなかった。
全444件中、221~240件目を表示