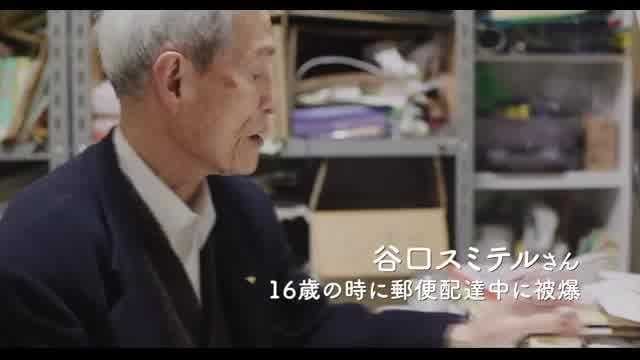「いろいろな方も、そして広島県に在住・出身の方も(参考知識入れてます)。」長崎の郵便配達 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
いろいろな方も、そして広島県に在住・出身の方も(参考知識入れてます)。
今年230本目(合計506本目/今月(2022年8月度)6本目)。
18歳まで広島市にいた事情、および行政書士合格者レベルの目線です。
この映画はタイトル通り長崎の原爆を扱う内容ですが、先行する広島への原爆投下と似た事情、違う事情がそれぞれあります。この映画はもっぱら長崎のそれに焦点をあてて描かれた内容です。
日本の教科書では小中、そして高校ともに、「広島、長崎に原爆が投下され…」程度で、この2つの出来事は同列に扱われますし、一般的な理解はそうですが、それぞれ同じ経緯であるもの、たどったものもあれば、違う経緯や違うその後も存在します。
映画内で扱われているように、長崎はその歴史の性質上キリスト教文化が広島より盛んであったため、原爆に関しても一定程度キリスト教(や、教会その他)に関することが出ます。ただし、これらのことは、長崎県・長崎市などの公式ホームページ等で拾える範囲です。
この手の映画は概して、そして特に当事者(広島県・長崎県在住、出身者)の立場だと「原爆はダメ、戦争はダメ」という立場「だけ」になりやすいのですが、そもそも論として「なぜに日本は第二次世界大戦に突入するに至ったのか」という論点を忘れてはならない、そう思います。その点を考えないと、当然、一定程度、また一般常識として「原爆・戦争はダメ」という考え方に流されやすいところ、結局は「日本はそれまでに何をしたのか」という逆の論点(加害論点)がすべて消えてしまうからです(被害論点ばかりを論じても、加害論点が消えるわけでもない)。
なお、映画内ではちゃんと、「広島・長崎の原爆投下の事情における事情の異同」については描写がありますが、長崎県・市の公式ホームページ等を見ておくと有利です。また、この映画はエンディングロール等がローマ字表記が併記されているようで、この観点でも高く評価できます(どちらに偏ることなく、事実のみを淡々と述べる映画は海外でも見られるべき)。
減点対象はまるで見当たらないのでフルスコアにしています。
なお、「広島と長崎が戦後歩んだ歴史」について下記に書いておきます。
----------------
▼ 参考 広島と長崎が戦後歩んだ原爆投下の被害に対する対応の違い
・ 程度の差はあっても、現在も今も、広島のほうが居住者が多かったこともあり、広島のほうが多く語られやすいのですが、この2つは等しく扱われるべきものです。
さて、広島と長崎が戦後歩んだ、原爆投下に伴う福祉行政(被爆者に対する福祉の扱い)について。
この点は長崎と広島は大きく分かれ、広島は現在にいたるまで被爆者と行政との闘いが存在しますが、その過程として、「被爆者援護法に基づく被害者への援助」に関して、広島県・広島市のムチャクチャな対応が存在したことが背景にあります。
「被爆者援護法」はそもそも、被爆者として認定された方に対して健康手帳など福祉サービスを提供する趣旨の法です(広島・長崎に対して通常は適用される。そもそも、場所を限定していない)。一方、広島長崎を含め、東京大阪など、戦後の混乱期にはそもそも「職業につく」という概念すら存在しえなかったほか、居住すらまともに確保できないという戦後の混乱期が存在します。そのため、海外(特にブラジル)に移住した方もいます(国籍を日本に残したままで)。
ところが、「被爆者援護法」にはどこにも「外国にうつると支給認定に伴う福祉サービスの支給がなくなる」などという趣旨は存在しないのに、通達(広島の原爆では「402通達」と呼ばれます)でなぜか「海外になると打ち切りになる」という趣旨のものが出され、それが下級行政庁(ここでは国→都道府県その他なので、広島県・広島市)を拘束し、その通りになってしまい、その運用がしばらく続きました。
ところが法にそのようなことは書かれておらず、元の通達そのものが法に基づかなかったため、海外(大半はブラジル)に移住して戻ってきた人達が援護法に基づいて福祉サービスを求めたところ、時効(地方自治法に定められているもの)にかかったものの大半について「時効にかかっている」として支給しなかったという経緯があり、これが問題になり最高裁まで争われています。
結局(平成19年)、「そもそも通達自体が違法で、その通達に基づいて運用した下級行政庁(ここでは、広島県・広島市)が、それに基づいて運用すれば、その通りに運用する限り当該当事者は申請すらできないし、しないのが普通なのに、今度は通達が違法だという判断でその通達が廃止されたとたんに、また時効を援用するのは支離滅裂で信義則に反する」という最高裁判例であり(いわゆる「402号事件」「 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件」などと呼ばれるもの)、これにより一律救われるようになりましたが、このような経緯があったため、広島と長崎とでは行政(ここでは、原爆に関する福祉行政を指す)に対する不信感の違いが決定的になり、それが今日に至る「黒い雨訴訟」などにもまで影を落とします。
※ 高裁判決(平成18年)でさえほぼ同趣旨のことを述べており、明らかすぎて広島県・市に勝ち目はなかったものの、結局お金の出どころは国になるため、国が上告(高裁→最高裁への控訴は「上告」)すれば広島県・市もそうせざるを得なかったという事情もあり、この点では広島県・市は「そもそも違法な通達に拘束されたという点で被害者」でもあります(現在(2022)は、国と地方は対等な立場」で、国防など特殊な事案以外は、通達に拘束されないため、こういった論点は発展的に解消されています)。
この点が大きな違いで、結局「人口の差」に来る「当事者の数、福祉行政の差(サービス量の差)など」にあるとしても、「行政に対する不信感」は広島・長崎で大きく異なったもので、この点は意外に忘れられやすいです(各種国家試験では、司法試験と行政書士試験では必ず触れる内容です)。