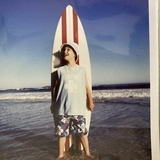聖地には蜘蛛が巣を張るのレビュー・感想・評価
全126件中、61~80件目を表示
空から撮った映像とタイトルが重なる
衝撃的な内容なうえに、見終わった後に難題を突きつけられる作品。物語の早い段階で犯人を映し出し、その鮮烈な犯行シーンをありありと見せつけられる。
ジャーナリスト・ラヒミを物語に入れることで、イランの女性蔑視、男尊女卑に関することも浮き彫りに。
娼婦を悪、生きる価値がないとみなして、一掃しようと勝手に使命を持つサイード。
サイードが捕まった後も、無罪だと声を上げる信者や家族(普通におかしいだろ!?)。
宗教の恐ろしさを痛感させられる。
そして、娼婦を生み出す社会にも問題があるし、それを放置する警察や政治もめちゃくちゃだ。
ラストは2度にわたりサプライズが用意されているが……
息子が取材に淡々と応じて、反抗シーンを説明するところも恐怖だった。第二のサイードにならないでほしいと願いたいが、いずれ第二のサイードが誕生するのだろう。
なかなかよく出来たストーリーだった。
後味の悪いサイコ人間ドラマ
タランチュラ男 vs 女郎蜘蛛
クモは巣を張って待ち構えるタイプとタランチュラのように巣を作らないで動き回って獲物を捕らえるタイプに大きく分類されます。
題名から女郎蜘蛛の話だと思ってました。
原題は Holy Spider 。
この映画の題材となった実際の事件で、聖地で商売をする街娼を聖地浄化を理由に次々に殺害にする犯人をマスコミがヒーロー視してスパイダーと呼んだことがはじまり。巣を張るのではなく、みずから獲物を探しにバイクで出掛ける。イラン第2の都市マシュハド。シーア派の聖地が舞台。
イランの映画は「英雄の証明」、「白い牛のバラッド」、「ホテルニュームーン」しか観てない。
これらの映画では裁判と処刑がうんとスピーディ。宗教が絡んでか?三権分立がちゃんとしていない感じ。
「ボーダー 二つの世界」の監督の作品。この監督はイラン出身だとこの作品で知りました。北欧の人とばかり思っていました。
新聞社をセクハラで不本意なかたちで解雇された女性ジャーナリストが真相を追ううちに自らをオトリにしてしまう展開はもちろん期待もしていましたが、あのおデブ姉さんの死んでからのアシストがなかったら完全にクモの糸でグルグル巻きにされてましたね。犯人は手首が治るのをなぜ待てなかったのかと言ったら野暮ですけど。
ハラスメントに苦しむ女性ジャーナリストが街娼に肩入れする気持ちはひしひしと伝わって来ました。イスラムは女性差別が色濃く残る世界。
個人的に、あんなきれいな若い嫁さんがいて、小さい可愛い子供も三人もいるのに、夜な夜な出かける初老のジジイは何考えてんだ???でしたけど。
しかも自宅。
繰り返される絞殺シーンもなかなかリアルでエグかった。
このオジサンはネクロフィリアのケもありそう。繰り返すうちに絞殺自体に恍惚感を覚えてしまったのではないか。従軍体験もきっかけだった可能性も大。イスラム世界は死後6時間以内の死姦は許されるらしい。よくわかんないけど😵🌀
傑作でした。
殺人犯であり、決して英雄ではない。
夜な夜な街で客を取る娼婦たちを殺害して街を浄化しているという犯人。娼婦たちは生きていくために家族のために仕方なくやっているんだろうに。娼婦だけが悪い?買う男たちは悪くないのか?浄化するなら客の男も浄化するべきではないのか?
逮捕された後の街の反応にも驚きである。息子は学校でいじめられるどころか、英雄の息子として称賛され、買い物に行けば、ただで物をくれたりと、街中が応援体勢。犯人の奥さんまで、娼婦を悪く言い、夫を正当化する。
最後の父親の行為を再現する息子、娼婦の役を妹にやらせる。母親も止めないんだ!異様な国た。
タイトルなし(ネタバレ)
イランの聖地マシュハド。
イスラム教の聖地であるが、夜になると街中には娼婦が溢れている。
そのマシュハドでは娼婦をターゲットにした連続殺人事件が続いており、都度、新聞社には死体遺棄現場の告知が犯人から届けられていた。
警察の捜査は進まない中、女性ジャーナリスト・ラヒミ(ザーラ・アミール・エブラヒミ )は危険を顧みずに、単身、事件を追うことにした・・・
といったところからはじまる物語ですが、いわゆる犯人捜し・意外な犯人のミステリではなく、巻頭早々に犯人は明らかになります。
エンタテインメント性からはかなり遠い作品といえます。
興味深いのはイスラム社会、イランの生々しい現実。
冒頭殺される娼婦の出勤準備の様子から、これまでのイラン映画とは全然異なることがわかります。
薄暗い部屋で、上半身裸で濃いルージュを引き、ヒジャブ代わりの派手なスカーフを被り、身支度を整える女性。
傍らには幼い子ども。
マシュハドの中心街も煌煌とというにはほど遠い街角に娼婦たちがたむろしている。
そして、殺人・・・
殺害の様子も生々しい。
女性ジャーナリスト・ラヒミに対する扱いも甚だしく、独身女性が単身でホテルに泊まることは忌避されているようで、難癖をつけて宿泊を拒否。
(最終的にはジャーナリストとわかり、部屋は確保できるのですが)
また、取材に応じた警察幹部も女性蔑視は明らかで、なにかにつけて性的な行為に及ぼうとしたり、と兎に角ひどい。
この生々しい現実は後半、おぞましさに変貌します。
犯人が最後に殺すベテラン娼婦とのやり取りはすさまじく、これまでならばヒジャブによる絞殺に至るのだが、体格差からそうはいかず、激昂した犯人は素手で何度も何度も殴ります。
このシーン、ほんとにすさまじい(一瞬ですが、日本の今村昌平監督作品を思い出しました)。
この惨劇が、アパートの自宅の一室で行われていることが、さらに気分を陰鬱にさせます。
で、最終的には、ラヒミが自らを囮にして犯人は逮捕されるのですが、そのあとはおぞましさが浮かび上がってきます。
犯人は、イスラム法を実現しただけと反省に色はなく、市民の多くも犯人に共感を寄せる。
十代の息子も、犯人の父親を尊敬し、最後には父親から聞いた殺害の様子を、さも誇らしげにテレビカメラの前で披露する・・・
『ボーダー 二つの世界』では、生々しいファンタジーの世界を描いたアリ・アッバシ監督。
今回は生々しくおぞましい現実社会を描きました。
監督自身がイランのテヘラン出身ということで、これまで描かれなかったイランの現実社会を描いたのでしょうが、海の向こうの世界、他所のハナシというように傍観しているだけでいられないところも感じました。
どうも、身の周りの社会も少しずつおぞましさが表れつつあるような感じがして仕方がないのです。
戦慄のラスト
社会にはびこる哀しき現実
「お前何様だよ!」怒りの感情がコントロール不能になった
街を浄化するだと?
娼婦16人を殺害、イランで実際に起きた事件に着想を得た作品だがドキュメンタリー映画と思う程の恐ろしさがあった
実際は犯人を支持し英雄視する市民は一部だったそうだが
だいたい買った男達は何なのさっ!
こっちの浄化はどうする?
不平等で不公平な現実に怒りと切なさが止まらなかった
被害者にも家族がおり、それぞれの事情と悲しみと真実を少しでも訴えたかった監督の気持ちが伝わってきた
犯人の妻も同じ女性である被害者達を罵倒し軽視する…同性であっても環境や境遇で格差が生じてしまうのは哀しき現実なのだ
事件を追う女性記者を演じたザーラ・アミール・エブラヒミ
危険を顧みず犯人に近づく後半は異様な緊張感に体が震えた程、迫真の演技でした!
カンヌで女優賞を獲得したのも納得!
犯人の息子がゲームを楽しむかの様に幼い妹を
モデルに父の手口を再現する
それを止めもしない母親…あまりにも衝撃的で哀れな結末に嘆きの溜息しか出なかった
人権意識の低さはと他人事ではない
イランを舞台にしているが、これは日本にもあてはまる。男女差別が濃厚な上に、不甲斐ない自分を認めることが出来ず社会的な弱者を攻撃する。狭量な見識と不寛容、自分にとって都合良く神を利用する反知性主義。人を思いやる感受性の欠落した人は至る所、すぐ隣りにも居る。それは自分かもしれないのだ。先ずは個人であり、自分の足下を見詰め、常に内省を心掛ける。この作品は社会と個人の在り方を問い、差別の根源を社会だではなく、自分に問う啓蒙作品でもある。1人の人間に立ち返り、自らを鑑みて鑑賞すべき映画である。決して他人事ではない。知らず知らずのうちに自分にもこびり付いたものが見つかるはずだ。無関心、無自覚な自らを内省しつつも、糾弾するためのヒントを辛くも与えてくれる佳作である。
神のためにやった。俺の手はきれいだ。
イランで発生した娼婦連続殺人事件が映し出す欺瞞
「イランを舞台にしたサスペンス」という、なかなかお目に掛かることのない希少なカテゴリーの映画ということで、物珍しさから観に行きました。
内容的には、2000年から2001年にかけて実際にイランの宗教都市・マシュハドで起こった16人もの娼婦連続殺人事件をベースにして創られたもので、本作の主人公の一人である殺人犯サイードは、実在の殺人犯であるサイード・ハナイをモデルにしており、名前も一緒。もう一人の主人公で、殺人事件を取材し犯人逮捕に貢献した女性ジャーナリストであるラヒミは、本作が創作したキャラクターですが、実際の殺人事件を取材したドキュメンタリーで本物のサイードにインタビューを行った女性(サイードは、この女性インタビュアーに、「次はお前が標的になったかも知れない」と仄めかしていたそうです)や、事件を埋没させないよう奮闘したジャーナリストたちを集約した存在だったようです。
サスペンスと言っても、サイードが犯人であることは早々に分かるというか、犯行の様子が最初から映し出されるので、刑事コロンボの倒叙法よろしく、観客には分かっている犯人をラヒミが突き止める過程を描いた作品でした(コロンボのような陽気さはかけらもありませんが)。ただこうしたサスペンス的な要素もさることながら、本作のメインテーマはイランにおける歪なミソジニー(女性蔑視とか女性嫌悪)でした。一般に報じられているように、イスラム諸国の中には女性の権利が大幅に制限された国があり、タリバンが政権を握るアフガニスタンなどはその最右翼で、女性は大学どころか中学にすら行かせない政策を採っているようです。
一方本作の舞台となったイランにおいては、「実際のところイランでは、女性たちは男性に比べても進学率も高く、高学歴であったり、様々な職業で重要な地位に就いている場合も少なくない(本作のパンフレットから引用)」そうです。ただ、「一般的に、離婚の権利や親権の問題、相続など男性に比べて不利な立場に置かれているのも事実(パンフレットから引用)」だそうで、女性の置かれた立場は相対的に低いようです。さらに、「イスラーム体制のイデオロギーにおいては女性の貞節と良き母親という役割が強調され、預言者ムハンマドの娘であり、イマーム・アリーの妻であったファーテメ(ファーティマ)が理想とすべき女性像とみなされる(パンフレットから引用)」という土壌もあるようです。
本作の主人公である女性ジャーナリストのラヒミは、「高学歴で様々な職業で重要な地位に就いている女性」の代表格である一方、殺人犯サイードの妻であるファテメは、名前が示すとおり「イスラーム体制で理想の女性像」とされるファーテメの化身として描かれています。
実際ラヒミは、娼婦殺人という、解釈によっては宗教的に擁護される事件を調べていく過程で、上司だけでなく、警察官からすらもセクハラを受けています。一方のファテメは、夫の行った殺人が明るみに出た後も、夫の行動を支持し、彼を擁護する立場を貫きます。
ミソジニーというのは、一般に男性から女性に対する蔑視とか嫌悪感情を指しますが、女性自身が女性に対しても持ちうるものだと言うところが難しいところのようで、これはイランとかイスラム社会に限った話ではないと思われます。
また、実際の娼婦殺人事件においても本作中においても、犯人のサイードは宗教的な使命のために娼婦を殺したと主張する訳ですが、実際に殺された16人中13人とサイードは、性交渉を持ったとのことです。本作では、殺した後の娼婦の身体にキスをするサイードが描かれており、要はイスラム教の教義だけが殺人の理由ではなかったのではないかと考えられます。
イスラム教というと、日本ではなんとなく怖いイメージが先行しますが、結局イスラムが怖いものであるというイメージを与えている一因となっているミソジニーとか男尊女卑というのは、宗教と密接に関連はあるものの、それだけで語れるものではないようにも思えました。我が日本においても、夫婦別姓制度が、選択的という条件を付けていながらも、G7参加国で唯一認められていません。普段は自由主義陣営の一員を自認しているのに、そのメンタリティーは、程度の差こそあれどちらかというとイランやアフガンに近いようにすら思えます。
話を本作に戻すと、特にサイードの犯罪に関しては、宗教行為を偽装したレイプ殺人と捉えることが可能ということです。ところが事件当時イランにおいて、彼を擁護するイスラム教徒が一定数いたことも事実であり、この辺りが大量殺人という事の重大さに反比例して、実に滑稽なイラン社会の在り方を表していたように思えます。
以上、娼婦に対する連続殺人事件を扱った映画でしたが、単なるサスペンス映画の領域を遥かに超え、イラン社会、そして実は世界中に蔓延るミソジニーを告発する作品だったとも言えます。こうしたテーマ性から、当初計画したイランでの撮影は、イラン当局から許可が出ず、ヨルダンのアンマンで撮影を行ったようですが、馴染みの薄い中東の街の風景を観ることも出来、非常に興味深い映画でした。
イランを舞台に成功したサスペンス映画
日本の遥か彼方、アメリカに言わせれば、北朝鮮と並ぶ悪の枢軸であるイランが舞台。2000年代初めに実際にあった事件を基にした犯罪サスペンスだ。
セリフはペルシャ語で、20年以上前が舞台とはいえ、貧しいイランの庶民の生活が生々しく再現されている――。
なかなかに骨太な作品だ。
仰々しいだけであちこちに忖度したようなハリウッド映画や、世界市場を視野にいれて最近は小賢しくなってきたような韓国映画に比べると、ちょっと荒々しく、見るのには手ごわい印象も受ける映画。だが、見終わって強い印象を残す。
新聞の映画評を読んだだけで、監督もキャストのことも何も知らない、調べることもないまま映画館へ。
イスラム教にガチガチに縛られている(と思われる)イランでこんな映画が撮れるわけもないが、イランとイスラム社会を告発するという社会派作品というわけではない。
映画はイラン人の視点で描かれ、事件を追う女性ジャーナリストがどういう目に遭うのかというハラハラ感もくすぐる映画的面白さも追及している。
売春婦殺しというのは切り裂きジャックに代表されるように、犯罪ものでは一種古典的テーマだ。それがイスラム世界で起きたらどうなるか――。実際にあった事件に重ねて、虚実入り混じったような終盤の物語り展開も、なかなかに面白い。
最後まで飽きさせず、強い印象を残した良作だ。
継承
映し出される遠景。
街の光が、雨の雫を抱く繊細な蜘蛛の巣のように美しい、そこはマシュハド。
巡礼の聖地といわれる都市で起きた二十数年前の犯罪を元に構想された本作。
そのリアリティは、鋭利な刃物をちらつかせ、退廃的な路地裏の怪しい静けさにうごめく恐怖を連想させた。
そして、そこからわかるのは、人権、差別、貧困、薬物、教育格差など、目を逸らしたくなることもある負の連鎖にうまれる問題が、あたかも弱点を追い詰めるように狙いを定めてくること。
このダークサイドに関わるのは、皆、〝自分を〟生きる為に…だということ。
当然、こどもたちの無垢と無知は環境と一緒にいる大人の理論の影響を存分に受ける。
もちろん全てが悪ではないが、もし、それがどんなに不条理だとしても、常識と非常識が独自に設定されていく。
それを選ぶことはおろか、知ることさえないまま。
そのなかに、いつのまにか蝕まれゆく危うい継承があることを犯人の心理とその一家の様子、ジャーナリストの視線を軸にして語っていくのだ。
………
戦地から戻ったサイードは、突然コントロールできないほど自分を見失う行動をみせる。
心に深い傷を負っているのは明らかだが、普段は建築関係の仕事で家族を養う子煩悩な父親であり優しくい夫だ。
そして彼は街を震撼させている娼婦連続殺人の犯人でもあった。
街の〝浄化〟を大義名分に立て闇に彷徨うサイード。
犯行声明を出し存在をちらつかせ、怪しいと目撃されながらもなかなか捕まらない。
それはなぜなのか。
一方、この犯人逮捕への手がかりを得ようと、身を呈してマシュハドに乗りこんでいくジャーナリストのラヒミ。
危険極まりない事件への恐怖を越え、真理のために目をそむけない彼女の勇敢さ。
それをかりたてるラヒミ自身の過去とは。
さらに悲しいことにそう言ったことが未だに身近にはびこっていることを織り交ぜてみせていく。
ショッキングなラスト。
〝父の後継者に〟と一部の人々から推されたことを意気揚々語る処刑されたサイードの息子。
父から伝授された手口を誇らしげに話す姿。
それを楽しそうに手伝うあどけない妹。
一筋のためらいもなく撮影する母親。
サイードはもういないが、その正義は確かに継承されたのだ。
遠い国の話、宗教やお国柄がからむ話、と、そういった選別や偏見なく、この流れはどこにでもおこりうるのだと感じ思わず眉間に皺を寄せた。
誰かの信じるものを頭から否定するつもりはない。
けれど、ビデオに映ったあの息子は大丈夫か?娘は?母は?
親としての私の感情が手伝い、混沌とした気持ちが押し寄せる。
おそらく事件はおさまっていない。
ずっとずっと、国、法、地域性、宗教が社会情勢とかわらない連鎖に絡み合い、矛盾を匂わせながら続いているのだろう。
光るあの雫は、幸せな暮らしの灯りではなく、歪んだ正義が呼ぶまやかしだったのか。
いや、断ち切れないつながりがこぼした切ない涙なのかもしれない。
忍び寄る今夜のとばりにも、生きるために死ぬかもしれない彼女たちは街角に立つのだろう。
サイードのような正義を掲げ、誰かが近寄ることをわかっていたとしても。
では、どうすれば?と考える。
選べずに、生きていくこと、信じること、受け継ぐこと。
知識や道徳教育の重要性がわかっていても、かえられないものもある。
単純にはいかない問いかけの難しさが、自分の足枷になったように帰り道の足取りが重くなった。
しばらくたつが答えは降りてこない。
⭐︎の数、間違えてたので修正しました。
イスラム法と民主主義は理解しあえないという絶望。
娼婦は殺しても罪ではないというのを私は受け入れられない。
しかし、彼ら(女性も含む)が娼婦殺しを正当化し、犯人を英雄視する理由は理解できる。
繰り返すが、とても受け入れられない。
彼らや彼女らは何世代にも渡って生まれたときからコーランの教えの中で生き、男性中心、男尊女卑が当たり前の世界で暮らしてきた人達だ。コーランに娼婦は重い罪だとある。そんなヤツらが町の外にいてやたら目につく。そいつらを殺すのは、正しいこと・良きことであり、町の浄化になる。全くその通りの正論(彼らにとって)で、反論の余地もない
とにかく彼らの主張を私は全く受け入れられない。20年以上前の事件だが、たぶん今も変わってないと思う。
「イスラム法と西洋型(欧米型?)民主主義はお互いに受け入れられない」というのが最近の私の絶望的な考えだ。
2023/4/20(木) 吉祥寺uplink
女性や法をめぐる不気味なあいまいさ
2022年。アリ・アッバシ監督。イランの保守的な聖地で起きている連続娼婦殺人事件。取材に乗り込んできた女性ジャーナリストは様々な障害に会いつつも、体当たりの取材で犯人に迫っていく。一方で、退役軍人である犯人は神の教えと自らの欲望と承認欲求がないまぜになって殺人衝動を抑えることが難しくなっていく、という話。
同時多発テロと同時期に実際にあった事件に基づいている。イランは宗教的には保守的なシーア派だが文化レベルは極めて高く、文化と近代文明が齟齬をきたすところはかつての日本に似ている。この映画でも、警察や裁判所や新聞社の人々が近代的な法的枠組み・理念と宗教や文化に基づく大衆的欲望・感情の間に立ち、どちらかに肩入れしたり板挟みになったりしている。
この映画の秀逸なところは、その境界をだれかが決めているわけではないところを明確に描いていることだ。犯人は宗教的な「浄化」を果たしているとして民衆から英雄視され、退役軍人会や検事と裏工作で助け出す口約束を交わす。実際、一部の刑罰が免除される様子も描かれる。ところが、実際には死刑になるのだ。その判断にどこまで誰の意思が反映しているのかはわからない。犯人を見つけ、厳罰を求めるジャーナリストの努力はまったくの無駄でもない代わりに、見える形で効果的だったというわけでもない。この不気味なあいまいさが、法や女性をめぐって、イラン社会を覆っているのだ。
日本では馴染みのない宗教クライムサスペンス
全126件中、61~80件目を表示