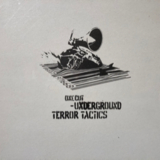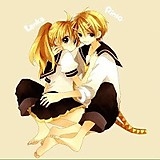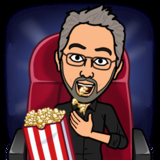線は、僕を描くのレビュー・感想・評価
全277件中、21~40件目を表示
映像が綺麗
日本家屋、庭園、水墨画、映像が綺麗で心が浄化されるような時間。
筆で、薄い色や濃い色太い線から細かい線。水に墨が広がっていく波紋。描かれてゆくのを見ているのがとても心地よくてずっと見ていたい。水墨画ってこんなに奥深いんだ、と気づかされた。
美しい映像を見るための映画なので、ストーリー重視で見る映画ではない。大きな画面で見たほうがいい
自分的に、水墨画を描いているシーンがもっと多くてもよかったなーというかんじ
書道をやっていたので、見入ってしまった。お手本を綺麗に真似するのは簡単で、自分を表現するような文字を書くのって難しいもんなー。
真っ白のキャンバスに、何を描くか、その描いたものが自分を形作っていく。それは、水墨画だけに限らない。
誰が描いたの?
水墨画に昔から興味はあったものの、チャンスなく年月が去り……
大学のサークルにあったなら、参加してただろうなぁ
羨まっ!!
大大大好きな女優:富田靖子が少し残念だったのは、きっと役柄のせいです
ハイ
いい年の重ね方をしている三浦さんも、江口さんもメチャこの役にハマってました
適役とはこういう場合に使うべきだと思います
主人公の横浜さんも、清原さんも決して悪くはなかったけどね
外国の大使?あれは??
水墨画の良さが分かる前提?
あそこだけは、この映画の流れの中で要らないシーンだし、要らない登場人物ですね
たとえそれが原作にあったとしても
3年も経っているのに庭の椿が残っている??
刻んだ背の高さを書いた柱も??
ありえないなぁ
大学の講師には謝礼金は誰が出すの?
細かいところは気になったけど、まぁいいか
★特筆すべきは、エンドロール★
1つ1つの水墨画の完成度も凄過ぎて、誰が描いたのか調べても出てこなかったのが残念
ただ、コンポジットをSUPER SUPERというラボが担当したのは分かった
名前の出し方も斬新でいいし、味のある筆致!
描く順番などを意識して、まるでそれを再現してるかのようなコンポジションには震えた
きっと、横浜さんの人気と相まって水墨画のファンが増えるだろうなぁという映画でした
実際、保存して、水墨画にチャレンジしたいなと思ってます
一発真剣勝負の世界
原作未読、「ちはやふる」も未視聴のまま鑑賞。
ちょっと想像していたものと違った。
青春映画という触れ込みだが、ストーリー展開は、それにしては弱いと思った。ドラマチックな場面もあまりない。
ただ、恋愛要素を排除した展開は良かったと思う。霜介(横浜流星)と千瑛(清原果耶)が恋愛するようなことになったら、「水墨画」という舞台設定が台無しになっていただろう。
主演、準主演もよかったが、それ以上に良かったのは、湖山(三浦友和)と湖峰(江口洋介)。2人のパフォーマンスシーンは、水墨画というものが、描き直しのできない孤独な真剣一発勝負の世界なのだということをダイナミックに伝えてくれた。
パフォーマンス以外も、この2人の演技が良かった。やっぱりキャリアの違いが出たか。
もう少し、霜介と千瑛、湖山と湖峰を通して水墨画の世界の奥深さを味わえるような物語にしてほしかったというのが個人的感想。主演が主演、テーマがテーマ、狙っている客層が客層なだけに、そこまで欲張るのは無理だったのかもしれないが。
映画のタイトルは秀逸。とてもよく考えられていて凄いと思いました。
墨に現れるモラトリアム
霜介も千瑛も同世代で、自分の進む道を探している時期。
霜介は法学部に通う大学3年生だが、家族を亡くした後悔と苦悩、孤独に3年間苛まれ続けている。将来進む道を考える時期だが、自分が何者かでいる感覚も何者かになれる自信も、湧いていない。
そんな中友達の代わりに来た水墨画イベントの設営で、ふと見た椿の水墨画に家族を思い出し涙する。
水墨画の巨匠に出会い、弟子入りは烏滸がましいので生徒になり、椿を描いた、千瑛と出会う。
千瑛もまた、巨匠を祖父に持ち、素直に祖父に教えを請えない距離感になってしまった関係性と、作品を賞の目線で酷評されて以来楽しいだけの水墨画ではなくなってしまい表現に彷徨っていた。
そのような心模様は、水墨画では線に出るという。
繊細な霜介の線に、形にとらわれず、思い通りにはならない自然に任せて好きにして良いんだと声をかける巨匠の温かみ。
巨匠は霜介の繊細さをいち早く見かけていたとともに、礼儀正しさにも気付いていたと思う。
受けたアドバイスを何度も練習して、現実を忘れるが如く水墨画にのめり込んでいく霜介。そのうち、向き合う事が難しく、蓋をしていた心のつっかかりと向き合い、3周忌に故郷に足を運ぶ覚悟がやっとできた。
上京する日に喧嘩したきり、家族が水害で流された。自分を責め、戻らない現実を悔い、あの日以降も戻れずにいた故郷に戻る道中、抱えていた経緯を千瑛に打ち明けて話す事ができた。
千瑛もまた、祖父が2度目に倒れたことで、まだまだ聞きたい事が沢山あるのにと素直な気持ちを出す事ができた。写実的な画風の千瑛もまた、自分の命をかけて心を表す線を描くことに苦戦していたが、家出をし、本心と向き合い、霜介の故郷を一緒に訪れることで自我の解放をできるようになる。
二十歳前後の年齢は、将来進む線を描くのがとても難しいことに激しく同意する。
その頃、本人自身がこれと思う選択に心を決めるまで、ゆったりと支えて待てる大人達がとても理想的に見えた。三浦友和も江口洋介も、子供を成人させている。自分と家族を支えて育てる責任の過程を経験してきた俳優にしか出せない、若者を見守る目線がある。
そして、横浜流星の横顔が惜しげなく写る。
かっこ良いだけではない、隠しきれない真面目さ。筋の通った、でも素直で優しく繊細な感性が、佇まいや所作に表れている。持ち合わせる雰囲気が、ストイックに突き詰める何かや、日本の伝統的な要素とぴたりと相性が良い。空手にボクシングに華道に料理に色々見てきたがどれもしっかりと身になるまで習得していてすごい。
作中で霜介は自分の線をかける精神状態になってから、一気に作品を仕上げるのだが、それをできたのは生徒になって以降、真面目にひたすら練習を重ねて技術を身につけていたからだと思う。
家族と植えて剪定した椿の思い出を通して、水墨画が心に響いてその道が開けたり、筆使いにも現れる礼儀正しさや優しさが千瑛の心を開いたり、亡くした家族による導きを感じずにいられなかった。
霜介の友達も「何年も止まっている霜介を家族が喜ぶと思うか」と鼓舞してくれて、周り全員が霜介の心の回復と霜介が自分だけの人生を謳歌するよう見守ってくれている。きっと家族も。
清原伽耶もまた、凛とした芯の強さが際立つ。聡明で、素直じゃない役ばかりだが、笑顔で誤魔化す必要のない演技力や他の子とは混ざらない別格感のある存在感がある。
作中でもそのような場面があるが、日本の誇る水墨画で作品を撮る以上、いい加減な恥ずかしい仕上がりで撮るわけにいかず、難しい部分はプロの手捌きを使うにせよ、ある程度のレベルまでは本人が仕上げて挑むだろうと信頼された俳優にしかキャスティングが来ないような気がする。
その意味で、ひとつひとつ積み重ねてきた横浜流星に信頼を寄せられてのキャスティングだったのだろうなと思うと嬉しいし、1年以上特訓し立派にこなした横浜流星はやはりすごいなと感じる。
掛け軸の水墨画を何度見ても、滲んだところと濃いところがあるなとは思うが画法が長年わからずにいた。
千瑛の説明で、筆の中に3層の色の濃さを作ってコントロールすると聞いて初めて、言われてみれば竹の節は確かにわかりやすいと気付いた。にしても、いきいきと躍動感のある、描き入れた瞳に魂を吹き込まれたようなタカも、のびのびと力強い龍も、技術もとんでもないのだがそれを通り越してダイナミックで心が魅了される衝撃があった。
雪舟の時代とはまた違う水墨画の世界が、見ていてとても楽しかった。
何とも清々しい
GACKT
泣ける!
いきなり素人大学生が超有名な絵師の生徒になってしまうトントン拍子なスタートでしたが、椿の花への想いがあとから分かって泣けました
清原かやちゃんがとても、かっこいいですね
スンッとした佇まいや雰囲気がすごく合ってました
【この映画が好きな人におすすめ(かも)】
3月のライオン
感受性豊かな男青山
仮に水墨画が出てこなかったとしてもいい内容の作品だったろうと思う。
うまく表現できないが、簡潔に言うならば「自分と向き合う」ことについてのドラマだ。
横浜流星演じる主人公青山と清原果耶演じる千瑛は互いに、周りの大人に、そして水墨画を通して成長する。
見えていなかったものが見え始め、世界に自分を溶け込ませる。世界から疎外された自分ではなく、自分で自分を受け入れたとき、澄んだ心で見ることができるようになる。
自分の心のフィルターを通すことで自分を含んだ世界に変わるのだ。
そして彼らの心の変化は水墨画を通して物語となる。水墨画だけではない映像によって心境変化、彼らの成長が描かれているところも素晴らしい。
物語終盤、青山と千瑛が青山の家があった場所を訪れたあと、穏やかな小川の流れや飛び立つ鳥は青山の心の映像だ。
冒頭に湖山先生が描いた鳥の水墨画は木に止まる鷹だった。湖山先生が青山に執着していたことを考えると、あの鷹は青山だ。
飛んでいなかった鳥が飛んでいる。家族を押し流した濁流は穏やかなせせらぎに。青山の心がどう変わったのかをこれだけで表すのはいい。
そして、ラストの青山の水墨画は本当に素晴らしい。
青山が見る夢のシーン。過去の家の中にいる自分。窓の外を眺める自分。窓の外には椿が。
この夢こそが青山の心だ。心のフィルターを通すとは、ここを通らなければならない。
青山の水墨画に描かれたのは椿。夢の中でずっと見ていた椿。描かれた椿は光が差し込んで、ガラス窓を通して見たような椿だった。
夢の中でずっと見ていた椿をそのまま描いたのだ。
自分の心を通した線が活きた線となり、その線は、タイトルにもなっているように、翻って自分を構成する。
心に蓋をして、偽って、見ぬふりをして、これで生きているといえるだろうか。
映画は娯楽であり芸術だ。映画ファンとしては、芸術に対するエモーションは重要である。心を殺さないことの大切さを描出されたら評価せざるを得ない。
涙を流す青山くんの場面から物語が始まるが、彼の中に特別な想いがあったにしても絵を見て泣ける感受性には感心する。
あの感性で映画を観たらもっと面白いだろうなと羨ましく感じた。そりゃあ湖山先生も弟子にしようとするよね。
白と黒の世界
余計な色が一切ない映像だった
淡白でいて、繊細でいて、されど奥深い
1枚のキャンバスに白と黒で描かれているだけなのにキャンバス以上に世界が続いていくように、見る人によって色が付け足されるように、そんな水墨画のような世界観が描かれていた
人によって描き方が違うことが人生観の違いであったりして本当にいい映画と思うんだけど、大臣要素はちょっと浮いてたかな?あとは「家族」というワードへのこだわりがもう少し欲しかったかも。
俺にも描けたら良いのになぁ
江口洋介が持ってったーー!
三浦友和は、いい人なのだと思うが
いい役者かと言うと うーん、、、と思う私である。
百恵ちゃんのご主人、それがすごく彼のクオリティを上げちゃってるというか、、失礼な言い方で申し訳ないです。
息子(次男)の方が 最近 余程良い。
役者って 努力とか 善良とか
そういうんじゃないんだろうなあ。
この大先生の役だってね、なんだろう、、声が若過ぎるというか 、、違和感が拭えない。
白髪頭が取って付けたようにしか見えないし、国宝級の人物としての重みを感じ取る事が出来なかった。
横浜流星
彼も ちょっと苦手です。
(竜星涼も苦手)
「私たちはどうかしてる」という泥臭いドラマに出てた事が原因なのか。
相手役の浜辺美波は「私の娘は彼氏がいない」で私の中では回復し その後 朝ドラ らんまん で好きな女優さんになってしまった。(神木隆之介も大幅にランクアップしてしまう)
こうやって考えると、どういう作品に出るかどう解釈して演技するかってすごく重要なのだなあと思う。
これは小説なのか漫画なのかの原作があるらしい。
とても評判の良い原作のようだが、映像化の評判もいいらしい。
それでも 私には 映像化したこの空気感が あまりつかめずに見終わった。
『鳥獣戯画』と『信貴山縁起絵巻』を生まれて初めて見た。
最初で最後になるが、小学校5年の頃、僕も『三墨法』で竹を描いて年賀状を送ったことがある。
水墨画や書道には興味はあったが、小学校3年生から3年間書道教室に通って、結局、初段にもなれずに止めてしまった。才能がないのは致命的。同期の女の子は有名な書家になった。消されるから、名前は書けない。
さて、本日は水墨画ではないが、東博へ『大和絵』を見に行った。『鳥獣戯画』と『信貴山縁起絵巻』を生まれて初めて見た。
さてさて、
来年正月は1月2日からまた『長谷川等伯』画伯の『松林図屏風』が展示される。毎年見ていて、もう何度も見たが、東博で見る回数は後、七回。東博へ行く事が僕の初詣。
この映画の画伯は『男はつらいよ 夕焼け小焼け』の『宇野重吉さん』をリスペクトしている。フーテンの寅さんを、画伯が気にいられた理由が分からなかった様に、この映画の主人公が、どういった理由で、この映画の画伯に気に入られたかそれが最後まで分からなかった。
追記
書家は主に紙を扱う商売だから、禁煙すべきだと思うが。
線の先にあった
ここ数年で1番好きな邦画
全277件中、21~40件目を表示