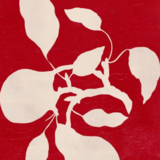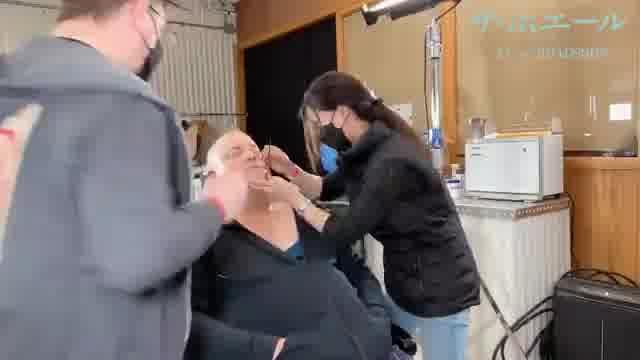ザ・ホエールのレビュー・感想・評価
全258件中、1~20件目を表示
傷つけ合い支え合う人間たちを単純化せず描く
この作品には、生きづらさや喪失感を抱える登場人物しかいない。彼らの背景は物語が進むにつれ明らかになるが、理解し共感できる面と過ちに思える面とが背中合わせになっていることが多く、どうにも切なくなる。
主人公のチャーリーは、かつて男性の恋人アランのもとへ行くため妻子を捨てた。そのアランは、父やカルトの教会から理不尽な仕打ちを受けたことが原因で亡くなった。
彼の体を覆い尽くした脂肪は、積み重なった苦悩が具現化したものだ。大切な伴侶を失った失意と、妻子を置き去りにしたことへの自責の念。彼はその苦悩に今や命を奪われつつある。体調悪化に苦しみながらも病院に行かず、娘に残す資産を貯める姿は、償いのために命を差し出しているかのようだ。
因果応報と言って突き放した目で見るのは簡単だ。だが、知性と感受性を持ち合わせた彼が苦悩と後悔で凝り固まった巨体に命を蝕まれつつある姿を見ていると、彼の思いがこちらに否応なく流れ込んできて、とても苦しい気持ちになった。
チャーリーの肉体の表現がいかに大切かが分かる。アロノフスキー監督は当初実際に肥満体の俳優を使うことも考えたようだが、体力的に長時間の撮影に耐えられない恐れがある等の事情により、特殊メイクを選択した。OAC(肥満の人とその家族を支える団体)と密な話し合いをしながら撮影を進めたそうだ。
ブレンダン・フレイザーの少し困ったようなベビーフェイスが、チャーリーという人物にぴったりとはまって、ただ陰鬱なだけではない彼の魅力を作り出している。
チャーリーを献身的に介護するリズは、アランの妹だ。親友とはいえ何故彼女がここまで彼に深く関わるのか、だんだんとその理由が見えてくる。親もカルト宗派ニューライフの関係者だったリズにとってチャーリーは、兄を亡くした悲しみを共有出来る唯一の相手だった。リズはチャーリーといることで、アランが生きていた証を感じられたのだろう。ある意味チャーリーは、その存在によってリズを救っていたとも言える。
ニューライフの宣教師トーマスは、訪問による布教を禁じられ、誰かを救っている実感を求めてチャーリーの家にやってきた。その実感により、トーマス自身が救われるからだ。あなたを救いたいと宣言してはいるが、実態はエゴでしかない。結果的に彼はチャーリーやリズを救うどころか、彼らの心の傷をえぐることになった。
一方エリーは、終始周囲に怒りをぶつけ続けるが、結果としてトーマスが地元に戻るきっかけを作り、チャーリーの最期に立ち会って彼の望みを叶えた。彼女の言動は時に鋭利な刃物のようだが、本音のみでおためごかしがない。文章作法においても率直な表現を好むチャーリーの目に、それは彼女の美徳として映った。母のメアリーが悪魔だと吐き捨てた彼女を、傷つけられても受け止め続けることで、チャーリーもまたエリーを救った。
トーマスとエリーの姿を見ながら、人が何によって救われるかを第三者が理解することは時に難しく、救おうとする意思は少しひとりよがりになれば簡単に傲慢さに変わるものなのだと思った。カルトはその傲慢さの象徴で、その対極にあるのがチャーリーにとってのエリーなのだろう。
彼らに元妻のメアリーを加えた、不完全で不器用な人間たち5人の感情のアンサンブルが、ラストぎりぎりまで静かに加速してゆく。ブレンダン・フレイザーをはじめとした俳優陣の、真に迫る演技が素晴らしい。
人の在り方を単純化も美化もせず、複雑で多面的なまま描き出す脚本が秀逸。チャーリーが死の間際に娘と心を通じ合うラストなどは、凡百の映画なら平気でありきたりなお涙頂戴描写をして終わらせるところだが(お約束通りだからよい、という場合もあるにはあるが)、本作は決してその轍を踏まない。
あふれる光の中で、エリーの表情が初めて柔らかくなる。その一瞬のうちに、それまでの反抗的な態度の奥にあった父に捨てられた悲しみ、その悲しみの根元にずっとあった父への思慕までもがはっきりと見える。チャーリーにもそれは確かに伝わった。
本作のオリジナルは舞台劇だそうだが、映画ならではのこのラストが舞台ではどう表現されているのか興味が湧いた。
スタンダードサイズの映像世界に凝縮されしもの
スクリーン上のスタンダードサイズは、さながら窮屈なアパートのようだ。我々は、この場所からいっさい外へ出ることなく、ソファに座り込んだら立ち上がれなくなる主人公の生活に触れ、死を意識した中での心のうごめきをも覗きこむ。ブレンダン・フレイザーが体現するこの人物は、自らを否定するかのようにオンライン講座でカメラをオフにし、ゾッとするほど暴食を繰り返し、命の危険を指摘されても治療を拒否する始末。ここに映し出されるのは人生の集約図であり、様々な過去や感情の重荷によってすっかり身動きが取れなくなった状況を、メンタルとフィジカルが痛切に相まった形で凝縮させている。ただし、たとえ狭苦しくとも本作にはサッと風を循環させる巧さがある。展開ごとに印象を添える登場人物たち、モビー・ディック、そして主人公が唯一望む娘との絆の回復。全てがラストの光に向けて進んでいく、空間と肉体と精神の一点透視図法のような作品である。
ホン・チャウの名前を覚えておこうと思った
270キロ以上の巨体で家から出られなくなった男は、大学のオンライン授業で顔を見せずに講義を行う。顔を見せないオンラインの通信は、つながっていないようでつながっている、か細い人との関係性を象徴しているようだ。余命いくばくもない彼の元には、宗教の勧誘にきた若い男性と、親友の看護師の女性、そして生き別れになっていた娘。小さなアパートの一室で繰り広げられる会話劇は心の傷を深くえぐってくる。生きるに価する人生を送りたいと誰だって思う。ままならない人生の中で苦しんできた男は、最後に思いがけない救いを他者にもたらし、自らも救われる。
この映画、主演のブレンダン・フレイザーは当然素晴らしいのだけど、看護師リズ役のホン・チャウがすごい。彼女のパフォーマンスはオスカーに値するものだったと思う。
生きているといろんな失敗もして、誰かを傷つけてしまうことはあるけれど、重たいしがらみを引きずっていても悔いのない人生はおくれると強いエールをおくる傑作だった。
ブレンダン・フレイザーの声の良さ。
ブレンダン・フレイザーが、人を惹きつけると同時に安心もさせてくれる、素晴らしい声の持ち主であることを忘れていた。全員を特殊メイクのファットスーツで覆われていても、あの声だけで、この主人公がただ憐れむべき存在ではなく、魅力も知性も備えた人物であることが伝わってくる。大げさに聞こえるかも知れないが、フレイザーが発する主人公の声を聞いた瞬間から、このキャラクターを本質的に信用していい気になった。
正直、たまに脇役を演じている姿を見かけるだけだった近年は、ブレンダン・フレイザーが真価を発揮できていたとは思えなかった。しかし本作では、堂々たる主演スターとして演技力も天賦の才能も存分に発揮している。しかも、相棒役であるホン・チャウの演技も素晴らしくで、社会とは切り離されたところで繋がっている二人の絆が感じられる。
監督の演出力を過小評価するつもりではないが、これはダーレン・アロノフスキーの、というよりも、ブレンダン・フレイザーとホン・チャウの映画だ。そして俳優が屋台骨を支える映画も、作家主義で評価される作品と同じ比重で評価されてしかるべきだと改めて思った。
身を持て余した鯨の決意。
なんて凄まじい映画なのだろう。こんな映画が作れるダーレン・アロノフスキーは、健常者を描いたことがない監督かも知れない。欠落を補うために過剰な無理を強いられる、または強いる自我を持つ存在を主人公に据えて、限界の境界線を描き続けている。
『サ・ホエール』の主人公は、同性の恋人を失った反動で過食症となり太り続けた身体を持て余した男。身を起こすだけでも一苦労、歩行補助器がなければ室内の移動も困難で、テレビのリモコンを手にするためには捕獲棒が必要だ。
タイトルが示す通り巨大な白色鯨への復讐に取り憑かれた片足の船長を描いた小説「白鯨」が重要なモチーフになっている。主人公の日常を見つめていると、自分の住処から出られなくなった哀しき“生きもの”を描いた井伏鱒二の小説「山椒魚」が思い浮かんだ。食べ過ぎたために外に出たいが身動きがとれない。究極のジレンマの中で禅問答のような自問自答が続く。
男は身を持て余す極度の肥満体型だが、彼の思考には一切のブレがない。大学の通信講座でロジカルに語りかけるその声は透明感を保ち、文学表現のインストラクターとして仕事をしている。つまり頭脳明晰なのだ。
「山椒魚」と異なるのは、彼には定期的に訪れて面倒を見てくれる義妹がおり、外界とコンタクトする術がある。稼ぎもあるから特大のピザを2枚注文することもできる。
戯曲が描いた閉塞感を伝えるためにスタンダードを採用したダーレン・アロノフスキー監督は、じっと座り続け、決して清潔とはいえない汗かき男の体臭が染み込んだ壁、ジャンクフードが食い散らかされた部屋の臭気が滲み出すかのような暗い映像で、彼の生態を映し出していく。
冒頭、ある行為に身悶えした男が突然の発作に襲われる。なんとか心を穏やかにするために彼は「白鯨」を評したエッセイを読み始める。だがそれも叶わなくなる。その時、新興宗教の勧誘員がアパートの扉をノックする。「これを読んでくれ今すぐに」と床に落ちた紙に視線を送る。初対面の青年が「鯨を描く場面は退屈だ…」と読み上げる。
その後、青年の朗読によって落ち着きを取り戻した彼のアパートに義妹がやって来る。不審な青年を追い払った彼女は、ルーティンとなっている血圧チェックと呼吸器系の診察を始める。
尋常ではない血圧と肥満した身体に宿った病のために彼の人生はあと僅かだが、断固として入院を拒み続ける。自分が生きた証を示すために何が出来るのか。考えた末に別れて暮らすようになって娘と会うことを決める。
身を持て余した鯨の決意。それは生きることの限界への挑戦である。部屋に引きこもった鯨が起こした行動は、やがて小さな波紋となって広がり、感情が結びついていく物語へと昇華されていく。閉塞感と暗い映像の先には、魂の咆哮が呼ぶ奇跡の瞬間が待つ。映画だからこそ描ける奇跡の描写が胸に突き刺さる。
再起の物語と俳優キャリアの復活を重ねる、ハリウッド得意技の最新事例
かつて妻と娘を捨て同性の恋人との人生を選ぶも、恋人と死別した喪失感から過食症と引きこもりになったチャーリー。肥満体による負担から心不全が悪化し、余命わずかだと悟った彼は、娘との絆を取り戻そうとする。
ファットスーツと特殊メイクで体重272キロのチャーリーをリアルに体現しただけでなく、本編の9割がた居間のソファに座ったままという制約の中、表情と台詞とわずかな体の動きだけで観客の興味を持続させたブレンダン・フレイザーが、今年のアカデミー賞で主演男優賞を受賞。オスカー受賞の前には、ヴェネツィア国際映画祭での本作「ザ・ホエール」のプレミア上映を伝える報道の中で、それまでのフレイザーが度重なる手術、セクハラ被害、離婚を経験してうつ病になり、俳優として低迷していたことを知った映画ファンも多いはず。そんなフレイザーの困難な時期を思いつつ観るなら、自暴自棄で世捨て人のようになっていたチャーリーが一念発起し、鯨のような巨躯を奮い立たせて娘との距離を縮めようとする姿に涙を禁じ得ない。
本作は舞台劇の映画化だが、ダーレン・アロノフスキー監督は過去にも、心臓に難のある中年プロレスラーが人生の再起を賭けて大一番の試合に臨む「レスラー」で、長年低迷していたミッキー・ロークを見事復活させた。アロノフスキー監督のこれら2作に限らず、過去の栄光から転落を経て再起しようと奮闘するキャラクターに、実際にキャリアが低迷していたかつてのスターを起用してカムバックさせるのはハリウッドの得意技。ヒーロー映画で一世を風靡した俳優が再起をかけてブロードウェイの舞台に挑む「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」で主演したマイケル・キートンや、17歳にして大スターになったジュディ・ガーランドが40代の借金生活から起死回生を図る「ジュディ 虹の彼方に」で主演したレニー・ゼルウィガーなどが好例だ。最近の公開作では、ニコラス・ケイジがどん底の俳優ニック・ケイジという自虐的なキャラクターを演じた「マッシブ・タレント」にも、そうした傾向が認められよう。
特殊メイクを施しても尚、輝く個性
最愛の恋人を亡くした喪失感が過食症を招き、272キロにまで膨張した巨体をほぼ一日中、カウチから動かそうとしない大学教授。この設定はかつてブレンダン・フレイザーが『ゴッド・アンド・モンスター』(00)で演じた役柄の逆バージョンだ。あの時、彼が演じる庭師はイアン・マッケラン扮する引退した映画監督の前に現れて、枯渇したクリエイティビティを刺激したのだった。
翻って、この『ザ・ホエール』の主人公、チャーリーが住む家には身の回りの世話をする看護師や離婚した妻や疎遠だった娘やピザ配達人たちがやって来るが、みんなそれぞれに悩みを抱えていてチャーリーの心を癒してはくれない。むしろ、彼らはチャーリーに癒しを求めているようなのだ。
ここで、フレイザーが文字通りオスカー級の名演を披露する。分厚いファットスーツやメイクに囲われていながら、その瞳から隠しようのない優しさが零れ落ちて、劇中の訪問者と、観客までも温かく包み込むのだ。特殊メイクを施しても尚、俳優の個性が輝く好例だと思う。
ブレンダン・フレイザーの渾身の演技に圧倒される!
重度の肥満症となった主人公が部屋のソファにほとんど座っているような異色の室内劇の映画化に挑戦し、緊迫感みなぎるヒューマンドラマに仕上げたアロノフスキー監督の鬼才ぶりに改めて感嘆します。愛するものと疎遠となり、死を意識するほど精神的に追い詰められた人間の心の軌跡を描かせたらこの監督の右に出る者はいないのではないでしょうか。観客は主人公の部屋の中にいるような錯覚に陥るほど息づかいを感じ、登場人物たちの内面世界に連れて行かれます。
そして、毎日メイキャップに4時間を費やし、45キロのファットスーツを着用して40日間の撮影に挑んだフレイザーの渾身の演技に圧倒されます。観客は冒頭からその肥満体型に度肝を抜かれるでしょうが、いつの間にかフレイザー演じるチャーリーの深い悲しみと愛、その人間性に心を震わせられるに違いありません。第95回アカデミー賞助演女優賞にノミネートされたホン・チャウが演じる、チャーリーを支える看護師リズが、ふざけて体をくすぐった時に見せるチャーリーの愛嬌のある笑顔が、この作品の雰囲気を一変させるのです。
わがままと正直に魅入られた人々
あらすじ。自己中心的で自分の正直さとわがままを貫き通すお話。舞台は現代アメリカの片田舎にあるアパートメントの一室が舞台。そこに超肥満体型の男にまつわる過去の話と『白鯨』を組み合わせた登場人物の魂の救済に重点を置く。超肥満体男の人生最後の最高な一週間の物語。
印象的な台詞は『disgust me』私はおぞましいか?胸がむかつくか?と遭う人に同意を求める場面。ダブルミーニングで全ての台詞が比喩的で掛けられていて面白い。
また自分の内面を文章に表す詩的な世界を表現する為に対比的な見た目を重要視する所が悲しくもあり胸に詰まる。
印象的な立場は、最初から幼い娘より教え子を選んでしまった後悔と苦悩しながら納得したくて生きている娘に救いを求める場面。
最初の心臓発作から娘の『白鯨』感想文を読んでいる事が終始物語の中心である事が再度見ているとよくわかる。。アメリカだけにキリスト教圏の世界に対する罪と罰の姿勢がよく分かる構図になる全体的に暗い撮り方が緊張感を増していて良かった。
印象的な場面は、やはり最初の登場から最後の最後に救われる偽宣教師トーマスとの関係が印象的だった。主題が罪と罰であり、絶望と贖罪の物語であるだけにみている人に伝わりやすい表現だなと感じた。
超肥満体型の最後の一週間ならではの死にそうな名演技は目を見張るものがある。
また最愛の人を亡くしてしまった絶望感から自虐的な過食へと発展していく過程が凄まじい。。。結局人間は主観的にしか生きられないのかもしれないという疑問を投げかけられた。
そして最後は天国に行きましたとも取れる表現がキリスト教的でハッピーエンに満足できるが安易な終わりに現代に投げかけられる闇を感じ取れる苦しくも感じた温かい映画。
食べることの意味
人生を見つめ直したくなる、心に響く言葉の数々。
多くの人が救われる言葉があり、人生について深く考えさせられる作品です。
主人公のチャーリーは、過去の喪失と罪悪感から暴飲暴食に走り、巨漢となって自力では身動きが取れない状態にあります。
そんな彼の“最期の5日間”を、ほとんど自宅の中だけで描くという非常に閉鎖的な構成の映画です。
主演の演技は圧巻で、巨体をリアルに再現した撮影方法が気になり、思わず調べてしまうほどでした。
序盤ではその生活の過酷さや絶望感に思わず息を飲みますが、展開が多少ゆっくりのため、飽きる方もいるかもしれません。しかし物語が進むにつれ、彼が歩んできた人生や心の内が少しずつ紐解かれていきます。
彼が最期の5日間で果たそうとしたのは、生き別れた娘との絆を取り戻すことでした。
彼女は反抗的で、いわゆる“グレた少女”として登場しますが、その奥には人を思いやる優しさや、救われたいという願いが見え隠れします。
「正直であることの大切さ」を何度も訴えるチャーリー自身も、きっと人生でずっと“正直になりたかった人”なのだと感じました。
そして、彼の放つ「どんな人であれ、誰かを気にせずにはいられない」という言葉が、強く胸に残ります。
自らの死を悟ったとき、私たちは残された時間で何を語り、どう過ごすのか。
家族愛、友情、そして人生そのもの――あらゆる角度から深く考えさせられる映画でした。
なぜか心惹かれる
チャーリーの部屋の中だけで完結するワンシチュエーション作品。
登場人物も少なく展開も地味なのになぜか引き込まれる不思議な作品でした。
なかなか解釈も難しく、見終わった後もこの作品は何だったんだろうと釈然とせず、でも心惹かれてすぐに再視聴。
うまく言葉にできませんが、「人生」を濃縮したような作品だと感じました。
チャーリーはアランとの恋で自分の人生を使い果たしてしまったのかなと思いました。
きっとチャーリーの中はもう空っぽで、偶然生きながらえたその時間で過去への贖罪と死後の希望を見出したかったのかなと。
エリーも無償の愛を求めていて、憎いけど大好きな父親を赦せたことで、きっと素敵な未来につながっていくのだろうと希望を感じるラストでした。
リズはどうなのかな、、、彼女の中にも何か希望が生まれることを祈っています。
なんとも…
タイトルなし(ネタバレ)
同性愛者の主人公チャーリー
家族を犠牲にしてまでも愛した男性アランの死によって極度の肥満になり、死期を迎える月曜日から金曜日までの5日間を描いた物語。(多分五日間)
チャーリーはエッセイストであり、オンライン教師である。
エッセイでは、本当の自分、内なる自分の心を写すことが美徳であると教える。それは、邪悪でもいいのだ。本来の心を写す事、ただそれが美しいのだと。
彼が心から美しいと思うエッセイがある。
“白鯨”。人間が鯨を殺すことを計画する物語。白鯨には、感情はない。だから全ては無駄だ。と、8歳の娘が描いたエッセイだ。このエッセイは彼の最後の生きる力となっている。娘であり、自分の体の一部のような彼女を愛し続ける。極度の反抗期と皮肉屋な彼女を、君は完璧だと言い続ける。娘と父親には同じ魂が半分づつ宿っているように感じた。8歳の時に父親に去られ、父親を大っ嫌いなようだが、どうしても離れられないもどかしさ。怒りをぶつけるために父親に会いに来ているようだが、彼女の表情や言葉と態度、全てはチャーリーとの時間を共にしたいというエリーが心底認めたくないであろう父親への愛を表していた。(素晴らしい女優さんだったー…)
映画全体で、緊迫感を促す音楽や画角表情など、見ているこちら側まで伝わる”狂気”の表現が秀逸であったと思う。
おぞましいか、という言葉が何度か出るが、映画全体におぞましさと狂気が在る。白鯨のように大きな体が動く度の悍ましさ、音と表現力。序盤から迫力で圧巻された。
ピザ屋のダン。声だけで彼と関わる。いつも心配してくれ、名前まで伝え合い、チャーリーの日々の心の支えとなり始めたところで、彼の姿を見たダンは嫌悪感で去っていく。人への希望と失望を一気に浴びたチャーリーは狂ったように食べ、吐く。どん底の時、宣教師の若者が、エリーに助けられたと彼の前に現れる。エリーが人を思いやる気持ちがあるとわかった彼は、また少し楽になるのだ。
宣教師の彼は、自分の過去に後ろめたいことがありながらも、どうしていいか分からず宣教師活動をしている。ただ、エリーに心を許した彼が言った本当の言葉を、彼の家族が聞き、家族のもとへと帰ることができたのだ。エリーの行動が彼を救う結果となる。彼の真実の言葉が、彼を救えると感覚で理解し行動したエリー。真実が美徳だと伝える父チェーリーとエリーは、遺伝子がつながった親子であり、魂を分け合ったソウルメイトなのだと心打たれた。
エリーは、彼自身が生きた証であり、自分の人生の最高の作品だと信じている。病院にも決して行かず、生き延びることを認めない彼だったが、死ぬ間際、何度も読み返したあのエッセイをエリー本人の言葉で聴き、死ぬ。彼は最期、自分の人生の全てを認めることができたのだろうか。エリーが、彼女らしく美しいまま生きていけると実感し天へ登ることができただろうか…。そうであると信じたい。
矛盾する感情が詰め込まれた箱
繊細で不器用で、それでいて大胆な人々によるドラマ。誰もがもどかしい中で行われるやりとりは不思議な面白さがある。
繊細なのに臆病にならず思いきった行動に出てしまうところはアメリカ人的なのか。ブレンダン・フレイザー演じる主人公チャーリーは引きこもりのような状態ではあるが、どちらかと言うと大胆な行動の結果そうなってしまったわけで、そこにネガティブさはない。
ブレンダン・フレイザーがアカデミー主演男優賞を受賞したので観たいとは思いつつも、この物語がどういったものなのか想像しにくく不安だった。
主人公は娘との関係を取り戻したがっているとあらすじにはあったが、300キロ近い巨体になってしまった男がただ懺悔するだけだったら共感できそうもなかったから。
しかし実際に観てみると、それぞれが抱える苦しみが見えて、苦しみを克服せんがため更に泥沼に嵌まるような物語に引き込まれた。
物語の核をなすように登場するのはメルヴィルの「白鯨」。そしてエッセイ。
チャーリーは自身が鯨であり、鯨を倒したい船長でもある。つまり自分で自分を滅したい、罰したいのだ。
それは、恋のために娘と妻を捨てた過去と、アランを失ってしまったことへの自責。全てが自分の過ちだったかのように自らを罰する。
一方で、エッセイに対して自身の気持ちを語れと彼は言う。
素直になってぶつかっていけ、思うままに進めということだ。
チャーリーは心のままに生きた結果、今の後悔があるはずなのに、それが良いと言っている。
この、相反する感情や状況が面白いし、それはチャーリーだけではなく幾人かの登場人物にも当てはまる。
例えばリズは、チャーリーに対して太るから食べるなと言いつつ、高カロリーそうなサンドイッチを手作りし与える矛盾。それはリズがチャーリーの世話をすることとチャーリーが食べることの根幹がアランへの愛情からくるという同一のものだと理解しているからだが、言っていることとやっていることのチグハグさもまたチャーリーと同一だ。
物語全体で、行動と結果がうまく噛み合わないもどかしさ、可笑しみ、そういったものが凝縮された作品で、実に面白かった。
傷心から270kgは凄い💦
ブレンダン・フレイザーはハムナプトラでの
勇姿以来、久々に見ましたが、本作での
迫真の演技は素晴らしかったです👏
アカデミー賞 主演男優賞受賞もうなずけます。
.
とはいえ、最近、涙腺が脆弱化していますが、
本作では「うる」っと程度です。
(嗚咽している人も結構いました)
個人的に、A24作品との相性が良くないので、
少し警戒もしましたが、その辺はいらない心配だった半面
良くも悪くも「普通」な作品だったかのように感じます。
.
.
愛する人の「死」を受け入れられず
そのせいで人と距離を置き、
満たされない心を食事で補う。
わかる!ものすごくわかる!だけど!!
毎日特大ピザやブリトーじゃ飽きちゃう😩←
どうせなら、お肉も魚も甘いものも、和洋中伊仏…
美味しいものを色々食べて太りたいw←えw
.
.
色々と説明不足な部分があります。
アラン(亡くなった彼)の死についも触れられておらず
(おそらく自死)
またチャーリー自身のことも「いま」しかわからない。
なにかと観る者に委ねる感じですが
本作はLBGTQだけじゃなく宗教問題も絡んできます。
宗教は複雑すぎてわかりません。
そこは詳しい方におまかせします
ラスト、なぜふんわりファンタジー色を付けくわえたのか
あの演出はあまり好みではありませんでした🤣
3.37 映画としては豪華
映画としてのクオリティは高かったものの、若干期待しすぎたかもしれない。
また主人公のキャラクター性に共感ができなかったのもあるだろう。
全体を通してクジラがテーマとして流れており、戯曲的なストーリーラインも心地よく感じた。
ようやく観た
映画館で観る機会を失い、U-NEXTのマイリストに追加してからしばらく経ち、ようやく観終わった。
なんといってもチャーリーの外見に圧倒される。
本当にいるもんね…。
どこまでも娘に優しいチャーリー。
何を言われても娘を責めず、元妻に罵声を浴びせられても怒らない。
自業自得だから?
自分の生きた証を残そうとするチャーリーが切なかった。
シーンがほぼほぼ部屋の中なので息が詰まりそうであった。
海のシーンでホッとする。
トーマスが出てくるとちょっとホラー(笑)だが、娘が大麻を勧めて動画を撮って送って…ってちょっと意味がわからん。
あなたにも人を救う力があるんだよってこと?
あとピザの配達人ダン。
出てくるところを待ち構えて騒ぐ?
オンライン講座の受講生達も。
なんでみんな平気でパシャパシャ撮るんだろうか。
なんだかなぁ。
作った人が何を伝えたいのかがよくわからなくなってしまった。
全258件中、1~20件目を表示