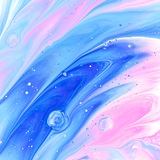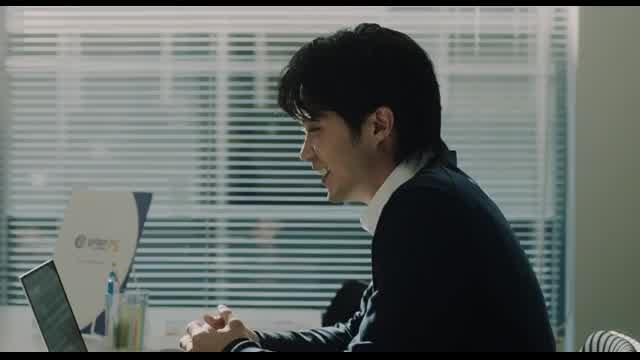PLAN 75のレビュー・感想・評価
全399件中、21~40件目を表示
老人問題ではなく貧困問題
生活資金もなく誰からも愛されていない老人は死んでください、という救いようのない映画。
役者さんたちはとても良い。
ワントーンでひたすら暗い。
全くリアリティがなくてイライラしながら観る。
そもそもストーリーの年代はいつなのか、未来な感じがしないし、情景がひと昔前の様に古い。
主人公、働き者の老人が若い頃2度結婚してどんな生活だったのか?多少の貯蓄もできなかったのか?年金制度がない世界なのか?それとも若い頃から少しも支払ってなかったのか?
住まいもなぜ急に無くなるのか?会社の寮だったとか?
老人になっていきなり貧困になることはないと思うから
若い頃の生活に多少問題があったのでは?としか思えない。
この世界でも贅沢せずとも暮らせるだけの資金がある老人と、それなりに家族とうまくやっている老人は「プラン75」なんてなんの関係もないのでしょうね。
なぜ火葬場に運ぼうとしてるの?
安楽死できなかったら帰されるの???
最後まで釈然としないの暗い映画でした。
無気力
75歳で安楽死を選択出来る。
ストーリーは淡々と進み、大きく感情を動かされる訳でもなく、メッセージ性も感じない。
方や、ヘルパーをしていた外国人の女性は、国に残した5才の娘の心臓が悪く、救う為に、懸命に遺体の遺品処理の仕事に、勤める。
それも淡々と。。
安楽死と言うワードは考えさせられるが、この映画は何を伝えようとしてるのか?
後で気付いたのは「無気力」と言うことか?
どこかの国は、安楽死を認めてる所があったのじゃなかったかな?
歳じゃなく、いろんな厳しい条件をクリアした人のみ?
映画の内容でなく、重度な介護が必要で、施設に入れない人とか?
国で決まった政策なら、いろんなパターンがあるだろうが、「無気力」を表現したかったのなら、納得かも。
孤独
65歳以上の高齢者人口の割合において日本は世界最高
そして、65歳以上の4人に1人が働いている日本
私は現在36歳ですが、一体いつまで働くのだろう、これだけ働いてその後はどれくらいゆっくり過ごせるのだろうとか、人生のほとんど働いて終わり?とか、いろいろ考えたりします
これは、75歳以上の方が選択死するというお話ですが、年齢に関係なく人はみんな孤独と戦っていると思います
結婚しているから子供がいるから孤独じゃないという訳でもなく、家族や友達がいてもふと孤独に押し潰されそうになることがあります
高齢社会により、社会保障費など現役世代に対して更なる負担が予想されること、実際いろんな問題がありますが、もしこの制度が成立したとして、周りの人が利用しようしたら絶対止めたい、でもその後自分には何ができるのか…
全然纏まりませんが、いろんなことを考えさせられる作品でした
切ない
母親が76才で、見ていて感情移入してしまって切なくなった😭
社会問題に切り込んでるのかな?とは思いつつ
面白く見られました👍
自分の老後や親の老後など、色々考えたり悩んでる人には見てほしい映画。
あと何年ぶりかに見た倍賞千恵子が年取ってた!!
でも名演!!素敵過ぎる!!
「善」か「悪」か
死を自ら選べるようになった世界で、その制度は果たして善か悪か。もちろん現実では実現していない制度だし、明らかに監督側がこの制度を悪として描いているのはわかるのだが…。
しかし、失業して新しい仕事も物件も決まらず、生活保護は受けたくないといった最後の矜持まで蔑まれ、途方に暮れていた倍賞千恵子に、少しの間ではあるが、彼女の精神的な支えとなったのは、plan75の職員、河合優実であった。
河合優実がいなければ、もしもplan75がなければ、倍賞千恵子はそれこそ彼女の友人のような死に方をしてしまう未来もあったのではと思う。
とはいえ、死を選択しなかった彼女が今後どうなるのか、考えただけで少し暗い気持ちになるのだが、この映画は、そこまでの問題提起をしていないようにも感じる。
淡々と進められていく死へのカウントダウン、どことなく冷たい彼女の友人たち、そして不動産職員。対して、主人公をはじめ、その周りの登場人物たちの人としての優しさ(思いやり?)が、なんとも言えない対比になっていて、生々しかった。
自分はもちろんこの制度に賛成というわけではないのだが、かといって完全悪とも言い切れないのが、今の日本の現状だと思う。
折角の問題提起がぼやけているような
75歳になったら誰でも理由なしに安楽死できる法が成立・施行されたという話。
安楽死法賛成!
PLAN75は、理由不問のところがとても良い。
理由を病気に限定すると、医療関係者のお気持ち次第になってしまい、自己決定権がないからだ。
ただ、年齢に関係無く施行する必要があるだろう。
国は高齢者に年金支給や生活保護給付をしたくないがために法制化するわけだが、映画でも、10万円の支給やら豪華宿泊体験やら、手を挙げた者が心変わりしないよう担当者を配置するなど、どんどん75歳以上の者が自主的に死んでもらうための制度の充実に余念がない。
こうなると、75歳以上なら苦しまずに楽に死ねる権利があるのに、その権利のない若者から搾取してまでして年金や生活保護を貰って生きたいのか?との空気感、同調圧力が出てきて、やがては忖度死せざる得なくなるだろう。
国としては期待する流れなわけだが、これでは「長生きは罪」なディストピアでしかない。
ただ、主人公(倍賞千恵子の役)には、感情移入出来なかった。
バイトがなくなったら即家賃も払えないというのは、その年齢でどういうライフプランなのか。
贅沢している様子にも見えなかったが、年金2000万円問題ではないが、身体が動かなくなった時用に備えてすらもいなかったのか?誰かに騙され、資産を失った設定なのか?それとも、年金支給が急にゼロになった世界なのか?
また、全然死にたくないのに手を挙げて、結局、服薬を中止して逃げ出してしまったけれど、家もなく、この先どうするつもりなのだろうかとも思った。
夕陽なんか眺めている場合じゃないんだが?
主人公の生き方とは関係なしに、映画の高齢者あるある話は、かなり頷けた。
1つは、仕事。
主人公はクビになったため、ハロワに出掛けるが、その年齢では求人なし。
ある程度の年齢以上になると、大抵の者は新しいことを覚えるのが苦手で、そのため未経験の仕事を得るのは難しい。
体力勝負の仕事は、自身がキツくて続けられない。
子守は送迎だけと言えど命を預かる仕事で、高齢者に任せることは敬遠されるだろう。
手に職のない者は、主人公のように詰んでしまうわけだ。
1つは、お喋り。
高齢者は話を聞いて貰いたがる傾向があるようだ。
傾聴ボランティアというのまであるくらい。
自分の話を聞いてもらうのはドーパミンが出るそうだから、科学的な話でもあるのか。
PLAN75の担当者と縋るように会話する主人公が、とても哀れだった。死の促進をする役の相手に、遠慮しながらも、たったの15分間の会話を愛おしむ。
担当者も立ち位置を理解しているにも関わらず、主人公に感情移入してしまって、こんな調子だといつ離職するかわからなそうだったが、メンタルがやられそうな大変な職場なのは間違いない。
ところで、映画では、PLAN75の担当者が、PLAN75での遺体はゴミと一緒に廃棄されることを知っており、叔父の死体を担いで火葬場まで持ち込もうとして、速度違反で捕まる場面があったが、あれは必要だったのか?
歌ではないが、私はここにはいないのだ。
私自身が死んだら、生ゴミと一緒に焼却して貰って全く構わない。気にもならない。いや、死んでるので、そもそも気すら存在していない。多分、叔父さんも同じ気持ちではないか。
といった遺体の処遇は遺族次第という話は、PLAN75の問題というより一般的な葬儀の話にもある。
高齢者の惨めな生き方を描きたかったのか?
高齢者あるある話がしたかったのか?
死者の尊厳についての話がしたかったのか?
安楽死施策を支える者たちのメンタル的負担を訴えたかったのか?
折角、PLAN75という法を出したんだから、"高齢者の安楽死"の問題点についてだけに絞って物語を紡いでくれたら、倍賞千恵子の演技力も素晴らしいのだし、もっと名作になったと思う。
それと、ここにこんな間はいらないだろうと思われる場面が、明らかに何カ所も意図的にあって、何なんだ?と思った。
希死念慮を持つ私からみたplan75
私は自殺未遂を何度も繰り返した経験がある。正直、今も死にたい気持ちは変わらない。外国で安楽死を認めている国があるが、それは身体的に問題がある人のみが認められており精神的な問題を抱える人には適用されない。
対して、この映画で出てくるplan75は75歳以上の人ならどんな人でも死を選ぶことの出来る制度だ。「死にたい」と思う人には良い制度だと思う。若者の負担になりたくない、これ以上生きていても明るい未来が見えない、身寄りがない、様々な理由がある。
全国で高齢者を憎む若者による高齢者を狙った事件が多発しようとも、その事件に支持者が現れようともその人達の意見はごく少数に思う。だが、plan75の制度が出来てからのこの映画に出てくる高齢者達は「私たち生きていていいのかな」と肩身の狭い思いをしている。肩身の狭い思いからこの制度を利用する人が必ず現れる。そうなれば国が、社会が人殺しをしているのと同じだ。
植松聖が起こした障害者を狙った大量殺人事件。あの事件にも賛否が生まれる時代。私も正直正解は分からない。辛い思いをするのは障害者本人でありその家族である。ならば障害を持って生まれそうな場合は子供を産むべきではないのでは無いか。この事件でもそのような考えが社会に生まれこの事件をきっかけに子供を持たない人もいるのだと思う。それが正解か不正解かは分からないが。
現在23歳の自分の祖父母は毎日のように自分も含め、子供や孫が家に訪れる。倍賞千恵子に比べれば祖父母は幸せなのかなと思ったりもしたが、本当にそうなのか。実際、祖父母が友人と出掛けるのは年に数回(友人を多く亡くしている)だし祖父は未だに現役で仕事を続けているが祖母はほぼ毎日家と近所のスーパーの往復だ。家に訪れて話や食事を共にするだけでなくボーリングやカラオケなどたまには祖父母と一緒に行ってみようかなと思えた。
「みんな歳とるのにね」というセリフがあった。その通りだ。みんな歳をとるのに新しい職が見つからない。新しい家が見つからない。雇う側にも家を貸す側にもしょうがない事情があるだけに難しい。
理論的に言えばplan75は正しい制度なのかもしれないが、人間的に見れば正しくない制度。
希死念慮を持つ私からすれば正直安楽死制度はあってもいいように思っていた。ただ、この映画を見た事でその制度が認められることで起こる様々な問題が見えてきた。
私は自分で死を選ぶことは決して悪手では無いと思っている。ただ、制度化してしまうとこの映画で出てきたような問題が起こるのなら、自殺する人はせめて他人に迷惑がかからないように死のう。
終活を考える
75歳以上の人は健康な人であっても、安楽死を選択できるという制度「PLAN75」。国も積極的に広報活動を行い、推奨しているという架空の社会を描いた話。
未来に希望が持てない毎日を送っている老人にとっては、利用したくなる気持ちも分からなくはない。
PLAN75に関わり、恩恵を受けている側のヒロムやコールセンタースタッフの瑶子、マリア。でも心のどこかでこの制度に疑問を抱いている。しかし、思ったところで社会は何も変わらない。最後にヒロムがおじさんのために行動を起こすシーンで、少し救われたような気持ちになった。
賠償千恵子がおばあさん役を若造りなど全くすることなく演じているのが印象的。美しくて上品で、80を超えていまだ主演をはることのできる人はなかなかいない。
年のせいか、こんな制度があってもいいかな、と思えてくる。
とてもリアルだった。
他の方のレビューには、「死を選べる制度」が日本に成立するリアリティがないとの感想もいくつも書かれていた。
その通りだ。こんな法案が、どういう経緯で誰が言い出して、世論の支持を得て、国会で成立してしまうのか。まったくイメージできないし、この映画を見ても分からなかった。
それでも、リアルだった。この映画で描かれている、法案「PLAN 75」が成立したあとの日本は、いまの日本と何も変わらない。昔ほどの勢いはないけれど、世の中は比較的穏健で、礼儀正しく、親切な人たちのたくさんいる場所だった。
年をとるにつれ、仲のよかった友だちも亡くなったりする。幸い自分はひどい病気もなく、働けている。パートアルバイトなら年齢制限なども特にないし、そこそこ求人もある。住むための物件もたくさんある。それでも、いちど仕事を失うと、採用してくれるところが見つかるまで時間がかかるようになった。年配者に肉体労働をさせる職場は、お年寄りにやさしくないイメージに見えてしまうのだね。確かに、お年寄りに部屋掃除させてる一流ホテルなんてないですよね。
もう少し安い部屋に引っ越そうと思う。不動産屋さんに部屋はたくさんあるようなのだけれど、なかなか決まらない。年寄りには、なるべく貸したくないのだね。ある日突然死なれたら、あとの借り手がみつかりにくくなる。それもわかる。
娘も孫たちも、お金持ちではないけれど元気にやっている。電話すれば声も聞けるし、いっしょに暮らせたらいいなと言えば、きっと迎えてくれる。でも私は一人で暮らせてるし、そんなことお願いするのは気が進まない。私はいまのところ大丈夫だ。
「PLAN75」という仕組み、批判している若い人たちもいるけれど、そんなに悪い制度ではないのでは?とふと思ったりする。もう十分働いたし、無理に働かなくても良いのではとも思う。楽しい日々もそれなりにあった。私といて楽しいと思ってくれる人もいなくなっちゃったし。最後に美味しいもの食べて、そのまま静かに眠れたらいいんじゃないかな。そのまま目が覚めなくても。社会保障も若い人たちの重荷になっているのですよね。
倍賞千恵子さん演じる主人公の心の動きは、とても自然で、とてもよく分かる。
あと10年ちょっとで、私もその年齢になる。「PLAN75」、やっぱり気になる。1年前にこの映画を観たときのメモを見ながら書いているけれど、感想は変わらない。その日まで、1年短くなっただけ。選ぶのは私だから。選ばないのも私だけれど。
長々とした年寄りの感想文を、最後まで読んでくれてありがとう。
これ、おもしろいの?
悲しい現実…
おばあさんが今後どうなってしまうのか気が気ではない
高齢になったら社会を支えて生きてきたご褒美に安らかに
ありえそうな未来
考えが変わる映画
「PLAN75?希望者のみなのね。だったら何も問題ないよね、賛成賛成」と思って映画を見ました。
もともと私は氷河期世代としての恨みつらみが強く、高齢者優遇政策に反対派です。
強制75なら問題ありだけど、希望者75なら、何が問題?ぐらいの気持ちでした。
そんな私が
見終わると「PLAN75には反対!」と、考えが変わりました。
このように自分の考えが視聴前後で変わる映画は初めてです。すごい映画です。
もともとこういう何の説明もなく、淡々とした話は苦手です。
それなのに!
「これはこういうことかあ~」という、「説明なくとも分かる」シーンが多くて、リアリティーがあって、怖い怖い!
主人公の孤独感、炊き出しの所PLAN75の案内、もらえる10万円、テレビニュースではPLAN65にするか議論開始、産業廃棄物処理場…
特に孤独感が怖くて。
これを見た人はきっと、結婚したり友人増やしたりしようって思うんじゃないでしょうか。
人付き合いが煩わしいと思ってる若い人に見てもらうと婚姻率が上がるのでは、少子化に効果あるのでは、とすら思います。
生きることと死ぬことについての内省の中で
正直、「PLAN75」を観たのはかなり前で、実を言うと未だに何を書こうか迷っている。
誰もが迎える可能性のある「一人で死ぬこと」について思うこともあれば、「一人で生きていくこと」について考えずにはいられない部分もある。
誰だっていずれは死ぬ。歳をとればとるほどその事実は確実に自分ごとになり、逃れられない未来の出来事に対し、自分なりに受け入れ、折り合いをつけながら、先に旅立っていった人たちの人生を噛みしめる。
大人になってから随分経ったからか、いつか自分が死ぬことについて、恐怖よりも忌避感よりも、諦念とも違う、もっと身近で当たり前のような、「風邪をひいたら熱が出る」、に近い感覚で「死」を感じるようになった。
それでもやはり、自らどこまで続くか分からない「生」を手放す気にはなれないと思う。良い死に方がしたい、それは「キレイな幕引き」のことではなく、「満足するまで生きたい」と同義だ。自分の肉体が限界を迎えていないのに、精神のエゴで自らに幕引きなどしたくない。
そういう意味で、もし現実にこの映画同様の法案が成立していたら、私はこう思うだろう。
「生き辛い時代になったな」と。
この映画では、初めて身近な存在の死を思う若者たちの姿も描く。若い頃私が感じたような、見知らぬ老いた人間の記号的な「死」ではない、自分が言葉を交わしたり、人柄に触れたり、その人の人生を垣間見たりした人の「現実に訪れようとする死」が眼前に迫ってくる、悲しさと淋しさと恐ろしさ。
高齢になって、たった一人で、つましい毎日を過ごすことは誰にでも訪れる可能性があるのに、自分も当事者なのだと感じられない。うまく想像できないから、今その状況の人々を数字や記号でしか捉えられない。それが形になって襲いかかってきたとき、どうしようもなく、ただ生きていてほしいと願わずにはいられない。
いつか見知らぬ誰かが消えるのではなく、今目の前に存在している人にもう二度と会えない、それが死なのだという衝撃が、「PLAN75」の若者たちにはある。
それはもしかしたら、現代の社会構造が近しい人を亡くす経験自体を少なくしていることの現れなのかもしれない。
見送る側と見送られる側、その両端から描かれる「生きること・死ぬこと」についての思いの中で、自分の死生観を見つめ直す。それが出来る映画はなかなか無い。
ディストピア
映画。と言えばわかりやすいが
大切な問題提供を行う映画。だと表現したら人はどう思うのだろうか?
死は国籍人種出自実績地位に関わらず等しく訪れる
イベントである。この死の捉え方が歪んだ時代に生きると
こう言う世界観に引き込まれるのだろうと思った。
つまりなにを言いたいかと言うと
死は決してネガティブで陰な世界に留まる出来事ではなく
ある人にとっては最高の機会。改変ポイントであると言うことでもあるのだが、その死すら遠のき、生のみが幸福とされる実世界に縛られて囚われる事態に、実世界の不幸と救われなさ。を感じずにはいられない◎
と言う、それこそがディストピアそのものである。と言う
事実に、現代実世界に生きる人のどれだけが気づいているのか?と言うことだろう。
僕は一度死に接して死にきれなかった部類の人間である。
それ故に、自然な死に憧れ恋焦がれる毎日を過ごしているのだ。
全399件中、21~40件目を表示