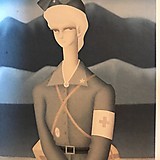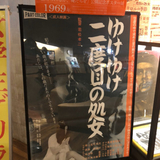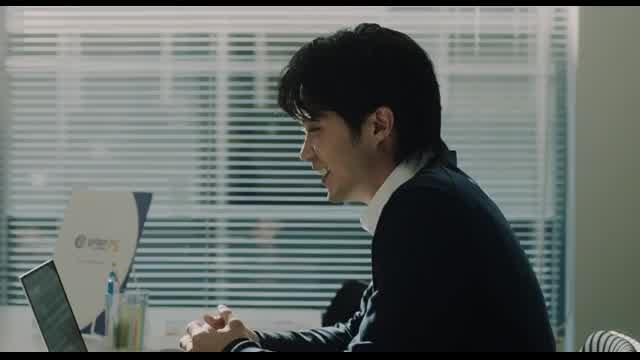PLAN 75のレビュー・感想・評価
全398件中、181~200件目を表示
決して楽しい映画ではないが望みはある
倍賞さんの手が印象的、誰にでも演れる役ではない。死んだおじさんを持ち出し火葬場へ、倍賞さんは逃げ出し、オペレーターの子は何かを決意し、やっぱり政策は違うという雰囲気に、俺も一人だったらどうしよう。奥さんを大事にしよう。
ありえない? ありうる、のかも。
カンヌ国際映画祭で新人監督賞の次点になった話題作。40代の女性である早川千絵監督の初めての長編映画。
75歳以上の高齢者に生死の選択を認めるプラン75という国の制度。このプランを選んだ人には使い道自由な10万円の給付金が支給されますー。
もちろんフィクションですが、現在の日本は“超高齢社会”であり、高齢「化」なんて甘いもんじゃない!おまけに少子化は進む一方。今、絶対見ておくべき作品だろうと鑑賞しました。
説明的な描写はほとんどなくて余白の多い演出。たとえばある人が亡くなるシーンでもその姿を近くからは撮影しない。引いた絵だけで語ってきます。
音楽もほぼ無しで淡々としているのに俳優の目、姿、声などから全てしっかりと伝わってきてまるでドキュメンタリーを見ているかのような感覚に。長編初メガフォンとは思えない監督の手腕に次回作への期待も高まります。
主人公のミチは78歳で一人暮らし。とてもきちんと丁寧に生活している人。そのミチを寅さんの妹さくらだった賠償千恵子さんが演じていて、あの可憐なさくらも今や深いシワがたくさん刻まれた高齢者なんだ、と。誰もが平等に歳をとっていくのだ、という現実を突きつけられます。
高齢を理由に解雇され、仕事が無くなると身寄りのない者は住むところも奪われる…
ずっしり。
何を感じるのか。何を考えるのか。
ラストシーンの意味も含めて、こちらにまっすぐ問いかけてくる作品です。
老後資金などございません。
さぁどうやって生きていきましょうかねぇ。
人間にとって大切なことは変わらないのです。
「河合優実さん出演作にハズレなし」は無事に更新となりました。
本作はプラン75というシステムがある社会で生きる人々・・・システムの利用を選択する人、勧める人、利用サポートする人、実施する人・・・その人達の命の終わりを自由に選択できる・・・つまり「形骸化した命の価値」への向き合い方を描いた作品でだと思います。
本作は「命の尊厳」をテーマにしたものではなく、75歳を過ぎた人にはどんどん死んでもらいましょうという国のお達しの中、踠く人々を通して変わってほしくない、失ってほしくないと願う「人間の心の形(あり方)」を描いたのではないかなぁ?
本作を見終わってパッと思い浮かんだのは小さい頃読んだ童話「姥捨山(うばすてやま)」です。姥捨というのは制度ではなく風習ではありますが、死を選ぶ人、促す人、実行する人などなど登場する人物像は似ているんですよね。その話を読んだ時とかなり似た感情を持ちました。姥捨山ってお話も風習についての話ではなく、風習に翻弄される家族を描いたもの(母と息子にフォーカスしてますけどね)でした。そう考えると、本作は現代の姥捨山のお話なのかなぁ?って思います。
世の中のシステムに合わせて心も変わってくれれば苦労しないんですよね。システムほど人間の気持ちや情はそんなわかりやすいもんじゃないですし、人は記憶(思い出)や経験で考え方、感じ方は変化していくものです。そして知るのでしょうね、幾つもの「かけがえのないもの」を。命の価値が形骸化しようとも、かけがえのないものは変え難いものであると。大切なものは変わらないだろ!と。カメラ目線の河合優美さんの目がそう語っているようでした。
そして、ラストは人間への願いでしょうかね。ミチを通してそれを描いている気がしました。昨今の世界情勢や日本経済の落ち込みなどなど、とっても辛いことが日常生活の中でも発生しています。やなことだらけです、心配なこと、不安なことだらけです。けど、きっと明日は太陽が昇るんです。新し1日が来るのです。足掻けるうちは足掻いた方がいいのでしょうね。けど、その気持ちも「かけがえのないもの」の一つだと思うのです。
賠償さん。すばらしかったな。
現代楢山節考
78才迄働いていたミチはすごいと言うべきなのか、その年になるまで糊口をしのぐため働かざるえなかったと言う実態、それがなんともやるせ無い気持ちにさせた。
演出がとても細かい。
前半のミチは、ホテルで忙しく働き、自宅で立ち上がる時 年取ったら誰でも言いがちな「どっこいしょ」を言わなかった。
クビになった時、自分のロッカーの扉を丁寧拭きそれに向かって ありがとうございましたと言って去っていく、また、ちょっと贅沢した出前の寿司桶を洗い終えてきれいにフキンで拭き、その布巾のハジを整えて掛けていた。そして電話相談の時間が超過した時は、本当に申し訳ないと何度何度も見えない相手に丁寧に頭を下げていた。そんなふうに キチンと誠実に生活していた人が職を失い 糊口と生きるハリが無くなってしまった時に ふと入り込んだ魔法のプラン。
誰でも ふと考えてしまいそうだ。そこも怖い。
え〜、現代の楢山節考⁉️
横並びではなくて個々に 人生年齢を区切らせる選択を提供するってどう言う事⁉️
老いは悪なのか?
誰にでも等しく自然現象の老いは訪れるのに 生産性のない人間は 長く生きていてはダメだと言うのだろうか。
『人間』と名乗る者は 障害もなく精神も健全で ある程度資金が足り 誰の手も借りずに生活できる人こそ
生活していくのに値すると言われた気がする。
でも ミチが最後にした選択は、普通に生活して来たヒトの強さ、当たり前に生活して来た人の生き方が現れたのだと思った。
宮本役の河合優実は電話の声が良く アップのシーンの表情はとても良かった。
静かなトーンの中に 細かい演出、残酷な出来事、もしかしてありうるかもしれない怖さを秘めた映画で とても考えさせられた。
少数派になりつつある若者として
よく映画を観ますが、今作は明らかに年齢層の高い中、妙な緊張感で鑑賞。題材も作品としても良かったです。考えさせられたし、自分の中にある「歳をとった時、膨大な医療行為と薬で延命してまでひたすら生き続けるのはちょっと嫌かもなぁ」という感覚がまさにヒット。
引っかかるところが一点。
根っこにあるのは"世代間の断絶"じゃないのか?ということ。
PLAN75対象者は軒並み「仕事などで社会との接点はある(あった)が、若者との交流を継続しておらず、崖っぷちに立って始めて若者との繋がりの良さに気づく」ところが、高齢者にとってのみ都合がよいような気がしました。
繋がる努力はしてきていないけれど、自分が大変になったら若者に理解を求めるし助けて欲しくなった、という感覚の厳しさ。だから観た人はこれから気をつけよう、という監督なりの警鐘なのかもしれませんね。
今の高齢者の方々が現在の日本になるよう仕事や育児をして支えてきた!という事実はもちろんのこと、自分も前の世代がいなければ生まれていないから基本的な感謝はある。
でも、さすがに死を選ぶしかないぐらいに孤立してしまうまでに、きっといくつも分岐点があったはずで「同世代とのみ生きていたら詰む」という話な気もして、我が身も省みつつ、なんだかな〜という気分で鑑賞を終えました。
迷惑をかけない、というのは建前で、血縁の有無に関わらず若者との交流を怠っていたらそりゃそうなるよな、という登場人物の結末の迎え方が散見されました。
生き物は通常、満足に生命活動ができなくなったら死を迎えるけれど、人類はただ一個体の寿命を延ばすことに躍起になり、ひたすらに生き続ける状態を賛美するあまり、自縄自縛になりつつある気もします。この作品のメッセージも結局は"生き続けよう"になっていて、わかるけど、既に若者側は結構腹括ってますが……と言いたくなる。
とりあえず、血縁を抜きに他者と繋がり続け、世代間の交流を絶やさず、健康に生きていくしかないので、この作品は自分への戒めとしたいと思います。
画面いっぱいのシワ
ひたすら続く閉塞感、リアル
ファーストカットから、それぞれのキャラクターの背景など、思ってたよ...
ディストピア?ユートピア?
考えさせられる内容でした。
仕事柄高齢者に関わる機会が多いのですが、要介護状態、認知症の方と接していて、最後は人に迷惑かけることなく、できればお金もかけることなく人生の幕を降ろせたらと考えてしまうことが多くなりました。
年金に関しても、どの年齢で受給しても12年程度で国側はマイナスになる計算であると聞いたことがあります。100歳以上が珍しくない現代において、財源の分配を子育支援や教育にまわす比率を高めるため、未来のために見直す必要があるのではないでしょうか。
主人公は労働意欲もあり、生きることにも前向きな様子がうかがえますが、生活保護を選択するならプラン75を選択するという考えを持つ人も少なくないのではないでは?
最後の解釈には賛否あると思いますが、もう少し突き放した終わり方でも良かったかなと思いました。
只今40代。行きつく未来はいかに。
タイトルなし
上映後、トイレ待ちの高齢女性たちの談笑が聞こえる。「もうちょっとリアルな話かと思ったのに」とのことで、えーっと思った。個人的には、もうすでにそうなっている話。
注目すべきは、高齢者が捨てられるというところだけでなく、若者も、将来捨てられるために捨てる仕事をしている(させられている)ところ。若者だってこのベルトコンベアーに載せられているのである。
ディテールの描写のリアルさ細かさには、なんとも言えない居心地の悪さがあり、そこにこの映画のメッセージがあると思ったけれど、結局最後はヒューマニズムみたいな着地がちょっと物足りない気もした。しかし、機械的組織への一体化を突き破る第一波は、個人がきちんと人間であろうとする衝動ということだろう。適応しないことの大切さ。
考える機会
年老いた叔母がこの映画を観たいと言っていた。一緒に観るかと聞いたら、友だちと一緒に観るからと言っていた。今日一人で観たけど、一緒に観ていなくて良かったと思う。考えがまとまらないので、叔母にはこの映画を観たことはしばらくは黙っておこうと思う。
公開されて約1ヶ月、空席が目立つ劇場で、観客は年老いた人たちばかり、一人で歩くことができない人もいた。いずれの方々も死を意識しての観賞だと思うのだが、いま75歳を過ぎた人たちはこの作品を観て何を思うのだろうか。
少子高齢化が進む近未来の日本における考えさせられる作品だった。倍賞千恵子演じる主人公ミチは、夫と死別した78歳、年老いてはいるものの穏やかで、発する声と話し方に品がある寂しい老婦人を実に見事に演じている。すごく歌が上手いのにカラオケを歌うシーンではあえて歌下手な老婦人を演じるあたり凄みを感じた。
市役所でプラン75の申請窓口に務めるヒロム。75歳の誕生日に市役所へ訪れた叔父に20年ぶりに会った。この叔父と甥のストーリーが老婦人のストーリーと絡んでいく。最後のシーンは、是なのか、非なのか、鑑賞された人たちと議論したいほどです。
PLAN60でも
少子高齢化対策の帰結としてPLAN75が生み出されて有りや無しやが語られていたが、問題はPLAN75ではなく、高齢化社会の雇用や住宅問題なわけで。それとは別に生きるのと同様に死ぬ選択ができてもよいと思っている。死ぬことをいつ死んでもよいと思える時に自分で決められるならこんな幸せなことはないだろう。
逆にできることなら死にたくないと思う人を何らかのロジックで死に追い込む仕組みは特攻と同じだ。
そうではなく自分の死ぬ時を自分で選べることに意味があると思っている。75ではなくもっと早くてもよい。また生きたいひとは好きなだけ生きればよい。もしそれができない社会なら、そもそもPLAN75の問題ではない。そこを一緒くたに語ることに意味はないと思う。
その視点で見ていたので、PLAN75に問題ありきの展開に全く入り込めなかった。むしろもっと別の方法があっただろうと忸怩たる思いで最後まで見た。
脚本、演出、俳優、全て良かった
暗すぎる
邦画とは思えぬ完成度。
凄かった。75歳になったら自分で死を選択出来るPLAN75の利用者と運営者の群像劇です。
余計な会話は無く、絵が、余白が、研ぎ澄まされていて全てを語る。ギリシャのヨルゴス監督思い出した。
誰も泣かず、誰もが熟考し、淡々と死に向かっていく。
社会が、政治が、教育が、経済が人を分断し、さらに孤独が友達となった、、、その究極形がPLANE75かも知れない。
だから僅かな役者の表情の変化が、見る人に伝える情報量は大きい。この無駄の無さは監督が一度このテーマを短編で作っているからなのかも知れない。まだ作品数が少ない監督ではあるが、楽しみ。
出演者も当然ながらレベル高し。
倍賞さんも良い仕事に恵まれて全力投球だ。
高齢者にも若者にも、感情移入できる視点は用意されている。
初めのPLAN75誕生の話はキャッチな要素かも知れないが、、無くても良かったかもしれない。
先生の目線がこちらに向いた時、あなたはどう思う?と振られた気がした。
同じこと考えてた
ある年齢なったら生死を自ら選択できるようにして欲しい。何年も前から同じような事を考えてたことがある。こういう制度を作って欲しいと。わたしはお金持ちではないので、老後には不安しかない。ある年齢まで生きれば死ぬ権利が与えられる。もちろん希望する者だけ。もしこのような制度があったら、将来の不安はとても軽くなる。
わたしにとっては本当に欲しい制度だ。これが映画になるとは驚いた。もし実現すればこんな感じか。というイメージが明確になった。
わたしには全く否定的には感じない。これからこの国で高齢者になる者にとって決して悪ではない制度だとわたしは改めて思った。
主人公の女性はあれからどうしたのだろう?この国でこの先彼女はどんな人生が待っているのでしょう?
ホラーよりリアルな怖さ
全398件中、181~200件目を表示