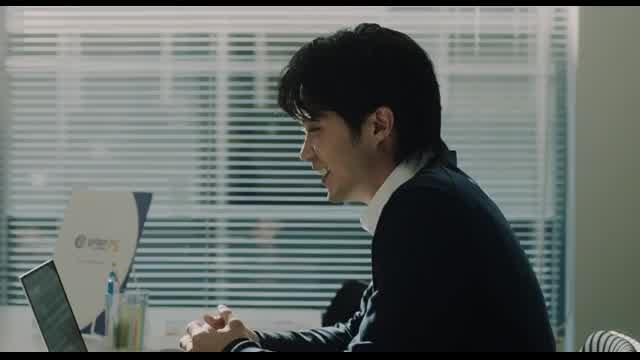「寅さんが見たら悲しむだろうなぁ~(:_;)」PLAN 75 流山の小地蔵さんの映画レビュー(感想・評価)
寅さんが見たら悲しむだろうなぁ~(:_;)
これが長編デビュー作となる早川千絵監督が、是枝裕和監督が総合監修
を務めたオムニバス映画「十年 Ten Years Japan」の一編として発表した
短編「PLAN75」を自ら長編化。
本作は、75歳以上が自ら生死を選択できる制度が施行された近未来の日本を舞台に、
その制度に翻弄される人々の行く末を描くものです。
少子高齢化が一層進んだ近い将来の日本。満75歳から生死の選択権を与える制度「プラン75」が国会で可決、施行され、当初は様々な議論を呼んだものの、超高齢化社会の問題解決策として世間に受け入れられるようになりました。.
1983年のカンヌ国際映画祭は、老人を山に捨てる今村昌平監督の「楢山節考」に最高賞パルムドールを授与した。そして今年の同映画祭では、再び老人を捨てる邦画が世界の注目を浴びたのが本作でした。しかし、現代の“姥捨”はより狡猾に洗練されていたのです。
物語は、近未来の日本。75歳以上は自身の生死を選べる新制度「プラン75」が導入されました。
夫と死別して以来、誰に頼ることなく、長らくひとりで暮らしてきた78歳の角谷ミチ(倍賞千恵子)は、ホテルの清掃業をなりわいとしていて、同世代の仲間たちと寄り添うように、つつましく生きてきたのです。仲間うちでも新制度は話題の的。皆なんとなく現実を受け入れているようでした。
けれども同僚の稲子(大方斐紗子)が勤務中に倒れたのを機に、彼女の暮らしは一変すします。「高齢者を働かせるなんてヒドいじゃないか」という世間からの叱責の声は、ミチたち高齢従業員の解雇という最悪の結末をもたらすことになったのです。さらに団地の取り壊しも決まり、ミチは仕事と住居を同時に探さなくてはならなくなる羽目に。だが高齢者であることを理由に、断られ続ける日々がつづきまます。次第に追い込まれていったミチは、ついに「プラン75」の申請を決意するのでした。
申請窓口では職員が手取り足取り笑顔で指導。「プラン75」による安楽死の奨励は立派な国家事業となっていたのです。
一方、市役所の「PLAN75」の申請窓口で働くヒロム(磯村勇斗)、死を選んだお年寄りに“その日”が来る直前までサポートするコールセンタースタッフの瑶子(河合優実)たちスタッフは、上司からは「情が移るから対象者とは交流を持つな」と言われていて、杓子定規的な対応を心がけていました。当初は、た彼らだが、ひょんなことから「プラン75」の対象者たちと接点を持つこととなり、それぞれの思いが交錯。やがて自分の行動に疑問を抱くようになり、それがきっかけで、このシステムの存在に強い疑問を抱いていくように変わっていくのでした。
また、フィリピンから単身来日した介護職のマリア(ステファニー・アリアン)は幼い娘の手術費用を稼ぐため、より高給の「PLAN75」関連施設に転職。利用者の遺品処理など、複雑な思いを抱えて作業に勤しむ日々を送ることになります。果たして、「PLAN75」に翻弄される人々が最後に見出した答えとは―――。
「死ぬ時くらいは選びたい」。拡散されるスローガンはまるでハーメルンの笛の音。“老人ホイホイ制度”に導かれ、高齢者は自分の足で断崖絶壁へ進みます。若者が老人を山頂までおぶって、罪悪感で苦しむ必要もないのです。同調圧力に弱く、考えることを諦めた現代人の姿がここに映るのでした。今の日本の空気がリアルに漂い、奇妙なほど説得力を持つドラマとなったといえるのでしょうか?
野に咲く花のようなしなやかさと強さを持つ主人公ミチを、倍賞千恵子が繊細に演じていて素晴らしかったです。ただねぇ、大の寅さんファンのわたしとしては、もし年老いたサクラがミチのような孤独で老いぼれた姿になっていたら、どんなに寅さんが嘆くことかと想像してしまいました(^^ゞ
サクラとしての倍賞千恵子に馴染んできたものとしては、本作で描かれる冷酷さにはとても違和感を感じてしまいました。彼女の代表作「男はつらいよ」の世界は、言葉は乱暴でも中身は温かさに包まれていたので、その落差の大きさに面喰らってしまいました。
映画の中では、老人に対し、誰もが優しい笑顔と柔らかい言葉で接します。しかし態度とは裏腹に、誰もが冷酷に老人を突き放しているのでした。そしてこんな姥捨山制度にて対して、プラン75のスタッフは何の疑問もなく、使命感を持って働いていること。加えて世間での受け止め方も、もうそれが当然という感じで、強い反対運動は描かれませんでした。さらに「プラン75」を申請する高齢者は、何のためらいも、迷いもなく静かに次々と安楽死を迎えるのでした。
少なくとも最近公開された『スーパーノヴァ』や『ブラックバード 家族が家族であるうちに』などの安楽死をテーマにした作品では、安楽死に至るまでの本人とその家族、友人らの葛藤が色濃く描かれていました。ところが、本作ではプラン75に沿って、老人をホイホイと安楽死させてしまうのです。
ヒロムや瑶子ら遂行する側に立つ若者たちの視点も交えてはいるものの、疑問を持つ止まりでした。現実にそんな立場で疑問をもてば、即刻仕事を退職し、反対運動の先頭に立ってしまうことでしょう。
さらにミチは口数が少なく、尊厳死を選ぶ理由さえ、セリフで説明されません。そのためミチの安楽死の決断が唐突に見え、ラストの不可解なオチにいたる行動にも、イマイチ感情移入できませんでした。
高齢者が一律75歳で自ら望んで安楽死してしまう近未来社会。それをステレオタイプに近い演出で取り組んだ早川監督の意図は明確です。「PLAN75」とは、現在の政府の福祉政策は姥捨山に向かっているという警鐘が鳴らしたいということです。その究極の姿をメタファーとして描いたのが本作です。
いま昨今の福祉政策は、少子高齢化のためピンチを迎えています。長らくつづくデフレの前には、消費税を連続で上げても、かえって景気は冷え込み、歳費の減少は止まりません。その中で福祉や介護が必要とする高齢者は年々増えていく一方です。
こんな状況の中で、景気対策や経済成長の予算を削減して、福祉予算ばかり拡大しては、デフレが増長していき、歳費収入は先細りしていくことでしょう。
極論として、こんな恐怖の姥捨山映画を作って、国民に恐怖の予感を与えるくらいなら、倍賞千恵子が慕う小津安二郎のような家族の絆を強めるような作品を作った方がマシだと思います。少子高齢化とデフレが続く中で、政府が何から何まで国民の生活を公費で賄うことには限界があります。だからこそ求められるのは家族の力です。江戸時代はそうやって子が親を養うのが当然でした。それがいまや政府が養うのが当然と考えている人が増えてきたのはいかがなものでしょうか。
家族のない人には、経済的に成功した人のたしなみとして、高齢者や生活困窮者に手を差しのべる社会貢献活動をもっと定着させていくべきでしょう。
社会には、そんな優しさが必要だと強く思わせた作品となりました。