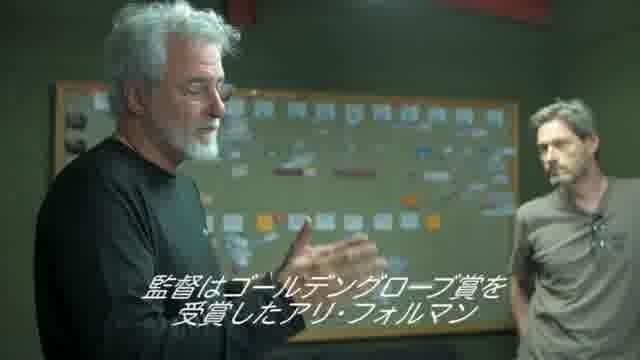アンネ・フランクと旅する日記のレビュー・感想・評価
全54件中、21~40件目を表示
問題は、それほど単純でも簡単でもない
アンネの物語をそのまま映像化するのではなく、「キティー」という仕掛けを使って現代の世情を織り込んだのは、難民問題を提起したかったからだろう。そして、「人種差別や弱者への不寛容、そして戦争や侵略に苦しむ人々の姿は、80年前と何も変わっていない」というこの映画の訴え掛けが正しいのは、ウクライナの現状を見るまでもなく明らかである。
ただし、背景も実態もまったく異なるユダヤ人への迫害と現代の難民問題を同一に描くのは、問題を単純化し過ぎているような気がするし、劇中、それが、いとも簡単に解決してしまうのも腑に落ちない。
あくまでもファンタジーということで、アニメーションという手法を用いたのであろうが、そこには、すべてが「絵空事」に見えてしまうという落とし穴もある。
青少年に、差別や不寛容について考えるきっかけを与える入門書としては最適だろう。
あらためて自由ということ
アンネの日記
(原題) Where Is Anne Frank
子供だけで150万!
同じじゃないけど重なってしまう
事情や目的が異なるので同じでないが、やはり難民や避難する人達の映像を見てすぐ
この映画を観てしまったのでウクライナのことを思い浮かばないわけがなかった。
アンネの生み出したイマジナリーフレンドが現代に現れたらというファンタジーな物語だけど
何か現実以上に危機として考えさせられる映画だった。
とんでもな部分もあるので、えってこともあったけど、そもそもファンタジーなので
野暮なことだと思う。
映像は、時に華やかに時にオドロオドロシく場面の心情が伝わってくる色調としなやかな線によって描かれておりとても良かった。
音楽もすごく好き
時を経てもまだ争いが絶えず、難民も増えつづけ不安な日々がいまだに続いていることに
人は変われないのかと絶望を感じるも今だから何か考えるキッカケになる映画だと思う
すみませんが、ちょっと意味不明だと思います…。
アンネとオランダの難民を結びつける?
架空の少女キティーは、最初、誰にも見えない存在だったが、なぜか現代に現れると姿が見える?
何を描きたかったのか?アンネではなく、キティーを描きたかったのか?
しかし、最初は少年にもキティーは見えていなかった。なぜ、途中から見えるようになり、キスしたりのラブストーリーになるのか?
キティーはアンネがホロコーストされたことを知らず、少年に教えられ、涙を流す…。
キティーは難民の強制送還反対を訴えるが、難民と何か関係があるのか?
何を描きたかったのだろう?オランダの難民問題を訴えたかったのか?
そうだとすると、アンネの日記を題材に使うべきではないだろう。
皆さん、感動したり、ウクライナと結びつけたりしているようですが、私には理解不能でした。
劇場でお確かめください。
キティに責められているようだった
戦時中の日本では、空襲爆撃を避けて田舎に避難することを疎開と言っていたと思う。島国の日本ではどこへ行っても日本語が通じるから、言葉の苦労はない。
しかし他国と地続きのヨーロッパでは、言葉が通じないことは衣食住の確保を困難にし、死や病気になる可能性を高くする。必然的に他の言語をマスターするようになった筈だ。特にユダヤ人はディアスポラと呼ばれる離散以後は、世界各地に散り散りになって、住み着いた地方の言葉をネイティブと同じように話した。ヘブライ語も喋るから、たいていのユダヤ人はバイリンガルだ。中には女優のナタリー・ポートマンのように6ヶ国語を話す人もいるくらいである。
アンネ・フランクは4歳の頃に危険なフランクフルトからアムステルダムに移住したから、4歳までに覚えたはずのドイツ語よりもオランダ語のほうに馴染みがあったに違いない。オランダ語で日記を書くのは当然である。アンネは日記にキティという名前をつけた。
ユダヤ人迫害の閉塞状況の中で、それでもティーンらしく未来への希望や広い世界の想像がキティに記されていく。アンネは迫害されても人を信じていたのだ。それは父オットー・フランクが人格者であったことに由来するものだ。アンネは心が広くて優しい父親が大好きだった。母親は嫌いだったけれども。
本作品は日記であるキティが現代のアムステルダムに現れて、世界がアンネの願った状況とはかけ離れていることに衝撃を受ける話である。プーチンが戦争を始めたときに公開されたのは、偶然とはいえ、奇跡的なタイミングであった。
世界中で出版されていて、タイトルは広く知られているにもかかわらず、世界はアンネの苦しみをちっとも理解していない。精神性の弱い人たちが、自分勝手な思い込みと狂った被害妄想で、他人を傷つける。キティはそのことが耐えられない。アンネの苦しみの全量を背負って現代に現れたキティだが、苦しみは増すばかりだ。
世界がどんなに平和に見えても、人の心には悪意があり、被害妄想がある。戦争はあなたたちの心にあることを、どうしてわからないの?と、キティに責められているようだった。
繰り返される悲劇…だけど過去から学び変えることができる
アンネフランクは想像の友人キティに向けて日記を書く。
そのキティが現代によみがえり、アンネの日記で描かれなかったその先を見届ける。
アンネ・フランクは知っているが、日記は読んだことがなかった。
アンネは明るく活発、想像力豊かでユーモアもある。しかし、戦争がそんな彼女を変えていってしまう。
罪もない未来への希望に満ちた子供が犠牲になる…
あってはいけないことだと改めて思う。
しかし、現代でも同じことが起きていると今作は伝えてくれる。
さらにロシアのウクライナ侵攻も起きている。
なぜ悲劇は繰り返されてしまうのか?
何度も戦争、差別反対のメッセージはさまざまな媒体を通して伝えられてきたのに…
悲しくなりつつでも今作は、過去から学び変えていけることはできるという希望に満ちたメッセージを伝えてくれる。
戦争、差別を無くすことはできないかもしれないが、
過去の悲劇は伝え続けなくてはならない、途絶えさせてはいけない。
こういった映画は今後も作られていかないとダメなんだと思った。
イマジネーションに溢れたアニメーション
イマジネーションに溢れたアニメーションが素晴らしく、予告編でも見られた「アンネの日記らしき本から文字が浮き出て一人の女性になっていく…」という冒頭部から引き込まれた映画だった。
そして、全編にわたって素晴らしいアニメーションによって、第二次世界大戦下にユダヤ人のアンネ・フランクが空想の友人あてに綴っていた「アンネの日記」に基づくドラマが展開される。
10年ちょっと前に観た『戦場でワルツを』のアリ・フォルマン監督作品であり、『戦場でワルツを』で見せてくれた「戦争の記憶を辿る流れの物語で、アニメーションとドキュメンタリー映画の融合のような描写が見事だった」が、それは本作でも同じような感覚が感じられた。
本作では、アンネ・フランクの空想の友人キティという女性の視点からアンネの生涯を辿るドラマとなっている。
現代のオランダの博物館で保管されている「アンネの日記のオリジナル」の文字が「本から抜け出るように動きだしてキティとなるシーン」は見とれてしまう。キティは時空を飛び越えた認識が無いのだが、日記を開くと過去へ遡って、親友のアンネ・フランクと再会する。このイメージ映像も見事!
『戦場でワルツを』や本作を作り上げたアリ・フォルマン監督の手腕は、本当に素晴らしく、近年のCG映画へのアンチテーゼとも思わされる見事なアニメーション映画の佳作✨
必ず、かの邪智暴虐の大統領を除かねばならぬ❗️
『アンネの日記』
読んだことは無いのに、タイトルと表紙に使われている笑顔の写真の記憶が強く残っています。
年の離れた兄と姉がいたためか、幼い頃の私にとって内容がよくわからないけど印象に残った本、というのがけっこうあります。アンネの日記もそのひとつで、ポプラ社の怪人二十面相シリーズ(少年探偵団シリーズ⁈)とか、ビニールカバーの豆本的真っ赤な毛沢東語録とか(兄が思想的にかぶれてた記憶はないのでひとつのファッションアイテムのようなモノだった気がする)、あのねのね(マスの書き方を教えてください、という質問への回答が酒桝の立体図だったりする、まぁ無意味な本でした…でもよくある自伝とは違う、芸能人としては目新しい分野のバラエティ本だったと思う)とか長嶋茂雄引退特集のアサヒグラフとかが全部ごっちゃになってた本棚の記憶があります。
『アンネの日記』はたぶん姉の学校における読者感想文の課題本だったと思います。つまり、極東の日本における戦後教育においても子どもという弱き立場の者の人権について啓発を促されていた訳です。
教育によらずとも、ロシア(ソ連)はドイツとの戦争で民間人を含めると3,000万人とも言われる犠牲者を出し、戦争の悲惨さをこれ以上ないほど知っているはずなのに、なぜ今あんなことを…
プーチンに対しては、『必ず、かの邪智暴虐の大統領を除かねばならぬ』と今、メロスだけでなく世界中の人が怒ってます。
※日本で気になるのは、カーシェアリングの話でもしてるかのような軽さで、ニュークリアシェアリング(核共有)の議論を始めようとしてる人たちがいることです。
憲法や非核三原則が日本の平和にどれだけ貢献してきたかの総括を冷徹にすることもなく(自国の軍隊が他国民をひとりも殺傷していないことで攻撃の対象とされずに済んできた)、他国が強権的、軍事的になりつつあるから、日本もそれに伍していこう、という短絡的な感じがとても怖いと思います。
日本の最大の弱点は、大いなる力を持った時に大いなる責任を感じて考える政治家がいない。少なくともそういう信頼を持って、今の政権に負託している有権者はほとんどいないと思うのですが、どうなんだろう?
話がとっ散らかってしまいましたが、とても良い映画です。
ラストナイトインソーホー?
アンネ・フランク関連は、何となく不穏な雰囲気になりがちですが、絵柄も色彩もとても綺麗に描かれています。
そして、ナチスの問題だけではなく、現在も世界中で行われている(これを書いているときはロシアによるウクライナ侵攻中)、少数派に対する人権侵害や不寛容をテーマとしています。もちろん、我が日本でも(日本人すら出てきます)。さらに、アンネ自身が消費の対象になっていることに対する抗議ともとれます。
構造としては、アンネとイマジナリーフレンドとの時空がシームレスに入れ替わる、ラストナイトインソーホーと同じ作りになっています。このため、おそらく本作のターゲットになっている小中学生には初見でよく分からない場面ががあります(キスシーンが長いですが)。特に、アンネの日記のことを事前に知らないと。作品の重要性に対し、皆さんにオススメですよにはできませんでした。EU諸国では基礎知識が拡がっているからかとも思いますが。
とても良かったところは、英語が聞き取りやすく、難しい言い回しやスラングがないので、理解しやすいです。中高生は字幕を見ずに絵に集中して見てみましょう。
アンネから現代の若者へ。
アンネ・フランクが生み出した空想上の友達キティーが日記から飛び出し戦時下のアンネと現代を繋ぎます。美しく繊細なアニメーションと音楽は必見です。
12年間で600万人。その内子供は150万人と言われるホロコーストの犠牲者。「東へ連れて行かれたら二度と戻らない」と言う噂を聞き恐怖の中で過ごした2年間に及ぶ隠れ家での暮らし。息を潜めて生活する中でキティーは唯一本音を打ち明けられる大切な友達。現代の思春期の若者と何ら変わらないごく普通の少女がユダヤ系というだけで迫害され、やがて劣悪な環境の収容所で命を落としてしまう。15才9ヵ月。
なぜユダヤ人は迫害されたのか。なぜ隠れなければならなかったのか。最期と悟って見た車窓からの景色は15才のアンネの瞳にどう映ったのか。キティーと共にその軌跡を追いながら胸に刻みます。アンネにしか見えないはずのキティーが現代では一人の少女として存在するという構成が巧みで素晴らしかった。
これからも日記と共に生き続けるアンネ・フランクとキティー。そして600万の命。それは言うなれば600万冊の日記。その1つ1つに物語があるということを忘れてはならない。若い世代にこそ観てほしい1本。
この映画は決して二番煎じではない。 人々がなぜアンネ・フランクに惹かれたのかを再認識させてくれる
第二次世界大戦の悲劇の1つとして、今もなお語り継がれるアンネ・フランクの物語。
彼女が書いた日記を基にその悲劇は、様々な創作の題材とされ、隠れ家での日々や同居人たちとのやり取りを知らない人は少なくないはず。
でも、この映画はそんなアンネの悲劇の物語を再演するようなものではなかった。
日記に登場する架空の人物キティが、現代のアムステルダムに具現化され、日記の記述を手がかりにしながら友人であるアンネを探す。そう、日記から生まれたキティはアンネの最期までの道のりを知らないのだ。
アンネを探す旅の中でキティはある社会問題を目の当たりにする。その問題を抱える現代はアンネ・フランクが望んだ未来とはかけはなれていた。キティはアンネ・フランクの最期を知らなかったけれども、アンネの心は誰よりも知っていた。そのキティが取った行動にハッとさせられた。
監督はこの映画を通じて、観る人に問いかけているようだった。
私たちはなぜアンネ・フランクに惹きつけられ、今もなお彼女たちの隠れ家に長蛇の列を作って訪れているのか。その理由は忘れて、「アンネ・フランク」を神格化し、彼女の日記を崇拝対象のように飾っていることに対する皮肉も混ざっているように感じられた。
解りづらい
邦題がメルヘンすぎるかも…
架空の友達が飛びだす独創的映画。 原作も架空のともに語りかける内容...
全54件中、21~40件目を表示