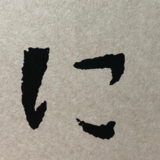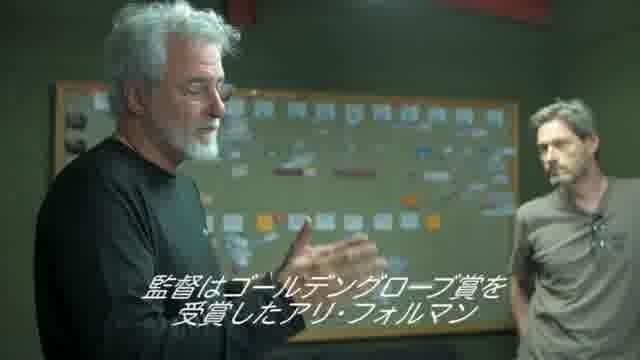アンネ・フランクと旅する日記のレビュー・感想・評価
全64件中、21~40件目を表示
アンネ・フランクの人生を「友人」を通して語りかけてくる作品です。幻想的な表現が効果的で、ゆっくりと心に沁みてくる感じです。
実のところを言いますと
アンネの日記もアンネ・フランクの伝記も
これまで読んだ記憶がありません。 うーん
第二次世界大戦時、収容所に送られ命を落とす
一人のユダヤ人の少女が書き残した日記。
戦争の悲惨さを突きつけられる話に違いない と
その重さに耐えられる自信が無く
意識的に手にとるのを避けてきたような気がします。
で、今回
アニメ作品が上映されているのを知りました。
実写よりは表現の生々しさは薄れているかも
これを観なかったら今後見る機会が無いかも と
一大決心をして観に行きました。
(※ 鑑賞前日に「学習まんが アンネの伝記」で
アンネ・フランクのことを予習したのはここだけの話)
◇
ドキュメンタリー風なのかと思ったのですが
そうでもなく、特に後半
ファンタジーの色合いが濃くなります。
アンネの友=日記帳が擬人化したキティが現代に現れ
居ないアンネを探して回ります。
「 Where Is Anne Frank ?」 (アンネはどこ?)
そう。
キティは、アンネが記した日記。
そこに、アンネの最期は書かれているハズも無く
キティはアンネを探します。
街で出会ったペーター少年や難民の少女。
アンネの日記の「原本」を手に、彼らと共にアンネを探すキティ。
最後の場面では
難民の少女の父親が作っていた気球が空に浮かびます。
その飛行船の横腹に書かれた文字が
「 I am here 」 (私はここにいる)
この作品のタイトル(原題)の問いかけ。
それに対する答えが、これだと言うことなのでしょうか。
一見して分かりやすい対比に見えるのですが
すごく意味ありげにも思えて、
飛行船のメッセージの意味をあれこれと考えています。
・アンネ・フランクはここにいる。
・難民は現代でも無くならない。
けれど寄り添う者もここにいる。
・人は自分の意志でどこにでも行くことができる。
うーん。
正解はあるのかなぁ。
この作品、
アニメーション作品なので表現は柔らかいのですが
実はかなり奥の深い作品だなという気がしました。
「アンネの日記」も読んでみようかな。
そんな気持ちになりました。
観て良かった。
◇あれこれ
知らなかったこと その1
劇中でアンネは「アン」と呼ばれていました。
本名が「アン」なのかと混乱したのですが
調べてみたらアンネ・フランクの本名って
「アンネリース・マリー・フランク」 だとか
そうだったのか と納得。
※けど
「アン」と呼ばれる場面の字幕が
「アンネ」なのがすごく違和感でした…
知らなかったこと その2
「アンネの日記」が
収容所で書かれたものと思い込んでました。 (…汗)
そうなら没収されてますよねぇ…
考えてみれば分かりそうな事
知らなかったこと その3
収容所に送られたアンネの家族の中で、
父親が唯一生き延びたこと。
アンネの日記が後世に伝えられたのは、せめてもの救い。
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
風化させないための新たな表現
不勉強極まりないのですが僕は「アンネの日記」を読んだことがありません。ですから知っている情報はネットの情報でしかありません。それを前提に感想を。(悪しからず)
本作はアンネが日記内で語りかけた(日記名でもあったようですが)キティを擬人化し、<キティの想いや思い出=アンネの日記に込められた想い>という新しい切り口の表現作品です。本作を見終わったときに思い出したのが、昨年鑑賞した「8時15分 ヒロシマ 父から娘へ」という作品です。その作品を制作された美甘さんは「原爆の事実を後世に伝えるためには悲惨な映像を見せても敬遠されるだけ。見やすい作品にすることで、若年層への認知の裾野を広げる必要がある」とおっしゃってました。
本作はそれと同じく「アンネの日記」の中で描かれる厳しい戦争や迫害の事実や辛さをそのまま伝えるということではなく、キティという存在をクッションにして柔らかく、見やすく、受け入れやすい表現にして、アンネを知らない若い方々を中心に多くの方々に広げる目的で作られたのではないのかな?って思いました。このようことは過去の悲しい出来事を風化させないためにとても有意義ではないのかな?って思います。
また原題の「Where is Anne Frank」はとてもしっくりきます。アンネの願いや想いが具現化されたキティから見ると現在の世界はまさに「アンネ(の願いや想い)はどこ?」ってことなんでしょう。彼女の名前をつけてるだけで魂が受け継がれていないという悲しさと戸惑いがキティから伝わってきます。まさに「風化」そのものだと気づかせてくれるのではいでしょうか?タイミングとしてとても悲しい出来事が毎日ニュースで流れている今、忘れてはいけないこと、あの頃と何も変わっていない今を我々は知らなければならないと思いました。決して人間の本質はわからない。だから、多くの人が気づき是正する努力をしなければならないのです。
本作は戦争や迫害だけではなく、差別全般に広げるなど現代にも通用する話にまで展開していますから、ぜひ若年層や子供たちを中心に見て欲しいですし、観賞後にご家族で色々と話して欲しいなぁって思う作品でした。
とっても見やすく綺麗なアニメーションですし、これからの世界を作る人々こそ見るべきと思います。
インク文字から紡ぎ出されたキティが美しい
最高の擬人化ファンタジー!
問題は、それほど単純でも簡単でもない
アンネの物語をそのまま映像化するのではなく、「キティー」という仕掛けを使って現代の世情を織り込んだのは、難民問題を提起したかったからだろう。そして、「人種差別や弱者への不寛容、そして戦争や侵略に苦しむ人々の姿は、80年前と何も変わっていない」というこの映画の訴え掛けが正しいのは、ウクライナの現状を見るまでもなく明らかである。
ただし、背景も実態もまったく異なるユダヤ人への迫害と現代の難民問題を同一に描くのは、問題を単純化し過ぎているような気がするし、劇中、それが、いとも簡単に解決してしまうのも腑に落ちない。
あくまでもファンタジーということで、アニメーションという手法を用いたのであろうが、そこには、すべてが「絵空事」に見えてしまうという落とし穴もある。
青少年に、差別や不寛容について考えるきっかけを与える入門書としては最適だろう。
難解
メッセージ性の高い作品で、しかも、アニメだから表現が抽象的で難しいかもしれないけど、なんで、アンネではなくて、キティが主人公なのかを理解すると、今に生きて未来を作っていく我々へのメッセージだと理解が出来ると思う。
戦争は偶然で起こるものではない。
誰かが誰かを殺す目的で起こるものだ。
被害者にも加害者にもなってはならない。
あらためて自由ということ
アンネの日記
アンネ・フランクの Imagenary Friend が世界を変えようと現代で奮闘する切なすぎるファンタジー映画
アンネ・フランクのことはあんまり知らないおじさんですが、この映画を支持します。
いまウクライナで起きていることが80年前の世界と何ら変わらないことに人類として情けない気持ちで一杯です。
秋田犬返せ❗
難民の問題は戦争や内紛、無能な統治者の問題と直結します。難民がめざす国に選ばれたオランダにも限界はあるでしょう。しかし、救いを求められるだけマシ。この素晴らしいファンタジーに敬意を表したいと思います。
過去の映画へのオマージュも感じられました。
たとえば、飛行船を作る場面では船の帆を縫う職人が気球を作って東ドイツから西ドイツに亡命した話とか。
ツェッペリンはドイツですが、ナチスとは関係ありません。I am here. と書かれた飛行船は輝く未来への希望とキティの覚悟の象徴です。
アンネの日記を商標などに使うことへの抗議もありました。
難民問題に話をすり替えたとは全然思いません。戦争や内紛と難民問題は切り離せないからです。
キティを支えたいと頑張るスリの少年ペーターには悲しすぎるエンディングでした。それだけに、アンネがキティに託した思い=キティがアンネを想ってやり遂げようとしたことはとても尊いことだった思います。
(原題) Where Is Anne Frank
子供だけで150万!
アニメの表現
アニメならではの表現を盛り込んでナチスの怖さ等々をわかりやすく表現していて良いと思った。
アンネの名前を街や施設に残すことに意味があるわけではなくそこから人々がアンネの想いを受け取ることが大切だと言う主張は現在の戦争なんかを思い出してとても強く刺さった。
同じじゃないけど重なってしまう
事情や目的が異なるので同じでないが、やはり難民や避難する人達の映像を見てすぐ
この映画を観てしまったのでウクライナのことを思い浮かばないわけがなかった。
アンネの生み出したイマジナリーフレンドが現代に現れたらというファンタジーな物語だけど
何か現実以上に危機として考えさせられる映画だった。
とんでもな部分もあるので、えってこともあったけど、そもそもファンタジーなので
野暮なことだと思う。
映像は、時に華やかに時にオドロオドロシく場面の心情が伝わってくる色調としなやかな線によって描かれておりとても良かった。
音楽もすごく好き
時を経てもまだ争いが絶えず、難民も増えつづけ不安な日々がいまだに続いていることに
人は変われないのかと絶望を感じるも今だから何か考えるキッカケになる映画だと思う
すみませんが、ちょっと意味不明だと思います…。
アンネとオランダの難民を結びつける?
架空の少女キティーは、最初、誰にも見えない存在だったが、なぜか現代に現れると姿が見える?
何を描きたかったのか?アンネではなく、キティーを描きたかったのか?
しかし、最初は少年にもキティーは見えていなかった。なぜ、途中から見えるようになり、キスしたりのラブストーリーになるのか?
キティーはアンネがホロコーストされたことを知らず、少年に教えられ、涙を流す…。
キティーは難民の強制送還反対を訴えるが、難民と何か関係があるのか?
何を描きたかったのだろう?オランダの難民問題を訴えたかったのか?
そうだとすると、アンネの日記を題材に使うべきではないだろう。
皆さん、感動したり、ウクライナと結びつけたりしているようですが、私には理解不能でした。
劇場でお確かめください。
キティに責められているようだった
戦時中の日本では、空襲爆撃を避けて田舎に避難することを疎開と言っていたと思う。島国の日本ではどこへ行っても日本語が通じるから、言葉の苦労はない。
しかし他国と地続きのヨーロッパでは、言葉が通じないことは衣食住の確保を困難にし、死や病気になる可能性を高くする。必然的に他の言語をマスターするようになった筈だ。特にユダヤ人はディアスポラと呼ばれる離散以後は、世界各地に散り散りになって、住み着いた地方の言葉をネイティブと同じように話した。ヘブライ語も喋るから、たいていのユダヤ人はバイリンガルだ。中には女優のナタリー・ポートマンのように6ヶ国語を話す人もいるくらいである。
アンネ・フランクは4歳の頃に危険なフランクフルトからアムステルダムに移住したから、4歳までに覚えたはずのドイツ語よりもオランダ語のほうに馴染みがあったに違いない。オランダ語で日記を書くのは当然である。アンネは日記にキティという名前をつけた。
ユダヤ人迫害の閉塞状況の中で、それでもティーンらしく未来への希望や広い世界の想像がキティに記されていく。アンネは迫害されても人を信じていたのだ。それは父オットー・フランクが人格者であったことに由来するものだ。アンネは心が広くて優しい父親が大好きだった。母親は嫌いだったけれども。
本作品は日記であるキティが現代のアムステルダムに現れて、世界がアンネの願った状況とはかけ離れていることに衝撃を受ける話である。プーチンが戦争を始めたときに公開されたのは、偶然とはいえ、奇跡的なタイミングであった。
世界中で出版されていて、タイトルは広く知られているにもかかわらず、世界はアンネの苦しみをちっとも理解していない。精神性の弱い人たちが、自分勝手な思い込みと狂った被害妄想で、他人を傷つける。キティはそのことが耐えられない。アンネの苦しみの全量を背負って現代に現れたキティだが、苦しみは増すばかりだ。
世界がどんなに平和に見えても、人の心には悪意があり、被害妄想がある。戦争はあなたたちの心にあることを、どうしてわからないの?と、キティに責められているようだった。
繰り返される悲劇…だけど過去から学び変えることができる
アンネフランクは想像の友人キティに向けて日記を書く。
そのキティが現代によみがえり、アンネの日記で描かれなかったその先を見届ける。
アンネ・フランクは知っているが、日記は読んだことがなかった。
アンネは明るく活発、想像力豊かでユーモアもある。しかし、戦争がそんな彼女を変えていってしまう。
罪もない未来への希望に満ちた子供が犠牲になる…
あってはいけないことだと改めて思う。
しかし、現代でも同じことが起きていると今作は伝えてくれる。
さらにロシアのウクライナ侵攻も起きている。
なぜ悲劇は繰り返されてしまうのか?
何度も戦争、差別反対のメッセージはさまざまな媒体を通して伝えられてきたのに…
悲しくなりつつでも今作は、過去から学び変えていけることはできるという希望に満ちたメッセージを伝えてくれる。
戦争、差別を無くすことはできないかもしれないが、
過去の悲劇は伝え続けなくてはならない、途絶えさせてはいけない。
こういった映画は今後も作られていかないとダメなんだと思った。
全64件中、21~40件目を表示