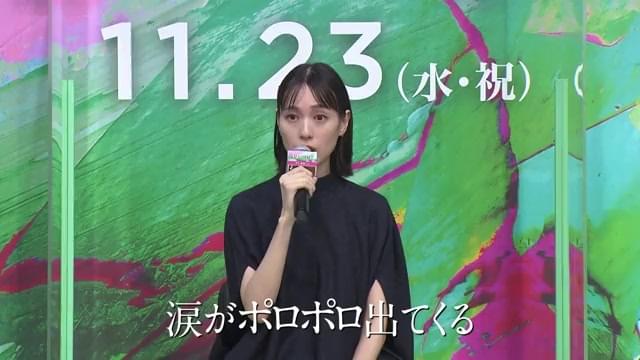母性のレビュー・感想・評価
全333件中、1~20件目を表示
母親になりきれない母とただ母を守りたかった娘と
子供を産み育てても視点が娘のままの女性。ルミ子ほど極端で、かつ自らを正しいと信じている人間はさすがに多くはないだろうが、心のどこかにそのような視点が残っている女性は結構いるのではと思う。
いびつな母性という主題は「ロスト・ドーター」を思い出させる。あの作品は母性を欠いた主人公と彼女の抱える罪悪感の話だったが、見ていて自然に母性神話について考えさせられた。
今回、原作は読了している。
母親はこういうつもりで言ったことを、娘はこういう印象で受け止めていた……といった対比を表現して母娘の行き違いを描くような作品なのかと思っていたが、そのような場面は原作・映画共に思ったより少ない。ごくざっくり言えば、いつまでも娘でいたい母親が、不幸に見舞われながらも、一貫して自分の娘に嫉妬したりコントロールしようとしたりする話だ。特に前半、ナレーションの多さに驚く。本を読み返しているような気分になった。物語の大筋もほぼ原作通り。
ルミ子を中心とした3代の母子関係を中心に、出てくる登場人物はおしなべて歪んでいる。特に田所家に移り住んでからは、周囲の癖の強さはルミ子の母性の問題が霞むほどで、ちょっと焦点がぼやけた気がした。
そんな田所家の中でも、清佳の母としてより義理の娘として義母に気に入られることを基準に行動するルミ子。義母の高畑淳子があまりに怪演過ぎて(一番原作に沿ったイメージだったが、さらに盛られていたような)、さすがにルミ子がちょっとかわいそうになってしまった。
しかしその強烈過ぎる義母の、律子が出て行った時の反応が本作の中で一番人間臭くて、ルミ子の母娘関係と対照的だった。大地真央が演じたルミ子の実母などは、ああいう役柄ではあるが、あまりに演劇じみている。原作の非日常的な言葉遣いの台詞がほぼそのまま使われていたことも、その印象を補強した。あのように、ある意味作り物のような「理想的過ぎる母親」だったからルミ子が親離れ出来ず、母親観にゆがみが生じたということだろうか。
これは原作に対する感想にもなってしまうが、ルミ子があのように育った理由の部分を、もうすこしじっくり描いて欲しかった。
個人的には、血の繋がった母娘の年季の入ったいざこざというのは根深いもので、どうにか凪いだとしても基本的に一生わだかまりが残るものと思っている。嫌悪だけでなく愛憎相半ばするとはいえ、母親が娘に嫉妬し続けて首まで締めたなら尚更だ。だから、最後に社会人になった清佳が妊娠した時に、JUJUの解決ソングが流れる中母親に電話報告、なんて流れには抵抗を覚えた。
原作では、清佳の妊娠を聞いたルミ子は「おばあちゃんが喜ぶわ」と喜び、清佳は「ママはどう思ってるの」と思いつつ尋ねない。なんだかルミ子は娘視点を脱却できていないようにも見える。それでも父親の浮気問題なども1ページ分程度の文章で決着がついて、大団円のようなのだ。
ちなみに、小説の方は簡単な叙述トリックが施されていて、節々で登場する女性高校教師=清佳であることは終盤まで伏せられている。映画では教師になった清佳も必然的に永野芽郁が演じたためトリックにはなっていないが、それなら原作に沿って合間合間に教師としてのトークを挟む必要があったのかな?冒頭にあのシーンを置いたのだから、ラストで初めてその後教師になった姿を見せた方が、終盤まで清佳の生死が分からず緊張感が加味されたかな、という気もした。
湊かなえが書き続けてきた“母と娘”。その破滅的な愛のミステリーを映画化
思い起こせば湊かなえのデビュー作「告白」は、勤務先の学校のプールで命を落とした幼い娘のために壮絶な復讐を仕掛ける女性教師の話だった。実生活でも作家になる前に結婚し長女を出産しており、育児をしながら執筆に取組んだことが影響しているのか、湊かなえの小説は母と娘の関係が重要な要素になっている話が多く、映像化されたものだけでも、WOWOWのオムニバスドラマ「ポイズンドーター・ホーリーマザー」(6話中の「ポイズンドーター」と「ホーリーマザー」)や、菊地健雄監督の映画「望郷」(2編のうちの「夢の国」)などがある。そして本作「母性」もまた、母と娘の“愛”をめぐるディスコミュニケーションを「藪の中」タイプのミステリーに仕立てた小説であり、映画化では超売れっ子の廣木隆一監督(今年の公開作は5本!)がメガホンをとった。
1988年生まれの戸田恵梨香と1999年生まれの永野芽郁、11歳差の2人に母娘を演じさせるというのも思い切ったキャスティングだし、ドラマ好きならさらに興味のポイントが加わるのではないか。というのも、戸田は2019年の「スカーレット」、そして永野は2018年の「半分、青い。」と比較的最近のNHK朝ドラで明るく元気なヒロインをそれぞれ演じたし、2021年のコミカルな連ドラ「ハコヅメ~たたかう!交番女子~」では先輩後輩の婦警役でW主演を務めていた。そんな2人が母・ルミ子と娘・清佳、しかも愛情のねじれや心の闇を感じさせるキャラクターで共演するのだから。
戸田と永野による、ドラマでお馴染みのポジティブな役柄とは大きく異なる複雑な演技に加え、ルミ子の実母(大地真央)とルミ子の義母(高畑淳子)、それぞれの子への思い入れが絡み合い、観客も改めて“母性”って何だろう、と考えさせられるはずだ。
役者の演技の上手さという視点で見ると面白い一方、物語としては期待し過ぎずに見るのが良さそうな作品か。
本作は、「告白」という名作映画の原作を書いた湊かなえの同名小説を映画化した作品です。
「告白」(2010年)は中島哲也というノリに乗っていた鬼才監督によって映画化されたこともあり、「R15+」指定を受けながらも第34回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀脚本賞、最優秀編集賞と、文字通り総なめの状態になるくらいのクオリティーでした。
そんな背景もあり、本作を原作者の湊かなえが「これが書けたら作家を辞めてもいい」とまで語っていたため、否が応でも期待値が上がってしまいました。
さらには、「母の証言」「娘の証言」と、それぞれの視点で描かれていくため、勝手に「どんでん返し」的な物語なのだろうと思っていました。
ただ、個人的に「どんでん返し」的なものは、思っていたほどには感じませんでした。
「告白」のようなものを期待して見ると、やや肩透かし状態になるのかもしれないので、見る際には役者の演技の応酬を中心に見るのがいいかと思います。
中でも戸田恵梨香の演技の使い分けは注目に値します。
また、義母役の高畑淳子の怪演ぶりには、場内からたびたび笑いが飛び出すほどの状態になっていました。
個人的には、本作が中島哲也の監督・脚本バージョンだとどうなるのか興味を持ちました。
ネタバレ要素になり得るため詳しくは書きませんが、時代設定がやや分かりにくいのかもしれません。
見る人によってはタイトルの「母性」というキーワードにハマって、より物語に入り込めるのかもしれませんし、癖の強い、割と極端な登場人物たちが多く出てくるため、そのセッションを楽しむのが良いと感じました。
娘の名前
終盤で母親が娘の名前を連呼した時に、娘の名前を初めて聞いた。その時に自分も娘の永野芽郁を、まるで母親の所有物かのような、一個人ではない「母親の娘」として見ていたことに気付く。それほどに母と娘の切り離せない関係を感じていた。
そして、この母親はそれまで娘の名前を愛情を込めて呼ぶことはあったのか、きっとなかったのではないかと思った。それは夫の母親高畑淳子が自身の娘の仕事を心配し、娘がいなくなった時は大声で名前を呼び泣きわめく、母親として当たり前の感情をあらわにしていたことで気付かされる。
年齢を重ねた戸田恵梨香が、母親の大地真央に言動が酷似していて、幼い頃からの長年染み付いた呪縛から逃れられないことを悟った。その演技もまた素晴らしい。
愛情のかけ方、度合いが適度でないと間違った方向にいくことは想像でもわかることだが、難しいのは人によってその程度が異なるということだと思う。正解がないということ。
そのうえ、母性もすべての女性に生まれつき備わっているものではないこと。
考えさせられる映画だった。
気持ち悪ぃ話
男で結婚していない、女兄弟無しで、母は別に好きでも無いので、この映画は劇場にわざわざ足を運ぶのでは無く、サブスクで見ました。
登場人物全員キモい。
初めは『母と娘が持つ考えが違うなどあってはならない』がテーマというか根底にあった。なぜそうなったのか説明がないから、そこに共感できない。
まぁママっ子なのはいいけど、なかば母に従う形で結婚をしたのもキモイ。そして母の選択ならお前の選択なのに『田所の血が』とかもキモイ。
家全壊してないなら別に頸動脈切らんでよかったよね
義母の事故物件で不倫する夫もキモいし、その相手もキモかった。標準語もなんか気持ち悪い。そうねあなた、なんて言うの?気持ち悪い。丁寧な暮らしを心がけて結局全部において上辺だけスキミングしかしてきてないような奴ら。
永野芽郁演じる娘もキモかった。
正しいの押付けと、中途半端な覚悟と、それでも母を愛するのキモイ。別に女は母と娘だけじゃないからね?
もしかしたらいちばんキモくないの田所の母かもしれない、『肝心な時に怖気付いて!』って首を吊った娘を見て1番に救急車を呼んだところで持ち直したね。嫌な母の役が上手い。
演技はうまかった、話は考え方には一切共感出来なかったが、全く別の思考回路で生きている人たちと割り切ってみればまぁ良かった。しかし、演技とかじゃなく考え方のキャラのキモさと、いつまでも義母の家にいる母の執念に近いいじらしさと、母子観についてがキモかった。
てか、ほとんどキメェ〜と思いながら見てた。
そもそも、仔細な描写から気持ちを読み取るタイプの映画でもあるから、原作小説はつくファンはついてそう。
色々な虐待の話を聞いた事があるが、どれだけ虐待された子供でも、やはり親は見限れないものらしい。だから、それでも親を愛してしまうんだと思う。だから親は子供に愛されるのは当たり前で、そこにあぐらをかいてはいけない。巣に帰ってくるのは当たり前なのだから、巣をより良い物にしておかなくてはならない。
覚悟
この作品を観るのに気持ちの整理が必要だった。
題材が母と娘。
重い作品だよな〜と思うとなかなか観るに至らず
観るためには精神状態が正常な時に見なければ。と覚悟が必要だった。
実際、覚悟して観て正解だったかな。
時代は昭和で、
戸田恵梨香さん演じる娘と大地真央さん演じる母
大地真央さんは戸田恵梨香さんを思いやりのある優しい娘に育てあげていた。
ハタから見たら、優雅でお嬢様育ちの普通の親子だったように思う。
優しい言葉、耳障りの良い言葉の裏側には、愛に隠された裏側には一体何が隠されていたのかな、とゾクッとした。
母は娘を確かに愛していてたけれど
一見、普通に見える娘の歪みに蓋をして
家族を持てば変わるとか、良い人と巡り会えば変わるとか、そういう他人任せな思考が昭和の母だなと感じた。
家が火事で燃えた時、自分の娘より自分の母を優先する娘を見てさぞ怖かったことだろうな。
私でも怖い。こんなに依存していたのかと愕然とする。
同時に自分を責めてしまうかもしれないけど
目の前で自殺した時は、大地真央さんも恐ろしい母だと思った。
結局は、娘は母の願いを聞かざる得ない状態になり、思いを縛ってしまった。母の願いを叶えるために。怖い。。。
これじゃあ、願いを込めた人形のよう
思考も、思いも願いも全て母のもので、自分がない。
母が望む娘でいたいという願望だけが残った人形
それは、高畑淳子さん演じる義母が老いた時に叶うという皮肉さ
それを怪演した戸田恵梨香さんは演技がとても上手くて、観ててゾクッとした。
永野芽郁さん演じる娘は
母が喜ぶから、正しくあろうとしていた。
自分本位な正義感を振り撒いていて、歯止めがわからない状態だった。
祖母からの愛は言葉にできて
母からの愛は言葉にできていなかったのに
母に愛されようと顔色を伺う子供だった。
言葉の節々にも、母と同じ考えだ、と母を強く意識していた。
母と娘、二種類いると考えているようだけど
正しく歪んでいる娘は、また、娘なんだろうな。
体面だけを整えられた、とも言っていたけれど
体面を気にしていたのは誰なのかな。
母性は作られるもの、これは分かる。
もともと備わっている人は少ないと思う。
遊び心がないと言われていた子が同僚と飲みに行っている様子から、断ち切れたようにも思われるけれど
自分が自殺しようとした経緯から、同じことをした子を調べようとしていて、その帰りに母に妊娠したことを電話で報告。
母の言葉を聞いて、お腹を撫でながら私はどっちかな、と呟く様も皮肉が効いていたように思う。
理解できるようで、共感できない部分も多く
最終的には夫は何してんの。と思ったよ。
実母に依存している妻から目を逸らして
義母から妻を守らず、他所で癒しを求めるくせに
自分の母親の面倒は押し付ける。
こんな夫は絶対イヤ。
あげく、子供からも逃げて、言い訳だけは立派ってどんだけなんだ。
娘が歪んだ一因を持つ父親。
愛人が自分の子供を傷つけるのを黙って観てるところもイライラしたよ;;
この作品は戸田恵梨香さん視点、永野芽郁さん視点で構成されてて、結局はお互いの証言だけで真実は一切語られてない。ここにも皮肉が効いててお腹いっぱい。
不完全燃焼
私自身毒親育ちなのでどんなストーリーか気になっており、原作未読のまま鑑賞しました。
強く声を荒げたりはしないものの、冷静ではありながらも目や言葉で圧をかける。大人の顔色を伺う人間になる育て方とはこういう事かと思いました。
聖母のような大地真央さんと、鬼のような義母高畑淳子さん。
どちらも演技が凄まじくて、釘付けになりました。
それぞれの母親像にも、愛情や母性はあるはずなのに子どもを苦しめる。家庭も子育ても正解がないから難しく悩ましいのかなと思いました。
それにしても夫はもう少し何とかしてあげられなかったのか、、何かしたところで受け入れてもらえなかったのか、謎でしたが見ていてイライラしました。
冒頭で女子高生が自殺したという報道はてっきり永野芽郁ちゃんの事だと思っていて。
どんな風に繋がっていて当人達が何を思ったのか、ぼんやりとしかわからなかったので、原作も読んでみたいと思います。
母親が苦しい
タイトルなし(ネタバレ)
1回目:2022.11.10 試写会
2回目:2022.11.11 試写会
気分悪くなるとコメントを見ていたから覚悟していったけど、かなり好きだった。
重いストーリーが好きなんだなと改めて思った。
終始異様な空気の作品だけどその中でも特に母とその母の関係は特に"作りもの"感満載で、でもお二方の演技がぎこちないとかじゃなくて確実に"演技っぽい異様な関係性の親子の演技"をされていてその異様な空気に徐々に慣れていった。
とにかく終始キャストの皆さんの圧巻の演技で、異様な世界観に気付いたらどんどんのめり込んでいた。
母(戸田さん)が異様なように思われがちだけど、毒って遺伝するともいうし、母(戸田さん)も娘(永野さん)も、同じように母と同じ答えが正しいと思っていたことから、母(戸田さん)も母(大地さん)に同じように育てられたのかもしれないと思った。
私自身、自分の経験を思い出すシーンもあって。娘でいたい母ではなかったし、ここまでではないけど、母親の言った通りに、決められた道を進むべきという考えを昔から植え付けられていたなと思った。
母親と同じだと嬉しいとか母親に毎日その日のことを報告して褒めてもらうとか、自分もやっていたなと。褒められたくて認められたくてやっていて、母と同じ答えが正解なのだと長年思っていて、それが当たり前だとも思っていたけど高校生の頃に友人に母が毒親要素少しあるよねと言われ、そこで初めてなんとなく自覚した。あまり実感はなかったけどこの作品を見て、皆さんのコメントを見て、ああ本当に普通ではなかったのかと初めて実感した。もし自覚せずに見ていたら何がおかしいのか分からなかったかもしれないと思うと、当たり前とか無意識って怖い。
私は共感できてしまったけど、毒親育ちではない人にはどう映るのか、気分悪くなる人にはどういうところが嫌にうつるのか、凄く知りたいと思った。
この母娘も一見普通に見えるし、実際やっていることが(エスカレートするとはいえ)犯罪とも言えず何とも言えないからこそ家族って難しいし、閉鎖的で怖くもあると思った。
娘視点に同情しがちだけど、お互いの視点で描かれているだけで客観的に、真実を描かれていないのが面白さでもあり怖さでもあるという講評を聞いて凄く納得した。
母目線と娘目線、同じ場面でも表情や細かい動作から全く違うように伝わってきてその演技が凄かった。
娘視点で語られた母にとっては"小道具"という言葉が最後まで覆されることがなく、ずっと作り物感が変わらず、異様な空気感だった。
ラストシーン、突然JUJUさんの良い曲流れて金10ドラマみたいな普通の恋愛ドラマのような雰囲気で終わるところまで含めて異様で、世界観として凄く凄く引き込まれたし、忘れられない作品。
〜細かいシーンの話なのでよりネタバレ含む〜
最後の方、娘が名前を初めて呼ばれた時、思わずドキッとしてしまった。確かに、名前、一度も呼ばれていなかったじゃん、、、と。
「子どもはまた産める」ってセリフ、本当凄かったな、、ここで多くの人が抱いていた「母(戸田さん)、、、ほんの少しでも良いから娘に対して母性を持っていてくれ、、、」という願いが消滅して絶望に変わった瞬間だと思う。その後の死の真相も衝撃的だったな、、、
高畑さんが最後、恐らく認知症になってずっと介護してくれている母のことを娘だと誤認識していて、そこも何か考えさせられたし意味がありそうな気がした。
結局、おめでとうではなくあの言葉が出てくるということは、最後まで母(戸田さん)は自分のお母さんを通してしか娘を見ておらず、この関係性はまだこれから先も続いていくと思ったし、娘の娘も同じ経験をするかもしれないと思った。
〜〜〜〜〜〜
2度目観賞後
1度目は、私自身娘ということもあり、娘視点になってしまいがちだったので母親視点で観るよう意識した。
最初に桜の花びらが窓から入ってくる場面がある、ルミ子がお母さんだと言ったのも桜。
ルミ子と母の時は玄関に置いてあった絵の中の花は、赤い薔薇、父がこっそり使っていた時は青い紫陽花。花言葉にも意味がありそうだと思った。
〜
農業を手伝うシーン、それ以前にもあったけどルミ子曰くルミ子が周りの人に奉仕したい気持ちを持ったのは母からの愛を受けたから(母から愛された証拠)。なぜ義母にあそこまで言われても我慢できるのかと1度観た時は疑問だったけど、あんな義母でも敬うことができる=母から愛を受けたから、なのかもしれないと思うとゾクっとしたし、だから清佳が祖母に口答えした時、反抗した時、あんな風に怒ったのかと納得した。
〜
途中手伝うシーンで、一生懸命頑張れば義母の娘にもなれるのだみたいなセリフがあった、実際それは叶って、最後は認知症になった高畑さんに娘と誤認識されていた。清佳のセリフで、「母か娘」か2種類とあったが、結局ルミ子は娘でいたい母だったのか、義母の娘になることができてきっと幸せなのだろうと改めて腑に落ちた。
〜
「私たちの命を未来へつないでくれてありがとう」というセリフ、妊娠した清佳におめでとうより先に「怖がらなくて良い〜未来へ繋いでくれてありがとう」という母の言葉が出てくるということは、やはり娘のことはまだ母親を通してしか見られないのだと思ったのに加え、なぜあのルミ子が火事の中助けてくれたのかと最初に見た時疑問だったけど、きっとあの瞬間母の遺言(願い)が命を繋ぐに変わったから、清佳に死なれては困るので火事から助け出したのかと思うと、母の無償の愛、母性は恐らく無く、母の遺言のために助けてもらっただけなのかもしれないと気付いて切なすぎた。
やはり何度見ても家も、何か違和感があるような、作り物感があってやっぱり奇妙だったけど、どこかでまた観たいと思っている自分もいる。
母娘。自分に共通するもの。
湊かなえさんの小説を映画化した本作。
ちょうど、小説を読んでいた頃に映画化が決まり、わ〜これは急いで読まないとと思っていたのに、妊娠、出産、育児に没頭していて、いつの間にか公開から3年近く経ってしみった、、、ようやく見れた!
(ちなみに、小説は結局最後まで読めず)
母親に愛されたい娘。
↑コレ私ですね。
と、本作を鑑賞しながら、思ってました。
共通点!
人から愛されたい!と異常に求める人は、愛情をきっちり受けていないからだと言う話はよくありますが、自身が母になって思うのは、同じように愛情をかけて育てても、受け取り側が違うので、もはやそんなん難しすぎ〜。ムリムリ。と思う。
母親に愛されている事が分かっていても、もっともっとと、それを永遠に求めてしまうのは、自身の問題だと思う。それくらい、母の事が大好きで、母にとって自分という存在が大きければ大きいほど幸せに思う。
でも、結局、母の人生は母のもので、娘の人生は娘のもの。各々が、依存している母娘もいますが、依存し合ったところで、一つにはなれないからね。
この映画では、戸田恵梨香さん演じるルミ子お母さんと、その娘である清香ちゃん(永野芽郁さん)が同じ出来事をそれぞれの目線で描いています。
一番、うんうんと納得できたのは、妻を裏切って幼馴染の女性と浮気を続けていた父親の浮気現場に乗り込み、父親へ「ママに謝れ」という清香ちゃんの場面。
自身の父親からの暴力におびえ、自分一人では何も出来ない男。そんな男が、妻や不倫相手に守られている姿に呆れてキレる娘にせの一言一言が、ごもっともすぎて。
自分のせいで、大切な誰かの大切なものを奪ってしまうという事実はとてつもなく辛いし、重い。その苦しさから逃げ出したくて、自死を試みる清香ちゃん、助かって本当によかった。
倒れていた清香ちゃんの顔に触れた時、ルミ子お母さんはどんな気持ちになったのかな、、、死んでまさかホッとしたりしてやしないのか、、とか思っちゃったよ。
ルミ子お母さんは最後まで、ルミ子ちゃんという娘でいたかったように私は思います。
女は2種類。母か娘か。
うーん、ここはイマイチ納得いかないのだけど、まぁ、女という性自認であれば、その人達は誰かの娘には値するんだけどね。
でも、なんとなく、そのカテゴリー分けよりも、一人の人間としてどんな関係でも立ち位置はそこでいたいなと思う。
また、母性とは人が持って生まれたものではなく、経験を経て身についていくものだという点についてはわかるかなーと思いながら、ついでにいうと、経験したからといって必ずしも持てるものでも無いとも思う。
そもそもその感情が母性というものから来ているのかどうかすら、私にはわからないのだからね。
3回目のデートで結婚を決めてはいけない
お互いにね。
原作の方の意気込みとかあらかじめ見ていて期待をしていたのですが、さほど「どんでん返し」的なところは無く、ちょっと残念ではありました。
ん~、まあ戸田恵梨香さんの怪演には見るべきところがありました。
同じシーンを母親と娘の視点で見ると全く違うってところがこの映画の売りなのでしょうけど、結局は全部娘の視点が正しくて母親の視点は自分の中で捻じ曲げて記憶してたということなのでしょうか。
最初は3.5を付けようと思ってたのですが、思い返すたびに点数が減っていきました・・・
今回は2.5でお願いします。
よくある愛憎劇
好きな先生におススメしてもらったから観た。
私には一般的な母や家族のかたちがわからない。なのでほとんどファンタジー映画のようで、共感があまりできず苦しくて寂しく感じた。
全員が誰かに愛を注いで注がれて、この世界にはもう純粋な愛など存在しないかもしれないと思った。そういう点で、普遍的な愛憎劇のようにも映った。
正直、死なんのかいって思ってしまった。結局ハッピーエンドかあ。もしバッドエンドだったら、もう少し気分が晴れていた気がする。でもそれは、原作が湊かなえさんってわかってたからかも。湊かなえさんの作品がこんなあっさり終わるはずがない!原作読もうかなあ。
私はずっと誰かからの愛を求め続ける生き物なのかもしれないとこわくなった。母になれないかもしれない。
先生はこれ見てなんて思ったかな。
トラウマレベル
原作未読。アマプラで視聴。
作り事!的な感想を書いておられる方も見受けましたが、ひと昔前はあるあるだったと思います。
戸田恵梨香の実母に対する思いは確かに異常性を感じますが(嵐の場面で、子どもなんてまた産めばいいんだから、なんてね)
義母に気遣う余り実娘が蔑ろになるってありがち。知人の母子の関係性を思い出してゾッとしました。
今現在は親なんてちっとも偉くないのでピンと来ないかもしれませんね。
でも逆に母子が共依存になったりしてて、女同士って難しい。
嫁姑の仲違いで夫に別宅あり、もありがちでした。
避暑地みたいな土地柄にブーフーウーの木の家的安っぽいメルヘンなおうち(だから簡単に壊れる)から作業服を着て夜勤に出かける夫(ここはどこ?)実家からどれくらいの距離があるのかしら?
絵画が趣味で出会ったわりにアトリエなし、とかいろいろ不自然な点は気になった。
最後妹が居酒屋やってそこそこ幸せそうなのはホッコリする場面でした。
これはホラー?(笑) まともな人物が登場しないヤバい世界。母親が好...
肩すかし感
愛が一番
小説既読の方の評価が悪いようですね。
戸田恵梨香が本当に細いです。薄幸な感じか醸し出されてます。
可哀想なお話しですが、当てはまる人はあまりいないケースだと思われるので自分ごととは思えず、どこか遠くの他人の不幸を覗き見している🫣気持ちになります。
あまり無いケースという意味は、適切な愛情をたっぷり受けて育った人の情緒や自己肯定感は普通もっと安定していると思われるからです。
ぱっと見には分かりませんでしたが、子供が独特に育った理由について、戸田恵梨香が演じた女性の母が毒親だとレビューされてる方もおられました。
きっちり育てられたようですが、手土産そのまま渡していたのはあれよあれよと結婚してしまい、そのあたりの礼儀作法はまだ習っていなかったからか?
他人事と書きましたが、そういえば知り合いにもいました、相互依存してる母娘。姉妹化してます。
娘さんは独身で表面上は結婚願望なく周囲を不幸にはしてないです。
あなたの大切な人を思い浮かべて下さい。海の上で全員は乗せられない場合、あなたは誰をボートに乗せますか。
評価:3.3
全333件中、1~20件目を表示