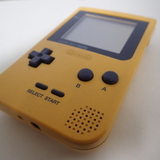ナイトメア・アリーのレビュー・感想・評価
全285件中、261~280件目を表示
欲に溺れた男が迷い込んだ悪夢の小道
1940年代のアメリカを舞台に、デルトロならではの怪しく魅惑的で危険な世界観の中で、自らを過信し欲に溺れた愚かな男の姿の物語が、おぞましくも美しい悪夢のように描かれていました。
美術や舞台背景、衣装の一つ一つが素晴らしく、本作の世界観を作り上げています。特に前半のカーニバルの不思議で怪しく可笑しな空気感がとても魅力的。一見スタンは賢く器用で、一座の人間は危険で胡散臭いように感じますが、そう単純な話ではなく…。
そしてスタンが独り立ちしてからの、危ないと分かっていながら惹かれてしまう・やめられない、そんな中毒性のある危険な橋を渡る様は、俳優陣の完璧な演技と空気感も相まってとても見応えがあります。
読心術と名ばかりの詐欺師によるアメリカンドリームの成れの果ては、踏み込んではいけない悪夢の小道に誘われた結果のように見えました。
闇に落ちていく主人公が悲しい。
◇暗い映画だ。主人公のスタンが自分の中にある闇のままに落ちていく。だけど回りはスタンが道をはずさぬよう、闇に落ちないよう、何度も何度もたしなめてくれる。それは言葉だったりゲンコツだったりタロットだったりする。だけどスタンが自分で運命を変えていってしまうのが見ていて悲しい。ケイト・ブランシェットと出会った後半も、彼の恋人 ( 妻 ?) が何度もブレーキをかけてくれるのにスタンは落ちていく。原作小説がノワールだから見終わってから暗い気持ちになる。
◇アカデミー作品賞にノミネートされている。ストーリーは分かりやすくて、本命の『パワー~』の「なんじゃコリャ?」感はないけど暗すぎて2度見る気にならない。(『パワー~』のほうはもう一度見ようかなという気にはなったが結局見てない )
蛇足
アカデミー賞ってアメリカ映画を盛り上げるイベントだとずっと思ってたのに、何年か前に外国の作品が作品賞にノミネートされててビックリした。私は映画関係者じゃないから日本の作品が受賞しても別に嬉しいとは思わない。(『ドライブ・マイ・カー』は面白くて2度見た。ちょっと長いけど。)
なんとなく読めるオチ
異形のカルト・ノワールを現代のエンタメとして見事に蘇生させた、ウェルメイドな人間ドラマ
原作は既読(扶桑社版)。
本作のリメイク元の『悪魔の往く町』(タイロン・パワー主演、エドマンド・グールディング監督)も、昨年シネマヴェーラで鑑賞済み。
結論から言うと、想像していたより、ずっと「まっとう」なノワールだったし、ものすごく「ちゃんとした」エンタメだった。
『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞も獲って、功なり名遂げて好きな映画を撮る自由を手に入れたデル・トロが、次回作で自分の偏愛する往年のフィルム・ノワールのリメイクをやるってきくと、どうしても「個人的」で、「マニアック」で、「趣味的」な映画になるんじゃないかと思ってしまう。
でも、実際に観た本作は違った。
むしろ、如何に「古い中身」を「現代のエンタメ」の器に注ぎ込んで「再生」できるかに腐心したような、とてもよくできたウェルメイドな人間ドラマに仕上がっていた。
デル・トロ、大人だなあ。
『ナイトメア・アリー』の原作は、かなり変わった小説だ(傑作だけど)。
出だしは、カーニヴァルの見世物小屋から始まる。芸人や猛獣使い、占い師、フリークスたちの居並ぶ一座に、若いマジシャンが入ってくる。上昇志向の塊のような彼は、とある経緯で女占い師とコンビを組んで読心術の舞台を務めるようになり、遂には秘伝のタネ本を手に入れ、一座で知り合った電気椅子芸の女性とボートヴィルに進出、夫婦で出演する読心術ショーで大成功を収める。
しかし、彼の野望はそこで終わらなかった。彼は「降霊術」を用いたペテンで、より大きな金と成功と名声が見いだせると気づき、霊媒稼業と宗教的活動にのめり込んでいくのだ。やがて彼は、とある女性精神分析医と運命的な出会いを果たす……。
各章の頭にはタロットのカードが掲示され、物語が運命に支配されていることを示す。キーとなるカードは、「吊るされた男」。貧困層の野心家が犯罪行為に手を染めて成り上がろうとする筋立てと、典型的な「ファム・ファタル」の登場という、ノワール特有の枠組みをもちながら、ショービジネスの内幕ものとしても、コンゲームものとしても読める独特の世界観を示す。なんというか、ネタのビザールな異形のノワールというか。やたら詳細にカーニバルの隠語や、手品のタネ、降霊術のトリックが明かされる、ある種の(『白鯨』的な)「情報小説」としての個性も強い。フロイト流の精神分析がふんだんに出てくるのはいかにも40年代的で、『白い恐怖』や、マーガレット・ミラーあたりのニューロティック・スリラーを想起させる。
主人公のスタンが切羽詰まったり、酒びたりになったりすると、思考の流れに則して「文体まで壊れてゆく」という、ジェイムズ・ジョイスのごとき文学的実験を、一般向けの小説でやっている点も面白い。さらには、アルコール依存の末、舌がんになって、最後は無一文で野垂れ死に同然で自殺したという著者ウィリアム・リンゼイ・グレシャムの人生も、作品と呼応するようで興味深い。
タイロン・パワー版の『悪魔の往く町』は、小説のヒットを受けて、翌年の1947年には公開されている。
112分と、当時としてはかなりの長尺の部類に属する映画でありつつも、とても原作の全部は入りきらなかったと見え、マジシャンとしての活動期の話や、スタンの過去と家族との関係性、霊媒師として積み重ねるペテンの数々などが、大胆にカットされている。また、ヘイズ・コードの影響で、ラストが大きく変更されている。
総じて、スタンという野望に燃える色男が、三人の人生を変える女との出逢いを受けて、どのような流転の生涯を送っていくかに、ぐっと焦点を絞った作りとなっているといえる。主人公も、明らかに犯罪者気質の強いピカレスク・ロマンである原作と比べると、かなり善なる部分をも内に併せ持つ穏当な描き方となっている(そうしておかないと、あのラストにつながらない)。
前半のカーニバルの描写から、ラスベガスで成り上がるまでの描写は、ノワールというよりはショービズもののノリで、トニー・カーティス主演のハリー・フーディニの伝記映画『魔術の恋』(54)を思わせる。後半、物語が降霊術関連の話になだれ込んでいくところも両作はよく似ていて、これは『ナイトメア・アリー』の主役の人物造形に際しても、フーディニを参考にした部分が大きいからだろう。
で、本作『ナイトメア・アリー』だが、映画のパンフにあるデル・トロのインタビューによれば、もともとは何十年も前(『クロノス』を撮っていた頃)にロン・パールマンに薦められてから、ずっと温めてきたリメイク企画らしい。
映画としては、明らかに原作準拠というよりは、『悪魔の往く町』準拠。すなわち、映画版のリメイクとしての色彩が強い。
物語の展開も、カットの仕方も、タイロン・パワー版にだいたい準じている。
ただし、前半の見世物小屋の描写、とくに原作にある「野人(ギーク)」の描写を、あえて再度復活させていて、ラストも「ほぼ」原作通りに修正されている。
まあ、「ここがこの映画のキモだ」と、デル・トロ監督も考えたんだろうね。要するに、ヘイズ・コードに阻まれて旧作では割愛せざるを得なかった、究極にビザールで皮肉で衝撃的なラストのギミックを、再映画化に際してきちんと補完してみせた、ということだ。
冒頭からの布石が、きれいに円環を成す、美しいエンディングだ。
なんとなく、ブラッドリー・クーパーの「アレ」は、ちょっと『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』のラストのデ・ニーロを思い出したなあ。
ああそうか、直前で「アマポーラ」が流れてたからか(笑)。
序盤のカーニヴァルから、デル・トロらしい映像美は充分発揮されている。
ただ、思っていたほどは、はっちゃけていない、というのが僕の正直な感想かも。
デル・トロなら、ヘネンロッターの『バスケットケース2』や、バーカーの『ミディアム』みたいな乱痴気騒ぎだってやれたと思うのだが、あくまで「控えめに」トッド・ブラウニングの『フリークス』を参照し、心からのオマージュを捧げた、という感じだ。
原作で出てくる「半分人間(ハーフボーイ)」みたいな面白ネタも、映像化を自粛してるし。
なんというか、一般の観客がウゲっとならない程度のマイルドさで、カーニヴァルの幻想性と郷愁を追求していて、『フリークス』ほどのぞっとするような「リアリティ」は、敢えて「封印」して臨んでいる。
主人公の手技の使えるマジシャンとしての要素や、当時のインチキ霊媒における定番だったラップ現象やエクソプラズムみたいなベタな要素も、ほぼ映画ではオミットされていて、あくまで「読心術師」が、そのままの勢いで終盤のアレに進むという構図になっている。
要するに、あんまり珍奇でクセの強い部分や、普通の客が観て趣味に走りすぎていると思うようなところを、監督は非常に注意深く避けて通っているようなのだ。
一方で、後半の「いかにもノワール」と思われる展開に入ってからは、完成度がぐっと際立ってくる。
とくに、ケイト・ブランシェット。彼女がとにかく、圧倒的に素晴らしい。
旧作の映画版よりも。……おそらく、原作よりも(笑)。
この人、台詞の内容と、その言い方の演技と、それを言っているときの表情の演技に、それぞれ「ズレ」をもたせてくるんだよね。
恐ろしいことを言っているときに、悲愴さを漂わせ、
攻撃的なことを言っているときに、弱さを漂わせ、
優しいことを言っているときに、非情さと狂気を漂わせる。
スタンに襲われてるときの演技とか、ちょっと余人に代えがたい壮絶さで、何人ものケイト・ブランシェットがひとつの身体のなかでせめぎ合っているかのようだ。
彼女のおかげで、本作の「ファム・ファタル」登場シーンは、たぶんデル・トロと脚本家が意図していたよりもずっと多層的で、深みのある複雑さをまとうことになった。
思想的な部分でも、『ナイトメア・アリー』は、現代の思想的な分断だったり、資本家と貧困層の対立だったり、集団のなかでの孤独だったり、今と共鳴できる部分をきちんと強調してきているし、「虐げられる弱者の連帯と精神的勝利」という、デル・トロ本来のテーマにも連関させている。
結果として、本作はピーキーで趣味的なカルト作というよりは、監督が愛してやまない変わり種のノワールを「今の一般的な観客でも咀嚼し、ふつうに楽しめる現代的な感性の映画」に再生させたものとなった。
まあ、それだったら、わざわざこんなクセの強い素材をリメイク元に選ばなけりゃいいのに、どうせやるならせっかくだし、とことんキッチュで、ビザールで、コテコテに頭のおかしい映画が観たかったよ、という意見ももちろんあるだろうが、デル・トロは、「そっちにはいかない」人だったということだろう。考えてみれば、そういうバランス感覚は昔からずっとある監督だよね。
サム・ライミやピーター・ジャクソンと一緒で、自分の出自や偏愛には噓をつかない「誠実なオタク」でありながらも、「ちゃんと」関わったみんながハッピーになれる映画を頑張って撮ろうとしているわけだ。
だからこそ。
本作はノワール好きや、カルト好きや、『フリークス』好きだけでなく、一人でも多くの「一般の人」に観に行ってほしいと願ってやまない。
で、逆にこの手のビザールな世界、あるいはノワールの魅力に目覚めてくれれば。
たぶん、それはデル・トロのいちばん望んでいることだろうから。
ダークな寓話
1940年代のアメリカを舞台に、金と酒で身を滅ぼした一人の男が描かれる。
良くも悪くも万人受けしない作品かと。私は結構のめり込みましたが…。終始薄気味悪く鬱々としている。ジャンルはサスペンススリラーだけど、スリラーというほど怖くもない。そしてラストの展開は大体読めてしまう。やっぱりね、こう来たか〜って。
タロット占いとか、読心術とかそういった類のものが好きな人は引き込まれるはず。とはいえ、描かれるのは人間の本質だったり愚かさで。
スタンは何に怯えたいたのだろうか?何を望んでいたのだろうか?
本作で語られること、例えば父親の影響や読心術の話などは、私たちにも大きく関わることなので意外と学べることがある。
なんと言っても注目すべきはケイト・ブランシェット。彼女の妖艶さに加えた怪演っぷりには息を呑む。そして、ウィリアム・デフォーの凄さを改めて実感した。
ずっと引っかかっているのが、あの大富豪の老人の用心棒を演じた人誰だっけ?(エンドロール見過ごしました)。
めちゃくちゃ見る顔なんだけど、名前が出てこない、、、。知ってる人いれば教えてください🙏
【”人道外れし者、蠱惑的ラビリンスに迷い込み自らの野心を果たすべく謀略を画す。”善悪、美醜、貧富。相反する価値観を包含したサスペンス・スリラー。魅惑的且つ魔窟の如きギレルモワールドを堪能する作品。】
ー 冒頭、荒涼とした一軒家で男が重い荷物を引きずり、床に開けた穴に放り込み、マッチを擦り躊躇なく穴に投げ込み、家は炎に包まれる。男は、平然とした顔で家を後にする・・。-
◆感想
・印象的な冒頭のシーンが、ラストでもう一度”細部まで”映し出される。そして、その男、スタン(ブラッドリー・クーパー)が善性薄き男である事が分かる。
・汚れた姿のスタンは、”獣人”をメインの出し物にする怪しげなカーニバルと出会い、率いる男(ウィレム・デフォー)に気に入られ、タロット占い師ジーナ(トニ・コレット)、後に恋人になる”感電ショー”の人気者モリー(ルーニー・マーラ)とも関係性を築き、を磨いていく。
- ”獣人”は”こんな筈じゃなかった・・”と何度も繰り返し、最後は雨中に放り出され、息絶える。そして、ジーナのタロット占いは、独立するというスタンの不吉な運命を言い当てていた・・。-
・都会に進出した、スタンはモリーを助手にして、読心術師として名を上げる。そんなある日、出会った謎めいた心理学博士のリリス(ケイト・ブランシェット)。
- スタンと、リリスの駆け引きが面白い。観客の前で、”バッグの中身を当てて・・”と挑発するリリス。スタンの読心術で辛うじて危機を脱するが・・。
ブラッドリー・クーパーと、ケイト・ブランシェットの瀟洒な意匠に囲まれた部屋での駆け引きは一見に値する。妖艶とした微笑みを浮かべ、スタンを挑発するファム・ファタール、リリス。ー
・そして、リリスから紹介された”訳アリの富豪”エズラ・グリンドル(リチャード・ジェンキンス)は”亡き恋人”の出現を要求する。
- モリーを”亡き恋人”に仕立てようとするスタンであったが・・。-
<年月は流れ、再び身をやつしたスタンが訪れたカーニバル。主人の脇には、以前にも見た母親を胎内から殺した”クレム”が同じようにホルマリン漬けにされている。
主人は”読心術は時代遅れだ・・。獣のような恰好で舞台に出るのはどうだ・・。”とスタンに告げる。
それを聞いたスタンは、自らを嘲笑うようにヒステリックな声で笑う・・。
今作は、人道を外れた者が、巡り巡ってその報い受ける、シニカル且つ耽美的で蠱惑的な因果応報の物語である。>
業ですかね。
人間でいられるか、ギークになるのか
映像はかなりショッキングな連続なのですが、ストーリーは特にラスト20分くらいから落とし所は見える感じでした。
ただ、人間の業というかドロドロを上手く描写してこわいながらも惹かつけられました。
ただ、シェイプオブウォーターと同様、映像の色使いガ鉛色というか、閉塞感のある映像が続くのがどうにも個人的には抑圧感が強くて疲れました。
とても重厚な作りで見応えがあった。
美と栄光と破滅の超特急
初めてギレルモ・デル・トロの映画を観ました。ハッピーエンドではないですが、ストーリーはわかりやすく、「七つの大罪」をテーマに幻想的な世界観ですっかり没入してしまいました。
舞台は1939年のアメリカの田舎町。そこに流れ着いたのは主人公スタンは町のカーニバルで行われているショーをタダで観た見返りに後片付けの手伝いをさせられる。カーニバルの団長に気に入られたスタンはスタッフとして働くことになった。ある時、読心術を扱える老人ピートと出会い、彼の人生は大きく変わってゆく。
読心術を使った降霊術をスタンは金儲けしようと目論むのですが、絶対ロクな目に合わないなと思いました。そして、スタンの耳がある人物に銃で撃たれるシーンがありますが、結構グロかったです。自業自得かな、と思いましたが、最終的には思いもよらぬどん底になるとは思いませんでした。
かなり人間性の本質を突いている
手の内を明かして育ててくれた世界から、 強い言葉で脆い自分を隠す権力と金の世界へ
ブランシェットとルーニーの久々の共演を楽しみに見ました。時代背景も舞台設定も好みでした。
フリークスとか見世物とか悪夢に惹かれる気持ちがムクムクと出てきた。家族など身近な人への愛憎入り混じる感情や後ろめたさや過去を美化する心情、誰だって多かれ少なかれ覚えがあると思う。そんなことを考えながら見た。
職場は屋外で雨が降っても笑顔があってチョコを食べて本を読んで幸せなモリー、寒くて雪ばかりでも暖かい室内に居られるが幸せでないモリー。ルーニー・マーラ、ますます輝いていた。
鏡、煙草、ラジオ、本、占いカード、鍵、腕時計、お酒など小道具全部が効いていた。横にJesus、その真ん中のsから始まって縦にsavesとあったネオン「イエス(神)は助けてくれる」。最初は全部が灯っていたのに帰りはJesの部分だけ灯りが消えていた。何だろう?usavesとなるから「助けない」になった?多分。冒頭のギークの場面はかなりかなり苦手なので指の隙間を少し開けつつほぼ目隠ししてた。
フライヤーその他に「ショービジネス」の世界の話とあったけれどそんなんじゃなくて見世物稼業だ。だからこそ、その胡散臭さといかがわしさに私たちは惹かれる、貧しくても金持ちでも。
アンティークなミステリー
いささか長さを感じる150分
ある男の宿命を描くこの作品、デル・トロ監督特有の深みのある世界観は、それに見合う豪華キャストたちの濃厚で見応えのある演技に、デル・トロ映画のファンに限らず一定以上の満足度は感じられると思います。
ただ原作は古典作品であり、プロット的には意外性はなく150分はいささか長く感じます。特に、途中のジリジリした展開はやや飽きてしまう印象も否めないかな、と。
そういう意味では、逃げ場のない劇場鑑賞が望ましい1本とも言えるかもしれません。勿論、多くのシーンが全体的に暗く、深く、細かい造形で作り込まれている点においても、液晶画面ではそのコントラストを押さえきれないでしょう。
ま、サーチライトなので、Disney+でわりと早い時期に配信されるんじゃないかと思いますが…
オスカー候補だけど、まあまあ
宣伝にあるようなサスペンスとかノワールというようなイメージはありません。
「人生の絶望」といって肯定的に評価する人もいるかもしれませんが、話は遅いし盛り上がりやサスペンス、スリラーはなく、よく言えば淡々と悪く言えばダラダラしているので、退屈な映画といってよいでしょう。
個人的には何となく重厚で少し幻想的な画面なので結構好みです。
大まかなストーリーはわかりますが、「あの人なんなの?」「どうしてそうなるの?」「その話どう関係あるの?」みたような疑問がたくさん残ります。多分原作読めば微妙な心理とか描いているんでしょうが、映画では省略しているので結構???ですね。
とにかく2時間半かける作品ではない。1時間半で十分。
全285件中、261~280件目を表示