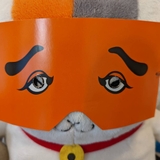土を喰らう十二ヵ月のレビュー・感想・評価
全125件中、41~60件目を表示
70代男性版の『リトル・フォレスト』
ずっと気にしていた作品ですが、11月の大作の公開ラッシュに4週遅れでようやくの鑑賞です。
まずは何はさておき、予告編から目が釘付けになる土井先生監修の精進料理。子供には理解できないけど、大人になってみれば大枚叩いてでも食べてみたい料理のあれこれ。作品内でも真知子(松たか子)が完全に胃袋を掴まれていますが、さもありなんと言わざるを得ない説得力でお腹の鳴りが止まりません。そして、こんな調子が1年分続いては「リアル垂涎」しそうだと感じている中盤、物語は動き出します。
そもそも観る前に抱いていた本作への印象は『リトル・フォレスト 夏・秋(14)&冬・春(15)』ですが、概ね間違ってないと感じました。これらはまさに「死生観」のお話です。二つの作品の違いは単に主人公が「20代女性」か「70代男性」であり、若い時に思い悩む「生きる意味」と年齢を重ねて逃れようのない「死ぬということ」という、一見真逆の話のようでありつつ結局は生と死は表裏一体なことを「自然」と相対しながら気づいていく物語で、どの世代にもこういう生活に憧れる理由がまさに「生きている」「例外なく死ぬ」意味を直感的に感じられることが想像できるからなのだと思います。
一般論として、「死」には当然のようにネガティブな印象がありますが、劇中で亡くなり送られるある人物の「葬式」という儀式で、集う人たちが笑い合って故人にいて語らう様子を見ると、やはり重要なのは「生き方・生き様」なのだなと思いつつ、やはりツトム(沢田研二)が仕切る「通夜振る舞い」にまた涎が止まりません。あぁ、美味しいそう。。w
お腹は空いたけど心は満腹になりました
2022年映画館鑑賞69作品目
12月4日(日)フォーラム仙台
リピーター割引1100円
原作未読
監督と脚本は『ナビィの恋』の中江裕司
13年前に妻を亡くし長野の山奥で自給自足の生活をしている老作家の話
老作家は口減らしでまだ幼い頃に禅寺に預けられ13歳で脱走した
時折仕事で尋ねる女性編集者とは男女の関係になりつつあった
老作家は食生活の1年間をエッセイで書き記すことにした
地元には妻の母が一人暮らしをしている
ある日義弟夫婦に頼まれ義母を家を訪ねると義母は亡くなっていた
義母の葬儀は筋違いだが老作家の自宅で行われることになった
老作家は遺影も棺桶も地元業者に頼み女性編集者に助けられ料理を作り義理の弟夫婦が坊さんを呼んでないのでお経を読んだ
そのうえ遺骨も預かることになった
冒頭のジャズっぽい騒々しい音楽はいらない
車と自然の音だけで良かった
タイトル出しが好き
主人公が作家という設定を有効活用している
殆ど吠えない大人しい犬が愛らしい
一般的には室内で飼うタイプじゃないが豪雪地帯なら当然
馬鹿犬とも言われるが実際は賢そうでユーモラス
後ろ姿にも悲哀を感じた
いるといないとでは大きく違う
身勝手な義理の弟夫婦が面白い
かかあ天下なところも相まって
主人公が決して怒らずお人好しな点もなかなか
真知子が乗ってくる車が松本ナンバーから最後は横浜ナンバーなっている
芸が細かい
昼飯食べないで昼過ぎに鑑賞したので空腹感が半端なかった
小僧時代に禅寺で精進料理を覚えた作家のツトムに沢田研二
担当編集者の真知子に松たか子
ツトムの亡くなった妻の弟の妻・美香に西田尚美
ツトムの亡くなった妻の弟・隆に尾美としのり
チエの遺影を作成した写真屋に瀧川鯉八
ツトムが小僧時代にお世話になった禅寺の和尚の娘・文子に檀ふみ
チエの棺桶を作ってくれた大工に火野正平
ツトムの亡くなった妻の母・チエに奈良岡朋子
必見!仙人ジュリーの自給自足お料理教室!! 人はやがて対人関係を卒業し、自然と一つに...シニア版"リトル・フォレスト"映画
少年時代に京都の禅寺で精進料理の作り方を教わった著者が、記憶をもとに1年間に渡って身近な食材で作り続けた料理について綴ったクッキングブック兼味覚エッセイを原作とした自給自足の食生活映画。
雪深い山荘で気ままに暮らす初老の男の一年の食事、それに連なる他者と自然との交流を通して研ぎ澄まされていく彼の死生観。
自分の身の周りの自然と向き合い、土と格闘しながら何か月も前に仕込んだその実りを喜びとともに口にする…そこにある些細な現実に一つ一つ感謝しながら生きる生活は素敵ですが、それと同時にほぼ自己完結して人と人との友愛・軋轢と対立する生き方でもあり、ただそこに在ろうとするのかそれとも我を撒き散らし合いながら爪痕を残すのか、その相克とバランスを問うた作品でもあると感じました。
何はともあれやぱりジュリーファンがその客層の大半ではあるかとは思いますし、その向きに決して不興を買うような内容でもないと思いますが、そうではない層にもそうではない層それぞれにそれぞれの形で刺さる作品ではないかと思います。
門前の小僧習わぬ経を読む
この作品が水上勉のエッセイが原作という理由だけで観に行きましたが、中々興味深い作品でした。
私の中での水上勉という存在は、高校時代(半世紀前)に日本映画の名作を見漁っていた頃の名作映画の原作家という印象が強く、それで原作も釣られて読み好きになった作家さんでした。
その水上さんが一時期でもこういう生活をしていた事に驚きましたが、大正・昭和前期生まれの人ってこういう根本的強さをまだ持った人が多くいたような気がします。
更に、少年時代の禅寺での修行によって“三つ子の魂百まで”ではないが、そこで習った“生きる”ことの原点を身に付けていた人だからこその達観なのでしょう。
私らの様な昭和中期以降生まれの人間には環境が揃わないと中々出来ない様な自給自足生活で、個人的には非常に羨ましかったです。
ただ、同じエッセイが原作の作品だと『日々是好日』の方が映画自体の面白さは感じたな。
人は達観した人生より、自分に近い未熟(不完全)からの成長の方が見たいですからね。
土を喰らう 旬の膳の映画
水上勉の晩年に書かれた生活と旬の料理のエッセイ、を原作にし中江裕司監督と料理家土井善晴氏が脚本にしたフィクション
原作はずっと昔に読んだ記憶があるけれど、歳の離れた恋人で編集者の真知子(松たか子)とやり取りする物語は記憶にありません。
自然の光の中の撮影が美しく、旬の素材が土から芽吹く存在感が素晴らしい。
ちょっと暗い家の台所。昔あった土間にタイルの洗い場が懐かしい。自給自足の生活には土を流せる洗い場は必須。
とにかく旬のものを損うことなく食す膳がこの映画の魅力。
土に根ざした生活、自分のありのままに生きているツトム(沢田研二)は全てに達観している様に見える。
恋人?という設定の真知子を旬の美味いもの、本当の精進料理でもてなし自分の皿のものまで与える。
それを美味しそうに食べる真知子の姿にご満悦。
時にはマチコ、マチコと呼び手伝わせる。
自分との距離感がパートナー(伴侶)というよりも
愛犬のサンショとかぶって見える。
人恋しさもありマチコと共に生活するも家族ではなく、ただ時を過ごしているように見える。
ツトム自身が倒れ自分の健康が損なわれてからは
「独りで生まれて独りで死んでいく」と言う、このくだり。
世捨て人の義母の葬儀を取り仕切り、
やはり人は人と生きていることを感じたはずなのに…
迷惑をかけたくないという思いもあるだろうけれど
ちょっと最後が独善的に見えた。
「昔の人は旨いもん食ってたんだなあ」と言う火野正平が素直。
旬の料理で日本酒が飲みたくなる。
贅沢の極み
地に足のついた、土の匂いのする映画
タイトルなし(ネタバレ)
最愛の妻を13年前に喪い、長野の古民家で一匹の犬一匹と暮らす作家のツトム(沢田研二)。
ツトムのもとを訪れるのは、ひとり暮らしの師匠である年上の大工(火野正平)と女性編集者の真知子(松たか子)ぐらいだ。
ここのところ筆の進まないツトムに対して、何か書いてくださいと迫る真知子に気おされて決めた随筆のタイトルは『土を喰らう十二ヵ月』。
幼い時分に修行に出された禅寺での出来事を交え、山深い村でのひとり暮らし、特に食べることに焦点を当てて、思いつくままに綴ろうというものであった・・・
といったところからはじまる物語で、立春をはじめ短い文章とともに二十四節季のいくつかが、そのときどきの暮らしとともに映し出されます。
丁寧に撮られた映画、というのが鑑賞後の感想で、これほど丁寧な映像は近頃珍しい。
ツトム演じる沢田研二は年を経て、かつてのスリムな印象は霧消したが、独特なユーモアセンスがにじみ出ていて好演。
ちょっと色悪的な雰囲気もあって、料理する様などに独特の色気を感じます。
料理を担当したのは、料理研究家の土井善晴。
手間暇かけて素朴な材料の良さを活かした素朴な料理が素晴らしい。
(「料理は簡単でいいんです」といつも話してるが、映画に登場する料理の数々、手間暇かかってますよ)
映画に独特のユーモアを与えているのは、沢田研二のほかにも、亡妻の老母チエ(奈良岡朋子)や義理の弟夫婦(尾美としのり、西田尚美)などがいて、特にチエを演じる奈良岡が素晴らしい。
(遺影の写真の表情がまたいいんです)
チエの葬式で村人たちが、大きな数珠を回しながら念仏を唱えるのも興味深い。
(キリスト教のロザリオを思い出しました)
監督・脚本は『ナビイの恋』の中江裕司。
監督らしい映画です。
(巻頭、ビートとリズムの効いたジャズではじまるあたりも、ちょっと人を食った感じで、独特のユーモアを感じますね)
適度に運動して‼️❓まともなものを喰い‼️❓それなりに恋をしたら‼️❓
タイトルなし(ネタバレ)
土と植物と生と死が食によって繋がっている。
季節ごとの主人公のモノローグ(台詞が原作からの引用なのかは分からないが、すごく胸に響く言葉)と、折々の山の幸を収穫し調理する姿だけでずっと見ていられる。冒頭の山菜(ヤマゼリだったか)を炊きたてのごはんに和えるカットで思わずおいしそうと声が出てしまった。沢田研二の語りの声がまたいい。
ストーリーは義母の通夜ぶるまいを承に、主人公自身の行く末の話となり転結が描かれる。映画の展開上必要だとは思うが、食の主題とのつながりは若干ぼやけたように感じた。死を意識しつつ「生きるために食べる」というところに最後は戻ってくるのだが、せつない。
五感で感じる映画
四季の移ろい、食を含めて自然の豊かさを五感で感じる映画でした。しいんとした田舎の古民家で登場人物が食べる「音」がやたら響きます。耳で味わうことができるのです。そして、ツトムが雪からほうれん草を取り出すシーンや、 蛇口の水で野菜を洗うシーンは、本当に冷たい気分になるんです。ほくほくした小芋を味わうときは、自分もアチチ、と思いながら見てる。村の人たちに評判のいいゴマ豆腐も、無意識に想像しながら自分も味わっている。いつのまにか、自分も体験している、そんな映画でした。
沢田研二さんも松たか子さんも、ほかの共演者さんたちも自然な演技で素晴らしかったし、映像的にもとても美しかったし、最高、といいたいところですが、ストーリー的に疑問を感じてしまったのは否めません。死生観に浸って「みなさん、さようなら」って死ぬ覚悟はいいけれど、このまま死んであとに残ったサンショのことは考えていないのかしら?とか思ってしまいました。
でも、最後の沢田研二さんの歌が素晴らしすぎて、疑問なんて吹き飛んでしまうくらい、観終わったあとすがすがしくなります。こんなに心にしみる歌を歌う人だったんですね。子どものころの流行歌手といったイメージだけでしたが、歌い方も声も伝わってくるものが素晴らしい。歌を聞いていてここまでじいんとしたのは初めてです。すごい歌手だと思いました。(今さらですみません)ぜひまたTVでも歌っていただきたいです。
ジュリーにオファーしてくださってありがとう
正直言ってキネマは不満だった、納得いかなかったので、これがあって、ほんとに良かった。よくぞジュリーにオファーしてくださった。
マチコが車でやってきた長野の家では、ツトムが炊飯器ではなくかまどでご飯炊いて、蛍光灯ではなくランプを灯りにして、ストーブではなく囲炉裏で暖をとってる。時代はいつ?w
電話が使えるんだから電気は来てるのに。
食事も同じ、肉も魚も卵も食べない冷蔵庫の要らない暮らし。時代は関係ない、自分がどう生きるか。
拘り強い。芸術家だ、言っちゃ何だが偏屈だ。
いやー。ぴったりじゃないですかw
雪深い長野であんな大きな窓のある家が囲炉裏でどれだけ暖まるか。冬は寒いのが当たり前なんですね。抗わない。
弟夫婦は普通の人だ。拘りなさそう。肉も魚もしっかり食べてそう。姑やツトムを同類の偏屈だと思ってそう。だから姑と折り合い悪い。
姑が亡くなって。姑と同じように独り暮らしてたツトムは独り暮らしをやめようとする。気持ちはわかる。いつ自分だって姑みたいになるか。一方で、ツトムは奥様を亡くしてる。亡くなった時、奥様には自分がいた。『いた』けど亡くなって、ツトムはきっと無力感でいっぱいだっただろう。ずっと遺骨を手放せない。姑と奥様の何が違うのか。きっと考える。
以前、人間が生きてれば老いるのが当たり前で、枯れて朽ちていくのが美しいんだとインタビューに答えてらしたジュリー。煩悩の塊みたいな芸能界にあって、お坊様みたいなことをいう人だと思ってたらぴったりの役が来たw
まるでこの映画のために作ったかのような96年の『いつか君は』を主題歌にしたと発表されてから今日まで何度リピしたことか。
食と生き方、そして死に方。
沢田研二が演技をしてるのをあまり見てません。
かなり昔ビールのCMで自然でいい感だったのと、
魔界転生は、、あれは人間じゃなかったな、、、決して優れているとは思わないんですが、独特の抜け感というか、自然な感じが素敵だなと思う人です。
嫌な感じの西田が新鮮。
壇ふみは佇まいが素敵すぎる。
松たか子は前半もっさり後半仏頂面、主人公に人生振り回される可哀想な役回りであったが的役であった。
話は精進料理と自然の中でつつましく生きる作家の話し。個人的には俗な部分である彼女との関係なんかもっと掘り込んでも映画として面白かったと思うんだけど、あえて触れてない。
ある意味身勝手な作家の食と終活を描いただけの話しなんだけど四季を愛で、その恵みをいただく生きかたは日本人にはビンビン来る。
どの料理も美味そうで身体に良さそう!
しかしまあ、そんな生活していても病気にはなるし、いずれは死ぬんだなと、、だったらジャンクフードにまみれ飽食して死ぬのも対極として有りだな、、などと色々思うことあり。
身も心も洗われる様な映画だった。
美味しそうなお料理と日々の移ろいを眺める時間。
作家をしながら山中の家で身の回りで採ったものをいまだく、自給自足に近い生活を送るツトムさん。
冷蔵庫はないみたいだからお野菜は漬けるし、ご飯は釜で焚き火で炊くし、季節ごとに収穫できるものをシンプルに調理して食べる。
幼いときに修行したという京都のお寺での経験やお父様の教えを実践するツトムさんが素敵だった。
土井善晴さんが監修されているという、シンプルながらとても美味しそうな料理(釜炊きごはん、お芋のいろり焼き、山菜、たけのこ、梅干し、ゆず味噌大根など)も素敵だったなあ。
しかし通夜振る舞いをある食材のみでメニューから組み立て、ほぼ自分で作るツトムさんがすごすぎる…(参列した地元のおば様方のウケもばっちり)。
食材はほとんどスーパーマーケットで購入する私たちは忘れがちな気がするけど、食べ物はすべて元々生きていたものたちで、植物には旬がある。
自分で収穫したものを、丁寧に向き合いながら調理し、いただくこと。
料理に限らず、例えばお掃除だって、自分の手で床を掃き清めたり、雑巾がけしたりすることは、その対象に向き合う、ということだ。
そしてそのように食べるものや暮らしの上で接するものに時間をかけて向き合いながら生きることが、いわゆる「丁寧に生きる(暮らす)」ということなんだろうなあと、本作を観ながら思っていた。
(とりあえずほうれん草の根っこはこれまでのように切り落とさないで調理してみようと思う…)
「効率的」とか「便利」はそれも確かに豊かな暮らしに不可欠だし、正直今さら文明の利器は手放せない。
ただそうだとしても、「目の前のものに向き合おうとすること、知ろうとすること」は放棄はしないでいたいなあ、としみじみ思いながらスクリーンの中でゆっくり進んでいくツトムさんの生活や山の景色を眺めていた。
良い時間だった。
少し残念だったのがストーリー。
特にこの作品においての真知子さんという存在はいったい何だったのだろうと個人的には腑に落ちてない(松たか子さんは素敵だったのだけど)。
あとツトムさんの義弟夫婦の感じの悪さと残念っぷり(最初から最後まで良いところ一個もなかったぞ…)もこの作品に果たして必要だったのか…?と少し疑問。
個人的な感想としては、本作に関しては起伏のドラマなんていらないから、ツトムさんの訥々と語られるモノローグや、日々の心のゆらぎ、地元の人たち(ツトムさんの師匠の火野正平さん、素敵だ…)とのやり取り、山の風景やお料理の様子のみに焦点を当てて走り抜けて欲しかった気がしなくもない(原作?原案は未読なので原作に沿ったものなのかもしれないけど)。
いろいろ考えさせられ、誰かと語りたくなる映画です
自然を喰らい生と死を見つめる
「生きることは喰らうこと」
「生きることは喰らうこと」。
自然なかで自然に感謝して生きるという、現代では難しくなった昔のような生活を長野で体現している作家を主人公とした水上勉さんの作品を原作にした作品。
私のような効率化自体を目的化してしまっているような生活とは真反対のような生活であり、とてもすごいなと思いました。毎回の食事を丁寧に手作りし、それに使う食材も自分で調達して。
出てくる料理がどれも本当に美味しそうで、映画の題名通り12ヶ月の四季の移ろいがとても美しく表現されていました。
経済的には豊かではなかったとしても、「食」という軸となるものを勉さんはしっかりと持っていて自分の道をしっかりとゆく素晴らしい生活をされているなと感じました。
また、松たか子さん演じる恋人との関係や、そのお婆さんや地域の人達との関係も温かくていいなぁと思いました。
全125件中、41~60件目を表示