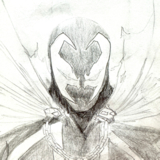ベネデッタのレビュー・感想・評価
全29件中、21~29件目を表示
久しぶりのヴァーフォベン作品
17世紀の話 宗教やペスト、同性愛と現代と変わらない。偉いさんは、言う事聞かないのは排除したいんだな。ベネデッタは香里奈みたいな雰囲気だ。
自分をムチ打っても悪魔は出ないな。
ベネデッタ
最初の奇蹟から掴まれたし、展開がずっとスリリングで飽きさせない。
バルトロメアの参入で、ベネデッタが苛まれながらもどんどん変容していく様がたまらなく良かった。
彼女の聖と性のバランスが絶妙で、両義を体現する主人公ベネデッタはホント見る者を揺さぶってくれる。
・・聖痕騒ぎからやがて院長へ、
からの、刑場の場面はホント骨頂でした。
宗教(組織)の欺瞞な感じの描き方も良かったし、はなから信じていなかった(であろう)元娼婦の院長フェリシタの振る舞いも、ベネデッタという訝しげな聖女によって最後ひっくり返ってしまう。
まったく人間ってやつは腐りおちて堕落することもできるし、奇跡だって起こせる(にちがいない)
そんな人の無限の可能性を感じてしまった
何故か厩舎での裸の二人をみてそう思えた
この罰当たりが~
ポール・バーホーベン監督作品。御年85歳。
木彫りのマリア様の下半身をディルドにしちゃうのは罰当たり過ぎますな。
ベネデッタはいわゆる演技性パーソナリティー障害だったんでしょうね。
もっとも、ベネデッタを誘惑して開発したのバルトロメア。お下品な娘。
クリスティーナはベネデッタが好きだったから飛び降り自殺したのでしょうか?
可哀想でした。
熱湯
聖痕
苦悩の梨という拷問器具
どこの穴に刺し込んだのかなぁ
痛みがなにより確かな深い信仰のしるしでもあり、異端の証の実証に使われる。おそろそや。
ポール・バーホーベン監督、歳をとるほどにどんどん屈折して変態になっていきますな。
OPPAI
かなり口コミが良さそうだったので鑑賞。今年1本目のR18+作品。
んー分からなかったというか相性が悪かったというのか…作品のテンションに乗り切れない自分がいました。
女性同士の性描写のシーンは思っていたより映っていなかったので興奮も何もなく、拷問シーンは映ってないけれどマジで痛そうでした。シーン自体は多くないのにこんなにもゾッとさせられるとは思いませんでした。見る人によってはゾクゾク具合が限界に達しても仕方がないレベルだと思います。
自分は宗教とかは普段触れないので、何に崇拝しているのかとかもチンプンカンプンです。そのため、黒死病がたまたま起こらなかった地でベネデッタを神の嫁として讃える絵面の凄さは、圧倒的ではありましたが、よく分からないままでした。
火炙りにされる直前で、ベネデッタを信じている市民が大逆襲を仕掛けて教皇大使を殺すまでいきますが、それほどこの時代の信仰心は強かったんだなと思いました。めっちゃ殺すやん笑となりましたが、フィールドに大きな変化が無いので、絵面のインパクトはそこまででした。
完璧に監督の性癖が全開な映画でした。とにかく全裸を見せまくるので、R18+に相応しい作品にはなっていました。自分にはどーにもハマりませんでしたが。御免被る。
鑑賞日 2/19
鑑賞時間 19:30〜21:50
座席 H-4
タイトルなし(ネタバレ)
女性が虐げられていた社会で権力を握るために、神からの刻印「聖痕」を矛にしてのし上がり、民や周囲をコントロールしようとするベネデッタ。これは神からの使命か、はたまたペテン師か。倫理や信仰、男性優位社会に強烈な楔を打ちつける。あまりにも鮮烈な一撃。
・女にも性欲があることを剥き出しに惜しげもなく描き切る。よくぞキリスト像をあのような使い方にしてくれたというか…さすがというか、唖然というか…
・バルトロメアを男らの暴力から匿い、自分が神の申し子を名乗ることで男たちに虐げられてきた村社会にメスを入れるとか、そんなところでは確かにフェミニズムなのかもだけど。
ただ「痛みに耐えてこそ強い女」像は前作「ELLE エル」でも同じように描かれてはいたが、特にあの拷問シーンはどう捉えていいのか。ストレートなフェミニズム映画ではないし、前作同様、これはフェミニズム?なのか??と思ってしまう過激な性描写もしばしば。(ああも裸体晒しすぎて女優のダメージ気になる)フェミニズムどうのこうのよりも、倫理やモラルに揺さぶりかけたいどころか、なぶり倒して混ぜっ返したいってだけのような気もする。
今回はそこに信仰や神という視点を据え置いた。すごい変だし、ものすごい捻れている。見てる方の、ジャンル決めつけの脳みそを、ぐちゃぐちゃに混ぜっ返したい。野心と狂気しか見えない。
・ペテンなのかマジもんの超人なのかはどうでもよくて、「神」を引き剥がして丸裸にされたのは人間の欲とか業とかでした。ぐらいのことなんだろうとは思う。
・バルトロメアの恥辱の行進は、ゲースロのサーセイを思い出した。
神を信じる者は救われたのか?
同性との情欲に溺れる破戒尼僧?であるベネデッタが時に周囲を欺きながら、時に人間としての欲望に忠実に強く生きた話・・・といったら現実派、理性派の皆さんはなんとなく腑に落ちるかと思います。
ただ、私の評価は全く逆で「神の声を聞いたベネデッタが、同様に神を信じて疑わない善良な人々を当時、黒死病と恐れられたペストから救った話」と確信しています。いや、史実はそうなってますしね。
後者のスタンスをとった場合、捉え方によっては色情狂、そして異端とされるベネデッタを神格化することにも繋がり、これでは厳格な宗教界から総叩きにあうでしょう。
だから監督はわざわざバランスをとり評価を曖昧にするために彼女が肉欲に溺れるシーンは大胆に、より煽情的に描く必要があった訳です。
このシーンに至るまで監督の小出しの人の情欲の見せ方、盛り上げ方、煽り方は本当、一流と言わざるを得ません。必要悪?とはいえ、結果として随分と目の保養になったことをここに告解いたします!
話はちょっとそれましたが、ベネデッタは聖職者としては論外で完全アウトじゃないかという濡れ場シーン、そして最後まで確定演出を出さなかった聖痕の自作自演の疑い、神のお告げが基本夢の中で、たまに変な内容になり信憑性に乏しい様(笑)・・・などで彼女自身の信憑性という点で煙に巻きますが、終始一貫して変わらないことがひとつ。
「神の存在を疑わず、絶えず崇拝してること」なのです。これを示すシーンのひとつで、ベネデッタの遠くを伺う様な視線は神の指示をリアルタイムで仰いでいる様で印象深く、非常に好演だったですね。
これとの対比で鮮やかだったのが、元院長と教皇の存在です。どちらもベネデッタ以上に欲望まみれ(笑)ですが、「立場上、見かけ上は神を崇拝してるようにみえるが、心の底で神様なんかいる訳ない」と考えています。態度に如実に現れていて、こちらの演技も良かったですね。
彼らが悲惨な目にあって自滅した結果論からしても、「神を信じるか信じないかが問題」であり、個人の欲望の追求、倫理観の欠如などは、「神への愛」が前提としてあれば十分許容されるという主張が映画の中で示されています。
また監督がベネデッタが妄想を叫ぶ狂人、もしくは狡猾で嘘ばかりついていたのでなく、実際「神の声を聞いていただろう」シーンをさらっと入れていることにも注目です。
夜空を不吉な光(実は彗星の尾)で彩られたのをみて、聖職者は不吉の前触れペストの襲来の予兆だと言い民衆を煽りますが、それを制止する様に彼女は「神に守られている証拠」と言い、暴徒化するのを防ぐシーンがありました。
彼女はこの民衆への大声での説明(煽動)の前に「あれは彗星」みたいなことを独り言で呟きますが、これって実は彼女が生きた17世紀において、こと修道院の教育、知識環境においては知り得ない事実です。
またペストの感染経路についても相応以上の知識があったと言わざるを得ません。都市ロックアウトは想像の範囲内ですが、教皇の脚を自らの手で洗う際にペスト感染者(後に発覚)の脚に噛みついているノミを意識的に潰してます。
ペストは患者間で飛沫感染する他、ネズミなどに寄生するノミを媒介して人間にも拡がります。
彼女はこの知識がベースにあって感染経路をつぶす対策が出来てたんじゃないか、と疑わざるを得ません。ペストの感染経路のメカニズムなんて、もっと後の時代に判明したのは言うまでもなく、彼女のこの知識は、彗星の存在を認めたことに並び、時代を超えたオーパーツ(時代考証的にあり得ないもの)であると考えられます。
これらの先見的な知識が神によってあらかじめ彼女にもたらされ、最終的に同じく神と彼女自身を崇拝してやまない民衆だけが彼女に導かれペストの難から逃れた、というのが落とし所としては最適かと思います。
神を信じるものは救われる。その主義主張だけだと実につまらない映画ですが、その過程が複雑で美しくかつエロティックな良作でございました。
ネタバレかつ、長文失礼しました。
うそ
色々なテーマが絡み合う作品で、パンチの多いシーンが続くのだが、自分は表題についてのテーマに絞ろうと思う
『嘘も方便』 もっと言えば『鹿を指して馬と為す』 あの時代の狭いコミュニティの中に於いて、しかも科学が全然未発達で、宗教のみが人生観の殆どな世情で、勿論フィクションとは理解しているものの、あれだけの力強い女性が存在していたならばと言う仮定をストーリーに落とし込んだ監督の手腕に脱帽である 演出、編集としての主人公に偏重したカット、最後の種明かしの指摘でさえも強い意志で跳ね返す堂々たる勇姿 "神"という名を借りればそこに主体としての自分は消え去り、器としての肉体、強靱且つ薬物の力も図らずも借りてしまった意志が、単純に言えば"裸体"であっても恥の概念の削除という、禁断の実を食べる前のイヴと同化したかのようなエンドは、その世界観の滑稽さの上での気高さを演出されていた "毒をもって毒を制す" 全ての人間が出来ることではないからこそ、善悪を超越した一連の行動に、人は普遍性の上位概念を想像するのかもしれない
さて、自分だったら…凡人なので何も自ら行動せず、『苦悩の梨』を持った赤いベールの男のように石をぶつけられて殺されるのだろうな(苦笑
やっぱりすごい
ポール・バーホーベン監督の最新作が映画館で観れるという喜びを感じつつ、2021年に海外で公開されてから2年越しの日本公開で、やっと映画館で観れた!!という気持ちの方が強い笑 一時はビデオスルーになるかと思いました。
相変わらず良い人だろうが悪い人だろうが容赦なくボコボコにして描くポール・バーホーベン作!!
「スターシップ・トゥルーパーズ」だったり茶化してるのか、本気なのか分からない映画を撮るのが上手い!絶対に(100%!!)茶化しているんですが、本気で信じ込んでいる人には本気の映画になっているように作ってるし、「ブラック・ブック」や「ELLE」のように女性が差別や権力に反旗を翻す映画にもなっている。
また、本当なのか嘘なのか、最後まで分からない、この映画として答えを出さないというのもバーホーベン監督らしく、「トータル・リコール」でも「氷の微笑」でも嘘か本当か?どっちか分からないし、
「ブラック・ブック」ではナチス側もユダヤ人側からも差別を受ける主人公を描く、どちらが悪いかは描かない。非常に冷徹でフラットでフェアな監督だと思っています。
バーホーベン作の特長として、"まともな人が1人もいない"か、"1番まともそうな人が死ぬ"というのがあると思いますが、本作は後者で、とある人物が自害するシーンは衝撃的。まさに神の言葉(的な)ものに従ったが為に、1番大切な人を失うというもうどうしようもない悲しいシーンがあるのですが、このシーンでシスターフェリシタを演じるのは大ベテラン女優シャーロット・ランプリングで、このシスターフェリシタの境遇だったりラストに至るまで辛い。
主人公は幼少期より自分にたまたま起こった出来事を神の啓示と結びつけてしまい(最初の神の啓示が鳥の糞というのも馬鹿にしまくっていて最高です笑)、それゆえに一種の妄想に取り憑かれてしまう。ベネデッタは自分の見るビジョンが神からの啓示であることを最後まで一切疑わない。ここまでいくとある意味清々しく、ラストシーンの勇ましさと馬鹿馬鹿しさが共存する彼女の後ろ姿はどんな感情で観れば良いのかわからない笑
また、神からの言葉ということが当時の教会で女性が発言力を持つ唯一の方法であったことと、その言葉がある意味荒唐無稽なことであっても神の言葉ということであれば(それが怪しいと気付きつつも)従わねばならないというルールのバカバカしさを映画としてしっかりみせてくれます。こんな狂った世界で最初に死ぬのはやっぱり1番まともな人なんです笑 さすが、バーホーベン監督。
パンフレットやポスターまで、ポール・バーホーベンが大好きな高橋ヨシキさんデザインで、さすがの出来でした。
色んな批判を受けても全く映画スタイルを変えない84歳のポール・バーホーベンを見ているだけで1番元気が出ます笑
全29件中、21~29件目を表示