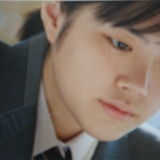こちらあみ子のレビュー・感想・評価
全116件中、1~20件目を表示
ハゲか兄貴か。ホクロかお母さんか。そういうことじゃ。
オレは広島出身だし、舞台はなじみある呉市だから、どうしてもひいき目はあるもんだが、「この世界の片隅に」に並ぶ呉映画の代表作といっていい。
「この世界の片隅に」がオレのおばあちゃんの話であるならば、これは、オレの話であり、オレの娘の話だ。
「こちらあみ子」
・
・
・
しかし、まあ、情報量の多いこと。これを21日間で撮ったとのこと。ちょっとどうかしているほどにヤバい。スゴイ。原作未読だが、本作を観れば、作り手がどんなに原作を愛し、咀嚼し、腹に落とし込み、作り上げたのかが、滴るように感じる。
オレはこのあみ子を特別な子とは思えないし、ましてや発達障害だという風にも思っていない。あえて言うなら、ノリ君の苗字が分からないところぐらいか。
■見える世界
カメラは基本、「ある視点」で少し距離をとってあみ子を描写する。時にあみ子からの視点となるのは、
・サチコのホクロ
・同級生の小坊主
の2点。
お父さんの新しい奥さんになるサチコをホクロオバケというあみ子にコウタは自分のハゲをみせ、わしははげか、兄ちゃんか?と尋ねる。あみ子は兄ちゃんだと答え、コウタは「そういうことじゃ」と返し、あみ子はへたくそなスキップで「お母さん♪」と喜ぶ。
実際にサチコと生活すると、ホクロばかり見てしまうあみ子。
しかし、臨月のサチコが病院から帰ってくるのを、猛暑の中、外で待つあみ子。そのあみ子をみて、「びっしょりじゃね」とサチコはあみ子の顔、頬を手で愛おしく(一方で執拗に)汗をぬぐう。この時にあみ子から見るホクロはなぜか小さくなっている。
ここで初めてあみ子から見て、ホクロオバケではなく、お母さんになったのだろう。
しかし、実は死産という結果で、あみ子の家庭は崩れていく。(オレはこの死産の理由が、サチコの崩れようからして、ちょっとイヤな想像をしているが、ここでははっきりと描かれていない)
もう一点、同級生の小坊主との会話。小坊主のある言葉を境に、風向きが変わる。(本当にカーテンの揺らぎが変わる!)そこから小坊主はあみ子からの視点となる。
子供は残酷だとか、無垢だとか、発育障害だとか、親からして、人間からして、そういうことではなく、向き合うきっかけは誰にだって必要だ。
この2点はあみ子の視点。そして大体を占める「ある視点」だが、これはラストとエンドクレジットでわかる。
「おーい、水はまだ冷たいじゃろ」と問いかける声は、エンドクレジットでトランシーバーが横に書かれた監督、いや監督だけでなく、オレらの声なのだ。
「大丈夫じゃ」と答えるあみ子。
「ある視点」とは監督のこの作品への誠実さの表れであり、またオレらの誠実なまなざしでなければいけない。
■予兆
落ちてこないミカンは、その後の誕生日の食事の悲しい出来事の予兆。
とうもろこしのビシャビシャは破水の予兆。
テレビで流れる「フランケンシュタイン」は「ミツバチのささやき」のオマージュと、そこから聞こえる悲鳴は、病院にいるサチコの悲鳴。
保健室でのチャイムの音の音程がズレるのは、その後の悲しい出来事の予兆。
玄関のすりガラスは不安を感じさせ、玄関からところどころ物語が展開する。
■お気に入り
あみ子が霊の音を感じ始めるところはちょっと「エクソシスト」を思い出し、家の階段もちょっと「エクソシスト」を感じさせるんだよね。だけどそれはホラー的な見せ方ではなくって、あくまで作り手が映画好きってことだろう。(サチコの伏せた髪はさすがに貞子ではないだろう)
ノリ君の腹キックを不謹慎に笑ってしまったり、保健室の先生役播田美保が妙に怪演で笑ってしまった。
追記
ちょいちょい挟む小動物
「僕らはみんな生きている」
そういうことじゃ。
文字から映像へ、あみ子のしあわせな跳躍
たまたま、まわりの人たちと原作本を回し読みししており、「そういえばこの本、映画になるらしいよ」と話題にしていた。イメージどおりの女の子のちらしや予告を目にして「わー、楽しみ!」と盛り上がりながらも、「いったい、どんな映画になっているんだろう…という不安というか、怖いもの見たさのような気持ちも、むくむくと膨らんでいた。
小学5年生のあみ子は、(傍目からは)自由気ままに生き、枠からはみ出しまくっている。同級生・のりくんを好きでたまらないあみ子が、こっそりと「赤い部屋(母の書道教室)」を覗き見ているように、読者もこっそりと、あみ子の真っ直ぐではちゃめちゃな言動を覗き見ている…気持ちになる。(ぼとぼとと汗がしたたり落ちるシーンでは、読み手の立場を忘れて「見つかった!」と叫びそうになった。)でも、映画はそうはいかない。暗闇の中とはいえ、無数の見知らぬ人たちと時間と場所を共有し、あみ子の物語を追うことになる。想像すると、自分が覗き見されているようで、何ともむずがゆい気持ちになった。
さて、本編。早速あみ子は、スクリーンの端から端をめいっぱい動き回る。教室が並ぶ校舎や川沿いの通学路を遠景で捉えた、ヨコ移動の繰り返しが印象的だ。粒のように小さくても、あみ子の生き生きした存在感は群を抜いている。「とても見ちゃおれない」と思っていた覗き見のシーンも、のりくんへの2度の告白も、不思議な明るさと力強さに満ちていて、文字から映像が立ち上がる瞬間を存分に味わえた。のぞき穴に閉じ込められていたあみ子が、スクリーンという広い活躍の場を与えられたのは、大正解・大成功だったのだ。
「弟」の誕生を控えた10歳の誕生日をピークに、あみ子の家はゆっくりと壊れていく。母は(ホラー映画さながらに)乱れた髪をテーブルに投げ出して反応しなくなり、兄はライオンのような髪をなびかせながらバイクで轟音を撒き散らす。そして成すすべのない父は、その日暮らしがやっととなる。けれども、あみ子の中では、彼らは何も変わっていない。(自分にきょうだいがいないからかもしれないが、)特に兄との関わりには、心打たれるものがあった。ベランダからの「霊の音」に日々悩まされ、追い詰められるあみ子を唐突に救ったのは、幼いころにグミの実を跳び上がって取ってくれた兄。(絶妙なコントロール!)幼いあみ子の好物を書き留めていた母も、あみ子との生活をつなぎ止めてくれた父も、それぞれにあみ子と繋がっている。
冒頭と同様に、画面いっぱいの道をひとりで歩いてきたあみ子は、広々とした海に出る。そして「あるもの」たちに大きく手を振る。映画ならではのラストと、エンドロールに寄り添う音楽の余韻が、じんわりと心にしみた。
帰り道、「えー、何かわかんなかった!」と小5男子は頭を抱えていたが、「好きやー」「殺す!」、「好きやー」「殺す!」の告白シーンの再現は、やたら面白がっていた。自分も、何かにあれほど情熱を傾けてみたい。そしてもし、子がそんな告白を誰かにしたら/されたら、本当にうらやましい、と心から思う。
側転のシーンはまるで奇跡。
原作が好き過ぎるので、どうしても映画単体として観ることができない限界を自覚した上で言うと、よくもまああみ子を演じられる子供を見つけてこれたものだと驚くほかなく、大沢一菜=あみ子を見ているだけで料金分の価値はある。なんだあの側転のシーンは。あんな映像が撮れたというだけで奇跡みたいなものではないか。
とはいえ原作から加えられたものがどうしてもプラスに機能しているようには思えず、そこは原作未読で映画を観た人とはどうしても同じ見方はできない。特に幽霊たちにサヨナラをするラストシーンは、どうしても大人の理屈で成長させられてしまうように感じられて、ラストのセリフともども蛇足であるように感じた。
さりとて、では原作とは違う表現として映画としてどう終わらせればいいかと考えた時になにか別案があるわけでもないのだが、作品としては大沢一菜ありきというか、大沢一菜に頼り過ぎではないかという印象ではある。
男系社会がゆえの男目線な少女の第二成長期
原作者が女性だからたぶん原作は大事な事は忘れていないのだろうが。
原作は読んでいないが、そんな事は絶対に無いと思っての映画のみのレビューなり。
発達障害の純粋無垢な行動を羅列するだけなら許せる。だが、あみ子はいつ女性になるのか?それがこの映画では全く描かれていない。
つまり、
「禁じられた遊び」だけで終わっている。
男にDVにあって鼻血を出す事。それが生理の訪れ?
隣に座る少年に臭いと言われる事が生理臭なのか?
いずれにしても、この演出家はそれを完全に見逃しているとしか思えない。そうであっても図式化されているにすぎない。
だから「特に」父親には、意識的に
存在感の無い俳優が選ばれたのだ。
従って、あみ子役以外は図式化された役者しかいないと言う事になる。そう、母親に至ってはホクロを付ける以外に母親としての心理は全く描かれていない。
従って「ルート29」では、同じ俳優を使って、女性になってしまってからの少女におかしな事をやらせる。それは形而上学的に出鱈目なことになってしまうのだ。
二回目の鑑賞になるが、もう一本の映画を見て、考えを変えた。
哀れみポルノを乗っこして、寧ろ、不快感を抱く。
子供の成長は例え発達障害であっても止まるわけではないし、人間の成長は男女関係なく進むのだ。
この映画では時間が進んだのは鑑賞時間のみ。
実に哀れな時間なり。
追記
「わたしたちの島で」アストリッド・リンドグレーン著を読む事をお勧めする。
黄色いトランシーバーは片方が失せているから、 もはや会話が不可能だと我々に解らせるサインだろう。
奈良美智を彷彿とさせるこの面構えったらない!(笑)「こちら あみ子」。
子どもは こじれてなんぼだ。
このポスターのスチール写真をもって、映画の価値は決まったと云うべきだろう。
傑作だと思うのだ。
映画を観ていない人でも、この写真は一度見たら忘れられないものね。
・・・・・・・・・・・・・
でも、中身は違った。
今村夏子原作。
「ポスター写真」のインパクトは天晴れだが、
実際の映画は、う~ん、だ。
非常に難解であり、多くの問題提起やヒントを視聴者に投げかける。
消化するのが難しい。
★の数は僕の好き嫌いで決めた。
思っていたのと違ったのだ。
ラッセ・ハルストレムやリンドグレーンの主人公たちのような、大人社会にはまだ染まっていない=生き生きとした子供時代と、その子供たちの生き様へのあくなき肯定・賛美を描いたストーリー・・とは違ったのだ。
恐らくあみ子は
(劇中、触れられないが)、自閉症スペクトラムや、多動性注意欠陥障害の「患者」にカテゴライズされる存在なのであろうが、
同居者は拳骨を握りしめて歯を食いしばり、あみ子との生活を耐えに耐えているのであり、
学友たちは自分をころしてあみ子のヤングケアラー役を背負い込み、
教師たちは特別支援学校に回されなかったあみ子との騒動を、教室や保健室でスルーするような態度にも出ている。
強情で聞き分けのない子どもに手を焼くと「きっといつかはこの子も成長して大人になってくれるはず」と親は自分に言い聞かせて、祈りながら耐える。
「誰に似たんだろう」とも思う。
でも快癒の可能性とか、希望の未来が見え得無いのであれば、
これはあの映画「どうすれば良かったか、」の前段に位置するだろう破壊的な世界なのだ。
尾野真千子の母も、井浦新の父親も、
あみ子には手を上げない。
というか もう既に疲れ切っていてその気力すらなく、母は金切り声の絶叫ののち床に伏しており。父は脱力感と諦念。兄は制御できぬ世界へと脱出し、
・・つまりこのあみ子による逆DVの家庭環境で、家庭が“死に体”になっているのだ。
物語はスッキリしない。
というか、非常に嫌な後味すら残す。
今村夏子があの「星の子」を書いたご本人なのだと知れば、「ああ、なるほどね」と思った。
歪んでいるのだ、この人は。
そして無理心中だけが回避されて映画は終わってしまう。
検索すればこの映画についての考察や分析の寄稿が山ほど読める。どれもこれもが歪んだ出来ばえゆえだ。
「あみ子はかつての私自身です」とか、原作者が言ってくれれば良いものを、我関せずの投げっぱなしの《虫唾の走る放置》に我々は取り残されてしまう。
ぞっとするばかりだ。
原作者とも対話は出来ないと感じた。
・・・・・・・・・・・・・
付記
「岬の兄妹」のレビューで触れた事だが、我が家では精神疾患の女の子を児童養護施設から預かって長く一緒に暮らした修羅場の経験があるもので、今回、作者のネタ探しの文章と、あと一歩を踏み込まない距離を固持する血の気のない創作態度には
共感が出来なかった。
鑑賞中は あみ子ではなく、父と母と兄の姿だけを凝視した。
心に寄り添える人が必要なのです。
今村夏子の小説「こちらあみ子」と同時収録された「ピクニック」は、さらっと読んでしまうとそこに潜む不穏な空気を理解できなくなるので注意が必要だ。なのでこの映画も予備知識なしに観てしまうとあみ子もただの変な子だとか親もダメダメだなぁとかしか感じないかも知れない。今も昔(映画の時代背景は80-90年代か)も世の中は「不寛容」が渦巻き、ほとんどの人々が自己中心で生きている。イガグリ頭の同級生(ノリ君ではない)や保健室の先生みたいな人はむしろ珍しい。疲れ切ってしまいあみ子を育てることを諦めた父親を責めることは我々には出来ない。病院で診て貰うとかそれなりの施設を探すとかも解決策と思えない。あみ子は継母であろうが母親を好いていた。不幸な出来事でその関係性が壊れたことが残念でならない。心に寄り添える人がそばにいて適切な教育をゆっくり行えば何とかなると思う。これから一緒に暮らす祖母に期待したい。少なくともあみ子は幽霊たちにバイバイできたのだから強く生きていく意思はあるのだから、、。
色んなことを観客に考えさせた素晴らしい映画であった。この題材を監督デビュー作に選んだ森井勇祐に拍手を送りたい。
大沢一菜の演技力がすさまじい映画・・・
あみ子役の大沢一菜がとても演技に見えなくて、彼女こそ当時のアカデミー主演女優賞を取るべきでは?と思いながら観た。
おそらくはASD、ADHD、あとLDもあるだろう発達障害コンプのあみ子によって、誰も悪気は無いのに家庭が崩壊していく様がまさに地獄だった。携帯が出てきていないことから作品の時代背景的には90年代なのだろうか。「発達障害」なんて言葉がまだ知られてなかった頃だ。いまならもっと早い段階であみ子を療育に繋げられただろうか。
母親も父親も兄も限界の状態で最終的にあみ子が切り捨てられていく様が痛々しくしんどい。あみ子に対して愛情が最初からなかったわけでは無いのが余計に苦しい。
いじめられても怪我しても血を出しても状況を理解できていないのか、泣くこともしないあみ子。でも何も感じていないわけでは無い。ヘルプのだし方もよくわかっていないのだ。このままだと何か事件に巻き込まれても状況を説明することすら出来ないだろうト余計な心配をしてしまう。(実際に身体障害、知的障害のある女性が性的加害のターゲットにされることなどはよくあることで、あみ子のような発達障害のある女子もその例外では無いだろうと思う)どうかなんとか療育に繋げてくれないかと祈るようなしんどい気持ちで観た。
映画はフィクションながら、現実で療育に繋げられることも無いまま家族にも切り離され孤立したまま大人になった発達障害のある人が数多く居ただろうことを思うと胸が痛い。
世の人たちは自分の子が健常者として生まれてくることを疑いもせず軽々しく子供をほしがるが、この映画をみて自分の子があみ子のようでも愛せるか真剣に問うた上で子供を作って欲しいと思う。
どんどん嫌な気分になっていくし、あとから考えてもやりきれなくなる
自分の心拍数で生きるということ
自分の幼少期を思い出しました。
誰にも届かない声の切なさを、周りとは違った時間軸をかけてゆっくりと自分だけのスピードで認識してくあみこ。周りと自分が違う認識は未だあみこには生まれてないが、思春期の自己認識に辿り着くのが遅いせいでひしひしと周りの人間が崩壊し、社会的に生きる人達の脆い人間性が見る側の倫理観や道徳心を問われる。そのコントラストによって、自分の世界を貫けるあみこのようなブレない人間がどんな現実よりも強いんだなと感じさせられた。
あみこの小さな成長は、きっと小さな傷から少しずつ生まれていき、それを癒す術も彼女の世界でこれからもゆっくり流れてくんだろうという余韻。
もちろん希望だけでなく、現実との境や歪みは、あみこ以外の世界で起きていき、彼女のなかではそれらが悲惨なほど浮き彫りになることはなく、ほんの少しの寂しさや虚無のような空白が生まれることで、新しい世界を見るようになってく。こういった主観的な成長を見事に表現した作品だし、周りの愛情や葛藤も繊細に表現されてる良い作品でした。
個人的に好きだったのは、あみこがトランシーバーで独り言のようにお兄ちゃんに助けを求めると、久方ぶりに現れ、あみこがずっと苦しんでいた異音の原因を壊すシーン。鳥の巣を投げ捨て、部屋から出て、白昼にバイク音を響かせる。お兄ちゃんは心のどこかでは常にあみこのことが気がかりであった背景や、自身もどうにもならず非行に走ったのだと、兄としての妹に対する責任感などが現されたシーンだったので、絶望的な家庭崩壊のなかで、確かに存在していたあみこへの寄り添いや愛情に希望を感じました。
ラストの波打際で手招いてるお化けたちについては、私自身も現実で似た体験をしたことがある。ただ私はあみこのようにはできず、まだそっちには行けないんだよと泣いていただけだったが、あみこが大きく手を振る姿に、彼女の世界に張られたまっすぐな命の根と、漠然とした生物的強さに感銘を受け、彼女のように自分の世界を主観で生き抜く強さを、自分の心拍数を大切にしようと思わせてくれました。
寝ぼけた人が見間違えたのさ〜
小学・中学の時にクラスメイトが泣いててなんで泣いてるの?をしつこく聞いちゃって黙れ😡っていわれたこととか、一つ学年の下の男の子に自分が勝手につけたあだ名で呼んだら叩かれたことを思い出してとてもその時期はやらかしてたな〜と思った
自分の過去と重ねて興味深く見入ってしまった!
お父さんから貰った誕生日プレゼントのカメラであみ子がお父さんとお母さんと兄ちゃんの写真を撮ろうとしたらちょっと待ってってお母さんが鏡を見て髪の毛を整えている時に撮っちゃってお母さんが怒って嫌な思い出だからお婆チャチに引っ越す時の荷造りの時いらない❗️ってカメラ投げ捨てちゃったのかな?🤔
あみ子が保健室でお化けなんてないさを大声で歌うところから保健の先生が「鼓膜破れる」の所を何回も再生してた😂
あみ子を障害とカテゴライズしなくて良かった
心が痛くなる
まだ観ていないが、最近公開された綾瀬はるか主演のルート29という映画に興味があり、その監督の初期作品という事で、レンタルDVDで鑑賞しました。
主演の子役は、ルート29にも出演していた大沢一菜という子らしいのですが、女子だか男子だか判らない独特な外見と、どんな波乱にも一切動じない無頓着さ、言い換えれば最強の鈍感力を表現し切った演技に驚かされました。
あみ子の人格の設定が、ADHDの様な病理的な原因によるものなのか、単に天真爛漫なだけなのかは判りませんが、他人の機微にも無頓着だし、自分が酷い仕打ちをされても無頓着だし、悪意はないにしても、周りの「常識的な」人達がことごとく影響を受けて人生を破綻させていくにも関わらず、本人はそれでも飄々として我が道を突き進む姿勢に、複雑な気持ちになりました。
ピュアすぎる故に、周囲に理解されず取り残されてしまっている可哀想な存在なのか、それとも無邪気過ぎる言動故に周囲を不幸にしている悪魔的な存在なのか、理解に苦しみました。
こちらあみ子という風変わりな題名も、作中に登場するデバイスから取られていたのだと判りましたが、劇中では結局これが通信成立する場面はなかったし、終盤では片方を紛失してもはや一方通行でしか存在し得なくなった状態になっても尚これは捨てきれず、逆に本来は家族の思い出が詰まっているはずの別デバイスは、執拗に捨てようとする場面は、いつまでも周囲に理解されず、一方的な送信のみで終わってしまっている人間関係と、一番大切にしたかったものが何なのかを物語っている様に感じました。
最後まで感情を露わにしない父親にも、優しいのか冷たいのかよく判らない不気味さを感じるし、本当は優しいはずの兄も義母も、本音が見えないし、そんな無関心な周囲に囲まれて健気に生きているあみ子が不憫に感じました。
あの世からの誘いも毅然と跳ね除け、毅然と生きていく超鈍感な姿勢に、生物としての根源的な強さを感じました。
最後に声をかけてくれた人が誰なのかは判りませんが、救われれば良いなという一抹の清涼感を感じました。
主人公のあみ子の大沢一菜さんが凄く良い
これは、凄まじい映画でした。
女の子の発達障害を描いているのだけれど、救いがない。全く救いが無いけれど、映画全体として絶望感はなく、基本的に明るい物語。
私としては楽しい良い映画だと思いました。
やっぱり発達障害って、そんなに甘いものではないなー、と改めて思う。
父親役で井浦新さん、継母役で尾野真千子さん。
子役で、主人公のあみ子の大沢一菜さんが凄く良い。
大沢一菜さんの演技にグイグイ
コミュニケーションの苦手な発達障害児・多動症・自閉症など協調が難しいキャラクターの子どもはたくさんいて、ようやくそれらが認知され始めているが、中々世間に受け入れられていない。
あみ子ちゃんも、暖かな家族に守られていたけど、大きくなると、周囲と乖離してくるので守りきれない。
親御さんの御苦労が痛々しい。
誰も悪くないからなお辛い。
ラストの海のシーンで、父に捨てられ自殺するのかと、ドキッとしたが、お化けに別れを告げたのでホッとした。
鑑賞後よく考えたら、自身の変なことが何であるかを気にしていたので、少しずつ大人になっていっていたのだから自殺は考えられない。時間はかかってもおばあちゃんと幸せに暮らしてほしい。
監督のデビュー作から
自宅近くのミニシアターで「ルート29」の上映予定を知り「ん?綾瀬はるかが単館系に?」と気になってググると監督のデビュー作『こちらあみ子』の高評価ということで鑑賞。大沢一菜は現代日本のアナ・トレント(2022年当時)。フランケンシュタインの映像は「ミツバチのささやき」へのオマージュ。
ルート29を見た後、U-NEXTで視聴。重いテーマだが、主役の役者...
沈む
ボクシングとインド人はまだしも…
「はだしのゲンをする」って何?
発達障害か何かなのかもしれないが、直接の言及はないし、とにかくあみ子にストレスが溜まる。
映画としてずっと見せられるのは、身近にいるのとも違う。
しかも、食べ物を粗末にしたり無神経な言動•行動に対して周りがまったく注意をしない。
散々繰り返した末の諦めなのかもしれないが、一度も描かれてないのではネグレクトにすら見えてしまう。
粗筋には「純粋で素直な行動」とあるが、結果としていい方向に作用することはない。
唯一クスッと出来たのは写真を撮るくだりだけ。
結果としてあみ子は祖母の家に預けられることになるが、母親の精神を守るためだったのかな?
兄の珍走団入りは親のストレスとして描かれていたワケでもないし、よく分からない。
片方を失くしたトランシーバーや1枚しか撮らなかった使い捨てカメラも、意味深なだけで活かされず。
鳥の卵が出てきた時は「おっ」と思ったが、ぶん投げた上に木に引っかかって無事って…
あみ子の世界を表したにしても、バッハや歴代校長、トイレの花子さんらの行進は浮いていた。
彼らが再登場するラストシーンは、先日観た『ルート29』に被りすぎ。
こちらを先に観ていたら、安西先生ばりに「まるで成長していない……」と思ったことだろう。
あの作品のように全員なら意図的と解釈するが、本作は1割まともなので棒演技も悪目立ちしてた。
何も好転しないし、あみ子自身は「気持ち悪いとこ教えて」という自覚がやっと芽生えた程度。
穏やかな雰囲気とは裏腹に、後味は良くない。
クッキーの件は気付かないよう願っていたが、のり君にはトラウマ級であろう。
男女を囃し立てる同級生は、何故いつもイガグリ坊主なのか。
ホントに演技未経験?
青葉市子の音楽が素晴らしい
原作既読。
原作のストーリーはもちろん、雰囲気もかなり忠実に描かれている。
よって個人的な感想としては原作を読んでの感想とおなじである。
「こういう子いるな」「こういう子の見ている世界ってきっとこんな感じなのだろう」と納得。
テンポもよく演者も上手い。
主演の子の眼差しはあみこの純粋さと持て余すほどのエネルギーを映し出しているし、
井浦新・尾野真千子夫妻も安定の上手さである。
(森井勇佑監督はこれが初監督作品とのことだが、よくこの二人をキャスティングできたと思う。二人が今作が初共演というのも意外だ)
が、特に感動したりすることはない。
自分にとっては既定路線という感じだった。
つまらなくもないが面白くもない。多分世界観が自分に馴染みすぎているのだと思う。
しかしながら、音楽はかなり良い。
ちょっとしたシーンの音楽からして良いのだが、
お化けの歌が主人公のイマジネーションと共に
フルサイズ(?)で流れるシーンの曲の展開は目(耳)を見張るものがある。
「これは凄い!」とおもって最後のクレジットをみたらなんと青葉市子であった。
彼女の楽曲は結構好きだが、劇伴までするとは知らなかった。
普段のライブなどで見せる以上に高く深い音楽性と技術があるのだと驚いた。
ちなみに本当は河合優実さんが惚れ込んだという「あみこ」と間違って鑑賞した・・・。
全116件中、1~20件目を表示