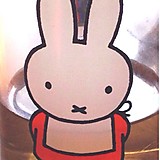天才ヴァイオリニストと消えた旋律のレビュー・感想・評価
全45件中、21~40件目を表示
邦題のトホホ加減について
映画は素晴らしい。このことはまず言っておかねばならない。良作であるがゆえに、この邦題のいい加減さ、投げやりさが腹立たしくて、ここに糺しておく。この映画に寄せる愛もシンパシーもない、一体にセンスのない邦題をつけたのは誰だ。なんだこれ。シリーズ物のサブタイトルか。「名探偵コナン 天才ヴァイオリニストと消えた旋律」てか。
もはや芸術的価値を貶める犯罪的行為とさえ言えよう。
まず〝天才ヴァイオリニスト〟などという、口にするのも恥ずかしい露骨で下世話で幼稚な言葉を使ってしまっていることからして神経を疑う。〝消えた旋律〟に至っては意味不明。失踪のことを指しているのか? 旋律ってのはメロディーだが、特定のメロディーに焦点が当たることはないから、ただ雰囲気だけでつけたのは明白。この映画の何が売りどころなのか、プロモーター君にはわからなかったのだ。
『The song of names』が原題。見た人には納得のいくタイトルだ。names と複数形になっているところがミソで、ここをうまく表現できないとダメ。「名前の歌」ではね。それでもまだ現タイトルよりはましだが。まあしかし、邦題に膝を打つ作品が少なくなった。今回のはあまりにトホホすぎて映画がかわいそう。仕事が雑過ぎるんじゃ。
35年後という設定が切ない。ところで最後のオチは何?
彼らが共に過ごしたよりも多くの時間を、お互い何に費やしていたのか。長い時間が経過しても、止まったままの時間を探さなくてはならないマーティンが切ないです。
コンサートのすっぽかしはラビの歌でようやく分かったけど、黙って姿を消す理由は全くわからない。しかし、ドヴィドルの最後のソロ演奏と映像でやっと彼の35年間が分かり始め、彼の家族写真を入れながら引っ越しの準備を粛々と行う妻の姿、置いていったバイオリンと最後の手紙で「個として生きない」と語り、ようやく彼が背負い込んだ果てしないものが分かった気がしました。
ラビの歌声とバイオリンはとても美しかったです。
ただ、最後の、”本番前の4時間”のマーティンの妻(当時は恋人)とドヴィドルの関係を明かすことで何を伝えたいのか。考えるほどによく分かりませんでした。
彼が既に別の人になっていて、行ってしまったことは分かるとは思いますが、何を伝える為のエピソードなのでしょう?
最後で弦の調律が甘いユダヤ受難曲
コンサート直前に失踪した天才ヴァイオリニストを第二次大戦中、戦後、現代の三時代にまたがって追跡する音楽ミステリーです。お話しは時系列でなく、目まぐるしく三時代を行き来するのに、混乱せずストーリーにグイグイ引きつけられるのは、監督のフランソワ・ジラールの語り口の上手いところです。とは言え、またもやナチによるユダヤ受難もので、正直いい加減食傷気味です。原題の『名前の歌』の意味のインパクトは強いけど主人公が急に信仰を取り戻して、結果として恩人一家に恩を仇で返すのは身勝手で共感できません。そのため、胸にモヤモヤ感が残り、どうもすっきりしないのが残念。役者では、ティム・ロスがいい感じのフケ具合で、役柄の雰囲気にぴったりの好演だし、クライブ・オーウェンも暗い情熱が感じられ、違った顔が見られました。
ユダヤ人の悲劇には同情するけど、節度あるお涙頂戴映画だ。
ティム・ロスとピアノ
ヴァイオリンでは救われなかった
仏教の開祖であるゴータマ・ブッダは、ひとつの著書も残さなかった。残したのは口伝のみである。彼の説法は常に口頭で行なわれた。経典に残したのは後世の弟子たちである。キリスト教のイエスも同じだ。文言をパピルスに刻んで聖書としたのは、やはり後世の弟子たちである。イエス自身は教えを始めて以降は文字ひとつとして書かなかった。
法事で禅宗の坊さんが歌うのを聞いたことがある。お経の中には節がついているものがあるとのことだ。この坊さんの歌がやけに上手くて、テノール歌手の歌を聞いているみたいで大変に見事だった。
ベトナムに行った際にもベトナムの坊さんのお経を聞いたことがある。日本のお経よりもキーが高くて、語尾が上がるようなアップテンポなお経だった。寺を訪れたときに聞いたのでそれがお経だと解ったが、別の場所で聞いたらベトナムのラップかと思ったかもしれない。
本作品ではユダヤ教のラビが歌う。しかしラビが歌ったのは旧約聖書ではなく、強制収容所で亡くなった人々の名前だった。原題の「The Song of Names」はこのシーンに由来するのだろう。
本作品のフランソワ・ジラール監督が2016年4月に演出した舞台「猟銃」をPARCO劇場で観劇したことがある。記憶が少しあやふやだが、中谷美紀の独演で、赤いドレス、下着姿、和服と、ゆっくりと着替えながら台詞を言い続ける。服装ごとに違う3人の女を、中谷美紀がひとりで演じるというややこしい劇だったと思う。井上靖の微妙な叙情がいまひとつ伝わって来なかったのが残念だった記憶がある。当方の感受性不足かもしれない。中谷美紀は2007年のジラール監督作「シルク」にも出演していて、流暢なフランス語を喋っていた。
本作品は映画だから舞台よりもわかりやすい。少年マーティンは最初ドヴィドルに嫉妬するが、あらゆることで実力が違いすぎて、嫉妬はすぐに尊敬に変わる。罰を恐れて世の中に盲従するマーティンに対して、ドヴィドルはどんなルールや基準からも自由だ。二十歳を過ぎても友情は続くが、自由なドヴィドルと常識や規範に縛られるマーティンという図式は変わらない。
マーティンがドヴィドルに願うのは、自分との約束だけは守って欲しいということだ。しかしいちばん大事な約束が破られてしまう。それを忘れることが出来ないまま35年が経過したある日、コンクールに出たひとりの少年が松脂の容器にキスをするのを見て、マーティンの追跡劇がはじまる。ドヴィドルの癖と同じだったからである。
ドヴィドルと関係した3人の女たちが登場する。ドヴィドルの天才に魅せられ、ドヴィドルの我儘を愛し、ドヴィドルの人生を受け止めた女たちだ。マーティンはドヴィドルを追いかけ、35年前の真実を知る。すべての空白が埋まれば、それ以上ドヴィドルを追いかける理由はない。
ドヴィドルを変えたのがラビの歌だ。4年前にユダヤ教を捨てて無宗教となった筈のドヴィドルだが、たった一度聞いたこの歌によって、ユダヤ教の教徒となる。しかもとびきり敬虔な教徒だ。
ドヴィドルはヴァイオリンでは救われなかったのだ。ヴァイオリンの演奏がもたらすのは人々の賞賛と金銭だが、ドヴィドルにとってそれはゴミでしかない。マーティンはそこだけがどうしても理解できない。世界的なヴァイオリニストになれたというのに、その道を捨てたドヴィドル。彼を救った信仰とはどんなものなのか。覚束ないラテン語で祈りを唱えてみるマーティンなのであった。
ジラール監督はラビの歌声をハイライトシーンにしたかったのだと思うが、やはり目立つのはヴァイオリンの演奏シーンだ。ヴァイオリンが演奏されるたびにストーリーを離れて思わず聞き入ってしまう。どの演奏も驚くほど音色が美しい。演奏したレイ・チェンは21世紀を代表するヴァイオリニストだ。本物の天才である。
魂を救済する音色
ちょっと自分にはわからない
よく出来てる。
特に冒頭のコンクールのところなど出場者の演奏がちゃんと若干のわかりやすいズレ(後で機械的にいれたのかもしれないが)が入ってたり細かいところまで作りこんでいる。
ドヴィドルの運指と音がずれていることもありアフレコで全部ちゃんとやってるのは凄い。
天才演奏家を題材にしてしまうと、いかに天才的なプレイを説得力をもって表現するかというのがいちばん大変なところになるのだがこのくらい作ってあれば好感をもてる。
子供時代も萩尾望都とか竹宮恵子のマンガを思い出すいい雰囲気にできている。
ただ、イギリス貴族の考え方やユダヤ人の宗教観などが自分には理解できなくて全く感情移入できず終盤は興味を失ってしまった。
切ないヴァイオリニスト
【少しネタバレ】ロンドンはじめヨーロッパの街並み、重厚な雰囲気は良い。ホロコーストは糾弾すべきだが、本作では生々しいのか空回り。
第二次大戦でナチスドイツに屈しなかったイギリス。
ホロコーストの悲劇
ユダヤ人の苦悩
1941 1951 1986
ロンドン、ワルシャワ、ニューヨークロンドン
演奏会の前に消えた天才青年ヴァイオオリニスト・・・
一人だけイギリスで難を逃れ、ポーランドの家族が強制収容所以降行方不明の青年
そりゃ苦悩するだろねぇ
ただ、約束の演奏はしようよね!
寝過ごし(ネタバレか??)・・って反則だよねぇ
ユダヤの宗教は「シンドラーのリスト」の描写くらいしか知識ないから
少しムズカシイ部分もあるけども、苦悩はよくわかる。
あと私がクラッシック音楽馴染んでいればもっと楽しめたのは
相違ない。
ただ、曇天雨天のヨーロッパ、石畳の古風な街並みの描写
と少しミステリアスな展開は雰囲気が良い
最後は全くの予定調和だけども、プチカミングアウトのネタ明かしはよく考えたねぇ。
追悼の祈り
1951年ロンドンでデビューコンサートの日に消えたポーランド移民のユダヤ人天才ヴァイオリニストを巡る話。
1938年にロンドンのマーティン家にやって来たドヴィドルと、モットルことマーティンが共に過ごした12年をみせつつ、35年後、松ヤニキスにドヴィドルを感じたマーティンが、彼の行方を追う様を差し込んでみせていく。
サスペンスなのかとも思ったけれど、時代背景とドヴィドルの背景からしても、やはりホロコーストに纏わるヒューマンドラマですね。
なぜ彼はいなくなったかよりも2人とマーティンの父親やヘレンとの物語がメインに置いて思い入れを強くさせていく展開は上手いですね。
そして疾走当日の衝撃が35年後の話に繋がって、とても哀しく、そしてやり切れず。
状況は異なるけれど、ビルマの竪琴がちょっと頭を過った。
落ち着いたよい作品
騒々しい作品が多いなか、落ち着いたよい作品でした。
ユダヤ人に対する抑圧、弾圧を描いた作品は途切れなく作り続けられます。マルクスはお金による支配から人間を解放しなければユダヤ人問題は解決しないといいましたが、このように民族の記憶を執拗に伝承し続ける以上、マルクスの考えはおおむね正しいとしても完全ではないと感じます。
この作品は、歴史を知る人、音楽を愛する人にとっては非常に印象に残る作品だったのではないでしょうか。主人公の境遇とヴァイオリンの音色のすばらしさが涙を誘います。最後のヘレンの言葉は、この作品の重さを倍増させます。ヘレンにスポットを当てても一つの作品が出来上がると思いました。
ラスト10分はクラシックコンサートのようでした
人間にとってあまりにも不条理で、これ以上ない過酷で悲惨な仕打ちを、自然災害などではなく、他ならぬ人間自身が行ってしまう。
この事実は、どんなに形を変えようと次の世代に語り伝えなければならないし、犠牲者の名前(names)を刻むこと(伝えること)は、大勢の犠牲者としてひとくくりにされるのではなく、刻まれた名前個々の人生を悼むことになる。
現在でも、大きな災害や事故のあと、その場所に犠牲者全員の名前が刻まれた慰霊碑が建つのはそのためなのだと思います。遺族でなくても、そこを訪れた人間は、その名前ひとつひとつに想いを馳せ、どんな人生を送っていたのか、或いは送るはずだったのか、そんなことを想像し、二度と起こしてはならないという想いを抱くことになります。
(私が政治家だったら、交通死亡事故現場などに、遺族の同意を前提としますが、亡くなった方の名前と年齢を記した慰霊碑を建てることを議案にして提出してる? かもしれません)
ユダヤの人々はディアスポラによって、土地に紐付いた慰霊碑や記録を残したりすることが困難であった歴史があったので、口伝で引き継いでいくことが伝統的に身に付いたのでしょうか。それはそれでまた、〝一所懸命〟という言葉を持つほど土地とは切り離せない生活を送ってきた日本人には身体的、経験的な理解がとても難しい感覚です。
映画から学ぶこと、知らない世界について考えるきっかけを与えられることは本当に尽きることがないし、ありがたいと思います。
美しくも悲痛な旋律
ユダヤ人の悲劇を十分に知っているつもりでいたが、収容所で息絶えた人の名前を口伝で忘れないようにしていたことを初めて知った。死んだ人の名前を朗誦するラビの歌声とドヴィドルが奏でる鎮魂のヴァイオリンがオーバラップするシーンでは、美しくも悲痛な旋律に心が揺さぶられる。
ドヴィドルが家族や同朋の魂が安らかであって欲しいと祈る気持ちは当然理解できるが、生き残ったユダヤ人として何をすべきかということに関しては想像できていなかった。マーティンの妻と同じで、ドヴィドルを責める気持ちを強く持っていたが、最後の最後になってドヴィドルが失踪した理由に納得ができた。
作品で流れるヴァイオリンの音色は極上で、α波が出過ぎきて眠眠打破を投入してしまった。それもそのはずで、レイ・チェンという一流のヴァイオリニストが演奏を担当しているとのこと。しかも使用している楽器はストラディバリウス。
音楽は生きている人間を癒すだけでなく、死者の魂までも鎮める力がある。改めてそう思った。
【”The Song of Names"ポーランド系ユダヤ人のドヴィドルがデビュー公演時に姿を現さなかった訳をミステリータッチで描く。シナゴーグでの口頭伝承による、ラビの歌が心に沁みる作品。】
ー 第二次世界大戦中と、大戦終了後。そして35年後の現在を行き来しつつ、物語は進む。ミステリー要素をはらみながら・・。-
◆感想
・第二次世界大戦中、ポーランドから9歳のドヴィドルは英国の同じ年のマーティンの家に越してくる。マーティンの父親は、音楽界を催す興行師であり、音楽を深く愛している。
最初は、相入れなかったドヴィドルとマーティン入れだが、あっと言う間に仲良くなる。
- 生意気なドヴィドルが、ヴァイオリンを手にすると、美しいメロディが流れ出す。才能の発露であろう。羨まし気に見るマーティン。彼の両親もドヴィドルとマーティンを分け隔てなく、大切に育てている。だが、戦況が悪化する中、ドヴィドルは故郷ワルシャワに居る両親と幼い姉妹の安否を心配していた。一枚の家族写真を常に身に付けながら・・。-
・21歳になった二人。ドヴィドルの晴れがましいデビュー公演が決まるも、彼は開始時間になっても姿を現さない。そして、35年が過ぎる・・。
・マーティン(ティム・ロス)は、行方知れずのドヴィドルを探す。そのきっかけは、演奏前に弓に塗る松脂に口づけする奏者を、オーディションで観たからである。
その仕草は、且つてのドヴィドルと同じ仕草だったから・・。
- ポーランド、ニューヨークとマーティンはドヴィドルを探し続ける。それは、我が子同様に育てた父を裏切ったドヴィドルへの憎しみも含まれていたであろう。が、それ以上に、何故に彼は公演に来なかったのかが知りたかったのであろう、且つての親友として・・。-
<漸く、見つけたドヴィドルが語ったデビュー公演の前に彼の身に起こった出来事。
”個”と”家族”と”宗教”。
そして、”口頭伝承”によって生まれた哀しくも美しき響きの、”The Song of Names"
愛する家族がトレブリンカ収容所に収容されたとドヴィドルが聞いたあと、シナゴーグで、彼の家族の名前がつづられた、ラビが朗々と歌った歌が心に沁みる・・。
哀しき、ミュージック・ミステリーの佳品である。>
全45件中、21~40件目を表示