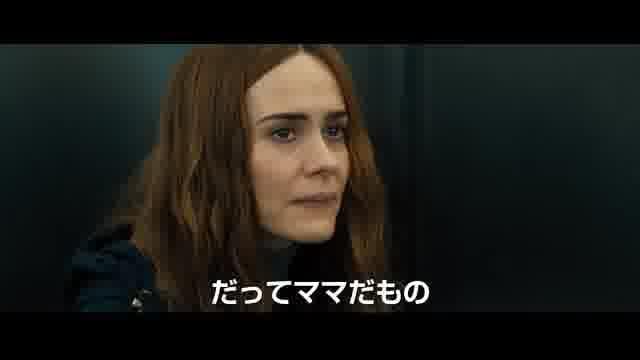RUN ランのレビュー・感想・評価
全190件中、81~100件目を表示
どこかで観たことのあるような‥
この監督作品好きかも
search-サーチ-鑑賞済の人は、序盤でドキッとする?
分かりやすいストーリーながら、最後までハラハラできるTHEスリラー作品で非常に面白かったです!
(設定は違いますが、「ミザリー」を思い起こさせるようなスリル感でした)
劇中の主人公の行動(薬への違和感を素直に母に質問してしまう、暴力で反撃しないなど)も、母娘の関係だからこそそうなると理解できるので、違和感無く観進める事ができました。
徐々に不信感を募らせていくという描写が丁寧で良かったです。
(薬剤師さんに薬の情報を聞き出そうとするシーンや、終盤にコードブルーのアラームで看護が手薄になった瞬間を狙って母が娘を連れ出すシーンなどは、ご都合主義に感じたり「そうはしないだろう!」と思ったりもしましたが…)
序盤、search-サーチ-に登場するフリー素材の女性が出てきたと思うのですが、私の記憶は正しいのか…?
密室系サイコスリラー
この母親は怖い
母親が子供に怪我をさせたり、入院中に点滴等に細工したりして病状を悪化させる母親がニュースになったこともある。それは、「お子さんが大変な状態なのに、あなたはしっかり看病して大変ね、よく頑張っているわね」と自分に同情して欲しかったり、認めてほしいなどのために危害を加えることがある。恐ろしいことだ。この映画もそういう話かと思ったが、そこまでではなく、ただ可愛いがために自分のそばにおいておきたい、と思ってのことのようだ。
でも、なんとこの母親は自分の子が命を落としたために他人の子を誘拐して自分の子として育て病気にさせている。本当の両親の元で普通に育っていればと思うととても気の毒である。ラストの彼女の言葉で、結婚をし、子供にも恵まれて幸せそうに暮らしているようなので、一安心!
サイコスリラーの良作だと思います。
RUN ラン
ママ恐ろし
愛情というものは時に狂気に変わる事があるが、本作はそれを真っ当に描いているサイコホラーだ。サクッと観れる尺だが、こんなにも背筋が寒くなる作品は久しぶりだった。人は幽霊なんかよりも怖いものである。
主人公が身体的なハンデを複数負っている時点でハラハラさせられるだろうと予想はしていたが、観ていてじっとしていられない程のハラハラ感を味わえた。監督のデビュー作、「search/サーチ」もそうだったが、登場人物らの動線は少ないが、その限られた場所にしか無い特有の雰囲気が本作でも体感できる。そこでの様々な攻防こそが本作の見所のため、深く書くことはしないが、変に予備知識だけ増やしてしまうと楽しさの半減は間違いないため、基本まっさらな状態からの鑑賞をおすすめする。
キャッチコピーにもこれは記載されているから書くが、結局のところ母の異常な愛情から娘が逃れる物語だ。タイトルの「RUN」は逃げる意味でのRUNで良いのだろう。
序盤であっさりと片鱗が伺える母が買ってきた緑のカプセルの飲薬。これに娘が疑問を抱いたところから一気に母が恐怖の対象になる。そこから先は優しさすらも狂気に見えるほどのサイコっぷりを全開で発揮する。こういう作品をサイコホラーと呼ぶのだろう。
断罪される母性の狂気
現実の世界でも、母性の狂気にまつわる犯罪はしばしば起こるが、何かしらの同情や理解が伴うものだ。 この作品では、 常軌を逸した方法で実子でもない娘を支配し、彼女の青春を奪ったこの母親?への同情は一切ない。 最終的には、身勝手極まりない悪行として娘から断罪され、始末?される。
最初は、悪意をもって娘を陥れようとしているようには描かれていない。 人格の破綻したサイコなのだから悪意もクソもないが、その表情と言動からは、娘が自分から離れることに怯えている母親の姿しか見えない。 車椅子の娘とそれを支える母親の関係からは、 深い絆さえ伺える。
母親の歪んだ支配欲・独占欲を、 母性と母娘の濃密な関係に転換して見せる演出が、非常に巧だ。 この描き方が、後半の盛り上がりにドライブをかけることになる。
個人的には、 母親の怪しさを確信できて以降も、少しは同情の余地があると思いつつ、 この大人しそうな娘がどう行動するのかを観ていたが、 展開が進むにつれて甘い考えは吹き飛んだ。
娘の疑問が確信に近づいてくると、母親の隠していた狂気が凄まじい形で露出し始めるのである。 そして、愛が裏切られたことを悟った娘の怒りと悲しみは、異常者の狂気を遥かに凌駕する。
結末は、想像以上に厳しいものだった。
仮に、これが自分の身に起きたならと想像してしまう。 血のつながっていない他人であり、自分を支配し殺そうとした鬼・悪魔である。 しかし、自分を育ててくれた母親であり、幼いころからの思い出を共有している唯一の人間でもある。
果たして、殺れるものか。 いやぁ…。
やっぱり殺るしかないかねぇ…。
考えさせられるサスペンススリラーであった。
「自分がいないとダメな人であってほしい」という思考
よくある親の監禁系
誘拐して軟禁するのはよくあるパターン。
「全てがあなたのため」
よくあるセリフ。
サラさんがお母さん役を演じてたため緊迫感恐怖感が増した。
最後は娘?(他人)の復讐。
ちゃんと復讐で返すのは気持ちがいい
もっと露骨なB級演出を
及第点
全190件中、81~100件目を表示