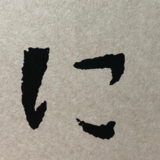サウンド・オブ・メタル 聞こえるということのレビュー・感想・評価
全27件中、1~20件目を表示
苦悩の先に答えなんてなくていい。
突然重度の軟調になったメタルバンド(正確にはデュオ)のドラマーが、否が応でも生き方を変えることを迫られる。その道程はもちろんたやすいものではない。主人公に麻薬中毒の既往歴があり、恋人(バンドのギターボーカルでもある)には自傷癖があり、ふたりが小宇宙のような安全地帯を築いて、支えあって生きていることも、生き方を容易に変えさせてくれない要因になっている。
ただ、この映画は主人公たちの七転八倒をスリルたっぷりに描くわけではなく、起きてしまったことと向き合うまでの時間を、丁寧に、繊細に見つめようとする。オリヴィア・クック演じる恋人は、中盤は出番がないのだが、彼女にもまた、自分と向き合うための試練の時があったことを、われわれ観客は窺い知ることができる。
結末めいたものはある。しかし、彼らが何か求めていたものを得られたのかどうかは明示されない。確かにふたりの人生は大きく変わったが、答えが示されるわけでもない。いや、実際のところ、答えなんて見つからないものであるという真理を信じているからこそ、あの瞬間で潔く映画を終えられたのだと思う。彼にとってはとても大きな瞬間だが、その後も人生は続いていくのである。
聞こえるいうこと
見る前は副題ダサいなと思っていたが、「聞こえるということ」の答え?がラストにわかる。
主人公は突発性難聴で耳が聞こえなくなるが、音楽系の仕事をしている人ほどこの病気になり仕事が出来なくなるという悲しい病気。
主人公が治療のため入っていた施設は厳しい規律があり、外部との連絡遮断のためスマホ等没収されたり、主人公が手術をして治した後はすぐ出て行かされたりした。
施設主、の耳が聞こえないということは病気ではなく個性だから治すものでは無いという考えも理解できる。
最後は頭に埋め込んだ機械のおかげで耳は聞こえるようになったが、周波数の関係か全てが機械音に聞こえてしまう。手術したのを後悔してるかどうかはわからないが、静寂の世界も悪くないのかもと思わされる映画だった。
評価基準にかなり苦しんだが・・・・・
このエンディングはとても美しいと思った‼️即ち最後の最後に静寂の美しさに気が付いた主演のリズ・アーメッド・・・。それは孤独を受け入れると云う事を悟ったと云って良いのだろうと思う。音を扱った作品の中でこれほどまでの美しさを持ったエンディングは久しぶりである。
音の質・・・聞こえれば、それで良いというものでは無いのが分かりました。
ルーベンの場合(ミュージシャンが音を失ったら?)
身につまされるストーリーでした。
目(見える)と耳(聞こえる)のどちらかを失うとしたら、
目と耳のどちらを選ぶだろう?
そんな問いかけをしたことがありませんか?
私は、やはり「目」を選ぶと思います。
ミュージシャンでドラマーのルーベンは、ボーカルでギターを弾く
ルーと2人、レーラーハウスで全米を移動しながら、ツアーをするのが
ここ数年の日常だった。
ルーとルーベンは恋人関係にあり、マネージャーであり
公私を共にするパートナーだった。
ある日突然ルーベンは難聴を発症する。
それは瞬く間にルーベンの聴力を奪った。
病院で聴力検査を受けて診断を聞く。
取り急ぎ2人は、教えて貰った
「聞こえない人たちのコミュニティ・・・支援センター」を
訪ねる。
突然の事に苛立つルーベンをリーダーのジョーは暖かく迎える。
失聴を受け入れて「手話」を学び、役割分担をして協力し合って
共に生活をする。
静かで豊かな思い遣りの生活があった。
映画を見た限りでは健常者で指示したり命令を下す人は居なかったように
見受けました。
ボスはジョーだけ。
失聴を受け入れた様子のルーベンだったが、
彼ははまだ諦めていなかった。
トレーラハウスを売り払い身の回りの金目のものを売り払い、
難聴を治す最後の手段、
《人工内耳インプラント手術》を受けたのだ。
耳の奥に人工の内耳チップを埋め込む手術を受けて、
4週間後に《音入れ》という操作を行う。
補聴器のようなサウンドプロフェッサーを装着して、
「スイッチオン(音入れ)」をするのだ。
確かに聞こえる。
しかしキンキンして不快感がある。
実際には入念で根気強いリハビリテーションが必要とのこと。
個人的には「難聴のインプラント手術」
これは初耳でした。
この映画は、
無音、
ノイズ、
(メタル・・金属を埋め込んだ音は、耐え難く不快だし、
(ノイズはパーティーなどの多数の人がつとろう場面や、
(交通量の多い雑踏などがうるさく感じる、ようです。
手術を受けたルーベンはルーの実家の父親(マチュー・アマルリック)を
訪ねる。
ルーは留守だったが、夕方、2人はひさしぶりに再会を果たす。
すっかり印象の変わった2人。
黒髪でボブヘアのルーシーは、すっかりしっとりした大人の女性に
なっている。
ルーベンも髪を殆ど坊主頭にして、雰囲気が変わっている。
身を引くように、翌朝、ルーの家から出て行くルーベン。
あてはあるのだろうか?
ベンチに座ると教会の鐘が鳴っているようだ。
それはグワーン、プワーンと反響して耐え難く五月蝿い。
思わずルーベンはサウンドプロフェッサーを、外してしまう。
ホッとして安堵して寛いだ表情を取り戻すルーベン。
そこで映画は終わる。
彼が今後どのように決断して生きていくのかは、分からない。
ただ支援者センター長のジョーの言った言葉。
「聞こえないことはは障害では無い。」
「静けさを受け入れた先に平穏な生活がある」
この言葉が耳に残っている。
とは言っても若者が仙人のような境地になのは簡単ではない。
人はパンのみで生きるもにあらず・・・だし。
やはり悩ましいです。
自尊心をブッ壊す凄まじい葛藤と静寂に心打
第93回アカデミ-賞のノミネ-ト枠で上がっていたので
作品名は知っていた程度。
或るときラジオ番組で この作品の紹介をやっていて
興味が湧いたので 先日やっと
鑑賞に至ったので、ここに記したいと思う。
感想から言うと、久しぶりに心を強く打たれた。
この手のセカンドライフへ誘う思いをさせる作品は
何十年ぶりかだと思う。素晴らしい作品だった。
mc:
ルーベン・ストーン役(主役、難聴者):リズ・アーメッドさん
ルー役(主役の彼女):オリヴィア・クックさん
ジョー役(自助グループ所長):ポール・レイシーさん
身体障害者の作品や役で、盲人演出と言えば
白杖や、盲導犬や、役者の演技でそれらしく見せているため
映画演出しやすかった。話せるし、聞こえるし。
映画にとってこの役柄の相性は良い。
一方、聴覚障害者の演出は実は難しいのだ。
見た目が 健常者と一見変わらぬため
演出が非常にしずらい。伝わるようにするには
サウンドエフェクトを酷使するしかないのである。
勿論役者の演技もそれなりで無いと伝わらない。
映画を甘く見ていた私は、最初寝っ転がって見ていた。
主人公ル-ベンの やんちゃな香りがする風格の男が
ドラムをバンバン叩いている・・・そこから始まった。
そう、彼はバンドのドラマ-なのだ。
最初は全く普通に改造バス生活で暮らしていたが、
或るとき ん? ん? 音の聞こえ方が お・か・し・い。
極度にコモッた様に聞こえてきて、焦る 本人。
実は 私も中耳炎になった事が有るので
この心境は凄くわかる。
やがて、医者に診てもらうと 80%の聴覚を失っている事実を
知る。このシーンを目の当たりにして ハッとした。
すかさず姿勢を正して 映画を真剣に見入る様になった。
彼は、急遽 聴覚障害者ばかりで生活する自助グル-プに入れられる。
ココでの生活が彼を唯一救うと思っていたからだ。
しかし、そんな簡単な問題では無かった。
健常で育った期間が長い彼にとって
ココでの生活、これからの運命は到底受け入れられない・・・
彼の孤独な毎日が続く。
何とか現状を打開して、元の彼女との生活に 元の仕事に
戻ろうとするが、まずはココの生活に慣れて
コミュニケ-ションを図らないとダメだった。
ろうあ者のコミニケ-ションが 物凄く静かに会話されて
盛り上がっているのが 不思議な世界観だった。
この感覚に慣れるかが、ルーベンの生きる道であった。
今までヤンチャなミュ-ジシャン ドラマ-が
ココでの生活に溶け込めるとは思えない。
しかし、少しづつ 子供たちと親しくなり
会話がみんなと出来る様になった姿に
観ているこちらも安堵していく。
そう、いつの間にか 私は彼を心から応援していたのだ。
これがこの映画の力点だと思いますね。
ジョ―に 部屋に籠って ノートに文章を書け!
言われて しぶしぶ書いていくルーベン。
この教えの意味する所が 最後に繋がる。
約束事でグル-プ施設の外界とは遮断されているのだが、
隠れる様にして PCをこっそりいじりネットで
彼女の現状を知る。
歌手として活動を続けるも、彼が居ない彼女のバンド活動は
へこんでいた。
彼女の新曲プレビュ-動画を再生するも
彼には全く聞こえない。 涙するよねココね。
この現状を打開すべく、彼は折角 施設に慣れてきたが、
全私物をお金に換えて 聴覚を取り戻すべく
手術に挑み 人生の賭けに出る。
やっとの思いで、本当にやっとの思いで
補聴器を両耳の神経に当てて 音を大きく聞き取れる
様には成ったが・・・何かが変だった。
そう、音質、質感の相違である。
健常者時の頃と同じように聞こえると、
戻れると思っていたが
それは 大きな間違いだった。
この 愕然とする 深い喪失感は
本当に同情した。
もう、ミュ-ジシャンに戻れないのか?
それはジョ-の言った通りのことだった。
インプラント(手術・補聴器)を試しても
ダメだったと 彼が言っていたのを思い出す。
しかし日常は話せるようになったのは良かった。
相変わらず 音質はメタルっぽいから嫌だけど。
久しぶりに彼女 ル-に会いに行って
もう一度 俺とバンドツア-をと 言い出すが、
二人に その未来は待ってはいなかった。
それを悟るルーベン。
二人で涙しながら抱き合う姿は
とてもジーンと来たよ!
本当に良いシーンでした。
そして 翌朝 早くに、彼女の元を去るルーベン。
行く宛は 多分施設へ戻るのだろうか。
そう思った。
金属音質な補聴器を 両耳からそっと外す・・・
そこに広がる 静寂な世界。
心地よい風が吹き、木漏れ日が彼の顔を照らしている。
そう、彼に セカンドライフが訪れた瞬間だった。
そこから 彼は 少しずつ次の人生を
歩んでいく事だろう、きっとそう成る。
私の心は 彼を応援し続けていた。
いつか、心のドラムを思いきり叩く
彼がいる事を 願いたい。
タイトルを見返した
最初、ASMRみたいに音がクリアに聞こえる。
中盤
彼の不安や音が聞こえない感じを体験できるようにしてる。
見ていて思ったことは
聞こえるということは、どういうことか。
手術後のルーベンの聞こえ方を一緒に体験して、その後聞こえるシーンになったとき、聞こえるということがこういうことかと思った。
手術後の音は不快でうるさく、クリアに聞こえない。元には戻らない。
タイトルのメタルはインプラントのことかな。金属がつくるうるさい音。
聴こえなくなったら!
ある日聴こえなくなる!
うそだろ!
ミュージシャンだけに
治す方法は?
主人公は俺に必要なのは、ガンだ!
支援センターにいき
徐々に安らぎは取り戻すが
やはり
手術する。
その代償は?
静寂の中に安らぎは見つかるのか?
これからの生き方
ヘビメタ?が原因なのかわからない(結局原因もわからなかった)が、聴力を失っていく若者の苦悩。
アメリカはこういう感じなのか、あそこが特殊なのかは判断がつかないが、支援グループがあるのは心強いだろうね。
ああいうコミュニティがアメリカ全土にあるのかな?
日本ではちょっと考えられないかも。
ルーベンが手話を覚え馴染んでいくのがよかった。
とはいえ、やはり元に戻りたい気持ちが強く、全財産をつぎ込んで手術を受け、案の定うまくいかったなんて。
元の鞘には納まらなくても、この先なんとか生きていけそうな光が見えたのがよかった。
“Deaf”という単語を知ったのは、<87分署>でだった。
飛び道具的な演出ではあるが、この内容ならコレが必然なので。POVが段々手詰まり感を覚えてきていただけに、こういう主観的な音響表現に力を入れた作品がもっと出てきてほしい。くぐもってたり歪んでたり無音になったりするの、だいすき!
呼吸音すらはばかられるような静寂は、昨今中々体感できない。同じ回を鑑賞していたお客さんがみな、わかってらっしゃる方々ばかりだったので、音響効果を余すところなく体験できた。
クリーン(clean)というのだね、ふむふむ。あのコミュニティ/学校の人はポール・レイシー以外は…?
補聴器でも、調整したり慣れるのが結構大変と聞くが、ラストシーンでちょっとだけ、「ああっ、それもいいかも。ちょっと羨ましいかも」とつい思ってしまった。
タイトルなし(ネタバレ)
メタルバンドのドラマーのルーベン(リズ・アーメッド)は激しい演奏のせいかどうか、突発性難聴に襲われてしまう。
原因は不明。
器具を埋め込む手術をすればいくらか聞こえるようになるかもしれないが・・・と言葉を濁す医者。
しかし、手術費用は高額。
恋人で一緒にバンドを組む恋人ルー(オリヴィア・クック)は、伝手を頼って、難聴者のコミュニティに連れていくが、コミュニティの主催者ジョー(ポール・レイシー)は、聾や難聴をハンディとして捉えず、その状態を受け容れての生活をルーベンに勧める。
ルーと離れてコミュニティで暮らすルーベンであったが、現実を受け容れることはなかなか難しかったが、コミュニティでの居場所・立場が出来たことで、少しずつ現実を受け容れられるようになっていく。
しかし、手術をすれば・・・という思いは立ちがたく・・・
といった物語で、タイトルの「サウンド・オブ・メタル」には3つの意味が掛けられているように思えました。
ひとつめは、主人公が演奏するバンドのメタルサウンド。
ふたつめは、難聴に襲われ、聞こえづらくなってきたときの、ノイズ音。
みっつめは、手術後に器具を通して聞こえる金属的な歪んだ音。
それらみっつの音質を見事にサウンド化しており、アカデミー賞音響賞受賞もなるほどと肯けます。
映画的には、ある種の宗教色を感じました。
ひとつは、ジョーが主催する難聴者のコミュニティの描き方で、教会が支援しているということが告げられますが、ジョー自身が牧師のようにみえるよう演出しています。
牧師のような様相ではないのですが、デニムシャツの下に着ている白いアンダーシャツが襟元から覗いており、それが牧師のホワイトカラーのようにも見えます。
また、難聴はハンディキャップではない、と言いつつも、健聴者を排除していることから、逆に排他的であり、他の宗派を受け容れないキリスト教の頑なさとも重なってきます。
もうひとつは、最終盤。
手術しても元のように聞こえず失望したルーベンに教会の鐘の音が鳴り響くのですが、その歪んだ音に耐え切れなくなった彼は、手術で取り付けた器具を外し、静寂を選び取ります。
キリスト教会の鐘は、イスラム教徒のルーベン(明確にそうだとは描かれていませんが)を救ってくれないように読み取れます。
ルーベンを救うのは、静寂を選んだ自分自身・・・
そう考えると、かなり遣る瀬無くなるラストですね。
病気になって失うもの、そして•••
コロナ後の公開ラッシュで、配信で観られるものは観てしまえの勢いでアマプラで観ました。
良かった。特に聾者(になりつつある人)の聞こえ方などがリアルに再現されていた(自分が突発性難聴になった時と凄く似た感じだった)。
病気になる喪失感、その後、病気になって初めて得られるものがエンディングで体験できた。
劇場で、もう一回観るかもです。
究極の愛の物語
恋人同士ながら、同じバンドで活動し、2人でトレーラーに寝泊まりしながら全米をツアーする男女の話。
ルーベンは徐々に難聴に陥り、やがて会話がまったく聴き取れなくなる。
ツアーを続けたいという主人公・ルーベンと、今すぐ中止して治療に専念してほしい恋人・ルー。
ルーベンはミュージシャンとして最も大事な聴覚を失うというどん底を味わう。
なるほど、中盤くらいまでは、このルーベンの喪失と再生の話かと思っていた。
入所した聴覚障がい者の施設でも、徐々に彼は居場所を見つけていく。
ここまではまあ予想できた話だ。
しかし、終盤に至る彼の行動はルーに対する究極の愛だったのだろう。
家庭に恵まれなかったルーベンに居場所を与えてくれたルー。
そうか、彼が本当に取り戻したかったのは聴覚ではなく、聴覚を取り戻し、ルーとまた音楽をして、彼が居場所を取り戻すこと。なるほど、深い。
しかし、彼はパリを訪れた際のルーの雰囲気や生活に、そして自分の聴覚が思ったものとは違うという自覚に、彼女を取り戻すことなく、自ら身を引く。
最後のシーンはまさに彼の身上を象徴するような名シーンだった。
この映画はたった一つの愛の形を見せたものだと思う。彼はルーを通して何を観たか、何を得たか。そして、聴覚を失って彼のルーに対する愛は大きくなったのだろう。
しかし、やはり愛は脆い。彼の最後に見せた行動もルーへの究極の愛だった。
予告編の雰囲気から、自分がこういった感想を持つとは思わなかった。
しかし、これもまたこの映画の深さかと思う。
あと、内容とは別に今作の音作り。
劇場では他の作品よりやや大きい音量に設定されていたような気がする。
あの音の設定はきっと劇場レベルの音響じゃないとできないものだろう。
まさに疑似体験と言えるだろう。
あの不快な音は、自宅レベルで体験することはできない。より、主人公の不快な音を体験するのは劇場に限る。
何が聞こえるのか、が大切
見終わってわかった、ポスターの写真は術後のものだった。とにかく聞こえるようにさえなれば、愛する彼女とまた幸せな日々を取り戻せるはず・・・全てを手放して手術を受けた結果、もう元には戻れないことを悟る。不快な歪みを帯びた響きと共に。
音を失ったらそれまでの人生全てを諦める覚悟をしなければ、平安に生きられないと言っているようで、あまりに悲しく惨いと思ってしまった。せめて、愛する人の側で安らげたら良かったのに。静寂を受け入れる事だけが新たな生き方、というのではなく、現実と向き合いながらもポジティブにもがく、というのもありであって欲しい、と私は思う。
希望と絶望、これからどうやって生きていくのか、静寂のなかでなにかを見つめる姿に胸が痛む。
解釈の仕方
あるミュージシャンが聴力を失い、ろう者として生きることを迫られるのだが、その失望から外科手術によって聴力を回復しようと試みる。しかしもともと聞こえていた音とは異質なものしか聴こえなくなっていた。彼はこれからどう生きていくのか。
彼は音楽活動のパートナーである女性から、「ろう者」に言葉以外の手段でコミュニケーションをとったり、現実を受け止め互いにいたわり合うことを学ぶプログラムを受けることを勧められる。様々な葛藤を経て、施設の仲間との生活に馴染んではいくのだが、音楽への思いを断ち切ることができなかった。
聴力を失っていく過程をどう描くのかという点がこの映画の見どころである。特に主人公の音の聴こえ方を音響的にどう表すか。当事者の聴こえ方を正確に表現することは無理なことだから、イメージの世界になるのだが、映画的に言えば「不安」を音で表現するということではないだろうか。そういう観点では、うまく作られていると思う。単に音が小さくなっていくのではなく、不規則な金属的な雑音が混じりこんでくる。不安であり、不快である。
この映画をどう受け止めればいいのだろうか。素直に捉えればミュージシャンにとって音を失うということがどれほど重大なことかを伝えている。そこから延長すると、人間は自分にとって大事なものを失うリスクを抱えて生きており、それは突然現実化する。また、それは自責によるものとは限らず、他責によったり、単なる偶然であったり、運命的なものであったりする。そういうことの表現とも解釈できる。さらに考えを広げると、人間は皆、生きる過程で大なり小なり心身のハンデを抱えており、環境に脅かされているのであり、そういうものとして見た場合、人種やその他の区別を乗り越えて共感し、理解し合えることができるのだというメッセージとしても受け取れるのである。アメリカは分断社会であり、それは益々深刻化している。アメリカの映画人はその危機感を背負っている。私としてはそこまで拡大して解釈したい。
繊細な音の表現
主人公のルーベンは恋人のルーと共にバンドを組みトレーラーハウスでアメリカ各地を移動しながらライブに明け暮れる日々を送っている。
しかし、ある日突発性難聴を患い、ほとんど耳が聞こえなくなってしまう。自暴自棄に陥るルーベンをルーは世間から隔絶された、聴覚障がい者の支援コミュニティーに入ることを提案。これまでとは全く違う環境で、ルーベンは自らの人生を前に向けるため、ある決断をする…。
まさに音に導かれる120分間だ。
冒頭のメタル演奏のシーンから観客はルーベンが感じ取っている音の世界に一気に包み込まれる。
爆音の中、ルーとの息の合ったセッションからは逃れることができず、片時も目が離せない。
しかし、それは突然やってくる。
突如耳鳴りがしたかと思えば、そこからはジェットコースターを降るかのように音を失っていく。
今作はその『音』に深く重点を当てている。繊細な音の表現が難聴の疑似体験かの如く観客を魅了していく。
シネマート新宿さんのブーストサウンドの重低音が身体の奥の奥まで響いたかと思えば、細かな自然の音は優しく耳を撫でる。まさに極上の音像体験だ。
ろう者の支援コミュニティでのやり取りも骨太だ。彼らは『耳が聞こえない』というハンディキャップをひとつの経験として捉えている。つまり、ハンディキャップではないのだ。『耳が聞こえない?だからなんだ?』と言わんばかりの強いメッセージ性には胸が熱くなる。
また、手話のできないルーベンと被せて、敢えて手話に字幕を入れない演出はとても粋だ。
耳が聞こえなくなり、自暴自棄になった主人公が前を向き、少しずつ再生していく様子を描く本作。突如として自分の身に降りかかった現実を受け止めることの難しさや困難さは、"明日は我が身"という言葉がある通り、映画を観ている私たちも120分間疑似体験することができる。喪ったものを数えるのではなく、いま自分にできることを見つめ、まさしく五体満足の私たちが、今日、明日やれることを考えると、日々はより輝いていくのではないでしょうか。
二人がとてもステキ Rock Steady❗
ドラムがカウントとって始めれば、ライブなんとかなるんじゃないのかと、難聴になっても諦め切れないドラマーのルーベン。ボーカル&ギターで、彼女のルーとの会話もままならないし、やけっぱちになるが、ルーは薄い眉毛の見た目と違ってものすごく冷静で賢かった。そして、施設のJoe が素晴らしかった。ベトナム戦争で難聴になったといっていた。携帯、トレーラーの鍵も取り上げる。ルーとのコミュニケーションも断たれる訳だが、ルーのSNSをPCから隠れて時々チェックし、すこしづつ落ち着いてゆくルーベン。ルーはルーベンのために永遠の別れも覚悟したかもしれない。あの施設で手話を学び、コミュニケーションできるようになり、聴力障害の子供たちからの信頼も得て、見違えるほど生き生きとしてゆくルーベン。ジョーも施設でジョーのプログラム(聴力障害を持つ薬物依存者の支援)の手伝いや教会の学校で子供たちの世話をする正職員としてすごさないかと持ちかける。しかし、聴力を取り戻し、音楽活動を再開するために、2万ドル以上する手術(人工内耳)にこだわり、トレーラーハウスの中の機材やドラムセットを売り、とうとうトレーラーハウスも手放し、ジョーに黙って手術を受ける。
ジョー役のおじさんが渋くてカッコよかった。
ドラムセットを手放す前夜のソロ演奏が森の中に響く。シンバルはジルジャン。ドラムはたぶんパールだろう。スティックはパールが出しているヒッコリーの量販品だった。私もパールのバーチシェルのBXシリーズを譲ってしまう前は辛かった。お茶の水で30年以上前に新品で買ったもので、色はこの映画同様、パールホワイトで、シンバルを増やして60万円以上は当時使った。
補聴器の音は一定せず、周囲の環境によって違ってくる。ハウリングやディストーション、突然の爆音などかなりきつい。ルーベンのあてははずれだった、と思う。
彼は聴力のみならず、バンドやドラムセットも器材もトレーラーハウスも失ったが、ルーとジョーや子供たち、子供たちの先生役の笑顔が眩しいローレン・リドロフ(エターナルズでの出演が控えている)からかけがえのない大切なものを貰った。その自信に裏打ちされた最後のシーンでの表情がそれを雄弁に語っていた。
テーマも斬新で、見せ方、聞かせ方が素晴らしかった。なにより、ルーとルーベンの関係がよかった。ルーのお父さんの弾く曲は変わってた。フランス人の役者さんで、シャンソン風。ルーはもうロックは足を洗ったよう。シックだった。
そういえば、15年ぐらい前、骨伝導機能携帯が発売されたが、今も売ってるのかな?
恋愛映画でもある
お偉いさんがマンチェスターCのファンなんじゃ???
主人公の名前が気になりつつ、主人公はサラーに似てる。
日本版だけなのかもしれないが、生活音の説明的な字幕の入れ方に興醒めした。
2人が施設前で離れ離れになるシーンだって、もっと詩的と言うかアカデミックに表現したら、世界観にのめり込めたと思う。
ーーーーーー
人生の途上で障害を負うことのしんどさ
辿り着いた先人の教え
生まれ変わる覚悟が清々しい静寂と共に訪れる
彼女の家を出た後の街並がそれまでとガラッと景色が変わるのは果たして、、
全27件中、1~20件目を表示