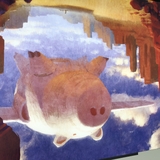サウンド・オブ・メタル 聞こえるということのレビュー・感想・評価
全114件中、81~100件目を表示
ドラマティックな受容プロセス
認知症や障害、もしくは余命宣告を受けた人(そして時にはその家族も)がたどる心理的なプロセスは、概ね否認→混乱→努力→受容となるようだ(プロセスの区分はいろいろある)。私も母が認知症になったとき、同じような思いをした。自分が障害を持つことになったら受容までにかなり時間がかかるんじゃないかと想像してしまう。ましてやバンドのドラマーとして活動していた人が聴覚を失うなんて、そのショックは想像以上だろう。
聴覚障害者を支援する施設で生活するようになったルーベンが、徐々に皆を受け入れ交流していく過程、特に静寂の部屋でノートに向き合うルーベンの変化がとてもよかった。実際にこんなセラピーもあるのかもしれない。
でも映画だからここで終わるわけがない。ルーベンが手に入れたかったのは元の自分と元の生活。やはりそれを取り戻そうとしてしまうのだろうか。ガン患者とその家族が怪しい民間療法にすがる姿とダブってしまい切ない気持ちになった。そしてインプラント手術で手に入れた機械仕掛けの音たち。聞こえたのは美しかった世界の物音ではなく、歪んだエフェクトのかかったノイズでしかなかった。最後、イヤホンをはずしたルーベンの表情はまさに「受容」。元の静寂の世界に戻る彼の姿はとても穏やかで美しかった。
まさにフクロウみたい
私は、聴力を失った男性が、元には戻れず、
彼女とも別れ、インプラントの手術をしたものの結局は聞こえない世界で生きる姿に、元には戻れなかったと悲しくなりました。
しかし、一緒に見ていた人は、
最後彼が晴れ晴れした顔をしていた姿から、再び歩き出す印象を受けたそうでした。
自分の感じたことは否定しませんが、
私は自分の視点(もし自分なら)で、
彼がかわいそうだ。と思いながら見ていたが、友人は彼の視点で映画を体験していたのだなと思った。
彼のフクロウのような
何か薬をやっていた、やっていそうな
顔つきからだんだん変わる演技がすごいなと思いました。
また、映画館でオデッサという?すごいところで見ましたが、
逆に音が大きすぎて、耳が痛くなってしまいました。
それでも、聞こえなくなる時
正常に聞こえている時
静寂
その違いがよく分かり、帰り道では耳をいろいろな音に傾けたくなりました。
自分が、当たり前に聞こえていることに感謝です。
静寂は自分を包み込んで許してくれる。
人にそれを求めるのじゃなくて、
周りの静寂は、いつでも私を許してくれているのだということに気づきました。
文句なし!胸にズサリきた映画
我々が日々あたり前に聞こえている音が突然聞こえなくなった時人生はどうなるか。改めて考えさせられた映画だった。ドラマーのルーベンが突然難聴になり恋人のルーに難聴者コミュニティに釣れていかれたがコミュニティの人々と過ごしながら現実を受け入れることに苦労しながらも徐々にコミュニティに馴染みながら自分の人生を前に進めていく決断を描いたストーリーは胸にズシッときたし考えさせられた。人生の挫折、再生の描き方は文句なし。今年のベスト洋画候補。ぜひおすすめしたい。アマゾンプライムの配信映画も侮れない。
(劇場版は)デフォルトで「バリアフリー上映」です。
今年130本目(合計194本目)。
アマゾンプライムなどでは先行で観られたようですが、劇場版では内容のメッセージ性に配慮してすべていわゆる「バリアフリー上映」ということです(公式サイトに記載あり)。
そのため、アマゾンプライム版の感想とはまた違ったところがポイントになるのかなと思います。
「バリアフリー上映」というのは、たとえば音楽が流れてくるところは「♪~」とか表示されたり、視覚障害をお持ちの方であれば音声で「●×が入っていくシーン」とか聞けたり(貸出できる専用の機械があるそうです)タイプの映画の類型を言います。
上記のような事情から、劇場公開は今日ですがすでに多くの感想があり、お話の流れ「それ自体」は同じであり、他の方と同じことを書いても仕方がないのでほぼほぼ省略しましょう。私自身も感想としては多少の差異はあっても多くの方の感想と同じところに行きついていますから。
ここでいう「サウンド・オブ・メタル」はやはりダブルミーニングであり、「メタル系音楽」と「機械を通じて聞こえてくる金属的な音」という意味に解するのが妥当に思えます。
さて、そのような事情のため、「音楽映画」と最初は思いますが、ストーリーの8割以上はろう者・難聴者のコミュニティの話になります。そのため、その文化の理解がある程度ないと、わかりにくいかな、とは思いました。
▼ (聴力検査を受ける時)単語を繰り返して?って聞かれるシーン
→ 聴力テストのことです。日本では身体障害者の認定基準は区分(この場合なら、聴覚)ごとに決まりがあり「ランダムなひらがな表を医師等が読んでどれだけ聞き取れたか」で決まる等級があります(ただし、詐術されやすいので、できるだけ客観的な聞こえる範囲を測定できるデータと一緒に申請することが日本では望まれています)。
▼ ろう者コミュニティで机をバンバン叩くシーン
→ 音は聞こえないか聞こえづらい(難聴の場合)ですが、音が立っていることはいわゆる独特な「震源」でわかります。このように、どんどんばんばん叩くのはこのためです
▼ 「あなたのサインネーム」
→ サインネームは、日本でもろう文化において、特定の個人を簡単な手話で表す表現のことです。似た概念でいえば「ハンドルネーム」「ペンネーム」などが近いのでしょうか。
▼ 「いや、問題ないんだ、口で読むから」
→ このような方法を「読唇術」(どくしんじゅつ)といいますが、この映画は架空のお話で撮影等もコロナ問題勃発前だったのでしょうか…。今はマスクをつけるのが常識になっているので、舞台のアメリカも、ここ日本も、読唇に頼る方がいるのもまた事実(簡単な内容なら、それで聞き取れてしまうが、全体の理解度は4割程度(相手がゆっくり話せばその率は上がり、むちゃくちゃ話されると0に近くなる)とされる)です。
これらの部分の説明がなく、また、一部を除いてアメリカ手話の字幕もないところがあるので、それは「誰が見ても」わからないのでは…と思います(日本手話(※1)とアメリカ手話はそもそも語の体系が違います)。この部分は、「日本においては」、日本でアメリカ手話を理解できる方というのはかなり少ないのではないかと思いますので(日本手話とそもそも違います。日本手話は言語的には、韓国手話や台湾手話に影響を与えたほう)、その意味で「誰も聞こえない・わからない」空間を作ることに、結果的には「成功した」とは言えるかな、とは思えます。
-----
(※1) 日本では、伝統的に使われる「日本手話」と、いわゆる中途失聴の方を対象にした「日本語対応手話」の2つがあります(後者は、てにをはまで全て表現する)。ただ、どちらも一長一短な面があるため、日本ではこの良い点を混ぜて使う「中間手話」というのが一般的な理解での「日本手話」です(NHKなどの「みんなの手話」や「手話ニュース」も、特段のことわりがない限り、中間手話基準です)。
-----
ということで採点です。
------------------------------------------------------------
(減点0.3) 劇場版はすべてバリアフリー上映とのことで、それは「バリアフリー」、換言すれば「機会の均等性」を保証したという意味では画期的かと思います。
そのために字幕が倍以上になっている(半分は、ろうの方や難聴の方向けのもので、(…)で、かっこ書きされている)部分があります。
また、カテゴリ的には「一応は」音楽映画なので、エンディングロールも音楽が流れますが、そこもバリアフリー上映というところも(♪~)なだけです。
(もっとも、この部分は英語で歌を歌っているだけで、聴者でも聞き取れないと無意味)
登場人物があまり多くない関係で、その(♪~)の部分、つまり音楽も長くはないですが、かといって「音楽」をテーマにしているのも事実であり、そうであれば、その配慮(どうしても、この映画のテーマは「一応」音楽であるため、それを全部(♪~)にすると、聴者はわかっても、ろうや難聴の方は確かめる方法が少なく、おいてけぼりにされてる?と勘繰られても仕方がない状況になっている点はこれは否めず、それはそれで「バリアフリー上映」の趣旨を没却しているかな、と思いました。
------------------------------------------------------------
トレーラーハウスで生活。旅しながらライブハウスで演奏し、生活するカ...
生は静寂の中に
昨年Amazon Prime Videoで配信された本作。来月から劇場公開に。
その前にU-NEXTでも配信され見れた事は嬉しいが、やはり劇場で観たかった気もする。注文付けるならば、音響設備のいい劇場で。
(と言っても、私の住んでいる近くでは上映しないだろうけど)
音。
この音の体感、臨場感!
序盤、激しいヘビメタ・ライブは耳に大音量を叩き込む。
突然の聴覚障害。キーンという音が続き、身の回りの音や相手の声もゴソゴソ程度にしかほとんど聞こえない。実際の聴覚障害者もあんな感じだと思うと…。
ネタバレだが、インプラント手術を受ける。また聞こえるようになるが、まるで無線のような雑音入り交じりのこれまでとは違う音。
合間合間の身の回りに溢れた自然音、生活音。
そして、静寂。
それらを巧みに“聞き分け”。
オスカー録音賞は当然。
劇場の大音響で聞きたかったが、ヘッドホンしてじっくり視聴したので、それはそれで良かったかも。
話はお察しの通り、
恋人ルーとバンドを組み、トレーラーハウスでアメリカ各地を周りながら、ライブに明け暮れるドラマーのルーベン。
時々耳が聞こえ難い事に気付き、医者に診て貰うと、聴覚を失ってしまう事が…。
ほぼ治る見込みはナシ。
インプラント手術を受ければまた聴こえるようになるが、金が掛かる。
耳が聞こえないなんて、一ミュージシャンにとって死活問題。
突然道を阻まれ、奈落の底に落とされたような…。
元々感情が激しいルーベン。荒れに荒れる。
ルーベンも痛ましいが、ルーもまたそう。
彼を支え、助けてあげたいけど、私の力じゃどうする事も出来ない。
そこで知人に相談し、聴覚障害者のコミュニティを知る。
他に手段も手立ても無い。
ここで暮らすには、外界とのやり取りは一切絶つ事。
つまり、ルーとは離れ離れになり、メールなど連絡すら取れない。き、厳しい…。
この一旦の別れの時のルーの台詞が印象的。
「自分を傷付けているという事は、私も傷付けているという事よ」
ルーベンとルーは似た所がある。
ルーベンは元薬物依存者、ルーは家族との関係に問題あり。
それぞれ背負ったものを、愛し、一緒にいる事で、支え、克服してきた。
彼女と再会する為に…。
ルーベンはコミュニティでの生活を始めるのだが…。
ここはあくまでコミュニティであって、病院ではない。
故に、また耳が聞こえるようになる治療や手術など行わない。
では、何を行うか?
耳の聞こえない困っている人たちへの支援。心の救済。
聴覚障害者としての生き方を受け入れる。
それが分からないのが、ルーベン。
俺は手術を受けたいんだ。また耳が聞こえるようになりたいんだ。そしてルーに会いたいんだ。
聴覚障害者の生き方やコミュニティの生活ルール云々なんて、どーだっていいんだ!
手話も分からない。
全く馴染めない。
また別のイライラが募る。
しかし、それでも徐々に、少しずつ…。
聴覚障害の子供たちとの触れ合い。あんなに何もかも受け入れを拒否してた男の心を開く子供たちの存在って凄い。
運営者ジョーの見守り、厳しさ、導き…。
手話も覚え、気付けばこのコミュニティ皆の人気者に。
元来人に好かれるタイプなのだ。
入所した時は思ってもみなかった、穏やかな日々…。
リズ・アーメッド、大熱演!
これまでのイメージを覆すワイルドな見た目に変貌。
ラッパーでもあり、半年間ドラムを猛特訓。手話もマスター。
でもそれ以上に、
絶望、焦り、怒り、苛立ち、悲しみ…。
音を閉ざされた独りの男の姿を体現。
そして、忘れ難いあのラストシーン…。
まさに、入魂。現時点でキャリア最高。
恋人ルー役のオリヴィア・クックも単なる支え役に留まらない複雑な役所。
特筆者は、運営者ジョー役のポール・レイシー。本作で知った初めましての方だが、名演! これぞTHE助演!
ルーベンを受け入れ、諭し、導く。存在感も抜群で、非常に美味しい役所。
手話にも長け、聴覚障害の両親の元に生まれたからだとか。
彼の存在がリアリティーを与えていた。
コミュニティでの生活や触れ合いはドキュメンタリーのよう。
過激なヘビメタ・シーンから始まり、主人公の感情に合わせ暗く重く、ドキュメンタリータッチも交え、辿り着いたラスト。
ダリウス・マーダーが初監督とは思えない手腕。
きっかけは、時々こっそり忍び込んでパソコンで見ていたルーのソロ活動。
ジョーからはいつしか頼りにされ、ここに残ってコミュニティの運営を手伝って欲しいとまで言われる。
おそらくルーベンは、そんな事を言われたのは初めてなのだろう。
悩む。選択。
彼が選んだのは…
やはり最初からの考えを変える事を出来なかった。
確かにここで、聴覚障害者としての生き方を学び、救われた。
でも、俺には俺の人生がある。会いたい人がいる。
ただ時間だけが過ぎていく、ここにいつまでも留まっているのは、俺の人生じゃない。
自分の人生が好転するか、間違いだったか。
例えそれが愚かであっても。
ルーベンの起こした行動は、愚かか、否か。
ジョーに黙って手術を受ける事を決意。手続きを済ませ、金はドラムなど身の回りのものやトレーラーハウスなどを売って。
苦渋の決断だが、ルーと再スタートする為なら…。
そして受けた手術。
また聞こえるようになったが…、期待と違った。
もうかつてのような音=世界ではない。
一度失ってしまったものは取り戻せない、残酷な現実。
再びコミュニティに戻るが…
コミュニティは耳の聞こえない困っている人たちへ助けの手を伸ばす。
手術で聞こえるようになったから…ではない。自己チューの者へ助けの手は伸ばさない。
ルーベンはルーの実家へ。
ここら辺で展開は予想出来た。
ルーはソロで成功。
確執あった父とは和解。
その日は賑やかなパーティー。
ルーベンにとってはただのうるさい雑音。居られやしない。
待ち望んだ再会、以前のような2人での暮らし。
そうか…。
これもそうだったのか…。
世界は音に包まれている。
音は素晴らしく、美しい。
しかし時としてその音が、苦しい時もある。
聞こえるという事は、生きる事だ。
耳を引き裂くような雑音、騒音。
人それぞれ捉え方はあるだろうが、また聞こえるようになったとは言え、こんな世界で生きていくのは苦だ。
彼は再び聴覚障害者としての生き方を受け入れる。そして辿り着く。
静寂の中の、生。
疑似体験
月並みですが聴こえることの有難さ、健常であることの有難さをしみじみ感じさせてくれる疑似体験型社会派ドラマ。
うるさい!というのはメタルロックでは褒め言葉だそうですが耳をつんざくような爆音から始まりラストの無音の終焉までこれほど耳を澄まし目を凝らしてしまった映画は珍しい。
ミュージシャンの主人公が聴力を失うというのも酷な話、かのベートベンもピアノの鍵盤に歯形が残っていたという逸話がある。
主人公と少年が滑り台を叩いて振動を体で感じて微笑むシーンは秀逸でした。象の足の裏には感音組織があり遠くの仲間と低周波音でコミュニケーションしているとテレビで聞いたことがある。
個人的には無音と静寂は別物、静寂は心で聴くのであって風にそよぐ木の葉の擦れる音、小川のせせらぎ、星の瞬きなども広い意味では静寂だと感じています。
映画のラストシーンの無音の街の光景とは真逆な印象ですが、昔、ウォークマンを付けて街へ出た時、見慣れた光景がまるで映画の一シーンのように変貌した体験は強烈に覚えています。聴覚が担っているのは実用的なコミュニケーション能力だけではないのです。
ただ映画の中でも語られるがろうあ者だから皆が不幸せと決めつけるのは短絡的なのでしょう。
メンタル的には観ていて楽しい部類の映画ではないので強いてのお勧めはできません。
人生賛歌
失うものがあれば、得るものもある。
そして、得るものがあれば失うものがある。
陳腐な言い方だけど、強く感じたのはこのこと。
たとえばルーベンは聴覚を失ったけれど、
これまでのジプシー生活では想像もできなかった心の平穏を、一時的にせよ得ることができた。
そしてインプラント手術で取り戻した聴覚は、以前のそれとは全く違うもの。
これはルーとの関係にも当てはまって、ルーの場合は無意識的なストレスからの解放というか、
これまで執着していたものから離れてみたら、意外と平穏じゃんっていうね。
お互いに「人生を救ってくれた相手」っていうのが切ないんだけど、
ルーベンとルーに幸あれ、と思わずにいられなかったし
すごく人生賛歌みたいな、ポジティブな物語に思えて爽やかな後味だった。
2回目は是非イヤホンで!!
日本語のサブタイトルは「聞こえるということ」となっていますが、どちらかというと主人公のルーベンが「聞こえないということ」を受け入れその生き方を選んでいく過程を描いた作品だと感じました。
サウンド・オブ・メタルというタイトルには、「ヘヴィメタルの音」と「補聴器を通した金属音」という2つの意味があるんですね。
【ラストについて】
暗くなりがちなテーマなので「ルーと再開したら新しい恋人がいた」というバッドエンドだけはやめてくれ!と恐れながら観ていましたが、そんなチープな発想は軽く払拭してくれる、余韻の残る良い終わり方でした。
考えさせられるラストですがルーベンは2つの選択をしました。
1つ目の選択は、別の生き方を見つけたルーに対して、自分と一緒ではまた腕を搔きむしるような破滅的な生活に戻ってしまうことを予感し「別れを告げたこと」です。ルーはルーベンのことを想って「また放浪生活をしてもいい」という態度を取りかけていました。それだけにルーベンにとっては勇気のいることでした。
2つ目の選択は、インプラントを外して「音のない生き方を選んだこと」です。そこで映画は終わるので、そのあとルーベンがどういった生き方をするのかはわかりません。おそらくはインプラントに頼らない自然な生き方をすることになるのでしょう。もしかしたらコミュニティに戻ったのかもしれません。そうなってあの学校の先生と付き合ったりしたら最高ですね。
この2つの選択には、「自分よりも他人の利益を考える」、「つらい現実を受け入れて前向きに生きていく」という大事なメッセージがあると思いました。メタルバンドのドラマーで薬物依存症というルーベンが、コミュニティでの生活を通じてこの選択をできるようになる。この成長が良かったです。
【イヤホンでの視聴をおすすめします】
今回、TVに繋いだスピーカーの調子が悪かったので、偶然イヤホンで本作を視聴することになりました。途中まではどちらでもよかったのですが、インプラント経由の音を聴いた瞬間まるでルーベンが聴いている音を自分でも聴いているように感じるほど臨場感が段違いに変わりました。入ってくる音の全てが金属的で「今後この音でしか聞こえないのか・・・」というルーベンの絶望感が痛いほど伝わってきました。ルー宅のパーティのシーンでは周りの音を上手く聞き分けられないルーベンが感じた疎外感がよくわかり、つらい気持ちになりました。
ということで本作へより没入したい方にはイヤホンでの再視聴をおすすめします。
突然耳が聞こえなくなる、話の中心に思えたこの事態が悲劇ではなかった...
生き方考え方を教わる。
ろう者の状態が分かって、
自分には関係ないものではなく身近なものとして感じられる
映画でした。
どんどん耳が聞こえなくなる主人公と、
その状況に合わした音で辛さが理解出来る。
とても不快で不便でイライラが手に取る様に分かった。
そこから、ろう者のコミュニティに入り、
最初は馴染めずにいた主人公が、
どんどん、真人間というかイライラがなくなってる
のを感じられるが、彼女のために手術を決断する。
手術は成功なんだろうけど、
その音がとても不快で金属を通して伝わるような
ノイズ混じりで主人公は絶望する。
コミュニティの人が静けさを得ただろ?
ろう者にはろう者の生き方があるんだよ。と諭すシーンが
印象的。
物語を通して、
序盤は耳が聞こえて良かった。耳大切にしよと思うのだけど
ラストには、それって幸せか?と思う不思議。
蔑んだり比べたりするではなく、
人には人の生き方があって、
哀れんだりする自分の心の醜さを知ってしまう映画でも
ありました。
あの後の主人公がどうなりどこへ行くのかはとても気に
なります。
インプラントって歯科領域だけじゃないのね・・・
彼らの音楽はメタル?どちらかというと前衛的なパンクに聞こえたのだが、メタルという意味はもっと後から出てくるんかな?などと期待は高まっていく。
医者からは治る見込みはないと告げられるし、インプラントは2~4万ドルとひどく高価な手術だという。恋人ルーの勧めもあって、ろう者コミュニティに参加したルーベン。最初は手術を受けることしか頭になく、手話も覚える気がなかったのに徐々に馴染んでいくのだ。
今までにないほど素直になれる作品。というのも、こうした突発的な病気に罹ってしまったら、癇癪を起したり独善的になったりと、彼の風貌からしても乱暴者になることが想像できるのに、まったくそうはならない。ある意味、従順で高潔なイメージさえもたらしてくれるのだ。しかし、子どもたちにドラムの基礎を教えたりピアノの音を触って感じる訓練をしていくうちに、ドラマーに戻る希望を断ち切れなくなってしまい・・・
後半は手術を受けてからのルーベンの様子。全体的に鳥のさえずりとか自然の音が効果的に用いられているのに、都会に住むルーの家の周りにはノイジーとしか思えない雑音ばかり。完全な聴力回復ではなく、脳を刺激するという手術には弱点があったのだ。ルーの歌う曲でさえ雑音に阻まれ良さがわからなくなってくるルーベン。トレーラーハウスでジプシーのような全国ツアーは互いを救ってくれたし、二人をそれぞれ幸せに導いてくれた・・・それだけを思い出にして新生活をスタートできるのか?ドラマーだからといって繊細なメロディーを追わなくてもすむのか?彼の決断がラストシーンに集約され、見事な余韻を残してくれる。
自然の音と比較して雑踏の中の騒音。澄んだ音から重苦しくメタリックな効果音が脳を突き刺すのだ。この音作りがとても凄い。オーバードライブさせて、ファズをかけて、メタリックな倍音とホワイトノイズを付け加えたような、風邪ひいたときに頭がガンガンするみたいな感覚にさえ陥ってしまう。静寂の美しさもたまらん!
最高の映画だった
作品賞、主演男優賞
獲れると思っていたが、残念。
それほどに最高に
この人生と運命に素直な映画だった。
リズアーメッドのピュアな演技。
まるで全てが初めてというような顔。
素晴らしかった。
オリビアクック、
最初の方では彼女だと気づかなかった、、。
ジョーを演じたポールレイシーの演技も良かった。
諦めと悟りの間で生きている感じ。
難聴のリアリティと、
そして最後、サイレントになった世界で
その素晴らしさ、繊細さに気づく主人公。
我々も完全に彼と同化して、
改めてこの世界の美しさに気付かされる。
そこに報いや軌跡がなくても。
根っこは善人なのに辛いことがいくつも起こる。 それが障害の怖さ、人間の身体の摂理
難聴になったドラマーの話。今年のアカデミー賞ノミネートも納得の良作。
自分みたいに爆音音楽好きな人間は気をつけないと、いや覚悟しないといけないなと身につまされた。
全音楽ファンに見てほしい。
人によって考えの違いはあれど、悪人がまったくいない。
主人公も根っこは善人なのに辛いことがいくつも起こる。
それが障害の怖さ、人間の身体の摂理なんだな、と。
難聴になっていく過程がとてもリアルで、ドキュメンタリー感すらある。
タイトルの”メタル”がトリプル・ミーニングくらいになっている物語構造も面白い。
主人公を演じるリズ・アーメッドがめっちゃイケメン。
一番かっこいいときのチノ・モレノっぽいセクシーさ。ツボ直撃でした。
彼の心情の動きを見る映画。
それを成り立たせている演技は見事でした。主演男優賞いけるんじゃないか?
ちなみに主人公のバンドは日本でいうメタルでなくMETZやJapandroidsみたいなオルタナ系。
だから余計に自分みたいにノイズやらを聴いてるのが一番あぶないと怖くなったり;
主人公の着てるバンドTが面白くて、アインシュタイン・ノイバウテン、Rudimentaru Peni、Youth of today、そしてなんとギズムも!
こりゃニヤニヤするでしょー。
つまりは自分みたいな音楽趣味が一番危ない;
ただ作中では大音量のせい、とは明確に描いてないんよな
聞こえないということ
自分を受け入れることの大切さと難しさ
全114件中、81~100件目を表示