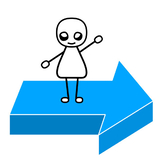サウンド・オブ・メタル 聞こえるということのレビュー・感想・評価
全115件中、41~60件目を表示
聴覚を失うことの意味を知った
ドラマーのルーベンはギター/ヴォーカルの恋人ルーとヘビメタのバンドを組み、トレーラーハウスでアメリカ各地を巡っていた。
しかし突然(ほとんど)聞こえなくなった。
これは厳しかった。
自暴自棄になるのもやむなし。
支援コミュニティへ参加して上を向いた。
更に手術して元に戻るかと思いきや、そこはアンナチュラルなノイズの世界だった。耳で聴く音とはまったく違っていた。
二度絶望してからのこれから。
ルーベンは音のない世界で前を向く予感が。
大丈夫だという予感が。
これはハードな作品だった。
自分は果たして受け止められるだろうか。
不思議な感覚
【ヘビーメタルバンドのドラマーが、聴力を失い、難聴者施設に入りながらも夢を求めて、”決断”する姿。だが、世の中は歪んだ音に溢れていて・・。ラスト、彼の無音の世界を愛おしむ清々しい表情が素晴しい。】
<Caution ! 内容に触れています。>
◆感想
・突然、耳が聞こえなくなったら、眼が見えなくなったら、私はどうするだろうかと、観賞しながら思った。絶望故に、自暴自棄になる可能性は高い・・。
・今作のヘビーメタルバンドのドラマー、ルーベンはある日、聴覚がおかしくなっている事に気付きながら、恋人ルー(オリビア・クック)と組むバンドツアーを続ける。
けれども、それも限界にきて、ルーの勧めで医者へ。診療結果で、聴力の75%が失われている事が分かる。手術には4-8万ドルが掛かる事も・・。
- ルーベンの苛立ち、ルーの哀しみと心配を綯交ぜにした表情。ルーベンは逡巡もあったが、ルーと一時的に別れ、聴覚障碍者のジョーが運営する難聴者コミュニティに入る。
そこで、彼は手話を覚え、子供たちと交流し、コミュニティには欠かせない存在になって行く。
楽しそうに子供たちと手話で会話する姿。
だが、ある子どもと、滑り台で手でドラミングをして遊ぶ中、彼の心は揺らぐ。
ルーベンを演じたリズ・アーメッドの表情の変化。
苛立ちから、絶望、そして僅かの希望、恋人ルーへの想い。ー
・又、今作では独特な音響効果と、字幕が印象的である。資料によるとバリアフリー字幕とある。成程。
・そして、ルーベンは耳の手術をする決断をする。が、それは彼が馴染んだ難聴者コミュニティとの別れも意味するのである。
- ルーベンが手術した後、ジョーに申し出た”少しで良いから、ここにおいてくれ”と言う言葉を哀し気に断るジョー。-
・ルーベンはフランスに戻ったルーの実家を訪れる。そこで出会ったルーの父、リチャード(フランスの名優、マチュー・アマルリック!! 個人的に嬉しい。)との会話。
”昔は君が嫌いだった・・。だが、今は違う。”
そして、一緒にツアーをしていた時とは別人の様なルーの姿。
ー ベッドで抱き合いながら、二人で流した涙。
そして、ルーベンはルーはもう自分とは違う人生を歩み始めたのだ・・、と思い、翌朝一人静に、ルーの家を後にする。
彼が、人間的に成長した事が良く分かるシーンである。
<街中に出たルーベンに聞こえて来るディストーションが掛かった街中の車の音、鐘の音、子供たちの声。
その音に耐え切れず、手術後に取付けた骨導インプラント器具を自ら外すと、そこには無音の美しき世界が広がっていた。
その際のルーベンの晴れやかな顔は忘れ難い。
どん底に叩き落とされた男が、数々の経験をし、人間としても成長を遂げ、辿り着いた境地。
彼の未来は、きっと明るく、開けている筈だ。>
<2022年11月21日 刈谷日劇にて鑑賞>
失うことの怖さ
タイトルなし(ネタバレ)
メタルバンドのドラマーのルーベン(リズ・アーメッド)は激しい演奏のせいかどうか、突発性難聴に襲われてしまう。
原因は不明。
器具を埋め込む手術をすればいくらか聞こえるようになるかもしれないが・・・と言葉を濁す医者。
しかし、手術費用は高額。
恋人で一緒にバンドを組む恋人ルー(オリヴィア・クック)は、伝手を頼って、難聴者のコミュニティに連れていくが、コミュニティの主催者ジョー(ポール・レイシー)は、聾や難聴をハンディとして捉えず、その状態を受け容れての生活をルーベンに勧める。
ルーと離れてコミュニティで暮らすルーベンであったが、現実を受け容れることはなかなか難しかったが、コミュニティでの居場所・立場が出来たことで、少しずつ現実を受け容れられるようになっていく。
しかし、手術をすれば・・・という思いは立ちがたく・・・
といった物語で、タイトルの「サウンド・オブ・メタル」には3つの意味が掛けられているように思えました。
ひとつめは、主人公が演奏するバンドのメタルサウンド。
ふたつめは、難聴に襲われ、聞こえづらくなってきたときの、ノイズ音。
みっつめは、手術後に器具を通して聞こえる金属的な歪んだ音。
それらみっつの音質を見事にサウンド化しており、アカデミー賞音響賞受賞もなるほどと肯けます。
映画的には、ある種の宗教色を感じました。
ひとつは、ジョーが主催する難聴者のコミュニティの描き方で、教会が支援しているということが告げられますが、ジョー自身が牧師のようにみえるよう演出しています。
牧師のような様相ではないのですが、デニムシャツの下に着ている白いアンダーシャツが襟元から覗いており、それが牧師のホワイトカラーのようにも見えます。
また、難聴はハンディキャップではない、と言いつつも、健聴者を排除していることから、逆に排他的であり、他の宗派を受け容れないキリスト教の頑なさとも重なってきます。
もうひとつは、最終盤。
手術しても元のように聞こえず失望したルーベンに教会の鐘の音が鳴り響くのですが、その歪んだ音に耐え切れなくなった彼は、手術で取り付けた器具を外し、静寂を選び取ります。
キリスト教会の鐘は、イスラム教徒のルーベン(明確にそうだとは描かれていませんが)を救ってくれないように読み取れます。
ルーベンを救うのは、静寂を選んだ自分自身・・・
そう考えると、かなり遣る瀬無くなるラストですね。
雑音のない世界
生き方を考える
病気になって失うもの、そして•••
コロナ後の公開ラッシュで、配信で観られるものは観てしまえの勢いでアマプラで観ました。
良かった。特に聾者(になりつつある人)の聞こえ方などがリアルに再現されていた(自分が突発性難聴になった時と凄く似た感じだった)。
病気になる喪失感、その後、病気になって初めて得られるものがエンディングで体験できた。
劇場で、もう一回観るかもです。
究極の愛の物語
恋人同士ながら、同じバンドで活動し、2人でトレーラーに寝泊まりしながら全米をツアーする男女の話。
ルーベンは徐々に難聴に陥り、やがて会話がまったく聴き取れなくなる。
ツアーを続けたいという主人公・ルーベンと、今すぐ中止して治療に専念してほしい恋人・ルー。
ルーベンはミュージシャンとして最も大事な聴覚を失うというどん底を味わう。
なるほど、中盤くらいまでは、このルーベンの喪失と再生の話かと思っていた。
入所した聴覚障がい者の施設でも、徐々に彼は居場所を見つけていく。
ここまではまあ予想できた話だ。
しかし、終盤に至る彼の行動はルーに対する究極の愛だったのだろう。
家庭に恵まれなかったルーベンに居場所を与えてくれたルー。
そうか、彼が本当に取り戻したかったのは聴覚ではなく、聴覚を取り戻し、ルーとまた音楽をして、彼が居場所を取り戻すこと。なるほど、深い。
しかし、彼はパリを訪れた際のルーの雰囲気や生活に、そして自分の聴覚が思ったものとは違うという自覚に、彼女を取り戻すことなく、自ら身を引く。
最後のシーンはまさに彼の身上を象徴するような名シーンだった。
この映画はたった一つの愛の形を見せたものだと思う。彼はルーを通して何を観たか、何を得たか。そして、聴覚を失って彼のルーに対する愛は大きくなったのだろう。
しかし、やはり愛は脆い。彼の最後に見せた行動もルーへの究極の愛だった。
予告編の雰囲気から、自分がこういった感想を持つとは思わなかった。
しかし、これもまたこの映画の深さかと思う。
あと、内容とは別に今作の音作り。
劇場では他の作品よりやや大きい音量に設定されていたような気がする。
あの音の設定はきっと劇場レベルの音響じゃないとできないものだろう。
まさに疑似体験と言えるだろう。
あの不快な音は、自宅レベルで体験することはできない。より、主人公の不快な音を体験するのは劇場に限る。
失い、向き合った日々
これは開放か破滅か
ポスターを見る限り、タイトルの「メタル」はきっと「ヘビーメタル」なのだろうな
と思い鑑賞するも、違っていた。
テーマは「依存からの解放」だと思える本作。
本当に欲しいものが手に入らないから、代替品にしがみついてしまう依存。
そんな依存のうちに迷走する主人公は、ドラッグに始まり、ほかにも生活の至る所に依存の対象が顔をのぞかせている。
その一つが音楽だったとして、
音楽を追えば追うほど「真に欲しい物」こそ手に入らない様が、
むしろすれ違いと勘違いで失われてゆく喪失感が強烈だった。
だからして最後、しがみついてきたもの全てを手放したとき訪れる安堵と平穏は救いのようにも感じられるが、
同時に、しがみついてきたものばかりで出来上がっているような主人公にとってそれは「無」を感じさせてならず、
エンドロールが流れている間、これで主人公は本当にこで救われたのか、
救われるのか、
果たしてその逆まで行き着いてしまっただけか、とても考えさせられた。
ろうの世界を体験できる音響演出が、時々自分はちゃんと聞こえているのか、
不安にさせるリアルさ。
ゆえに音楽で煽る演出はまるでないものの、
そんなことなど忘れさせるほどの濃い作品と鑑賞する。
とにかく進むしかない
その選択が最適解だったのかは、その時はわからない。
中途で聴覚障がいを受け入れざるをえない過程をリアルに描いている
障がいを負って、その障がいを負担に思い、拒み、悩み、逃れようとするのが普通。しかし多くの場合は、病気と違って治らないから障がいとされているのであり、よしんば治す手立てがあったとしても元の状態にはまず戻らない。よって心の持ち方からはじめて、心身共に健やかな生活を送るには、障がいを受け入れる必要がある。障がいがあっても、自分で自分を幸せだと思える生活はできるのだと。「障がいは不便ではあるけれど不幸ではない」
しかし、簡単なことではない。映画はそこを描いている。できなくなること、失うものは覚悟しなければならない。それまでの積み重ねたものを一切破棄するこを強いられたりもする。そんなことをしてまで、その先の人生に意味はあるだろうか、と思い悩む。しかし、それしか道のないことをやがていやおうなしに悟る。
障がいには先天のものと中途のものがある。この軌道修正は中途の場合に強いられる。また聴覚障がいの場合、障がい者の人数が多いため、聴こえない社会、聴こえない文化というものができあがっていて、健常者の世界と隣り合わせに存在している。手話はその地の国語に依存しているが、言語が違えば文化は多少異なってくる。つまり、新たな人生のはじまりであり、生まれ変わることを強いられる。映画はそれを描ききっている。
トレーラーに住んで各地でドラムを叩く暮らしが、個人的にはそれほど魅力を感じなかったので、主人公ルーベンの悩みについていけなかった面はあるけど、本人にとっての大問題は、しょせん本人にしかわからないもの、という「孤立して闘わねばならない辛さ」はよく伝わってきた。
乗りこえたら楽になるのだろうけど、障がい以前の幸せが、大きければ大きいほど足をひっぱりそうである。戻りたかった暮らしがもう戻れそうにない感じに壊れていった点が、ルーベンには救いであったかもしれない。ときに絶望は、つぎの希望を導きもする。ルーベンは強引に障がいを打ち消そうともがいたが、前を向くことだけは外さなかった。だから最後の最後、絶望の向こう側に足を踏み入れることができた。よい終わり方だっと思う。
さすがアカデミー賞の音響賞・編集賞受賞作品。
全115件中、41~60件目を表示