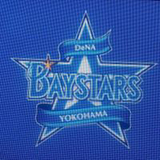ビバリウムのレビュー・感想・評価
全137件中、101~120件目を表示
エグキモい
とりあえず緑色と七三に対して
嫌悪感を抱くようになる映画
オープニングの描写がすべて。
それを人にしてみせていくわけですが
見せようとしたこと以外にも
子育ての側面を皮肉った感じ
などエッセンスがすごく
痛烈に心をえぐられた。
ミッドサマーとはまた違うえぐられ方でした。
田舎のミニシアターでしたが
観客も多くクチコミなのかな?
みんななんだかんだでこういう映画好きなんですね笑
ラストの終わり方とか、明確な答え欲しい人には
嫌かもですが
個人的にラストにみせられた描写が
すごく痛烈で
中盤の同じことの繰り返しをみせるより
そこらへんを
もっと掘り下げてほしかった
もっとそのせかいをみたかったです。
良くも悪くも好き嫌いわかれる作品
メンタル調子良い時にご鑑賞をどうぞ笑
理想と迷宮は紙一重。地獄にもなり得る。
マイホームを持ち、家庭を築きたいという「理想」。
概ね誰しもがそのような「理想」を描いたことがあるだろう。
しかし、それは抜け出すことのできない「迷宮」であるかもしれない。
家を買い、子供を産み、育て、死に、またその子供が家を買い、家庭を築く。
それは「理想」であるが永遠に続く「迷宮」でもあり、場合によっては「地獄」にもなり得る。
しかし、人間には少なからずも欲望があり、「理想」を描いてしまう。
それは人によって様々で、大きくもあり、小さくもある。
もし、それが今手に入るなら?
喜んで手を出してしまうだろう。
だから、このようにまんまと「理想」というワナにはまって抜け出せなくなってしまうのだ。
本作は様々な作品からの影響も受けつつ、極めて芸術的かつ斬新にこれを描いている。
あまり見ない挑戦的な作品だ。
本作の世界観はまるでマグリットの作品を彷彿とさせるような、美しいほどにシンプルで、夢にも見そうなまさにシュールレアリスティックな世界。
それが故により一層恐怖感を覚えるのであろう。
登場人物も少なく、割とシンプルに淡々とストーリーが進んでいく。
その中でも、イマージェン・プーツの演技は目を見張るものがあった。
愛らしい顔からは想像もつかない、『ヘレディタリー』でのアニー・グラハムを思わせるような怪演。
絶叫する表情表現は見事で、思わず引き込まれてしまった。
いくつか伏線もあって詮索するのも面白いが、できればただ純粋にこの世界観を楽しんでほしいと思う。
中途半端。
詰めが甘いのでもったいない
アバンで、托卵がテーマであることが明示され、それ以上でもそれ以下でもない映画。
ニュータウンの雰囲気、主人公カップルの距離感、不気味な不動産屋や子供など、あちこち面白い絵づくりはあるものの、軟禁されてる生活がとにかく退屈。
たくさん同じ家が並んでいるのになぜこのカップルしか住んでいないのか、子供に対して気持ちが変化することはないのかなどなど、そういった小さい描写の積み重ねがないので、せっかくのクライマックスの面白い画像が活きてこないしオチも昔のマンガみたい。
荒唐無稽でも「US」はその辺りにこだわりがあったなあ
ホラーのくせに淡々としすぎてる
家を探していたカップルが案内されたのは、同じ形の家が並ぶ住宅地。そこから脱出できなくなった2人は赤ん坊を託され育てることを強要されるというシチュエーションホラー。
序盤は予告で観ていたレベルを超えず、しかも淡々と進むので眠気と闘うのに精一杯だった。しかも眠気に負けてしまったときもあったし。
冒頭でカッコウの託卵の映像が流れたのでそんな話なのかと思ってたら、そこからブレることはなかった。子どもの叫び声が不快というだけで全然怖くなかったのだが、唯一おっ!と思ったのが、家の前の縁石を持ち上げて地下に潜っていくシーン。あの不気味な感じは悪くなかった。やっぱり他にもそんな人がいたんだねと。ただ、それ以上に深まることはなく、あれが一応のクライマックスだったようだ。
ラストも妙な雰囲気そのままで悪くはないのだが釈然とはしない。それなりに面白そうだと思っただけに残念だった。
まさに都市伝説にありそうな映画
なかなか良い
オープニングシーンがしっかり結末に。
【ゲームの世界に生きる】
なんか、ゲームの世界に生きるのは、こんな感じなんだろうなという気がする。
なんの気無しにゲームを始めて(モデルルームを訪ねて)みる。
目標(男の子を成長させる)を設定され、それを少しずつクリアしていく。
ふと疑問に思っても、もう止められない、止まらない。
どんどん深みにハマ(穴を掘っ)って、周りが見えなくなる。
本当は、自分の墓かもしれないのに。
確かに、ゲームの世界の何者か(子供)は成長するが、確かに、これは托卵のようでもある。
ジェマは、托卵は自然の摂理みたいに言ってたんだから、別に、本当の母親じゃなくても良いでしょって、後にマーティンになる子供が言ってる気がする。
それに、そもそも、後にマーティンになる子供の叫び声は、エサをくれと大声で鳴いているカッコーみたいじゃないか。
そう、ゲームの世界では、これが自然の摂理なのだ。
しかし、本当に成長しているのは、このゲームの世界を仕切ってる連中なんじゃないか。
肥え太るゲームの世界を仕切る連中。
ただ、ゲームの世界を仕切ってる連中だって、入れ替わる。
ゲームクリエーターなんて使い捨てかもしれない。
古いマーティンみたいに。
そして、痩せ細る殆どのプレーヤー。
そして、繰り返される。
賛否両論だと思うけど、皮肉たっぷりで、緊張感も続くし、僕は楽しめました。
本当は、不動産を巡って、翻弄される生活がテーマみたいなんですけどね。
新しい感覚のホラー
人間存在の意味を問うという新しい感覚のホラー映画である。次はどうするのか、主人公ふたりの選択をあれこれ想像しながら、面白く鑑賞できた。
序盤でカッコウの托卵のシーンがある。主人公のひとりトムが穴を掘って、落とされた雛を埋葬するのだが、それが何かのメタファーであることは薄っすらと想像がついた。
母性は少なくとも極限状況に於いては正しい判断の邪魔をする。特に人間の母性は動物のそれとは違って厳しさに欠けている。本作品でも主人公のひとりジェマの、おそらく母性に因すると推測される選択が、トムの行動を必定の方向に促してしまった。結末はメタファーの通りになってしまう。
ストーリーとしては一本道だが、元の世界と隔絶された、巨大な閉塞空間が舞台であり、主人公ふたり以外の人間との接点が皆無であることが、じわじわとした恐怖感を生み出す。変な化け物が登場するようなありふれたホラー映画よりもよほど怖い。
さらに怖いのが、変化のない毎日にただ年老いていくだけのトムとジェマの、人間としての存在意義の喪失感が引き潮のようにふたりからエネルギーを奪っていくことだ。熱気、活気、元気といった概念の対極にあるかのような底しれぬ寂寥感がふたりを包む。
リインカーネーションはホラー映画ではお馴染みだが、少なくともこれまでのホラーでは憎悪や怨恨といった動機も一緒に転生する。しかし本作品のリインカーネーションは何も継承しない。そこが逆に恐ろしい。人間は意味もなく生まれて意味もなく死んでいくだけなのだという知りたくない真理を事務的に開示されているかのようである。フランス映画みたいに哲学的な作品だ。傑作である。
アイデア100点だけど…
穴掘り仕事
【正直な感想書きます】
托卵(たくらん)を人類に置き換えた、こわ~い話。
「ビバリウム」(原題:Vivarium)。
とてつもなく気味悪いけれど知的な面白さがある。マトモな人なら困惑する映画だが、それは大自然に対する人間のエゴイズム(利己主義)なのかもしれない。
動物の托卵(たくらん)習性を人間に置き換えた実験的な作品。
新居を探すカップルのトマとジェマが、挙動の怪しい不動産屋に紹介された"Yonder(ヨンダー)"は、同じ形、同じ間取り、同じ色の建売住宅が並ぶ不思議な住宅開発地。案内された"9番の家"を内見していた2人が気付くと、近くにいたはずの不動産屋の姿が見えなくなっていた。
帰ろうとした2人がクルマを走らせるが、どこまでも続く同じ形の家。迷い込んだ2人が車を止めると再び"9番の家"の前。"Yonder(ヨンダー)"から抜け出せなくなったカップルの恐怖の生活が始まる。
毎日、食料や消耗品が入ったダンボールが家の前に届くが、いつ、誰が置いていくのかも分からない。そんなある日、ダンボールには赤ん坊が入っており、"育てれば開放される"の文字。
人間とは思えないスピードで成長していく赤ん坊に戸惑いながら、主人公たちとともに観客もどんどん精神崩壊の道連れになっていく。
この映画にフィクションとしての典型的なオチを求めることはできない。実際、先に述べたように単なる"托卵(たくらん)"の隠喩でしかないのだから。
"托卵(たくらん)とは、卵の世話を他の個体に托する動物の習性のことである。代わりの親は仮親と呼ばれる"(出典:Wikipedia)。
鳥類のカッコウが自分の卵をオオヨシキリの巣に托卵するようなもの。鳥類だけでなく昆虫や魚類でも同様の行為が見られ、自然界では特にレアケースというわけでもない。
自然界における人類は、動物の種のひとつに過ぎない。
もし人類に托卵を仕掛ける種がいたとして、それでも淡々と生活を続けるとしたら。
知恵を持つ人類は、"動物の頂点に君臨している"と勘違いしている。だから地球を汚し、傍若無人な行為に気をとめることもない。そんなことをこの作品は遠回しに警告しているのか。
カッコウの托卵については、"そういうもの"と理解してしまう割に、我々はこの作品の持つ隠喩に理不尽と思えるような混乱を受ける。
本気で、種の多様性を守るとしたら、すべての人間が生き残ることを前提とした自然環境活動さえも否定しかねない、こわ~いテーマだったりする。
(2021/3/13/TOHOシネマズシャンテ Screen1/G-10/シネスコ/字幕:柏野文映)
「怖い」ではなく「気味が悪い」止まり。でも及第点
ホラー映画の正解が「怖いこと」であるとするならば、この映画はギリギリ及第点といったところでしょうか
きちんと怖くて、なによりも気味が悪い
怖がりだった幼少期の自分が映画館で見ていたらおそらくトラウマになっていたことでしょう(笑)
とはいえ、あくまでも及第点。他の方もレビューしている通り、自分の想像を裏切ってくれないもどかしさや小道具・設定の説明不足による不完全燃焼を感じたのも事実です
それはさておいて、1番の謎はエイリアンはなぜあんなに回りくどい方法で子育てをしているのかです…
全137件中、101~120件目を表示