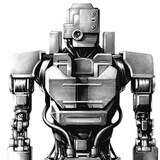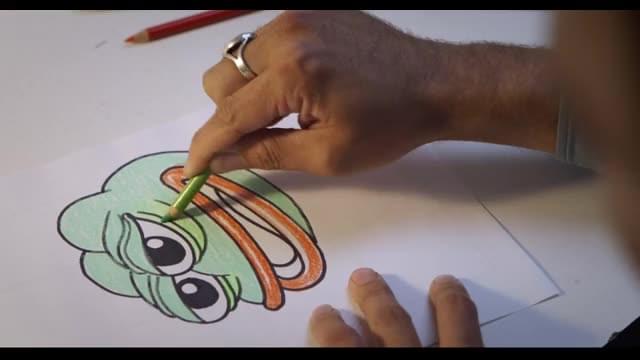フィールズ・グッド・マンのレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
カエルのPEPEに降りかかった苦悩と一筋の光。
現代社会が持つ光と影を鋭く突き付けるドキュメンタリーだ。これは決して高い垣根の向こう側の事例ではなく、この時代に生きる誰もが即座に関わりを持つかもしれない話。そもそも強固な連携によって「カエルのペペ」をカルト的人気を誇るキャラへ飛翔させたのもネットの力ならば、そこから一転、作者の意図とは全くかけ離れた”ヘイトシンボル”へ変貌させたのもネットの力だ。そしてペペがもはや制御不能となって増殖していく一方、本作の基軸となるのは、血の通った人間である作者、マット・フューリーの個性だろう。おおらかで柔らかな印象を持つ彼はいつも陽気に微笑んでいる。この曖昧な態度が事態を悪化させたとも本編中では指摘されるが、しかしそんな彼だからこそ皆から愛されるキャラを生み出せたのも事実。ペペとマットがこの先どんな運命を歩むのか見当もつかないが、ラストに示される”希望の胎動”が何よりの救いに思えたのは私だけでないはずだ。
A Humble Cartoonist's Work Hijacked by the Internet
Just passing out of the insanity-inducing Donald Trump presidency, Feels Good Man has us look back at one of the phenomena that promoted his initial campaign's success. I had seen Pepe the Frog pop up on my social media many times, but I was always confused as to what it really was. This documentary should set the record straight. But maybe you want to catch a break from all the Trump talk first.
アメリカのネットミームとなったペペ
マンガのキャラクター「カエルのペペ」が
作者の手を離れて
4chのネットミームになり
さらにトランプ現象によりヘイトシンボルとして
登録されてしまう
作者であるマットフェーリーの対応が遅すぎるという意見もあるが
日本でも変に規制をしようとすると
「表現の自由」という意見のために
対応が難しいとも思ってしまう。
ペペがヘイトアイコンになった理由はいろいろあるが
子供でも描ける、邪悪さを冗談にみせれるなどがあるらしいが
結果としてはただの偶然の産物なんだろうと思う
最後のほうにカエルのペペが
香港の民主化運動のアイコンとしても使われていたので
ペペは「弱者」「負け組」のアイコンとして使われやすいのだろうと思った
日本も対岸の火事ではないと考えるが
基本的に特定のキャラクターが政治的なムーブと結びつくことは少ないと思った
カエルのペペに近いのは「チーズ牛丼」ネタのイラストくらいかな?
日本は猫ミームなど実写を加工したミームが多い気がする
トランプは大統領再選したが
2024年もカエルのペペみたいなヘイトアイコンは
このときにあったのはわからない
その気持ちよさは誰がために
アーサー・ジョーンズ監督作品は初見。
『Boy's Club』も未見で、ペペの存在はトランプ大統領就任前に何度かSNSに流れてきてるのを見たことがある程度。
日本でも様々なキャラクターや人物をミームにしてシンボル化する現象がある中で、ヘイトシンボルになったネットミームをテーマにしたドキュメンタリーとして興味があったので観てみた。
観るまでは"被害者目線から悪意の基にヘイトシンボルにされた被害の経緯とインターネットの悪意の恐ろしさ"を描くのかと思ってたけどいざ観てみると、作者は被害者って言うよりもネットミームやヘイトシンボルひっくるめて利用した人間まとめて救済しようとしてるようにさえ感じた。
最初は純粋に創作物として産み出したものがネットの海に流れたことでデジタルタトゥーになりえる危険性は、ネットリテラシーの中でも最初の方に書かれていてもおかしくないくらいSNSや掲示板に昔から触れていた人には周知されているだろうけれど、この場合は作者のマット・フューリーさんが優しすぎたのとそれが4chに目を付けられるって言う最悪の取り合わせの結果ここまでの流れになったように思えた。
途中のシーンで4ch創設前から2ちゃんねるはあったのにそこに言及してないのは(本題から逸れるからってのは理解出来るものの)気になったな。
観賞後に4chについて調べてみたら日本の2ちゃんねるよりもかなり過激で、扇動やテロ活動、犯罪予告して実行に移す人間も多いってのを改めて知ったので4chがどういう掲示板なのかもうちょっと詳しくやって欲しかった気もするけど、この監督とプロデューサーが次作の『アンチソーシャル・ネットワーク 現実と妄想が交錯する世界』でそこについて描いてるのを知るとこの一作では語りきれないと思ったからこの作品で省いたのは理解出来た。
このドキュメンタリーで描かれた『Boy's Club』の概要だと、主人公のペペは(友人の擬人化とは言え)多種多様な動物と共に暮らし末っ子的な立場の友達として接してる"友愛"や"和平"のキャラクターでありながら、その背景を知らない人々に"暴力"や"分断"のアイコンとして使われているのはこの上ない皮肉に感じるし、4chanの(自称)虐げられている側の匿名の人々がペペをネットミームやヘイトシンボルとして使うことで作者や自由を掲げる人々を虐げる側の一員になり、”自分達が大統領を当選させるんだ”と右翼に扇動されて候補者への攻撃を仕掛け、インプレッション数や利益を得る一部のセレブ、富豪の都合の良い傀儡と化しているのも特段皮肉が効いているようにも思えた。
ただ最後に香港での民主化運動で、ペペが"友愛"や"和平"のシンボルとしてデモ隊のメンバーと手を繋ぎ"友愛"や"和平"のデモをしている姿はマット・フューリーさんが『Boy's Club』や他の作品で描いてきたことを体現しているようで感動した。
後々インタビューで、サンダンス映画祭に出品する2週間前に流れてきたニュースを見て急遽追加した、本来想定していないシーンだったことを知ってより驚いた。
今現在、トランプ政権が再び生まれてしまったけれど、もし選挙戦前にこれを観る人がもっと増えていたら結果は変わっていたんだろうか。
想像するよりも現実は非情だし情報操作して扇動する人々はいるのでネットリテラシーを持っておくことは必要だけれど、自分はマット・フューリーさんの描く作品や香港の民主化運動のように、"暴力"や"分断"の為に行動するんじゃなく"友愛"や"和平"の為に行動して「feels good man(気持ちいいぜ)」って言える、どこかにある人間の善性を信じたい。
PEPEはペペと発音するのに、MEMEはミームと発音するんだね!
4channelの存在も知らなかったし、アメリカのネット業界に興味津々となった。マット・フューリーが生み出したお気楽カエルの“ペペ”がやがてネット上で一人歩きをし、極悪なオルタナ右翼たちによってヘイトシンボルとして利用されてしまった。やがてそれはドナルド・トランプにまで・・・
日本でもネトウヨが蔓延っていますが、この映画を見る限り、オルト・ライトと似たような存在だと考えれば、同じように引きこもりでニートなのだろう。ただし、アメリカはそこからネオナチやトランプ支持の過激な差別主義者も現れたことだし、日本はまだおとなしいのかもしれない。
極悪イメージを払拭させるため、ついには使用停止訴訟も起こすマットだったが、ネットの個々の書き込みに対しては難しいのでしょう。コンピュータで数億のペペを抽出してましたけど、そのくらい大変な作業だ。そして、葬式まで出したのに右翼の使用は止まることを知らない。だけど、香港でのデモに使われたところで感動!やっぱり大勢の人に使われると効果絶大ですね。最後に日本人へのメッセージがあったりしたのですが、優しい気持ちにさせてくれました。
【“悲しみカエル”2016年の悪夢の米大統領選挙の前から起こっていた”模倣の負の連鎖”。悪意溢れるSNSに利用されたキャラクターや作者が経験した事を描く、恐ろしきポリティカルドキュメンタリー。】
ー サブカル漫画の少しキッチュな主人公ペペは、お気楽なカエルであった。
だが、劇中で発した一言”FEELS GOOD MAN”が、”ミーム”の対象にされ、作者のマット・フューリーの世界を飛び出し、世に不満を持つ一部の4チャネラーや、人種差別主義者、オルタナティブ右翼(オルト・ライト)、偽ニュースサイト運営者に、イメージを改悪されていく様や、果ては愚かしき米国前大統領の選挙の際に、利用され、ペペとマット・フューリーは、名誉棄損防止同盟から”ヘイトシンボル”として任命されてしまう・・。ー
■感想
・ペペを創作したマット・フューリーの初動対応の拙さが、歯がゆい。何で、早期に著作権違反として、無断使用した連中を告訴しなかったのか?
彼もまさかあんなことになるとは、思っていなかっただからであろうが、SNSの”負の”拡散威力を目の当たりにし、背筋が寒くなる。
・そもそもミームという言葉自体が、劇中でも説明されていたように、リチャード・ドーキンス博士が遺伝子学の観点から提唱した用語であり、現在の言葉の使われ方も、本来の趣旨とはかけ離れている。
・劇中でも、屡登場する4チャネラーのミルズが、自宅の地下室で語った言葉。温和な表情だけに、逆に怖かった。あの引き籠りの男性は良く、出演を了承したなあ。流石に両親の顔にはモザイクがかかっていたが・・。
・仮想通貨にまで使用されていたとは・・。
・トランプの勝利は、プアホワイトや、国粋主義に染まった人々を巧みに誘導した結果だと思っていたが、今作で描かれた「インフォウォーズ」や、”オルト・ライト”も巻き込んでいたのか・・。
それにしても、ヒラリーがあのタイミングで、ペペ擁護のコメントを出していたとは・・。火に油を注ぐようなものだろう・・。
<結局、マット・フューリーは幼き頃から愛してきた、ペペを自ら葬り、ペペのキャラクター像を悪用した「インフォウォーズ」や、”オルト・ライト”に勝利するのだが・・。
アンダーグラウンドに蔓延る、”模倣の負の連鎖”の実態に戦慄した作品。
香港では民主化運動のシンボルともなるラストに、少し救われた感があるが、あれも又”善意ある模倣である”と言う事を考えると・・。
この国も、”悪意ある模倣”が起こりえる国であり、決して対象外ではない・・。>
<2021年5月30日 刈谷日劇にて鑑賞>
コレも胸クソ
日本語でいうところのパンピね、とかね
ネットの怖さ
ペペという虚像。
「ペペ」漫画Boy´sClubに登場するカエルのキャラクター。作中で放った「feel´s good man」の一言がなぜかネット住民達から支持を集め瞬く間に拡散されてゆく。生みの親マット・フューリーの手を離れネットミームとしてひとり歩きを始めるペペ。最終的には一部の過激なドナルド・トランプ支援者達によってオルタナ右翼のヘイトシンボルに祭り上げられてしまう。マットは遂にペペ奪還作戦を開始。関わった人々の証言を元に構成されたドキュメンタリー映画です。
今なお分断を続ける大国アメリカ。その影に取り込まれたペペと巻き込まれたマット。しかしマット自身は家族と自由を愛する至って平和主義者。そもそもなぜペペだったのか。ネットの空想社会から現実社会への刺客として。なかなか闇が深い内容でした。ペペを通して見るアメリカの思想。もはや笑えない。
一方、自由と尊厳を懸けた闘いが続く香港。若者達の間でその光を担うキャラクターが誕生した。まさに光と影。ペペはこの先何処へ向かうのか。
ちなみに、私はペペには申し訳ないですが全生物の中でカエルが最も嫌いです。母曰くものすごい小さい頃からカエルを異常に怖がったそうです。きっと前世で何かあったんだろうと思ってます。
日本では起こり得ない
SNSの怖さを知れるが実感が持てない
インターネット・ミーム。
本作で初めて知りました。日本では同様のものは無い(目にした記憶がない)ですねぇ。
元キャラのパロディなどは見ますけど、それってミームとは違うのかなぁ?と。
仮にネットのどこかにあったとしても、キャラクターの作者が意図しない性格と考え方を持ち、ましてや政治的な使われ方をした・・・・なんてやっぱり聞いたことがないなぁ。
それはネットを利用する(ネット住民)の国民性によるものなのでしょうかね?政治への参加意欲の違いなのでしょうかね?
いずれにしても、匿名世界のきっと遊びから始まったであろうミームがいつの間にか、意思を持つシンボルになっていくという様は、現在のSNS全盛の今だからこその状況なのでしょう。
きっと、キャラクターを使って何かをしたい・・・なんていうのは、ほーーーんの一部の人なんでしょう
。しかし、キャラクターが思想を持ち発言するに至る間の変異は、途中介在している匿名の方々の
「誰かがやってたからやっていいんだ」
「面白いし、やっちゃおう!」
という軽い気持ちがそうしているのでしょう。でも仕方ないです。僕でもそうしちゃいます。
人気が出てくれば、そのキャラ使えば「いいね!」もらえそうだし。どんどん拡散も止まらないですよね。そして、力を持ったところで、ほーーーーーんの一部の意思ある者に利用される。
その意思が<善意>なのか<悪意>なのか?
コミュニケーションツールが便利で手軽になればなるほど、その「場」は参加しやすくなり、匿名であればそこに拍車がかかる。本作を見ると匿名が作る民意の恐ろしさが伝わります。無責任な一票。
それが民意と言えるのでしょうかね?しかし、出来上がってしまう事実があることは無視してはいけないですね。
ただ、まだ日本においては実感が持てないですね。同ケースが見当たらないので。しかし、匿名の意見の集合が民意になっていく・・・これはもう始まっていると思います。そう思います。
集まる意見の数で判断するのではなく、本質を見極める、情報を見極める。それが情報の受け手の義務なんだろうと、強く思うわけです。
あと、キャラクター作者は・・・こういう世界になっているということを知ってかないと・・・。
ま、結果論なんですけどね。
複雑な気持ち
人の善意と悪意を同時に見せつけられた本作。
掲示板やSNS(や同人誌)でのファンアートは黙認しても、政治的または差別的な利用については著作者は容認しちゃいけないし、早い段階で法的対処を取らないと取り返しがつかないという現実をつきつけられました。
多くのアーティストがそうであるように、作ることしか興味ない人が多いのは理解できるが……
ほったらかしにしていた時期が長く、自分のキャラクターが極右にトランプと一緒に描かれた絵が売られるようになってからやっと動いたって時点で、手遅れ感しかなかった。
と同時に、様々な例を見て知っている2021年に、無関係な他人事として観たからそう思うだけであって、当時に私がその立場だったら、まともに先手を打つ判断ができたとは思えないとも感じたり。
いろいろ複雑な気持ちになりました。
日本のネット事情も連想してしまう空恐ろしさ
差別主義者の象徴となってしまったカエルのキャラクター「ぺぺ」。ぺぺを作り出したマンガ家が辿った軌跡を伝えるドキュメンタリー映画。
ぺぺが色んな人に使われていくきっかけがネットの掲示板で、徐々に差別主義者たちに悪用されていく過程は初めて知った。日本の2ちゃんのようであり、「モナー」を連想してしまった。あれもネトウヨに悪用されたりしてたことを思い出す。
リア充への嫉妬・悪意、陰キャ・童貞・ニートたちの劣等感、「祭り」を待望する退屈感…、出演している「4チャンネラー」たちの言ってることも、日本の2ちゃん(今は5ちゃんか…)で語られていることにそっくりでビックリした。負の感情がヘイトにつながるってことを目の当たりにした感じだ。
ただ、希望がないわけではない。ぺぺが香港の若者たちの間で民主化を象徴するキャラクターになっているということは驚いた。ドキュメンタリー映画としては出来過ぎな結末だろう。
それにしても改めて思うのは、トランプが大統領になったことはアメリカだけでなく世界的にも重大な危機だったんじゃないかということ。SNSを含むネットの負の力が世の中を悪く変えてしまう恐ろしさを感じた映画だった。
書いてるうちほとんど関係ない話をし始めています。
.
.
元々ギャグ漫画のキャラとして作られた政治的意図の全くないカエルのぺぺが、ネットで拡散されたことで人種差別的なシンボルとして広まり、さらにはトランプ支持者のシンボルにまでなってしまうドキュメンタリー。
.
元々ネットでぺぺが広まってしまうきっかけに、インキャで社会から脱落したと自らを卑下している4chanという掲示板の住人達が、自分の劣等感をぺぺに投影したこと。
.
私はそもそも陰キャと陽キャという言葉が嫌いで、明らかにカースト上位の人はそんな言葉使わないし気にもしないのに、勝手に自分達で最初から自分たちは地味だから陽キャには相手にして貰えないとシャットアウトしてる感がすごい嫌だ。
.
結局他人に傷つけられたくないから、自分から最初に防衛してるだけなんだよなぁ。フィールズグッドマンが次第に政治を巻き込んでいったように、最初はアメリカで広がってる持つ物と持たざる者の分断の根っこはここなんだろうな。
.
それで、トランプの背中を後押ししたのがネットの力でそのどっちでもなかった陣営が面白そうだからそこに参戦していったこと。元々政治に興味なくてもトランプのような目を引く面白そうな人がいると、そっちを応援したいバカが沢山いるのはわかってるよ。
.
アメリカの問題に日本は関係ないって思ってる人でも、陰キャと陽キャなら馴染みが出てくるんじゃない?
.
こういう私は自分のこと何よりも1人で映画見てるのが好きだけど陰キャだなんて卑下したくないし、オシャレ写真をインスタに載せてキラキラアピールもしたくないです。
.
【続くバトル】
どこか寂しげで優しそうなペペの表情が、最初に引きこもりの人たちの共感を得たのだろうか。
通常、インターネットミームは、SNSや匿名掲示板のアカウントが、アレンジを繰り返したりしながら拡散していくのが特徴とされるが、ただ、仮に引きこもりとされる人たちでさえ、特定のミームで繋がっていることが判ったとたん、アニマルスピリットのマーケティングや、政治的喧伝の対象になることが明らかで、ここではペペが利用され、オルトライトと呼ばれる極右の悪意も取り込んで、予想もしない方向に進んでしまった。
独立したアーティストが権利を主張することの難しさなどもあるとは思うが、画像などの権利はまだしも、ミームのひとつとされる言い回し表現なんかの場合、管理はより困難というか、不可能に近いと思うので、効果云々というより、ネット世界の現状に暗澹たる気持ちになる。
ただ、これは、個別のインターネットミームの問題として考えるより、ネット社会のモラリティなどを、差別や誹謗中傷、権利侵害、虚偽の拡散などの観点から考えて、政治も含めて社会として、或いはまた、法規制として、どのように対処するのかを方向性を明示し、地道に啓蒙しないと、ダメだなと思う。
20年のアメリカ大統領選挙にも、ロシアが介入しようとしていたというニュースが飛び込んできたばかりで、国家単位で、不正を厭わない連中がいるのだから、個人では、極力、頭を駆使して、変な連中にジャックされないようにしないといけないと感じる。
昨年、夏ぐらいまで、日本のTwitterは、ネトウヨの差別的投稿や誹謗中傷を放置する傾向があったが、アメリカのTwitterが大統領選挙前にフェイクの書き込みなどに対する方針を大きく転換したことや、3月17日に略式起訴された黒川元検事の問題についての日本のTwitterデモもきっかけになって、ネトウヨの差別的投稿や誹謗中傷の書き込みの削除、アカウントの停止・凍結が多くなった。
実は、Twitterの中には「春のネトウヨBAN祭り(ヤマザキ春のパン祭りにかけたもの。季節に応じて夏でも秋でも冬でも構わない。BANは、英語の禁じるの意味)」という地道な活動があって、ネトウヨが好む特定のワードをTwitterのなかで検索して、そこでヒットした書き込みを読んで、差別や誹謗中傷であれば、Twitterにどんどん報告するのだが、これは実に効果的だ。
ネトウヨのなかには、自分達にも表現の自由があるのだから、こうした行為、ムーブメントは止めさせろとTwitterに抗議するのもいるらしいが、差別や誹謗中傷がそもそも禁止行為なのだから、ネトウヨがBAN(禁止)されるのは当たり前だと気が付かないところがバカなんだなと改めて感じる。
更に、BAN祭りをするアカウントを炙り出して、Twitterに報告する方法を編み出したという頓珍漢なネトウヨもいて、BAN祭りをしている側は、どんな禁止項目に該当するのか、項目をチェックして報告しているだけなのに、どんな方法を編み出して、報告する人を炙り出しているのか、本当に分からないので、つくづくネトウヨの頭の中は常人とは異なっているのだろうなと苦笑してしまう。
最近だと、芸能人が行ったアイヌへの差別表現問題について、ネトウヨから、「アイヌ民族などいない。いるのは日本人だけだ」みたいな差別発言を擁護するようなヘイト投稿があるらしい。
所詮、愛国とか言いながら、頭のクソ悪い自分が大好きなだけのクズな連中だ。
是非、時間のある人は、Twitterで、#春のネトウヨBAN祭り を検索して欲しい。
このプロみたいな方が複数いて、やり方も見せているケースもあるので、トライしていただければ、皆さんの報告もまた、蓄積して差別や誹謗中傷を減らすのに役立つ気がする。
昨日、3月17日、GoogleのAIが、3億件の違反広告を見つけて対応したとニュースでやっていたが、こうした地道な差別や誹謗中傷の報告を学習して、将来はTwitterのAIが、オートマティックに差別や誹謗中傷を削除することになるのだろうなと考えている。
行政や、極右もいるバカ政権が動かないのであれば、個人や社会が良識を示さないとダメなのだと思う。
対抗措置は絶対にある。
また、バカにつける薬はない。
4chan
独立アーティストの悲哀
一連の経緯を、時系列に沿ってスッキリ整理していて、分かりやすい作品だった。
単に事実を語るのではなく、「実写 & アニメ」の形式で「エモーショナルに真実を伝える、ユニークなスタイルのドキュメンタリー」を意図して制作したらしい。
アメリカ国内のディープな背景や、「オルト・ライト」の実態をよく知らない自分には、本作品の真偽や価値判断はできない。語られたまま受け取るのみである。
2ちゃんねる(「4 Chan」)と非リア充やニート、ネトウヨや極右などなど、「ふーん、アメリカもそうなんだ。現象面では日本と共通点も多いな」が、一番の感想だった。
終映後のマット・フューリーや監督を交えたトークで気づかされたのは、この問題の根底にあるのは、マットが独立アーティストということだ。
ミッキー・マウスその他、有名になるキャラは、大会社によって権利が管理されている。
ところが、この“カエル”は権利で守られておらず、マット自身も表現者の一人として、二次創作を制限したくないという気持ちが働いていたことが、“初動対応”を間違えた原因のようだ。
だが、「4 Chan」の“不幸で惨めなカエル”にとどまっているうちは、まだ良かったのだ。
マットも、どんな形であれ“カエル”が有名になることには、まんざらでもなかったかもしれない。
しかし、トークではさかんに「reinvent」という言葉が使われていたと記憶するが、この“カエル”は2005年頃からずっと存在していたのに、約10年経って急に“ヘイト”のシンボルに再考案されてしまったので、マットも使用の差し止めの訴訟を起こさざるを得なくなった。
「インターネット・ミーム」という存在については、自分は初めて知った。
同じ“カエル”が、アメリカでは極右のシンボルとなり、逆に、香港では民主化運動のシンボルともなる。その発展は、迅速で自在である。
今のところ日本には、この種の影響力をもつ“画像ミーム”は存在しないと思う。
しかし、“ゆるキャラ”が好きな日本人である。政治の世界にも、“画像ミーム”が登場するのは、時間の問題かもしれない。
国会答弁での「鬼滅の刃」使用について、作者はどう思っていたのか、知りたいところである。
バランス感覚としては至極まとも
マット・フューリーという漫画家が生み出したキャラクター「カエルのぺぺ」がインターネット上で様々な使われ方(ミーム)をする話で、マットがほったらかしにしている間にぺぺがトランプ支持者、過激な白人至上主義者のキャラクターとして使われるようになってしまった。ネットだけならまだしも、流石のマットも立ち上がる。
難しいのは、キャラクターには著作権がないということだ。マットが描いたぺぺのイラストや漫画は著作物だから当然著作権があるが、ぺぺというキャラクター自体は著作物ではないから著作権は生じない。商標登録をすれば、有効期限は権利を守ることができる。
ぺぺは香港の民主化運動の象徴としても使われているらしい。マットはそちらは特に反対しない。極右に使われるのは嫌だが民主化運動ならいいというのは、バランス感覚としては至極まともである。
アベシンゾウやガースーやヘイトのキャンペーンにドラえもんや鬼滅の刃が使われてしまうことを考えれば、キャラクターを守るための何らかの規範が必要だと思うが、知的財産権というアメリカ由来の考え方が種子にまで至って世界の農家を苦しめている現状を顧みれば、規範が諸刃の剣になりうることも含めて、難しい問題だと改めて思った。
全21件中、1~20件目を表示