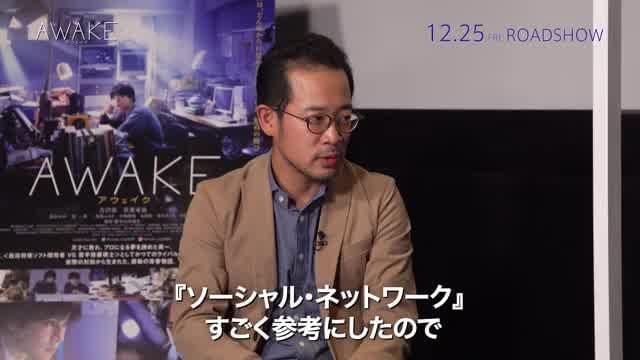「一風変わったものを扱うが良い内容。」AWAKE yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)
一風変わったものを扱うが良い内容。
今年3本目(合計70本目)。
私自体は将棋は時々ネットで指す程度(将棋ウォーズで4級=ある程度の戦法を理解して対局が成り立ち、簡単な詰め筋がわかる程度(要は楽しめる、という程度)。もちろん、アマチュアの級段とプロのそれとは当然違います)。
公開自体は去年の12/25のようですが、気になっていたことと「○回観ると1回無料」みたいな特典があったのでこちらを選びました。
内容は特集やレビューで触れられている通り、将棋。
ストーリーについてもそちらについて書いてあるものがほぼすべてです。
諸般の事情なのか一部の人名などは差し替えられていますが、大筋という点では史実と同じであり(とはいえ5年くらい前…)、その意味では「史実に基づくと言えうる」かと思います。
また、ここでストーリーの紹介をし始めると、将棋とは何ぞやとか奨励会が何かとかルールが何だのかんだので(制限文字数の)5000文字を埋め尽くすので省略します。
古くはこうしたゲーム(数学的には、2人零和有限(=有限の時間で決着がつく)確定(=乱数要素がない。すごろくは満たさない)完全情報(=すべての情報が場に示されている。麻雀はそれを満たさない)ゲーム、つまり「2人零和有限確定完全情報ゲーム」はコンピュータが発達する前から研究されていました。有名なところは、もうとっくにコンピュータにとって代わられたと言われるチェスやオセロ(リバーシ)、今回扱われている将棋などがあります。唯一、2020~2021年時点でまだ人間にかなわないと言われる囲碁(ただ、プロ中堅レベルでは負けてしまう模様)も、数年で破られるのではないか、と言われています。それほど人工知能に関する研究はここ数年で指数関数的に進んでいるのです。
※ なお、麻雀など「完全情報」を満たさないものでも、乱数要素を確率論で処理し、もっとも有利になる打ち方をすることで、数学的な定義は満たさないものの「そこらのプレイヤーでは手も足も出ない」ようなプログラムはもうあります。
今回はそうした特性を持つゲーム類の中から将棋が選ばれています。海外ならチェスが選ばれて映画化もおそらくされているんでしょうね(されているはず)。数年先には囲碁もその対象になるのでしょう。それだけコンピュータサイエンス(情報数学)の分野はどんどん研究が進んでおり、それが難病の薬の開発などにも応用されています。
すると、人間とコンピュータはあたかも対立関係にあるかのように見えますが、それは表面上のことであり、テーマが将棋(にせよ、囲碁にせよ何にせよ)に選ばれているだけであり、人間みんなの願いは「コンピュータサイエンスのさらなる発展」であることは間違いなく、その点の描写が薄かった点はちょっと残念でした。ただ、それ(人間とコンピュータサイエンスの対立)を描き出すと3時間4時間いってしまうのでやむを得ないでしょう。
評価は下記減点0.2ですが、特に大きな傷と思えないので5.0まで切り上げています。
-------------------------------------------------------------------------
(減点0.1) 物語序盤、主人公がコンピュータ将棋に興味を持って大学の部活動(人工知能を扱う部)に行くと、「そんなに入部したいならこれでも読んでろ」と渡されるのは一般的なコンピュータ言語の開発本(その内容や、のちのストーリーで描かれるプログラムの構文から、CかC++と思えます)。
ただ、そのあと1週間後に「読んだから正式に入れさせてくれ」というまでに本を読んでいる描写はあるものの実際にコンピュータに開発ソフト(Visual Studio=統合開発環境ソフトなど)を入れて勉強した描写がなく、下手をすると「コンピュータ言語は実際にコンピュータに向かわずとも本だけで学習できる」と誤解されかねず(特に、情報処理に興味のある少年の観客の子)、ここはまずかったかな…と思います。
※ 例えば、C言語などをすでに8割理解している方が親戚言語のJavaなどを学習するときはその軽減がありますが(かなりのレベルで類推が効く)、「知っている言語」(←当然、プログラム言語を指す)に「日本語」と書くような主人公が予備知識があると考えるのはどう考えても無理。
(減点0.1) 物語のポイントとなり、実話でもある「2八角戦法」については、実際にこれをプロ側が誘導してコンピュータを「ハメ」にいった件については、少なからずの論争があり、コンピュータサイエンスの側からは「公式戦でもないのにハメ手を使って勝負すらさせないのはフェアではない」という猛烈な抗議があがった一方、一般紙(朝日新聞など、将棋に特化しない、普通の新聞)では「どちらの立場も理解できる」としたものであり(もちろん、将棋雑誌などではこの点で色々な識者が意見を出し合い大論争になった)、その描写が「まったくなかった」のはちょっとフェアではなかったかな…とは思います。
ただ、この「2八角戦法」が何を意味するのかは、将棋をある程度かじっていれば「明らかにまずい」という点はわかるものの、「将棋映画」とはいえ、一応には不特定多数が見に来ることが想定されるのであり(もっとも、ポスターなどは将棋将棋って書いていたので、将棋映画であることは誰が見ても明らか)、そこは説明するとまた1時間コースになりかねず、仕方なかったのかな、と思います(登場人物を架空の人物などに入れ替えたとか何とかという点(名誉の問題)ではなく、単に時間がのびのびになる)。
-------------------------------------------------------------------------