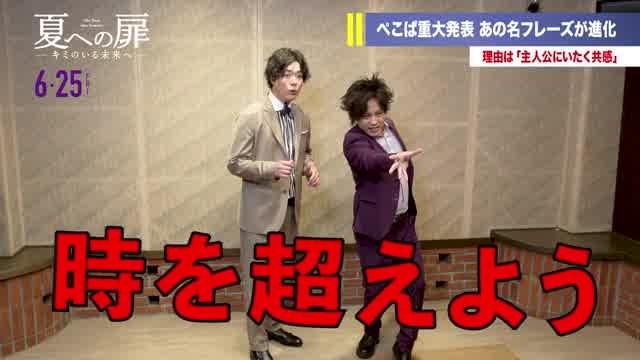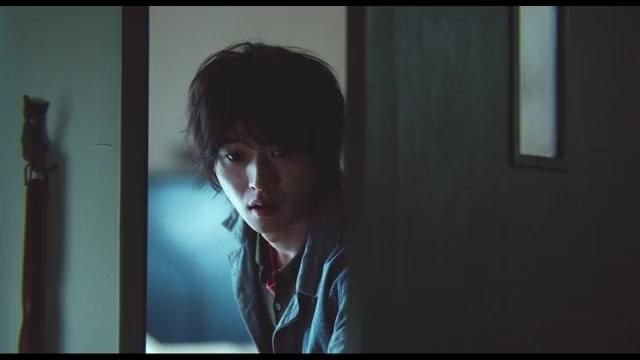夏への扉 キミのいる未来へのレビュー・感想・評価
全228件中、41~60件目を表示
素直に感動出来なかったです。
監督が昔から大好きな三木孝浩さんだったのでハズレはないだろと思いDVDで鑑賞しました。
映像が綺麗で、山崎賢人さんや清原果耶さん、藤木直人さんや猫など登場人物のキャラもとても良かったです!
しかし、ストーリーが初めから助かる未来で、その後はなぜその未来になったかの説明みたいになっていて個人的に納得できなかったです。『黒幕は俺だ』と言われた瞬間『はっ?』という心の声が漏れました。
話の展開が早すぎ
開発者である高倉。
あるすごい発明をしたが、会社に裏切られ、研究のすべてを奪われた。
そして、高倉は会社の人間によって冷凍にされ、眠らされた。
30年後に目を覚ました高倉は、その間に何があったのかを調べ、自分がするべきことを知りそれを実行したという内容だった。
話の展開が早すぎてなにか物足りない気がしました。
もう少し、黒幕が誰なのかとか話を引っ張って欲しかったです。
昔と現在の高倉が、協力するのかと思っていましたが、それがなく残念でした。
あと、会社の人間高倉からすべて奪ったのに活かしきれていないのだったら、あの話の展開必要あったのかと思いました。
コールドスリープのCMに小林涼子さん出ていて、良かったです。
及第点。なぜこの原作、日本で大人気なんだろう…
ハインラインの(特に日本で)人気SFの映画化だが、内容はプロットをもらって、日本を舞台にした「似たストーリー」を撮ってみたもの、と思った方がいいです。そのきわだつ部分は、原作では構想にとどまっている「護民官ペトロニウス(ピート)」が本作では完成し主人公とともに活躍するとなっている点。その設定は自分も楽しく観られたので、成功しているのではないでしょうか。
自分の中では及第点って感じでした。山崎さん、清原さん、藤木さん、みな頑張っていたし。そうなんだけど、なんだかなあ・・・
映画化にあたり、何度もトライしなぜか読み終えることができなかった原作を始めて完読した。日本で大人気だった理由を、WikiPediaは「そのロマンティックなストーリーが日本のSFファンに愛され」としているが、自分は、「科学技術は素晴らしい未来を切り開く」という原作の根底に流れる思いが、刊行された1958年当時の日本人にジャストミートしたのではないかと思う。かつ、主人公ダンは、科学者ではなく技術者だということもミートしたのではないだろうか。新しい理論を完璧に理解しなくても、それを使いこなしていく技術者という主人公像は、これから高度成長期を迎える日本のすでに技術者になっていた人、そしてこれから技術者になろうとしている多くの若者たちに、大きな夢を見せてくれたんだと思う。
原作は楽しく読んだのだが(とうとう完読できたのだが)そっちで満足してしまったせいか、自分にとって、本作はなんだか淡々とした映画だった。なにが足りないのか、よくわからないが、なんだかエンタテインメント性に欠け、訴えてくることもなかった映画だった。
<おまけ・原作を読んでの感想の続き>
原作に描かれる 「オートマチックセクレタリー」 は、主人公が人口冬眠から覚めた30年後でもまだ実現していない。 「音声文字認識」である。 GoogleやAppleのSiriがかなりのレベルでそれを行なっている日常を過ごす俺たちには、この実現が非常に困難と描かれている本作は、意外に映るかも知れない。
しかし、作者が本作を書いた1956年は、コンピューターは既にあったとは言え、まだまだ基礎的機能の拡充段階、インターネットもその始点となるARPAネットの誕生1969年を十数年後に待つ時期だった。それを考えると、それを用いた並列処理と機械学習の仕組みによって、たった60年後にこれほど精度の高い言語認識ができるようになると予測することは、SF作家であっても難しかったということだ。これは、ここ30年でのコンピュータとインターネットの発展がいかに急速なものだったかを示す例だと感じる。現代で言う3D CADにあたる 「製図機ダン」は、原作の30年後の世界ではちゃんと出来上がっている点をみても、機械学習の発見がいかにエポックメーキングな出来事なのか、改めて痛感させられる。
わかりやすいSF
口答えする機械
原作未読
率直にいうと面白みに欠ける。
ストーリー自体はよくまとまってるし、何か大きな破綻や変なところがあるわけではない。
あえて言うなら“整いすぎている”そう思った。
全てのパーツがひとつも逃すことなく埋まっているからこそ物語として盛り上がるところがどこかがわかりにくい。
あと、未来に行くまでの話が長い。
いや、全体を通してみるとあれだけの分量をかけて現代パートをしっかりと描く必要があることはわかる。
しかし、CMでタイムスリップするSF物という知識が入ってしまっているがために「いつ主人公が未来に行くのか」とヤキモキしてしまった。
そういう意味ではこの作品はあまりSFというところを打ち出さずに宣伝するべきだったのかもしれない。(もちろん原作が世界的なベストセラーなのでなかなか難しいことではあると思うが。)
特筆すべきはSFに関する演出と美術。
最初に3億円事件などの史実に混ぜて時間転移装置というフィクションを紹介するので、ロボットの発展具合等々のSFが現実と見事にフィットしていて全く違和感を感じなかった。
さらに、未来の世界の美術も極端にSFにせず、白を基調とした美術によって、ほんのりとSF要素を足しているのが良い。
なんなら作中に登場した自動運転タクシーなんかは本当に4年後には登場していそう。
加えて、藤木直人さんの怪演。
ヒューマロイドという人間とロボットの中間という役柄を動きで気持ち悪くなりすぎず表現していてリアルなSF世界の構築に一役買っていた。
他にもアンドロイドのエキストラの方の動きもレベルが高かった。
タイトルなし(ネタバレ)
面白かった。
原作を積読していたので、映画でストーリーを知っちゃったからもう読まないかな^^;
作中で時間の転移について「並行世界なんてない」「ループしている」と言っていたけど、結末を見るとやっぱり並行世界なんじゃないの?って感じがする。
凡人だからループ理論が理解できない。
1995年の世界のロボット技術やコールドスリープの技術が現実よりだいぶ進んでいるのに、その他の技術(テレビや携帯電話等)の技術は現実通りなのがアンバランスで奇妙に感じた。
どうしても気に入らなかったのが、ヒューマロイドやたらと人間ぽい質感なこと。
実際に実現したとして、家族や人間関係を構築する目的ではない,純粋なお手伝いロボットをあんなに中年らしい肌質にはしない気がする。
『A.I.』のジゴロ・ジョーみたいな皺や毛穴がない肌質の方がロボットっぽいし、製造しやすそう。
そゆことか!
ストーリーのメインが分かりにくい
この映画のジャンルは、恋愛映画なんでしょうか?SFなのでしょうか?
恋愛映画と言うほど、熱い恋愛は無いですし、やはりSFなんでしょうね?
ただ、メインとなるタイムマシン的なものは、主人公が開発したものでもなく、なんとなく中心が、ぶれてる感じがしました。
役者に助けられてる感じはあります。
ロボットと人間が仲良く共存している、『Detroit: Become Human』が理想としたような世界を舞台にした一作。
1956年に発表されたハインラインの名作小説を原作としているためか、作中のSF要素は、『テネット』などと比較して極めてシンプル、というか素朴です。これはもちろんハインラインの設定に問題がある、という意味ではなく、執筆当時の、少年少女達が科学の未来に無限の可能性を抱いていた時代ゆえの、未来に対する信頼感、肯定感が作品を裏打ちしている、ということです。
原作は1970年代から2000年代を舞台にしているため、現時点では既に過去となった時間軸となっていました。そこで本作では1995年から2025年という、微妙に過去の世界から微妙に未来の世界に時代設定を移行させています。この映画ならではの設定はなかなか絶妙で、インターネット黎明期からスマホ全盛期移り変わる中で、どのように世界が変わっていったのかを、そのギャップをスマホやキャッシュレスに驚く山崎賢人、という実に見事な方法で見せています。タイム・パラドックスについて何の言及もなかったり、主人公の周辺がいい人ばかり(あるいは分かりやすい悪人)だったりする点は気にならなくもないけど、その分置いてけぼり感を持つことなく、安心して鑑賞できます。既存のSF作品におけるコンパニオン・ロボットは、従来女性型が多かったけど、今回は藤木直人演じる中年男性ロボットが主人公と行動を共にします。『ターミネーター2』(1991)のA・シュワルツェネッガーとE・ファーロングのような関係性ですが、藤木直人は持久走が得意なことを除いてはそれほど超人的な能力を持っていない、というか結構感情の赴くままに行動しており、作中で最も次の行動が予測できない、面白い役どころでした。
一方女性役については未消化な部分が目立ち、夏菜演じる白石鈴の末路の描き方はあれでいいのか、とか、清原果耶演じる松下璃子の重大な決意について、あんなにあっさり済ましてよいのか、など、ちょっと「軽いタッチ」で済ませるにはひっかかりが大きい部分が目立ちました。脚本の段階で枝葉の部分を落としすぎたのかな?と勘ぐってしまいました。
本作の製作に当たっては、プロデューサーの小川真司氏が特に力を入れていたようで、インタビュー記事も読むといろいろと発見があっておもしろいです。
ストーリー改変で
以前に原作を読んで、面白かった小説と記憶に残っている。が、この映画は全然ダメ。ストーリーの改変でグダグダ。小説ではちょい役だった女の子との絡みがほぼメインイベント。また、独自に作られたあのキャラ、あのアンドロイドみたいなロボットは、何の必要性があってあれほど存在感が有るんだ?で、一緒に過去に戻る必要あるの?あと、幼いときに主人公に憧れていた少年がライバル会社社長になって・・・というのは話を難しく登場人物を無駄に増やしている。原作のヌーディストクラブでの出会いが日本ではありえないのはわかるが、もっと登場人物をスッキリさせて欲しい。小説読んでなくて、この映画を初めて観た人はごちゃごちゃしたストーリーおよび登場人物がよく追えると思う。
好きな俳優・女優でも出てれば、印象も違ったのだろうけど、好きな小説だったという理由で観た者にとっては苦痛。SF小説が二人の恋愛映画になってしまっている。
爽やかでライトなSF
うまくまとめられている佳作
この映画は大きく言うと2つの優れたアイデアプロットでできている。
まず第一のアイデアは、未来へはコールドスリープで、過去へはタイムマシンで行くというもので、これによって主人公は1995年-2025年-1995年-2025年と時間移動する。
第2のアイデアは物語が複雑化することを避ける工夫である。
物語は過去(1995年)と未来(2025年)にまたがっている。この映画での1995年は現実世界の1995年とは異なりコールドスリープ技術が確立されている。企みによってコールドスリープさせられ、2025年に目覚めた主人公は、状況に導かれるようにタイムマシンで過去(1995年)に戻るが、過去で自分を直接的に助けたりはしない。自分が行く未来への種をまくだけ。未来での活動を4日間、過去に戻っている期間も10日間と最小限にとどめることでタイムリープものによく起きる因果関係の複雑さを巧みに避けている。10日間でやるべきことを終えた主人公はコールドスリープで2025年に再び行きつく。1995年時点では宗一郎は二人いて、どちらもコールドスリープするというのがミソ。
1995年での協力者・佐藤に対する描写は不足していると思う。未来からもたらした情報、たとえば奥さんの病気が治せるようになるとか、ピートによる説明部分とか、もう少し丁寧であってほしい。単に善人だからという理由で宗一郎を助けてくれるのはちょっと納得感に欠けると思う。
1956年に書かれたという原作ではどうなっているのか、読んでみたいと思った。
全228件中、41~60件目を表示