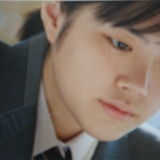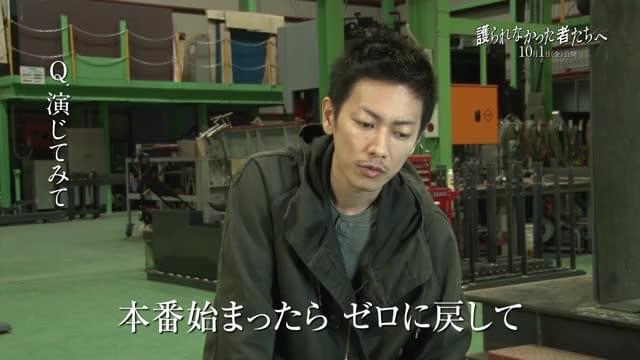護られなかった者たちへのレビュー・感想・評価
全354件中、1~20件目を表示
公助が崩壊した社会
こうした正邪を割り切れない骨太な人間ドラマをヒットに導けるのは、日本では瀬々敬久監督だけになっている。震災で多くの生命が失われ、残された者たちは懸命に生きる。しかし、震災で生き残れても貧困が襲いかかる。本作は生活保護を題材に、社会の理不尽を描く。だれもが精一杯生きている。精一杯生きているから追い詰められて、最後には疲れてしまう。なぜ役所の人間は、生活保護が必要な人をぞんざいに扱うのか。彼らも終わりの見えない業務に疲れ果てている。そのツケがどんどん弱い人のところに溜まっていき、悲劇が見えないところで起こっている。
自助・共助・公助という言葉がコロナ禍で使われたが、自助だけでは生きていけず、震災のような未曾有の災害が起きれば皆が苦しいのだから、余裕を持って共助できる人は限られる。そういう人間を救うのが公助の役割なのだが、法律改正によって公助で救われる人が少なくなってしまった。そのことへの怒りがこの映画にはある。
役所の人間が、生活保護法の改正の件について長台詞で「説明」する。あれは完全に説明ゼリフだ。巧者の瀬々監督も脚本の林さんも、あれが映画全体の中で浮いてしまうことはわかっていたはずだ。それでも、はっきり言わねばならないことだったのだ。
生活保護×3・11のテーマ性がある社会派ミステリー作品。刑事モノのミステリー映画を楽しみつつ大切な仕組みの知識も得られる!
本作は宮城県が舞台で、東日本大震災において最大の犠牲者を出した「津波」で被害を受けた人たちにまつわる話がメインです。
そして、私たちが知っておくべき「生活保護」という大切な仕組みが大きなテーマにもなっているので、是非とも社会問題の1つとして考えてみてほしい作品となっています。
本作は少し独特な作りとなっていて、大きく「2011年」と「2020年」の2つの時間軸が行き来するのです。
最初は「2011年」から始まりますが、その後で「9年後」という親切な表示が出ます。ただ、それ以降の表示はなく、いつの間にか「2011年」に戻っていたり、「2020年」になっていたりします。
さらには、「2011年」と「2020年」と“その間の期間”もあるため、「今はこの3つのどこか」と時間軸を見分ける集中力も大事になるのです。
それが出来れば、あとは生活保護に関する大事な解説や事例が分かりやすく出てくるので、それを知って観察してみると、「制度の理不尽さ」や、職員の対応がどうなのか、など普段あまり目にしないものが自然と見えてきます。
ただ、現実に役所は人が足りないことも事実ですし、今回のケースでは、大災害によって仕事量も半端ではなく、全ての人に寄り添って対応をするのには無理もあります。
「生活保護」という仕組み1つをとっても、これだけ多くの考えるべき材料があることが分かる、とても大切な映画。
もちろん佐藤健、阿部寛、清原果耶を筆頭に役者陣は非常に上手く、その演技の応酬も見どころの1つである良質な作品です。
豪華キャストの入魂の演技とアンサンブル。生活保護の問題に迫る姿勢も貴重
容疑者・利根役の佐藤健は、前に瀬々敬久監督と組んだ「8年越しの花嫁 奇跡の実話」の主人公や、朝ドラ「半分、青い。」の律役など、善良で優しい青年を演じさせても十分、上手い。だが、役者としての凄みを感じさせるのはやはり、怒りや恨みといった負の感情をふつふつとわき立たせて爆発させる本作のようなキャラクターだろう。衝動的な言動の場面での深い闇を感じさせる眼は、アドレナリンが過剰に分泌されているのではないかとさえ思わせる迫真度だ。
利根を追う刑事役の阿部寛はもちろん、連続殺人事件の被害者に永山瑛太と緒形直人、第3の標的に吉岡秀隆と、比較的出番の少ない役にも主役級の演技派を贅沢に配し、彼らのアンサンブルも味わい深い。大物から旬のスターまで、瀬々監督からオファーがあれば他の仕事を断ってでも参加したいという俳優が大勢いることをうかがわせる。
一連の事件の重要な背景として描かれるのが、東日本大震災で被災して家族を失ったり生活困窮者になったりした人々の体験と、時折報道でも取り上げられる生活保護をめぐるさまざまな問題だ。俳優たちの熱演に加え、日本で生きる私たちに直接突き刺さるような鋭い社会派のスタンスがあるからこそ、本作の鑑賞が“体験”として心に深く刻まれるのだろう。
殺人の裏側に隠された衝撃的な現実に涙する良作
東日本大震災と生活保護という一見シンプルな題材から、殺人犯が現れるという意外な作品。
登場人物の大半が心に深い傷を抱え、仕事をしながら必死に生きていこうという姿が伝わってくるうえに、基本的に温かみを感じるシーンが多い。
しかし、殺人が起こってしまう。
餓死という形は、何かの暗示なのか。
殺人犯が残酷な行動に至るまでの大きな道のりが本編にはヒューマンドラマという形になって隠れている。その原因は、序盤から丁寧に描かれているため、もう一度見返してみたくなる映画。
佐藤健(容疑者)と阿部寛(刑事)の演技は言うまでもなく、豪華なキャストが演じる役柄も重厚で、発する言葉や表情を一瞬でも見逃すことはできないほど奥深い。
まずは、エンターテイメントとして1回目を見て楽しみ、可能なら、2回目で社会をより深く考えるというレベルの濃密な内容。
「守る」ではなく「護る」になっているという理由のヒントが本作には詰まっている。
人間の尊厳
もしかしたら3回目の視聴かもしれない。
しかし、当時はボーと見ていたので、詳細な内容についてまで考えていなかった。
ここ数日このタイトルが目に留まったことで、もう一度見てみようと思った。
このタイトルは狭義の範囲内で多義的要素を持っている。
震災で亡くなった方々にたいするもの 守れなかった家族に対するもの 守るべき国民がいるにもかかわらず守ろうとしない人々に対することなどが含まれている。
さて、
この物語は震災をモチーフに、貧困層の救済のハードルを大きく上げている「生活保護制度」とそこで働く人々 そして貧困で亡くなったケイさんという登場人物に焦点を当てながら、「心の傷の深さ」を描いている。
そして、物語は「殺人事件」という動きで紡がれていく。
この殺人事件の動機こそ、震災で誰かを失った深い心の傷を、復讐という形で表現している。
幹子のセリフにもあるが、「震災とは怪物で、立ち向かうことなどできない」
どうしても抗えないことに対し、ケイさんが死んだのは「人間の所為」として、そのはけ口を生活保護制度を管理する者たちに向けた。
このごく一般的な視点と深い心の傷によって、幹子はどうしても許せない3人を襲った。
この物語はミステリーとしてもよく出来ていた。
犯人の目的は明確にもかかわらず、そこにどんでん返しを仕掛けている。
また、事件を追う笘篠刑事の心の傷を描くことによって、同じ境遇の人々それぞれの矛先が違うのも考えさせられた。
そこには立場の違いがあったが、同じ痛みを共有していることで、わかり合おうとする「繋がり」を感じることができた。
震災という名の怪物によって傷ついた人々
身寄りのなくなった3人が、家族のように生活を始めたこと
ケイさんの過去の心の傷 娘の存在と決して自分の存在を知られたくないことが、生活保護申請を取り下げた。
その事はお金の問題でしかなかったが、ケイさんは失ってしまった家族が震災によって復活したかのような幸せを手にできた。
他の誰かの養子となった幹子は、震災で死んだ母よりもケイさんを母だと思っていた。
仕事を求めて宇都宮に行った利根ヤスヒサ
彼の状態は震災直後からどこか他の人とは違っていた。
そこに貼られた伏線
回収まで少々長く、それそのものがミスリードとなっていた。
「全員を救うことはできない」
これは本当のことだろう。
しかし、幹子が市役所に入って「救い」と「復讐」を兼ねたようなことを決意していたのは、かなり驚きだった。
ケイさんを連れて申請に行き、ケイさんが餓死して担当者に詰め寄るヤスヒサ
担当者の冷酷な言葉を聞きながら、高校生の幹子は「決心」したのだろうか。
連続殺人事件が報道されたことで、ヤスヒサは犯人は幹子ではないかと疑った。
だから育った家に行って住所が書かれた郵便物を拝借し、彼女のことを調べた。
ただしこのことは詳細には語られない。
同時にミスリードという設定を殺すわけにはいかない。
このあたりが、この作品の難しさと是非だった。
そして着地点を、笘篠刑事の息子の最期に沿えていた。
これこそ笘篠刑事がずっと探していたことだった。
それに応えるように息子の形見の時計のアラームが鳴る。
「はいよ」
そのアラームに答える笘篠
そこには息子の最期を見届けてくれた感謝と、息子はもう空にいるんだとあきらめに似た納得があった。
深い心の傷に向き合うことはいったいどんなことなのか?
この作品は、やり場のない憤りを描きながら、それを共有していたわりあう作品だった。
2回目鑑賞
何故最後にありがとうと
社会性あるテーマとミステリー
血のつながり以上のもの
未曾有の災害の裏で、同じようにそれぞれの苦しみをかかえた人々が存在するのだろうと思った。血のつながりは関係ない、それ以上のつながりも存在し、それを糧に生きている人もいて、その絆は相当のものだと。
佐藤健の演技がすごかった。迫力が画面越しに伝わってきた。
皆傷を負っている
本当は★5。震災ネタと言う事で客観性を保つ意味で-0.5を理解して欲しい。
再確認を。
様々な問題に正面から堂々と切り込んだ作品です
護られなかった者、護りたかった者。
観て良かったです
う〜ん
サスペンスと思いきや生活保護について考えさせられる作品
震災と生活保護を題材とした殺人サスペンス
殺人に関してはリアリティがないけれど、生活保護を申請する側、受理する側、どちらも震災で疲弊していた状況は当時現実にあっただろうし、今現在も未来にも起こり得るのだろうと考えながら鑑賞した。
生活保護の不正受給や扶養照会を恐れての辞退など、現実的で根深い問題も扱っているため考えさせられる。
作中では生活支援課の職員が悪役的に描かれているが、一方では被災した墓地の片付けをしていたり、餓死を招いてしまったことを後悔していたり、そう単純ではない。誰しもが護られなかった者、あるいは護れなかった者として、天災および人災の被災者として描かれている。
護られなかった存在として描かれるおばあちゃんだが、震災孤児となった主人公達を護り、生活保護を辞退することで生き別れた娘を護ろうとした事もどこか皮肉的だ。
全てを救うことはできないと悟りつつも、せめて、助けるために声を上げて欲しい、助けてもらうために声を上げて欲しい、この辺りが作品として伝えたいメッセージなのだろう。
全354件中、1~20件目を表示