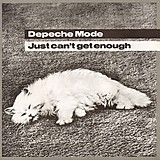ファースト・カウのレビュー・感想・評価
全118件中、1~20件目を表示
絆を掘り起こすために
ケリー・ライカート監督作品。
2021年に特集が組まれて4作品とも凄い作品だったから、本作もみれてよかった。風景とロードは『ウェンディ&ルーシー』『リバー・オブ・グラス』だし、西部劇の捉え直しは『ミークス・カットオフ』、男同士の絆は『オールド・ジョイ』と通底するものがある。他にもバディ・ムービーとしてみればなどいくらでも他作品との共通する部分は指摘できる。けれどルックをみれば瞬時に分かる。これはライカートの画だと。それにもカメラワークや演出などと言うことができるが、もう言語化に留まらない作家性の発露なのだ。
本作は二人の男・クッキーとルーの絆の物語である。
森でキノコを採取して開拓に従事していたクッキーが、裸一貫のルーに出会う。クッキーは集団で蔑まれいじめられていたから、ルーを助けることで絆が生まれる。そして二人は意気投合して「ビジネス」を始める。それはクッキーの料理人の腕とルーのビジネス感を合わせて、ドーナツを販売することだ。しかし美味しいドーナツのためにはミルクが必要で、そのミルクは商人の所有物で“富の象徴”の牛から盗まなければいけなかった。
まずキノコからドーナツへの移行の描写が素晴らしい。
「キノコを採取すること」は、人間と自然の相互循環システムを端的に語っている。人間は空腹をしのぐために必要な分だけキノコを採取する。キノコは採取され、間引かれることで移動し、繁殖する。過度にされれば乱獲による絶滅や大量繁殖で生態系の変容につながる危うさはあるが、本作では循環したエコシステムとして描写される。
「ドーナツでビジネスをすること」も似ている部分はある。ドーナツは人間が食べるためにあるし、自然の食材が必要だ。しかしドーナツは木になっていない。人間の手によって、「お菓子」として生み出されなければいけないのだ。そしてビジネスにするためには、お腹を満たす以上に利益を獲得しなければならないから大量生産が必要になる。それにより素朴なエコシステムからはみでる人間の自然への介入がされることになる。しかも必要なミルクは森にいっても採取はできないから、さらなる介入としての「犯罪」が行われる。
このようにキノコからドーナツへの移行は人間と自然の相互システムのあり方と介入による変容を鮮やかに描いている。そしてもはや人間と自然は二項対立的に語ることは不能で有機的なつながりがされていることもラディカルに描かれているのだ。
そして「ドーナツでビジネスをする」といった原初的なビジネスのあり方は、西部劇における「未開の地」の「男の冒険」による開拓とリフレインされ、ラディカルに捉え返しされることになる。
そのひとつがルーの表象である。ルーは中華系の移民であるのだが、この存在は端的な事実を語っている。すなわち「西部劇は白人男性だけのものではない」ということである。ジョン・フォードの『駅馬車』を引用するまでもなく、古典的なハリウッドの西部劇では、白人男性を主人公にして、同じく仲間の白人男性とインディアンなどの「未開の者」または敵対者と闘うことで絆や女性との恋愛をすることが定型であった。この語りはアメリカの「フロンティア精神」を体現しているのだが、やはり極めてホモ・ソーシャルでナショナルな語りであるからジェンダーやコロニアルの観点から批判的に捉えるべきであろう。そしてその視座があるからライカートは現代において西部劇を展開し、『ミークス・カットオフ』では女性の物語を、本作では移民の物語が語られているのではないだろうか。
さらにルーという存在が現前されることで、クッキーとルーは「移民」として等値に置かれる。その時、クッキーに表象される「白人男性」は、アメリカに不動に存在し、屈強に冒険をする人間ではなく、生きるために移動せざるを得ない脆弱で異質な他者性を帯びた「移民」として捉え返しが可能なのである。
それでは二人の絆はなぜ破綻するのだろう。クッキーは闘争ではなく逃走で、全くもって非ドラマな崖からの転落で頭を怪我する弱々しい存在に終始する。二人の結末は、二人並んだ骨が物語っている。西部劇をラディカルに捉え返したのに、ハッピーエンドに終わらないことはなぜなのか。
「ドーナツでビジネスをすること」はもうひとつのテーマとリフレイン可能である。それは「資本主義経済」である。この経済様式では生産のために資本が必要になる。資本はドーナツでいうところの食材である。では資本≒食材はどのように集めるか。ドーナツを売り始めたら、その利益で食材を買えばいいのだが、原初にはそうはいかない。だからキノコと同様に自然からの採取を行われなければならない。そしてミルクと同様に犯罪による収奪がされなければならない。実はこの「収奪」は資本主義経済を語る上で労働力の「搾取」と同様に資本の本源的蓄積のためにされてきたことだ。そしてこの収奪と搾取はジェンダーやコロニアルの観点からも発見された構造だ。つまり収奪と搾取を根本的に抱える資本主義経済では、絆は死に向かわざるを得ないことを言っているのではないか。私にはそう思えるのである。そして現代もまた資本主義経済である。そうであれば本作は西部劇でありながら極めて現代的なテーマを語っているし、現在において絆を幸福に帰結させる困難さを描いているとも言えよう。
私たちにはハッピーエンドがない…?そうではない。本作はそれでも希望を描いているし、絆の物語なのだ。
私が本作で一番いいと思ったショットは、二人がミルクを収奪したのがバレて、商人の警備員がベッドから身支度をして外にでるショットである。警備員がもたもたしている。寝間着からズボンにわざわざ履き替えて、その間に二段ベッドにいる仲間に先を越される。二人を捕まえる最もスリリングな場面なのに、このショットをみて笑ってしまった。けれど、これがライカートの映画なんだと思ってしまった。精巧で緊張感のあるショットに突如現れる弛緩の時間。この時間にこそ親密さが充満し、絆が紡がれ育まれているのではないだろうか。そしてそれを撮るのがライカートなのだ。
絆は「掘り起こされる」。掘り起こす主体が犬と女性であるのが、まさしく作家性の表出ではあるが、私たちは本作をみて、かつて、そしてあり得べき絆を掘り起こすことが求められているのである。
2人の絆の痕跡が現代まで残る
気負いとか気取りのようなものが全然ない映画だなと思った。そして、それがとても尊い美徳になっている。
西武開拓時代、とある街に流れ着いた2人の男、仲間に置いてけぼりにされた料理人のクッキーと中国人移民のキングルーは、街にたった一頭しかいない牛のミルクを夜な夜な絞り、甘いドーナツで稼ごうと画策する。一攫千金を夢見る西部開拓時代で、随分地味な計画を立てるものだ。2人の地味めな男がせっせと牛の乳をしぼり、せっせとドーナツを作って売りさばく。しかし、それが結構繁盛していまい、牛の所有者の名士にも気に入られるが、ミルク泥棒がバレるんじゃないかと気が気でない。
そして、やがて2人の行為がバレてしまい、逃避行が始まる。しかし、2人の男の絆は死んでもきれないのだ。ここを映像で描くショットがとてもさりげなくも美しい。二人の友情の痕跡が。
冒頭とラストがリンクするのだが、そこには人間は滅んでも豊かな大自然が残っていることを示唆している。牛と森と川、そこに映される自然の姿はシンプルに美しくて、自然に生きる人々の豊かな生き方というものがてらいなく映されているのがいい。この時代、おしつけがましくならないことは貴重なことだが、この映画はそれができている。
この運命的な川辺でしみじみと沁み渡っていく感情
好みが分かれる作品だろうとは思う。せかせかした日常を送る我々にとってまず必要なのは、ケリー・ライカート監督が描く開拓時代の気が遠くなるほどスローなペースにどっぷり身を浸すこと。時計など気にせず、この永遠に続くかのような会話速度に身を預け、森の静寂と暗闇をこよなく愛し、そこで育まれる彼らの関係性を幾ばくか微笑ましく感じ始めたなら、その頃合いからようやく、我々はこの世界の住人なのだ。川面をゆっくりタンカーが過ぎていく。その200年前、当地で初めての雌牛がいかだでゆっくりと運ばれていく。そのミルクを用いて男たちがスコーン作りで大成功を収める・・・一連の顛末は「わらしべ長者」さながら。と同時に、冒頭の「結末」に向けひたすら流れ、導かれていくこの寓話は、恐らく開拓地オレゴン史上初の友情物語。骨格標本に肉付けしていくかのように丹念に織りなされるストーリーが美しく、唯一無二で、しみじみと沁み渡っていく。
映画の冒頭とラストが見事にリンク
西部開拓時代のアメリカ、オレゴン州には、アメリカ人だけではなく、様々な国籍の人々が一攫千金を夢見て集まってくる。そこで行われるのは物々交換によって限られた富を奪い合うという原始的な手法だ。
物語は、乳牛の乳と小麦粉を練って油で揚げ、砂糖をまぶしてドーナツを作って荒んだ男たちの舌と心を潤そうとする料理人のクッキーと中国人移民のキング・ルーにフォーカスする。だが、そもそも2人のビジネスは犯罪の上に成立したものだった。
西部開拓時代の物々交換という斬新な視点、ドーナツの真相がいつバレるかとハラハラさせる展開、見どころはいくつかあるが、アメリカンドリームのかけらもないオレゴンの森で知り合い、意気投合したクッキーとキング・ルーが育む友情の意外な重みが、最高に心を打つ。しかも、それを表現するために映画の冒頭とラストを見事にリンクさせた手法が、この映画を忘れられない1本にしている。
なぜか日本では紹介される機会が少なかったアメリカ・インデペンデント界のトップランナー、ケリー・ライカートの最高傑作と呼ばれる本作。願わくば、賞レースを賑わせた昨年度から間を置かず公開して欲しかった。
ファースト・カウ
時代も距離も隔てて彼らとの繋がりを感じる
それまで名前も知らなかったのに、2021年の特集上映で過去作をまとめて観て一遍にお気に入りになってしまったケリー・ライカート監督の最新作です。もう、これは楽しみでなりません。
監督の『ミークス・カットオフ』(2010) 同様にアメリカの西部開拓時代のお話です。オレゴン州の山奥ではまだ貧しい暮らしを強いられていた頃、村で唯一匹の乳牛のミルクを夜中にこっそり搾り取ってドーナツ商売で一山当てようとする流れ者の男二人のお話です。
いやぁ、この映画には参ったなぁ。これまでのライカート作品は、不要な説明や台詞を抑えながらも物語の奥に深い主張を忍ばせている様に感じさせたのですが、本作ではそんな明らかな主張は影を潜め、ただ淡々とお話が語られるだけなのです。でも、それに見入ってしまい目が離せません。腰くらいのやや低めの位置から中距離レンズの固定カメラで映し出される二人の暮らしぶりに癒されたり、ハラハラさせられたり、思わず目を瞑ったり、自然に魅入られたり。それでもやっぱりお話は静かに進みます。
そしてラストシーン。えっ?ここで終わるの?と思わされながらも、それがオープニングシーンに見事に繋がって行く事に気付くと「うわぁ~! やられたぁ~」とゾクゾクしてしまいました。今の僕からは遥か遠くの土地、遥か昔の物語でありながら、こんな男達は確かに居たんだろうなぁと感じさせられ、彼らの踏みしめていた土地から今僕が居る場所と時代まで地続きで繋がっている様に感じられたのでした。 (2024/1/2 鑑賞)
1820年代のオレゴン・・・夜の闇が本当に深く暗い
本物に拘ったのかどうか分かりませんが、
夜の描写は真っ暗闇で、殆ど何も見えないのでした。
配信が故障なのかと目を凝らすと、暗闇で動く動作が微かに見える。
画面のサイズは正方形に近い長四角です。
音楽がとても独特でした。
古楽器なのかギターともバンジョーとも判別のつかない音で、
単調なフレーズを何回も繰り返す。
ピアノなのかチェンバロなのか?のメロディも聞こえます。
アナログの極みみたいで、妙に味わい深い映画でした。
西部開拓期のアメリカのオレゴン州。
コロンビア川の流域。
一攫千金を夢見たのか?
土地に居づらくなったのか?
2人の男がいます。中国人のキング・ルーと
料理人だったと言うクッキー。
お腹を空かした2人は、ある事を思いつきます。
たった一頭、タンカーに乗って川を登って送られてきた雌牛。
その牛乳を無断で絞って、
粉と塩と重曹に絞った牛乳と混ぜて
「ドーナッツ」を作ること。
商売を始めるのですが、売るのはたったの8個。
なんか小汚い塊です。
味見した客はその美味しさに、かなりの衝撃を受けた様子。
そのうちにクッキーが路上で油の鍋に液状の種を流し込む。
えーい!!
本当にドーナッツです!!
私が自宅で昔作ったみたいに、タネから四方にヒゲのように広がって、、
なんか、じゅうじゅう音がしそうです。
実はドーナツは手作りが一番美味しいです。
評判になったのがマズかったですね。
仲買人(トビー・ジョーンズ)が買いに来る。
中隊長のパーティーに呼ばれる。
そこで綺麗なティーカップにミルクが注がれます。
牛は紅茶に入れるクリームのためだったんですね。
西部劇といえば、《カウボーイ》
何千頭の牛を馬で追って市場まで届ける仕事。
200年前のオレゴンの田舎には「牛がたったの一頭⁉️」
そこから繁殖して増やしたのかしらね?
ともかくドーナッツが評判になって、小金を貯めて町で商売を
しようとしていた2人は追手に追われる身になってしまう。
ラストはファーストシーンで提示されてるように、
森の中で空を見上げながら、寝込むのです。
2人が離れ離れにならなかった事は確か。
蜂蜜を塗ってシナモンを振ったドーナッツは、美味しそうでした。
ミスタードーナッツ(ミスド)の始まりの物語・・・だったら、
もうちょっと洒落になったかなぁ。
最高傑作
火をくべて、部屋を掃き、花を飾り、料理をして、裁縫をする。住むことができる場所が少しずつ作られていく動作。人間の暮らしというものが何をベースに支えられていくのかという根底を問うものだ。比喩的に言えばそれは窓の内側。派手なストーリーやアクションを窓の外側だとすると、ケリー・ライカートは、登場人物を通して鑑賞者が窓の内側で存在することを可能にした。
これまでの映画なら、男たちがケンカを始めればカメラも外に出ただろうし、男たちが散歩に出ればカメラもすぐさま出ただろう。しかし本作は店に残された赤ちゃんや、部屋に残った女たちの表情に眼差しを向ける。
開拓の名のもとに人間の欲望が溢れ出す中で、クッキーもルーも自分の善性を決して諦めなかった。良心の人々が追い詰められるこんな世界に、果たして私たちの住む場所はあるのか。
豊かな自然の恩恵を採取する営みと、森に存在しない材料を使って作る人間の知恵と文明。
果たしてアダムとイヴは楽園を追放されたのか、それとも楽園から解放されたのか?という難題。
可愛い雌牛とクッキーの温かい交流がこの難題に対する一つの答えのようだった。相手を金儲けの道具として見ないこと、相手の存在を尊重する誠実さ、それが私たちに残された最後の希望だ。
ケリー・ライカートの視力によってあらたに世界が始まっていくことを祈って。
新たな西部劇
行列のできるドーナツ屋たちがみる夢
群生するシダが左右前後にのびのびと埋め尽くす。
苔むす道なき道は川べりに続くグラス類に変わり風のざわめきで割れると、その先におだやかに流れる水を舟が渡ってくるのがみえる。
何やら珍しいものが運ばれてきたのを手作業をとめて眺める原住民たち。
ゆるりとした様子が暮らしぶりを伝えるように、オレゴンの大自然のなかで人々は物々交換をしながらのんびりと共存しており、開拓者の欲が派手に渦巻き煙り原住民を激しく支配するイメージを覆す。
時はアメリカ西部の開拓ホヤホヤ時代なのだ。
優しくのんびりやな料理人クッキーと商売気質で強気なキング•ルーがそこで出会った。
国籍も経歴も違う彼らは、夢はあるが元手がなく貧しさと孤独な境遇が共通し意気投合、2人で一獲千金を企てることに。
そしてある秘密により行列ができるドーナツ屋としてみるみる繁盛。
それがあの時岸に着いた珍しい貨物に関係し、成功と欲がさらなる運命を連れに動き出す。
人間のやりとりはほぼどの過程も淡々とし暗めの静寂で間合いが多く、時折ふと笑みがでるユーモアや一瞬で裏返るシリアスさが点在する。
自然や動物たちは常に生き生きと描かれ目が覚めるほど美しい。
それらが四角の画面に見事に凝縮され、多彩に色付き、たわわに実り、なんとも巧みな味を醸し出しながら独特な空気感のなかに〝人間たち〟を映し出す。
地球の恩恵に感謝して領域を冒さずに暮らしている間、すべての関係性はあの弦楽器の音色が自然のなかの一部であり邪魔することなく奏でるバランスだったことを感じて私はなんだか寂しい気分になった。
巨大な貨物船が巨大なビジネスを載せ、あの日と同じ川の流れに悠然と過ぎていく現代の冒頭シーンに繋がったからだ。
逃亡に疲れ果て眠りに落ちるクッキーのそばで儲けが入った巾着をじっと見るキング•ルー。
きっとこの時彼はお金では決して買えないものの価値をちょっと感じたはずだ。
頭を寄せ横たわったとき欲望のかけらがひとつ転がり落ちたのをみた気さえした。
ベリーやナッツをふたりで収穫しながら希望を膨らませ、ハコヤナギの穴に儲けを隠しわくわくした2人の日々も夢の跡。
皮肉なお伽話のようなその顛末を変わらぬ景色たちに語り草にされながら、彼らは仲良く並んでひと休みしたまま永い夢を見続ける。
ディカプリオのあの作品とは対極の味わい。
温かく哀しく深い余韻がのこる。
追加済み
食い物の恨みは恐ろしい
映画は巨大な船が川を進むシーンから始まる。その川べりを犬と散歩する一人の女性。彼女がある物を見つけたところで、舞台は現代から一挙に開拓時代へ。そして同じ川を、小さな筏に乗せられた牛がゆっくりと運ばれてゆく。川が“流れゆく時”のメタファーだとすると、ここで時代は遡り、そこで育まれる時間が非常にゆったりとしたものであることを示しているのだろう。と同時に変わらない物として、森や大自然の美しさも対比させている。
一方で、川は“忘却”の隠喩でもある。今では西部劇として美化されてしまっているが、本作に登場する男たちは、テンガロンハットやカウボーイ・ブーツなど身につけない薄汚れた格好で、ヒーローとは程遠く小汚い姿である。描かれるのも乗馬ではなく、牛の乳搾りだ。そしてクッキーはユダヤ系、ルーは中国人というマイノリティな存在で、劇中ではネイティブ・アメリカンともごく普通に共生している。「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」でも描かれていた、これがこの時代の実態だったのであろう。(奇しくも両者にリリー・グラッドストーンが出演している)そして、こうした真実は全て忘れ去られているという現代アメリカへの風刺なのかもしれない。
しかし、本作のメインはやはり2人の友情物語。ユーモラスな出会いから、徐々にビジネスが軌道に乗っていく様は爽快なのだが、牛の所有者にバレてしまうのではないか、どちらか片方が欲に目がくらんで相棒を裏切るのではないかと、ハラハラドキドキしてしまう。
そして冒頭のあの場面。そことリンクするのだから大体の予想はつくのだが、肝心のそこへ繋がるシーンを飛ばしている。つまり、如何にそうなったかは観客の想像に委ねられているのだ。その上で同じく冒頭の「鳥には巣、蜘蛛には網、人には友情」というウィリアム・ブレイクの格言とも結びつき、静謐な感動をもたらすのである。
川の流れのように・・・
スタンダードサイズの画面に映る穏やかな流れの川。左から右へゆっくりと画面を横切っていくタンカー。この映画の中の時の流れを象徴するようなシーンだ。最初にこの映像をゆっくりと見せることで、観客を映画の世界に引き込もうとしているのかもしれない。
地味なロケーション、地味なストーリー、地味な演技。だが地味も極めると味わい深い。
地味だが、オレゴンの自然はとても美しい。日の当たる木々、川、鳥の鳴き声。ずっと観ていたくなる。
そして、一攫千金を狙う手段がドーナツとは参った。牛の乳を盗んでつくるドーナツ。バレたらやばい。しかし、やばさを感じない。一向に緊張を感じない。映画の世界に引き込まれてすっかり弛緩してしまっているからか。
まあ、牛のかわいいこと。祖父母の家で牛を飼っていた小学生の頃、餌や水をやって世話したことを思い出した。牛は人懐こくて、可愛いんです。人の声を聞き分けるんです。だから、毎晩話しかけているクッキーが近づいたらああなるよな、と納得の動き。
冒頭の衝撃的なシーンの回収をラストで行う演出もよく考えたなあ。しかも、敢えてはっきりとは繋がりを描かないところもよく考えられている。
ゆったりと映像の世界に入りこんだ2時間だった(2024年映画館鑑賞12作目)。
【18世紀、オレゴン。西部開拓時代を舞台に、印象的なアコースティック音楽を背景に、夢を叶えようとする二人の男の姿を恬淡と描いた作品。アメリカンドリームを目指した二人の男の友情の物語でもある。】
■アメリカン・ドリームを求めて未開の地にやってきた料理人のクッキー(ジョン・マガロ)と中国人移民のキング・ルー(オリオン・リー)。
意気投合した2人は、ある大胆な計画を思いつく。
それは、この地に1頭しかいない仲買人(トビー・ジョーンズ)の牛からミルクを盗み、ドーナツを作って一獲千金を狙うというものだった。
<感想>
・冒頭、2体の白骨が河原で少年により掘り出される。2体は並んで埋められている。
ー この冒頭のシーンがラストシーンと時を越えて繋がるのである。-
・その後、先のショットの延長上で男がキノコを探す姿が映し出される。
ー この連続ショットの繋ぎも絶妙に巧い。-
■クッキーと中国人移民のキング・ルーは、クッキーがキング・ルーを助けた事から共に放浪をする。
そして、クッキーは仲買人の牛の乳を夜な夜な盗み、ドーナツを売りドンドン金を稼いでいく。
だが、仲買人が噂を聞き、ドーナツを買いに来たことで、彼らの運命は徐々に変わって行く。
リリー・グラッドストーンが仲買人の奥さんとして、少しだけ出演していたのも、嬉しい。
<今作は、いつものケリー・ライカート監督作と同じようにシンプルなストーリーテリングながら、結末を予測させるシーンを敢えて排除し、スリリングな展開を用意し、観る側を惹き込むのである。
今作は、印象的な、優し気なアコースティック音楽を背景に、アメリカンドリームを目指した二人の男の物語なのである。>
あらくれた時代の優しい物語
こころやさしいクッキー、お金儲けに励みながらもどこか静閑な空気をまとうキング・ルー、静かにクッキーにこころを許す雌牛。
交わす言葉は多くはないが、おたがいを思いあうふたり(と一頭)の強いきずなはよく見えた。
富を負い求める血気盛んな男たちがはびこるなかの、優しい物語。すべてを語り尽くさない
描き方が、観るものの想像を膨らませてくれます。
歴史の端っこの方で
今年ナンバーワンに良いかも。ケリー・ライカートの作品は油断してると...
今年ナンバーワンに良いかも。ケリー・ライカートの作品は油断してるととても精神が傷つく作品もあるけど(映画としては最高だが精神的にヘビーダメージ)
ファースト・カウは、終点は始めのそこで決まっていて
ちょっとしたお伽話のような浮遊感とそこに確かにあった友情とゆうか“2人”がいたとゆう事実に胸が締め付けられるような幸せなような、なんとも言えない気持ちになる。こんな気持ちになる映画はなかなかない気がする。
私は映画館で受付で売ってるオヤツのドーナツとコーヒー片手に観たファーストカウをずっと忘れない。めちゃくちゃに良い映画を観る時間だった。
ケリー・ライカートの山の湿度や、河原のカサついた植物の手触りが画面から伝わってくるようなカメラワークはほんとうに神がかってる。
物語自体に深みを感じなかった
全118件中、1~20件目を表示