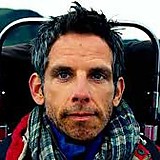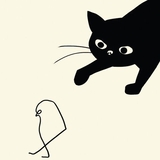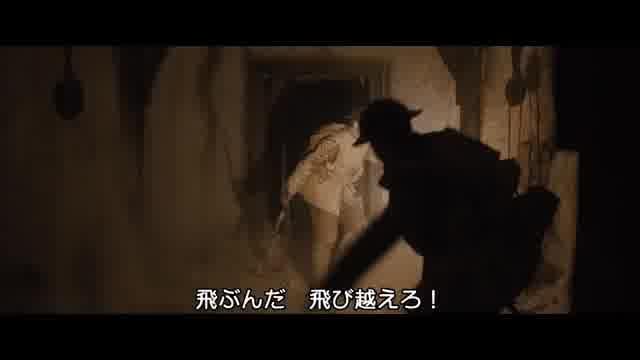1917 命をかけた伝令のレビュー・感想・評価
全132件中、21~40件目を表示
地獄めぐり、幻想的
主人公たちを追いかけていくカメラで、緊張感があり、ハラハラ、ドキドキ、観ていると、不意に幻想的な風景の中に出ることがあって、桜が咲いていたりして、現実感が無くなる。戦地では、現実感が無くなりそうだな、人が人を殺している非現実感、みたいなものが、だから戦争ものは一種ファンタジーのようにも見えるのかな、野火もそう感じたなぁ。
階段から落ちて気を失ってからの、加速していく非現実感が、印象に残る。シンメトリーな映画の作りも、寓話的で、ワンカット風の体験型映画という面白さだけじゃなくて、場面場面の美しさが、心に残る映画だった。
戦争体験
全編ワンカット風なのだが、繋ぎ方が自然なので没入感がとんでもなく戦争の空気感が感じられる、まさしく戦争体験映画でした。個人的にな見所はやはり、クライマックスの戦場を全力で駆け抜けるシーンで、鳥肌が止まず声が出るほどハラハラさせられました。
とても素晴らしい作品でした。
1917
全編ロングカットの戦争映画。
重要な任務を任された二人が最前線にいる大佐に命懸けで伝令を伝えに行く。
ストーリー自体はシンプルで分かりやすい。
ロングカットの技術が凄い。
それよって主人公目線で映画の世界にのめり込みながら鑑賞できた。
罠にハマったり命懸けで走り抜けたり常にハラハラした。
伝令を伝えに行く事が優先で殺しを最小限にしていたのが良かった。
来週になれば命令が変わるかもと言う
大佐の言葉が重い…
戦争はダメだ…
臨場感
臨場感たっぷり。あたかも自分も同行してるかのような。
目線が同じ高さにあり塹壕の中での行動の仕方がリアル。
敵陣へ向かう時に稜線に気を付ける。
空戦してるときの距離感。
草原の広がり。
狙撃されたときの敵の見え方。
対面した敵のシルエット。
いろいろと目線が現場にいる感じで。
そして戦場の悲惨さ。
死んでる人、馬、犬。
ほったらかしでそのまんま。
臭いそうで気持ち悪い。
そんなのを映像で見せてくれるのは、知らない人間にとってはありがたい。
そんな場には立ちたいと思わなくなるから。
調べてみたら、インド人兵士。
インド人の部隊はあったらしいが、同じ部隊にいることはなかったろうとのこと。
名もなき兵士への追悼
イギリスにおいては、第二次世界大戦よりも第一次世界大戦の方が印象深く語られ、そして記念碑も多くセレモニーも催されると言う。
ヨーロッパは歴史的にも大きな戦いの連続で、多くの若い命が戦争によって失われた過去で成り立っている。人間というものは争わずには暮らせない生物なのかもしれない。
美しいフランスの草原で昼寝をしている青年が
叩き起こされるところから物語は始まる。
全編通して、人の暮らしを破壊しつつ行われる戦争の荒々しさを見せつけ、超人でもなければこれと言った能力もない、言ってみれば運さえない若者の戦争体験。
ストーリー展開に起伏は感じられないのに、なぜか惹きつけられ目を離せない。
「兄はすぐに見つけられる。僕によく似ている。」
そう言い、みるみる血の気を失っていく友を置き去りにしなければならない過酷さ。
(その言葉によって、見る側は彼に似た顔を探すんだけどまあ大して似てなくてちょっとガッカリ。だって結構印象的な顔だから)
飛行機や戦車が発明され死ぬ人間の数も格段に増える。
そしてこの戦争に勝利した連合軍。
イギリスはドイツに多額の賠償金を請求するがお金のないドイツに代わりアメリカが支払い、ドイツはアメリカに借金返済して行かねばならず、国家的な困窮に陥るわけで
それがドイツ労働党を台頭させる事につながる。
そういった連鎖を断ち切るために戦後の賠償金のシステムを廃止すると世界は決定。
だが今の国連を見るとそういう良心という機能が働いているとは到底思えない。
奇跡的に平和な今の日本に生まれ、育ち、戦争とは実質無関係に生きて来られた事に感謝しつつ、今後も我が国土が戦地とならない事を心の底から祈ってしまう。
走れ。
原題
1917
感想
観客が戦場の最前線を走り抜ける兵士たちの息遣いをもリアルに感じられるように最初から最後まで映像がひとつにつながったワンカット映画体験。
ワンカットっていうかワンカット風ですね。
目覚めてすぐに任務を告げられて目的地を目指すだったので非常にRPGのゲームしてる感じでした。
主要人物との会話や色んなイベントで没入感があり約2時間があっという間でした。
相棒が思ったより早く戦死したのはびっくりでした!
中盤の相討ちで目覚めた後はちょっと中だるみだったような…笑
戦争映画ですが激しい戦闘シーンはないのでそこは期待しないでください。
でも分かりやすく、見やすい作品でした。
※この戦争が終わるのはー最後の1人になった時だ
圧倒的臨場感
第一次大戦の悲惨さをドイツ軍側から描いた異色の反戦映画の名作「西部戦線異状なし(1930) 」と対をなすような傑作です。
まるで戦場にいるかのような圧倒的臨場感は手振れのない4Kステディカムなど最新の撮影機材とスタッフの技術に支えられていますが、キャスティングの妙や往年の巨匠黒澤明作品を思わせる映像の格調高さも加わっており、メンデス監督のセンスと手腕には脱帽です。
目的地まで15キロと分かっていても道のりの険しく遠い感覚は、この撮影手法によるところが大きいでしょう、同僚のブレイクが助けた独軍のパイロットに殺されるシチュエーションは突飛ですが、そこかしこに横たわる遺体の山、水筒にいれた牛乳が赤子の役に立つなど日常感覚と非日常の交錯が巧みに配置され心が掴まれます。
エンドクレジットでこの物語を話してくれたアルフレッド・H・メンデス上等兵へ捧ぐと出ますが製作・脚本・監督のサム・メンデスさんの祖父です。似たような軍務に就いていたのでしょうが本作の内容はフィクション、独軍の西部戦線での戦略的撤退、アルベッリヒ作戦は史実ですが、第一次大戦の塹壕戦に詳しい専門家は砲兵部隊による援護なしの突撃作戦は考えられないとしているので、使命の重要性を高めるための脚色でしょう、ただ「攻撃中止命令は第三者も入れた場で伝えろ、攻撃しか頭にない指揮官もいる」というスミス大尉の助言はメンデスさんの祖父の実体験が滲み出ているようにも思えますね。
1917
走る、が印象的な作品。
目標に向かって走る主人公を見る映画は素晴らしい。
フォレストガンプを思い出させる。
最後のシーン、ブレイクの兄に友の訃報を伝えて、兄からの言葉『最後にいてくれてありがとう』
この言葉が唯一の救いだった。
1600人の命だけでなく、ブレイクの家族も救った。
話題性だけではないワンカット
物語は、第一次世界大戦中のアメリカの上等兵・スコフィールドが、前線部隊に伝令を伝えに行くというシンプルなもの。その上等兵をカメラが追いかけて、映画ははじまり、終わる。
「ワンカット」に意味がある。話題性や企画としてだけでなく、「戦時中」という環境にいる・「伝令」という役割を持った人間を映すには、「ワンカット」がとても適している。
一つの視点=一つの役割を与えられた人間、一つのこと、つまり「それをするしかないという状況」に追い込まれている主人公に対する、一つの視点が「ワンカット」。
伝令の任務を終えても、待っていたのは達成感ではなく喪失感。大佐には「明日になれば新しい命令が…」的なことを言われ、友(ブレイク)の命と引き換えに達成した伝令の無意味さを感じながら、友の約束を守るため、ブレイクの兄にブレイクの伝言・最後を伝える。
すべての目的を終えたスコフィールドは、喪失感を抱えながら、冒頭シーンと同じよう態勢(木によりかかり戦時中のひとときの憩いをかみしめる)で座り込み、大切な人の写真を見て思いにふける。
それは、また戦争が繰り返されることを暗示しているようにもみえるし、そこで終わりにしたいと思っているようにも見える。
計算されつくされた映画。客を楽しませよう、物語を伝えよう、戦争の悲惨さを映画で伝えよう、素晴らしい精神(スピリット)で作られた映画だと思いました。素晴らしい。
迫力
レンタルでパッケージにワンカット撮影とあるが、観る頃にはそんな事は忘れて普通に見てたw。滝を落ちる所は変わった撮り方してるなぁと思ったが、そうかワンカット撮影だったんだと。
自分としてはドルビーアトモスでの音声の迫力の方が良かった。もの凄い戦闘シーンが多いワケでは無い。一対一、せいぜい一対二程度の銃撃戦くらいだが、その銃撃戦の音声、他の音も効果的に聞こえる。
ストーリー的には「うん?」と思う箇所も多々有るが、ドキュメンタリー風では無いのでそれは演出の範囲内かなぁ。
戦場の優等生なメロス
若手俳優の中でも頭ひとつ抜け出た演技派であるジョージ・マッケイの成長ぶりを見たくて鑑賞。
14.5km先の前線で撤退すると見せかけたドイツ軍の罠にかからんとする同胞に、将軍の突撃中止命令を伝令する若き兵士二人の戦場ロードムービーである。
ひたすらのどかで美しい草原の真っ只中である。名カメラマン、ロジャー・ディーキンスは、その美しい情景を引いて撮ることを得意とする名匠であったはず。ところが本作では、二人の伝令にグッと寄った画が多かった。おかげで、画面から見切れているところに敵がいないかと始終気にしどおし、体に変な力が入った。いつどこから撃たれるかもしれない緊張感を共体験させようという目論見だったのだとしたら、まんまとハマったということだろう。批評などでは長回し中心の撮影方法が話題となっていたが、寄りの画によって視野を限定するための最善の方法として、それが必然的に選択されたということではないか。決して長回しを売りにしようという意図ではなかったと感じた。そんなのはデ・パルマ作品で十分だし、そもそもサム・メンデスはそんな映像作家ではない(と信じたい)。おそらくは彼の祖父であろう方から戦時中のエピソードを聞いたときの臨場感をそのまま作品にしたかったのではないか。サム・メンデス監督が得意とする、凝ったシナリオでなかったのも、そのためだったと思う。
「プラトーン」や「プライベート・ライアン」などのようなドラマチックな展開はない。
戦友を失った悲しみに浸ることすら禁じられた道行で、使った弾薬も、殺した敵兵も、戦争映画の中でも少ない部類(ハクソー・リッジは別にして)に入るだろう。
淡々と任務を遂行するジョージ・マッケイは、過剰な演技を滅多にしない俳優としての資質を存分に発揮していて適役であった。塹壕の中で隠れて暮らす少女と赤子に出会い、束の間の安息を得ても、「行かないで」と言われても、死んだ友との約束を果たすために走り続ける。途中から、完全にメロスだったが、太宰のような照れ隠しの表現は全くない。静かな使命感の灯火を燃やし、走り続ける。
見事伝令の役を勤め上げ、死んだ戦友の兄に最期を看取ったことを伝えた先に、果てしなく広がる美しい草原。カメラマンも、俳優同様にずっと我慢し続けた景色を、ラストシーンで余すところなく描き切った。「これを踏みにじり、汚すのは誰だ?」という静かなメッセージを感じた。どこまでも品のある、優等生な作品である。
「将軍命令です」「直接命令です」
映画「1917 命をかけた伝令」(サム・メンデス監督)から。
現代は「1917」・・これではなんだかわからない。
「1917年」のある1日を、全編ワンカットで描いた、とある。
観た感想は「ワンカット風」だけど、新鮮な映像だった。
冒頭「1917年4月6日」の字幕が出るのだから、
タイトルも日付まで入れた方が、リアルだったのにと思う。
戦争のシーンが多いので、メモも少なかった。
ただこの場面設定は、ほぼ100年ほど前の「第1次世界大戦」、
この後「第2次世界大戦」が続くと考えると、
ずっと昔の話ではないってこと。この事実に驚く。
伝令のために、命を懸けるなんてことが、行われていたし、
「将軍命令です」「直接命令です」の一言で、
どんな場所へも入っていける組織体制に驚かされた。
上等兵の身分なんて、最初から誰も疑っていない。
それだけ軍組織として、上の命令は絶対だったってこと。
この頃って、まだ無線が発達していなかった?
敵に傍受される危険があったから、使わなかった?
確実に届くかもわからない「兵士による伝令」よりも、
いいと思うんだけどなぁ。
最後まで見届けよ
封切り時に見逃したが、今回のコロナのせいで、リバイバル(というほど古くはないか)上映をしていたので、見ることができた。
期待通りの素晴らしい映画だった!
名作揃いの戦争映画の代表作として、長く記憶に残りそうな気がする。
(正直言って、似たような長回しと撮影技法のあの映画より、ずっと)
全編ワンカットという触れ込みだったので、興味深かった。古くはヒッチコックに始まるギミックと思うが、違和感なくつなぐ手法に感服。もちろん撮影自体がワンカットなわけはなく、CG等駆使して、そう見えるように作ってあるのだと思う。それが現代のというものだろう。(主人公のひとりが敵兵に刺されたときは、顔色がみるみる蒼白になっていく。メイクだけでこれはできないだろう。)
その効果の絶大なこと。
一人称で語られる小説を読んだようだ。
絵画や写真などであるような、人物の視線の先に何を見ているかを想像させることで、どんなパノラマよりも情景を雄弁に語っている。
しかし、ときに、カメラは主人公の背中に回り込み、答えのように実際にその光景を見せてくれる。そこには想像を超えた悲惨な状況が繰り広げられ、見たものを戦慄させる。
そこかしこにある死体の山、死臭さえ伝わってくる。カラスもいい演技をしている。馬の死体はどうやったのかな?
画面の外に何かあるのかを予想させる手法は、サスペンスやホラーでよく見るが、画角が切り取られることの制限をうまく使っていると思う。
途中で椅子から飛び上がるほど驚いたシーンが2度ほどあったけど、それも音響とサスペンスのなせる技だ思う。
主役のスコことジョージ・マッケイは、不明にして知らなかったが、子役から20年以上のキャリアを持つ役者のようだ。初出のシーンでは無表情で目も細く、相方のズングリしたブレイクことチャップマンとのコンビはSWのあのコンビを彷彿とさせる。二人とも少年兵と言ってもいいほど幼い顔立ちだ。しかし、困難を克服するにつれ、次第にたくましく大人の表情になっていく様子がみごとだとおもった。たった一日の話だが、実話に基づいていて、より重さが記憶に残る。
キングスマンの二人と、カンバーバッジが出ていたことを見るまで知らなかったけど、ちょい役なのに、印象的な役だった。
良かったけど、ちょっと気になる
8時間かかるって言ってだけど
2時間で着いたことになる?
あと、赤ちゃんのシーンがいらなかった
赤ちゃんに牛乳あげてよかったーって
いろいろおかしい^ ^テンポも狂ったしね
これでいいの?
ワンカット風が話題ですが、そこは特になんとも思いませんでした。
戦争時の実話なので、様々な人間模様があったと思うのですが、その辺りは割りとあっさりです。
引き込まれるシーンもあるのですが、命題である『攻撃中止』はあっさり告げられ、ハイおしまいという感じです。
べちゃべちゃの泥地を歩くシーンはリアリティありますが、幾多も出てくる戦死体は安っぽい作り物感が高く醒めてしまいます。
ワンカットを優先しストーリーを軽んじた作品と感じました。
悪くはないけどまあまあです。
1カット影像が売りだけど、大事なのはそこじゃない!
アカデミー賞受賞作で1カット影像が売りの大作。ということで、戦争映画好きとしては期待半分心配半分で観に行きました。
第一次世界大戦の戦場で、敵の罠を知った司令部が、最前線の部隊に攻撃中止を命令するため、2人の兵士に伝令を命じてその二人が悪戦苦闘して命令を遂行するというストーリーです。
映画の売りは、前編1カット影像と言う事。最初から最後まで1台のカメラがずっと主人公達を追い続けるという、とても難しい撮影方法を取っています。(もちろん上手く編集してつないでいるだけなのですが)しかし、その凄さよりも、それによって得られる副次的な効果の方が僕は素晴らしいと感じました。
それはまず第一に、1カットで撮るために練りに練られた脚本です。無駄を省いてテンポ良く作られた話の進み方が非常に良く出来ています。本来映画はいくつものカットを別々に撮って、後で編集でつなぎ合わせるわけですが、編集の仕方によっては冗長になったりあるいはせせこましくなったりと、本来の脚本で描きたかった事とは別の印象になってしまう事もままあります。しかし、1カットで撮るために、最初に脚本を何度も推敲しているため、シーンの構成に無駄が全くないのです。
第二は、1カット撮影という緊張感です。NGの許されない撮影のためか、非情に緊迫した影像が見ている方にも感じられるのです。これが戦争映画としてピッタリで、キリキリと胃が痛くなるような緊迫感が映像から伝わってきます。
そんな副次的な効果によって伝わってくる映画のテーマ、それは戦争の無残さです。主人公のスコフィールドは元々相棒のブレイクに誘われて命令を受けたため、最初この命令に乗り気ではありませんでした。しかしブレイクの兄が最前線にいて、命令を伝えないと戦死するかも知れないと知り、徐々に使命感が高まっていきます。そしてそのブレイクの死によって、彼の遺言と最後の姿を伝える役も引き受け、命がけで戦場を駆け抜けるのです。
彼の走る姿を映すカメラは、同時に戦場の様々な影像を映していきます。あちこちに無残に散らばる戦死者の遺体。メチャメチャに壊された街や、人々の生活。そして塹壕にうずくまる疲れ切った兵士達。この無残さを伝えるための1カット映像なのだ、と観ている人間に訴えかけてくるのです。
ようやく最前線に到着するも、第一陣の突撃命令が下り、その中を横断しながら部隊指揮所にたどり着くスコフィールド。直ぐに攻撃中止の命令が下り、彼の使命はとりあえず成功に終わります。しかし、指揮官はこうつぶやきます。「来週はまた別の命令が下る」と。友の命さえ失う命がけの伝令も、結局は戦場のたった一つの駒に過ぎないという事実。なんという残酷、何という無残。ただ一つの救いは、司令部を出る際に、入り口に立っていた少佐がつぶやいた「ありがとう」の一言。彼の連絡は、とりあえず1600名の命を明日につないだのだから。そしてブレイクの兄に弟の死を伝えるシーンは、涙無しには観られませんでした。死ぬかも知れない兄が生き残り、助けに行った弟が死ぬなんて…。合掌。
見に行く人のために一言。この際1カット影像というのは忘れなさいと言う事。そこに拘っていると、肝心のストーリーを追うのがおろそかになりますので。大事なのはそこじゃない!戦争の無意味さ・無残さを是非感じ取って欲しい作品でした。
技術
バードマンの時よりも技術は向上されてるみたいだ。あんな事もこんな事も出来るようになってる。
ただ…映画としてはどおなんだ、と思う。
「全編1カット風」
この演出技法が作品に必要であったかと問われれば絶対ではなかったと思える。
意味付けは出来ると思う。
戦争映画である事から、過ぎていく時間とか戻らない命とか、そおいうものの印象は深く表現されてたように思うのだけど…作品としてはのっぺりした印象だった。
映像見本市を見てるようでもあった。
業界へのプレゼンならば満点の仕上がりだとは思う。
本作品を見て思うのは「よく出来てるなぁ」だ。この手法が緊張感を増してくれる風でもなく、感動をもたらしてくれる訳でもなかった。
1カット風に出来るのは凄い事なのだけど、1カットでやんなくてもいいじゃんと思えちゃった事が残念だった。
どおせなら「この作品は1カットじゃないとダメだったんだ」と思いたかった。
大変な撮影だったと思う。
撮影環境も従来とはガラッと変えたのではと思うし、カメラも違うんじゃないかと思ったり…この作品がもたらした技術革新は結構なモノじゃないのかとは思うけど…技を観たいわけじゃない。
ラストの平原を疾走するカットは凄い良かった。なんだろう…やっぱ何を撮るかによるんだろうな。演者の心情にリンクするというか…表現するというか。
そんな基本的な事を改めて考えた作品だった。
ぶっちゃけ途中から飽きる。
二番煎じ以上の技術革新はあったんだろうけど、コンセプトとしてはやはり、二番煎じであった…。
映画を観て「上手に撮ってんなぁ」は褒め言葉でもなんでもないと思う。
むしろそこを評価されたら失敗だと思う。
殆どワンショット!
実際は違うのだろうけれども、全編ワンショットで途切れなく続く。すごい技術だと思う。ただ、実際の戦場はもう少し汚かったろう。主人公の一人が救おうとした敵に呆気なくやられるのは、戦争の不条理感を出そうとしたのだろう。
全132件中、21~40件目を表示