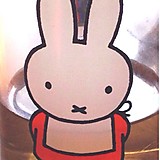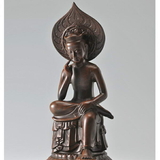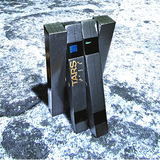フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊のレビュー・感想・評価
全192件中、21~40件目を表示
傑作ですね。
フレンチ・ディスパッチ(新聞の日曜版別冊)最終巻の記事を映像化したというつくりの映画。
個性ある記者の面白い各記事がエピソードとしてオムニバス的に映像化されるとともに、この雑誌そのものの編集風景、編集長の死(遺言により最終刊行となっている)が底流として描かれるという凝った造り。
各エピソードがいつものウェス・アンダーソン風短編映画としてとても面白いし、挿入されている編集長(ビル・マーレイ)の人柄、編集方針や編集の過程の描写もとても素晴らしく、各エピソード(記事)の舞台裏がわかるとともに、複数のエピソードを有機的にリンクする役目を果たしている。
驚くような豪華キャスト。え、彼はこれだけしか出てこないの?みたいな。
完成度の高い傑作です。
天才が再現する“こまかすぎてつたわらない”記事
カットごと構図をキメるのが小津っぽい。
すべてが意識的な矩形(スクリーンorモニター)の絵になっている。
その“絵”がマンガのように次々に切り替わってストーリーが語られる。
芸が細かく、ウェス・アンダーソン監督、病状がさらにすすんでますね──てな感じの映画。
架空の街、架空の雑誌の編集長が急死した。
かれの遺書により4記事と追悼文が掲載された。──という話。
情報によると本作は監督の雑誌「ニューヨーカー」にたいする愛情に触発されており、記者や記事などじっさいのものから着想を得ている──とのこと。
とはいえ、アンダーソン監督のこだわりは、おそらく一般庶民にとっては「小津安二郎の赤ケトル」みたいなものでしかない。よってそれぞれが感じたままにたのしむのが適切だと思われる。
記事ごとの私的な気づきを挙げる。
①サイクリングレポーターはオーウェン・ウィルソン演じる記者が自転車で街を巡り過去と今を比較する地元記事。The Bootblack District、The Bricklayer’s Quarter、The Butcher’s Arcade、Pick-pocket Cul-de-Sac。過去と未来がスプリットで並ぶ。並べたかったんだろうな──と強く感じた。
②コンクリートマスターピース──の記事。
気になったのはエイドリアン・ブロディの鼻とマロングラッセ。
子供の頃お土産にもらったマロングラッセを食べたことがある。
三年に一度ていどしかまみえない稀なお土産だった。
どこに売っているのか知らない。
おおきめな栗が丸で個包装されている。
ビニールをやぶるとべとべとした糖膜。
ほおばると少しリキュールをまとった複雑な蜜がひろがる。
栗はやわらかくて甘く、それをふくんでいるあいだは幸せだ。
で、もう一個ということになるが、マロングラッセにはかならず厳格な制限がもうけられていた記憶がある。
その記憶からするとマロングラッセが獄舎で看守を買収するお金の代わりとなったとしても不思議はない。──とシモーヌ(レア・セドゥ)がもぐもぐするのを見ながら思った。
③あるマニフェストの改訂版──の記事で萌えるのはジュリエット(リナ・クードリ)のゴーグル付ハーフヘルメット。このクラシカルなヘルメットを女の子が被るとやたら映えることはオー、モーレツ!のCMによっても立証されている。(という例えが伝わるか解らないが・・・)
喫煙率の高いこの“章”では英語とフランス語が交互に飛び交い、夭逝したチェスの達人兼革命家ゼフィレッリ(ティモシー・シャラメ)をクレメンツ記者(フランシス・マクドーマンド)が回想する。
④警察庁長官の私的な食事会──の記事。ジジが捕らわれているアジトに娼婦がいる。シアーシャ・ローナンが演じていた。物置に拘束されたジジは彼女に眼の色をたずねる。小窓から覗くときパートカラーになった。その鮮やかな青い眼!。
アニメは横視点のメトロイドヴァニア風だった。
編集部ではエリザベス・モスの射る目つきが主張した。
ラストシークエンス、バックミュージックのピチカートがとても決まる。
モーゼス(ベニチオ・デル・トロ)の抽象画もエピローグのイラストもいい。
映画っていうよりウェス・アンダーソンという一個のメディア。
ところで知識層にウケる欧米のものが日本に入ったとき、ほんとは万人向けなのに、(日本国内では)権威をまとってしまうことがある。ウェス・アンダーソン映画もその性質をもっている。もちろん映画自体に罪はない。映画がおしゃれと抱き合わせで語られてしまうようなスノビズムがきらい。
(伝わるか解らないが)つまり──わたしはこの映画をそれなりに楽しんだ。だけど「おいらは田舎の百姓なんでウェス・アンダーソンの映画はわかんねえや」──という労働者の率直な感想もわかる。──という話。
理解不能・意味不明、でも……
既視感はあるものの何だったか思い出せない
ウェス・アンダーソン作品、恥ずかしながら初見です。いくつかの作品は気になりながら見逃していて、高名のみ伝え聞くに、なんとなく敷居高そうな、めんどくさそうな、でも波長合いそうな気がしていた。
今作、どうもフィルモグラフィーの中では特異なポジションのようだが、飄々としてなかなか好きなセンス。どことなく初期のウディ・アレンを思わせる批評眼とぺダンチックなナレーション。パステルカラーの色彩とやや浅いモノクロの画面が交互に出てきて、規則性があるようなないような。
演劇的な演出と横スクロールがお好みで、2次元的表現が相当好きなんだなあと思ってたら実際にアニメーションまで飛び出した。どこまでも人を食ったような設定、ストーリー、キャラクター。今さらだけど、これはギャグ映画なんだね。
高踏的というのか、都会的というのか、パリのエスプリというのか、既視感はあるものの何だったか思い出せない妙な感覚。モンティ・パイソンか? 60〜70年代の風俗を相当意識しているのは明白だが。
エンドロールに登場するフレンチ・ディスパッチの表紙イラストが楽しい。このアートワークは極めてレベル高い。画集が欲しいぞ。
唯一無二の記事をたっぷり掲載。名誌に敬愛を込めて
ウェス・アンダーソンの長編監督10作目に当たる本作。
インディーズ界の異色の俊英から、いつの間にか現代映画界屈指の鬼才にして人気監督へ。それも唯一無二の手腕と作風の賜物。
コミカルでシニカル。カラフルで、計算し尽くされたカメラワーク、編集。個性的な登場人物らが織り成す風変わりな群像劇…。好き嫌い分かれるが、ハマったら病み付きになる。
題材も毎回毎回ユニーク。キテレツ家族物語、海洋冒険、ロードムービー、ストップモーション・アニメ、青春コメディ、グランド・ホテル殺人ミステリー…。
本作は、“雑誌社”。記者たちによる人間模様は、なるほど確かにアンダーソン群像劇にぴったり。
…と思いきや、ちょい(と言うか)いつもながらの変化球。
20世紀。フランスの架空の街にある、アメリカの雑誌社“フレンチ・ディスパッチ”の編集部。
国際問題、アートにファッション、美食に事件…多岐に渡った記事で長年人気を博していたが、編集長が急死。彼の遺言に従い、廃刊が決定…。
作品で描かれるのは、記者たちの人間模様ではなく(勿論それも描かれるが)、メインは最終号の掲載内容。言わば、記事の“映像化”。
アンダーソンのスタイルである群像劇でありつつ、それよりオムニバス形式風。短編のオムニバス映画を撮るのが念願だったという。
エピローグとプロローグで挟んだ全4章。
エピソード1:自転車とレポーター
編集部がある街アンニュイ=シュール=ブラゼを、自転車に乗った記者が巡る。美しい街並みから怪しい地区へも…。
紀行記事。
エピソード2:確固たる(コンクリートの)名作
服役中の天才画家が女性看守をモデルに新作を発表。芸術評論家による批評。
芸術記事。
エピソード3:宣言書の改訂
女性ジャーナリストが学生運動を取材。そのリーダーである青年の恋や青春を記す。
社会記事。
エピソード4:警察署長の食事室
美食家記者が警察署長のお抱えシェフを取材。署長の息子の誘拐事件に巻き込まれ…。
事件記事。
我々が新聞や雑誌を読む時、特に気に入った記事や特集があったりする。
どれも個性的だが、気に入った記事(エピソード)を探すのもお楽しみ。
個人的には、エピソード4。ミステリー風がアンダーソン作品の中でも特にお気に入りの『グランド・ブダペスト・ホテル』を彷彿させて。
事件解決に、お抱えシェフの料理を利用。誘拐犯一味に、毒入り料理を差し入れ。シェフ自ら運ぶが、毒味をさせられ…。
毒じゃなく睡眠薬でいいんじゃないの?…と非常に突っ込んでしまったが、ユーモアもあって毒もあって。一命を取り留めたシェフを記者が取材。掲載から外そうとしたその記事から、風変わりながら料理人や記者のプロフェッショナルを感じた。
アートに社会派、誘拐ミステリー…一本の作品の中に、様々なジャンル。これぞオムニバスの醍醐味。一粒で多種の味。
オリジナリティー溢れる脚本。
カラーとモノクロ、ワイドにスタンダードと映像や構図も作風や時代に合わせて表現。
美術や衣装は勿論、アンダーソン作品はロケーションも魅力。ウディ・アレンが『ミッドナイト・イン・パリ』を撮った時と等しく、フランスの風景に堪らなく魅せられる。
常連アレクサンドル・デスプラによるリズミカルな音楽。
ラスト、突然のアニメーション挿入。(新聞や雑誌によくある4コマ漫画的な…?)
EDの表紙アートもナイスセンス。
常連~ベテラン~個性派実力派~初参加のキャストによる極上アンサンブル。その面子は豪華過ぎていちいち名を挙げてたらキリないので、割愛。出てくる出てくる豪華な顔触れは、ご自身の目でのお楽しみに。
“アンダーソン・ワールド”は本作でも健在。
独自のスタイルを踏襲しつつ、長年住んでいたというフランスへのラブレター。
フランスの文化、文学や芸術や映画、活字へ愛を込めて。
アンダーソンが自分の好きなもの、やりたい事を惜しみなく“掲載”したような一品。
アンダーソン作品好きなら今回もたっぷり楽しめる。
自分も独特のアンダーソン作品は好きで、楽しいのは楽しいが、ここ近年の『犬ヶ島』『グランド・ブダペスト・ホテル』『ムーンライズ・キングダム』ほどはハマらなかったかな…。
フランス語の言葉遊びなど、分からないと面白さがさらに深く伝わり難い。
分かり難い部分もあり、エンタメではあるが、ちょいアート性や作家性より。これまでの作品より“愛読者”になれるか否か、好み分かれそう。
でも、それもある意味一つの乙。期待を裏切らないアンダーソンの世界観を眺めているだけでも飽きはしなかった。
本作はあくまで“最終号”を映像化したまで。
“フレンチ・ディスパッチ”は長い歴史がある。
つまり、ネタ尽きない記事がある。
もし、他の号も映像化したら…。
また別の魅力があり、また別のお気に入り号や記事もあるだろう。
そんな事をふと思った。
こんな事もふと思った。
“フレンチ・ディスパッチ”は惜しまれつつ廃刊したが、私もすでに廃刊した好きだった映画雑誌とかあったなぁ…。
“ロードショー”とか“DVD&ブルーレイVISION”とか…。
また読みたい。
何回でも楽しめる♪
ウェス・アンダーソン的エスプリ
良くも悪くもウェスアンダーソンらしさしかない
雑誌を映画にするというアイディア、白黒とカラーが頻繁に入れ替わる世界、急なアニメーション、いつものキャスト、いつものカメラワーク、いつものミニチュア風世界。
「ウェスアンダーソンの映画ってどんな感じ?」と聞かれて1番簡単に初見の人に伝わるのはこの映画を見せること、と言えるくらい監督節全開です。
ただしウェスアンダーソンの世界を「知る」のではなく、「好きになる」入口としては、初見の人に自分は勧めないかな。初めて監督の作品を見るなら今作より「グランド・ブダペスト・ホテル」や「ロイヤルテネンバウム」をお勧めします。ストーリーがまだ分かりやすい過去作を1〜2作視聴後に今作を見て、作品の独特な雰囲気や間合い、言い回しに心躍れば立派なウェスアンダーソン中毒です笑。
あの街に遊びに行きたい
キャストも含め、すばらしい美意識で偏執的なほど画面がデザインされていて目が喜ぶ。出てくる人みんな、おかしな人たちだなあと思うし、眠たくなるところもあったけど、意味もストーリーも求めてないのでこれでいいのだ。シェフの話が面白かった。面白さは求めてなかったのでラッキーだ。
家人がBlu-ray出たら買うと言っていたので、発売情報が出てきたら上手にさりげなく目に入れようと思う。またアンニュイ=シュール=ブラゼに遊びに行きたい。
余談だけど私はなぜか学生運動の話にまったく興味が持てない体質のようだ。好きな刑事ドラマとかでも学生運動が絡んだ回になると録画したのを何度再生しても途中で寝てしまって話が分からなくなる。克服したいなあ。でも興味ないなあ。
独特の絵柄
「ああ、ウェス・アンダーソン監督らしいね」
これで納得できるか出来ないかで、評価は分かれるだろうな…という作品。「犬ケ島」が気に入った人の8割は大丈夫かと思うけど。役者が演じるのだけど、ストップ・モーション風やら絵画風の特徴的な画が目に付くので、そこから入ったら、すんなり入り込めるかも。古いテレビドラマ風の画面に、最初は違和感あったが、どこか懐かしさが手伝って、すぐに慣れた。
内容はなかなかついてくのが大変だけど、自分としては、モンティ・パイソン好きなので、風刺コメディ風の作りは大歓迎。彼がイギリス人だったら、もう少しパンチが効いた嫌味がちなネタとなるのだろうけど、そこはアメリカ人らしい良識で、抑えられているので、少し薄味に感じた。
とはいえ、文化的な背景が違うので、シニカルな部分は半分くらいしか理解できなかったと思う。1950年の前後15年くらいのフランスについて、もう少し前知識仕入れて観れば良かったか。
それでも、次々繰り出されるネタや、ドタバタ映像は、画面として観ているだけで楽しいし、4つの章編を繋ぎ合わせた構成で、それぞれの章の展開とオチも小気味よい。独特の間が心地よく、だんだん癖になる。たまには珍しい世界観に浸ってみるのも、また一興かと。
zzzzzzzzzz
フレンチなのでフランス映画かと思いきや、アメリカだった。
フランス映画とは相性が悪いからしょうがないかと思っていたが、違った。
とにかく全く理解できず、半分以上爆睡。
オムニバス的になっていたので切り替わる度期待したが、やっぱりその都度寝た。
なぜ他の方はこんな高評価???
もう書くべきこともない。
パンフレットに至るまで計算し尽くされた一作。
ウェス・アンダーソンの美的感覚とフランス映画(っぽさ)が融合するとこんな映画ができるのか、という驚きに満ちた一作。舞台となる街の名前からも分かるように、アンダーソン監督が描く「フランスっぽさ」は徹底的に意図的かつ戯画化されたものなので、そこは評価の対象にはならないはずなんだけど、観ているこちら側は、自分が持っている「フランス映画ってこんな感じだよね」っていう先入観を見透かされたような気がして、ちょっと居心地が悪くなることも。
作中のエピソードはどれも面白いんだけど、オムニバス形式なのかというとそれともちょっと違っていて、この不思議な構成は何?と思っていたところ、作品全体が「フレンチ・ディスパッチ」誌の見立てで、それぞれのエピソードは誌面を飾っている記事として描いている、という意図を知り、それでようやく先の不思議な感覚を理解することができました。
シンメトリーの構図と緑と黄色が印象的な淡い色調に統一された映像は、最高に形式的で最高に美しいものの、一歩間違えれば(イメージされた)フランス映画のまねごとに見えそうなところ、徹底的に計算された画面構成で、その陳腐さを紙一重で躱しているとしか言いようのない名人芸はさすがのひとこと。
ほとんど台詞のない役どころまで超豪華キャストのため、しばしば目移りしてしまいますが、どの俳優も楽しそうに生き生きと演じているところが非常に印象的。
そして作品の延長線、というか内容を凝縮したようなパンフレットは、内容も豊富で読み応え十分のため、購入を強くおすすめ!
なんだろ、わからないのに面白かった
体調管理が重要
全192件中、21~40件目を表示