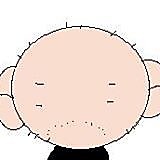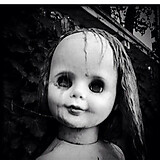ミッドサマーのレビュー・感想・評価
全633件中、181~200件目を表示
地獄のウルルン滞在記
「ヘレディタリー継承」のアリ・アスターの新作ということで気にはなっていたけど、グズグズしている間に公開は終了。先日アマプラの見放題に入ってきたのでやっと鑑賞した。
基本的には「悪魔のいけにえ」や「グリーン・インフェルノ」などに代表される、常識の通じない場所に迷い込んでひどい目に遭う系ホラーのプロットに則った作品だから、超常的な存在は出てこないしハッキリと直接的なグロシーンも殆どないけど、アリ・アスタ―の真綿で首を締めるようなあの演出は、観終わった後もずっとボディーブロー食らったみたいにじわじわ効き続ける。
特に、人が死ぬまでを最初から最後までじっくり見せるとことか、ホントに嫌な演出するよね。
また、前作「ヘレディタリー継承」も本作も主人公がカルトに取り込まれるというコンセプトは一緒だけど、前作のピーターはどちらかと言えば本作のクリスチャンに近い感じすべてを奪われた絶望の末に取り込まれるんだけど。逆にダニーはカルトに取り込まれることが彼女にとってある種の救いとして機能してるんだよね。
宗教的儀礼への恐怖
個人的に日本の祭も含めて宗教的な意味合いを持つものに対して恐怖心がある。
より正確に言うなら宗教的儀礼の持つ意味を知らないままにそれに従わされることに、だ。
何故この手順を踏まえるのか、何故この格好になるのか、そしてそれに反した場合どうなるのか。
自分が参加した祭でさえもその奉納されている御神体さえ我々は満足に知らないはずだ。
この作品ではまさによく知りもしないままに好奇心あるいは無教養で祭へと参加した主人公たちはその価値観に大きく揺さぶりをかけられる、気付いた時には抜け出せない深みにハマってしまっていた。
随所に散りばめられた暗示はいささかやりすぎのきらいもあるが、信仰者たちの奇妙な文化を異物感として表現しているのかもしれない。
奇妙なセックス。
グチャグチャになるゴア表現。
など即物的でショッキングなシーンが多い一方で花をふんだんに使った装飾の瑞々しい美しさなど、もう少し描く角度を変えればめちゃくちゃオシャレな作品にも化けた気がする。
カルトノリが好みじゃない
まず登場人物が全員嫌いでした
濃厚メンヘラ女に薄情いい顔しいのごみ彼氏、それを囲むチル友のエリート学生
そこに漬け込むトラディッショナルカルト集団
濃厚メンヘラ女が1番気持ち悪くて大嫌い
きーきーうるさいし
後時間長くて無駄に引っ張りすぎなシーン多すぎ歌とか踊りとか
シーンのカットインもしつこいて
ってなる
稀に見る思わせぶりなクソ映画でした
「?」
まさにタイトル通りの作品。
まじで眠くなるし、ジャンルブレブレだし、気持ち悪いし、謎展開が多すぎる。
ある意味話題作にはなるかなとは思うけど、これを面白いと思える人とはちょっと相容れないかも。
恋愛もの?コメディ?ホラー?
結局なんなの?あれは。
つまらないとかっていう以前に、ずーーーっと不快感に苛まれ続けてた。
なんの音楽もなしの食事シーンとか、ずっと聞こえる赤ちゃんの鳴き声とか、グロいかと思えばエロ?なのかコメディ?みたいなのもある。
見ててずっと手汗が止まらんかった。それくらい不快。
なんか評価二分してるなぁとは思っていたが、見終えて逆に二分していることに驚いた。
こーれはひどい。
二度と見なくていいかな。
同じく見たくなくなった作品に「SEVEN」があるが、あれはまだストーリーが綿密に作り上げられており、ただそのストーリーがエグすぎて心が辛くなったのでもう見たくないなと思った。
ただこれに関してはそのストーリーすら意味不明の連続で、間延び(というか自分から見たら無駄な)するシーンも多いし、グロいのをわざわざドアップで見せつけてきたりとか、何がしたいのか全く意味がわからなかった。
ただただ不快でした。
私は何を見せられているのだ?
刺激的
兎に角、刺激的な映像が満載
田園風景に釣られてはいけない
ペアチケットで見た人の感想が気になる
これはかなり気まずい映画で
ラストも人を選ぶ仕様
一部界隈で高評価なので前々から見ようかな、とは思ってたけど
ウィッカーマン、グリーン・インフェルノ的な気配を感じ取って二の足を踏んでいた。
某配信者のウォッチパーティーでやってて、ちょうどいい機会だったので視聴
想像よりも、かなりのぶっとんだ映画だったが、ストーリーは個人的に予想可能な展開の範疇、食傷気味なので実況コメント見ながらじゃなかったら早送りしてた
閉鎖したコミュニティの気持ちの悪さ
古い儀式、風習
小道具の細かさ
画面の明るさと凄惨さ
行き過ぎレベルのゴア表現
映画の画面づくりはとても良かったが
シュールすぎて笑えてくるシーンが多すぎて、なんとも言えない気持ちにさせられた
ダイレクトホース
原形なくなるレベルの損傷
毛
アシストババア
干鰯、もしくは犬神家
ペラッペラ
着ぐるみ
家族、友達で見ると気まずい
ツッコミどころ満載でネットでやいのやいの言いながら見るのは楽しいが、地上波では絶対に見れないタイプの映画なので、ウォッチパーティで見れたのは良かった
長時間、生理的嫌悪感のある映像が多数
個人的にはあまり好きではないが
新しい映画の楽しみ方を知った作品だった
てっきりひと夏の青春ものだと思い、何も知らずに観てしまいました。実...
一周まわって良い映画
熊が焼かれるシーンのシュールさったら。
本気なのか冗談なのか曖昧なラインで進んでいくホラー。
いや、ホラーって言っていいのかな。
はっきりした悪意を持ってる登場人物は一人もいないのに
それでも進んでいく凄惨な事態っていう。
主人公・ダニーにとってはハッピーエンドなんだけど
”オズの魔法使い”よろしく旅の一行にとっては…。
先述のシュールさもあって初めは呆気にとられるけど
見た後も意識のどこかに引っ掛かり続けるのは確かだし
物語のいろんな側面も含めて、作りこみがしっかりした作品だ。
ひとつ圧倒的に説明不足だったと感じるのは”90年に一度”の部分。
それだけ盛大な祭なのは分かるんだけど、その頻度にしてはみんな慣れすぎてないか?と。
物語の根幹にかかわる部分だけに
そこは自己消化に任せるんじゃなく、ちゃんと説明して欲しかった。
ともあれ、テーマの掘り下げがしっかりした”作品”であることに変わりはない。
好きかどうかは置いといて、間違いなく良い映画だったと思う。
いい意味で悪趣味
〈郷に入れば郷に従え〉
主人公のダニーは、信じられないくらい悲しい事件が起こり、恋人のクリスチャンを頼りますが、クリスチャンは友人達に彼女は病気だなどと言われ、愛がどんどん冷めていきます。そんな折りに友人の内の一人に海外に誘われ、ダニーも一緒に異なる文化の北欧の村のコミュニティに参加します。そこで冒頭のシーンにあるような世界がひっくり返る経験をします。最初に違和感を感じる性的な描写や、後々の死に繋がっていく命の輪へのショッキングなシーンは、観る人を確実に選びます。ディレクターズカットシーンも観ましたが、子供を生贄に捧げるような描写があり、それは本当にハラハラしました。主人公とその彼氏は困惑しながらも、村の文化に対応していきますが、一部の理解できない外部の人間には最初は村の人たちも優しく諭しますが、やはり生きては帰れません。花が咲くように、命は巡るように生贄としての肉となります。後日、ダニーは村の女王を決める踊りで最後の一人となり、優勝します。彼女はその村の『女王』として、共同体の『家族』となります。一方、主人公の彼氏は、村の女の子に誘われ、裸の女性が何人も手を繋いでる儀式の場で、その子とまぐわいます。しかし、そのシーンをダニーは鍵穴から観てしまいました。すると、女王の使者の女性たちが激しく嗚咽する彼女と共に嗚咽し、泣くと泣き、女王と同じ『共感』をします。そのシーンは、優しさもありますが言葉にできない怖さがあります。後日、山の神に捧げる生贄が必要となります。その決定権は女王となったダニーです。命の循環のために命を捧げます。女王が最後に高らかに笑うシーンは圧巻です。徐々に適応していく主人公のダニーと、誘ってくれた友人の思惑と、女王としてダニーが席に着いた際の、草や花のまるで生きているような動き。このコミュニティでは毎日繰り返されているライフサイクルの仕組み。そのすべてが、悲しみのどん底にいた主人公のダニーを呼ぶ為のものだったのではないのかと思います。
「明るいホラー」という視点では面白い。グロシーンは苦手な人には厳しい。
アマプラにて視聴。
公開時に話題になってたから、軽い気持ちで見に行こうかなーと思ってたけど、グロは好きではないので劇場サイズで見なくて正解でした。
「明るいホラー」という、幽霊や怪奇現象ではない不気味さは面白かった。
でも不意打ちでグロをくらったらいやなので、先にネタバレを見てからそういうシーンになりそうなときは薄目で見ました笑
きっといろいろ伏線とか細かい描写とかあって何回も見るとより見方が変わってくるのかもしれないけど、何回も見るエネルギーはないなー。。何回も見たら慣れるのかもだけど。
グロ好きじゃないから、ミッサマに限らずストーリーは面白いと思うけど痛いシーンは好きじゃないって作品が結構あって(SAWとかCUBEとか)、グロカット版を出していただけるとありがたいです笑
同じアリ・アスター監督の「ヘレディタリー/継承」も心と時間に余裕があるときに見てみようかな。
(これも先にネタバレ見てからにしようかな…)
共鳴と依存
主人公のダニーは、家族を一気に亡くして彼氏のクリスチャンに依存している。妹の双極性障害のこともあってか、ダニー自身も精神が不安定で依存気質であり、本人もそれを自覚していて、苦悩しているようだった。
一方クリスチャンはそんなダニーを重荷に感じ始めていて、二人の関係に終わりが近づいているような雰囲気だが、別れる決心がつかずになんとも微妙な関係が続いている。
本当は男友達だけで論文のための研究(と羽目を外すこと)を目的に行くはずだったスウェーデンにダニーも一緒に行くことになり、それがまた絶妙に嫌な空気を醸し出しているので、これは恋愛映画とも言えると思う。そうして訪れたホルガ村で恐ろしいことが起こる、というお話。
主人公たちが訪れたホルガ村は小さなコミュニティで、メンバー同士の絆や先祖に対する尊敬が怖いくらい強く描かれている。印象的だったのは、相手が泣いたら無く、喚いたら喚く、苦しんでいたら苦しむ、というように、ホルガの人たちが感情を共鳴させていたこと。まさに一体となって、全身で感情を表していた。
この共鳴は、研究(私欲)のために禁忌を犯した者や、先祖に対する尊敬の気持ちを欠く者に対して牙をむく。それはそれは恐ろしいやり方で。
怖いと感じるシーンは宗教儀式に関するものばかりだったけれど、やはり所々「そうはならんやろ」と思うところはあった。痛みを感じない、と言われて飲んだ薬?が全然効いていなかったりして、それは薬物による幻覚なんて何の救いにもならない、という意味にも受け取れた。
ダニーは最初クリスチャンに依存していたけど、段々頼りにならなくなってきて、時折投げかけられるペレの言葉に少しずつ絆されて(いるように見えた)、なんだかんだでホルガに適応していく。多分ホルガ特有の共鳴がダニーの依存気質に作用していたんだと思う。
ラストは、ダニーの決断が潔いと感じる部分もありつつ、多分ペレと結ばれるのかな……ペレは実際ダニーに恋心みたいなものを感じていたのかな……と思った。
見ない方がいい、みたいなレビューも見受けられたけど(そしてそう言われると見たくなる不思議)、大人の精神力なら受け止め切れない残忍さでは無かったかな。あまり積極的に勧められない作品であることは事実ですが。
ギャグオカルトという新ジャンル
ギャグでしかない。とにかく爆笑であった笑
謎の公開セックスでは、盛り上げ役?達が喘ぎにチョイチョイ合いの手を入れてくるし、終盤に今更なモザイク入れ出したと思ったら、挙げ句ナマの熊の着ぐるみ着せられたり。え、なんで?www
他にもツッコミ所が満載で、アリ・アスターはもう完全に笑わせに来たとしか思えない。
新ジャンルに出会えたという感覚で楽しかった笑
レビュー
二作目のジンクス
つ…か…れ…た……。
観たいな観たいなと思っていた作品を、やっと鑑賞。
正直、終わって直ぐの感想としては「疲れた…」でしたね(笑)。
スウェーデン出身の学生が、休みを使ってスウェーデン旅行に行こうと友達を誘い、山奥(と言ってもかなり開けた場所)で、一見平和に暮らしているコミュニティの生活を体験することに。
しかし、そこでは目を覆うような儀式が行われていた…。
所謂…カルト教団ですよね。
このどうしょうもない友達を誘ったのも、ダニーを誘ったのも全て計画の上。
っていうか、崖から人が飛び降りて死んだのを見ても、死にきれずハンマーで頭部を潰されてたのを見ても 大して衝撃を受けた風でもなく…。
ロンドンから来たカップルの反応の方が真っ当かなと。
あそこのコミュニティで生活をしている人達は、どうやって来たんだろ…。
常に変な液体を飲まされて、明らかに全員がコントロールされてるって感じ。
彼氏のわいせつ行為を敢えて見せる辺り…確信犯でしょ。生贄ありきなんだよね。
だから、あのコミュニティは、人が意図的に作った悪の教団なんだな。私からしたら。
本人達は悪とは思ってないかも知れないけど。
最後に建物ごと焼き払うシーンで、これまた変な液体を口に含ませて…痛みを感じないとかなんとかやってたけど、結局は断末魔の叫びを上げながら死んでいくと…。
その時に初めて“あんなものは妄想だ”と気付いたと信じたい。
主人公のダニーも、色々と不審に思いながらも のめり込んでいく理由が良く解らなかった。
精神的に病んでいるし、家族もいなくなってしまったからだとしても…家族を失う辛さとか人一倍解る筈なのに、お年寄りが自殺に追い込まれて(あのおばあさんの顔は死にたくない顔だった(多分(笑))!)死ぬシーンを見ても、非情だとは思わなかったのかなと。
いくら薬物を盛られてるとしても、彼氏を生贄に選ぶ“正常さ”はあるのだから、………んー、あの異常な世界観に飲み込まれてしまったのかな…。
「へレディタリー/継承」も言う程 凄かったー!とは思わなかったし、この作品も駄作とまでは言わないけど、大して面白くもなかったかなーって。
なんか普通に感想を述べてしまった…(真面目かよ(笑))。
あまりに安っぽい
以前から気になっていたが、ネトフリに追加されたのでみてました。
うーん、、、なんだこれ?笑
いかにも、こういうの不気味でしょ?みたいなのが透けすぎてて、ちょっと冷めちゃう。
カルト集団があまりに安っぽい。しかも90年に一度なのになんでこんなに手慣れてるんだ???
サイコでもホラーでもなくて、ちょっとグロいブラックコメディって感じでした。
話題になってて期待してた分、がっかり笑
夢でダニーが置いて行かれたとこが一番怖かった笑
全633件中、181~200件目を表示