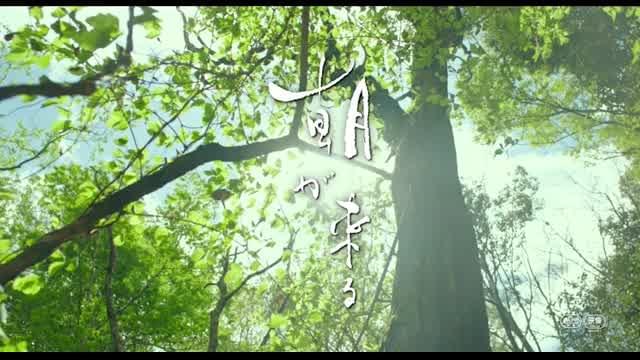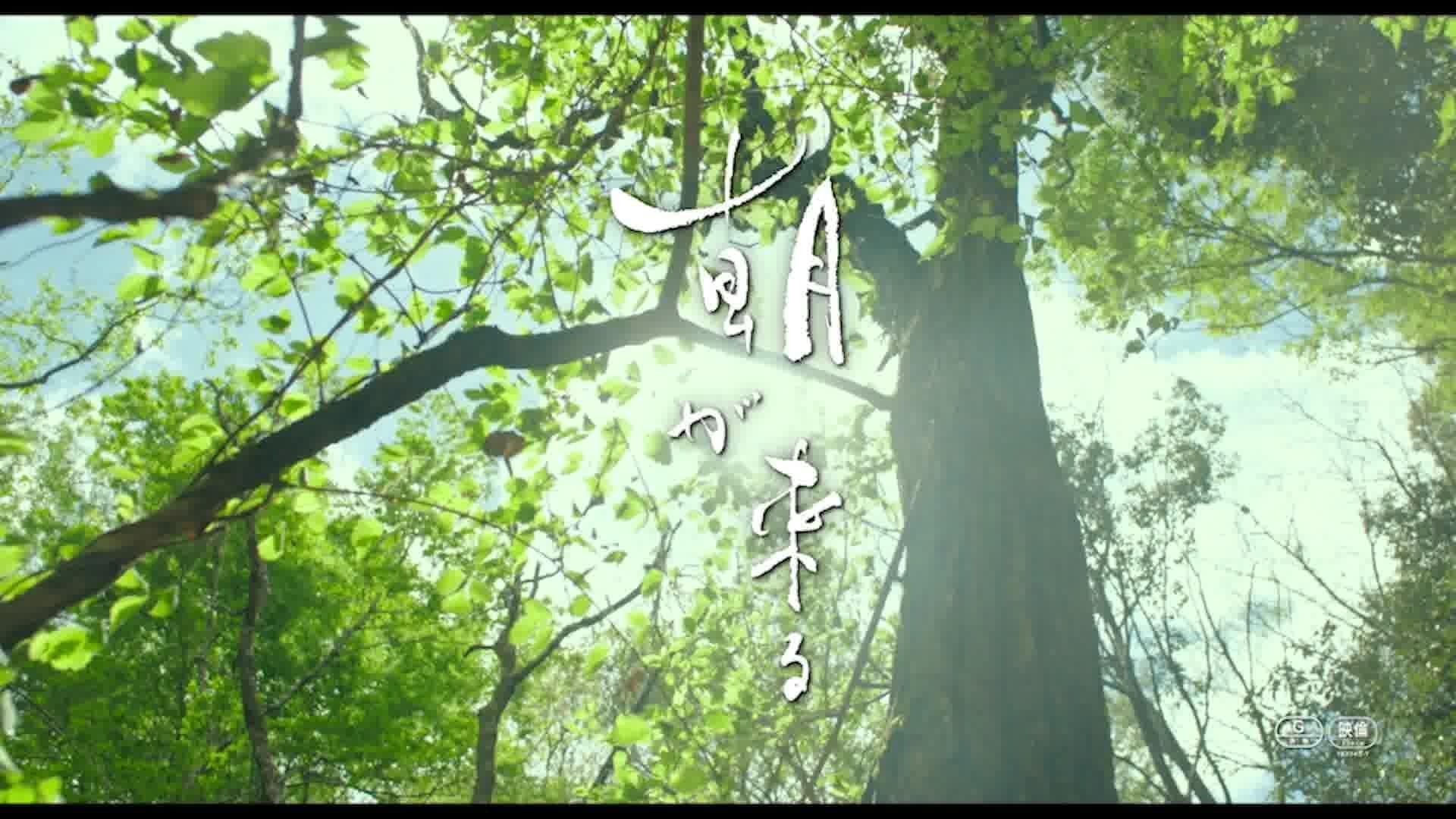朝が来るのレビュー・感想・評価
全212件中、61~80件目を表示
免罪符系ホラー
河瀬直美には、なんかがあるような気がしていた。
寡作な印象があるが、wikiページを見ると1992年から年一ペースで、映画をつくっている。すごいキャリア、かつ多作だと思う。
ただ、作風が地味なので、公開規模は狭かったと思われる。
カンヌをとった殯の森(2007)以降は注目されたが、おそらく大衆認知に至ったのはあん(2015)だと思われる。
あんにもその次の光(2017)にもお涙臭があった。
確実に「可哀想な主人公」で釣る作風だった。
あんや光は一杯のかけそばの「貧困」が、ハンセン病や盲目に変換されただけの話だった──と思う。
で、河瀬直美はなんかがあるひとではなく、たんにメロドラマの作家だと、個人的には認識した。
ただし、かつてはメロドラマが顕著ではなかった。
憶測に過ぎないが、アーティスティック(げいじゅつてき)な作風だったけど、大衆に下野する必要が生じて、──つまり、プロデューサーに「なんかもっと売れるもんつくってくれませんかねえ」と言われて、本来の姿「メロドラマ」が顕現した──のであろう。と思われる。
メロドラマの作家ならば、ザ日本映画の系譜にすんなり収まる。あんを見たとき「なあんだ、ふつうのザ日本映画の監督なのか」と思って、ある種ホッとした。
日本映画を見ていて思うのは、なぜエクスキューズするのかなってこと。
われわれ、大人は、現実世界で、同情を誘うような姿(人様から気の毒に思われてしまうような様子)を不特定多数に見せない。お恵みを乞う──意図がなければ。
ところが日本映画には、「わたしはかわいそうなんだぞ!」と絶叫しているような人たちばかりが出てくる。
お恵みを乞うているわけ。
たんじゅんに、同情を誘っているのですよ。
わかんないのかなあ。
にもまして、映画向きの、まことに好都合な不幸。小説(原作)ならば、暴れない筋書きが、映像になったことで突飛な話になっている──気がした。
登場人物は「むしろそんなところに嵌まる方がむずかしいんじゃね」──と言わざるを得ないような、トクベツに特殊でトクベツにお誂え(おあつらえ)でやたら強引な「可哀想さ」のある状況に陥っています。その(逆)御都合主義。不幸がなけりゃ、わざわざ探し出して、自らそこに入りこんじゃう人たちです。
また、なかったことにしないでって字があらわれる部分が社会派から探偵小説に飛んじゃったみたいで、ムリ感が半端なかった。
さらに大仰。シンプルに客観視するなら、たんに子供ができないってだけの夫婦だよね。そりゃ当人にしてみれば、悲しいことだろうさ。だけどな~んか仰々しい悲嘆が鼻につく。にんげん、四六時中、シリアスな局面で生きてるわけじゃない。適当に気を抜いたり笑ったりもするさ。絵にリアルはあるけど、人物像はリアルじゃない。
また永作さんの見た目が、やつれ感を強調しているのだろうけれど、あまりにも野暮。この人、演技がうまいのか、わたしには解らないが、おばさん(にしか見えないひと)を、これでもかというほど近接でとらえていて、ひたすら辟易した。これは容姿ではなく、絵のもんだい。
たとえば、是枝監督はリアリティに寄せるけれど、役者選定はかなり面食いをする。海街も他の映画もリアリティも追及するけれど前提にきれいな役者を使うわけ。つまりリアルなのはいいけれど、見にくい絵は、やはり見にくい──という話。
(ホラー映画で人物の表情を近接にとらえて皺や陰影を強調して醜悪に見せる手法(HereditaryのトニコレットやMilly Shapiroみたいな)があるけれど、この映画は、ほとんどそれに近かった。それが誤算度きわまりなく、案外ホラー映画と言っても差し支えない。──とわりとまじで思った。)
不憫・哀れっぽい・痛々しい、ひたすら気が滅入る話。田舎者の感性。いつもながら空間のリアリティだけは、ある。が、ありえねえって思えるコテコテの不幸をムリムリに設定して、しれっと免罪符にしちゃってる映画。ださい作風です。0点。
自分には合わなかったのかも
起きることは決してTVのニュースにはならない事件。出てくる人は全員...
朝が来ることを信じて
いつまでも余韻の残る素晴らしい映画。
それぞれの置かれた辛い、困難な状況の中でどう対応し、どう声に出して自分を伝えていくのか、思わず声に出してしまうのか。
思いのまま人を傷つける人たちが周りにいる中で、真摯に向き合う主人公役の永作博美。そしてもう一人の若い女性の蒔田彩珠。二人の表現力にはとてつもなく心に残った。
葛藤の中の不安、恐れ、本当に真実の心から言葉が発せられている。声、表情、リアリティさに脱帽した。
自分だったらどうするのか。どう接したらいいのか。問われている感じがした。真実のドキュメンタリー映画を見ているようだった。2時間強の映画だったが、ずっと緊張が続き目が離せなかった。
何が正しい選択になるのか。
最初の頃に出てくる夫役の井浦新の「この家には親になれる人がいる。」「家族をつくりたい。」のセリフは、この映画、また現実の世界に生きる夫婦、家族にとって、心の奥底に持ち続けなければならない言葉だと強く印象に残った。
河瀨直美監督の作品は過去いくつか見たが、今回がベストで、私が近年見た映画の中でもいつまでも余韻の残る素晴らしい映画であった。
で?その後は?
辻村深月さん本当に好きです
中・高校生にも観て欲しい
今年一番響きました
最後はちょっと…ズルい気がする。
魂が揺さぶられる名作!
久し振りに魂が揺さぶられるような思いのする映画に出会えた。
特別養子縁組制度について、子どもを差し出す側とその子どもを受け入れ育てる側の双方の心情が丁寧に描かれている。
不妊治療など苦労してようやく子どもを授かった親、子どもが欲しくても様々な事情から断念した夫婦、流産や中絶を経験している女性…そういう人たちにとってかなりセンセーショナルなストーリーだと思う。
俳優陣も永作博美、井浦新ともに期待を裏切らない演技。そもそも「八日目の蝉」で同じように複雑な立場の母親役を好演した永作を観るのが目的だったのだが、実際は蒔田彩珠の演技に釘付けになった。また一人凄い女優が出てきたと思う。さすが尾野真千子を見出した河瀨直美監督!と唸った。
ラストはきれいごとに終わっている感があり、現実はもっと厳しいと批判的な意見もたくさんあるようだが、僕は希望の持てるエンディングに納得し安堵し、そして涙が出た。
人生において子どもを育てるということとは
子育ては本当に大変なことで偉業である。人はなぜそこまでして子どもを生み育てるのか。
娯楽に溢れ、家族を持つことイコール幸せではなくなった現代に、その価値を問う物語。
河瀬直美監督の“役積み”により感情変化をじっくり丁寧に撮った作品。永作博美の悲壮感漂う演技が素晴らしい。
養子縁組など実際の当事者に話をしてもらったかのようなドキュメンタリータッチの演出で、以前の『光』を彷彿とさせる。
幸せのために子どもを生んだのに子育てに疲弊する家族という病のニュースや映画を最近よく見るが、子どもを持てることがどれだけ尊いことか、命の重さを改めて痛感させられる。
森林の描写は、自然は誰の子孫だとか関係なく全体で育んでいく象徴だからだろうか。
あらすじとしては、「子どもができない夫婦が養子をもらい幸せに暮らしていたある日、本当の母親が現れる」と簡単に言い表わせてしまうものだが、お互いの人生をそれぞれの視点から描きながら、それらが交わっていく時間軸を行き来しながら最後まで謎も引っ張る見事な構成。
子を持つ親としては、要所要所で涙腺を持っていかれた。
全212件中、61~80件目を表示