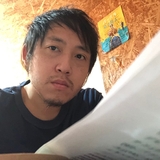燃ゆる女の肖像のレビュー・感想・評価
全171件中、141~160件目を表示
写真もない時代に肖像を描くということ
予備知識ほとんどなく観賞
こういうフランス映画もたまにはいいじゃないか的ノリです
感想としては
・シンプルでテーマは絞りやすい構成
・音楽がほぼなく集中力維持が大変
・目力ある女優さんの演技に惹き込まれる
・凝ったカメラワーク
色々賞をもらったというほどのインパクトは
感じないもののなかなか印象的な作品でした
18世紀のフランスで婚約の肖像画を任され
孤島にやってきた女流画家マリアンヌ
自殺した姉にもショックを受けている令嬢エロイーズに
最初は目的を悟られぬよう接しながら
少しずつ肖像画を描き上げますが肝心の本人に
出来を認めてもらえず
もう一度描き直す中でエロイーズは肖像画を描く
事を了承します
エロイーズは婚約を望んでおらず状況を少しずつ
理解しながら交流を進め距離を縮めるごとに二人は
(当時としては)禁断の愛に目覚めていきます
エロイーズがそもそも婚姻を嫌がっている理由が
それだったかは定かではありませんが
肖像画を描くという行為が相手を知りどんな人物かを
理解し一枚の絵から人物像が浮き出るよう描き上げる事で
それがきっかけで愛が芽生えてしまったわけです
マリアンヌの製作は捗りますが徐々に花嫁姿の
エロイーズが浮かんでは消えその絵の完成が
何を意味するかをマリアンヌも感じ取っていきます
そして自他ともに納得のいく肖像画が完成したところで
マリアンヌはエロイーズが嫁いで別れなければ
ならない事がつらいとつい吐露してしまいますが
エロイーズは突き放すマリアンヌに失望し
悲しみにくれますがやはり状況的にかなわぬ恋
途中出てきた有名なギリシャ神話のオルフェウスの
冥府下りになぞらえ別れ際の「振り返ってはいけない」
約束に対しマリアンヌはやはり振り返り
花嫁衣裳のエロイーズを一瞬視界に入れ
それ以降しばらく会うことはなくなります
その後マリアンヌは一度目は子供と一緒に絵画として
出会うことになりますがエロイーズの手には
自分の絵を残した本のページが記されており
もう一度オペラで会ったときには目も合わせることは
ありませんでしたがその眼には一筋の涙が伝うのでした
LGBTがどうとかといった話は一切抜きにして
素直にストレートな純愛ストーリーだったと思います
写真のない時代の肖像画というものの意味
音楽がほとんどなく集中力というか眠気が襲ってくる
部分もあるにはありますが頑張って観てみると
色々感じ取れていい作品でした
女たちの心を解き放つ
ジェンダーフリーの風潮のせいか、このところ邦画でも洋画でも同性愛の作品が多く上映されているように感じる。最近では「おっさんずラブ」というテレビドラマまであった。映画では2016年に鑑賞した「アデル、ブルーは熱い色」が最も印象に残っている。その4日前に観たのが邦画の「リップヴァンウィンクルの花嫁」だ。黒木華の演技に舌を巻いた記憶がある。
同性愛は太古の昔からあって珍しいものではない。古代ギリシアでは同性愛が当たり前だったという説があり、カエサルはバイセクシャルで、映画「テルマエ・ロマエ」で市村正親が演じたハドリアヌス帝は同性愛者という話だ。日本では在原業平は老若男女何でも来いだったようだし、江戸時代は男色が日常的だったらしい。
いつからか、同性愛は生殖を伴わない性行為として、キリスト教によって禁止されたり、または国家によっては法律で禁止されたりした。しかし聖職者が実は少年愛者で沢山の少年が児童虐待の被害にあったという「グレース・オブ・ゴッド 告発の時」みたいな映画もあったりする。
人間の性は個性と同じように、古来から多様なのである。フェチやマニアという言葉には沢山の接頭語がつく。性的な快楽は人それぞれであり、故に相性というものがある。相性のいい相手、言い換えれば同じフェチ、同じマニアであれば性的な快楽は増大し、そうでなければマイナスになる。人が浮気したり離婚したりする理由の「性格の不一致」は主に「性の不一致」なのだ。だから少し前まで結婚式の挨拶では「昼は淑女のように、夜は娼婦のように」という言葉が使われていた。多分いまの結婚式で使うと炎上必至の言葉だが、真実を衝いている言葉であることは間違いない。
国家という共同体の中の個人は、国家に守られている従順な羊の群れで、共同体が何かを禁止したら、それを悪いことだと思ってしまう傾向にある。精神的な自由を投げ出してしまうのだ。日本の男色や浮気を悪と定めて一夫一婦制を導入したのは明治の国家主義者である福沢諭吉たちである。ちなみに国家主義とは国家に主権があるとする考え方で、国民に主権があるとする民主主義とは正反対である。ナチスも国家主義だ。明治維新の国家主義者たちは、国の労働力や兵力を増強するため人口増加策として一夫一婦制を提唱したのであって、国民の幸福を願った訳ではない。
さて従順な日本国民は国家主義者の横暴に従い、一夫一婦制に背く行為を悪としてしまった。同性愛についても一部のマニアックな人の特有のものとして限定的な扱いを受けるようになったのである。「LGBTは生産性がない」という発言をしたのも国家主義者の国会議員だ。浮気が不倫として咎められるようになったのは人類の歴史で言えばごく最近の話なのである。民主主義国家は個性の多様性を認めるわけで、同時に性の多様性も人権として認めなければならない。
民主主義国家フランスには不倫という言葉はない。ミッテラン大統領の浮気や隠し子の報道があっても、それによって大統領が責められることはなく、逆に報道したマスコミの方が「プライベートに立ち入るのはよくない」と非難された。フランスの人々は性の多様性を認め、人間が物や人に飽きることも認めているのだ。
新しいものは誰しも試したくなるが、思い切って試す人と怖気づいて我慢する人がいる。我慢する人は試す人が許せない。不自由な人は自由な人が許せないのだ。他人の浮気を非難する人の心理はそれで、つまりは不寛容で狭量な精神性である。嫉妬や羨望もある。日本ではそういう精神性が支配的だ。だから浮気した有名人が、違法行為でもないし国民に迷惑をかけている訳でもないのに謝罪を強要される。非難する人たちの精神性はほぼ国家主義のネトウヨたちと同じである。日本に民主主義は根付いていないのだ。
本作品はフランス映画である。だから性の多様性が広く認められているという前提の上で作られていると思う。本サイトの解説によると、主人公の相手役となるエロイーズを演じたアデル・エネルは本作品の監督セリーヌ・シアマと交際しているそうだ。レズビアン監督が交際相手の女優を出演させてレズビアン映画を撮るのが普通の時代になったのは、古代の性に対する自由な精神を取り戻したようで、喜ばしい限りである。本作品の美しいレズビアンシーンを非難する人はいないだろう。
18世紀のフランスと言えば、1789年7月14日の市民によるバスチーユ監獄の襲撃事件が有名で、そこからフランス革命がはじまった。本作品はおそらくそれよりもかなり前の話で、貴族による封建主義の支配体制が残っており、女性の権利は認められていない。女性画家は男性を描くことが出来なかったり親が決めた相手と結婚しなければならなかったりする。
殆ど二人芝居のような映画で、互いの会話やアップで映される表情には、性衝動や人格のせめぎ合いや諦めや運命を受け入れる覚悟みたいなものが混ざりあったような、複雑な意識と感情が見て取れる。主人公の画家マリアンヌを演じたノエミ・メルランは、力強い目を存分に生かして繊細な女心を演じきった。対するエロイーズを演じたアデル・エネルは、主演映画「午後8時の訪問者」で見せた冷静さよりも、はじめて胸がときめいた性的な衝動と快楽、それに別れの予感に心が揺り動かされる感情を前面に出して、相手役としての存在感を十分に発揮した。両女優ともに見事である。
こんな時代をこんなふうに生きた女たちがいたという実存的な表現であり、冷たい潮風や固いパンや暖炉の熱が、あたかもその場にいるように感じられた。カメラワークも音響も秀逸だ。世界を実感するためにマリアンヌは絵を描き、アデルは海に入る。歌う女たちのシーンは素晴らしい。焚き火の向こうで火のついたドレスを気にせずすくっと立つアデルが印象的だ。そして音楽。女たちの心を解き放つのは自然と恋と芸術なのだ。ヴィヴァルディの「四季」は名曲だと、あらためて思った。
叶わぬ恋
18世紀フランスの離島を舞台に、望まない結婚を控えた貴族の娘と、彼女の肖像を描くために雇われた女性画家の、生涯一度の恋を描いたラブストーリー。脚本と監督は、思春期の少女の欲望と不安を題材にした「水の中のつぼみ」で注目されたセリーヌ・シアマ。今回も、女性監督ならではの繊細な心理描写を光らせ、昨年のカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した。
この映画の背景は、女性が思いどおりに生きられない時代。貴族の娘、エロイーズには結婚の選択権がなく、画家という職業を得たマリアンヌも好きに画材を選べない。そんな二人が、5日間だけ思い通りに笑い、愛し合う自由を手にする。そして、その思い出だけを糧に残りの人生を生きる。限りなくロマンチックで、限りなく切ない恋が、マリアンヌの芸術家のまなざしで切り取られていく。そんな恋物語を、ある逸話や切ないラストシーンを奏でる音色と共に物語全般を通しての演出が見事でした。
最初に思ったのは?
役者の芝居はとてもよく、お嬢さん役の俳優の目線だけで伏線をはるところ(回収も、とてもわかりやすくてよい)や表情の変化だけで語るところなど、なかなかやるなと思わせてくれる。
半面、些細なことが気にかかる。
海を渡るのに白いキャンバスを貼った状態で梱包して持っていくものなんだろうかというのがまず気になる。ロールと木枠を持って行って現地で張ったらいいじゃない。
木炭でやけに精密な下書きを描いて、その線を大切に消さないように塗り絵をしていくという必要以上に形を大事にするような描き方にテーマとの違和感を覚えつつも、ここまで薄塗りなら、こんな粗目のキャンバスじゃなく板に書いたほうが良いのでは?という疑問に・・・(もともと、板に描く設定をキャンバスに書き直してるなら辻褄があうなあ)
そもそも、貴族の肖像画がこのクォリティで許されるのか?などと考えつつみてると、なんとダメだしされて描きなおすはめに・・・
途中の状態を撮れば、発注する絵は1枚で済むからなのか?
肖像画は重要なアイテムなのでもう少し金かけてよかったんじゃないのかなあ?
などとホントに余計なことを考えてしまった。
退屈な美
私的には、テンポが合わないかな
本作品、予告編で見た時、絵にまつわるサスペンス映画なんだろうと勝手にイメージして見に来ましたが・・・・
私の勝手なイメージだったので、正直裏切られまいた・・・・
色々と見方はひとそれぞれあるでしょうが、私的には、合わない映画・・・
内容の方もあるような無いような・・・・お話が大変にゆっくり淡々と進むので、私的にはついて行くのがやっと・・・・
簡単に内容を話ば、お金持ちの娘の縁談の為に、肖像画を書く依頼を受けた画家が、対象となる女性と向かい合っているうちに、恋愛と言うのとは違い、互いを知る事による親近感を超えた想いと言うのですかね、男性同士で有れば、また表現は変わってくるのですが、女性同士なら、このような展開になるんでしょうね・・・
しかし、その感情変化などが、本作品のテンポや作り方で、私的には、その変化の過程が掴みにくいかな・・・
景色み綺麗だし、出てくる女優さんも大変に綺麗ですが、私的には、少し合わない映画だったかな・・・
自分は繊細ではないし女性でもないのだが・・・
「こんなにも繊細な作品は観たことがない」(グザヴィエ・ドラン)だそうだ。
「そうか、自分は繊細ではないし、LGBTでもないし、女性でもないのだから、理解できないのだ」と、何度も居眠りしながら観ていた。実に眠かった。
「きっと観る人が観れば、交わされた台詞やちょっとした仕草の背後に、微妙なニュアンスや秘めた情熱を感じ取るのだろう」と。
主人公の持ち込んだ2枚のカンバスが、イントロで強調され、その後の展開を暗示するなど、“芸が細かい”のは確かだ。
ところが、映画の終わり近くなって急展開し、話が怪しくなる。
二人の情熱は燃え上がるものの、実は互いのことはあまり理解し合っているわけではなかったようなのだ。
つまり、台詞や仕草には、別に深い意味は無かったということになる。
たかだか2週間くらいの間に、エロイーズが笑うようになり、「私も変わった」などと平然と言い放っているのを聞くと、「はぁ?」となってしまう。
少なくとも、肖像画の消された最初のバージョンの表情と、採用された最後のバージョンの表情は、逆であるべきではないだろうか?
まあ、最初のバージョンはクライアントのご機嫌を取るために、定型的に仕上げたのかもしれないが・・・。
映画のキモであるはずの肖像画そのものに、意味内容が感じられなかったのは残念だ。
どうも最近は、ジェンダーや人種が絡むと、ヨーロッパでの評価は“自動的に”高くなるのではないか?
「パラサイト」同様、カンヌの“ご威光で”過大評価されているような気がする。
こんな奇妙な状況が続くと、映画界にもトランプ大統領のような人間が現れても不思議ではない。
ともかく、徹底的に“女性目線”で、ほとんど男が出てこない本作品は、自分には難しすぎた。
なお、昔のブルターニュの田舎と言えば、ゴーギャンの絵にもあるように、少しエキゾチックな土地柄のはずだ。
火祭りの女達の合唱は、現地で採取した歌かは知らないが、民俗性が反映されているのかもしれない。
絵画のような美しい映像から見える怖さ
とにかく全てのシーンが美しく、抒情的。
波の音、暗い部屋、ろうそくの灯り、お祭りでの合唱。
18世紀のブリュターニュの孤島が舞台とのことだが、映像の美しさに圧倒される。
この時代の女性は、結婚して子供を産む道具でしかなかったのだろう。
主人公の女性も結婚はしないのかもしれないが、画家として、自分の名前で描くことはできず、父の名前で描いていたというところも驚く。
というより、女性が仕事を持って、自分の好きな人と結婚する自由を得ることができるようになったのも、まだ100年も経っていいないんじゃないか。
もっというなら、LGBTを公言できるようになったのだって、30年も経っていないと思う。
たぶん、本当に許されない愛、だったんだと思う。
その儚さと人を好きになるのにジェンダーは関係ないという燃えるような思いが、全編から痛いほど伝わってくる。
素晴らしいエモーショナルムービー
素晴らしい。もう『野菊の墓』(松田聖子主演)です。完全なる切ない恋愛。まあ絵描きの話くらいにしか思わず観に行ったのだが(笑)、アニエスヴァルダのような古典映画の快楽を持った現代映画。アデル、ブルー…も思い出した。
荒涼たる風景の、しかし壁の色、波の色、草木も光も絵画的な隔離された屋敷に、絵描きと嫁入り前の娘が肖像画を描くまで暮らす。その間に起こる魂の交換と原始的な恋愛のはじまり。狙いに狙ったバックショットが美しい。出会いの海辺の振り向きと、別れ間際の波打ち際の後ろ姿と。
ミニマルに攻めていって中盤ようやく音楽が加わり、ラストで一気に雪崩れ込む感情のピーク。オルフェのエピソードにもはっとさせられた。
音楽も説明も極力削ぎ落として語るモノとは。
期待したほどの濃厚なレズビアン場面もなくて個人的にはがっかりだが・・・
この作品、女性監督のセリーヌ・シアマとダブル主演のエロイーズ役のアデル・エネルがほんまもんのレズビアンカップルで付き合っているということで、大いに期待しておりました。「英雄は嘘がお好き」「不実な女と官能詩人」のノエミ・メルランの美しい裸体が惜しげもなく見られると思い、期待しておりましたが、その点では完全に裏切られて、チクビさえ見られませんでした。私と同様に邪な鑑賞動機の輩はさぞ肩透かしを喰らった感でありましょう。
しかしながら、冒頭のボートのシーン、海に落ちたカンバスをみずから飛びこんで拾うシーンはわざと濡れて暖炉の前での全裸シーンのためのもの。船に乗ったまま引き上げればいいのにね。ありがとうございました。
エロイーズ役のアデル・エネルは顔の輪郭や口元が石橋静河に似ており、二重瞼がきれいで、長いカットが多かったです。監督の強い思い入れを感じました。
素朴な祭りでの女たちの歌うアカペラの曲がエンドロールでもかかり、この作品の独特な雰囲気を感じることができました。
女中のソフィ役のルアナ・バイラミも魅力的で、3人の関係も面白かったです。とくに、ソフィの妊娠が発覚して3人が流産の手助けをするシーンが結構長く、面白かったです。浜辺で3人が草を探すシーンでは、花が枯れてはだめだとか言う会話がありまして、花に毒のある堕胎に使える植物があるのかな?タイの地方の豪族の一夫多妻を描いた映画(題名忘れた)を思い出しました。エロイーズの母親(女主人)が戻って来るまでにオロす必要があるらしく、相手はたぶんほっそりした若い下男だと思われました。ソフィはなかなかチャーミングで、堕胎を村の女性に頼んだすぐあとにそのシーンを再現したポーズをソフィとエロイーズにさせて、ひと作品描きあげるシーンも印象的でした。当時の女流画家はエロチックな絵は描いてはいけない風潮があり、テーマも男性画家に比べ極端に限られるとマリアンヌ(ノエミ・メルラン)自身がエロイーズに言う場面があったので、3人がマリアンヌの創作を応援していることがわかりました。オルフェィスとエウリデケのギリシャ神話を読むシーンは最後の二人の別れのメタファとなっており、28ページの余白にマリアンヌが描いた自画像をエロイーズが大事にしていたことがのちの絵画博覧会でのエロイーズと娘の絵にも表されています。娘の顔がなんとなく、マリアンヌに似ておりました。画家に注文をつけたのでしょう。最後の方で、別れを受け入れながらも、互いにいつ好意を感じたか聞き合う場面は二人が充分に愛を確かめあったあとだけにとてもいいシーンでした。エロイーズがマリアンヌが経験者であることに興味を示したときに、マリアンヌはこれはイケると思ったと告白するのですが、エッチだなぁと感心しました。最後はオペラの会場でマリアンヌはエロイーズを見かけますが、エロイーズがマリアンヌに気が付かないのかどうかわからないまま、ただただ泣いて終わるのが大変よろしかったです。
女優も映像も美しいが
切ない恋愛ストーリー(女同士だけど)
賞を取ってるから、どんな映画だろうと楽しみだった。それ以上の事前情報ほ無しで鑑賞したら、主人公の女性(画家をしている)がモデルの女性とキスして愛し合ってしまった( ̄▽ ̄;)
こんな展開だと思ってなくて、私のようなおっさんが鑑賞してるのは大丈夫かなと周りの目が気になった。
ざっくり言うと、主人公(マリアンヌ)とモデルのエロイーズが恋に落ち、だが別れなければならないと言う切ない映画だった。
この映画の登場人物はかなり少ないので予算はかけて無さそうだ。主人公(マリアンヌ)と貴族の娘エロイーズ、その母、貴族の使用人ソフィの4人がメインだ。母は途中からいなくなるけれど、この4人で話が進んでいく。
恋愛と言っても、男性が好きな裸のシーンは殆ど無い。(全くない訳では無い)
主人公(マリアンヌ)を演じるノエミ・メルランの誕生日は1988年11月27日なので、30代だと思うけど、キレイだった。ちょっとカルロス・ゴーンに似てるなと思った。やっぱり、フランス人の顔立ちということなのだろう。ノエミ・メルランは脱いでいる。冒頭の濡れた衣類を乾かすため暖炉の前で暖を取るシーンと、生理になった時にベッドから起き上がるシーン。暖炉の前のシーンではほとんど影になっているから胸の形が見える位でハッキリと裸は見えない。生理の時はアンダーヘアが見えたくらい。モザイクをしないのはフランス映画って感じだ。
貴族の娘エロイーズを演じたのはアデル・エネル。1989年1月1日生まれなので、こちらも30代。これからミラノの男性とお見合い結婚することが決まっていて、恋愛経験も無いようだったからもっと若い役だと思っていた。裸になるシーンはあった。マリアンヌと一緒にベッドの上にいて寝てる時に、左胸が露出していた。あと、脇毛が生えていた。これは当時のフランスでは当たり前なのかもしれない。
あとは裸のシーンはない。
使用人のソフィ役のルアナ・バイラミは2001年3月14日うまれ。未成年であるが、映画では妊娠してしまい、堕胎している。彼女が堕胎するシーンでは、対比するように隣には赤ちゃんと小さい子供がいた。子供を堕ろす行為はソフィにとっても辛いようで、泣いていた。
なぜ、マリアンヌとエロイーズが恋に落ちたのかは私には分からなかった。エロイーズの肖像画を作る使命を与えられたマリアンヌが映画の中盤で肖像画を完成させてしまったから、あれ?これからどうするの?と思っていたら、突然エロイーズとキスして、いつの間にか愛し合っていた。もしかしたらそういう空気が出てたのかもしれないが、私は気付かなかった。
最後のシーン(マリアンヌとエロイーズが別れてから最後に再開するシーン)ではエロイーズがオーケストラの演奏を聴きながら涙を流すのだが、これは多分マリアンヌのことを思い出したからだと思う。マリアンヌが肖像画を描いていた頃にエロイーズに演奏するシーンがあって、きっと同じ音楽だと思う。だからエロイーズはマリアンヌを思い出して泣いたと解釈した。このシーンはずっとエロイーズが映るのだが、役者の実力が無いと成立しないと思った。
映画の中で、純白のドレスを着ているエロイーズがふっと消えるシーンが2度ほどあるが、それが何を意味していたかは分からなかった。
マリアンヌが屋敷から出ていくシーンは悲しいシーンだった。
以下、ストーリー
マリアンヌは学生の前でポーズを取りながら、学生に指導をしている。学生の後ろに『燃ゆる女の肖像』というタイトルの絵が飾られていることに気付く。自身の作品だ。学生に問うと奥から出てきたとのこと。
過去に遡り、マリアンヌは小型の船に乗って島の貴族の屋敷へ向かう。船での移動中に絵画道具を海に落としてしまったのでマリアンヌは海に入って取りに行く。上陸し屋敷まで行くと、マリアンヌは部屋の暖炉の前で衣類を乾かしながらタバコを窘める。
屋敷では屋敷の主(主人の妻でエロイーズの母。主人の姿は無い。)から娘のエロイーズの肖像画を描いて欲しいと依頼される。肖像画をお見合いで使用するためだ。エロイーズの肖像画を描こうとしたことは過去にあるが、エロイーズが拒否して描かせて貰えないそう。このため、マリアンヌは自身が画家であることと、エロイーズの肖像画を描こうとしていることを隠しながらエロイーズの肖像画を描くことになる。
マリアンヌはエロイーズと散歩することにする。しかしエロイーズはマリアンヌの前を歩いたりして、なかなか顔を見せてもらえない。また、マリアンヌがエロイーズに視線を送ることも、気付かれてしまいそうで危うい。
エロイーズには姉がいたが、崖から落ちて死んでいる。転落時に叫ばなかったこと、エロイーズ宛の手紙に『許して』と書いてあったので、自殺と考えられている。
マリアンヌはエロイーズの目を盗みながら、エロイーズの肖像画を書き上げるが、エロイーズの母にエロイーズに肖像画を描いていたことを打ち明けたいと言う。
マリアンヌはエロイーズに肖像画を描いていたことを打ち明け、肖像画をエロイーズに見せる。エロイーズは肖像画の出来に否定的だ。マリアンヌも納得していなかったようで、肖像画の顔のところを削除してしまう。エロイーズの母はマリアンヌに怒るが、エロイーズがモデルになることを承諾し、母は5日間の外出から帰ってきた時には肖像画を完成させているように再び依頼をする。
マリアンヌはエロイーズを描きながら?、突如エロイーズとキスをする。(正確には覚えていない)。これから母が戻ってくるまで二人は愛し合うことになる。
ある夜、集会(何の集会か分からないが、何人かの女性が集まって歌を歌う)で、火を挟んでマリアンヌとエロイーズは見つめ合う。するとエロイーズのスカートに火がついた。エロイーズは慌てる様子もなく、マリアンヌを見つめているが、他の女性がすぐ様、消化した。
一方で使用人ソフィは自身が妊娠したことをマリアンヌとエロイーズに告白する。子供をどうするか尋ねられると、エロイーズの母がいない間に堕胎すると応える。
ソフィは堕胎する時にベッドの上で寝転ぶが、同じベッドの上には、赤子と小さな子がいた。堕胎中はマリアンヌとエロイーズはその様子を見ていた。医師?が堕胎を終えたことを告げると、ソフィは涙を流した。
夜、エロイーズは堕胎中の絵を描くようにマリアンヌに提案する。暖炉の前にマットを引き、ソフィを横にしエロイーズは堕胎のポーズを取る。その姿をマリアンヌは絵に描いた。
ソフィから明朝の朝、エロイーズの母が戻ってくると聞かされたマリアンヌは最後の夜もエロイーズと過ごす。母は肖像画を見て報酬をマリアンヌに手渡す。
マリアンヌは二人と別れて屋敷を後にする。
再び、教室に場面転換する。マリアンヌは学生の絵を見る。
マリアンヌは父の名前で展覧会に作品を出品する。当時のフランスでは女性画家には例えば男性の裸体が描けないと言った制約があるため、父の名前を使用している。
展覧会にはエロイーズがモデルとなった絵が飾られている。エロイーズの傍には小さい子供が描かれている。
マリアンヌはオーケストラの会場に入ると遠くにエロイーズが会場に入ってきたことを視認するが、エロイーズは気付かなかった。(または、気付いていたが、顔を向けなかった。)オーケストラの演奏が始まると、エロイーズは涙を流した。
なんか観いってる
視線と表情で描く究極の恋愛表現!!
まだ限られた職業でしか、女性は社会に居場所を見出すことができなかった時代の中で、多くの女性が社会進出のきっかけとなったのが画家という職業でもあったことから、マリアンヌは18世紀のフェミニストでもあるのだ。
しかし、固定され、限られた概念の中では、まだまだその先に進むということは、未知の領域であり、人間として、女性として許される行為なのかということも判断が難しい環境だった。
時代を通してみれば、同性愛というものは、18世紀以前から存在していたものではあるのだが、芸術や歴史の中で知っていることと、自分の身に起きることでは、全く違ってくるだろう。
マリアンヌはフェミニストではあっても、少なくともエロイーズと出会うまでは、異性を愛し結婚をすることへの反発はあったものの、レズビアンではなかったように思えるし、そもそもその概念自体がマリアンヌの中には存在してなかった。
それがエロイーズと出会い、肖像画を完成させようと、表情や仕草のひとつひとつを観察するうちに、マリアンヌの中に何かが芽生えてくることが伝わってくる。その伝え方というのが、映画的でわかりやすい表現などによるものではなく、マリアンヌとエロイーズの視線や表情からなのだ。
そこには、女性同意の恋愛を描いているという表面上的なものではなく、人間が人間を愛する瞬間を絵画のように、詩のように、美しい景色をキャンバスにみたてて描いていくのである。
手が触れるかもしれない、唇が触れるかもしれないという緊張と恐怖、愛を交わす喜びが自然と口元に現れる。
細かい視線や表情だけで、どうしてここまで人を愛すること、愛の誕生の表現が可能なのかというと、勿論、今までにも女性同士の恋の芽生えを描き、自身がレズビアンでもある監督のセリーヌ・シアマや撮影のクレール・マトンの力、そして俳優達の演技力もそうなのだが、監督とエロイーズ役のアデル・エネルは、かつて実生活において、恋愛関係にあった間柄なのである。
本編でみせるマリアンヌの眼差しは、正に監督自身の眼差しでもあるのと同時に、アデルの目線も監督を見る眼差しなのである。
結果的に別々の道を歩むことになり、別れてしまった2人にとって、肖像画を描き終えることは、愛に終わりがくるという、マリアンヌとエロイーズの心情に重なるというメタファーともなっているのだ。
美しい景色と、優しい波や風の音が凄く心地よい作品でもあることから、寝不足では観ないことをおすすめしたい。視覚、聴覚的にかなり眠気を誘われる作品である。
全171件中、141~160件目を表示