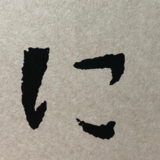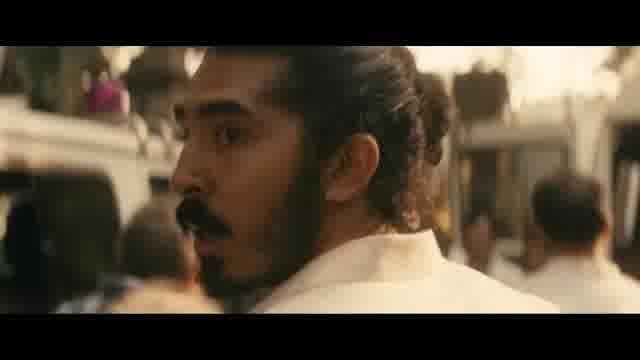ホテル・ムンバイのレビュー・感想・評価
全210件中、141~160件目を表示
恐怖の時間を目撃
123分の上映時間があっという間。それくらい無駄のないストーリー展開、緊張とスリルに満ちた場面の連続。スクリーンに釘付けだった。
宿泊客たち、そして彼らを守ろうと決意するホテルマンたちの行動にスポットを当て、一応、テロリストの少年たちの止ん事無き事情にも触れつつ、でも許されることのない行為の行く末、恐ろしい時間をスクリーンを通じて共有させられた。
様々な国の宿泊客数十人を一堂に集めた状態で、それを統率することなんてほぼ不可能。それぞれがそれぞれの考え方を持っているし、優れた指揮者がいるわけでもなく、ホテルのスタッフの言うことについて、自分の方が正しい、自分の思うように行動したい、そういう考えを持つ人は当然出てくる。勝手な行動は見ていて歯がゆくもやむを得ない。が、それゆえ危険にさらされるリスクも。
直ちに救出される可能性も薄く希望も持てない、困難極まる状況下でも決して諦めることなく宿泊客を守ろうとするホテルマンたちの心には胸を打たれる。
それほど昔ではない2008年。インドで実際にあったこの事件は記憶になかったが、本当に恐ろしい映像体験をした。最後は涙溢れて止まらない。
悲劇すぎるが過度なヒーロー劇でなくとても響く
ものすごい緊張感
今年、観るべき映画の一本だと思います!!
こんな悲惨で衝撃的な事件だったとは!(◎_◎;)
終始自分も宿泊客になったかのような緊迫感と臨場感が凄まじ過ぎて固まってしまうほどマジに恐怖を感じました。
アカデミー賞獲るんちゃう!?
間違いなく今年、観るべき映画の一本だと思います!!
職務を全うするホテルマンの勇気に敬意を表すると共に犠牲者の方々のご冥福をお祈りします。
☆4.6
実話と思いたくない作品
とにかく観てるのが辛かったです
でもこうやってこのテロ事件を知る事ができる観るべき作品でした
余計な音がなく、ホテルの中に放り込まれたように感じる緊張感がラストまで続きます
淡々と人を銃で撃つまだ若いテロリストたちですが、彼らの背景も描かれているので、自分たちで判断ができない操られている彼らも被害者なのだと思えます
彼らが言う「神のために」、ホテルの従業員の人たちが言う「お客様は神様です」、同じ神のために戦う対比が、さらにテロリストの彼らを悲しく思わせられました
特殊部隊がなかなか来ない広大なインド、ずっと「お願い、助かって」と思いながら観ていました
ハリウッドのアクション映画のようにヒーローがあっという間に悪者をやっつけて一件落着にならない現実、このテロ事件でのヒーローたちはごく普通に働く普通の人々、エンドクレジットの前のテロップには涙でした
犠牲になるかもしれない覚悟で宿泊客を助けた従業員の人たち、実際に犠牲になった従業員の人たち、そんな立派な人たちのためにも世界で二度とこんな事が起こらない事を願うばかりです
救いようのない問題
高級ホテルは従業員も高級だった
十年ちょっと前に、インドのムンバイで起きたテロ事件を題材にした作品だそうです(ムンバイってどこだよ、と思ったら、ボンベイのことだった)。
実話ベースですが、そうでなくとも、サスペンスの佳作として見て損はありません。
そして、サスペンス的なハラハラドキドキの他にも、見どころは山盛りです。利用客のために逃げずに残ったホテルマン、ずるい大人に利用されている実行犯の少年たち、テロリストとは一緒にされたくないムスリムの女性などなど。
映画では分かりにくかったけど、タージマハル・ホテルでの犠牲者は、利用客よりも従業員のほうが多かったそうです。ここは強調すべき点だったと思います。上司から「逃げても責めない」と言われた従業員たちが残ると宣言する場面は、胸が熱くなりました。
ちなみに、その場面で「Guest is god.」と言っていました。「お客様は神様です」なんて言うのは日本人だけかと思っていたので驚いたのですが、あとで調べたら、インドには昔からある(三波春夫も生まれていない、はるか昔からあった)概念のようで、二度びっくりでした。
今年暫定一位
迫力感動の連続
生々しい…。
ホテル・ムンバイの戦士たち
今月オススメの映画のひとつ
アーミー・ハマーが(TДT)
リアル
勇気と希望をいただきました
テロは他人事ではない!
平和ボケしてる自分が鑑賞中かなり衝撃を受けた作品。
見る前はホテルルワンダみたいなイメージ。
ポスターの青年がテロの中、大活躍する映画な印象だったが見事に裏切られた。
主役や、ヒーローはいない。危険なテロの中誇りを持って逃げずにお客を優先する姿に心を打たれた。
たくさんのホテルマンが犠牲になったようで、ご冥福をお祈りします。
この映画のよいところはテロリストの人間性が強くでていて元々貧しい少年達が家族の為やアラーの神様の為と言う大人の口車に乗せられてしまっているであろうところまで描かれていたところ。決して感情移入はできないが貧しい少年達が一つの強い決意で起こした行動はたくさんの犠牲者をうみ、戦争中の日本も天皇を神として同じような感じだったのかな?と少し思った。
1つ気になったのは、劇中でてくるアメリカ人とインド人のカップルの旦那。
行動は全てが裏目にでてますよ!!
赤ちゃん連れて右往左往。
あっさり捕まり、死亡フラグを自ら立てていく
うーん悪手。
タージマハルホテル、一度は泊まってみたいですね。
YouTubeみて平和ボケしてる日本人の皆様にみてもらいたいです。
なんてったってもうすぐオリンピックですからね。
世界でこんなテロがあったってことは記憶しててほしいと感じさせられました。
戦いを挑むことだけが勇敢ではない
悲劇が起きないことを祈る
この同時多発テロの約10年前、僕は、このタージマハル・パレス・ホテルに宿泊したことがある。
伝統や歴史、格式のあるホテルで、サービスもきめ細かく、相当、優越感に浸ることが出来る場所だ。
歓迎で懸けてもらう花輪の黄色の花はマリーゴールドで、ヒンドゥー教の神様に捧げられる縁起の良い花で、宿泊客の旅の安全を祈る意味もあるように教えてもらった。
こうしたこともあって、このテロのことはよく記憶している。
英領インドから独立したヒンドゥー教徒多住国のインドと、イスラム教徒多住国のパキスタンは、カシミールの帰属や、バングラデシュの独立を巡って数度にわたり軍事衝突を起こしている。今でも、カシミールのコントロール・ラインと呼ばれる付近では、小競り合いが絶えない。
このような背景で、観光客であふれるムンバイがイスラム教原理主義のテロ組織の標的になったのではないかと考えられているが、やはり、テロは悲劇でしかない。
ケサリというインド映画でシク教徒の勇猛さや優しさを知ったばかりだったが、この映画でもシク教徒のアルジュンは、優しく勇敢で冷静でもあった。
だが、宿泊客や、これを守ろうとしたホテル・スタッフの多くの命が失われた。
正直、次々に人の命が奪われる場面は目を背けたくなった。
動き回るな、強がるな、冷静になれよと声もかけたくなった。
以前より、テロの数は少なくなり、規模も小さくなったような気がする反面、宗教的組織的なものから、個人的なテロは増えているような気がする。ニュージーランドのイスラム教徒をターゲットにしたものもそうだ。
テロや戦争は一方方向ではないのだ。
この映画は事実を元に作られたものであるからこそ、多くのイスラム教徒は善良で、テロなど望んでいないのだということを頭の片隅に入れて欲しい。
今日、フランシスコ・ローマ法王が、カトリック教会の「世界移民・難民の日」に寄せ、自国以外で繰り広げられる戦争のために兵器を製造する国々が、その戦いから逃れてきた難民の受け入れを拒否していると非難したとのニュースを目にした。
ローマ法王は移民と難民の擁護を自らの姿勢の中核に据えて、トランプ米大統領や欧州の反移民議員らとしばしば対立している。
僕は、多くの人に世界中で起きてる争いの原因を客観的に理解してもらいたいと願う。
亡くなった方たちに哀悼の意を、生き残ったホテル・スタッフの勇気に敬意を表すと同時に、テロの悲劇が二度と起きないように祈りたい。
全210件中、141~160件目を表示