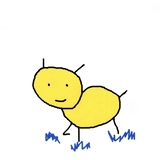ペトルーニャに祝福をのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
最初の一歩を踏み出したヒロインの祝福されるべき衝動
あらゆるドラマは意志と衝動によって生まれる。この映画のヒロインも日々の暮らしで様々な抑圧を受ける中、内側に秘めたものを徐々に膨張させ、マケドニアの小さな町に暮らすあらゆる人々が目撃しているであろう伝統行事の最も大切な瞬間に、つい炸裂させてしまう。この行為の意味を彼女が理解するのはだいぶ経ってからで、私はこの瞬間、ペトルーニャのことがどこか50年代のアメリカで白人にバスの席を譲るのを拒否した歴史的女性、ローザ・パークスのようにも見えた。きっとパークスがそんな行為に出たのも理屈を超えた意志と衝動がきっかけだったのではないか。それによって歴史はうねり、染み付いた悪しき常識はものの見事に覆っていく。本作はその最初の第一歩を、時にコミカルに、そしていつしか笑いを通り越しシリアスへと振り切れるくらいピンポイントに描きこんでいく。彼女のどんどん度胸が座っていく態度、表情、まなざしに興味が尽きない一作だ。
良作すぎる
ペトルーニャ最初は理屈ばっかりのめんどくさい女、友だちにも気分次第で悪態ついたりしてまあ最悪。こんな嫌な空気が続くのかしらと思っていたら事件とも言えない事件が起こり、母親や警察署長の常識一点張りで全然理論的じゃない主張にすっかりペトルーニャ頑張れーってなりますよね。ムダにジェンダー意識の強いリポーターやとにかく事なかれ主義の同僚カメラマン、ネオナチか?とも思うほどのおそらく教養も学もない生まれ育った街から出たこともないいわゆるヤカラ、別にこの事件自体はなんとも思ってないけどとにかく穏便に済ませたい神父、キャラクターの重量、配置が完ぺきです。いよいよペトルーニャに味方したくなる。そして何よりダルコが「連絡するよ」って言ってくれたの心の底から嬉しかった〜!ねーペトルーニャそりゃニヤつくよ。そして一件落着。だってホントは十字架なんてどうでもいいんだから信仰心ないし。あー面白かった。
【”伝統への固執は進歩を阻む。”保守的思想が蔓延る北マケドニアで実際に起きた男性のみの伝統儀式に女性が参加し”幸せの十字架”を手にした事から起こった出来事をアイロニック&ユーモアを塗して描いた作品。】
■北マケドニアの小さな町で暮らす32歳のペトルーニャは、仕事も恋人もなく、鬱々と日々を過ごしていた。
就職面接でも冷たくあしらわれ、最悪な気分の帰り道、ペトルーニャはキリストの洗礼を祝う神現祭に遭遇し、女人禁制の祭事に参加してしまうが、見事に”幸せの十字架”を手に入れるが・・。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・32歳のペトルーニャは、外見がポッチャリした可愛らしく、歴史にも通じた聡明な女性だが、縫製工場での秘書の面接で、面接官の男から相手にもされない。
ー 最近見た「金の国 水の国」で描かれた愚かしきルッキズムを思い出す。-
・そして、彼女はむしゃくしゃしていたのか、帰り道に女人禁制の祭事に参加し、川に飛び込み見事に”幸せの十字架”を手に入れる・・、が。
ー ここからの、警察や司祭や十字架を手に入れられなかった男達の愚かしき姿が、シニカルに描かれる。
“アバズレなどと,言われながら・・。”そんな中、ペトルーニャは臆する事無く、目をしっかりと見開き対応する。芯の強い女性である事が分かる。ー
■女性リポーターは上司と思われる男と電話で”これは大事な事だから”と必死に取材を続ける。
・そんな彼女に、男性警官のダルコだけが、優しい。そして、彼は言う。”僕も君みたいに勇気があれば・・。”その言葉を聞き、涙を流すペトルーニャ。
<ラストも良い。漸く解放されたペトルーニャに司祭が掛けた言葉”祝福を・・”。それを聞いて、ペトルーニャは司祭に十字架を返す。
彼女は、”幸せの十字架”が欲しかったのではない。
彼女は、女性としての尊厳を認めて欲しかっただけなのである。
保守的思想が蔓延る国で、自らの意思を貫き通したペトルーニャの姿は尊い、と私は思った。>
私は秘書希望です
「聖なる十字架」を勝ち取り、「一番福」となった彼女のこれからは?
本作の主人公は学歴もあり、聡明なアラサー女性だが、
世間体ばかり気にする「毒母」や世間の風習、世の男たちのメンツとデリカシーの無さなどに翻弄され、人生の行き詰まりを感じている。
ある日、某世界三大宗教の女子禁制の儀式に主人公は無許可でやけっぱちで参加。
そして、その一年幸福が約束されるとされる「聖なる十字架」を手にし、その場から逃走する。
もちろん、この彼女の行動は、教会・宗教・マスコミを
巻き込んだちょっとした騒動となる。
ただ幸せになりたい女性、
伝統を守りたい教会、
どう対処していいか混乱する警察、
この騒動を利用して虐げられている女性たちの代弁者となりたい女性リポーター、
儀式に参加した信心深いのか敬虔な信者なのか疑わしい男性たち....
登場人物は主人公を含めて卑しい奴らばかりだ。
(そこがこの作品の良さであり、人間社会のリアルを包み隠さず描いている)
私はどちらかといえば、フェミニストというよりはマスキュリストだ。
だから、この女性がこの後どうなろうが知ったこっちゃない。
したがって、祝福はできそうにもないが、
それでもどうか一年といわず幸せを感じられる人間になってほしいと願った。
マケドニアまで行かなくても灯台もと暗しヨ~(笑)
なんだかよくわかんないけど、村の習慣はもやもやしているなぁ
自分たちが何かにとらわれているとか、住民は知るつもりも無くて。
昔からの雰囲気で、女には自粛と“わきまえ”を求めるのね。
同様に雰囲気的に、男たちには“女性を支配する日常”が求められているの。
正教会の宗教者だって村社会の長(おさ)として2000年やってるし、
「眞子様問題」はずいぶんと尾を引いているけれど、皇国でも「祝福の十字架」は男系の占有物だし、
眞子様を叩いて足を引っ張るのは圧倒的に同性の女たち。
陸の孤島マケドニアと、海の孤島の日本はよくまあこんなに似ているなぁ、という鑑賞後感だった。
(そういえば、看護婦さんが土俵=男の聖地に登って大騒ぎになった事件を思い出した)。
ペトルーニャ本人が「ジェンダーフリー」とかは分かってなくて、後先考えぬ衝動的なのがとっーても愉快で、僕は好きだ。
友だちになりたいタイプ。
マケドニアから届いたフェミニスト映画
最初のくだりで、毎年行われる西宮神社の副男を思い出しました。日本にも同じような行事がありますね。はっきりとした根拠や理由はないけれど、「女性は土俵に上ってはいけない」的な女人禁制の行事や習慣や伝統があります。
面接でのセクハラ&パワハラシーン。男性は知らない世界かもしれないけれど、私も同じような質問をされたし、日常的に起こっています。暴力的でいやらしい質問をしつこくされたペトルーニャは、退席しようとした。内心は仕事がほしいはず。でもこうした理不尽な行為に毅然とした対応をする彼女に賞賛と尊敬の思いでいっぱいです。私なら、抗議できずに我慢してしまう。あるいは愛想笑いでやり過ごす。日本女性は長らくこうして過ごしてきすぎたのかもしれません。
警察の尋問でもペトルーニャの知的レベルの高さが表れています。本来、これは違法行為という訳ではなく、逮捕できる案件ではないはず。手を変え品を変え繰り出される警察官や神父の説得や脅しにも屈せず切り返し、相手はぐうの音も出ません。
いい意味でADHDなのかな?と思わせる落ち着きのなさや「空気を読まない」姿勢が、彼女をこうした大胆な行動に出させたのでしょう。
ところでラストで、ペトルーニャがあっさり十字架を返したのはなぜだったのでしょうか。
神父が彼女にも「幸運を」と声をかけてくれたことで、頑なだった心が溶けたからなのか。または警官とのラブロマンスの予感で、すでに幸運は手にしたからだったのか(笑)。軽~いラストに少々拍子抜けしてひっくり返りそうになりました。
面白かった。
最初は現地の女性軽視の抑圧を打ち破る女性の話かと思っていたらぜんぜん違った。
お父さんも、若い警察官も、地元の司祭も、近所のおっちゃんも別に女性を軽くは見ていない。
確かに女性を軽視する暴力的な輩たちや、女性軽視という概念に凝り固まった記者は出てくるが、この人たちは同じ穴のムジナで、規定に凝り固まって進歩がない偏った人種として描かれている(記者は自分の欲望のために家族を壊し仕事仲間も失っていく)。
デブで引きこもりの冴えないペトルーニャは十字架を取ったが、依存的な母親や頭の固い警官や脅してくる署長に尋問に反発する中でどんどん本来の自分を取り戻す。目には確かな知性の光が宿り、言葉はいっそう理知的になっていく。それを見て若い警察官や司祭や検察官は彼女は正しいとの答えに達する。
これはペトルーニャが自分自身のアイデンティティを取り戻し自立する物語だ。
自分には力がある、自分は素晴らしい人間なんだと再確認できた彼女は(大学はオールAの成績だから元は賢い女性なのだ)そうなるともう十字架などというお守りはいらない。
このお守りは、現実を切り開き幸せを掴む力のない哀れな者たちのためにあるのだ、と最後は十字架を司祭に返す。
なんだか全てに納得のいく物語で自分にはとても面白かった。
(若い警官とのラブはちょっと唐突だったけど。)
伝統対進歩でなく、自己存在を問う物語
北マケドニア版 #Me Too ? 毒親との決別物語か?
たとえば、関西の正月の風物詩・西宮神社の通称「福男選び」。一等賞が実は女子だとわかったら、令和の日本でもきっと同じ騒動になるんだろうな。でも普通わざわざ女子は参加しない。受けるダメージの方が大きいことが予想されるから。ペトルーニャもそうだった。きっかけはあくまでも偶然。本人も言っていた。自分は動物と同じことをしただけど。その日の朝には、過保護で保守的で近所の目を気にするお母さんに出された朝食をベッドの中で食してしまう程度のダメ子だった。
賽が投げられた後は、どこの国にもいそうな自己顕示欲の強い「頑張り屋さん」の女性レポーターの手にかかる。本件は「進歩を妨げる伝統への固執」を徹底的に糾弾する物語へと進化を遂げる。ペトルーニャも本領発揮した。当たり前のことを主張して、毒親へのきついジャッジを下した後、抱きしめた。賢い32歳だから。小さなロマンスにも恵まれ、アップの顔立ちがどんどん美形であることが強調されてきた。
ストーリー展開はちょっと冗長だった。
コメディじゃないよ。
逮捕?
いいぞペトルーニャ!
状況を超越する精神性の獲得
主人公ペトルーニャを演じた女優の演技が凄すぎて、映画が始まると同時にグッと引き込まれた。主人公に感情移入すると、上映中ずっと怒りと悲しみと恐怖の感情に揺さぶられっぱなしだ。
ペトルーニャの自由な精神性に対し、住んでいるシュティプという土地の精神性は封建主義であり、ギリシャ正教を強制する女性差別主義である。その代表選手がペトルーニャの母親というのだから、救われない。大学で歴史を学び、世界を科学的に客観的に評価することを学んだペトルーニャだが、母親の硬直した精神は溶かしようがない。
北マケドニアでも女性はご多分に漏れず容姿で評価されるというか、差別される。容姿のいい女性がいい仕事にありつき、キャリアを積むことができる。頭がよくても容姿がいまひとつのペトルーニャは仕事のキャリアがなく、キャリアがないことで面接で落とされる。
なんとも理不尽な出だしだが、帰り道で出くわした宗教イベントで、ペトルーニャの状況が一変する。男たちが真っ先に取ろうとして争う十字架を、タイミングよく川に飛び込んで取ってしまったのだ。女は取ってはいけない規則だと、ペトルーニャは土地のスクエアな精神性によってたかって責められる。その一番手は勿論ペトルーニャの母親だ。
敢えなく警察署に連行されてしまうペトルーニャだが、ここから彼女の頭のよさが発揮される。周囲にいるのは警察署長、司祭、それに十字架を女から取り返そうとする頭の悪い凶暴な男たち。ハリウッド映画であれば目に見える派手な解決場面を用意するだろう。フェミニストの団体が大挙してシュティプに押し寄せてペトルーニャを男たちから救い出すとか、または狂気のテロリストが、男たちをマシンガンで皆殺しにするとかだ。
しかしそんなことをすれば、その場ではペトルーニャの気は晴れるかもしれないが、明日からもシュティプで生きていかねばならないことを考えると、なんの解決にもならないことがわかる。フェミニストらしきテレビの女性レポーターは奮闘していたが、彼女の上司はスクエアな側だ。マスコミには何も変えられないことは、ペトルーニャには端からわかっていた。
本作品では、ペトルーニャの人生観や世界観が少しずつ広がっていく様子が伝わってくる。苦しい状況に置かれながらも、怒りや悲しみをコントロールし、徐々に恐怖を克服していく。司祭の身勝手な要求や警察署長の短気で愚かな質問を柳に風と受け流し、鋭い質問を浴びせて逆に彼らを追い込んでいく。
スクエアな状況が変わることがないのであれば、そんな状況を気にしないで超越して生きていく精神性を獲得するまでだ。短時間で波乱万丈の経験をしたペトルーニャは、すっかり成長してもはや怖いものがない。もちろん神など存在しないから、十字架にご利益などない。
頭のいいペトルーニャには感心したが、シュティプにも北マケドニアにも絶対に行きたくないと思ってしまった。
観る角度を変えて、上げた拳の下ろし所を考える作品だとしましょう。
以前に「岩波ホール」での予告編を観てから、なんとなく興味のあったのとタイミングも合ったので鑑賞しました。
で、感想はと言うと、ツッコミどころはそれなりと言うか、結構あってw、ちょっと変わってる。
でも観る角度を少し変えるとなんか気になる感じな作品。
北マケドニアの小さな町、シュティプに暮らす32歳のペトルーニャは、美人でもなく、太めの体型で恋人もおらず、大学で歴史を歴史を専攻していたが、卒業後も仕事は無く、無職の日々を過ごす。
ある日、叔母から紹介を受けた面接でも、セクハラを受けたうえに不採用になってしまう。
その帰り道、むしゃくしゃしたペトルーニャは地元の伝統儀式に遭遇する。
司祭が川に投げ入れた十字架を男たちが追いかけ、手に入れた者には幸せが訪れるというもので、ペトルーニャは思わず川に飛び込み十字架を手にするが、女人禁制の儀式に参加したことで男たちから猛反発を受けてしまう。だが最初に手にした十字架の事実はニュースで流れ、事件は大騒動へと発展する…と言うのが大まかなあらすじ。
マケドニアとなかなか馴染みの薄い国の作品で国の情勢などに関しての知識が少ないんですが、昔で言うところのユーゴスラビアでギリシャの隣との事。国の経済状況はあまり良くない感じ。
そんな経済的に余裕の無い国の三十路の太めのオバちゃんが、何を思ったか、男性限定の福男祭りに乱入して掻き乱す映画w
まず、大いなるツッコミどころとしては、思わず男性のみの伝統儀式に何故参加したのか?と言う点。それも思いついた様に突然w
これって、兵庫県の西宮神社で毎年行われる「十日戎開門神事福男選び」に突然乱入して、女性が一番にゴールするみたいなものかなと。
まあ「十日戎開門神事福男選び」は「福男」と明記されてますが、女性も参加できるんですがw
普通に考えたら、参加資格が無いのに何の準備もなく、フラッと現れて、フラッと川に飛び込み、十字架を手にして「私のもんだ!」と言われたら、「そりゃ周りは怒るわな」となりますわなw
まさしくそこが1番のツッコミどころで、あとはご乱心の如く、頑なに「これは私のものだ」と固辞する。
固辞したくなる気持ちも分かるが、突然乱入しての参加で横からかっさらうのってどうなんですかね?
また、女性レポーターが入って、この事件を大々的に取り上げ様とするが、周りもそんなに関心は無いし、そんなに広がらない。
女性リポーターの「女性蔑視」論だけが空回りしている感じ。
教会の牧師と言うか事を穏便に収めようとする教会側の意見の食い違いに統制が取れていない。挙げ句の果てに意見がコロコロ変わるから、ヤキモキと言うか、「お前本当に宗教者か?」と疑いたくなるぐらいに神に対しての思想思考が感じられない。
だから観ていても「なんだかな〜」な気分になるw
そんな感じの人達ばかりで、良い奴は皆無に近いし、事件らしい事件も無いから展開も薄い。100分と上映時間もなんか中弛みがする感じ。
じゃあ、全くダメか?と言うと個人的にはそうでもないw
「上げた拳の下ろし方」と言うか、不本意に張ってしまった意地をどう緩めるかに注目するとなんとなく面白いんですよね。
ペトルーニャにしたら、周りに祝福される訳でもないし、そんなに欲しい物でもないw
言うなれば、オークションでライバルと競り合って、意地で競り落としたが、ふと我に返ると「…これ、そんなに欲しかったっけ?」と言う感じw
周りは暇かどうかは置いといてw、ある程度の福男伝統儀式にそれなりに賭けていたので、横からかっさらわれたら「こんちくしょー!」となっても致し方無しだけど、これも拳の下ろし方を何処かで考えていたとしても、未だに男尊女卑が根強く残るお国柄だけになかなか難しいが、周りの反応が冷ややかなのは「正直、それどころではない」と言うくらいに経済不況の方が深刻。
なので、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」とばかりな感じな訳w
でも、周りの人達はペトルーニャの行為を「悪魔の所業」とばかりに避難する。
それも一番エキサイトしてる様に見えるのは実の母親w
そりゃあ、ペトルーニャも意固地になるわなw
でも、ダウンした母親にサッカーボールキックはあきまへんw
なので、ラストのオチもあっさりと言えばあっさり。
でも、上げた拳の下ろし方とすれば、タイミングとしては「ここでしょうね」と言うぐらいなんですよね。
…雪が降った景色を見ると、今までのわだかまりを全てを覆いつくして、ペトルーニャの心も洗い流す様に包み込んだ…と言うと綺麗にまとめ過ぎですねw
個人的にはレポーターとペトルーニャの問題の認識の温度差や、警察の不当逮捕的な拘束や警官同士の共有の不一致。
警察署前での暴動的な行為の見逃しや、友人女性の手のひら返し、面接での意味不明なセクハラと父親の草食っぷり。
そして、ペトルーニャの寝ている際の何故かのオッパイ描写と面接を受けた後に怒りのあまりに持ち帰ったマネキンの方が不本意にも気になりますw
また、ペトルーニャが大学出のインテリな筈なのに、その片鱗が見えない事や共感しにくい不美人な感じ(個人の好みによる)が、徐々になんとなく綺麗に見えていくマジック的な方が不思議。
また、警察署の取調室みたいな部屋の壁がジャングルの奥地の様な壁紙の方が不思議ですw
と、色々と?が付く感じの不思議な作品で、ペトルーニャの意固地になる程の意地は自身の置かれた立場からの逆襲と虐げられてきた怒りなんですよね。
母親にすら自身を信じてもらえない境遇と女性蔑視の数々。
「私は大学で歴史を学んできたインテリやぞ!」と言う声は別に強く秘書になりたかった訳でもない。でもお針子さんになりたい訳でもない。
とりあえず就職が出来れば良いが、下手なインテリが邪魔してるばかりにタチが悪いんですよねw
いろんな部分で見ている側も共感出来たり出来なかったりと慌ただしい作品ですが、マケドニアの作品と言う事も含めて、なんか珍しい作品で客観的に見た「上げた拳の下ろし方」を標準的に教えてくれる作品かなとw
凄く、お勧めな感じではありませんし、観た人の殆どが「是か非か?」なら多分非w
なので、あくまでも個人的な一意見と捉えてくれれば幸いですw
全23件中、1~20件目を表示