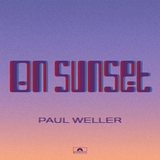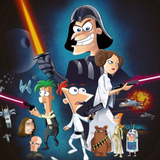ちいさな独裁者のレビュー・感想・評価
全64件中、41~60件目を表示
文句なしの傑作
権威とは何か。何によって担保されているのか。当方と同じく気の弱い一般人が畏れる権威や権力が、実は薄氷の上に建っている砂の楼閣かもしれないと思わせる映画である。
兎に角主人公の奸計が凄い。軍隊はヒエラルキーの組織だから上官の権威はほぼ絶対である。最上位の権威はハイル・ヒトラーでおなじみの総統だから、総統の名前を出せば大抵のことは通せる。首相案件という呼び方で国の基本である資料や統計を捻じ曲げる極東の小国にそっくりだ。
権威を証明するものは何かというと、これが意外に難しい。もしかしたら上級将校の軍服だけでも権威を得られるかもしれないというのがこの作品の設定である。必ずしもその人物が何かに優れている必要はない。権威に相応しい威圧的な態度や、横柄な言葉遣いがあれば、権威と認められることがある。
ナチスは役人でできた組織である。役人の基本は昔から自己保身と既得権益への執着だ。それは恐怖心の裏返しでもある。つまり、役人が権威と権力に従うのは恐怖心のためだ。もっと言えば、権威や権力は人々の恐怖心の上にかろうじて支えられているのだ。
主人公はナチスという官僚機構のそんな構造を知ってか知らずか、修羅場をくぐってきた老練な詐欺師のように、軍服ひとつで権威を獲得していく。最初は主人公の嘘がいつバレるかと思いながら観ているが、そのうちにナチスドイツという巨大組織そのものが、ハリボテの巨大な人形のように思えてくる。こんな嘘のかたまりが世界大戦を始めたのかと愕然とする思いだ。そしてそれを支えたのがドイツ人の恐怖であり、保身であり、既得権益への執着であったと考えると、同じことが世界各地で起きていることにも気がつく。現代にナチスがいたらチンピラに過ぎないが、それが虚構に膨れ上がると戦争を起こしてしまう可能性を持っている。人間はどこまでも小さく、そして愚かであることを改めて突きつけられた気がする。
全編にわたって綱渡りを観ているかのような緊迫感があり、目の覚める映像や衝撃的なシーンもふんだんに鏤められている。日本語訳詞の「さらばさらばわが友♪」ではじまるドイツ民謡が歌われるシーンでは、その歌が「わかれ」というタイトルだけに、いろいろな比喩を想像させる。最期の字幕で主人公のモデルとなった実在の人物の年齢を知って心底驚いた。文句なしの傑作である。
愚痴
人の壊れる音
胸くそ悪い
ちいさな独裁、大きな迷惑
昔、お坊さんが法事に呼ばれました。古びた袈裟で赴くと、今日は大事な法要があるから、托鉢に付き合う暇ないと、追い返されました。今度は豪華な法衣をまとい再訪。すると、丁重に奥座敷へ。そこでお坊さん、法衣を上座に供えつつ、皆さんが招待したのは、この法衣のようですな。ささ、よく拝みなされと言い残し、去ったそうです。この日、招待されたのは、晩年の一休さん。細川たかしも、びっくりな頓知話ですね。
問題だらけの映画ですが、最大の問題は、エンドロール。我々は、あの時代より、少しでも進化したのかと、問われているようです。満席近い劇場の御見物も、結構、引いてました。
指導者は、大きな嘘をつけ!。群衆は、大きな嘘に酔い痴れ、小さな嘘は見抜く…。(誰の迷言かは、探してね。)を、地でいくような話。ヒトを騙す方も問題ですが、嘘と知りながら、彼を利用する輩も問題です。
戦争の負の遺産と云えば、それまでですが、劇場でドン引きされた御見物の皆さんも、何かそれ以外に思い当たることが、あったのでは?。法と秩序を濫用する輩には、ご用心。
内なる残虐性
ゴヤの絵のように悪魔的に美しい映画だった。
第2次世界大戦の終戦間近のドイツ。敗戦が濃厚になったナチスドイツ軍では脱走兵が後を絶たず兵士達による略奪が行われていた。
脱走兵のヴェリー・ヘロルトは命からがら逃げている途中で軍用車両に打ち捨てられたナチス将校の制服を見つける。
その制服を着ることでヘロルトは大尉として扱われ、暴君へと変わっていく。
嘘のような本当の話。
このヴェリー・ヘロルトは実在の人物。
しかも最悪な事に劇中で起こる脱走兵の収容所の虐殺も本当の話。
なぜ20歳のあどけなさも抜けない青年がこんな凶行を行なったのか?
本人のサイコ的資質が戦争という時代にマッチしたんだと言えば簡単だけれど、私はどんな人でも何かのきっかけがあれば暴走すると思っている。
それを冷静に受け止め、本気で止める人がいない限りにおいて。
ヘロルトは軍を脱走するくらいだから弱い人間だと思う。だから弱い人に寄り添えるかと言うとそうではない。
理想もなく、自己保身が一番で自分さえ良ければいい。
私も含め誰しもそうだと思う。
この映画は戦争映画では無く、人は自分の都合のためにどう振る舞うかを描いている。
だから普遍的でどんな話にも当てはまる。
自己掲示欲の強い人たちが声高に叫ぶ世界で、私達はこの物語を直視しなければいけない。
生き延びる為には善も悪もないのだろう
描き方がいい
胸クソ悪い映画。だけど必見。
ほぼ 最初から最後まで クソみたいなストーリー。
大尉の制服を手に入れたことが契機となって、大尉らしく振る舞えた結果、かなりの地位を手に入れたかのように見えた脱走上等兵の話。
会う兵隊会う兵隊に、大尉だと思わせるためには、威圧的であると同時に、相手にとって都合の良い状況を作り出す必要がある。
それが重なった結果、極悪非道な行為にまで及ぶわけだが、そのエスカレーションが止まらないというのが怖い。正直、途中で「もう映画終わりでいいんじゃないの?」と何度も感じた。
大尉と詐称した男は、再度前線に送られる前に再び脱走兵となるシーンで、ただの「演技が上手い卑怯な男」だったことが描かれる。
つまり、どこにでもいる男だということ。この映画の怖さはここにある。
ここまで極端な例は、敗戦間近という極限状況でしか現れない稀有な例かもしれないが、人間が決して忘れてはいけないことだろう。
「人はみな、自分にとって都合のよいことだけを事実として取り入れる」
しかし、各自が「自分にとって都合のよい事実」だけを取り入れていくと、この映画の舞台である敗戦直前のドイツという状況以外でも、どこでもいつでも、こういうことは起きてしまうんだという点が、怖い。
各自が意識もせずに雰囲気というか環境を作り上げてしまい、そこに独裁者が生まれるという関係。
そういう意味で、この映画の主人公は、実は、大尉を取り巻く兵隊達の方で、大尉と詐称した男はただの狂言回しなんだな、と気づく。
独裁者は、彼の意思で生まれるというよりも、人々の勝手な受け取り方の結果で生み出される。
テロップの背後に流れる、「彼らが現代ドイツで我が物顔に振る舞っている映像」は、「現代に彼らが生まれてもなんらおかしくないんだよ。みんな、自分に都合よく考えるのではなく、ちゃんと考えようね」という監督からのメッセージか。
俳優みな上手いので のめり込みます。嫌な気持ちのまま。ほんとにしっかりつくってある。あ〜、疲れた。
史実を
戦争への道
作品としては良くできてるかと
借り物の権力
えぐい、グロい。
脱走したドイツの上等兵が、放置された車から勲章つき大尉の制服を見つけて盗み、生き延び、食事にありつくためについた「総統からの特殊任務のため…」というちいさな嘘から、どんどん気が大きくなって、虐殺、強奪、あらゆる犯罪を行っていく。
借りた力、盗んだ権威を振りかざし、汚れ仕事は忖度した周りの人間にやらせる。
また、大尉と信じた兵士たちは思考を停止し、いくらでも残虐な行為に手を染める。
20歳そこそこの若者がしでかしたこれらのことは、第二次世界大戦末期のドイツで起きた実話がベース。
ハリウッドの映画監督が、これをこの時期に、祖国ドイツでわざわざ作ったことは意義深い。
市民に武器を突きつける者達に、偽りの権力を与えているのは、独裁者その個人ではなく、彼等に同調する周囲の人間「支持者」なのだと。
制服に騙されていないか?
主に、アメリカ、イタリア、ドイツ、日本など、極右の政治家や政党が支持され、自国の利益のみ声高に叫ぶこの時代。
だからこそ、この映画は「ナチス時代の愚行から学んでくれ」という監督からのメッセージに思えました。
タイトルなし
終戦直前、脱走兵がナチスの軍服を拾って着用し、虐殺の限りを尽くす独...
お手玉
凄まじい演技力 詳しい方いたら教えて下さい
最近、史実に基づいた映画をよくみていたが、個人的には終わりは決まっているものだし、少し退屈なものが多かった。だが、今作はかなり好きです。
ストーリーとしては第二次世界大戦も末期の1945年4月、敗戦濃厚なドイツでは兵士の規約違反が多発していた。脱走兵ヘロルト(マックスフーバッヒャー)は偶然拾った軍服を身にまとい、大尉に成りすまして、人々を言葉を巧みに使い騙していった。
若い(20歳)の脱走兵が言葉巧みに大人や他の兵士達を自分の思うままに動かすスカッと感。序盤の脱走シーンのハラハラ感。そしてなにより主演のマックスフーバッヒャーの演技力には脱帽するほどであった。どこを探しても彼の年齢がわからなかったが、若いのにかなり落ち着いた言葉遣い、仕草をしていた。実在の人物を実際にみたわけでもないが彼と同様に人を惹きつけるカリスマ性はかなり持てていたと思う。将来が楽しみすぎる役者さんです。また、エンドロールも彼が実際に現代に生きていたらという程でドイツにいたが、それも現代のアメリカの繁栄ぷりを風刺するようで興味深かった。
映画の世界にかなり引き込まれるし、何と言ってもレベルの高い演技力は一見の価値大いにアリです。
全64件中、41~60件目を表示