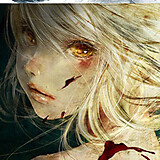「風間塵がギフトである理由」蜜蜂と遠雷 琥珀さんの映画レビュー(感想・評価)
風間塵がギフトである理由
換骨奪胎(先人の着想やアイデアを借用し、新味を加えて違う作品に作り直す)と言えるほど、違う作品に仕上がってるわけではない。かといって原作本来の魅力が活かされているわけでもなく、ちょっと残念な出来でした。
風間塵がギフトである理由……風間塵の才能が起爆剤となって、他の才能を秘めた天才たちを弾けさせる。真に個性的な才能たちが、風間塵の演奏を触媒として開花していくこと。
であるならば、風間塵の天才振りがもっと具体的に描かれていて欲しかったのですが、出てきたのはお手製の木製キーボードとボロボロの靴だけでした。これだと、練習環境に恵まれていない養蜂家の家庭で育った自然児であることは分かりますが、天才であることまでは伝わってきません。
映画の中で描かれたオーケストラの一部の配置換えのエピソードなど、原作では次のように風間塵の特異な才能が伝わるようなものとなっています。
本選リハーサルの場で風間塵は、自分は客席に降り、オーケストラだけでバルトークの三番、第三楽章を演奏させる。そしてやおら舞台に登り、椅子を引っ張ったり、譜面台をずらしたりするが、それは床のひずみのことも含めて、すべて音のバランスや伸びの効果を向上させるため。その後、一緒に演奏するのだが、指揮者や楽団員もびっくりするほど見違えるように(聞き違えるように⁈)音が良くなり、彼自身のピアノ演奏も楽団員の方が付いていくのに必死になるほど力強くその場にいる全員を完全に飲み込んでしまう。
そういう天才であるからこそ、マサルも亜夜も予選から彼の演奏を聴くたびにインスピレーションを与えられ、コンクールの中で成長していく。塵もまた、マサルや亜夜や明石の演奏から色々なものを吸収していく。一次審査から観ている聴衆側が、大会中の甲子園で闘うたびに強くなっていく高校球児をいつのまにか親心的に応援したくなるように、それぞれのキャラクターに惹かれ、思い入れや応援の気持ちが強くなっていく。そのような原作の魅力があまり感じられませんでした。
その他にも。
風間塵とホフマン先生の約束。
音楽を世界に連れ出すこと。今の世界はいろんな音に溢れているけど、音楽は箱の中に閉じ込められている。お姉さん(亜夜)も自分と一緒に音楽を外に連れ出すことのできる人。先生、見つけたよ。
亜夜の本来の音楽を解き放つことのできる〝天才〟がマサルや塵との出会いで復活する過程で描かれる「トラウマ克服」について、この映画ではかなり観念的に(映像のイメージでいえば、ラース・フォン・トリアー監督のメランコリアのように)描かれていますが、背中を押してくれたものの正体が今ひとつスッキリせず、明石の前で見せた涙の意味も、原作での複雑な背景に比べると、安易な印象が拭えませんでした。
もうひとつ気になったこと。
原作ではコンクールの4位と5位には韓国の人が入るのですが、この映画では欧米系の名前だったと思います。亜夜さんの前のキム・スジョンさん?がなんらかの理由で欠席のため、出番が繰り上がってたようですが、昨今の日韓関係の悪化と関係があるのでしょうか???
iPhoneから送信
風間塵は「ミツバチは刺したら死ぬという生態」のキャラクター設定だと感じました。
ミツバチは可愛いだけではなく毒と死を共有しています。風間が指から血を出しながら鍵盤を叩いていた時、そこにふとミツバチが飛んだのでそう思ったのです。
僕はかつてオルガン(パイプオルガン)弾きで、鍵盤を血で汚したことがあるので、音楽に命を削る風間には言葉抜きでの共感をしています。
(グレシャムさんとCB さんに同文コメント2回目送信=1回目が消えてしまっているので)。
私はこの原作を読んでないので、参考になります。
原作を読んでいる方のレビューを読むと、原作はもっと才能そのものが共鳴しあう感じなんですかね。
映画はもう少し人間的な部分が強く出ていたのかな。
なんか、よく分からないコメントですみません。
今日、本屋さんに行ったら、スピンオフ短編集が出てました。
タイトル『祝祭と予感』幻冬社刊、1200円+税。
巨匠ホフマンと風間塵の出会い、「春と修羅」誕生秘話など全6編。コンクール
後の塵と亜夜とマサルも出てきます。
原作好きにファンの多い奏さんも登場します。原作を飛ばしてこちらから読んでも映画世界をより豊かにしてくれますし、原作よりはるかに短時間で読めるのが何よりかもしれません(^.^)
かすやさん、ありがとうございます。
かすやさんのレビュー欄でコメントできなかったので、こちらで失礼します。
個人的には、役者さん達のイメージが残ったまま読んでもマイナスには働かないし、物語世界の広がりが更に増す効果があると思います。寧ろ羨ましいかも、です。舞台裏にいた調律師さんなんかもとてもいい味出してますよ。
レビュー見させて頂きました。原作未読です。何か端折ってるんだろうな、言いたいことが半分くらいしか理解し合え出来てなかったと。原作読んでまた観たくなりました。
CBさん、ありがとうございます。
ひとりでも多くの方が、映画とはまた違った豊穣なイメージを膨らませながら、原作にあたり、至福の読書体験を積んでいただけると嬉しいな、と思います。
自分が言葉足らずなのですが、私も、音楽的な主題は、ホフマン先生が、塵という劇薬をこのコンテストに出場させることによって、皆が、審査員やコンテスタントや我々観客(読者)が、「過去からの名曲を完璧に演奏することだけがピアノの、音楽の真髄なのか」というテーマを考え始める、ということなのだと思います。そこは、琥珀さんの言う通りかと。
ただ、そのことは、私で言えば、
原作を読み終える終盤頃から湧いてくる考えというか気づかされることでした。それでこの映画は、よりわかりやすい、亜夜の再生と明石の悟りをあえて中心におき、本来のテーマを最小限に抑え込んだのではないでしょうか?
読んだ人にはそのテーマが理解でき、読んでない人にはかすかに伝わる程度まで抑え込んでいますよね。
それだけに、映画を観て、原作にあたる人は、そこでまた映画とは別の感動を得られるわけで、ちょっと羨ましいですね。
いずれにしろ、本来のテーマを改めて気づかせてくれた琥珀さんのレビューに再度感謝します。
たしかに、ホフマン先生と塵と、多分、塵の父親から伝わる、原作が伝えようとする重要なメッセージの方は、今回大胆に省略されましたね。2時間という枠の中にどこに焦点を当てるのかは、本当に難しいことなんですね。琥珀さんのレビューのおかげで、気づくことができました。
今回の作品は、あえて栄伝亜夜の再生と、高島明石の生活とピアノの両立とは、の部分に焦点を絞って成功していると思うのですが、この映画のおかげで音楽やピアノへの感度が上がっている音楽素人の私が、続けてまったく同じ同じストーリーでホフマン先生と塵に焦点を当てた映画を観ることができたら、さらに音楽への理解が深まって、幸せこの上ないでしょう。
(それってすごい、と夢見てうっとり…)
映画と原作は別物、ということは承知の上ですが、この映画を一層深く理解するのに役立つかもしれないので、原作の一部を紹介します。
(映画を思い浮かべながら読むことで、更にイメージが豊穣になってより充実した読書体験ができると思います。)
一次予選で風間塵の演奏を聴いた時の反応。
ナサニエル『なんだ、この音は。どうやって出しているんだ?まるで、雨のしずくがおのれの重みに耐えかねて一粒一粒垂れているやようなーー』
高島明石『なんて無垢な、それでいて神々しい、天上の音楽のような平均律クラヴィーアだろう。』
マサル『訥々と、それでいてなんとも言えぬ歓びに溢れた音。誰の演奏にも似ていない。素朴なのに、一種煽情的ですらあるーー譜面を感じない。(中略)体験。これはまさに体験だ。彼の音楽は「体験」なのだ。』
亜夜『風間塵。彼はとても楽しそうだった。かつてのあたしのように。(中略)泣きたいような衝撃が込み上げてきた。どくどくとこめかみが熱く波打つのを感じる。弾きたい。風間塵のように。弾きたい。かつてのあたしのように。かつてのあの歓びを、もう一度弾きたい。』
月夜の晩、亜夜と連弾した時の風間塵の独り言のようなセリフ。
『僕ね、先生に言われたんだ。一緒に音を外に連れ出してくれる人を探しなさいって』
『おねえさんはそうかもしれない、って思ったよ』