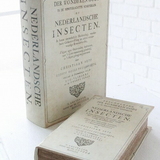僕たちは希望という名の列車に乗ったのレビュー・感想・評価
全64件中、41~60件目を表示
沈黙する教室
最強の青春映画。
同世代の若者たちが悲惨にも、勇敢な行動を起こしてたくさん亡くなった。このこと一点に心を揺さぶられて、たった2分間沈黙した高校生たち。彼らにとってこの行動は、好奇心と正義感、そしてまっすぐに死を悼む気持ちからでた純粋な行動だった。しかし大人たちは彼らを反逆者として、親の言うことを聞けない子供として、弾圧しようとする。もちろんこの映画は、当時の不安定な政治情勢を記録に残し、ナチスと社会主義、資本主義について現代人に考えさせる映画ではあるが、それに加え信念を持った高校生たちが大人たちに立ち向かう青春映画のようにも思えた。ちょっとしたいたずら心で始めたテオと父へのかすかな不信感から現在の政治情勢に疑問を持つ賢いクルトのように、クルト以外は初めこそ出来心からの行動だったと思う。しかし事実を知っていくうちに、そしてクルトの信念を感じることで、それぞれの中にまっすぐな正義が生まれてきて、1つの大きな決断に至る。ここまでには恋愛、嫉妬、将来への不安、裏切りなど高校生特有の未熟さもあるが、それを乗り越え確固たる信念に向かって成長していく姿は少し羨ましくも思えた。自分の高校生時代には全くない姿だったから。また彼らの親や校長も、社会主義を強制させる政府とは違い、子供たちの幸せを最善に考えていると言う点で家族愛も感じられる作品だった。最後にはテオやクルトの親が息子たちの信念を尊重していく姿に感動した。
彼らの将来についてもっと知りたい、そう思える作品だった。役者それぞれの表情や緊迫感がリアルで、引き込まれた。
タイトルと最後のシーンの組み合わせがとっても好み。
クレア役の子がめっちゃかっこよかった!笑
社会主義者の余裕のなさ
ベルリンの壁ができる前の東ドイツが舞台。
発端はそんなことで!?ということ。そんな当時の状況を理解できるかどうかがポイントに思えた。役人たちがそこまで過敏に反応するのは、資本主義との思想的争いが激しかったからなのかも。それにしても役人たちが厳格すぎる。この余裕のなさ、自由のなさが社会主義の敗北の要因の一つなのだと感じた。
友情、打算、プライド、裏切り、英雄的行動。内容は政治的かもしれないが、ちゃんとした青春の物語になっていた。
でも一番の見所は役人たちの尋問のような気がする。生徒たちを分断しながら、家庭の事情を小出しにし揺さぶっていく様はなかなか緊迫感があって面白かった。
実は一番の泣きポイント(であろう場面)は、かの有名な学園もの映画に似すぎてて感動が薄れてしまった。泣けなかったな。
でもいい映画!観て考えてほしい。
鼻すする 響き渡る音 映画館
静かに心に響き続ける
独裁政治の始まり
今作はまだ東ドイツが完全にソビエトから支配される前だからなのか、私が想像したよりも緩い空気を感じました。独裁政治の始まりは思想の制限から言論統制、厳罰化、密告、処刑と順を追って過激になっていくのかもしれません。だからこそ、思想の制限を国家が進める前に何とかしないといけないのではないでしょうか。日本では抗議することがマイナスのこととして捉えられる事が多いですが、抗議できない社会に生きる人間はどうなるのか、行き着く先にある社会はどうなるのか。抗議の持つ重みを改めて考えさせられてしまいました。
第二次世界大戦終結後に、ドイツが東西に分割され朝鮮も南北に分断されました。歴史にたらればはありませんが、もしかしたら敗戦国日本もアメリカ陣営とソビエト陣営に分断されていたかもしれません。そう思うとこの作品が他国のことの様には思えませんでしたし、過去の話とも思えませんでした。独裁政治はいつの時代も起こりうる事だと思います。
ジャングルの裸女を見るために僕たちは列車に乗った
1950年代の東ドイツの高校生達が、ちょっとした反抗心から国家に追い詰められる姿を描いた実話らしい。
ソ連占領下の状況描写が、個人的には少し弱いと感じたが、同じドイツ人でもナチスやソ連になびいた者に対する姿勢や国家体制への反逆者を追求してクラスの仲間が揺れて行く過程がリアル。
国の未来を担う若者をスポイルする姿は醜悪の一言。
多くを語らないラストも潔い。
余談だが、映画冒頭で主役の二人の高校生が、わざわざ西ドイツに観に行く映画が、「ジャングルの裸女」だったのがツボ。
1957年?のドイツ製女ターザン?映画で、劇中ではエロ映画扱いだが、名優ハーディ・クリューガー主演で当時としては異例の露出トップレス姿の美少女ターザンのみが記憶に残る怪作。
時代の空気
傑作。困難を乗越え信念を貫く若者達の気高さ、尊さに涙
時代と情報に翻弄されながら
初めはただの悪ふざけだった
これが現実の話なんて
サイレント・パートナー
きびしい映画だが、秀作である。信念と保身の間で揺らぐ緊迫した葛藤に息を呑む。
映像で見ると、いわゆる“黙祷”とは違って、“無言の抗議”という感じだ。元は軽いノリもあったのだろう。そこから生じた彼らにとって予期せぬ展開は、管理社会の重圧を表出している。描かれた内容は60年以上も前の話だが、現在でも依然として“言論の不自由”がまかりとおっている国はある。(彼らは“列車に乗った”が、残された家族や友人は迫害されなかったんだろうか。)
唯一残念なのは邦題で、長いし、あまりに情緒的すぎる。邦訳された原作の「沈黙する教室」でよかったのではないか。
この年代特有の真っすぐな思い。
今年の洋画ベスト候補
自由を求め惑う東ベルリンの若者たち
のほほんと生きていると…
一生忘れない1本です。
当時の葛藤が伝わってくる
石川啄木に「強権に確執を醸す」という言葉がある。26歳で死んだ詩人の胸のうちは今となっては知る由もないが、天皇を絶対権力として帝国主義政策を進める明治政府の強権的なやり方に反発を覚えていたのは間違いない。幸徳秋水たちによる大逆事件も少なからぬ影響を若い詩人に与えたはずだ。
本作品の若者たちも啄木に似て、社会主義のパラダイムを一方的に押し付けるソ連に対して、上手く説明できないながらも、精神的な自由を奪われつつあることに容易ならざる危機感を覚えているように見える。18歳ともなれば、思春期の反抗と違い、弾圧に対しては敏感に反応する、感性の鋭い年齢である。
予告編の通り、授業の冒頭にハンガリーの武装蜂起の犠牲者に対して追悼の意味の2分間の黙祷を実行し、権力側がこれを反体制(反革命)と見做して弾圧するというストーリーだ。かつての日本の過激派と同じく、仲間同士のリーダーシップや裏切りに対する倫理観が絡み、若者たちは一枚岩ではあり得ない。そして体制側は容赦なくそこにつけ込んでくる。そして若者たちの家族も、決断を迫られる。
役人たちは皆ソ連の傀儡だが、傀儡であることを卑下する気持ちはない。寧ろ自分たちは傀儡ではないと思っているフシがある。自分の立場を正当化する思いが強く、それがそのまま反体制的な勢力への弾圧に直結する。役人たちの若者への弾圧が容赦ないのは、それが役人たち自身のレーゾンデートルだからである。
かつてロシア革命に熱狂したロシアの民衆は、その後長きに亘って政治局による圧政に苦しむことになった。権力は必ず腐敗するという鉄則は、いつの世でも正しい。権力は統治システムとして官僚機構を構築し、官僚はある種の特権階級として国民を支配しようとする。国民はもはや国民ではなく、帝国主義時代の臣民に等しい。そしてソ連は自国だけでなく、世界大戦のドサクサで縄張りにした東側諸国のすべての国民をソ連帝国主義の臣民として支配しようとした。若者たちが反発するのは当然である。
映画の背景にある時代は、権力行使がストレートだったが、現代はインターネットの時代で情報が猛スピードで拡散するから、権力は以前のような暴力的な手法を取ることができなくなった。何をするかというと、インターネットを逆用してフェイク情報を大量に流すのである。流れてきた情報を取捨選択する能力のある人はいいが、多くの人はインターネットの情報をそのまま鵜呑みにしてしまう。自分で考えることをしないからである。現代の教育がそういう風に育ててきたのだ。
そして若者たちは情報の真実を探求することなく、権力のいいように操られ、投票する。かつての若者たちが命がけで戦ったことなど、もはや知る由もない。国のため、子どもたちのため、家族のためという大義名分は、権力が民衆を欺くときに使う言葉である。本作品の若者たちのように、国のためでも家族のためでもなく、自分のために戦うことが正しいことなのだと気づかなければならない。権力は常に腐敗する。若者たちが「強権に確執を醸す」ことは、世の中のバランスを保つために必要不可欠なことなのだ。
作品としては当時の様子や軍人が街中のいたるところにいるという戦後のヨーロッパの有り様が十分に伝わってきた。役者陣はみんな上手い。ナチズム、ファッショ、社会主義といったイデオロギーに関する発言が飛び交うのは、やはりそういう時代だったのだ。人は多かれ少なかれ、時代を背負って生きている。戦争の惨禍の記憶は未だに消えず、若者たちは不安と恐怖の中に生きている。安全無事を目指すのは簡単だが、強権と戦っている人々に対して恥ずかしい生き方はできない。当時の若者たち、そして彼らを取り巻く人々の複雑な葛藤が伝わってくるいい作品だった。
全64件中、41~60件目を表示